 トップへ戻る  読んだ本の分類 |
|
 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |
|---|---|---|---|
| E015-001 | 島津義弘 | 島津義弘の痛快な一代記 | |
| 管理番号:E015-001 | 51 伝記・一代記 |
出版社:学習研究社 | |||||||
| 書名:島津義弘 | ISBN4-05-901162-2 C0121 | ||||||||
| 学研M文庫 え5-3 | 価格:690Yen | ページ数:368P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2004/5/20 | 購入:2004/5/23 | カバーイラスト:村山潤一 カバーデザイン:堀 立明 ブックデザイン:中谷匡児 |
|||||||
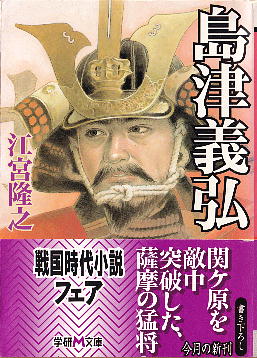 島津義弘の年代記。読んでからずいぶん経つのに、まだこっちに上げていませんでした。書きにくいところがあったんだろうか。単に忘れちゃったのか。ほかに理由があったんだろうか。 島津義弘の年代記。読んでからずいぶん経つのに、まだこっちに上げていませんでした。書きにくいところがあったんだろうか。単に忘れちゃったのか。ほかに理由があったんだろうか。序章は、85歳の老齢の島津義弘が過去を回想するシーンから。 天文4年7月23日(1535年8月21日)に生まれ、元和5年7月21日(1619年8月30日)に没したので、数えで85は最晩年のこと。 そして彼の戦に明け暮れた生涯が、物語として描かれていきます。 幼い頃に父親、島津貴久から兄の義久と共に、源頼朝の末裔を自称する島津家の歴史を学んだこと。 狼に育てられたというローマ建国神話を思い出させる、白狐の伝説。 島津家の分家のこと、今に至る分家同士の争い。 種子島銃の伝来とイエズス会の来航。 宣教師のひとりと出会った義弘が感じた「響き合う関係」。 島津宗家の家を守る戦の中で、若き勇将として名を知られる日々。 大隅を領する肝付一族との抗争。九州版「桶狭間」と言われる 大友宗麟との戦いの中で編み出された「釣り野伏」戦法。 情報に疎く頑迷な薩摩の土壌の中で、いち早く織田信長という人物の能力を見抜いた炯眼。 羽柴秀吉という男の「惣無事令」に対する判断。 小心ではないかと家臣に嘲られた兄・義久の避戦論への理解。 島津四兄弟による関白軍迎撃戦。 常に最前線で、しかも自ら鉄砲を撃つ義弘の指揮ぶり。 義弘の生き方の規準は「慈悲」であると頑なに思っていたのだという。 「慈悲」という規準を持って、人と人の「響き合う関係」が生まれてくると確信していたのだという。
九州渡航。明軍に 関ヶ原において天下に名を轟かせた敵中突破による撤退戦。 なるほど、島津義弘について、こういう風な描き方もあるのか。 ふむ。 で、だ。 「ラ」の音を440ヘルツにすると決めたのは、近代になって欧州のあちこちで音程の差があって、そりゃ困るからだいたいそのへんにしましょうや、ということで人為的に定めたルールです。欧米が決めたことで、日本では音程は奏する時々に定まっていたはずです。定まった規準はありません。統一規格の音叉のなかった時代、世界でもそうだったはず。440ヘルツの音は、世界中が昔から音合わせに使っていた音の高さではありません。 引用した文の「慈悲」とか「響き合う関係」とかについては、何言ってんスか? としか言いようがない。 慈悲の心で戦いを避ける、といういかにも近代の学者の考えそうな哲学を戦国時代の武将に求めるのはナンセンス。 そのほかあちこちの歴史的な伝承についても、頭をかしげるものが多い。 読み物として面白いのです。感動的ですらある。けれど、厳密な歴史的史料に裏付けられた考察に基づく歴史小説というより、ちょっと昔の痛快な歴史ドラマ的です。 ふむ。ちょっと残念。(2025/10/07) 読書メーターの記録より 読了:2020/11/18 |