 トップへ戻る 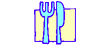 読んだ本の分類 |
|
 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |
|---|---|---|---|
| H104-001 | 帝国海軍の最後 | 駆逐艦乗りとして戦いぬいた男の物語 | |
| 管理番号:H104-001 | 52J 戦史・戦争ノンフィクション(日本) | 出版社:河出書房新社 | |||||||
| 書名:帝国海軍の最後 | 副題 | ISBN978-4-30942200-8 C0131 | |||||||
| 1955年河出書房より『帝國海軍の最後──矢矧艦長の実戦記録』、その後1967年『帝国海軍の最後』と改題され「太平洋戦記」シリーズに収録・再刊され、1975年河出書房新社より同シリーズ新装版として刊行したものを2011年に復刊、それを2025年に文庫化したもの。 |
| 河出文庫 は33-1 | 価格:900Yen | ページ数:256P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2025/7/30 | 購入:2025/8/26 | カバーデザイン:阿部ともみ(ESSSand) カバー写真:巡洋艦・矢矧の最後(Naval History and Heritage Command) カバーフォーマット:佐々木暁 |
|||||||
 本のオビに 映画「雪風 YUKIKAZE」がより深くわかる! という文章があります。この言葉でこの本がより売れるなら、そりゃあ結構なこと。 本のオビに 映画「雪風 YUKIKAZE」がより深くわかる! という文章があります。この言葉でこの本がより売れるなら、そりゃあ結構なこと。ただし個人的な意見ですが、そんなことはありません。あの映画は、お金をかけCGを駆使し、いまふうな戦記映画としてよく作りました。評価する向きもあるでしょうが、内容も時代背景を考えると変なところがいろいろありました。まァ映画です。感動したい人は感動すればよろしい。 ただ言えることは、この本のような戦場のリアルとは別物であるということ。 原為一、と言う名前は、日本海軍最後の艦隊出撃である「大和」の沖縄特攻のとき、随伴した軽巡洋艦「矢矧」の艦長の名として頭に引っかかっていました。駆逐艦「時雨」がらみでも、ちょっと。 でもあまり注目していなかったかも。 その人の書いた本、と言うことで読んでみました。 とはいえこの手の本ですと、特に共著者がいたりすると、終盤で戦争を嘆く言葉の羅列が始まったり、美しい詩を掲げたりするものがあります。著者の美学なんでしょうけれど、戦記にそんなものを持ち込まれると、こっちが鼻白むことになったり。ぶっちゃけ、白けます。 ところが、そんな事はなかった。この方は、戦争それ自体に思想的に賛成していませんが、運命の中で精一杯軍人としての職務を全うしています。 冷静・沈着に。果敢・豪胆に。短慮にならず無駄に躊躇せず、しっかり決断し断行。怠惰を嫌い、努力を惜しまず、率先垂範。奢らず誇らず無駄な反戦論に堕すこともない。そんな軍人の一人語りです。 緒戦のスラバヤ沖海戦。腰が引けた指揮ぶり、とその指揮官の戦いぶりに批判がある戦いですが、その中で新鋭駆逐艦「天津風」の駆逐艦長として原為一中佐は参戦します。戦争全体には不安があり、連合艦隊参謀長の宇垣纏中将に直々に意見具申するほどの直言ぶりを見せますが、戦うとなれば本気。第16駆逐隊の一隻として自分の職分をまっとうします。その中でも、護衛している陸軍の輸送船の走り方の油断しきった姿に苦言を呈していたり、真面目な軍人ぶりがうかがえます。
その後の「ミッドウェー海戦」に出撃する際、実戦指揮官として思う何ともまだるっこしい、何とも歯がゆい上の方針へ、そっとこんな言葉も残します。
ちなみに、Wikipediaの「天津風」の項目には、この本からの抜き書きが点在します。細かいことはあっちを見た方がいいかも。(笑) とはいえ、それだけならまあいいのですが、文章の中に「です・ます体」が混在しているのは何たることか。素人の集まりだからしかたないのかなぁ。 その後、1943年3月8日に原為一中佐は第27駆逐隊司令に任ぜられます。このとき同隊は第2艦隊第4水雷戦隊に属しており、「有明」「夕暮」(この二隻は初春型)、「白露」「時雨」(白露型)の四隻で編成されており、この四隻は準同型艦でした。「時雨」を旗艦とした原中佐は、5月1日付けで大佐に進級します。 のち、『呉の雪風、佐世保の時雨』と呼ばれ沈まない幸運艦として名を残しますが、「雪風」と同じく「時雨」も蛮勇ではない、伶俐に計算された戦術と訓練、常にあらゆる事を想定した航海術、戦闘術により生き延びたもの。 この本でも随所にそれが示されます。 27駆の司令が白浜大佐に替わったのは同年の12月25日ですが、そこまでの間「時雨」の指揮を取る艦長は山上少佐(在任1942/9/1-1943/12/8)でした。しかしどうも影が薄い。本の描写でも、駆逐隊への指示より「時雨」の操艦・警戒・戦闘への指揮の言葉ばかり。艦長はすっかり副長化しています(笑)。駆逐隊では、旗艦の行動を僚艦が注視・追従することで指揮を取るので、司令が旗艦を振りまわすのは当然なのでしょう。 43年10月、戦没した僚艦の後任として編入された「五月雨」と共に二隻となった27駆を率いる原大佐、「時雨」の艦橋でこんな会話を聞きます。
この直後、ベララベラ島の守備隊をブインへ撤収させる任務での戦いぶりの描写がヴィヴィッド。 日本海軍は日本兵収納のための輸送部隊と、第三水雷戦隊の6隻の駆逐艦が夜襲部隊となります。「時雨」は27駆として「五月雨」を率いる第2夜戦部隊。戦場で第1夜戦部隊を見失います。
この後に砲撃を開始しつつ敵情を監視し、敵部隊の三隻に魚雷で被害を与え、さらに砲撃で追い打ちをかけて撃退したとしています──が、実際はそうもいかなかったらしい。戦場ではそんなものです。 この戦いは、のちに第二次ベララベラ海戦と呼ばれます。原大佐の視点ですと絶体絶命の中での敢闘なのですが、実際の記録は意外に彼我の戦力に差がありません。おそらく米軍も同じように敵勢は常に強大に見えたのでしょうね。 その後に、ソロモン方面での激闘を戦いぬいた原大佐は、こんな言葉も残します。
そして原大佐は、「時雨」を不沈艦たらしめた理由をさりげなく語り残します。
戦争末期、空からの敵の攻撃に対して、やがてひとつ見極めたのか、原大佐は独特の戦闘方法を披瀝します。 敵機は夜間、超低空至近距離爆撃によって日本軍に大被害を与えている。これは日本の特攻とよく似ているが、飛行機も人名も捨てない、「生き残る必殺特攻」戦法ではないか。ではどう対抗すればいいのか。
原大佐は、最大戦速30ノットで突っ走る駆逐艦の艦橋で、血相を変えて見つめる乗組員の視線の中で、「そうだ、直進だ」と言い切り、生き延びました。 「時雨」は12月、船団護衛の任務と共に本土に帰還します。機関、主砲、魚雷発射管などの兵装はともかく、船体・探信義・機銃・舵機など、船体は傷だらけで大修理を要する状態でした。 しかし修理完了となった同月末、原大佐は駆逐隊司令を免ぜられ、水雷学校教官兼研究部員の肩書きと共に日本初の魚雷艇訓練所長に任じられます。今後の戦争に必要なものは大型艦ではなく、小型快速艇による奇襲戦法しかない、という流れ。 納得したのは戦場を見ていた最前線士官の認識故か。 翌1944年7月、原大佐は「必勝確実なる超緊急非常対策」なる案をまとめ、なんと高松宮( この結果は、書かれていません。おそらく黙殺されたのでしょう。下手をするととんでもないことになったはずですから。 1944年12月、原大佐は水雷戦隊旗艦・軽巡洋艦「矢矧」の艦長に任じられます。最後の海上勤務。 この艦との出会いは、むろん「大和」の沖縄特攻に終着します。 「矢矧」は10隻の駆逐艦を要する最後の実戦部隊、第二水雷艦隊の旗艦でした。戦隊司令官は古村啓蔵少将。 この戦いで原大佐中心に書き残すなら、まず、彼を含め実戦部隊の艦長たちは誰ひとりこの作戦に同意していなかったこと。やるなら、敵の延びきった補給路を叩くために「矢矧」は水雷戦隊を率いて太平洋深く暴れ回るべきだ、死ぬためだけの特攻などまっぴらだ、と原大佐は広言したとか。しかし、旗艦「大和」上に呼集された古村司令官が命令を受領した以上、従うしかない。 ドラマや映画で描かれた名シーン、全艦長が集まって説明を受けて怒号を挙げ、貧乏クジを引かされた草鹿龍之介連合艦隊参謀長の説得に伊藤整一司令長官が了解すると皆が涙を流した、という場はあったのでしょうか。この本では書かれません。 もう一つは、「矢矧」艦内に格納されていた食料のこと。米麦が一千名の乗員に対し20日分以上あったので、5日分を残して陸揚げしてしまえ、と原大佐は命じます。しかし民間人である徳山軍需部の水船の船長は、還納手続きが面倒なので嫌がったのだそうです。菊水作戦は軍の機密なので、このフネにはもう5日分以上の食料はいらんのだと言う訳にはいかない。 飢餓に瀕している国内の事情を考えたら、余分の米は一粒もいらないんだがな、と困惑した原大佐、一計を案じたのだという。酒保から酒三升を取り寄せて船長と船員、そして軍需部係員に渡してみたのです。 これが効果てきめんだったというのが、笑えます。
坊ヶ崎海戦で「矢矧」は、「大和」に先だって沈みます。 被害担当艦となって「大和」を長らえさせるため、という意図も原大佐にはあったそうですが、被害を受けてからしぶとく生き続け、多くの乗組員が生還できました。「矢矧」の沈没は1945年4月7日午後2時頃ですが、原大佐は日没間近、救助される最後の一人として生還します。 海に漂いながら、原大佐はこんな事を考えたという。
生還した原大佐は、淡々と敗戦を受け入れました。 やるべきことを真面目にやった人の戦記は、心になにか残るものです。(2026/01/10) 読書メーターの記録より 読了:2026/1/5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軽巡洋艦「矢矧」も好きなフネなので挙げたいのですが、駆逐艦乗りだった原大佐に敬意を表して、「時雨」を挙げます。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
