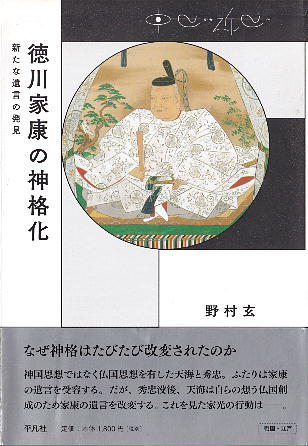 冒頭の「はじめに」は、こんな文章で始まります。 冒頭の「はじめに」は、こんな文章で始まります。
| 近年、静岡県静岡市では、民間企業と静岡商工会議所などを中心に徳川家康の遺体の所在を巡って「余ハ此處ニ居ル」と題した運動が展開されている(本書では天皇や歴史的人物、個人などへの敬語・敬称は省略する)。そこでは、久能山東照宮の関係者や一般の個人も参画するかたちで、家康は久能山東照宮の境内で眠っていると主張されており、栃木県日光市にある日光東照宮境内の「奥宮御宝塔(御墓所)」が家康の墓所であると考えられがちであることに対して異を唱え、家康の墓所は久能山東照宮境内の「神廟」であると主張することにより、静岡市域のかつての繁栄に思いを馳せ、今後の同市域の振興をも図ることが意図されているようである。[アドマック株式会社『季刊すんぷ』編集部2016]。(P8) |
これは、作者の主張ではありません。こういう、過去の歴史を覆いかくすような主張があり、運動があるということを提示しているのです。
かくも、歴史上の断定とは不安定なもの。この一点においてでも、注目に値するかな。

徳川家康(とくがわ いえやす)
天文11/12/26-元和2/4/17
1543/1/31-1616/6/1
享年75(73歳没) |
戦国時代から江戸時代初期の日本の武将、戦国大名、江戸幕府初代将軍(1603-1605)。徳川氏(将軍家、御三家など)の祖。 |
この問題は、実は素人が考えるような日本史の中のささいなことではなく、かつて明治政府がかなり関心を持ったことであったのだそうです。明治二年の公文書の中で明治政府の問いに対して静岡藩は、当初は久能山に葬られたが元和三年(1617)に日光に「移葬」したという記録があると答えています。これでわかるのは、少なくとも明治初年度においては、家康の葬られた場所がどこにあるのかがそれなりに重要な問題であったということ。
この問題は、単なる埋葬場所の問題のみならず、宗教的に考えて、家康は神格化されたことは間違いないにしても、東照大権現とはどういう存在なのか、他の神仏や天皇との関係をめぐっても定説がない状態であることも絡むのだそうな。
ではいったいどうなっているのか。
この本は、さまざまな方面に視点を移しつつ、神格化された徳川家康という存在の意味を問い直し、列挙されているさまざまな説を検討し、整理する試みです──と言っていいのだろうか。
正直言って、徳川家康が東照大権現として神格化されたという(素人視点での)一点の歴史的事実に、これだけ検討すべき(素人視点で言って)些末な問題が絡んでいるとはまったく認識していませんでした。歴史学とは、かくも奥が深いものなのなのか。
章立ては、こうなっています。
第一章 徳川家康の最期の日々 第二章 徳川家康の神格化の前提条件
第三章 徳川家康の神格化と久能山上の祭祀 第四章 徳川秀忠による家康の神格の決定
第五章 徳川家康の遺言をめぐる真相 第六章 東照大権現号の誕生
第七章 東照大権現という神格の段階的変容
東照大権現という「神号」(?)は、「明神」としたい以心崇伝・本多正純に抗して南光坊天海が「権現」案を主張し、最終的に「東照大権現」で押しきり、それにより将軍の側近の地位を固めた、というふうに漠然と認識していました。
しかし、歴史というものは単純なものではない。この例もご多分に漏れずかなり根が深い経緯が隠れていました。
主題は家康の埋葬場所というか、最終的に誰の意図でどこに埋葬されたのかですが、ここで描写されるのはさまざまな歴史的ネタとその背後にある政治的な駈け引きのあれこれです。
史学者ではない鐵太郎としては、歴史のこぼれ話的にあちこちのお話を頭に入れればいいかな。この世界でどのような議論がされ、定説はどうなのか、反証はあるのかなど、深いアカデミックな話はスルーしますよ?
晩年の家康の描写の中で、駿河国で病床に伏した家康に朝廷より太政大臣推任の知らせがあったとか。数年前の推挙では辞退していたため、なんとか生前のうちにと急いだそうな。これは朝廷からの動きというかたちですが、以心崇伝が働きかけ、太政大臣で死んで「豊国大明神」となった豊臣秀吉と同列になるよう計ったためだそうな。家康は太政大臣に就任したのち、一ヶ月後に亡くなります。
ここから、死んだ徳川家康を神として祀ることは既定路線なのですが、どのように祀るかの論争が始まりました。
初期のローマ皇帝は死んだとき原則として神格化されました。しかし元老院に嫌われて神になり損ねた皇帝もいます。私に免じてお願いしますよ、と次の皇帝に懇願されて、かろうじて神様になれた皇帝もいました。
このときの日本では、どういう感覚だったんだろう。太政大臣の秀吉が死んで「豊国大明神」という神様になったから、負ける訳にいかない、ということでいいのか。
神格化の前提条件として、キリシタンの立場というものがあります。少なくとも当時日本で自分たちの活動に危機感を持ちつつあったイエズス会の宣教師は、この神格化の流れが自分たちの宣教への障害になるかもしれないと危惧したようです。
しかし彼らは自分たちの発想、一神教のキリスト教に対する土俗信仰の対立という視点が日本人とズレていたとは思わなかった。この死せる統治者を神格化する行為が宗教的高まりを見せて反キリスト教の流れになるのでは、という発想が空振りになるとはわからなかったようです。
生前の家康は、神仏の教えに帰依していましたが、かといってキリスト教の布教に対し格別の迫害も妨害もしていませんでした。キリシタン排撃の流れになったのは別な事件、宗教的な原因ではなく「マードレ・デ・デウス号事件」や「岡本大八事件」などの取引上のトラブルがきっかけでした。そのため南蛮人が遠ざけられ、紅毛人がその地位を奪うのですが、結果として「伴天連の教え」は神仏の国である日本では「邪教」であるとされます。なんたる皮肉な歴史の流れ。
「権現号」と「大明神号」の間に上下や優劣の差はあるのか、という問答もあります。神道家・神龍院梵舜は、秀忠の招きで江戸に向かい、本多正純・土井利勝・安藤重信らと論を交えたのち、宿を尋ねた公儀からの内談の使者である星野閑斎と林永喜に対しこんな答えを返しています。
| 梵舜は、両者の間に差はないと答えたが、「サレトモ」としたうえで、権現号は伊弉諾尊・伊弉冉尊の神号であり、明神号は供物なども自由で徳川家康の官位にも相当する神であること、家康には大明神号が適していると申し渡したという。(P119) |
これは、元和2(1616)年5月3日のこと。すなわち家康の病没の17日後。
単なる慣習的、神道的、儀礼的な問いではないのではないか、と梵舜が気付いたのは数日後のこと。
あわてた梵舜が主家である吉田神社の吉田兼治に諮ってこの問いの意味と対策を考えるのですが、兼治が5月5日の時点で病没していたのだとか。
こののち、帰洛後の梵舜の動きと吉田家の狼狽、判断、そして吉田家の作法が「権現号」にどのように関わったのか。なんとまぁ、歴史の奥事情とは掘り返すとかくもややこしく、錯誤に満ちて面白いものなのか。
家康の末期の床に座り、その遺言を聞いたのは崇伝であったことは、歴史が伝えるところ。
その言を覆した天海はどのような論を述べたのか。
徳川秀忠はなぜ崇伝を冷遇したのか。
家康の遺言とは、いったいいくつあったのか。
家康の遺体は最終的にどこに埋葬されたのか。
徳川家光は東照大権現をどのようにして異国から日本を守護する軍神と位置づけたのか。
歴史は面白いですねぇ。(2025/09/20)
読書メーターの記録より 読了:2020/6/7 |



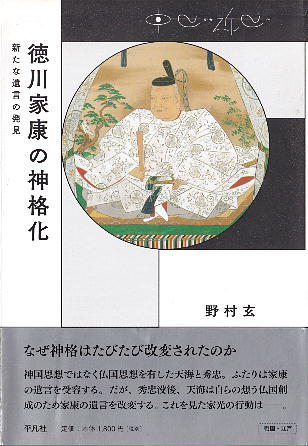 冒頭の「はじめに」は、こんな文章で始まります。
冒頭の「はじめに」は、こんな文章で始まります。