 トップへ戻る  読んだ本の分類 |
|
 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |
|---|---|---|---|
| N065-001 | ビザンツ帝国 | なぜいまこの帝国を語りたかったのだろう | |
| 管理番号:N065-001 | 53 史書・編年史 | 出版社:中央公論新社 | |||||||
| 書名:ビザンツ帝国 | 千年の興亡と皇帝たち | ISBN978-4-12-102595-1 C1222 | |||||||
| 中公新書 2595 | 価格:940Yen | ページ数:306P | 本のサイズ:新書 | ||||||
| 初版発行:2020/6/25 再版:2020/7/10 | 購入:2020/8/22 | ||||||||
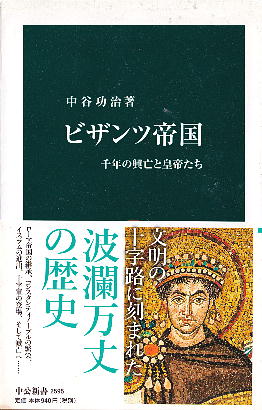 はじめに ではこんな文章から始まります。 はじめに ではこんな文章から始まります。
初期:地中海周辺に覇を唱えた古代ローマ帝政時代の後半、つまり4世紀のコンスタンティヌスから6世紀のユスティニアヌス1世の治世まで。中期:7世紀のイスラムの進出からビザンツ帝国が第4回十字軍の攻撃によって一度解体する1204年まで。後期:復活したビザンツ帝国が200年後に消滅する──つまり1453年のオスマン帝国による征服まで。 著者はこの波瀾万丈の歴史を、この中期を中心に描こうとします。
ちなみにビザンツ帝国という呼び方ですが、正式ではありません。彼らはほんの小さな街になった最後まで自分たちの国は「ローマ人の帝国」だと主張していました。これをビザンツと呼んだのは、明治期以後の日本の欧州史研究者が、ドイツ語の文献でコンスタンティノープルをビザンティウムと(ギリシャ語起源で)呼んでいた事からビザンツ帝国と呼ぶようになったのが起源だそうな。で、西洋美術史の分野ではこの国をビザンティン帝国(形容詞形でビザンティン)と呼んでいたので美術史世界ではそう呼んでいるそうです。ふん。 じゃあ統一してちゃんとした名前を付けろよと思うのですが、学者の世界はこういう点ではとことん頑迷固陋と相場が決まってますので、統一したわかりやすい名前に変わるとは思えません。暴論失礼。にや。 6つの章で構成されているんですが、序章と終章が前と後ろに付くので、実質8章立て。でもってその前後に余話的なコラムが合計9個入っています。ふふん。 序章 ビザンツ世界形成への序曲 ──4〜6世紀 まずニケーア公会議(AD325年)から。ここでキリスト教の神学上の問題が討議されましたが、同時に暦と週の日曜日を安息日とされ、クリスマスの日付が定められました。主宰したのはコンスタンティヌス大帝。彼が創建したコンスタンティノープルが新たな首都となり、ビザンツ帝国の開幕となります──が、お話的に彼の前に帝国を作り直そうとした皇帝ディオクレティアヌスについても語られます。 この皇帝は この二人と次のテオドシウス大帝がローマ帝国の様相を変え、ローマの元老院と平民の作り上げた国家を専制君主が官僚を駆使して統治する国家に作り替え、さらにキリスト教の教会を統治手段として受け入れる母胎を作り上げます。と同時にローマが東西に分裂する原因ともなりました。 この章の最後は、皇帝ユスティニアヌスの下で不遇な境遇におかれながらも、この時代最高の勇将として忠誠を尽くした将軍ベリサリウスを描いて終わります。 第1章 ヘラクレイオス朝の皇帝とビザンツ世界 ──7世紀 ユスティニアヌス1世の征服戦のあと、イタリア半島、北アフリカ、そしてペルシア地方から軍事的圧力が高まり、カルタゴの総督ヘラクレイオスの同名の息子が帝位についてこの混乱に一定の収拾を付けるまで。騒乱が続きます。しかし彼がササン朝ペルシアに対し勝利を挙げた直後、アラビア半島でムハンマドという商人が新たな宗教を興したのでした。 バルカン半島の一部と小アジア半島のみとなったビザンツ帝国は、しかしヘラクレイオスの後継者により内乱と政権交代を繰り返しつつ存続していきます。この時代から、ビザンツ帝国の政治に関与する宦官勢力が大きくなります。 第2章 イコノクラスムと皇妃コンクール ──8世紀 8世紀から9世紀は「イコノクラスム(聖像破壊)の時代」であり教科書にも登場する有名な出来事なのだそうです──が、西欧史って結構好きだったのに学校で聞いた記憶がないのはなぜだろう?(笑) ニケーア公会議以後、イエスをめぐる神学論争で帝国は揺れます。その結果否定された反主流派は「異端者」として排斥されるのですが、それなりに支持者もある訳。なかなか結論が出ないまま議論は紛糾し、アリウス派、ネストリウス派などが分派されていくと共に、異端者への迫害もまた盛んになります。イコノクラスムとは、この過程で起きた話。イコン(キリストや聖母マリア、聖人らを描いた聖なる画像)を崇拝することは、モーセが神から与えられた十戒の第四章「あなたは自分のために刻んだ像を造ってはならない」第五章「それにひれ伏してはならない。それに仕えてはならない」に違反するかしないか、つまりイコンを崇敬する行為は偶像崇拝にあたるかそうでないか、という問題。 そしてまた、皇帝の妃に帝国内の美女が選ばれた、という真偽のほどははっきりしないお話も、この時代を彩ります。 政情は安定せず国外には敵ばかりの帝国で、いったい何をやっていたのやら。 第3章 改革者皇帝ニケフォロス1世とテマ制 ──9世紀 911年の夏、帝国軍を率いた皇帝ニケフォロス1世はブルガリアの蛮族との戦いで罠にはまり命を落としました。ブルガリアの君主クルムは討ち取った皇帝の頭蓋骨を銀箔の酒杯にし、付き従うスラヴの族長たちに誇らしげにこれで酒をふるまったそうな。帝国側で書かれた年代記では、この皇帝はひたすら罵倒され貶められています。なんとね。 この皇帝は、当時の記録をもとに最悪の暴君として断じられていたのですが、最近の研究によると皇位を争って泥沼化した帝国の醜い騒乱を豪腕で解決し、放漫財政を引き締め、時代に先んじた改革を行ったビザンツ帝国の救い主として、高く評価されているのだそうな。この皇帝の業績とテマ制──軍管区制について解説し、その挫折まで描きます。 第4章 文人皇帝コンスタンティノス7世と貴族勢力 ──10世紀 七人目のコンスタンティノス(コンスタンティヌスのギリシャ語読み)として登極したビザンツ皇帝の話。軍事遠征に出ることもなく宗教問題もあまり関わらなかった彼が歴史に名を残したのは、彼が学識豊かな歴史家であり「マケドニア・ルネサンス」と呼ばれる文化活動を主導したため、らしい。 対外的に多少の出入りはあったものの比較的安定し、文芸復興をなしえたつかの間の時代。 第5章 あこがれのメガロポリスと歴史家プセルロス ──11世紀 「ヴィンランド・サガ」の頃のこと、北欧や西欧の人々が憧れ、聖地巡礼として目指し、そこへの遠征がサガに謳われた帝都コンスタンティノープルの時代。欧州のどこを見ても万を超えてようやく大都市と言われた頃に数十万の人口を誇ったコンスタンティノープルは、同時に軍事的にも政治的にも標的とされますが、ブルガリア、スラブ、イスラムからの攻勢にこの巨大都市は毅然としてその地位を維持しています。内部の争乱があっても、一応安泰。 しかしこの時代、「軍事力のアウトソーシング」がいっそう進むこと共に、蛮族からようやく這い上がった西欧諸国の文化大国東ローマへのコンプレックスが高じて、ビザンツという(西欧世界にとっては)侮蔑語が生まれ、この名前が東ローマ帝国の一般的な名称となってしまったのでした。 第6章 戦う皇帝アレクシオス1世と十字軍の到来 ──12世紀 悲劇の英雄として娘アンナによって書かれた歴史書『アレクシオス』の主人公皇帝アレクシオス1世とは、どんな人物だったのか。さまざまな国難を、西欧の蛮族あがりが「卑怯なギリシャ人」と罵倒する政治手腕で乗り切ったビザンツ帝国の底力とはどんなものだったのか。十字軍という「民族大移動」に、ビザンツ帝国はどのように蚕食されていったのか。 終章 ビザンツ帝国の残照 ──13世紀後半〜15世紀 1204年、世界をイスラムの魔の手から守り、聖地イスラエルを奪還するために生まれた十字軍運動のうち、正式な国際的キリスト教徒のものとしては4回目の十字軍の攻撃を受けて、ローマ帝国の正式な後継者であり世界のキリスト教の総本山である(と称していた)コンスタンティノープルは陥落し、ビザンツ帝国は滅びます。十字軍が去った後に同じ地に誕生した(いわゆる)ラテン帝国は、翌年にはブルガリアに大敗するなど後継者としての力不足を露呈させます。 1261年にコンスタンティノープルはビザンツ勢力によって奪回されますが、国内は王朝内でのいざこざの対応に追われ、商都としての地位はヴェネツィアやジェノヴァに牛耳られ、残ったものは神秘的な 最後に「我らはギリシャ人」としてのアイデンティティは勃興しますが、末期は「都市の女王」コンスタンティノープルを保持するだけの都市国家的なものにまで衰退したのでした。 とどめを刺したのは、オスマン帝国を率いる若きスルタン、メフメト2世。しかしコンスタンティノス11世麾下の守備隊は意外な強靱さで籠城戦を戦いぬいて華を咲かせ、1453年5月29日、最後の皇帝は戦場の中に消えました。 ではいったいビザンツ帝国とはなんだったのか。その都を新たな首都とし、後継者となったオスマン帝国が倒れた後も現代まで存続しているトルコに、どのような遺産を残したのか。 なぜ今著者は、あらたな視点をビザンツ帝国に向けたのか。 最後に著者はこんな言葉を残しています。
ああそうか。だからこの本の中に描いた人々に対する視点が、暖かく感じられたのか。 そういえば、ギボンが「ローマ帝国衰亡史」を書いた頃は、欧州のこの帝国への視点は冷ややかだったらしいのですが、むかし読んだときどう思ったんだろう。いつかまた読み直してみたいな。(2025/09/20) 読書メーターの記録より 読了:2020/11/2 |