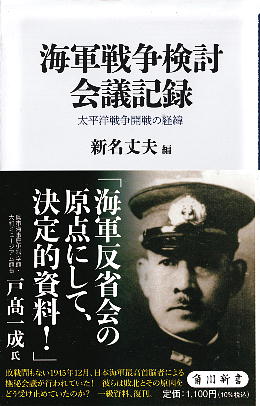 最初に<序に代えて>と題してこんな文から始まります。 最初に<序に代えて>と題してこんな文から始まります。
太平洋戦争が悲惨な敗戦に終わってまもなく、日本海軍の生き残った最高首脳社が集まり、過ぎにし戦争を検討する会議を開いた。敗戦の結果、軍は解体し、陸海軍両省は20年12月から第一(陸軍)、第二(海軍)復員省と変わっていた。会議は第二復員省の肝いりで、20年12月22日から翌年1月22日にかけて4回、特別座談会の名で開かれた。
出席者は、そのつど多少の出入りはあったが、永野修身元帥以下、開戦前夜の軍政軍令の責任者、幕僚など29名。
討議の内容は、日本海軍は何故太平洋戦争に突入したか、という問題であった。戦前、日本海軍は国際協調、平和主義を堅持していた。満州事変、日中戦争にも反対し、対米戦争に何の自信も持っていなかった。それだけに、どうして戦争にまきこまれたのか? 国破れて、海軍は亡びた。つわものたちも四散してゆく、そのときにあたって、過去を反省し、歴史の真相を明らかにしておこうというのであった。
出席者のなかには、戦前から部内ではげしく対立した人も少なくない。そのために討議はかえって突っこんだ追求、かくすことのない告白、きびしい批判となった。(P9-10) |
これは、この本をまとめた新名丈夫氏による文章の最初。氏はかつて「竹槍では間に合わぬ」という新聞記事で東條首相を激怒させたという気骨あるジャーナリストで、主に海軍に繋がりが多く、その中に米内光政元海軍大臣もいたそうです。
この「反省会」は海軍大臣としての米内氏の指示で行われたものですが、その後海軍省の解散により米内氏が民間人となったり、公式の戦史をまとめる管轄がGHQに移ったりしたため、資料の散逸を恐れた米内氏が新名氏に副本を一組託したそうです。これを新名氏は長く保存し、昭和51(1976)年になってから『海軍戦争検討会議記録』(毎日新聞社)として公刊し、これを底本としてこの本をまとめたのだそうな。
ここにもうひとつ、巻末の解説(戸高一成氏による)ではそもそも論として、米内氏の発案ではなく、昭和天皇の求めに応じて始まったことではないか、ともいわれているのです。だからこそ、これだけの重要人物たちを集めることが出来たのではないか、と。なるほどねぇ。
参加しているのは、以下の29名。(あいうえお順・軍人の階級は海軍で終戦時)
井澤豊(海兵58期・少佐)、井上成美(海兵37期・大将)、今村了之介(海兵49期・大佐)、榎本重治(大正2年高文合格、海軍経理学校教官)、及川古志郎(海兵31期・大将)、大野竹二(海兵44期・少将)、岡敬純(海兵39期・中将)、川井巌(海兵47期・少将)、近藤信竹(海兵35期・大将)、澤本頼雄(海兵36期・大将)、柴勝男(海兵50期・大佐)、住山徳太郎(海兵34期・中将)、髙田利種(海兵46期・少将)、竹内響(海兵46期・少将)、立花止(海兵52期・大佐)、富岡定俊(海兵45期・少将)、豊田隈雄(海兵51期・大佐)、豊田貞次郎(海兵33期・大将・軍需大臣)、長澤浩(海兵49期・大佐)、中島親孝(海兵54期・中佐)、永野修身(海兵28期・大将・元帥)、藤井茂(海兵49期・大佐)、古川勇(海兵60期・?)、前田稔(海兵41期・中将)、三代辰吉(海兵51期・大佐)、山本善雄(海兵47期・少将)、吉田英三(海兵50期・大佐)、吉田善吾(海兵32期・大将)
日本の本格的な終戦工作は、サイパン島陥落の責任を取る形で東條内閣を潰したあと、昭和19(1944)年7月22日に誕生した小磯・米内内閣において海軍次官として井上成美中将が就任したとき、部内で戦況を見た井上が
| 「この戦争、だめです。いまから終戦工作をはじめます」(P18) |
と米内にいった時から始まる、といいます。
兵学校校長に追いやられていた井上が中央に戻り、「ラディカル・リベラリスト」の本領を発揮した瞬間か。
そんな事もあり、この「反省会」での井上の舌鋒は鋭い。
単に、自分は悪くない、前から正しいことを自分だけはわかっていた的な、無責任な遠吠えではない。戦前、戦えば負けるから戦わないで国家を存続するために何をなすべきか心血を注いできた人としての、なぜあんな事をしてしまったのか、どうすべきだったのかの声です。
君らは国家の軍隊をなんだと思っていたのか、の声。
井上 国軍の本質は、国家の存続を擁護するにあり。他国の戦いに馳せ参ずるが如きは、その本質に違反す。前(第一次)大戦に、日本が参戦せるも邪道なり.
海軍が同盟に反対せる主たる理由は、この国軍の本質という根本観念に発する、いわゆる自動的参戦の問題なり。たとえ締盟国が、他より攻撃せられたる場合に於ても、自動的参戦は絶対に不賛成にして、この説は最後まで堅持して譲らざりき。
最高会議で幾回も、くり返して追いつめられたが、海軍が最後まで譲らなかったのは、自動的参戦はいやだという一点にありき。
なお同盟反対の理由としては、独に対する国力判断なり。独は世界の強国にあらず。伊は三等国なり。しかも独・伊は、従来幾度か外交上不信行為を反復し来たれり・・・ (P66) |
軍隊とはなんだと思っていたのか、同盟する相手がどれだけのものなのかわかっていたのか、客観的に評価して付き合ったのか、勢いとか見た目で意気投合しただけではないのか、と。こういうことを言うから嫌われるんだろうなぁ。
そもそも海兵(海軍兵学校)に入るほどの優秀な連中ですから、視野を広げて考えればわかるはずなんですが、視野が硬直していったことと官僚化した軍隊組織の中で、過去の成功体験を語り継いで偉くなっていくうちに、思考が硬直していったのでしょう。
これは別に軍隊に限ったことではないのだけれど、それが国の行く末を左右する組織に肥大化していったために取り返しのつかないことになってしまったのでしょうね。この「反省会」では、事あるごとに陸軍の横暴を訴え海軍は良識を持っていたと論じているのですが、そうなのか。海軍の手は白かったと言えるのか。
陸軍のせいで押しまくられてねぇ、でも国内で内戦状態にしてはいけないからなぁ、という論に反論する井上。
竹内 最近、米ハリソン海軍大佐が「日本の海軍は反戦なりしにかかわらず、真珠湾攻撃先頭に立ちたる理由」を米内(光政)大将に質問し、また近衛手記には、従来同盟反対なりし海軍が海相更迭後、急に賛成云々の記事あり。
及川 さき程豊田大将の言の如く、反対理由海相せり。ただし陸軍策動により、海軍反対理由を巧みに糊塗されしやも知れず。
豊田 当時陸海軍の対立、極度に激化し、陸軍はクーデターを起こす可能性あり。ひいては国内動乱の勃発を憂慮せられたり。何といっても軍の両輪、股肱の皇軍として、かかる事態は極力さけねばならぬ。
及川 真に然り。
井上 先輩を前にして甚だ失礼ながら、敢えて一言す。
過去を顧みるに、海軍が陸軍に追従せし時の政策は、ことごとく失敗なり。2.26事件を起こす陸軍と仲よくするは、強盗と手を握るが如し。
同盟締結にしても、もう少ししっかりしてもらいたかった。陸軍が脱線する限り、国を救うものは海軍より他にない。内閣なんか何回倒してもよいではないか。
2.26事件の時、私は米内長官の下、横須賀鎮守府参謀長で、陸軍が生意気なことをやるなら、陛下に「比叡」に乗っていただく積もりで、東京にも直ちに陸戦隊を出し、もし陸軍が海軍省を占領し、中央がだめになったら、長官に全海軍を指揮してもらって、陸軍に対抗する決心なりき。兵学校長の時も、士官学校生徒から兵学校生徒に、陸海軍仲よくせねばならぬとの文通しきりになりしが、自分は校長の責任において両校生徒間の文通を禁止せり。(P77-78) |
陸軍はろくでもないよね、でも表だって対立すると国内が乱れ陸軍が暴走するかも知れないから、反対しないで仲よくしておかないといけないよね、という事なかれ主義の先輩方に噛みつきます。喧嘩してでも国をあやまる政策には反対すべきだ、陸軍なんぞと仲よくする必要はない。
なるほど、嫌われる訳だ。
政治の話、国際政治の話、そして軍としての用兵論、戦備。ことごとく俎上に挙げて論じ合う話は、戦争が終わった直後という時代を考えると、歯がゆいところ、ならどうしてそこで止まっていたのか、などいろいろ思うところがあります。
これはまァ仕方がないか。

井上成美
1889/12/9-1975/12/15 |
日本の海軍軍人。最終階級は海軍大将。
海兵37期のクラスヘッド。横須賀鎮守府参謀長、海軍軍務局長、航空本部長、第四艦隊司令長官、海軍兵学校長、海軍次官などを歴任した。 |
開戦時において、海軍としてはすでに日米の兵力差、経済力差、資源の差、人口比など、すでに何もかも分かっており、勝てる訳がないと皆が思っていた。
ではなぜ開戦に反対できなかったのか。
なぜ「海軍は、対米戦争はできない」と政府にいえなかったのか。
東郷平八郎の呪縛とは、何だったのか。
ここで語られ、明かされたのは、読んでいて歯ぎしりしたくなる歴史の流れでした。
後半1/4程の量で、井上成美が航空本部長を辞して第四艦隊司令長官を拝命したとき、後任の片桐英吉中将に残した「申継」が載っています。1941年8月のもの。
ここにおいて井上は、海軍の空軍化を主張しています。
なぜその論が生まれたのか。
日本海軍の長年の方針は、対米戦の戦略を艦隊決戦による大海戦勝利に置き、そのための漸減作戦と大艦巨砲主義に基づく一点強化思想。量を質で補えという発想と、過剰な精神論。
井上はこれに論理的な反論をし、その上で現時点でもしアメリカに対抗するなら日本海軍を空軍化させ、潜水艦を通称破壊戦に専念させよ、と説きます。
このロジカルなところが、いかにも井上成美。
そしてその凄みは、もっと先を見ていたこと。
海軍善玉説の根源、と評する人もいるそうですが、こんな考えもあり、とすべきか。(2025/10/02)
読書メーターの記録より 読了:2025/9/6 |



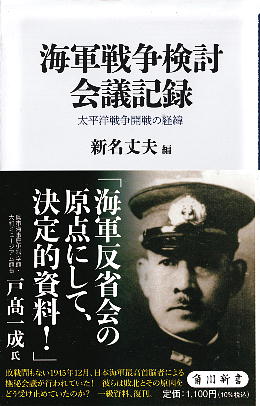 最初に<序に代えて>と題してこんな文から始まります。
最初に<序に代えて>と題してこんな文から始まります。