トップへ戻る  作家/分野 一覧 |
|
 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 書 名 | 翻訳者 | メ モ | |
|---|---|---|---|---|
| D039-001 | 白薔薇と鎖 | 和爾桃子 | 英王ヘンリー八世の時代の殺人事件 | |
| D039-002 | 教会の悪魔 | 和爾桃子 | 英王エドワード一世時代の陰謀 | |
 |
|---|
| 管理番号:D039-001 | 33 歴史小説・ミステリ | 出版社:早川書房 | |||||||
| 書名:白薔薇と鎖 | サー・ロジャー・シャロット<1> | ISBN978-4-15-001785-9 C0297 | |||||||
| 原題:The White Rose Murders(1991) | 翻訳者:和爾桃子 | ||||||||
| ハヤカワ・ミステリ 1785 | 価格:1300Yen | ページ数:280P | 本のサイズ:ポケット・ブック判 | ||||||
| 初版発行:2006/3/15 | 購入: | 装幀:勝呂 忠 | |||||||
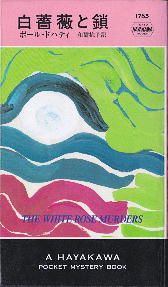 時は16世紀前半。舞台は混迷の時代が続くイングランド。主人公はロジャー・シャロットという無頼漢、1502年生まれ。 時は16世紀前半。舞台は混迷の時代が続くイングランド。主人公はロジャー・シャロットという無頼漢、1502年生まれ。物語はこのロジャーが、功成り名を遂げてガーター勲爵士サー・ロジャー・シャロットとして荘園の領主におさまり、90歳という齢を重ねながらも肉欲はいまだに現役のろくでもない爺さんとなったのち、若き日々の冒険を「掛け値なしの真実」として口述筆記させるという体裁を取ります。 当時イングランドは、1485年のボズワースの戦いで薔薇戦争と呼ばれた壮絶な内戦が終了して国内の二つの勢力が壊滅したのち、漁夫の利を得たヘンリー・テューダーが王位に就いてテューダー朝が開幕したものの、その息子が父王の死を受けて1509年にヘンリー八世として即位した政情不安定な時代。ヨーク家のリチャード三世を敗死させて簒奪者として罵っていますが、血筋から言ったらヘンリー七世の方が遙かに簒奪者にふさわしい経歴です──が、勝てば官軍は世の習い。 しかも周囲の諸国はというと、困った事にこの時代の欧州はあちこち火種がくすぶっています。 北方のスコットランドは、イングランド王家とは血筋的に強い結びつきがありながら対立していた仲。フランスとの盟約のためにイングランドと戦わざるを得なかった名君ジェームズ四世がフロドン(フロドゥン)の戦いで敗死したものの、その妻マーガレット・テューダー(ヘンリー八世の姉)は両国の間にあって不穏な状態。 大国フランスは、病弱だったルイ12世の死後に野心を持った娘婿がフランソワ一世(在位:1515-1547)として即位してフランスの軍事・外交・文化を伸張させて「フランス・ルネサンスの父」と呼ばれています。 ハプスブルク家第三代神聖ローマ帝国皇帝であったカール五世(皇帝在位:1519-1556 スペイン王在位:1516-1556 イタリア王・ローマ皇帝在位:1530-1558)は、イタリアとスペインの覇権を握ってカトリックによる中世的キリスト教帝国を目指す覇王。 オスマン・トルコでは大帝の誉れ高きスレイマン一世が、オスマン帝国第10代皇帝(在位:1520-1566)として対外戦争にことごとく勝利してオスマン帝国を最盛期に導いています。 こんな時代背景の中ですが、物語はイングランドとスコットランドの間で進行します。 出だし、スコウズビーという医者へのロジャー・シャロットの復讐から始まります。このヤブ医者の薬が母親を殺したという恨み。しかし盗みで捕まった裁判の治安判事がスコウズビーの兄貴で、絞首刑を宣告されます。そこを救ってくれたのが、ベンジャミン・トーンビー。かつて 法廷書記だったベンジャミンにたいし恩義を感じたシャロットは、この一見浮世離れしたボンボン的な青年になぜか惚れ込み、これ以後ベンジャミンの従者兼相棒となります。 このベンジャミン(とシャロット)を呼び出したのは、今をときめく権力者トマス・ウルジー枢機卿。ベンジャミンは実はこの(現時点で)国王の寵臣であり国家の重鎮である宰相の甥なのですが、いろいろ使って見てこの甥っ子は役立たずではないかと疑われ始めているのでした。
とはいえ信頼できる手駒があまりいないのか、ウルジー枢機卿はベンジャミン(とシャロット)にある任務を与えます。 いまだに野で不穏な様相を漂わすヨーク党(つまり薔薇戦争の残滓)は、リチャード三世の旗印である白猪にちなんで ここの経緯は、お話としても歴史的に見てもあちこち突っ込みどころがあります。そう、歴史上の欺瞞、つまり主幹的なタテマエですから当たり前なのですが。 この陰謀の流れのキーとなる人物が逮捕されています。故ジェームズ王の元侍医、アレクサンダー・セルカーク。ロンドン塔の一室に監禁されているそうな。情報を得るためならどんな拷問も辞さない情勢なのですが、なんと正気を失っているらしい。 心神衰弱のてい。意味不明の詩を書き散らし、ぼんやり独房の壁を見つめ、泥酔と泣くのを交互に行うだけの状態で、まったく会話が成り立たない。なにか知っているはずなのだが尋問しようがない。 そこでウルジー枢機卿は、一見役立たずの甥のことを思い出したのだそうな。そしてこう考えた。かつてセルカークを逮捕し、情に負けて逃がしてしまったベンジャミンなら、その(間抜けだが優しい)人柄でセルカークの好感を得ていることもあり、なにか情報を得ることができるかもしれない、と。 シャロットとしては罠の匂いがぷんぷんするのですが、ベンジャミンが無邪気にその命を受けてしまったのだから仕方がない。 二人は、まずセルカークの尋問に当たります。 ところがなんと警戒厳重なロンドン塔の、分厚い石の壁の独房の中で、このセルカークは毒殺されてしまったのでした。謎の詩(下)を残して。
窮地に陥ったベンジャミンとシャロットの二人。ともかく、枢機卿の名代としてこの事件の捜査に当たることはできます。これに失敗すれば、よくて失脚。悪くすれば命もない。 やがて、第二、第三の殺人がおきます。どれも、密室状態での犯人も犯行方法もわからない。 この状況の中で、最初青っちろい気弱なインテリかと思われたベンジャミンが、後半どんどん存在感を増していきます。命を張る度胸もあるし、窮地で脳髄をふりしぼって考える意欲もある。泥臭い仕事も辞さない。 自惚れるだけの行動力も知性もあるシャロットと上手く噛み合います。面白い。 イングランドだけでなく、スコットランドからフランス、パリまで股にかけた捜査は、どう進展するのか。 原題は〝The White Rose Murders〟で、これは明らかに白薔薇を記章としたヨーク家に絡む殺人を示します。邦題の「白薔薇と鎖」は、さらに一歩踏み込み、もう一人の王スコットランドのジェームズ四世が、父王の死に責任があるという自責の念により、自らに苦行を課すため鎖を腰に巻いていたという故事を踏まえています。この鎖が、事件にどう関わるのか。 すべてが終わり、この陰謀が白日のもとに晒されて然るべき恩賞を得たのち、ロジャー・シャロットはこう締めくくります。
そう、この物語はシリーズとなり、この本を含め6冊書かれ、ロジャー・シャロットは功成り名を遂げます、多分。 The White Rose Murders (1991) ・・・本書 The Poisoned Chalice (1992) The Grail Murders (1993) A Brood of Vipers (1994) The Gallows Murders (1995) The Relic Murders (1996) しかし、日本で訳出されたのは、現時点でこの一冊のみ。 残念です。面白いのに──かなりマニアックな舞台なのは痛いけど。(笑) (2023/3/23) 読書メーターの記録より 読了:2023/3/19 |
|||||||||||||||||
 |
|---|
| 管理番号:D039-002 | 33 歴史小説・ミステリ | 出版社:早川書房 | |||||||
| 書名:教会の悪魔 | ヒュー・コーベット<1> | ISBN978-4-15-001811-5 C0297 | |||||||
| 原題:Satan in St Mary's (1986) | 翻訳者:和爾桃子 | ||||||||
| ハヤカワ・ミステリ 1811 | 価格:1100Yen | ページ数:184P | 本のサイズ:ポケット・ブック判 | ||||||
| 初版発行:2008/4/15 | 購入: | 装幀:勝呂 忠 | |||||||
 ポール・ドハティの歴史ミステリ処女作です。つまり、上の「白薔薇と鎖」より前。 ポール・ドハティの歴史ミステリ処女作です。つまり、上の「白薔薇と鎖」より前。で、早川書房としては、この二冊でドハティの訳出はあきらめたようです。なんと。 舞台は中世イングランド。王座にあるのは、父ヘンリー三世より継承した権利によりイングランド国王にしてアキテーヌ公、そしてアイルランド卿であるプランタジネット家のエドワード。何世、というおまけがつかないのは、エドワードとしては最初の王なので。 この国王は、息子たちと王座を争ったヘンリー二世(アリエノール・ダキテーヌの旦那)の曾孫、悪名高いジョン王の孫に当たります。父王ヘンリー三世は在位期間(1216-1272)は長かったものの凡庸な王でしたが、エドワード(在位1272-1307)は父王の残した諸侯の不穏な情勢という宿題をこなし、第8回十字軍にも参加し、長身であったため「長脛王 Longshanks」とあだ名される精力的な姿を歴史に残します。 この国王がウェールズを征服したのは1283年。それから7,8年後のある日から、物語は始まります。 冒頭でエドワード王がイーヴシャムの勝利(1265)からかれこれ20年、そして主人公たるヒュー・コーベットが、王のウェールズ遠征(1282-84)で負傷してから7、8年といっていますので、正確な年代は西暦1285年頃と思って差し支えないでしょうね。 ちなみにこの時代の日本は、二度目の元寇を撃退したちょっと後の鎌倉時代。 王がイングランドの治安、自らの王権を揺るがせる陰謀について語る場面から始まります。相手は腹心のバース及びウェルズの司教にしてイングランドの法務官ロバート・バーネル。 彼の報告により、 対策として、大法官は王に一人の部下を当てると報告します。この者が失敗したら、もうあとがないと。 という訳で捜査に抜擢されたのが、主人公ヒュー・コーベット。妻子が流行病で死んで数年後、エドワード王に従ってウェールズに行き、王の前で敵襲を受けとめて名誉の負傷をした戦士でした。その功績で王座裁判所の書記に任じられ、ここ数年事務仕事をしています。その彼がなぜか、この事件に抜擢されます。 聖メアリ・ル・ボウ教会の事件とは、金匠ローレンス・ダケットが内側から施錠した教会の内陣で、梁の鉄棒にさげたロープで首を吊っていた事件。この男は、チープサイドでゆすり屋として悪名が高かったラルフ・クレピンを殺し、保護を求めて聖域である教会に逃げ込んだらしいのですが、自殺の姿で死んでいることが翌朝発見されたそうな。 しかしこの事件、政治的な裏があり、ダケットが自殺で死んだはずはない。 コーベットはまずこの事件から捜査にかかれと命ぜられたのでした。
ダケットの妹からの情報により、< で、だ。そのアリスという妖艶な女といい仲になってしまうというのが、ストーリー的に安直じゃないかと思うのですが、これはしかたがないかな。この女を突破口にして謎が明かされる──という流れになるかと思ったらちょっと違った。 なんと実は──という展開は、ありそうなのでちょっと興醒めかな。 舞台をロンドンからケンブリッジ、そしてロンドンへ移し物語は続きます。
悪魔崇拝の儀式とはなんだったのか。 史実を絡めて、異様な物語は一つの決着を見ます。とりあえず終わったけれど、この先の闇は深い。 お話的にはまだるっこしいところ、安直なところがあって残念なのですが、歴史をきっちり勉強した著者の描く中世イングランドの時代劇は、見事です。 この物語はこれを第一巻としてこのまま30年以上書き続けられます。 Satan in St Mary's (1986) ・・・本書 The Crown in Darkness (1988) Spy in Chancery (1988) The Angel of Death (1989) The Prince Of Darkness (1992) Murder Wears a Cowl (1992) The Assassin in the Greenwood (1993) The Song of a Dark Angel (1994) Satan's Fire (1995) The Devil's Hunt (1996) The Demon Archer (1999) The Treason of the Ghosts (2000) Corpse Candle (2001) The Magician's Death (2004) The Waxman Murders (2006) Nightshade (2008) The Mysterium (2010) Dark Serpent (2016) Devil's Wolf (2017) Death's Dark Valley (2019) Hymn to Murder (2020) Mother Midnight (2021) Realm of Darkness (2022) しかし日本では人気が出なかったんでしょうね、この一冊で終わりです。残念。(2023/4/3) 読書メーターの記録より 読了:2023/3/27 |
|||||||||||
