 古本屋をぶらぶらしていて、見つけた本です。 古本屋をぶらぶらしていて、見つけた本です。
イタリアの歴史を、四世紀末に生きたひとりの女性、ガラ・プラキディアから始め、十九世紀後半までの年月を、それぞれの時代に生きた人々の人生を、十話に分けて描写し、たどっていきます。
なぜその間を選んだのか。それはまず、四世紀末が、ローマを中心としたローマ帝国の末期であり、その後長い歴史を分裂した諸国家群として過ごしたイタリアが、一つの国家として統一されたのが1861年の1月だから。すなわちこれは、一つの大きな統一国家を作り上げるまでの、イタリアという世界の身悶えする苦闘の歴史なのです。
その長い時代の遍歴を、作家は人物史という流れを使って、実に軽やかな筆さばきで描いてくれます。最初ちょっと硬い本かなと思ったのですが、読んでいると止まらなくなります。面白い。
 さて第一話は、上に書いた皇女ガラ・プラキディア(Aelia Galla Placidia AD390?-450)の物語。 さて第一話は、上に書いた皇女ガラ・プラキディア(Aelia Galla Placidia AD390?-450)の物語。
彼女は、統一されたローマ帝国を統治した最後の皇帝テオドシウス大帝の長女。大帝の死後、二人の無能な兄によるローマ帝国の決定的な東西分裂の時代を生き、数奇な運命をたどって西ゴート王と短期間の西ローマ皇帝の妻となり、一時は西帝国の女帝の地位にも昇ります。のち皇帝の母となり、ラヴェンナの霊廟(左写真)に葬られます。
第二話は、女伯マティルデ(Matilde di Canossa 1046〜1115)の物語。
前の時代から600年の歳月を経ています。国家としての共同体も、言語すらも分裂した世界の中にあって、キリスト教だけがかろうじて連帯感の砦となった時代。宗教の頂点に立つローマ教皇に並立する世俗世界の頂点が、神聖ローマ皇帝の元にあるとされ、そのタテマエを現実にしようとする皇帝の出現した時代。
マティルデは、トスカーナ伯の地位を父親から受け継ぎますが、その本拠の城があったカノッサの名で呼ばれることが多い。なぜか。それは、波乱に満ちた痛快な彼女の生涯で、その城に滞在した時の教皇グレゴリウス7世が、神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世を破門に処した上に屈辱的な謝罪をさせた歴史的事件、いわゆるカノッサの屈辱があまりに有名だからなのでしょうか。
第三話は、聖者フランチェスコ(Francesco d'Assisi 本名 ジョヴァンニ・ディ・ピエトロ・ディ・ベルナルドーネ Giovanni di Pietro di
Bernardone 1182〜1226)の物語。
自分たちは一切の私物を持たない、ただ神の愛を伝え善行を施すだけ、という若者の一団を迎えて時の教皇は困惑します。その熱情は尊いが、それではあまりに厳しすぎるではないか、というとその先頭に立つ背の低い熱い瞳の青年が答えます。
| 「でももし所有を認めれば、それを守る腕力が必要になりましょう」 (P54) |
のちにカトリック教会最高の聖人の一人とされた、アッシジの聖フランチェスコの若き日の姿。この熱い心を持った青年が、カトリックをどのように変革させたのか。
聖人として崇められながら、あまりにもそのラディカルな思想が聖権力の頂点に立つヴァティカンに忌避されたのか、その名はずっと教皇の名となったことはありませんでした。しかし2013年3月13日に第266代のローマ教皇として立ったフランシスコ教皇は、始めてその名を使います。とはいえその理由は、聖者の教えや信仰ではなく、「環境保護の聖人」としての聖フランチェスコにあやかったのだそうな。
ほう。
第四話は、皇帝フェデリーコ(Federico II Hohenstaufen 1194〜1250)の物語。
父から神聖ローマ皇帝の地位を、母からノルマン=イタリア王国を受け継いだ、ホーエンシュタウフェン家最後の大帝。時代に先駆けた近代的君主として名高いが、その先進性により苦難の人生を生きた人。彼の提唱するイタリア統一国家を希求する「皇帝派(ギベリーニ)」と、既得権を守り分散した小国家の乱立の維持を望む「教皇派(グエルフィ)」との騒乱が、以後のイタリア半島の運命を決めたのでした。
第五話は、作家ボッカチオ(ジョヴァンニ・ボッカッチョ Giovanni Boccaccio 1313〜1375)の物語。
皇帝フェデリーコが世を去ってから80年後、フランス・アンジュー家が覇を唱えるナポリ王国で、若きボッカチオが世に出ます。フェデリーコのいないイタリアで覇を唱える事になるはずだった教皇庁は、西欧諸国やイタリア自治都市群に背を向けられていました。1305年に至って新教皇は、その教皇庁をローマからフランスのアヴィニョンに移すことになります。もはや勢力の中心としてローマに価値は無い。さらに1347年からその翌年、追い打ちをかけるように黒死病がヨーロッパを席巻。それを受け、若き作家は刹那的な快楽を楽しむ「デカメロン」を送り出し、その悔悟の中で世を去ります。
第六話は、銀行家コジモ・デ・メディチ(Cosimo de' Medici 1389〜1464)の物語。
1377年、教皇グレゴリウス11世は教皇庁と共にローマに帰還し、60余年にわたる「教会のバビロニア捕囚」が終わります。フランス人教皇のこの決断により、カトリック世界は沈静化すると思われたのですが、そうはいかなかった。
| その教皇庁との「八聖者戦争」を戦い抜いて、イタリアの「自由」の旗手と自他ともに許すフィレンツェ共和国も、教会大分裂が始まったこの年、暴動と革命の波に洗われていた。かつて皇帝軍との血みどろの戦いに耐えぬいた自治都市が、軒並みに僭主を戴く君主国家に転向していく中で、確かにフィレンツェは頑強に自治共和の旗を掲げて揺るがず、教皇庁を敵に回した後は、ウマネジモ(人文主義、ヒューマニズム)の新思潮を国是とし、自主独立の気概は当たるべからざるものがあったが、その内部には大きな矛盾を抱えていたのである。 (P146) |
この動乱の時代、フィレンツェの事実上の帝王としてこの街に君臨し、世界に誇る都市国家として残したコジモ・デ・メディチは、死後「国家の父」と称えられます。
第七話は、彫刻家ミケランジェロ(Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni 1475〜1564)の物語。
コジモが世を去ってから四半世紀ののち、フィレンツェに君臨するメディチ家の三代目、「イル・マニフィコ(豪華な人)」と呼ばれたロレンツォは、彫刻にたぐいまれなる才能を持った少年に目を留めます。この若き天才、ミケランジェロ・ブオナルローティはメディチ家に庇護され、才能を開花します。しかし時代は再びの動乱の入り口。レオナルド・ダ・ヴィンチ、ジロラモ・サヴォナローラ、ミラノ公スフォルツァ、教皇アレクサンデル6世、チェーザレ・ボルジア、そしてフランス王ルイ12世。
イタリアの凋落の始まりの時代、長寿を誇った万能の芸術家は、何を見たのか。
第八話は、国王ヴィットリオ・アメデーオ(Vittorio Amedeo II 1666〜1732)の物語。
サヴォナローラの登場ののち、キリスト教世界には「新教」という新たな分派が生まれます。聖書の教えに戻れ、組織の腐敗を許すな、という清廉な思想で始まったはずのこの新たな派閥は、キリスト教世界を分断する大勢力に膨れあがりました。そして悪名高き30年戦争(1618〜1648)のすさまじい惨禍を超えた所で、人は気づき始めます。
| これだけ殺し合えば、さしもの宗教的熱狂も冷めてくる。キリストの教えは本来愛であり、憎しみ殺すことではなかったではないかと言う反省も生まれてくる。教養ある人士の多くは宗教的寛容と信教の自由が必要であると言う事を認めざるを得なかった。それに、宗教的対立の舞台裏に民族国家の「国益」の追求があることは、だれの目にも明らかになりつつあった。フランス王室はカトリックであり、その政治を牛耳る宰相リシュリューは人も知るカトリック枢機卿であるのに、フランス軍は新教陣営に参加しているのである。そして問題が国益であれば、妥協は十分可能である。ようやく和解の兆しが生まれつつあった。 (P233) |
それから年月が流れ、大国のはざまピエモンテを統治するサヴォイア公カルロ・エマヌエーレ二世は、ヴィットリオ・アメデーオという息子を得ます。この男がサヴォイア公家、シチリア王位、サルディーニア王位を継ぎ、混乱の中でフランスの軍隊の侵入に耐えますが、ついに力尽いたのでした。
第九話は、司書カサーノヴァ(Giacomo Casanova 1725〜1798)の物語。
ヴィットリオ・アメデーオが死んだのち、トスカーナ大公国を統治した奇妙奇天烈な奇人、メディチ家最後の男ジャンガストーネを描写したのち、今度は別な町に視点が移ります。
| ヴェネツィア共和国。この国ほど華やかな斜陽の光の中に滅びていった国がかつてあろうか。海の女王と讃えられ、アルプスの北の諸大国からも恐れられるほどの軍事力を有したヴェネツィアも、今は衰えてみる影もない。東方航路を独占し、世界の富を集め、ヴェニスの商人の名を高からしめた経済力も、すでに二流の地位に転落して久しい。しばしば全市聖務停止の威嚇を受けながらも教会の暴圧に抵抗し、亡命者に隠れ家を提供し、思想の自由のために抵抗した伝統も、今は昔話に過ぎぬ。イタリア・ルネサンスの掉尾を飾り、ジョルジョーネ、ティツィアーノ、ティントレットら巨匠を輩出して、豊かな色彩を誇ったヴェネツィア美術も、今はローカル文化の地位に甘んじている。 (P261) |
こんな零落したヴェネツィアの最後の輝きの時代を、色事師として一世を風靡したジャコモ・カサーノヴァをアイコンとして描きます。1796年に、フランス革命政府の命を受けた将軍ボナパルトの豪腕によって解体させられるまで、ヴェネツィア政府は何を行ったのか。
第十話は、作曲家ヴェルディ(Giuseppe Fortunino Francesco Verdi 1813〜1901)の物語。
| ナポレオン軍の侵入は、眠りこけていたイタリアをベッドごとひっくり返した。自由・平等・友愛の標語を掲げたフランス革命軍は、たちまちのうちに半島の旧体制を粉砕、チザルピーナ、パルテノペアという耳慣れない名の共和国を南北に設立し、ピエモンテもトスカーナも共和化させ、ローマからは教皇を追い出して市民に共和制を布かせた。イタリアの進歩的文化人は、ナポレオン軍を解放軍と見立てて万歳を叫んだが、その「解放」はイタリア人のためではなく、もっぱらフランス政府の都合とナポレオンの野望に合わせて進展するものであることが、すぐに明白になった。 (P286) |
とはいえ、それだけではない。
| しかし、ナポレオンの侵略は、決してイタリアにとってマイナスでばかりあったのではない。彼の意図はイタリア解放でなかったとしても、彼の行動はこの国を隷属状態から開放するための刺激を与え、その土台を作ったのである。一口でいえば、それは政治・経済・文化の全分野での「近代化」の契機となった。 (P290) |
絶対平和主義、戦争は金を払って傭兵どもにさせ、自分たちは安全な場所から勝手気ままな主義主張を叫んでいればいいというイタリア人気質は、守るべき祖国、統一して他国に対抗できる強い国家、近代的な意味での独立とその上での自由というものの価値を、徐々に叩き込まれ、ゆっくりと変遷していきました。
ナポレオンの最後の皇后にしてオーストリア皇女マリア・ルイジア(マリー・ルイーズ)が、ナポレオン亡き後愛人ナイベルク伯と共に統治していたパルマ公国で見出した一人の若きオルガン奏者は、ジュゼッペ・ヴェルディといいました。粗野な田舎者だったこの気難しく風采の上がらないこの音楽家が、いずれ統一イタリア王国に至る苦難の道の火付け役になるとは、老いたある意味純朴な皇女にはまったく想像がつかなかったに違いない。
イタリア語では、「歴史」と「物語」はとは同じ言葉なのだそうです。イタリアでは、物語るという行為によって過去の時代を紡いできたのだそうです。であれば、歴史をこんな風に語るのも、イタリア的でいいじゃないか。
と、作者は考えたのでしょうか。
こういう、読みやすくて楽しい、しかし奥深い歴史の描き方って、いいですね。 (2013/8/27) |

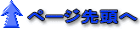
 古本屋をぶらぶらしていて、見つけた本です。
古本屋をぶらぶらしていて、見つけた本です。