 トップへ戻る  読んだ本の分類 |
|
 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |
|---|---|---|---|
| N072-001 | 千年、働いてきました | 老舗大国日本の底にあるもの | |
 |
|---|
| 管理番号:N072-001 | 64 エッセイ | 出版社:新潮社 | |||||||
| 書名:千年、働いてきました | 老舗企業大国ニッポン | ISBN978-4-10-121516-7 C0195 | |||||||
| 2006年11月 角川書店より新書で刊行したものを文庫化にあたり修正・加筆 | |||||||||
| 新潮文庫 の17-1 10972 | 価格:520Yen | ページ数:272P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2018/8/1 | 購入:2023/3/29 | カバー印刷:錦明印刷 デザイン:新潮社装幀室 |
|||||||
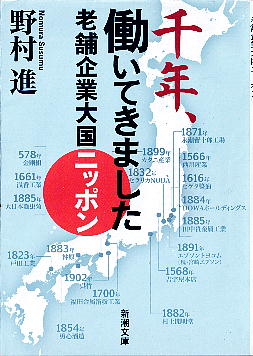 あとがきより、日本以外のアジアの国々を旅しているうち、著者は あとがきより、日本以外のアジアの国々を旅しているうち、著者は
そこで、日本で創業百年以上の会社を600社ほどリストアップし、業種を元にふるいにかけて百数十社を選び、さらにそれぞれの会社を調査して30社程度に絞り込んだそうです。それから取材に応じてくれた21社の企業を拝見してものづくりの現場を見せていただいたそうです。この本では、そのうち19社を取り上げます。 ここからわかるように、基本的に著者が関心を持ったのは「ものを作る」企業です。金融業、農水産業、林業などのような業種でどれだけ創業百年以上経過した企業があるのかわかりませんが、それは「ふるいにかけられた」ということかな。 調べてみるとそして長いあいだ生き残った企業には、ユニークな特徴があることがわかってきましたので、それをまとめたのがこの本。 ただし、元の本が2006年、加筆修正したこの文庫版も2018年刊行ですから、時代的にちょっとずれた事もある気がしますが、これはしかたないな。 世界最古の会社はどこか、というと、すでに知られている通り大阪にある「金剛組」という建築会社です。西暦578年に創業し、飛鳥時代の西暦593年、難波に四天王寺を完成させたのが公式記録にある仕事始めだそうです。「現存する世界最古の会社」にして「世界最長寿の企業」という看板は伊達じゃない。 ほかにも日本には、創業1300年になろうかという北陸の旅館、1200年以上の京都の和菓子屋、1100年以上の仏具店、1000年を超える薬局などが日本にはあります。 創業百年以上ならば、(この本の執筆時点で)十万以上あると推定されているそうです。 こんな老舗が多い国は、アジアでは日本くらい。実は世界でも日本くらいなのです。 欧州には「エノキアン協会」という家業経営歴200年以上の会社のみ加入を許される組織があり、この加盟者の中で最古の企業は、1369年設立のトリーニ・フィレンツェという金細工メーカーで、創業650年に満たない。しかし日本にはこれより古い店や会社が百近くあるのです。これはどういうことなのか、著者は理由を考えたそうです。 ※2025年現在の「今」の時点で補足しますと、まずエノキアン協会は ①創業以来200年以上の社史を持っていること ②創業者の子孫が現在でも経営者、もしくは役員であること ③家族が会社のオーナーもしくは筆頭株主であること ④現在でも健全経営を維持していること ということを条件としています。金剛組は現時点では②③条件に合致していません。また執筆時点以後、日本を含む非欧州の会社もこれに参加できることになり、現時点でこの協会内における最古の会社は「法師(株式会社善吾楼)旅館 創業718年」で、「トリーニ・フィレンツェ」は何らかの条件ではねられたのか、リストに入っていません。 取材した企業は以下の通り。
韓国には「三代続く店はない」という言葉があるようで、百年以上続いている店舗や企業は一軒もありません。社会主義化した北朝鮮は言わずもがな。台湾では1905年創業の彰化商業銀行があるばかり。中国にはさまざまな百年以上続く企業がありますが、社会主義体制下では株式会社という民間の組織形態は認められていないので、厳密に言えば設立百年以上の会社はないのだとか。香港で百年以上となると英国系のものになります。その他アジアを見渡すと、植民地主義のためか民族資本の老舗など育ちようがなかった歴史が見えてきます。植民地化を免れたタイでも、同じ流れが見えます。 あ、韓国で思い出したのですが、金剛組をこの本のエピローグで取り上げており、ここで英国の「エコノミスト」誌が金剛組の創始者を「コリアン」と明記したとわざわざ書いています。金剛組の方々は1500年の経っているのに、朝鮮よりの渡来人の末裔といまだに自称されているのでしょうか? 日韓翻訳版に出入りしていたとき、かの国(といっても何度も途絶していまの二国と縁はないのですが)からの渡来者は永遠に韓国人であり在日である、と主張されて辟易したことがあったので。閑話休題。 いまだカースト制に縛られるインドは、家業を継承できる利点はありますが、地縁血縁を越えて全国規模の仕事ができなかったので、個人商店レベルではともかく老舗企業といえるものはありませんでした。 筆者はアジアには「職人のアジア」と「商人のアジア」があるのでは、といいます。 アジアには一代で名を成した商人とか売り込みが買い上げでしたたかに生きる企業は多いのですが、職人と職人仕事が栄えたのはなぜか日本だけでした。そもそも、手仕事の家業や製造業がずば抜けて多い。 そしてもう一つ、大事なことがあります。日本では比較的血縁に縛られない。 中国などでは家業は無能であっても継がせます。そして絶対的な家訓により路線変更の自由がない。しかし日本では、腕が悪ければ実の息子であっても廃し娘に婿を取って家業を継がせることがあたりまえ。娘がいなければ赤の他人でも育て上げた弟子に継がせます。だから継続するのではないか。 そしてもう一つ、「職人のアジア」と「商人のアジア」に加え、「削る文化」と「重ねる文化」の違いもあります。 削りに削って木の中にいる仏を浮かびあがらせる日本の仏像と、粘土や装飾を塗り重ねて仏のかたちを造ろうとする日本以外のアジアでは、基本的な考え方が異なっています。 それが、科学技術の時代になったとき、軽薄短小と言われる日本式を生みだした「削る文化」を守った「職人のアジア」なのではないか。 日本の特質はまた別なところにも見られます。 「老舗の土台を築くのは、三代目あたりの養子」という言葉があるそうです。筆者は定説とまで言っていますが鐵太郎が初耳だったことはともかく、これは日本の老舗と呼ばれる組織の特徴なのだそうな。 老舗とは確かに一族経営が多いのですが、長男がいても養子に迎えた娘婿を後継者に据えることが珍しくありません。携帯電話のバイブ機能を開発した田中貴金属工業など、いまの社長は一族の一員ではありますが創業家とは血縁上まったく無関係なのだとか。
そういう考え方もあるなぁ、といろいろ腑に落ちるところがあった読後感でした。 とはいえ、最初に刊行されたのが2006年、加筆訂正されて文庫化されたのが2018年です。コロナ前ということは別としても(これだけでもかなり大きなパラダイムショックなのですが)、あの頃はまだ明るい希望の目をむけていた、あるいは、この国の未来を信じ誇れる思いをぶつけても違和感のない時代だったんだな、と思ってしまいます。 なんか、悲しいな。 鐵太郎としては、いま世界に伍して、この国の底力はまだまだ枯渇していないし、この国民の能力は信頼するに足るものだと思っていますが、そう思わない人が多くなったな、と嘆かわしく感じています。 人の足を引っ張ること、暗い面ばかり見ることをやめて、元気な日本が戻ってきてほしい、というのが、皮肉ではあるけれどもう一つの読後感でした。(2025/6/1) 読書メーターの記録より 読了:2023/7/4 |