 トップへ戻る  読んだ本の分類 |
|
 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 書 名 | 翻訳者 | メ モ | |
|---|---|---|---|---|
| T095-001 | ハプスブルク帝国1809-1918 | 倉田 稔 | ちょっと文は古いけど面白い歴史書 | |
 |
|---|
| 管理番号:T095-001 | 53 史書・編年史 | 出版社:筑摩書房 | |||||||
| 書名:ハプスブルク帝国1809-1918 | オーストリア帝国とオーストリア=ハンガリーの歴史 | ISBN978-4-480-51062-4 C0122 | |||||||
| 原題:The Habsburg Monarchy, 1809-1918: A History of the Austrian Empire and Austria-Hungary(1941-1947) |
翻訳者:倉田 稔 | ||||||||
| ちくま学芸文庫 テ15-1 | 価格:1600Yen | ページ数:560P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2021/8/10 | 購入:2021/8/12 | カバーデザイン:大倉真一郎 装画:19世紀ハプスブルク帝国紋章 |
|||||||
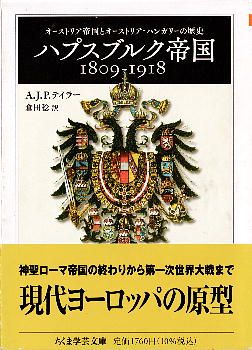 上掲した経歴でわかるように、著者は既存の歴史解釈に迎合する人物ではなく、反骨心のある歴史学者です。それがこの本の流れにどう影響しているのかよくわかりませんが、素人歴史好事家として読んでいて思ったのは、読者に迎合しない人だな、ということ。 上掲した経歴でわかるように、著者は既存の歴史解釈に迎合する人物ではなく、反骨心のある歴史学者です。それがこの本の流れにどう影響しているのかよくわかりませんが、素人歴史好事家として読んでいて思ったのは、読者に迎合しない人だな、ということ。序文において、著者はまずこれが1941年に刊行した同名の本を書き換えたもので、前作のほぼ半分の分量である、と言います。そして、内容の変更したところをふたつあげています。 ひとつは、オーストリアの外交政策を詳しく記述することで、第一次世界大戦を引き起こした原因のひとつとなったハプスブルク家の政治を描く必要があったこと。 もう一つは、「自由派への幻想」に支配されていたことからの修正ということがあります。これは、あるべき未来を規定して、そこに至る道筋になったことならなかったことを批判する姿勢とも通じます。最たるものが、民族運動は人民運動であったという20世紀までの思想的傾向です。 この結果としてここで描かれたハプスブルク帝国とはどういうものなのか。 翻訳者の そうして、「訳者はしがき」をこういう文章で締めくくりました。
ソヴィエト連邦が存在し、シュチェチン=トリエステ ラインの東側は共産圏だった時代の概念が今通用するのか。 過去に描かれたそのまた過去の歴史解説をどう読むか、まずここに注意する必要あり、かな。 とはいえ、 第一章 王朝 第二章 民族 第三章 旧絶対主義、メッテルニヒのオーストリア、1809〜35年 第四章 三月前期 第五章 急進派の暴動、1848年の革命 第六章 自由派の時期、憲法制定議会、1848年7月〜49年3月 第七章 新絶対主義、シュヴァルツェンベルクとバッハの体制、1849〜59年 第八章 連邦主義と中央集権主義との闘争、10月特許状と2月勅令 第九章 立憲的絶対主義、シュメアリングの体制、1861〜65年 第十章 古きオーストリアの終わり、1865〜66年 第十一章 二重帝国の成立、1866〜67年 第十二章 自由派の集落、オーストリアのおけるドイツ人の優勢、1867〜79年 第十三章 ハプスブルクの復活、ターフェの時代、1879〜93年 第十四章 混乱の時期、ターフェからバデーニへ、1893〜97年 第十五章 1867年以降のハンガリー、カーロマン・ティッサとマジャール人ジェントリー 第十六章 民主主義の装い、ハプスブルク帝国の小春日、1897〜1908年 第十七章 暴力による解決、1908〜14年 第十八章 暴力の装い、ハプスブルク家の終り、1914〜18年 エピローグ 王朝なき人民 という豪華な章立てで語られるハプスブルク家──オーストリア帝国の歴史は見事です。 なぜ内容について書かないかというと、書けばきりがないから。 たとえば、オーストリアは辺境の田舎の国ハンガリーを併合し、その統治に骨を折ったというふうになんとなく理解していたのですが、実はまったく異なり、ハンガリーとはハプスブルク帝国の中で最も広い領域と高い文化、産業を持ち、帝国の中で確固たる地位を持っていたということとか。 うん、書くときりがない。 とはいえ、不満もあります。内容のひとつひとつは面白いんだけど、記述や言葉遣いが煩雑すぎて読むのが結構苦痛。 翻訳が悪いのかもしれませんが、原文の面倒くささに問題があるのかな。 でも、学問として学ぶんじゃなくて歴史を楽しむものとして、良い本です、これ。(2025/5/2) 読書メーターの記録より 読了:2021/10/21 |