 トップへ戻る  読んだ本の分類 |
|
 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |
|---|---|---|---|
| Y048-001 | 地図をつくった男たち | 幕末から始まった日本の地図作りの歴史 | |
 |
|---|
| 管理番号:Y048-001 | 64 エッセイ | 出版社:KADOKAWA | |||||||
| 書名:地図をつくった男たち | 明治測量物語 | ISBN978-4-04-400718-8 C0125 | |||||||
| 角川ソフィア文庫 I168-1 | 価格:1040Yen | ページ数:334P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2022/10/25 | 購入:2023/1/1 | カバー図版:1万分の1地形図東京近傍12号「四谷」(明治42年測量図)、 台湾新高山(玉山)における一等三角測量隊の様子 カバーデザイン:大武尚貴 |
|||||||
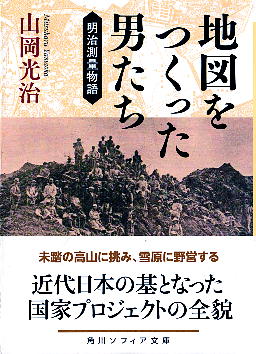 はじめに と題された序文で、平面測量原図の思い出と作るための手順が語られます。そして地図とはどういうものなのか、地図を作るとはどういう事なのか、地図を作るために育てられる測量技術者とはどういうものなのか、説明されます。 はじめに と題された序文で、平面測量原図の思い出と作るための手順が語られます。そして地図とはどういうものなのか、地図を作るとはどういう事なのか、地図を作るために育てられる測量技術者とはどういうものなのか、説明されます。著者の行ってきた地図製作の作業の一端を語って、このように結びます。
地図作りの土台となる「測量」という言葉を作ったのは、江戸中期の儒学者である 天をはかることを「測る」とし、地をはかることを「量る」と使い分けているこの言葉をつづめて、地球上の位置を求めることを「測量」と読んだのだそうな。 とはいえ当時はまだその言葉で天や地をはかることが一般的になった訳ではなく、そもそも天に規準を求めて位置情報を得る発想すら一般的にはなかったとのこと。つまり、地図の統一的な縮尺がなく、北の方向を合わせる発想もなく、まして緯度経度を規準にした地図を作る発想がまだなかった時代でした。 紆余曲折ののち、これらをすべて統括し、実際の測量を元に「天に規準を求め、地を量る」日本全図の作成が、1800年に伊能忠敬によってなし遂げられます。これが本格的な測量地図作成の嚆矢となります。 ここから、測量の歴史、和算・天文暦学の歴史、測量技術の歴史、そして明治の陸軍による陸地測量の歴史が語られます。 陸軍以外、国土の正確な測量及び正確な地図の必要性を認識していなかったという明治初期の時代の背景が面白い。 しかしその陸軍でさえ、測量地図の作成にあたって何らノウハウを持っておらず、一から始めなければならなかったのでした。しかも、明治の陸軍教育としてではなく、最初は徳川家が移封された静岡藩(駿河府中藩)の沼津兵学校など、各藩ごとの教育期間として始まります。 こうして、測量技術の進歩と地図作りの進歩、そのために心血を注いだ先人たちの歴史が語られます。 著者・山岡氏の先輩たち・同僚たちの苦闘ですから、描写にも力が入ります。 語られる内容は多いのですが、たとえば河川航路で重要な河川水面高の基準点について。
地形図から地図へ。 細心の注意を払って作られる地図。日本各地の深山幽谷をくまなく測量する苦労。
測量登山の話も、むろんあります。となると最大のネタはなんと言っても、新田次郎氏により書かれのちに映画化された「 これを主導し、最初に劔岳に登頂した測量官の
また戦場に送られた測量技師たちの物語もあります。 戦争と言っても、太平洋戦争だけではありません。幕末から始まった測量の歴史から、日清戦争、日露戦争と進む中で、新たに日本領土となった土地の測量だけでなく、外国領であっても測量し地図を作る必要ができたとき、さまざまな身分の測量官、測図手たちが「外邦図」を作成したのでした。
その他、測量官たちの生活や苦労などが淡々と書かれ、第19章 友の血で描かれた地図が、赤い焔と化して消えていく では、決死の覚悟で想像もつかない苦労をし、文字通り友の血で作り上げた「外邦図」が、太平洋戦争の終結と共に焼却されていった時代を振り返ります。 そしてそのために危険を顧みず地図を作成した技術者の行動は語ることを許されなかったことも。 戦後、フランス式からドイツ式へと変遷した日本の測量地図技術は、アメリカ式の合理的な地図作成方法へと転換しました。この結果、山岡さんは、地図の中に見られる「かきたてるもの」がなくなった、といいます。 アメリカ式の地図記号を取り入れた結果、日本で発展したわかりやすい地図記号が失われてはいないか、と。 「地形図から送電線の表示がなくなる」ことなどを含め、デジタル時代、ネット時代になってさらに、地図から視覚的に土地の情報がなくなっていないか。 なるほどね。地図を作る歴史を現場に立っていた専門家が書くと、こういうものになるのか。いいね。(2025/08/02) 読書メーターの記録より 読了:2023/5/27 |