トップへ戻る 読んだ本の分類 I・アシモフに戻る |
アシモフの科学エッセイ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
Ver. 3.05 |
|---|
| 管理番号:A003-011 | 55 技術史・科学史 | 出版社:早川書房 | |||||||
| 書名:空想自然科学入門 | アシモフの科学エッセイ[1] | ISBNなし | |||||||
| 原題:View from a Height(1963) | 翻訳者:小尾信彌・山高 昭 | ||||||||
| ハヤカワ文庫NF21 早川文庫763 | 価格:380Yen | ページ数:336P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:1973/4/15 | 購入:1978/4/24 | カバー:高野紘造 | |||||||
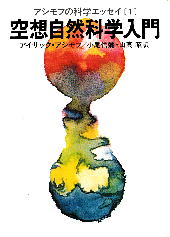
と同時に、アシモフはお節介なほどに世の中に知識を広めて上げようというサービス精神に満ちあふれた人です。 で、こんな科学エッセイを、「S&Fマガジン」に連載し、その後本にまとめました。 実はアシモフの科学エッセイ集としては、これが最初ではないのです。でも日本で刊行されるにあたり、ハヤカワはこれをトップバッターに選びました。意味がある、と思っていいのではないかな。 非常にたくさんの分野にわたっています。勉強家の天才アシモフの面目躍如といったところか。 第一部は、生物学。 生物の大きさの話から始まります。人間は生物の中で大きいのか小さいのか。単純に重さではなく重さの比で、そして対数でそれぞれの重さを比較するのがアシモフ流。出た結果は、人間はどちらかというと大きい生物なのだという結論。 さらに、もっと小さい生物を探り、バクテリアからウイルスまで。で、ウイルスは生物なのか。生命の定義とはなんだろうか。われわれが知っている生物だけの定義でいいのか、ほかに生物の定義はないのか。 第二部は、化学。 SFの古き良き時代に、無知蒙昧な若い作家たちはなにかというと「新元素」を持ち出したそうな。これは、1898年にキュリー博士がウラン鉱石からラジウムを発見したことに始まるのですが、これから新しい元素を発見するレースが始まります。分光器という装置ができて、元素分析はさらに佳境に入ります。物質を加熱したり、日食時に太陽のコロナを観測したり、遠くの星雲を分析したりして、さまざまな新元素が発見されます。大半が幻想として退けられたあとも、残ったものの中にたしかに新元素はあったのでした。その一つが、ヘリウム。不活性気体と呼ばれる奇妙な元素群の、もっとも軽いもの。 これを液化し、固化する奮闘と、発見された超伝導という特殊な状態。完全無欠な元素。 その他、元素に関する化学の話、いろいろ。 第三部は、物理学。 古代ギリシャの「科学」とはたいてい間違っていたのですが、ひとつ現代になってようやく追いついたものがあったといいます。それは、イルカのこと。 イルカは利口な生き物だと、ギリシャの記録は古代から伝えています。またアリストテレスはイルカを魚ではなく、哺乳類に分類したのだという。また音についても、(アシモフが言うには物理学でただ一つギリシャ人が正しかった例だと言うのだそうですが)彼らは正しかったのだそうな。弦の長さと振動数、水谷空気が媒体として存在しなければ音を聞くことはできないこと。音は波動であること。波動は干渉すること。 それから、極小の時間単位のこと。エントロピーのこと。温度の上の限界値。 ついでに指摘。第9章の最後の原注か脚注か知りませんが、
第四部は、天文学。 物理学の教科書に「アシモフの法則」や化学の教科書に「アシモフ反応」が載ることは諦めた、という話から。「アシモフの理論」も「アシモフの仮説」もダメだろうな、と。しかし温度に関してもしかしたら残せるかも、というのが最初のネタ。最高の温度についての仮説。 そして、毎秒あなたの体を100トリリオン(10の14乗)以上貫通しているニュートリノのこと。惑星を構成する元素のこと。太陽系の小惑星帯のこと。ラグランジュ・ポイントのこと。トロイ小惑星群のこと。 地球=月系のラグランジュポイントに核の廃棄物を集めて廃棄所にしようじゃないか、という面白い提案も。 最後、太陽系において生物が発見される天体はどこか、という疑問に対し、アシモフはなんと木星と答えます。なぜか。どのような理屈によるのか。 ちょっと理論は古いけど、やっぱりアシモフの科学エッセイは面白いねぇ。(2019/8/13) 読書メーターの記録より 読了:2019/7/7 |
|||||||||||
 |
Ver. 3.05 |
|---|
| 管理番号:A003-012 | 55 技術史・科学史 | 出版社:早川書房 | |||||||
| 書名:地球から宇宙へ | アシモフの科学エッセイ[2] | ISBNなし | |||||||
| 原題:From Earth to Heaven(1963) | 翻訳者:小尾信彌・山高 昭 | ||||||||
| ハヤカワ文庫NF22 早川文庫779 | 価格:380Yen | ページ数:328P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:1973/6/30 | 購入:1978/6/25 | カバー:高野紘造 | |||||||
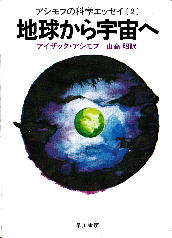 アシモフの科学エッセイ、(日本での)2巻目。 アシモフの科学エッセイ、(日本での)2巻目。テーマは、方向、化学、星、かな? アシモフは、全方位的に興味を持ち、なんでも知ってやろう、なんでも開明してやろう、そしてなんでもそれを話してやろうという、ある意味はた迷惑な人。話がどこにころがるか、わかりませんからね。 さて、第一部では。 まずは、アメリカ合衆国の最北の州、最南の州、最西の州、最東の州はどこか。南北は絶対の規準があるが東西はない理由。 海の大きさ。面積、体積。世界の塩水湖。淡水湖。 ああ、そうか。世界で一番高い山が規準によって三種類あるという話はここか。 一般的には海抜で計ってエベレスト(29,002フィート)ですが、麓つまりその山が聳える平原から計ったら、なんと世界一高い「山」はハワイのマウナ・ケア山という事になるのだそうな。また、高さを地球の中心からの距離と考えるのなら、地球は赤道部が膨れた回転楕円体なので、なんと一番高いのはアンデス山脈にあるエクアドルのチンボラソ山であるのだという。むろん、思考実験的な遊びですが。 島の話。大陸と島の違いとななにか。グリーンランドより小さなものを島と呼ぶこととした場合、この本が書かれた1960年代初めの時点で最も人口が大きい島は、欧米人にはなじみのない名前、「本州」であること。 SF作家の価値は、未来を予測することにあるのではなく、変化する未来が何をもたらすかを考察することにある、という。過去のテクノロジーを大袈裟になぞることが仕事であるはずがない。
第二部。 数学の魅力。「!」記号のこと。配られたブリッジの手札が前と同じものである確率は、5.3644735×1028分の一であること。「アシモフの数列」を発見してみたこと。 フッ素を抽出する方法。「キセノンとフッ素をニッケルの容器の中で混ぜるだけ」が出来るまでの数十年の苦闘と数十人の科学者の犠牲。 化学者を見分ける方法(“unionized”をどう発音するかと、“mole”をどう説明するか)。で。モグラではないmole(グラム分子量)の説明。アボガドロ数、ロシュミット数、理想気体。 19世紀の科学界の思想。「何といったって、僕は、何でもわかるほど若くはないんだから」。不確定性原理。 アインシュタインと不確定性理論。「破れない規則でも見つからなければ破れる」こと。中間子。 ミュー中間子、略してミューオンのこと。ミューオン崩壊。存在するのに検出できないニュートリノ。 第三部。 1日に二回満潮が起きる訳。潮汐力。太陽と月の地球に及ぼす影響は176:1の差があるのに、なぜ月が地球の潮の満ち干を支配するのか。金星や水星が太陽に対して時点を止めていない訳。 歴史の始まる前から多くの惑星に降り注いできた隕石のこと。何十万年ごとに巨大隕石が落下してきた可能性。この隕石、 ケプラーの法則。太陽の支配下にある最遠の惑星とはどのあたりにあるものなのか。ニュートンの介入と、惑星の質量を測定する方法。 現存するもっとも密度の大きな物質より密度の大きなもの。白色矮星。ニュートロニューム。中性子星。シュワルツしルド半径。質量が大きすぎて光すら脱出できない質量体。 ブラックホールという名称は、この本が執筆されたあと、1964年1月18日の『サイエンス・ニュースレター』に初めて載り、一般的には1967年にアメリカ物理学者ジョン・ホイーラーに提唱されたものです。 アルキメデスへのアシモフの敬意のこと。宇宙の大きさとそれがどのように拡大しているか。ハッブルの法則。観測可能な宇宙の大きさ。天地創造となる爆発は、複数回ではなく一回しかなかったのではないか。 そして、最後の言葉。
いま(2019年)の時点ではもう古くなった考えや理論も多いけど、アシモフのオプティミズムって、好きです。(2019/10/4) 読書メーターの記録より 読了:2019/9/4 |
|||||||||||
 |
|---|
| 管理番号:A003-014 | 55 技術史・科学史 | 出版社:早川書房 | |||||||
| 書名:時間と宇宙について | アシモフの科学エッセイ[3] | ISBNなし | |||||||
| 原題:Of Time and Space and Other Things(1965) | 翻訳者:山高 昭 | ||||||||
| ハヤカワ文庫 NF23 840 | 価格:360Yen | ページ数:312P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:1978/9/30 | 購入:1978/10/4 | 表紙イラスト: | |||||||
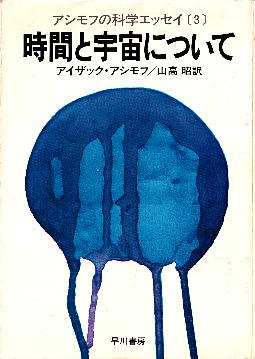 謙虚なふりをしながらそのあふれるばかりの知識欲を遺憾なく発揮した、アイザック・アシモフによる科学エッセイ日本版第3巻。(原著では4巻)テーマは、時間と宇宙とその他。 謙虚なふりをしながらそのあふれるばかりの知識欲を遺憾なく発揮した、アイザック・アシモフによる科学エッセイ日本版第3巻。(原著では4巻)テーマは、時間と宇宙とその他。はじめに という序文で、アシモフはこの本の概略を説明します。 人類は時間の観念を知る唯一の生物らしいこと。であるなら、時間の経過という概念とは何か、時間を正確に取り扱うとはどういうものか、考えなければならない──そしてその延長で、死の不可避性についても考察しなければならない。それがこのエッセイの目的であり、その先も考えよう、と。 第一部 時間と宇宙について とある会合で仲間同士が集まったときに行った、アシモフ自身の軽いスピーチの内容から始まります。一年は何日か、というこの本のネタへつながる話。というより、時間という概念の始まりについて。 欧州において(むろんアシモフは基本的に欧米中心主義です)大きな時間を計る最初の単位が〝一日〟から〝月〟になり、太陰暦が誕生し、月が地球を12周するより地球が太陽を回る方が約11日長いため、閏日、閏月の概念が生まれます。 そして月の満ち欠けなどよりナイル川の増水期の方が重要だったエジプト人が使っていたエジプト暦を元にユリウス・カエサルが制定したユリウス暦によって(紀元前46年が445日になる混乱はあったものの)、一応安定します。そののち1582年のグレゴリオ暦によりさらに細かい修正が加えられたのですが、イギリスとアメリカはこの採用を1752年まで拒否していたために、
その他、まだユリウス暦だった旧ソ連で生まれたアシモフは、本当の日より13日よけいに年を取っているんだなどという小ネタをはさみ、その他の暦の話、緯度の話、経度の話、天界の地図の話、星座の話、黄道十二宮の話などと続きます。むろん占星術などと言うタワゴトには与しないアシモフですので、皮肉なジョークを飛ばすのもお約束。 太陽系の惑星たち、衛星たちとその名づけ方のルール、月は地球の上から観測する限りにおいて自転して「いない」こと、別々な惑星や彗星に観測者がいるとしたらそれぞれの視点で地球の自転周期は一致しないことと「恒星日」のこと、太陽系の惑星それぞれとその衛星たち。 ここでアシモフは惑星と衛星について、真の衛星・捕獲された衛星という区分けを行うのですが、土星の衛星が8個と1個、木星の衛星が5個と7個とした上、
アシモフのこの本刊行以後、衛星テミストが1975年に発見され(て見失われ)、1979年にボイジャー1号によって3個発見されました。その後1999年以後光学機器の発達に伴って発見数は次々増え、2025年現在で95個が確認されているそうです。これを知ったらアシモフはどんな楽しげな悔しがり方をしただろうか。 ロシュの限界と土星の環の話。月の特異な軌道と月と地球の関係についての仮説。重力と電磁力、強い核力と弱い核力のこと。まだ発見されていない 夜はなぜ黒いのかという疑問と、オルベルスの スケールのでかいアシモフの思考散歩ですね。 第二部 その他について 最初の章題は、最初に読んでから半世紀近く経っていますが今でもよく覚えているネタ、〝忘れちまえ!〟です。 職業的な科学の〝 ここで文庫の中でルビになっている「キーバー・アッパー」なる言葉は、浅学にして何を意味するのかわかりません。 これでは科学の進歩に彼アシモフは追いつけない、取り残される一方ではないか。絶望の淵で私アシモフは、先日読んだ昔の本を思いだしたそうな。それは文学修士ニコラス・パイクによる『アメリカ合衆国市民のために書かれた新しい完璧な算術法』という題がついており、初版は1786年ですがアシモフの手元にあるのは1797年の〝増訂第二版〟だったそうな。 この本ではまず、読者が当然記憶すべき、ローマ数字におる50万までの表記とアラビア数字との相関、そしてローマ数字による計算方法が書かれています。そしてさらに読者が精通すべき換算表、たとえば布地の寸法でこんなことが。
さらにクォートやガロン、ファーキン、キルダーキン、バレル、ホグシード、パンチェオン、バット。 そしてそれらを足し算引き算、掛け算割り算する手順。なんとまあ。 アシモフはメートル法の合理性をここで語り、そもそもメートル法のような十新法に基礎を置く単位系に先鞭をつけたのはアメリカ人ではないか、と怒ります。それは、貨幣単位。 アメリカ人は英国の煩雑きわまる貨幣単位(4ファージングで1ペニー、12ペニー(ペンス)で1シリング、20シリングで1ポンドその他)を嫌います。1786年にトーマス・ジェファーソンによってこれが制定されました。
過去の文化や歴史遺産が消えることを残念に思うなら、とアシモフは言う。
そのあとのセンテンス、英語が世界中で使われるようになってほしい ってのは、ちょっとひっかかるところはありますが、世界に共通語があって相互理解を進められるツールとして活用されるべきだ、という論には納得できます。 そして最後の叫び。
そのあとの項目も、多彩。数字の由来と作り方、偉大なるゼロのこと。e=mc2と、1グラムの質量が放出できるエネルギー。アシモフの『われはロボット』が〝 キセノンという変わりものの元素のこと、不活性原子の化合物のこと。あくまで〝結婚〟を拒む三つの気体。アルゴン、ネオン、ヘリウムのこと。 反応促進剤、つまり触媒の歴史、錬金術のこと。化学者たちの何百年もの挑戦。 我が家のインコが死んだ話から始まる、生物の寿命のこと。哺乳類の中で、たった一つの種を除くと(概して小さい哺乳類ほど心臓搏動数が高い、つまり代謝が高いことを含め)、非常に大まかに言って約10億回の心臓の搏動が寿命となるのではないか、という仮説。そしてそのたった一つの例外である人類は、当時の平均余命でいって25億回の搏動に当たるし、最大の寿命を(当時の最高齢で)115歳だとすると40億回になるのだ、という話。 この人の未来への希望と期待は、いつも嬉しくなります。(2025/1/22) 読書メーターの記録より 読了:2020/7/22 |
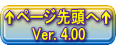 |
|---|
| 管理番号:A003-015 | 55 技術史・科学史 | 出版社:早川書房 | |||||||
| 書名:生命と非生命のあいだ | アシモフの科学エッセイ[4] | ISBN なし | |||||||
| 原題:Is Anyone There?(1967) | 翻訳者:山高 昭 | ||||||||
| ハヤカワ文庫NF24 早川文庫854 | 価格:480Yen | ページ数:432P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:1978/10/31 | 購入:1978/11/18 | カバー:高野紘造 | |||||||
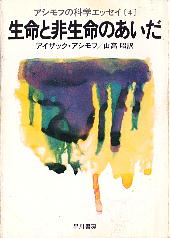 はじめに と題された序章で、SF作家として文筆業に入ったアシモフがかつて駆け出しだった頃、そもそもの生業(?)である大学の科学講師という地位とどう折り合いをつけたのか、生化学の教科書の執筆を分担するようになってから科学ノンフィクション執筆の世界に入ったとき、どう乗り切ったか、について回想します。 はじめに と題された序章で、SF作家として文筆業に入ったアシモフがかつて駆け出しだった頃、そもそもの生業(?)である大学の科学講師という地位とどう折り合いをつけたのか、生化学の教科書の執筆を分担するようになってから科学ノンフィクション執筆の世界に入ったとき、どう乗り切ったか、について回想します。結局アシモフは、謙虚なスタイルの中に隠した断固とした自信の通り、科学と、空想と、SFという分野において名を轟かす物書きになってこの本を書いた訳ですが、それでもまだ1967年のこと。 天才アシモフの驚異的な文筆生活は、実はさらに四半世紀にわたり、世界を席巻したのでした。 生命と非生命のあいだ、という言葉を邦題にしたこの本は、五つの部で構成されます。 第一部 かつて人間の精神とは物質より高い次元にあるものと考えられていた時代があった、と説き始めます。自然科学者たちもこの考え方に則って、精神病などに物質的な対応、治療はできないものと考えられていたそうな。そののち、LSDなどを始めとする化合物が現れ、人体に対し薬物が影響を及ぼしすことが発見されます。これにより、精神とは神秘の対象ではなく生化学の影響下にあると認識されたのでした。 そして記憶、肥満、血液型、化学的個性と話を進め、化学的知見・技術を駆使して人間を作れるのではないか、と筆を進めます。
第二部 可燃性気体である水素について初めて人類が認識した1766年から語り始めます。分解されることのない元素だと思っていた水が、二つの気体の化合物であることが判明し、科学界は驚愕したのでした。ここから、天然ではない新たなエネルギーが人類にもたらされ、さまざまな未来が開けたのでした。1953年に高準位のアンモニア粒子を活性して得られるエネルギー波はメーザーとよばれ、1960年に人工ルビーから発せられた可視光の新しい光はレーザーと呼ばれます。人類が新しく作り出した光でした。これからアシモフ翁が演繹したのは、兵器としての未来ともっと明るい未来。レーザーによるホログラフィーまで。
そして海中の鉱床のこと。地球大気、月と太陽、そして恒星のこと。宇宙を測る尺度のこと。片道切符のタイム・トラベル。 もし〝大爆発〟説が正しければ、という言葉で知る、当時の宇宙研究の最前線。 第三部 宇宙生物学(Exobiology)という言葉は、この時代既にあったそうです。太陽系の中であっても地球外に生物が存在しうるかどうか、誰も確信のなかったこの時代。しかしSF作家でもあったアシモフには確信があり、当時の最先端の研究結果を易しく解説してくれます。 そして太陽系外の知的生物の存在の可能性。コミュニケーションを取るとしたらどういう方法がありうるか。 最後に、空飛ぶ円盤を〝信じる〟か、と何度も質問されることへの苦言。そして当時の彼の言葉。
第四部 1960年代後半のこのとき、アシモフは近未来である1990年の世界を想像します。人口が30億人ちょっとだった1967年から60%は増加しているであろう。都市の人口がますます過密化し、土地や住居が決定的に不足するだろう。大きな肉食獣は絶滅するか、確実にその道をたどっているだろう。危険な昆虫、虫、微生物はもっと駆除され、ジャングルもあまり怖くなくなっているだろう。 スーパーマーケットでは商品はコード化され、客はカードに品物のコード番号を記帳して出すだけで商品は請求書ごとたちまち客の手に入る。原子力の利用が高まり、都市間の鉄道は衰微して小型の自動車が発達し、個人用ヘリコプターの利用が高まり、グランド・エフェクト・カーが本領を発揮する。 爆発的人口増加のせいで、機械化と自動化が極限まで進もうとする。人手不足のため家庭用ロボットが普及しても解消しない。自動化が進むため人々は週に30時間ほどの労働ですむため余暇が増え、退屈という病気が蔓延する。教育では数学や科学の割合が大きくなり、家庭ではテレビ電話が普及する。 そしてアシモフは、2014年の世界博覧会という途方もない未来の予想も試みます。 遙かな未来でなにが起こりうるのか。人類はいつ宇宙に出ていくのか。 アシモフの夢は、明るい未来だけでなく暗い可能性も追求します。その予測はかなり外れましたが、未来の明るさと暗さをアシモフがどう見ようとしたのかは、興味深い。 第五部 SFについて 現実の世界への逃避、としてアシモフはSFの一面を見ます。 虚構の背景による文学、として例に挙げるのは、ファンタジー、社会風刺、SFの三つ。前の二つを論じた後、アシモフはSFについてこう語ります。
しかしその努力は充分に報われるのだ、とアシモフは断じます。優れたSFは人々を遙かな高みに導きうるのだ、と。 アシモフの前向きなオプティミズム、好きです。(2021/08/28) 読書メーターの記録より 読了:2020/9/11 |
|||||||||||||||
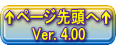 |
|---|
| 管理番号:A003-016 | 55 技術史・科学史 | 出版社:早川書房 | |||||||
| 書名:わが惑星、そは汝のもの | アシモフの科学エッセイ[5] | ISBN なし | |||||||
| 原題:The Stars in their Courses(1971) | 翻訳者:山高 昭 | ||||||||
| ハヤカワ文庫NF25 早川文庫884 | 価格:360Yen | ページ数:320P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:1979/1/31 | 購入:1979/1/31 | カバー:高野紘造 | |||||||
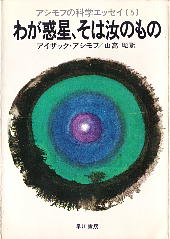
こういう若者の政治メッセージ的なものやヒッピー的なものは、どう考えても当時のアシモフの趣味に合うものではないよな、と思ったら、アシモフの突っ込む先はちょっとちがう方向。 「 のちに友人たちに感想を聞かれ、彼は如才なくこう答えたのだそうな。「ものすごい音量だったよ!」 で、その「
第一部 天文学
イマニュエル・ヴェリコフスキーの神話世界を説明するための科学理論なるものと、その出鱈目ぶりへの怒り。 第二部 物理学 天文学からの流れで、物理学の流れが描かれます。三体問題。ニュートンの力学。ヘンリー・キャヴェンディッシュ。地球の質量はどうやって求められたのか。地球の重さはゼロとなるのか。光速を越える事は可能か。 現状の科学理論を否定し新理論を唱えたいのならば、旧理論を完璧に理解しているのが鉄則であること。勉強もせずに避難する素人の理論は聞くに値しないこと。ドップラー効果と赤方偏移。膨張しているに違いない宇宙とはどういうことか。 第三部 化学 周期律表の話から、これが作られるまでの歴史。メンデレーエフに至る化学者たちのさまざまな考察。ここで暗示された新たな元素の探求の物語。 レントゲンが発見した、のちにX(未知)ではなくなった後もX線と呼ばれた陰極線のお話。原子番号の概念を作り上げ、それでもノーベル賞を授与されず、出征して1915年に戦死したヘンリー・モーズリーのこと。
第四部 社会学 アシモフが科学史ではなく〝まともな〟歴史を書き始めたのは、5年ほど前なのだそうな。その中でさまざまな歴史を興味の赴くまま扱ってみて、1752年こそが、真の意味での科学が日常生活に応用できるものとして確立した年であると確信したそうです。 その年の6月、アメリカ植民地の〝ルネッサンス人〟ベンジャミン・フランクリン(当時46歳)が嵐の日に凧を揚げ、雷の電気をライデン瓶に移したのでした。自然現象を科学の力で解明した瞬間です。 そこから避雷針が生まれ、紆余曲折を経て普及します。
科学がそれまでの世界を変えた、あれこれの業績。 科学者の犯した罪悪についても、一章を割きます。ニトログリセリン、ダイナマイト、原爆。 プロメテウスは人類に罪を与えたのか。科学が人間の手に負えないときが来るのか。 このまま科学が発展し、人口が増えていけば、西暦2000年にはどれだけになるのか。 地球の表面積二億平方マイルすべてがマンハッタンと同じ人口密度になるとすると、ほぼ20兆人だそうせす。現在(執筆当時)の統計による幾何学的増加が続くならば、全人口がその数に達するのに何年かかるか。アシモフはその年数を、585年と計算します。 アシモフの計算によると、西暦2540年代半ばにその数に達することになります。むろんその遙か前に破局は訪れます。 では海洋に生存圏を移すか。宇宙に移すか。いずれにしても、未来には叡智が限りなく必要となる。
読書メーターの記録より 読了:2021/7/22 |
|||||||||||||||
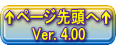 |
|---|
| 管理番号:A003-036 | 55 技術史・科学史 | 出版社:早川書房 | |||||||
| 書名:発見・また発見! | アシモフの科学エッセイ[6] | ISBN なし | |||||||
| 原題:Twentieth Century Discovery(1969) | 翻訳者:山高 昭 | ||||||||
| ハヤカワ文庫NF25 早川文庫884 | 価格:340Yen | ページ数:256P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:1985/7/31 | 購入:1985/7/24 | カバー:空山 基 | |||||||
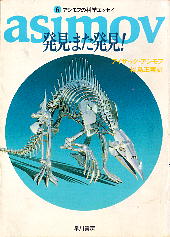 原題〝Twentieth Century Discovery〟という題名の本は、アシモフの英版Wikipediaにありません。別な題で出ているのか、ほかに何か理由があるのか、それは現在(2023年)でもわかりません。内容が、テーマを絞った他のエッセイと異なり、人類の文明のあけぼのから始まったテクノロジーの進化を受け、1960年代後半の視点で20世紀の発見をまとめ、紹介するというかたちになっています。 原題〝Twentieth Century Discovery〟という題名の本は、アシモフの英版Wikipediaにありません。別な題で出ているのか、ほかに何か理由があるのか、それは現在(2023年)でもわかりません。内容が、テーマを絞った他のエッセイと異なり、人類の文明のあけぼのから始まったテクノロジーの進化を受け、1960年代後半の視点で20世紀の発見をまとめ、紹介するというかたちになっています。5つの章で、分野を分けています。 1 六本脚戦争──殺虫剤プロジェクト 人口問題を提示します。1970年を目前として、世界には35億人が生きているが、21世紀になれば世界人口は65億前後になり、アメリカ合衆国だけで3億3千万人になるだろうという。さらに増え続ければ、人類は飢餓と病気に襲われ、戦争と暴動になりかねない、とアシモフは予測します。 実数は、世界人口は2001年61.3億人、2020年78.2億人。アメリカ合衆国の人口は、それぞれ2.8億人と3.3億人でした。アシモフの予想はちょっと多いかれど傾向は正しいな。 この人口増に対応するためには、農地面積には限界があるのだから、害獣から農業生産物や畜獣を守る、なかんずく昆虫から守らなくてはならない。という訳で、アシモフは昆虫との戦いに勝利を得るためのあれこれを考察します。 そのアプローチ、間違っていませんか? と今は思う。害虫・外敵と決めつけて駆除して、それは勝利とはならないんじゃないか。その理屈は近年のアメリカ外交・戦争戦略で破綻したよ。アメリカ人は自然が相手でも戦いや征服が好きなんだね。 2 はじめに・・・・・・ありき──生命の起源 生命とはなにかを問う生物学は、19世紀において二つの発見をします。①あらゆる生物が細胞から構成されている。②生命は簡単なものから複雑なものに進化した。 ということ。 そして細胞を形成する物質を究明する歴史が語られます。細胞はどのように生まれ、どのように発展したのか。そもそも細胞とはなにか。なにで構成されているのか。 いま見るといささか穴があるアプローチですが、かつてはこういう過程で一方方向に進化が進み、生物は発展し、その頂点に人類がいると言うのが一般的な考え方でした。その人類の頂点に、などと言うことまでは、まさかアシモフは考えなかったでしょうけれど。 3 どこまでも小さく・・・・・・ ──物質の構造 1960年代における物質の最小単位を極める科学者の歴史ですな。ドルトンが提唱した原子論から始まり、最小単位である原子を構成するその回の物質の存在の可能性の探究。電子、陽子、中性子。そして中間子。反陽子、陽電子。物質と反物質。 世界を形成する粒子の再構成。レプトン、メソン、バリオン。霧箱、泡箱。そしてクォーク。
4 惑星を見直す──太陽系探査
そうか、アポロ計画の尻すぼみ、その後の宇宙計画の軌道修正の背後にはこのような思想があったのか、と膝を叩きたくなります。アシモフの論が正しければ、です。 でももっと惑星研究は進めるべきではないか、と考えるアシモフは、コペルニクスから始まる太陽系を構成する星々の探求の歴史を見直します。そして、さまざまな(この時代に構想され実証されていた)科学的探査方法を駆使すれば、さらに深い研究そして発見ができるに違いないと断じます。 オプティミストですなァ、アシモフって人は。 5 のぼれ、高く、より高く──宇宙旅行 という訳で、この章ではさらに太陽系を探査するために方法としての宇宙旅行を総括します。 ギリシャ時代のダイダロスから始まる飛びたいという人間の願望を描き、気球、飛行船、そして動力飛行機。「反動式推進」の理論的進化と実践。ロケット兵器。(むろんアシモフが例として上げるのは、アメリカ国歌で歌われる〝ロケットの赤い焔 rockets' red glare〟です)そして、アメリカ人技術者ロバート・ハッチングズ・ゴダート。 むろんツィオルコフスキーの名も挙げています。理論家として。(笑) さまざまな挑戦の最後は、アポロ8号による1968年12月の、有人宇宙船での月面周回と地球への帰還。 1969年のアポロ11号の挑戦は、執筆時にはまだ未来でした。
読書メーターの記録より 読了:2023/1/14 |
||||||||||||
| 管理番号:A003-037 | 55 技術史・科学史 | 出版社:早川書房 | |||||||
| 書名:たった一兆 | アシモフの科学エッセイ[7] | ISBN4-15-050027-4 C0140 | |||||||
| 原題:Only A Trillion(1957) | 翻訳者:山高 昭 | ||||||||
| ハヤカワ文庫NF27 1912 | 価格:320Yen | ページ数:232P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:1985/9/30 | 購入:1985/10/5 | 表紙イラスト:空山基 | |||||||
 この本は、早川書房の「アシモフの科学エッセイ」としては7番目ですが、実は最初に書かれたもので、科学のノンフィクションを書くことの魅力にアシモフが取り付かれた時代のもののようです。これ以後30年以上にわたって書きつづけられた科学エッセイの嚆矢になったもの、といっていいかも。 この本は、早川書房の「アシモフの科学エッセイ」としては7番目ですが、実は最初に書かれたもので、科学のノンフィクションを書くことの魅力にアシモフが取り付かれた時代のもののようです。これ以後30年以上にわたって書きつづけられた科学エッセイの嚆矢になったもの、といっていいかも。はじめに と題されたプロローグでは、5歳の子どもの頃から数を数えることが好きだった自分を紹介し、さまざまな、一見何の役にも立たない「数を数えること」への偏愛を語ります。 そしてプロローグの最後は、こんな文章。
こうして、このエッセイはまず数を数えることから始め、半減期の話、 2025/11/05 実に40年ぶりに再読。これは天才アシモフの科学エッセイの嚆矢となるもので、日本では⑦となっているけれど実は一番最初。ここで書きちらした科学に関するあれこれが、のちにアシモフの文筆のひとつの柱になった、らしい。数を数えること、大きな数について考える事から始まり、統計的な意味での正常とは何かとか、生物を構成する原子とはどうやって組み合わさったとか、ウニと人間の共通点とか。この頃はまだDNAという言葉が今の意味では全く存在しなかったのに、アシモフはすでに別な言葉でそれを描写していたよ。さすがです。 今となっては古い考えも多いのだけど、その根っこの考え方は今も通用します。そうだ、3.11の時、原子炉について、放射性同位体について、統計と確率について、冷静な判断する重要さについて、科学の名を借りたデマについて、なぜある程度的確な判断ができたのか、今にしてわかる。そうだよ、僕はむかしアシモフを読んでいたんだぜ! 読書メーターの記録より 読了:2025/11/5 |
||||||||||