トップへ戻る 作家/分野 一覧 |
|
 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |
|---|---|---|---|
| E022-001 | ハプスブルク家の女たち | 近代欧州の歴史を彩った女性たち | |
| E022-002 | マリア・テレジア ハプスブルク唯一の「女帝」 | オーストリアの中興の祖の挫折と栄光 | |
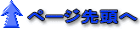 |
Ver. 3.00 |
|---|
| 管理番号:E022-001 | 53 史書・編年史 | 出版社:講談社 | |||||||
| 書名:ハプスブルク家の女たち | ISBN4-06-149151-2 C0222 | ||||||||
| 講談社新書 1151 | 価格:720Yen | ページ数:240P | 本のサイズ:新書 | ||||||
| 初版発行:93/6/20 第29版:12/8/24 | 購入:2013/2/8 | カバーデザイン:中島英樹 | |||||||
 著者の江村洋氏は、1990年に同じ講談社新書で「ハプスブルク家」を上梓したそうです。これが、当時のヨーロッパ共同体(EC)の拡大と重なって時ならぬハプスブルク・ブームが起きた事もあり、意外なほど(江村氏・談)好評を博したのだそうな。 著者の江村洋氏は、1990年に同じ講談社新書で「ハプスブルク家」を上梓したそうです。これが、当時のヨーロッパ共同体(EC)の拡大と重なって時ならぬハプスブルク・ブームが起きた事もあり、意外なほど(江村氏・談)好評を博したのだそうな。その中ではあまり焦点を当てられなかった女性たちに光をあてたのが、この本 なのだそうな。 描かれたのは、こんな方々。青太文字で書かれているのは、この本での名前の読み。それ以外は資料による一般的な読みです。  マリア マリー・ド・ブルゴーニュ(Marie de Bourgougne 1457/2/13~1482/3/27) マリア マリー・ド・ブルゴーニュ(Marie de Bourgougne 1457/2/13~1482/3/27)ブルゴーニュ公家の後継者。のちに神聖ローマ皇帝となったハプスブルク家のマクシミリアンの妻。彼女の死により、ブルゴーニュ家は断絶、その領土はのちにハプスブルク家のものとなり、名ばかりの貧乏貴族だったハプスブルク大公家の隆盛のきっかけとなる。  フアナ (Juana I de Castilla 1479/11/6~1555/4/12) フアナ (Juana I de Castilla 1479/11/6~1555/4/12)カスティーリャ女王。マクシミリアン1世の長男フィリップの妃。享楽的な夫に嫉妬するあまり、精神の平衡をを失ったという。夫の死後、父アラゴン王フェルディナンドによりトルデシャス城館に幽閉され、そこで狂気に陥ったまま約50年生きたといわれる。  マルガレーテ マルグリット・ドートリッシュ(Marguerite d'Autriche 1480/1/10~1530/12/1) マルガレーテ マルグリット・ドートリッシュ(Marguerite d'Autriche 1480/1/10~1530/12/1)神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世とブルゴーニュ女公マリアの長女。 マリアの死後、フランス王の嫡子シャルルの婚約者としてわずか3才でフランス宮廷に拉致され、約十年後にシャルル8世妃となるが、政治情勢により離婚、帰国がかなう。のち、スペインの王太子フアン(フアナの兄)の妃となるが、フアンが1497年に病死すると再び帰国。サヴォイ公国のフィリベール公爵の後妻となるが、1506年に公が病死するとまた帰国し、今度はネーデルラント17州の女総督としてその生涯を過ごす。晩年は兄フィリップの嫡子カールを神聖ローマ皇帝に推挙することに全力を注ぐなどして、ハプスブルク家を盛り立てた。  フィリッピーネ・ヴェルザー (Philippine Welser 1527~1580/4/24) フィリッピーネ・ヴェルザー (Philippine Welser 1527~1580/4/24)アウクスブルクの町でフッガー家と並ぶ名高い豪商ヴェルザー家の娘。皇帝フェルディナンド1世の次男・フェルディナンド、のちのチロル大公に見初められ、秘密結婚。身分の違うこの結婚は当初内外より猛反対を受けたが、のちに父皇帝はこれを許した。しかしこの夫婦の子孫はハプスブルク家の一員と認められず、この結婚はハプスブルク宗家の貴賤結婚の嚆矢となった。  アンナ・プロッフル アンナ・マリア・ヨゼフィーネ・プロッフル(Anna Maria Josephine Plochl 1804/1/6~1885/8/24) アンナ・プロッフル アンナ・マリア・ヨゼフィーネ・プロッフル(Anna Maria Josephine Plochl 1804/1/6~1885/8/24)湖沼地帯ザルツカンマーグートのアウスゼー村の郵便局長の娘。マリア・テレジアの孫、皇帝レオポルト2世の13番目の子であるヨーハン大公に見初められ、貴賤結婚した。仲睦まじかった夫婦は地元民に慕われ、ヨーハンはアルプス王と呼ばれて愛された。二人の間に生まれた長男フランツは、のちメラン伯爵の称号を得る。  マリア・テレジア マリア・テレジア・ワルブルガ・アマリア・クリスティーナ・フォン・エスターライヒ(Maria Theresia Walburga Amalia
Christina von Österreich 1717/5/13~1780/11/29) マリア・テレジア マリア・テレジア・ワルブルガ・アマリア・クリスティーナ・フォン・エスターライヒ(Maria Theresia Walburga Amalia
Christina von Österreich 1717/5/13~1780/11/29)皇帝カール6世の長女。父帝の嫡子が夭折したため、その死後若干23才でハプスブルク家の男系としては最後の君主となる。彼女以降、夫となったロートリンゲン家の皇帝フランツ1世の家名をとって、宗家はハプスブルク=ロートリンゲン家となった。夫のロレーヌ公家とは、貴賤結婚とはいわないまでも家の格に差があったとのこと。政治・軍事に才を持たない(しかし財政家としては非凡だったという)夫に代わり、20年間のうち16人の子を産み育てながら、皇帝としてオーストリア帝国の屋台骨を支えたという女傑。 なお、ハプスブルク家だけでも、マリア・テレジア、マリーア・テレーザ、マリー・テレーズなど、同名の女性は多いので、一般には「女帝」という称号をつけて呼ばれる。 彼女の人物評価は高いものの、その結婚政策に関して、江村氏の評価は辛いようです。  マリー・ルイーズ マリア・ルイーザ(Maria Luisa 1791/12/12~1847/12/17) マリー・ルイーズ マリア・ルイーザ(Maria Luisa 1791/12/12~1847/12/17)皇帝フランツ2世(のちにオーストリア皇帝フランツ1世)の長女。フランス皇帝ナポレオン1世の皇后(後妻)。後にパルマ公国女公。 1811年に嫡子(ナポレオン・フランツ のちのローマ王、ライヒシュタット公)ナポレオンが失脚しエルバ島に流されたのち、メッテルニヒの画策により護衛のナイペルク伯アダム・アルベルトと内縁関係になり、1817年に娘アルベルティーヌ、1819年にのちのモンテヌオーヴォ侯爵となるグリエルモ、その他2人の子をもうけることとなった。 才に恵まれた女性であったらしいのですが、運命に翻弄された生涯でした。 その他、何人もの女性が、あるものは男たちの陰になり、あるものは男たちの上に立って歴史を彩っています。 ハプスブルク家のモットーといわれるもの、「戦は他国にさせておけ、幸いなるオーストリアよ。汝は結婚せよ」という言葉は、この家系の特徴を良く捉えています。面白いね。 江村さんのとらえ方、人物像がちょっと甘過ぎという気もしますが、こんな感じの歴史紹介も、読んでいて楽しい。(2013/6/22) |
 |
Ver. 3.01 |
|---|
| 管理番号:E022-002 | 51 伝記・一代記 |
出版社:河出書房新社 | |||||||
| 書名:マリア・テレジア | ハプスブルク唯一の「女帝」 | ISBN978-4-309-41246-7 C0123 | |||||||
| 河出文庫 え6-1 | 価格:1200Yen | ページ数:400P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2013/9/20 | 購入:2014/1/17 | カバーデザイン:岩瀬聡 カバー写真:アフロ カバーフォトマット:佐々木暁 |
|||||||
 マリア・テレジアが生まれた1717年5月13日、ウィーンの王宮では、イングランドのエリザベス一世、あるいはイギリス連合王国のエリザベス二世と同じ言葉がささやかれました。 マリア・テレジアが生まれた1717年5月13日、ウィーンの王宮では、イングランドのエリザベス一世、あるいはイギリス連合王国のエリザベス二世と同じ言葉がささやかれました。
ここで例に挙げなかったヴィクトリア女王に至っては、生まれたときには王位に就く可能性など誰も考えてはいない、「その他大勢」でしかなかったし。 そんな背景の中で彼女たちは、即位することによって混乱に陥った王国の危機に直面し、それを曲がりなりにも解決し、国家の黄金時代を築いたのでした。 それは運命とだけで済ませられるのか。本人の持って生まれた才覚とそれ以上の不断の努力なくては、それはあり得ない。 マリア・テレジアもそんな一人でした。 サリカ法というものがあります。マリア・テレジアの生きる時代に合っては意味の無い古代の成文化された儀典なのですが、ここには王位には男しか就けないとされています。国により時代により、このルールはいろいろと解釈されるのですが、神聖ローマ帝国の王座はこのルールを厳守します。 マリア・テレジアの父親は神聖ローマ皇帝カール六世。その帝位は祖父レーオポルト一世の後継者で、自らは男子を持たなかった兄ヨーゼフ一世の死により受け継いだものです。父帝は夭折した長男ののち三女を得た皇妃にこれ以上子供ができないことを確認して始めて、とりあえず長女マリア・テレジア、愛称「レースル」に継承権を与えるために、相続順位法を発令して女子でもハプスブルク家の家督を継げるように制度を改めます。この結果父の死後、レースルはハプスブルク家の君主の地位に上がります。 しかし、ここまで何百年もハプスブルク家が独占していた神聖ローマ皇帝の地位は、形式上でも選帝侯による推挙とローマ教皇の承認・戴冠によって成立するもの。千年以上昔に成立したカビの生えたサリカ法による、男尊女卑の化石が、ものを言います。神聖ローマ皇帝は男子であるべし、と。 マリア・テレジアは基本的に平和を愛するひとだった、と著者は言います。伝えられるその紀伝によっても、その認識は間違いではなさそう。しかし同時に、政治・軍事・行政に関する「帝王教育」を受けなかったにもかかわらず、平和はそれを断固たる意志と不断の警戒、そして充分な軍備によって維持できるもの、という当時の世相を正確に理解していたのでした。 カール六世が逝去した1740年からオーストリア・ハプスブルク家が安定を取り戻すまでに、まずオーストリア継承戦争(1740-1748)が起きます。この間にバイエルンのカール七世の神聖ローマ皇帝即位(1742-1745)、マリア・テレジアの夫がフランツ一世として神聖ローマ皇帝即位(1745-1765)という政治的勝利は得られますが、宿敵プロイセンに対する外交革命を経た七年戦争(1756-1763)を勝ち抜いて、始めて安定が得られたのでした。 その間に、夫君フランツの故郷ロートリンゲンはプロイセンに奪われ、永久に戻らなかったなどという損失もありますが、とにもかくにも平和が勝ち取られたことはマリア・テレジアの意志によるもの。 マリア・テレジア以降のハプスブルク家が、ハプスブルク=ロートリンゲンと名を変えたのは、男系が途切れたから。婿の形で結婚した夫フランツの家名を加えて、その名にしたそうな。この夫がいたにもかかわらず、そして夫が正式な神聖ローマ皇帝であるにもかかわらず、なぜマリア・テレジアはその時代でものちの歴史上も「女帝」と呼ばれたのか。 それは彼女がハプスブルク家の当主の地位にあったから、というだけではない。彼女の積極的な意志と手腕、そして夫フランツの穏やかな性格によるものか、己の立場をわきまえた姿勢によるらしい。夫婦は共同統治という形で、事実上マリア・テレジア主導の政治が行われます。  それまでの王位継承問題の歴史を見ていたせいか、彼女は子供を生むことを自分の義務と考えたらしい。女帝としての激務の中の約20年間に、5人の男児と11人の女児を生みます。これによってヨーロッパ各地の王族と婚姻関係を結ぶことができました。 それまでの王位継承問題の歴史を見ていたせいか、彼女は子供を生むことを自分の義務と考えたらしい。女帝としての激務の中の約20年間に、5人の男児と11人の女児を生みます。これによってヨーロッパ各地の王族と婚姻関係を結ぶことができました。これが、必ずしも彼女の思惑通りに生きなかったのは、彼女の責任ではないかもしれない。 しかし末娘マリア・アントニアがフランスの王太子に嫁いだとき、政治センスの欠如した彼女が、悲劇の王妃マリー・アントワネットとしてギロチンにかかったのは、マリア・テレジアの教育による責任と言えないこともない。 その他、彼女の子供たちにはどうも彼女の政治センスが継承されていないところが多い。天与の才は遺伝しないと言う事なのですね、結局。 つまり、英明な君主は一時的なものなのだとすると、その君主が「老害化」したとき、そして後継者が凡庸ならともかく愚鈍だったら、あるいは真面目に働く大馬鹿者だったらどうなるのか。ここに、啓蒙君主よりわずかながらでも民主主義体制の方がアドヴァンテージがあるのかな、と考えてしまいます。ふむ。 そういえば、江村さんの筆致は、優しいね。 年を取るにつれて頑迷固陋の老害化していった(といわざるを得ない)マリア・テレジアを、最後まで優しく描きます。 晩年、亡き夫への墓参を欠かさない彼女の姿を描いたこの場面が、特に。
1780年11月29日午後9時、40年にわたる統治を終えて女帝マリア・テレジアは息を引き取ります。 その晩年に多少の瑕瑾はあったものの、オーストリア及びハプスブルク帝国という多民族国家をあたうかぎり平和に統治した女帝は、名君として今も語りつがれているとか。(2014/5/21) |
|||||||||||