トップへ戻る 作家/分野 一覧 |
|
 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 書 名 | 翻訳者 | メ モ | |
|---|---|---|---|---|
| G030-001・002 G030-003・004 G030-005・006 G030-009・010 |
ブーリン家の姉妹(上・下) 愛憎の王冠(上・下) 宮廷の愛人(上・下) 悪しき遺産(上・下) |
加藤洋子 加藤洋子 高里ひろ 加藤洋子 |
アン・ブーリンとその妹の物語 メアリとエリザベスの王家の争い エリザベスとロバートとセシルの物語 ヘンリー8世と三人の女性の物語 |
|
| G030-007・008 | 白薔薇の女王(上・下) | 江崎リエ | エドワード四世の王妃、エリザベスの物語 | |
| Ver. 2.23 |
|---|
| 管理番号:G030-001・002 | 32 歴史小説・西欧史 |
出版社:集英社 | |||||||
| 書名:ブーリン家の姉妹(上) | ISBN978-4-08-760560-0 C0197 | ||||||||
| 原題:The Other Boleyn Girl(2001) | 翻訳者:加藤洋子 | ||||||||
| 集英社文庫 ク 17-1 | 価格:838Yen | ページ数:488P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2008/9/25 | 購入:2012/4/14 | 装丁:刈谷紀子 写真 Columbia Pictures | |||||||
| 書名:ブーリン家の姉妹(下) | ISBN978-4-08-760561-7 C0197 | ||||||||
| 集英社文庫 ク 17-2 | 価格:800Yen | ページ数:440P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2008/9/25 | 購入:2012/4/14 | 装丁:刈谷紀子 写真 Columbia Pictures | |||||||
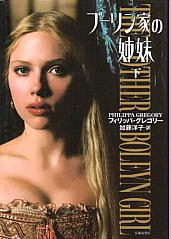 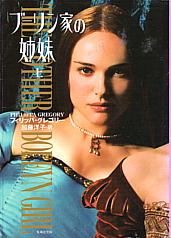 原題は、「もう一人のブーリン娘」。 原題は、「もう一人のブーリン娘」。ブーリン、というと日本ではそんなに有名ではない名前ですが、英国の歴史上では名が知れています。アン・ブーリンという名で。 アン・ブーリンとは、生涯で6人の王妃をめとったイングランド国王ヘンリー八世の二度目の王妃。王の命令で処刑されますが、イングランドの栄光の基礎となったエリザベス女王の母となりました。 この、エリザベス一世の母であるということ、そして悲劇的な最後のため、美化されて印象づけられることも多かったらしい。 アンを日本で言うと誰のような、といったらいいだろう? 淀君? 桂昌院? それとも?
いろいろな記録から探るこの女性の実体は、さまざまな説はありますが、一族ともども王の寵愛を得て正規の王妃を追い落とし、一族の名をあげて出世するためにさまざまな策をめぐらし、陰謀に明け暮れた事は事実らしい。 この上に立って、フィリッパ・グレゴリーはこんな素敵な歴史小説を書いてくれました。 またこの本は英米でベストセラーとなり、これを元に本のカバー写真のように映画になりました。 映画については、ナマはむろんビデオでも見てはいないのですが、是非見てみたい。原作そのままということはあり得ないにしても、どれだけこの本のテイストが映像化されたのかは興味あります。 主人公は原題の通り、アンの妹であるメアリー。 彼女の一人称で、話は進みます。 物語は年代と季節で章を形成していますが、最初の章は 1521年春。 13歳のメアリーは、去年結婚した夫ウィリアム・ケアリーや兄のジョージ、父のサー・トマス・ブーリンらと共に、母方の親戚であるバッキンガム公スタフォードの処刑を見ます。むろん、命令は国王じきじきのもの。当時30歳になったばかりのヘンリー八世。陛下は恩赦をいつ与えるのだろうとやきもきする少女の前で、公爵は断頭台で首を刎ねられます。
メアリーがアンの sister である事はたしかなのですが、史実の上では姉であるのか妹であるのか確認できないのだそうな。英語というか、ラテン語圏の言語の欠陥の一つでが、日本でも天智天皇と天武天皇のこともあり、こう言うことはなかなか確定できないものらしい。 しかし、彼女たちの経歴がはっきりしないと言うことは逆に、時代的に整合しうるものであれば、想像の翼をはためかせて新しい人物像を作り出すことが出来るということ。 メアリーは、12歳でウィリアム・ケアリーと結婚してイングランド王妃キャサリンの侍女となったのち、翌年一歳年上の姉アンがフランス王の宮廷から戻るのを迎えます。それが、第二章 1522年春。 メアリー13歳、アン14歳。そしてブーリン家の三人きょうだいのもう一人、19歳の兄ジョージは、イングランド宮廷で王の侍従として教育を受けています。 彼らに求められたのは、若い王を楽しませること。余暇を盛り上げること。退屈させないこと。 これを彼らは廷臣として貴族として叩き込まれた教育を駆使して、他の貴族の子弟たちと張り合って行うわけです。 その延長として、メアリーの実家であるブーリン家と、その母方の家系であるハワード家は、まずメアリーを王の寝室に送りこもうとしたわけ。 当時の、イングランド宮廷とはこういうものだったのです。 また新興のブーリン家と、名高いが権力はないケアリー家は、ときの有力家系であるハワード家の意のままにするしかなく、ハワード家がアンとメアリーを通して王の寵愛を得て地位や土地財産を得れば、そのおこぼれを得ることができるのですから、自分に益がある限り否やはない。 かくしてブーリン家の三人の兄妹は、叔父であるノーフォーク公トマス・ハワードの指示の元、ハワード家の隆盛のために暗躍することとなります。三人の心、考え、恋などは、まったく意に介されません。 さて、まずメアリーが王の愛人となり、彼の子を産みます。しかしこの子キャサリンとヘンリーは、王の庶子の扱いを受けられるかどうか、それさえも微妙な情勢。 しかし我が子たちを見たときから、メアリーの心が変化します。 才覚でも、知識でも、教養でも、機転でも、なにかしらアンに劣っていることを自覚し、才気あふれて魅力を振りまくアンと異なっているのは意識していたけれど、それなりにライバル心を持っていたメアリーでした。 しかしある日、アンにそっと打ち明けます。もう、宮廷の駈け引きなどに興味が持てないと。
彼らはお互いに、利用し合います。一人の地位が高まれば、遠慮なく他のきょうだいを下僕として使います。父の、母の、そしてそれ以上に叔父の命令には絶対服従します。王妃を敬愛していても、一族の命令ならば彼女を踏みにじるような行為もします。 一族のため、互いのために、人として許されない恐ろしいことも、行う事もあります。 しかし、互いに思いを、悩みを、希望を、未来をなんのわだかまりもなく語り合い、それを親も含めて他人には決して漏らしません。 こんな中で、語られた会話。噛み合っていないのは互いに承知し、価値観が異なっていくことに気づいていても、それでもきょうだいでした。 歴史が語るように、メアリーは王の愛人にはなれても、そこまででした。王の庶子を生んだのかどうかさえ、記録としてははっきりしていません。その二番目の夫との間がどうだったのか、さだかではありません。しかし、ささやかな幸せをつかんだ、と作者は描く。 アンはもっと高みを求めます。正当なスペイン王室から来たキャサリン王妃を放逐してその後釜に座る陰謀のなかで、王妃の地位に上がるまで王に体を許さないという微妙な手練手管を尽くします。その結果、どうなったのか。 面白い。こんな歴史もあったのかも知れない。 この作者は、この時代の別な世界も小説にしたようです。次を読んでみましょうか。 ツイッターで書いたのですけど、この本を標語であらわすと、こうかな。(一部訂正しました、N様) 一番高く上がらなければ、一番下に落ちることはない(爆) これ、ネタバレになるかな? よく考えると悲惨な歴史のはずなのに、爽やかな読後感でしたよ、これ。(2012/7/14) |
|||||||||||||||||
| Ver. 2.23 |
|---|
| 管理番号:G030-003・004 | 32 歴史小説・西欧史 |
出版社:集英社 | |||||||
| 書名:愛憎の王冠(上) | ブーリン家の姉妹 2 | ISBN978-4-08-760587-7 C0197 | |||||||
| 原題:The Queen's Fool(2003) | 翻訳者:加藤洋子 | ||||||||
| 集英社文庫 ク 17-3 | 価格:800Yen | ページ数:400P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2008/9/25 | 購入:2012/4/22 | 装丁:刈谷紀子 写真 Jeff Cottenden | |||||||
| 書名:愛憎の王冠(下) | ブーリン家の姉妹 2 | ISBN978-4-08-760588-4 C0197 | |||||||
| 集英社文庫 ク 17-4 | 価格:800Yen | ページ数:400P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2008/9/25 | 購入:2012/4/22 | 装丁:刈谷紀子 写真 Jeff Cottenden | |||||||
  「ブーリン家の姉妹」からひと世代あとの時代。 「ブーリン家の姉妹」からひと世代あとの時代。何度も妻を変えたイングランド国王ヘンリー八世の没後、王位はただ一人の嫡男エドワードに移りました。これは順当な王位継承。 この物語は、不思議な運命の中でこのエドワードと、その後イングランドの王位に就いた二人の女王、メアリーとエリザベスに仕えた宮廷の道化、ハンナ・グリーンを主人公として進められる歴史絵巻です。 厳密にはエドワードのあとに9日間だけ王位に就き、のちに反逆者として処刑されたジェーン・グレイという女性がいましたが、これは描写はありましたが重要ではないな、どうしても。 中世の時代です。女性には基本的に自立する権利はなく、家長である男の命令に従わなくては生きられない時代。 これは、この旧弊な時代を背景に、スペインの異端審問から逃れてフランス、オランダをさまよい、ようやくイングランドに移り住んだユダヤ人本屋の娘、男の子として生きようとしていた少女ハンナの物語です。
この年、イングランドの王位にあったのは、エドワード、10歳。母はジェーン・シーモア。 長姉メアリーは32歳、母はキャサリン・オブ・アラゴン。 次姉エリザベスは14歳。母はアン・ブーリン。 スペインなまりが抜けない幼いハンナが、本屋である父の使いとしてチェルシー宮殿のサー・トマス・シーモアに本を届けに行ったとき、始めて王女エリザベスを見ました。くすくす笑いながらサー・トマスから逃げまわり、つかまると14歳の少女にはとても見えない挑発的な表情で四十男の愛撫に恍惚となる姿を。 このとき、トマス・シーモアはキャサリン・パーの夫。このキャサリンはヘンリー八世の最後の王妃であり、王の娘たちとただ一人の王子の養育を献身的に行い、王の死後トマス・シーモアと再婚した女性。 つまり、この状況は危険な火遊びなのです。エリザベスという人物を、作者はまずこう描いてみせます。この無邪気な淫乱さが、したたかに粘り強く主役の座を追い求める策士、周囲の望む人物になりきるために不断の努力を怠らない統治者に育っていくさまが、何とも魅力的。 1522年、14歳のハンナは父と共にロンドンの小さな本屋の店を始めます。父オリヴァー・グリーンは、今そう名乗っていますが、元の妹はベルデ。ユダヤ人の本屋、書籍編集者、出版業者。身分は低いけれど、知性と教養が評価される職業。 ユダヤ人である、ということはすなわち、ユダヤ教徒であるということ。ユダヤ人は、当時もヨーロッパのあらゆるところに住み、ささやかなコミュニティを作っていたそうです。彼らは、たいていのところではユダヤ人と分かれば宗教上の理由により差別され、場所によっては改宗を強いられ、あるいは異端として裁かれるため、自分たちの素性を隠すのが普通。グリーン家もスペインではカトリックとしてふるまい、イングランドではプロテスタントとして生活しています。 店の前でハンナが、仕事のあいまのひととき日向ぼっこしていると、三人の紳士が父の名前を出して店を探しているといいます。ここからハンナの運命が大きく変わりました。 一人は、ロバート・ダドリーと名乗ったハンサムな若い男。 もう一人は、ジョン・ディーと呼ばれた学者風の年かさの男。 そして三人目は。
その裏に、思惑を秘めて。 アンナを 「ミストレス・ボーイ」 とからかって呼んだこの男は、やがてイングランドの歴史に名を残す事になります。 病弱の、死にかけた王に拝謁して気に入られたハンナは、その姉メアリの寵も得ます。政治的な野心を持ちようがない階層で、しかも純粋無垢に忠誠を捧げる正直者の道化、というハンナの設定は、その上ときに未来をかいま見ることができる能力と相まって、王、王女たちとも真っ直ぐに話ができて、歴史の中を自由に渡り、面白い人物模様を見せてくれます。 病弱ゆえに強い権力意識を持たず、しかし周囲のことに思いやる優しさを持っていたエドワード。 母のおかげで高い地位に就き、母の失墜と共に貶められ、それでも年の離れた弟と妹を愛し信頼し、愛され信頼されたいと願ったメアリー。 不幸の中でも強い目的意識を捨てず、なすべき事のために偽善の仮面をつけて耐えぬいたエリザベス。 はたして歴史の中で、この三人は本当はどんな人物だったのか、今となっては分かりません。 しかしこうであったのなら、彼らはこんな生き方をしたのかもしれない。 ブラディ・メアリとのちに呼ばれ、宗教の狂熱のためにイングランドを血まみれにしたと言われたメアリー・チューダーは、純な思いやりを持ち、毅然として不幸に立ち向かい、負け犬の姿を決してさらしません。 二組の母と娘の確執と因縁は、最後にこんなハンナの言葉で締めくくられました。
前回の顰みにならってこの本のモットーを作るなら、 一番高きを望み続けたものだけが、一番上に上れるのだ うむ、いまいちか。(2012/8/2) |
|||||||||||||||||
| Ver. 2.23 |
|---|
| 管理番号:G030-005・006 | 32 歴史小説・西欧史 |
出版社:集英社 | |||||||
| 書名:宮廷の愛人(上) | ブーリン家の姉妹 3 | ISBN978-4-08-760610-2 C0197 | |||||||
| 原題:The Virgin's Lover(2004) | 翻訳者:高里ひろ | ||||||||
| 集英社文庫 ク 17-5 | 価格:781Yen | ページ数:360P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2010/9/25 | 購入:2012/7/28 | 装丁:刈谷紀子 写真 Jeff Cottenden | |||||||
| 書名:宮廷の愛人(下) | ブーリン家の姉妹 3 | ISBN978-4-08-760611-9 C0197 | |||||||
| 集英社文庫 ク 17-6 | 価格:781Yen | ページ数:344P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2010/9/25 | 購入:2012/7/28 | 装丁:刈谷紀子 写真 Jeff Cottenden | |||||||
  前作、「愛憎の王冠」の最後にちょっと重なる時期から始まります。 前作、「愛憎の王冠」の最後にちょっと重なる時期から始まります。ただし、今回ハンナ・グリーンはちらっと話題にされますが、まったく話に関わっていません。市井の中にささやかな安住の幸福を見つけたのなら、そのままでいてほしいですね。 変わって舞台中央に出てきたのは、三人の歴史上の人物。 前作でハンナの保護者だったこともあるハンサムなロバート・ダドリーがまずその一人。 かつて宮廷に大きな勢力を持っていたダドリー家の嫡男。前女王メアリに対する反逆の罪で父が処刑され、自分も投獄されたことがトラウマになっています。 現時点で、エイミー・ロブサートと結婚中。子はなし。 エリザベスとは幼なじみでもあり、今もきょうだい以上の関係。再び宮廷の中心に返り咲く野心満々。
そして何よりも、エリザベス・チューダー。母親アン・ブーリンが正式にヘンリー八世と結婚していたのか、つまりエリザベスは正式に国王となる権利を持つ嫡出子なのか、という点が常に論じられていた王家の娘は、ついに頂点に登りつめ、そこで初めて気づきます。 頂点に立って統治する自らの孤独と、自分の一言が国家の運命を決めるという圧力がいかに重いか。 もう一人は、ウィリアム・セシル。エリザベスから 「 エリザベスの即位に伴い、下級貴族という立場ながら国務長官(Secretary of State)に任じられます。 政治・経済のスペシャリストであると共に、千人以上の情報提供者、スパイを自在に扱い、国家の重臣としてその手腕を発揮する男。 この物語は、エリザベスが即位する直前の1557年夏から、1560年秋までのわずか3年間の出来事を元に書かれています。長いエリザベス女王の治世の初頭のわずかな年月の間に、実は濃密な歴史がすぎていったのでした。 メアリ女王の夫、スペインのフェリペ王がイングランドの兵を率いてドーヴァーの村から出陣したのは1557年夏でした。それから半年後、1558年冬、イングランド軍は対岸の、フランスにある唯一の英国領だったカレーを失い、帰国します。〝イングランドとフランスの王〟という称号を使っていたイングランド王は、その根拠を失ってしまったのです。従軍して、失墜したダドリー家の名を再び上げようとしたロバート・ダドリーは、弟と名誉と財産を失って帰国しました。 年度が冬から始まるこの歴史絵巻でその夏のあいだ、ロバートは屈辱に耐えて農園にある妻の実家で過ごし、秋、メアリー女王崩御の報をエリザベスに伝えるという栄誉をようやく得たのでした。 ウィリアム・セシルの登用と共に、ロバートは主馬頭(Master of Horses)という地位を得ます。この地位は、政治的と言うよりむしろ王家の宮廷の世話係といった役どころ。 そして、歴史が始まります。 正式に戴冠される前にはやくもカトリックの儀礼に喧嘩を売ったエリザベス。 その早急すぎる決断に内心嘆息しつつ、イングランドの教会は女王の支配下にある、という政策に手足を付けるセシル。 政治的な判断より、女王と自分の中をいかに進展させるのかという立場でそれに口を挟むロバート。 こうして、ローマ教皇というくびきを振り払って独立独歩の道を歩み、そしてヨーロッパの中で大国としてのし上がっていくイングランドの歴史の中で苦悶する三人の、はなはだ生臭い物語が進みます。 当時フランスの王位にあったのは、アンリ二世。その嫡男フランソワの妻は、メアリー・スチュアート。フランスの大貴族ギーズ家のマリ・ド・ギーズとスコットランド王ジェイムズ五世の娘。 政情不安が消えないイングランドにさらなる心痛をもたらしたフランス軍のスコットランド侵攻が行われたのは、翌1559年夏。スコットランド国王の要請によって、国内のプロテスタント勢力を鎮圧する事が目的とされますが、その後にイングランドに攻め込んでスコットランド女王となるメアリーをイングランドの王位に就けようとする意図はありあり。 風雲急を告げる中、世情を常に把握し、国際政治の流れを熟知し、決して強国とはいえないイングランドだが、今立たねば国家が崩壊するとの思いから女王に決断を促すセシル。 政治の重みにあえぎ、口を開くたびに意志をころころ変え、内面に芯の強さを持っていながら不安の中で自分を支えてくれ、愛し合える伴侶を求めるエリザベス。 家の繁栄を取り戻し、宮廷内で地歩を固め、エリザベスとの結婚を視野に入れ、さらにその先をと野心をのばすロバート。 行き詰まる三人のゲームが、この三年間にイングランドに何をもたらしたのか。
最愛のロバートのある言葉が、その意図が、エリザベスにある決意をさせ、歴史が動きます。 1560年9月8日、エイミー・ダドリー、夫ロバートを献身的に愛し、女王と夫の不倫の知らせに心をかき乱され、それでも必死で生きて、夫を待っていた女性が、事故死します。 これが三人に、なにをもたらしたのか。 ロマンス小説的展開は鐵太郎の好むところではないのですが、この最後の場面はしびれました。なるほど、よくある展開かもしれないけれど、こんな書き方で描写されると、すごいね。 女王は王妃とは違う、女王の夫は王であることもあるし「王配」とされることもある、王の権力とは明確に個人に帰するものであって厳密には「暗黙の了解」など許されない、など、いろいろためになりますね。ふむ。(2012/11/15) |
|||||||||||||||
| Ver. 2.23 |
|---|
| 管理番号:G030-007・008 | 32 歴史小説・西欧史 | 出版社:メディアファクトリー | |||||||
| 書名:白薔薇の女王(上) | ISBN978-4-8401-3888-8 C0197 | ||||||||
| 原題:The White Queen(2009) | 翻訳者:江崎リエ | ||||||||
| MF文庫 ふ-3-1 | 価格:590Yen | ページ数:288P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2011/4/22 | 購入:2012/9/2 | カバーデザイン: 鈴木成一デザイン室 | |||||||
| 書名:白薔薇の女王(下) | ISBN978-4-8401-3889-5 C0197 | ||||||||
| MF文庫 ふ-3-2 | 価格:619Yen | ページ数:320P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2011/4/22 | 購入:2012/9/2 | カバーデザイン: 鈴木成一デザイン室 | |||||||
  「ブーリン家の姉妹」に始まる歴史小説群は、16世紀のテューダー朝イングランド王家の物語でした。しかし 「白薔薇の女王」 は、その時代ではありません。 「ブーリン家の姉妹」に始まる歴史小説群は、16世紀のテューダー朝イングランド王家の物語でした。しかし 「白薔薇の女王」 は、その時代ではありません。テューダー朝がイングランドの王家として確立するために、その前世紀イングランドは薔薇戦争(1455-1485)という優雅な名の戦争を30年にわたって体験したのです。この名前は、対立した二つの王家、ランカスター家とヨーク家が、前者は赤い薔薇、後者は白い薔薇を紋章としていたことから来ます。 つまり厳密には、この二色の紋章は後付によるものなのですが、そこはそれ。小説的にはこの方が面白い。 この二家は、兄弟だった二人の王子、イングランド王エドワード三世の次男ランカスター公ジョンと、三男ヨーク公エドマンドの、それぞれの子孫。元々の始祖が兄弟だったように、それぞれに荷担した王族、貴族、郷士、平民たちもそれぞれ、利益、しがらみ、運命などによって親族、いとこ同士、はては兄弟までもが二つの党派に分かれて相争ったのでした。
しかし現実は、そうはいきません。戦いの規模がエスカレートするにしたがって、二つの旗印のどちらかに就くことを人々は無理に強いられ、礼節や思いやり、同胞意識は都合よくうち捨てられ、凄惨な戦いの時代になっていたのでした。 ランカスター家のヘンリー六世は、ランカスター公ジョンの曾孫。この王に対して反乱を起こしたのは、ヨーク公エドマンドの曾孫、エドワード。建前として、「君側の奸」 を討つ、つまり、王が悪いのではなくその取り巻きが悪いのだ、悪い取り巻きを退治して王に正しい心を取り戻していただくのだ、という旗を掲げて兵を起こしたもの。むろん、目的は王位の奪取。だれの目にも明らかなように。 王ヘンリー六世がフランスに逃れたのち、フランス人であるその王妃マーガレット・オブ・アンジューが勢力を保つ北部へ進撃するエドワードの前に立ったのは、子供を二人連れた地方の小貴族リチャード・ウッドヴィルの娘エリザベス。彼女はランカスター家に従って戦死したジョン・グレイ卿の妻であり、亡夫の遺産である土地と財産の権利を自分に帰して欲しい、と新王として立つことを宣言したこの22歳の若者エドワードに嘆願します。 このとき、この27歳の美貌の未亡人にどれだけの野心があったのか、歴史は諸説さまざまに解釈されています。しかし彼女がエドワード四世となったこの青年の正式な王妃となったことは、歴史的な事実。 作者フィリッパ・グレゴリーは、彼女を主人公としたこの物語の中で、こんな解釈をします。 エリザベス・グレイ旧姓ウッドヴィルとこの長身の若者は、このとき互いに恋に墜ちたのだ、と。 このとき二人が何を思い、何を期待し、どう振る舞い、どう合意したのか。このあたりの歴史解釈が面白い。 作者はもうひとつ種を撒きます。フランスから来たエリザベスの母ジャケッタ(Jacqette de Luxembourg)を、単にブルゴーニュ公国王室の血縁、という史実だけではなく、水の女神メリュジーヌの血を引くもの、という設定を行うのです。それにより、ジャケッタもその教えを継いだエリザベスも、魔女の力を備えていたのだ、と。 このちからによって、エリザベスは王の目にとまっただけでなく、ただの愛人では嫌だとその地位を高くすることができたのだ、とすることは、安易かもしれないけれど面白い。 そんなわけで、若い二人は、多少の打算はあったにしても互いに深く愛し合い、たくさんの子供をもうけ、幸せに暮らしたのでした ──では終わらない。ここを序章として物語は進行します。 なにしろこの二人が結ばれた時点では、神に祝福され聖別された正しいイングランド王は、王としての支持は墜ちていたもののまだランカスター家のヘンリー六世でしたから。いま成すべきことは、この王をいかにうまく排除するか、いかにしてエドワードが正式に王として冊立される条件を整えるか。ここから動乱の歴史は混迷を深めます。 ヘンリーを廃して王位に就いたエドワード四世に対して、まず牙をむいたのは「キングメーカー」の異名を取るウォリック伯リチャード・ネヴィル。エドワードが兄とも慕い、長年忠実な味方であり相談役であった人物。 次は、ヨーク家の三兄弟として結束堅く戦ってきた次弟クラレンス公ジョン。さらには三弟グロスター公リチャードまでもが。 このすさまじい歴史の中で、夫を助け、子を守り、一族を育てたエリザベスの姿を、作家はどのように描いたのか。 鐵太郎の(いささか凝り固まった)視点で見ると、ロマンス小説的だな、という気がします。視点が女性的で、感情的。情緒的な発想と、ファンタジー世界への敬慕といったものも感じられます。 しかし、にもかかわらず歴史への取り組み方は骨太で、現実的。夢物語に逃げません。 こんな歴史小説も、いいよね。 「塔の中の二王子」として英国史の大きなミステリーの一つとなっている事件がこの歴史絵巻の中で発生します。この二王子とは、まさに国王エドワード四世と王妃エリザベスの息子たちです。 エドワード四世が病死したのち、エドワード五世として即位した長男と、弟ヨーク公リチャード。正しくは王子とはいえませんが、この二人がロンドン塔の中から忽然と消えた事件が、これです。 王位を窺う立場にあったグロスター公リチャードの責任あるいは犯行とされ、シェークスピアもそういう解釈で戯曲「リチャード三世」を書きましたが、真相は歴史の闇の中。この作家の解釈が、現代では一般的かもしれません。とはいえ、いまも謎のままです。 その、リチャード三世として即位したグロスター公とは何者だったのか。何を目指したのか。 やがて起こってきたランカスター家の巻き返しの中で、不意に現れた遠縁の若者、ヘンリー・テューダー。彼は何を巻き起こすことになるのか。 そして、謎の少年、ピアズ・ウォーリックが現れます。 ここで、実はこの本は唐突に終わるのです。ここで引くなよ、おい、と地団駄踏みたくなりますが、終わっちゃったんだからどうしようもない。 シリーズの第一巻なのですよね、これ。ふう。 続いて、〝The Red Qeen〟が刊行されており、それから〝The Lady of the River〟そして〝The White Princess〟と続いて薔薇戦争シリーズは完結するそうです。 たのむよ、どの出版社でもいいからさ、必ず出してよ、ね?(2012/12/19) |
|||||||||||||||
| 管理番号:G030-009・10 | 32 歴史小説・西欧史 |
出版社:集英社 | |||||||
| 書名:悪しき遺産(上) | ブーリン家の姉妹 4 | ISBN978-4-08-760630-0 C0197 | |||||||
| 原題:The Boleyn Inheritance(2006) | 翻訳者:加藤洋子 | ||||||||
| 集英社文庫ク17-7 | 価格:762Yen | ページ数:352P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2011/9/25 | 購入:2025/3/28 | 装丁:刈谷紀子(P-2hands) 写真Ⓒ Jeff Cottenden/アフロ |
|||||||
| 書名:悪しき遺産(下) | ブーリン家の姉妹 4 | ISBN978-4-08-760631-7 C0197 | |||||||
| 集英社文庫 ク17-8 | 価格:762Yen | ページ数:368P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2011/9/25 | 購入:2025/3/28 | 装丁:刈谷紀子(P-2hands) 写真Ⓒ Jeff Cottenden/アフロ |
|||||||
  この上下巻は、「ブーリン家の姉妹」の続編的なものですが、作者が作り上げる歴史絵巻のピースのひとつと言っていいかな。 この上下巻は、「ブーリン家の姉妹」の続編的なものですが、作者が作り上げる歴史絵巻のピースのひとつと言っていいかな。時代は1539年。「ブーリン家の姉妹」の3、4年後、「愛憎の王冠」の始まる8年ほど前。 イングランド王ヘンリー8世は、2番目の王妃アン・ブーリンを1536年に姦通罪などで処刑したのち、ジェーン・シーモアを次の王妃としましたが、彼女は1537年に王子を出産したのち産褥で死亡しました。 そのあと、敵同士であったスペインとフランスが同盟を結んだことで、イングランドは欧州大陸に同盟者を求め、新教徒であるユーリヒ=クレーフェ=ベルク公ヨハン3世の娘アンを次の王妃に選びました。物語はそこから。 これは3人の女性による、一人称によって語られる物語です。 一人目は、ジェーン・ブーリン。(おそらく)1505年生まれ。ならばイングランド王ヘンリー8世とは14歳差。 ただしこの独白では、30前だという。 伝わる肖像画、画像、銅像などがないため、個別の紹介コマは付けませんでした。  かつてイングランド宮廷の中でわが世の春を謳歌したブーリン一族の一人ですが、ヘンリーの2番目の王妃となったアン・ブーリンの失脚、処刑と共に凋落しました。とはいえ彼女自身はブーリン家の生まれではなくモーリー男爵家の娘で、アン・ブーリンのきょうだいであるジョージに嫁いだ人。(wikiなどによるとジョージはアンの弟となっていますが、このシリーズでは兄としています。まァ記録がはっきりしていない昔の事だし、あっちの親族名称
は年齢差が明確でないからなァ)しかし実家よりブーリン家の方がその時代遙かに勢力を持っており、彼女はブーリン一族として生きています──生きていました。 かつてイングランド宮廷の中でわが世の春を謳歌したブーリン一族の一人ですが、ヘンリーの2番目の王妃となったアン・ブーリンの失脚、処刑と共に凋落しました。とはいえ彼女自身はブーリン家の生まれではなくモーリー男爵家の娘で、アン・ブーリンのきょうだいであるジョージに嫁いだ人。(wikiなどによるとジョージはアンの弟となっていますが、このシリーズでは兄としています。まァ記録がはっきりしていない昔の事だし、あっちの親族名称
は年齢差が明確でないからなァ)しかし実家よりブーリン家の方がその時代遙かに勢力を持っており、彼女はブーリン一族として生きています──生きていました。1539年7月という「今」、3年前にジェーン自身がアンと夫ジョージが近親相姦しているという告発をしたことで、王妃アンは処刑され、一時隆盛を極めたブーリン家は没落します。一命と最低限の名誉を保つことができたジェーンは、かつての夫の称号よりロッチフォード子爵夫人、未亡人レディ・ロッチフォードと呼ばれ、ノーフォークのブリックリング・ホールに逼塞しています。 時は、1539年7月。 その生活は、彼女に宮廷での陰謀のすべてを叩き込んだノーフォーク公(第3代)トマス・ハワードからの手紙によって破られます。彼は今、イングランドで王に次ぐ権力者であり、戦場の呵責ない勇者であり、宮廷では表も裏もすべて知り尽くして一族の権威を高めるために暗躍する陰謀家。結婚のおかげで彼はわたし、ジェーン・ブーリンの叔父であり、教師であり、後ろ盾であり、主人。 知らされた新たな任務は、海の彼方からやってくるアン王妃の女官となり、王妃の腹心の友となること。 1539年12月、彼女はグリニッジ宮殿に戻る。かつて王の名を呼び、一目でいいから会いたいと願ったジェーン・シーモア、ヘンリー王の3番目の王妃の看病をし、その孤独な最期を看取った宮殿です。ここで新しい女官仲間と声を掛け合います。むろん彼女たち、この国の最高の貴族の家の女たちは、味方ではない。友として寄ってくる人もいるが、誰ひとり信用はできない。してはならない。 二人目は、クレーヴ公国の公女、アン。このとき24歳。この「クレーヴ」表記について、訳者は巻末でこう言います。
現在公国の王座に王座に即いているのは彼女の兄。精神の弱った父を閉じこめ、狂死させてその座を奪い、母と共に公国の独裁者となったユーリヒ=クレーフェ=ベルク公ヴィルヘルム5世。彼は母を自分の侍従長、執事、教皇として、一家と公国をその視野の狭い旧弊な考えで支配します。 やがてイングランド王の妃に選ばれたアンは、おもてむき全く従順な娘として旅立ちます。イングランドへの輿入れとして充分な教養も財産も与えらないままで、イングランド王妃となってそこを清教徒の国にせよという無茶な命令を与えられ、この従順でおとなしい妹。彼女が自分たちの教えを守ると確信して。二度と故郷に戻るまいと決心しているなどとは全く気づかすに。
そしてイングランド上陸と共に思い知ります。誰も教えてくれなかったイングランド宮廷の「暗黙の了解」を破ったため、王の激怒を買ったこと。 これで、イングランド王妃になれるのか。 三人目は、1539年7月の時点で14歳になった事を喜ぶキャサリン・ハワード。 (彼女の信頼できる肖像画はないそうですが、王妃の座に就いたので伝わる絵はあります)
継祖母のお気に入りではあるけれど、その目をくぐって恋人と逢瀬を楽しむ年代。 王妃さえいればその女官となって宮廷でひと目をひき、少しでもいい男を手に入れて恋を楽しんだのち結婚するのが夢、なのですが、肝心な王妃がいない、なんてこと。 今はハンサムな愛しのフランシス・ディアラムの恋人。彼に求められるままに二人きりで礼拝堂に入り、結婚の儀式をしますが、むろん保護者の承諾はない。彼らが芽が出ないまま生涯を送るなら、それはそれで、そのまま夫婦になったかもしれない。 それが、新たに欧州からレディ・アンが嫁いでくるということで、彼女にも侍女の声がかかります。となると下級貴族の恋人はどうでもいい。 この年ですでに宮廷内でのふるまいや男と女の駈け引き、媚びのテクニック、ベッドでいかに男を喜ばすかについては知り尽くしている彼女のこと、新たな希望に胸を膨らませることに。 レディ・アンに従う多くの女たちの1人として、〝牛攻め〟の催し物の観覧に参加していた時、事件が起きます。平民に手を振りにこやかにふるまうレディ・アンにとまどいながらも好意を持って見守っていた時、いきなり入室してきた無頼漢がレディ・アンに抱きつきキスをしたのでした。 戸惑い恐慌に陥りかけた人々は、変装したヘンリー王の戯れだとすぐ気がつきますが、ただ一人、レディ・アンはそんなことは知らない。謹厳実直で堅苦しい新教徒の小さな宮廷でそんな馬鹿なことはあり得ない。
彼女は、かつてイングランドいちの美少年と称えられ、今は48歳となって肥満し、完治しない足の古傷のため膿で悪臭を放つ、老境にさしかかった、それでもなお自分こそが最高の男だと「わかっている」男に、こう言ったのでした。
アン・オブ・クレーブは知らなかった。イングランドの宮廷では王の意志、王の言葉、王の気まぐれだけが正義であり、逆らえば破滅を、あるいは死を覚悟しなければならないことを。彼女の育った小さい宮廷の頑迷な新教徒的規範など何の役にも立たないことを。ここ、富裕で優雅なイングランドが、王がひとこと言えば国家を支える大貴族が一族もろとも処刑され、教会が燃やされてその財産が没収され、王妃が首を斧でたたき切らされる国であることを。王の前では王を満足させるためにあらゆる手練手管を使い、常に王のために自分が動かなければならないこと。ベッドでも然り。身持ちの堅い処女であっても。 そんなこと、誰も彼女に教えなかった。彼女はなにも知らなかった。 彼女は、必死で学ぼうとしている、ドイツ語と自分の習慣しか知らない、気立てのいい、そして芯の強い女性であった。それだけ。 上下巻に分冊されるだけの量はありますが、一気に楽しめました。 蝶よ花よと育てられた美少年が、そのまま等身大の自分を知らずに老いて暴君となった姿。 そして幼さ故の幼稚さを脱することができないまま誘惑に溺れてしまった少女。 巻き込まれた悲惨な境遇の中で世界を達観し運命を支配したつもりでいたのに、より高い陰謀に足をすくわれた女性。 言葉と文化の違いによる引け目で愚かと思われていたが、いつの間にかその人柄で信頼を集め、運命の石臼のなかでかろうじて生き残った人。 人の運命はかくも有為転変。 この短い時間のなかで起きた人びとの思い、運命、幸運と不運。政治。イングランドの歴史。 いや、面白い。アン・ブーリンの悲劇のあとで、こんな歴史があったのかもしれない。 それこそが、このあと歴史のなかに沈んでいくブーリン家の「悪しき遺産」だったのか。 久し振りに読んだフィリッパ・グレゴリー、すごいね。日本ではロマンス小説の範疇に納められているようですが、実にもったいない。見事な歴史小説です。
歴史小説の真髄とは(個人的意見ですが)「史実はこうだったが、こんな歴史があり得たかも知れない。だとすると人々はこう流れていたのかもしれない」と思わせる執筆者のペンの冴えに酔わされること、だと思っています。そういう本に出会えると、幸せ。 ちょっと調べたら、フィリッパ・グレゴリーの歴史小説の新しい邦訳が刊行されています。 本屋で見つけたので立ち読みして見たら、どうやらここに出てきた三人の主人公の一人、レディ・ロッチフォードつまりジェーン・ブーリンが主役のようです。「ようです」というのは、その名前が出たのですぐ立ち読みをやめたから。内容はよくわからないけど、彼女がもう一度出てくる話なら読んでみたい。──ちょっと間をおいて、ゆっくりとね。(2025/12/26) 読書メーターの記録より 上巻読了:2025/12/23 下巻読了:2025/12/24 |
||||||||||||||||||














