トップへ戻る 作家/分野 一覧 |
|
 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 書名 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| K050-001 | 傭兵の二千年史 | 歴史の中に見る傭兵の姿 | |
| K050-002 | 戦うハプスブルク家 | 近代の序章としての三十年戦争 | |
| K050-003 | ハプスブルクをつくった男 | 型破りな男の短い一生 | |
| K050-004 | ハプスブルク帝国の情報メディア革命 | 郵便制度がもたらした世界の変革 | |
| K050-005 | 神聖ローマ帝国 | 神聖でもローマでも帝国でもない国とは何か | |
| K050-006 | ドイツ誕生 | ドイツという言葉のないときにドイツを作った王 | |
 |
|---|
| 管理番号:K050-001 | 53 史書・編年史 | ||
| 書名:傭兵の二千年史 | 発行 2002年 | ||
| 講談社現代新書 1587 | 価格:¥720 | ページ数:229P | 装丁:新書 イラスト:中島 英樹 |
| 初版発行:02/1/20 | 購入:05/3/12 | ||
 世界で二番目に古い職業である「傭兵」にスポットを当て、古代ギリシャの昔より現代までの「傭兵」、つまり金で雇われた兵士について、大まかではありますがうまくまとめた歴史読本です。 世界で二番目に古い職業である「傭兵」にスポットを当て、古代ギリシャの昔より現代までの「傭兵」、つまり金で雇われた兵士について、大まかではありますがうまくまとめた歴史読本です。世界で一番古い職業については、割愛。ぼくは趣味の範囲を広く浅くをモットーにしていますが、それでも漏れるときは漏れるし、三塁線はハナから守備範囲外です。ご興味がおありの方は、自己責任にてご研究下さいマセ。(,⌒-⌒) v さて、いわゆる民主主義の萌芽であり、直接民主主義の華として褒め称えられるギリシャ時代。 ソクラテス門下でプラトンと机を並べたとされる哲人クセノフォン、「ソクラテスの思い出」で名高いとのこと。幸運なことに、ぼくは知りません。ましてその本が、高校の倫理の時間にテキストとなるものだとなると、知らない、あるいは忘れたことは、幸運としか言いようがない。(おいおい) いやその、哲学者としての面はさておき。 彼の有名な著述があるそうです。「アナバシス ─敵中横断六千キロ」 一万人のギリシャ兵を、ペルシアの彼方から祖国アテネまで連れ帰った激戦の記録だそうな。 問題は、彼らがなにゆえペルシアの奥地にいたか、です。 結論から言うと、彼らはペルシアの傭兵だったのです。 アテネは、市民皆兵の民主国家として始まりますが、ステータスとしての兵役もいずれは腐る。市民の定義を両親がアテネ市民である男と定めてしまったアテネは、国家の防衛をいつまでも上流階層である「市民」だけで行うことはできない。 こうして、ギリシャにも傭兵が誕生する。 この流れは、かたちを変えてローマ帝国でも起きます。ローマの方がはるかに「市民」のカテゴリーを広くしていたにもかかわらず、市民皆兵だけでは国防できない時代が来る。そして、傭兵が必要となる。 中世の時代にあっては、騎士と呼ばれた重装備、重攻撃力の少数が一時は覇を唱えますが、やがて武装した大群の波に流される時代が来る。 そのとき、多数の武器を持った兵たちを、いったいどこから調達するのか。それも、低コストで。 ここで、再び傭兵の時代となります。 「国家強権に支えられた税の一種であった徴兵制から、被傭者当人の意志によって雇われる傭兵制への転換」 が起きた例として、著者はヨーロッパだけではなく、律令制度の崩れた平安末期も例に挙げます。
さて、華やかな傭兵たちが覇を競ったイタリア・ルネッサンスから、血の輸出として悪名と武名をとどろかせたスイス傭兵、そしてランツクネヒトの時代になります。 ランツクネヒト(Landsknecht)。語源からして、怪しい。騎兵(Lanzen)から来たとすると、長槍歩兵を手兵力とした彼らの起源としてはおかしい。スイス傭兵に対して平地(Land)出身者であるとすると、彼らの多くを占めるチロル地方人などをどう説明するのか。都市ではなく田舎(ラント)出身者とすると、都会の食いっぱぐれから始まった彼らの起源の説明にならない。 国土(ラント)防衛では、あまりにも近代の歴史観に縛られる。そもそも、当時守るべき国家の概念は薄い。 てな訳で、謎のランツクネヒト。 彼らが近世の傭兵史を彩り、そして去っていく。 次に来るのは、三十年戦争を経て訪れた絶対王政の時代。マウリッツ、ヴァレンシュタイン、そしてグスタフ・アドルフの時代。国家の財政の安定を受けて、ルイ十四世が54年間の治世に34年間の戦争をなしえた時代。常備軍の整備と共に、傭兵の時代に日暮が。 しかし、傭兵の最大の不幸な時代はそのあとに起こるのでした。自由な傭兵が、奴隷となって売り飛ばされる時代が。 この日、ここにおいて世界史の新しい時代が始まる ─ ゲーテ 1792年9月20日 ゲーテが喝破したこの日、シャンパーニュ地方のヴァルミーで、傭兵軍を主力とするオーストリア・プロイセン連合国の前に、フランス革命軍は押されまくり、風前の灯火でした。このとき、誰が言い出したのかは歴史の謎ですが、フランス革命軍の中から「フランス国民万歳!」の声が上がります。 「フランス万歳」でも「国王万歳」でもない。 そして、フランス革命軍兵士は、「祖国か、しからずんば死か」つまり民族の軍隊としての自覚に目覚めたのです。 傭兵の時代の終焉でした。この戦いが国民軍という概念を作り、ナポレオンがそれを広め、その概念の前にナポレオンは敗れ去りました。そして傭兵たちは、雇い主に世界のどこにでも売り飛ばされる存在になっていったのです。 新時代の到来です。 このあとの、ナチス・ドイツのレームなどを経て、現代のいわゆるフランス外人部隊までの、もはやロマンチックな匂いのするようになった傭兵まで流して、この本は終わります。 面白い。こういう歴史的解釈もありか。 最後に、こんな文章が目にとまりました。
それは知らなかった。ふーむ。歴史は面白いですね。(2005/4/30) |
||||||
 |
|---|
| 管理番号:K050-002 | 53 史書・編年史 | ||
| 書名:戦うハプスブルク家 | 近代の序章としての三十年戦争 | 発行 1995年 | |
| 講談社現代新書 1282 | 価格:¥700 | ページ数:206P | 装丁:新書 イラスト:中島英樹 |
| 初版発行:95/12/20 第八版:04/12/3 | 購入:05/5/5 | ||
 三十年戦争という歴史のイベント(ほかになんと読んだらいいのだろう?)は、中世ヨーロッパという一種異様な舞台の中で、だらだらと行われました。この、訳のわからない世界、訳のわからない理念、訳のわからない人間たちを一種独特の視点で解説したのがこの本です。 三十年戦争という歴史のイベント(ほかになんと読んだらいいのだろう?)は、中世ヨーロッパという一種異様な舞台の中で、だらだらと行われました。この、訳のわからない世界、訳のわからない理念、訳のわからない人間たちを一種独特の視点で解説したのがこの本です。宗教改革に揺れながら、中世の倦怠から起きあがろうとしていたヨーロッパの中心に、ドイツと呼ばれる地方があります。神聖ローマ帝国の宗主権の元に、二千二百万人の人口が三百以上の帝国諸侯に支配されていました。驚くべきことに、平均は七万人かそこらです。 この時代の人々が求めたのは、宗教的な安定なのか、窒息しそうな社会の風穴なのか、颯爽とした英雄譚なのか。何なのでしょう? 戦争は、ハプスブルク家の覇権争いで始まり、覇権争いで終結します。 ドイツの国土に、ドイツとオーストリアが存在するのはなぜか。ハプスブルグ家が覇権を狙ってそこにいたからです。 しかし、先鞭をつけたのはスペインのハプスブルク家でした。彼らはネーデルランド、イタリアなども領有し、再びローマ皇帝、「神聖ローマ帝国」などというまがい物ではなく、真のヨーロッパ全土の症主権を持つ皇帝たらんとします。 こうして始まったこの戦いは、実は、オーストリア・ハプスブルク家当主であったボヘミア王ルドルフ二世の、信教の自由を認めた勅書から始まります。1618年5月21日、これをたてに取ったプロテスタント諸侯が、プラハの城で王の代官を窓から放り出し、17メートル下に落としたことで始まります。(25メートルという説もあり) なぜかこの落とされた三人は助かります。歴史の偶然です。 ここから、三十年戦争は宗教戦争として始まり、ハプスブルク家対ドイツ諸侯の構図から、天才傭兵隊長ヴァレンシュタインの台頭、北方の獅子グスタフ・アドルフ・スウェーデン王の華麗な登場と突然の死、傭兵隊長ヴァイマール・フォン・ベルンハルトの暗躍、フランス宰相リシュリューの介入など、歴史を彩る人物たちが縦横に活躍します。 そして、スウェーデン女王クリスティナの目の前で、1648年10月24日、ウェストファリア条約が締結され、戦争は終結します。 この戦争は、被害ばかりが誇大に語られるときもあります。中部ヨーロッパの人口は半減した、いや、四分の三が失われた、と言う記録もあります。農業生産力が元に戻るまで、二世紀を要したと書かれている本もあるとか。 そういう一面もあったかも知れない。しかし、これらの中から明らかな誇張を排除すると、その先に見えるものは勝利した偉大なプロイセンだったりする。つまり、プロパガンダとしての正義の主張です。 ここで、菊池氏は、この戦争、というより、だらだらとした戦争の連続が、ヨーロッパを国家単位で考える人々の集合体に作り替えたのだ、と主張します。 面白い視点です。 中世という遙かな過去は、連綿として現代の歴史につながっています。(2005/7/2) |
 |
Ver. 2.17 |
|---|
| 管理番号:K050-003 | 53 史書・編年史 | 出版社:講談社 | |||||||
| 書名:ハプスブルクをつくった男 | ISBN978-4-06-149732-4 C0222 | ||||||||
| 講談社現代新書 1732 | 価格:700Yen | ページ数:234P | 本のサイズ:新書 | ||||||
| 初版発行:2004/8/20 | 購入:2007/5/3 | カバーデザイン:中島秀樹 | |||||||
 ハプスブルク家とは、中世から近代まで、領主として、公として、王として、皇帝としてヨーロッパに君臨した一族です。その歴史は、1273年に、突如としてドイツ王に選出された貧乏伯爵ルドルフ・フォン・ハプスブルク(1218/5/1~
1291/6/15 在位1273~1291)に始まり、君主としては1918年のオーストリア=ハンガリー帝国の解体をもって終わります。 ハプスブルク家とは、中世から近代まで、領主として、公として、王として、皇帝としてヨーロッパに君臨した一族です。その歴史は、1273年に、突如としてドイツ王に選出された貧乏伯爵ルドルフ・フォン・ハプスブルク(1218/5/1~
1291/6/15 在位1273~1291)に始まり、君主としては1918年のオーストリア=ハンガリー帝国の解体をもって終わります。とはいえ、ハプスブルク家自体は今もなお存在しており、最後の皇帝の息子や孫たちが、欧州議会の議員となるなどして名士として活躍しています。 さて、この本の主人公となった「ハプスブルクをつくった男」とは、その初代のドイツ王ルドルフなのでしょうか? いや、違いました。ルドルフには違いないが、ルドルフ4世(1339/11/1~1365/7/27 オーストリア大公在位1358~1365)です。「建設公」(der Stifter)と呼ばれています。 肖像画の男ですね。 この破天荒な人物が、それまでルクセンブルク家、ヴィッテルスバッハ家と共に勢力争いをしていたハプスブルク家を大きく飛躍させ、ヨーロッパ随一の大帝国を築くきっかけとなりました。 この時代は、波乱の時代です。呪われた14世紀です。 ます、1310年頃からのちに「小さな氷河期」と呼ばれた寒冷期が10年近く凶作がヨーロッパを苦しめます。 1337年に、イギリス・フランス間に百年戦争が勃発します。 さらに1338年7月に蝗(いなご)が大量発生し、ヨーロッパは3年というものそれに苦しめられます。 1342年、ライン川とドナウ川が大洪水を引き起こし、4月には冬に戻ったような寒さになります。 追い打ちをかけるように1347年にオリエントから線ペストが襲来し、ヨーロッパの人口の1/3を奪います。 1348年、大地震が頻発し、アルプスで山崩れで地獄絵図を描きます。 中世最大の不況がヨーロッパを支配し、人々は終末思想に走り、神の恩寵にすがる時代となりました。  ルドルフ4世(1339-1365 オーストリア公・在位1358-1365)という、建設公という名の破壊者が現れたのは、何かの因縁なのでしょうか。 ルドルフ4世(1339-1365 オーストリア公・在位1358-1365)という、建設公という名の破壊者が現れたのは、何かの因縁なのでしょうか。彼は、この動乱の時代に、血縁的には岳父である神聖ローマ皇帝カール4世に対し、詐欺どころではない強引な要求と捏造によって、自らのハプスブルク家を「オーストリア大公家」に祭り上げ、さまざまな破天荒な改革を行って旧体制を破壊し、新しい秩序を打ち立てようとしました。 幸か不幸かというのなら、彼自身にとっても世界にとっても幸運にも、彼は在位わずか7年で、25歳の若さで世を去ります。幸運にもというのは、即位するや否や旧来の側近をすべて首にして若い配下とすげ替えたり、先祖を遠くカエサルその人にまで遡る捏造の系図を作ったり、ローマ皇帝ネロがオーストリアに未来永劫税を免除する事を命じたとする文書を「発見」したり、皇帝の裁可も待たずにハンガリーと婚姻関係を結んだり、ともかくよくもまあこれほどの無茶をすると言うような綱渡りを演じたのです。さらに、皇帝を選出する権限を持った七選帝侯たちの上位にハプスブルク家が来るのだというでっち上げとか、伯爵領を勝手に大公領にしたり。この綱渡りが破局しないはずがない。破局した結果、ハプスブルク家だけではなく神聖ローマ帝国の屋台骨が揺らぐ事になったでしょう。 それに至らなかったのはルドルフの早い死のせいだったとしたら、歴史はなんと皮肉なもの。 かくして、この傲慢きわまる欺瞞の上で、ルドルフの死後ハプスブルク家は大いに名を上げることになったという。 もはやなんとも言いようがなし。 歴史って、面白いですよねぇ。(2007/7/20) |
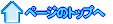 |
Ver. 2.21 |
|---|
| 管理番号:K050-004 | 55 技術史・科学史 | 出版社:集英社 | |||||||
| 書名:ハプスブルク帝国の情報メディア革命 | 近代郵便制度の誕生 | ISBN978-4-08-720425-4 C0222 | |||||||
| 集英社新書 0425D | 価格:700Yen | ページ数:222P | 本のサイズ:新書 | ||||||
| 初版発行:2008/1/22 | 購入:2008/1/31 | 装幀:原 研哉 | |||||||
 最初に読み始めたとき、この本は、中世ハプスブルク家の歴史を、郵便という方向から見た文化史だと思ったんですよ。そうなると、歴史の範囲としてはせまい。数百年程度だとしても。 最初に読み始めたとき、この本は、中世ハプスブルク家の歴史を、郵便という方向から見た文化史だと思ったんですよ。そうなると、歴史の範囲としてはせまい。数百年程度だとしても。ところが違った。 郵便制度の歴史を古代ローマ帝国の駅伝制度まで遡り、情報ネットワークを駆使したカエサルまで遡ったのは良いのですが、中世のハプスブルク家を経由して最後は21世紀のグローバリゼーションにまで話は広がります。郵政民営化を歴史的に見てくると何に似ているのか、なんてことは、こんな視点から見ないとわからないものですねぇ。 郵便制度とはなんのために作られたのか。 まず、これは公営のものであり、統治の手段として情報収集のためのものであり、軍事的な意図があったということを認識しないといけません。これが、すべての庶民とはいわないけれど、誰もがそれなりに利用できるようになるまでには何があったのか、何が必要だったのか。 序章で書かれた一つのエピソードは、三つのことを伝えます。 一つは、スペイン王フェリペ二世、「偉大なる」と形容しても良い存在だったカール五世の後継者であるフェリペ二世とは、カトリックによる世界統一の野望に取り憑かれ、国家の財政をとことん破壊し、スペインを生産国家から破産国家へと導いた国王であったこと。 二つ目は、フェリペ二世は、息子ドン・カルロスの動向を探るために平然と彼の私信を開封するように命じ、しかもそれは当時ごく当たり前のことであったこと。信書の秘密などという道徳観念がない時代だったのです。 三つ目は、タクシスという人物がハプスブルク家の郵便を、国家の承認の元に支配していたこと。ドン・カルロスの私信を開封した駅逓長タクシスとは、単なる郵便局長ではない。ライモンド・デ・タクシス(1515-1579)は、父の代よりスペイン王国の貴族として書信、小荷物、旅行者の輸送のすべてを支配下においた人物です。そしてタクシス家は、1867年にこの権限をプロイセン帝国に譲渡するまで、中央ヨーロッパの通信ネットワークを掌握し続けた家系だったのでした。 フランス大革命の時、革命派の重鎮ミラボーは1789年7月25日、信書の自由を守ったパリ市常任委員会の処置を弁護してこう演説します。 「自由になろうとしている民衆が暴君の常套手段を使用するということははたして正しいことだろうか? 決してそうではない」 拍手喝采されたこの言葉には、当時権力側では私信を開封することは常套手段であり当たり前のことであったことがうかがわれます。そして革命勢力が権限を握り、配下のボナパルト将軍がイタリアへ遠征する1799年になると、あっさりとイタリアへのすべての手紙が管理され、開封され、検閲されたのでした。権力側とは、結局そんなものです。(笑) この郵便が近代の開封禁止、低価格、一律料金の郵便制度になるまでの長い長い歴史を、あるときはストイックに、あるときはユーモラスに、さくさくとした文章で描いたのがこの本です。菊地さんの文章って、歯切れが良い。 扱う題材は堅いのですが、楽しめました。(2008/7/11) |
 |
Ver. 2.22 |
|---|
| 管理番号:K050-005 | 53 史書・編年史 | 出版社:講談社 | |||||||
| 書名:神聖ローマ帝国 | ISBN978-4-06-149673-5 C0222 | ||||||||
| 講談社現代新書 1673 | 価格:740Yen | ページ数:262P | 本のサイズ:新書 | ||||||
| 初版発行:2006/9/21 | 購入:2009/1/15 | カバーデザイン:中島英樹 | |||||||
 菊池さんの本の順番としては、「傭兵の二千年史」が2002年、「戦うハプスブルク家」が1995年、「ハプスブルクをつくった男」が2004年、「ハプスブルク帝国の情報メディア革命」が2008年ですから、この本は新しい方から二番目ということになりそうですね。 菊池さんの本の順番としては、「傭兵の二千年史」が2002年、「戦うハプスブルク家」が1995年、「ハプスブルクをつくった男」が2004年、「ハプスブルク帝国の情報メディア革命」が2008年ですから、この本は新しい方から二番目ということになりそうですね。こういう歴史の本って、硬いの柔らかいのいろいろありますが、菊池良生さんの本は面白い。ジェットコースターに乗ったように、一気に時代の流れを下っていけます。 この本では、神聖ローマ帝国という、名前だけは立派な古代国家の歴史を、頭からしっぽまで一気に流れ下ります。なにがどう神聖なのか、どこでローマとかかわるのか、どうやって帝国となったのか。 まず話は、政治家・文豪ゲーテ描くファウスト博士の見る酒場の歌から始まります。 神聖ローマ帝国が / 余命保つぞ摩訶不思議! この場面のある「ファウスト・第一部」は1808年のことですが、その原型となる1773年頃に書かれた「原ファウスト」と呼ばれる習作に、すでにこの場面は書かれていたという。名前だけは大仰でも、四分五裂で帝国とは名ばかりの形骸化した国家の残骸であった「神聖ローマ帝国」とは、いつできたのか。 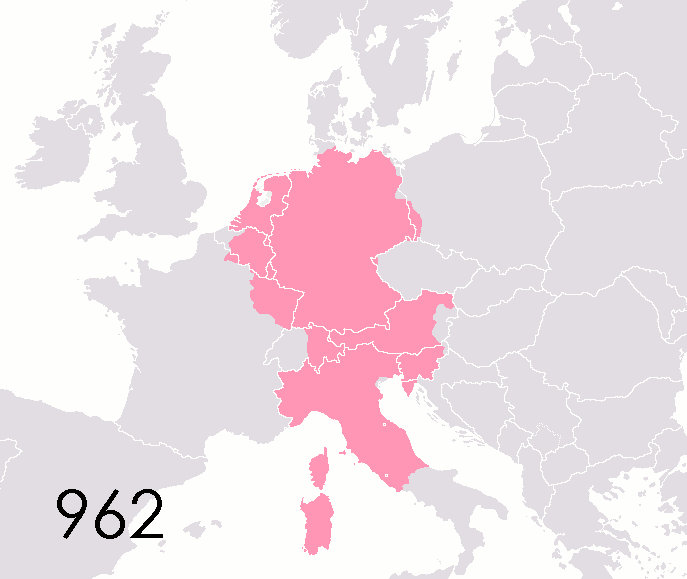 それは、オットー1世が皇帝として即位した962年である、というのがまあ定説でしょうか。 それは、オットー1世が皇帝として即位した962年である、というのがまあ定説でしょうか。西暦800年にカール大帝がローマ教皇レオ3世より戴冠されて皇帝となり、その帝国がルードヴィッヒの三人の息子によって分裂したのが843年。以後、分裂四散したこの「ローマ帝国」は、辺境伯より帝位についたアルヌルフが899年に死んだのちは空位となります。 この間、西フランク、すなわちのちのフランス王国では、統一政権を目指す方向に社会が動き、南部のイタリアは教皇領ローマを中心とした都市国家が発達します。しかし東フランクでは、選挙王政という方向に歴史が動くのです。このあたりが、不思議。 そもそもフランク王国の上級官吏であった称号が、貴族の称号となります。公爵、宮中伯、辺境伯、城伯など。彼らが、強大な皇帝が去った後のドイツで、名目上の国王を選挙で選ぶ方向に歴史を動かしたのでした。 ザクセン王家のオットーがドイツ王となったとき、状況は変わります。彼はこの現状の中で、各都市にそれなりの勢力を持つ教会の首長たち、つまり司教たちを各伯爵たちと同じ権限も与え、その上に自らの勢力を確保します。司教はむろん世襲ではないし、その任命権に一定の影響力を確保できれば、ドイツ王の権力基盤は大きくなる。さらにローマ教皇にすり寄ったあげくに手玉に取り、教皇の選出を承認する権利までかっさらい、イタリア王国まで併合してしまう。 かくして962年2月21日に、オットーは皇帝に即位します。しかし、名乗りはまだ「皇帝アウグストゥス」のまま。 この、ドイツ諸侯の連合体を背景に皇帝となった王たちにとって、神聖ローマ帝国とはいったい何だったのか、いやそもそも神聖ローマ帝国の皇帝をいつ名乗ったのか、その名をどう利用したのかについて、この本は描きます。 オットー1世の戴冠の962年より、フランツ2世が神聖ローマ皇帝位を返上した1806年までの約850年の間に、どんな歴史があってどのように推移したのか。ローマ教皇と神聖ローマ帝国は、いったいどのような関係であったのか。大空位時代とは何か。ハプスブルク家はいつ台頭し、どのようにこの帝国を牛耳ったのか。30年戦争を終結させた1648年のウェストファリア条約が、歴史上「神聖ローマ帝国の死亡診断書」と言われたにもかかわらず、なぜ帝国はそれから150年間も存在し得たのか。 「神聖でもなければ、ローマ的でもなく、そもそも帝国ですらない」とヴォルテールに揶揄だか諦観だかされたこの国家の歴史を、菊池さんのペンは軽やかに描きます。この人の文章って読んでいて楽しいですよね。全体として、やがて神聖ローマ帝国と呼ばれるようになる国家の歴史を語っているのですが、出てくる人物一人一人が読んでいてわくわくします。 たとえば、フリードリッヒ1世(1123~1190 皇帝在位1152~1190)の伝記作家による颯爽とした描写を紹介してから、書きます。
皇帝選挙という奇妙な制度が行き詰まったあげくに、選帝侯は鳩首して一人の義理堅い伯爵を選び、彼に1272年、ドイツ王の位を授けます。彼こそがルドルフ・フォン・ハプスブルク。正確には最後まで皇帝位は継げなかったものの、彼が「大空位時代」と呼ばれた混乱期を終息させ、神聖ローマ帝国の基礎を作り上げることとなったのでした。菊池さんはこの道のりを、信長の死後の秀吉の出世になぞらえて描いています。これ以降700年にわたって、ハプスブルク家はこの帝国を彩ることとなるのです。 ハプスブルク家で面白いのは、まずルドルフ4世(1339~1365)でしょうか。嘘でも法螺でも、大きく使って堂々と突っ張ればなんとかなる、という前例は素敵ですね。この人は帝位にはつかずオーストリア大公という肩書きをでっち上げただけでしたが、なんといっても楽しいのは帝位についたフリードリッヒ3世(1415~1493 ドイツ王在位:1440~1493 皇帝在位:1452~1493)ですね。「神聖ローマ帝国の大愚図」というとんでもないあだ名を付けられ、何一つ褒めるべきところもなく、愚図でのろまで陰険で何一つ美点がないこの人が、神聖ローマ帝国をオーストリアのものにしてしまったという話は、唖然とするばかり。 だから歴史って面白い。 ほかもいろいろあるのですが、終幕での菊池さんらしい言葉というと、ナポレオン時代の戦いの一つ、「三帝会戦」に付いてのツッコミでしょうか。いわゆるアウステルリッツ会戦(1805/12/2)。フランス皇帝ナポレオンに対して、ロシア皇帝アレクサンドル1世と神聖ローマ皇帝フランツ2世が連合して大敗した戦いです。フランツ帝はまあいい。アレクサンドル帝も東ローマ帝国後継者を名乗っているのでまあいい。ナポレオン皇帝とはなんぞや。いつお手盛りで皇帝ができるようになったのか。 これは、「漂白放浪する異人」だけがなしえたコペルニクス的転回なのだ、と喝破したのが菊池さんなのかどうかはわかりません。しかしこの文章の書き方は菊池節だなぁ。 歴史は、いろいろなことがあります。こういう本で楽しんで学べるのなら、これほど面白いものはないのですが。(2009/2/22) |
||||||||||
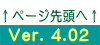 |
|---|
| 管理番号:K050-006 | 51 伝記・一代記・評伝 |
出版社:講談社 | |||||||
| 書名:ドイツ誕生 | 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世 | ISBN978-4-06-529980-7 C0222 | |||||||
| 講談社現代新書 2685 | 価格:920Yen | ページ数:240P | 本のサイズ:新書 | ||||||
| 初版発行:2022/11/15 | 購入:2025/1/14 | ||||||||
 はじめに、はこんな文章から始まります。
はじめに、はこんな文章から始まります。
 とはいえオットーの統治が順風満帆の中で進んだのではない。
とはいえオットーの統治が順風満帆の中で進んだのではない。