 コンスタンツェ・モーツァルトというモーツァルトの「悪妻」のことを知識として知ったのは大学の頃だったかな。その後映画『アマデウス』(1984)で描かれた彼女の姿を見て、かえってそんなに非道くはないじゃない、と思ったものでした。 コンスタンツェ・モーツァルトというモーツァルトの「悪妻」のことを知識として知ったのは大学の頃だったかな。その後映画『アマデウス』(1984)で描かれた彼女の姿を見て、かえってそんなに非道くはないじゃない、と思ったものでした。
とはいえ全般的に、歴史上彼女の評価はよろしくありません。よろしくないと言うより、悪い評価しか聞けません。で、そういうものかと軽く考えていました。

ウォルフガング・モーツァルト
出生名:ヨアンネス・クリュソストムス・ウォルフガングス・テオフィルス・モザルト
Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart
1756/1/27-1791/12/5 |
古典派音楽・ウィーン古典派を代表する大音楽家。 |

コンスタンツェ・モーツァルト
Constanze Mozart
1762/1/5-1842/3/6 |
オーストリアの作曲家、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトの妻。モーツァルトの死後、ゲオルク・ニコラウス・ニッセンと再婚し、ザルツブルクで没した。 |
そこで見つけたこの本。
なるほどね。この本の記述、あえて逆方向に持っていくバイアスで書かれたものなのかどうかはわかりませんが、ワングランスで人を評しちゃいけないよな、と考えさせられました。
序章は 琥珀のなかの「蠅」という題。
音楽学者アルフレート・アインシュタイン(1880-1952)とは、20世紀前半を代表するモーツァルトの権威だそうで、かの物理学者アルベルト・アインシュタイン(1879-1955)とは別人。かの天才と血縁関係があるのかないのか、今でも定かでないらしい。
このアルフレートが、『モーツァルト その性格 その作品(Mozart. Sein Charakter, sein Werk)』でこのように語っています。
| モーツァルトの妻コンスタンツェ・ウェーバーとは、何者だったのか? 彼女の名声が今なお続いているのは、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトが彼女を愛し、それによって彼女を永遠の中に連れていってくれたおかげである。それはまるで、琥珀のなかに蠅が閉じこめられたようすと同じなのだ。だからといって、彼女がこうした愛や名声にじゅうぶん応えていたとはかぎらない。(P8) |
アインシュタインはは、コンスタンツェはモーツァルトの妻の座を得て初めて後世に名を残せた、といいたいだけではない。彼女を「蠅」、御馳走に群がる醜く汚らしい蠅であり、モーツァルトという琥珀なくしては存在さえ許されない下劣なもの、と貶めているのです。
これはひとり彼アルフレート・アインシュタインだけでなく、数多くのモーツァルト伝で言われていたことでした。なぜこれほどまでに彼女は否定的に評されていたのか。
| それにしても、人はコンスタンツェにいったい何を見てきたのだろう? またそのような視線のなかに、人はどのような想いをこめてきたのだろう? 「悪妻」と呼ばれつづけてきたひとりの女性をめぐって、人間の抱える複雑な羨望と嫉妬を解きあかしてゆきたい。(P11) |
この本の主題は、ここです。
 まず、埋葬された墓、墓石から話が始まります。右写真は、ザルツブルク市にある聖セバスチャン墓地のもの。 まず、埋葬された墓、墓石から話が始まります。右写真は、ザルツブルク市にある聖セバスチャン墓地のもの。
1829年に亡くなったナンネル──モーツァルトの姉マリア・アンナの愛称──は兄嫁コンスタンツェに不満を持っていたのだそうです。理由は、かつて埋葬された父レオポルト・モーツァルト(1719-1787)の墓をコンスタンツェが我が物として、二番目の夫ゲオルク・ニコラウス・ニッセン(1762-1826)や実家であるウェーバー家の墓地とした事によるそうな。
墓を見るとわかるように、この墓でもっとも大きいのがコンスタンツェの墓碑で、その裏にニッセンの名が彫り込まれています。そしてその前にふたつの小さな墓碑があり、右がレオポルト・モーツァルトとオイフロジーナ・ペルトル(レオポルトの妻アンナ・マリアの母)の墓碑で、左がヤンネッテ・ベルヒトルド・フォン・ゾンネンブルク(モーツァルトの姉マリア・アンナの娘)とゲノフェーファ・ウェーバー(コンスタンツェの叔父の妻)の墓碑。つまり、尊敬されるべき大モーツァルトの父の墓碑が、その他の女性たちと同じ扱いにされてしまっているのです。
激怒したナンネルは、コンスタンツェの夫ニッセンが亡くなってここに葬られたのち、市内の聖ペーター教会の墓地に埋葬するよう遺言書を書き換えたのだそうな。
しかも、肝心のモーツァルトには墓さえもなかったのでした。葬儀はきわめて簡素に行われ、柩は関係者がだれひとり立ち合わないままでウィーン郊外の聖マルクス墓地の共同墓石に葬られました。コンスタンツェは長年にわたって墓地を訪れようとせず、墓に十字架が立っていたのかなかったのかも知らず、15年後に彼女が墓地におもむいたとき、埋葬場所を知る人はもうだれもいなかったそうな。晩年にバイエルン王ルードヴィヒ1世に謁見したとき、墓所に祈念碑がないのはなぜかと問われて、埋葬に関わった司祭が十字架を立てたと思っていたと答えた、という記録があります。
このような「事実」が、コンスタンツェがいかに冷酷で無神経な女だったのか、という例となりました。
本当にそうだったのか。
これには、当時の慣習や法を頭に置き、過去に何があったのかを考えると共に、数々の「信頼すべき伝聞」が本当に信頼できるものなのか、偏見の無い目で見直さなければならないことを考えさせてくれます。
1898年にこの墓について特別許可を取って墓を掘り起こしたヨハン・エヴァンゲリスト・エングルというモーツァルト研究家は、掘り起こした遺体から詳細な研究を行ったのですが、DNA鑑定ができた現在の調査研究とはまったく異なった研究結果を出してしまったのでした。
これは「悪女コンスタンツェ」ありきという背景による色メガネでみた結論であり、問題は彼らは自分たちが公明正大で正しい過去を発掘したと思いこんでいたことによる。
この墓碑に関する現在の「正しい答え」はこうなっています。
まず当時、ハプスブルク家の当主ヨーゼフ2世の政策により啓蒙主義的な改革が行われ、その一環として質素倹約が重んじる一環として葬儀・埋葬の簡略化が行われていたのだそうです。その結果モーツァルトが亡くなった頃も質素なのが当たり前で、柩を墓地へ運ぶ際でも親族や関係者が付き添うことも墓碑を建てたりすることもまれで、どこに埋葬したのかもわからないのが当たり前だったとか。この慣例は19世紀には廃れ、葬儀を大がかりにする方が一般的になったそうです。
またそもそも聖セバスチャン教会の墓地は共同墓所であり、さまざまな関連のない人々が葬られるものでした。外交官・伝記作家であるニッセンがそこに葬られて墓碑が建てられたあと、コンスタンツェが亡くなって葬られ、彼女のことをよく知らない第三者が墓碑を180度ひっくり返して間違った生誕地、生年などを彫り込み、そのあとで小さな墓碑が別な人間によって建てられたのだということ。またレオポルトは全然別な場所に葬られていること。
作られた歴史を正すためには、大変な努力がいると言うことです。
| こうして、後世の「思いこみ」と、それを補強する「科学的証明」による「事実」の誕生により、まったくの濡れ衣をコンスタンツェは着せられた。では彼女が着せられた濡れ衣は、聖セバスチャン教会の墓地に関するものだけだったのか? 続く第一章では、以上のような思いこみを生んだ、コンスタンツェとその実家に対するレオポルトとマリア・アンナの姿勢をつぶさに見てゆこう。(P26) |
で、第一章が始まります。
モーツァルトを愛するあまりその業績に益をもたらさなかった(らしい)その妻に嫉妬した人々が、自分の視点が嫉妬であることに気づかず築き上げた「悪女伝説」とはどのようなものだったのか。
なるほどね。
いろいろこの本の中から抜き書きしたいことはあるけど、著者の最後の言葉でじゅうぶんです。
モーツァルトを愛でるのはよい。後世に生きる私たちは、彼の音楽を、さらにはその人生を楽しめばよい。だからこそ高級そうな知識をふりまわして、あるいはそうした知識をもっていることを鼻にかけて、他人の悪口を言う真似はそろそろ慎んだらどうだろう。
コンスタンツェをいかに語るかという姿勢のなかには、それを語っている当人の本性が必ずや滲み出ているのだから。(P293) |
その言葉、胸に刻んでおきます。m(_ _)m (2025/5/4)
読書メーターの記録より 読了:2020/10/6 |

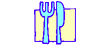

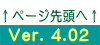
 コンスタンツェ・モーツァルトというモーツァルトの「悪妻」のことを知識として知ったのは大学の頃だったかな。その後映画『アマデウス』(1984)で描かれた彼女の姿を見て、かえってそんなに非道くはないじゃない、と思ったものでした。
コンスタンツェ・モーツァルトというモーツァルトの「悪妻」のことを知識として知ったのは大学の頃だったかな。その後映画『アマデウス』(1984)で描かれた彼女の姿を見て、かえってそんなに非道くはないじゃない、と思ったものでした。

 まず、埋葬された墓、墓石から話が始まります。右写真は、ザルツブルク市にある聖セバスチャン墓地のもの。
まず、埋葬された墓、墓石から話が始まります。右写真は、ザルツブルク市にある聖セバスチャン墓地のもの。