トップへ戻る 作家/分野 一覧 |
|
 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |
|---|---|---|---|
| M116-001 | 海軍兵学校生徒が語る太平洋戦争 | あの戦争は、どう解釈すべきなのか | |
 |
Ver. 3.04 |
|---|
| 管理番号:M116-001 | 52J 戦史・戦争ノンフィクション(日本) | 出版社:光人社 | |||||||
| 書名:海軍兵学校生徒が語る太平洋戦争 | 日中・日米戦の舞台裏 | ISBN978-4-7698-3007-8 C0195 | |||||||
| 平成20年1月「私観 大東亜戦争」改題 元就出版社刊 | |||||||||
| 光人社NF文庫 み1007 | 価格:760Yen | ページ数:264P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2017/5/21 | 購入:2017/5/13 | 表紙イラスト: | |||||||
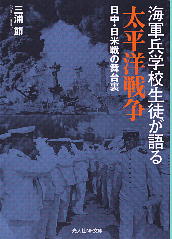 著者、三浦隆氏は、昭和16年に海軍士官学校を卒業しています。つまり海兵70期。このクラスは、戦争にともなって下級指揮官として最前線で指揮を執った初級士官が多く、入校した432名中生き残ったのは146名、戦死率66.2%という、兵学校卒業者死亡率トップだったのだそうな。 著者、三浦隆氏は、昭和16年に海軍士官学校を卒業しています。つまり海兵70期。このクラスは、戦争にともなって下級指揮官として最前線で指揮を執った初級士官が多く、入校した432名中生き残ったのは146名、戦死率66.2%という、兵学校卒業者死亡率トップだったのだそうな。そんな経験をした著者が、戦後半世紀以上経ってあの戦争について改めて論じます。 あの戦争では、本当に日本は悪者だったのか。
著者はこれに異論があります。 これを論文にまとめ、海兵70期の会誌に8年間に発表したものを整理し直したのがこの本。最初は元就出版社で刊行されたものだそうです。 アメリカが、1930年代の終わり頃には日本の外務省及び海軍の暗号を解読し、マジック情報として政府の叱るべき人々に配布されていたのは事実です。これにより、詳細はともかく日本の政治的・軍事的判断は英米には筒抜けになっていました。それを踏まえ、著者はこう論じます。
ナチスを屈服させるために妥協を許さぬ Unlimited War を唱える以上、日本に対しても当然同じ事を要求し、中途半端な Limited War しか想定していない日本を全敗に追い込んだのは、そういう理由なのだそうな。 正式な宣戦布告前の真珠湾攻撃をもって「卑怯な日本の征伐」という大義名分を得て、戦後も日本の朝野を後悔というくびきでがんじがらめにした論理は、実質的に日本を石油禁輸という荒技によって経済封鎖に追い込んだ時点で宣戦布告なき戦争をしかけたといえる。ならば正義を唱える権利がアメリカ側だけにあるという理屈は通らないはず。 ルーズベルトを囲むさまざまな人々の中で、戦争に至る歴史の流れが作り上げられます。西側社会に食い込んでいたコミンテルンの長い手もそのひとつであるが、その流れの中で間抜けにも一方的に袋小路に落ちこんで戦争に至った日本という国家はどういうものなのか。 満州事変・大東亜戦争は侵略戦争であったか という章で、侵略戦争をおかしたとして非難され、反省している日本の現状の中で、はたしてこれは事実なのかを検証しています。 そもそも1928年に生まれたパリ不戦条約において、戦争は「War of Aggression(Aggressive War)」と「War of Self-Defence(Defensive War)」に分類されました。この後者を自衛戦争と訳すには全く問題はないのですが、前者はそもそもが、国際法上挑発を受けないのに行う正当な理由のない攻撃を意味するものでした。「奪い取る」という意味はありません。では、「侵略」という訳語をあてはめるのはそもそも無理がある。「進攻」と訳すべきと言ったのは佐藤和男教授、「先制攻撃」を提唱したのは小堀桂一郎教授だそうですが、現在の日本では誤訳とも言える「侵略」が定着しています。 東京裁判というものは、そもそもが勝者が敗者を裁くものなのですが、満州事変及び大東亜戦争を War of Aggression と断じ、これは犯罪であり、その責任は指導者個人に追及されるという戦後に確立されたルールに基づく主張を行います。 しかしこれを単純に正義が悪を懲らしめる構図から離れ、歴史的事実を積み重ねると、違うのではないかという。 満州事変とは、日本が自力で政治的軍事的に真空地帯となっていた満洲という土地に権益を確立したことへの、日本を仮想敵国としたアメリカに背を押された中華民国の反発によるもの。すなわち、当時の情勢の中で世界中で行われた領土紛争のひとつであること。日本が国際連盟を脱退した引き金となったいわゆるリットン調査団の報告書でさえ、その事実を追認しているのである。 日華事変(日中戦争)に至っては、中立を標榜していた米国は現役の陸軍将官が率いる「義勇軍」を半ば堂々と中国に送りこみ、日本軍と正面切って戦っています。これは正当な行為なのか。 ならば善悪だの正義だのを論じても、勝者の言葉が優先する帝国主義の時代では無意味ではないか。 大東亜戦争に至っては、モンロー主義を国是として南北アメリカ大陸外の紛争に介入しないと宣言していたはずのアメリカは、あらゆる手段で日本の行動に掣肘を加えます。政治的、経済的な圧力に加え、第二次、第三次のビンソン案によるアメリカ海軍の増強計画を知って日本海軍軍令部は息を呑んだと言われます。どう考えても、アメリカは日本に対する敵視政策を露骨に示したとしか思えない。 それが正義のためであれなんであれ、日本が米・英・蘭に宣戦を布告して始まった太平洋戦争(大東亜戦争)は、アメリカの圧力に反発した側面があることは疑いようがない。 それを、敗戦した日本が「悪い国だったから征伐された」論で沈黙させられて、それでいいのか。 原爆投下の真相を問う の章はこの文章で始まります。
にもかかわらず、なぜ原爆投下へと至ったのか。 なぜ日本の降伏前に投下しなければならなかったのか。 日本本土上陸作戦で、米兵100万人が犠牲になるという神話はどうやって生まれたのか。 日本政府がポツダム宣言を「黙殺」したことは、原爆投下の原因のひとつであったのか。 真珠湾の奇襲にたいする復讐だという神話は、成立するのか。 筆者は 、満州事変・大東亜戦争と統帥権の独立について の章の最後に、こんなまとめを残します。
そのあと、重巡「妙高」で起きた魚雷の失敗談、戦艦「大和」の最後の時のエピソードなどが語られます。 沖縄特攻で生きのびた駆逐艦「霞」から脱出する時、「わたし」が艦長から受けた命令の話が最後になります。大破して味方に処分される直前、松本艦長はわたしに士官室へ入って金庫のカネを回収してこい、と命じたのです。この期に及んでカネとはなんだ、と思ったそうですが、そのカネが後でものをいうことに。艦と共に沈んだはずのものですので請求されることもないものですが、このカネを主計科にわたしたところ、その後に沈没して着の身着のままになった乗組員たちが他の部署や艦艇に配属される度、一つかみずつ選別として渡したのだそうな。士官には渡さず下士官・兵のみに。 何度も沈んだ艦から生還した歴戦の艦長ならではの心配りであったとのこと。 歴史とは、後世に書き加えられ、作り直されるもの。今の欧米中心の「勝った側の人々が作った」歴史が正しいとは言えません。またそれを正義と思ってはいけない。 立場を変えればこういう解釈もあり、こういう正義もある。 こんな文章を残してくれる人々を、尊重したいものです。 この論がメジャーになりうるかというと、今の時代では難しいでしょうけどね。(2017/9/17) 読書メーターの記録より 読了:2017/8/26 |
|||||||||||||