 トップへ戻る 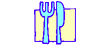 読んだ本の分類 |
|
 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 書 名 | 翻訳者 | メ モ | |
|---|---|---|---|---|
| S010-003 | シリウス | 中村能三 | 人間並みの知性を与えられた犬の物語 | |
| 管理番号:S010-003 | 13 SF古典 | 出版社:筑摩書房 | |||||||
| 書名:シリウス | ISBN978-4-480-44038-9 C0197 | ||||||||
| 原題:Sirius A Fantasy of Love and Discord(1944) | 翻訳者:中村能三 | ||||||||
| ちくま文庫 す26-3 | 価格:1300Yen | ページ数:348P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2025/7/10 | 購入:2025/7/21 | カバーデザイン:山田英春 | |||||||
 かつてこの本は、早川書房からハードカバーのSF全集として刊行され、1976年にハヤカワ文庫SF191として文庫化されました。翻訳はどちらも中村能三さん。 かつてこの本は、早川書房からハードカバーのSF全集として刊行され、1976年にハヤカワ文庫SF191として文庫化されました。翻訳はどちらも中村能三さん。この本は、それら元に、中村能三氏(1903-1981)の著作権者の了解のもとに一部表現・表記等を修正してちくま文庫で再刊されたものです。 この本をハヤカワ文庫で読んだとき、正直理解が十分ではなかったかもしれません。とはいえ、当時本棚の目に付くところに、そのとき読んだ本のベスト10か20を新たな本を読むたびに選ぶ直していたのですが、数年の間「シリウス」はトップスリーの座を動きませんでした。 だからといって、いまも上位にあるかというと、それは別問題。 物語の時代は、20世紀前半から半ば。正確には、1920年代半ばから40年代。 原題は、「シリウス──愛と不協和のファンタジー」。 第一章は、プロローグめいたもの──あるいはエピローグか。 プラクシーという女性と愛しあっていたという、「私」の一人語り。
それは「私」の愛であって二人の愛とは言えないのではないか、という疑問は、半世紀前は抱かなかったろうなぁ。 プラクシーの母親が病死した後、彼女は姿を消します。受け取った差出人住所が書いていない手紙によると、父の仕事に関係がある「変わった義務」のため会えないのだそうな。理解できない私はためらった末に彼女を探しに北ウェールズに向かい、苦労を重ね十日間ののちようやく山の中のフェスティニオグ村の近くで彼女を発見します。 そこにいた彼女は、一頭の大きな犬と共に暮らしていたのです。彼女は私の顔を見てちょっと驚き、かたわらの犬に話しかけ、犬はそれに答えたようでした。
この犬が、シリウスでした。 ここから20数年遡り、シリウスの物語が「私」の調査結果というかたちで語られます。 プラクシーの父親トマス・トレローンは偉大な科学者でした、といわれます。生化学者なのか、生物学者なのか、よくわかりませんが、生物の知能を増大させる研究を行っていました。世間の脚光を浴びることを嫌がる彼は、ケンブリッジのわずかな同僚と妻以外には研究について徹底的に秘密にしています。その研究はネズミ類から始め、ウサギなどを経てさまざまな哺乳類で実験を行った末に、本格的に犬を改造する研究を行うこととなりました。猫にしなかったのは、体が小さいので不適格であったから、だそうな。 ある種のホルモンによって大脳皮質の容積を増やすと共に、神経組織そのものを正常よりはるかに細くし、ずっと多数の結びつきが生じるようにしたことが、彼の研究の根幹でした。母親を経由してそのホルモンを注入するのですが、そのために母親の脳が生育しないようにすることが課題でしたが、これも克服されます。もし母親の脳が生育すれば、その頭蓋骨の中で破裂してしまうから。出産後の子供は頭蓋骨の縫合栓が閉じるのを遅らせるようにすると共に、頸部の骨格および筋肉を強化して、肥大した脳の重さに耐えられるよう改造されます。 北ウェールズの牧羊地帯に家を持って本格的に研究を進めたのは、約20年前。妻エリザベスと三人の子供、そしてやがて生まれて来る子供と共に。またこのとき、すでに第一世代の犬たちが育っていると共に四頭の生まれたばかりの子犬がいました。 最初の世代の犬たちは、「超牧羊犬」として近くの農家に売られました。 頭が異様に大きい犬を怪しんでいた農民たちですが、この犬が利口なんてものではない、牧羊犬としてすばらしい能力を持ち、教えたことはすぐに身につける上に農民が口頭で命じた事を理解して従うことに驚きます。メモを持って村に買い物に行くことすらできるのです。 なんだかよくわからない博士の研究とはこれだったのか、と周囲は思います。多くの科学者たちもここを訪れるようになり、超牧羊犬の需要が高まると共にトレローンの評判は高まりました。喜んだ農夫たちは、この犬たちの血統が次の世代に遺伝すると信じて繁殖させましたが、子供にその能力が継承しないと知って落胆します。トレローンのホルモン療法と外科的な処置なしには、超牧羊犬は生まれなかったから。 そしてトマス・トレローンの研究のゴールはそこではなかった、と知っているものはほとんどいません。 彼は、末娘と同じ年に生まれ、極端に成長の遅れている一頭の子犬に重大な期待をかけたのです。 人と獣を繋ぐミッシング・リンクとして。 四頭生まれ、その中でたった一頭生き延びた一頭、シリウスは、人間と同じ速度で成長しています。彼は妻を説得し、末娘プラクシーといっしょに育て、同じ教育を施そうとしたのでした。それが、彼の一つのゴール。 その結果、シリウスの苦難と挫折の生涯が始まります。 読んでいて、さまざまな違和感が生まれます。古いSFであるが故の設定の古さは、しかたない。まず最初の指摘と言えば遺伝子への言及がないことでしょうが、それ以外にもいろいろ。これは仕方がない。 人間に近くなれるように人造生物を育てようとする、という人間こそが最も優れた文明と知能を持っている考え方も、時代を反映しているからしかたないのかも。 だから、シリウスが手が使えないので人間のように自由に道具を使えないと悩むことも、この延長線上なのか。 シリウスが色盲なので美術的な感覚が理解できず苛立つ、という描写。どうなんだろう。犬は狩猟生物として人間とは異なる色彩を識別できるはずだし、なにより聴覚・嗅覚は人間の何十倍何百倍なので、ある程度彼の「教育」が進んで人間中心主義を客観視できるようになれば、絵画を鑑賞できない、景色の美しさを共感できないことなど無意味になると思うのだけど、どうなのか。 いずれにしてもシリウスは、人間に、それも学歴のある学究的で高等な「人間」たるべく育てられ、肉体的にも精神的にもそうなれないことに絶望します。犬としての自分を捨てられなかったから。 彼に課された教育は、人間の子供、学生、青年になるためのものだった。それが正しい進化だと信じられた。 獣の野生とは、進化の階梯の下にある愚かな因襲であり、打破すべきものだと思う人たちは、そう考えた。 宗教も絡みますが、愚かな時代錯誤の道徳を強制するものとしてでしかない。 キリスト教という文化は、良きにつけ悪しきにつけ欧米世界の文明の根幹を成していたのですが、この時代はもう時代錯誤の愚かな因襲と認識されていたのでしょうか。それもまた、文化。 時代は、二つの大戦を挟んだ時代から始まり、第二次大戦の中で、悲劇として終わります。 今回読んで思ったこと。この長い物語は、無理解な愚か者にシリウスが潰されるまでを描いている。そういうことかな。 愚か者とは、シリウスに致命傷を与えた無学な村人だけではない。犬を人間のレベルにまで引き上げたやろうと考えた、頭の良い愚かな人たち。 作者が何を望んで書いたのかは別、むろん。 この読み方は、おそらく正しくないという気がしますけど、個人的には今、この物語はベスト20にも入りそうにない。 読んでいて思ったもうひとつ。これは「フランケンシュタイン」(メアリ・シェリー)じゃないか。 むろんあの通俗的なホラー映画じゃない、小説の方。 若いフランケンシュタイン博士が作った人造人間──「怪物」は、自我を持ち、知識をむさぼり、それでも人間になれない自分に絶望し、自分を愛してくれる伴侶を求め、悲嘆の底で自分を迫害しようとする人を殺し、自分を生みだしたフランケンシュタインへの恩讐の果てに最後を遂げます。 シリウスと微妙に違うけれど、微妙に重なるところがある。
同じ連想をする人もいるんだなぁ。 半世紀後に読み直せた一作。いろいろな意味で感無量でした。(2025/09/06) 読書メーターの記録より 読了:2025/9/1 |
 両眼の上に二つの大きな淡黄色の斑点があって、それが彼の顔にふしぎと仮面に似た表情、あるいは、目穴の開いた兜を顔から上に上げた、ギリシャの彫刻のような外観を与えていた。シリウスが特にほかの犬と
両眼の上に二つの大きな淡黄色の斑点があって、それが彼の顔にふしぎと仮面に似た表情、あるいは、目穴の開いた兜を顔から上に上げた、ギリシャの彫刻のような外観を与えていた。シリウスが特にほかの犬と