トップへ戻る 作家/分野 一覧 S076佐藤賢一へ |

|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Ver. 2.23 |
|---|
| 管理番号:S076-019 | 32 歴史小説・西欧史 | 出版社:集英社 | |||||||
| 書名:革命のライオン | 小説フランス革命 1 | ISBN978-4-087-46738-3 C0197 | |||||||
| 仏語題:Le lion de la Révolution | |||||||||
| 集英社文庫 さ23-9 | 価格:476Yen | ページ数:240P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2011/9/25 | 購入:2012/5/19 | ||||||||
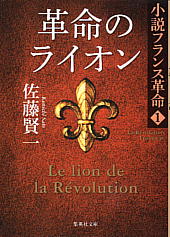 ハードカバーで出たのは2009年でしたか。そのとき読まなかったのは、「サトケン節」への拒否反応でしょうか。あくが強い文章を書く人ですからね、波長が合わないと思うとき、離れてしまうことがある。 ハードカバーで出たのは2009年でしたか。そのとき読まなかったのは、「サトケン節」への拒否反応でしょうか。あくが強い文章を書く人ですからね、波長が合わないと思うとき、離れてしまうことがある。この方の著作で名高い初期作品の、「ジャガーになった男」にしても、再読してみようという食指が動かない。(あれ、日本語変かな?w) で、この本を改めて文庫で買ってみたのは何故だろう。立ち読みしたときに、琴線に触れるものがあったのかな。 さて、フランス革命。 この発端をどこに置くのか、ということで佐藤さんの視点が決まるか。
佐藤さんはここで、ネッケルが就いたのはブルボン家の財務長官である、とさりげなく書いています。「フランスの」あるいは「フランス王国の」ではない。つまりこの時代、近代的な意味での「フランス国家の財政」というものは存在せず、変な言葉ですが、フランス王家がフランスを私物化した状態であった、ということか。いわゆる立憲君主国との違いをここでさりげなく書いているような。フム。 フランス革命に至る道程の中で、このフランス王室の膨大な赤字財政とその対抗策の失敗というものがあります。切り口としてわかりやすい。これに重ね、国王ルイ16世の失政とか、王妃マリー・アントワネットによるとんでもない乱費なども、原因として語るのに楽ですね。 主原因ではないと言うつもりはありませんよ。しかし導入しやすいアプローチです。 この財政を健全化させるために打った手のひとつが、全国三部会の開催。当時税金を取られることがなかったフランスの第一身分(聖職者)、第二身分(貴族)からも徴収する事を目的としたもの。これが紛糾したことが、第三身分(平民)たちを立ち上がらせる遠因となり、フランス革命が始まったといえるのです。
この時代の動乱を、作者はまず平民財務長官ネッケルから説き始めます。次にターゲットとしたのは、筋肉質で長身で見事な体躯を誇る巨漢、貴族であり伯爵の身分でありながら、平民の代表として三部会の舞台に登場した男、ミラボー。 この本の題となった「革命のライオン」とは、議会をそのとどろくような大声の弁舌で支配し、国民に絶大な人気を博したこのミラボーのこと。 次にスポットライトを浴びせたのは、風采の上がらぬ青年。早くに孤児となって苦労しますが、図抜けた頭脳を生かしてルイ・ル・グラン学院を主席で卒業し、弁護士となり、第三身分代表の議員となって登場した貧相な小男、ロベスピエール。 この巻は、三部会に絶望した第三身分議員が国民議会の新設を宣言して、1789年6月19日、第一身分である聖職者を抱き込むことに成功するまでを描きます。 革命の火蓋を切ったバスティーユ襲撃まで、あとわずか。(2012/9/4) |
|||||||||||
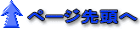 |
Ver. 3.00 |
|---|
| 管理番号:S076-020 | 32 歴史小説・西欧史 | 出版社:集英社 | |||||||
| 書名:パリの蜂起 | 小説フランス革命2 | ISBN978-4-08-746748-2 C0193 | |||||||
| 仏語題:L'insurrection de Paris | |||||||||
| 集英社文庫 さ23-10 | 価格:476Yen | ページ数:256P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2011/10/25 | 購入:2012/10/19 | ||||||||
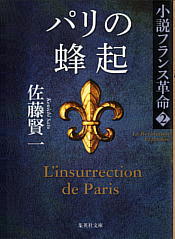 1789年6月19日に、ミラボー侯爵ヴィクトル・リケティが死んだという知らせが、その爵位を継ぐはずだった息子ミラボー伯爵に届けられたその翌日から始まります。 1789年6月19日に、ミラボー侯爵ヴィクトル・リケティが死んだという知らせが、その爵位を継ぐはずだった息子ミラボー伯爵に届けられたその翌日から始まります。この父とは絶縁状態だったミラボーの、父に認められなかった恨みつらみがじくじくと綴られます。 ああ、サトケン節だ。 ──そういえば、やたらと ああ、 という感嘆詞を挟むのもサトケン節だな。 鐵太郎にとって、この言葉遣いとコンプレックスだらけのうっとうしさに慣れるところから始めなきゃいけないのが、佐藤賢一本を読む時の心構え。(笑) 歴史上で活躍した人物を描き彼らもまた人間的な弱さも持っていたんだよ、と言う話のもって行き方自体は嫌いじゃないのですが、そろいもそろって同じような僻み丸出しのコンプレックスを抱いていると言うのはいかがなものか、サトケン節。もうちょっと違うパターンを読みたいねエ。 さて6月20日、雨のヴェルサイユで議場を閉め出された第三身分代表の議員たちは、呆然とたたずんでいます。やっと三部会が開催されたというのに、陰に陽に虐められ、屋根のある建物への入場を一見合法的理由により拒否されてしまう。
熱っぽく体のだるいミラボーは、やかましいばかりの議員たちの声に頭痛がひどくなり、するべき役を終えたのち、自分の弟子にしようかと考えているロベスピエールを連れて早々に立ち去ってしまうのでした。 人民の権利という概念が、アメリカ独立運動やさまざまな文献によって確立されたあと、じわじわと浸透していったこの時代、革命に至る流れはまだゆっくりで、試行錯誤の段階です。身分制度の不公平感をどうなくすのか。特権階級の特権はどこまで許容されるのか。国王にどんな統治して貰えばいいのか。
この時代、国王を排除するという冒涜的な発想を持った人はいたかもしれませんが、王制それ自体を排除しようという発想は、まだなかったと言っていい。その流れがいつ頃できたのか。 はるかな未来という 「神の立場」 にいる現代人が、当時の人々の愚行にも見える試行錯誤を笑うのはたやすいけれど、試行錯誤なしには新しい歴史は産まれなかったのです。 しかし時代の流れは容赦なく進む。特権階級の度重なる背信によって民衆の怒りが高まり、パリはついに蜂起します。 その中心に立ったのは、ミラボーとロベスピエールにたきつけられたカミーユ・デムーラン。このひ弱な青年が、民衆の先頭に立つ。 サトケン節にいらつきながらも、第二巻まで読み進めました。この時代の歴史を新しい視点で読み直すのは非常に楽しみなんですが、この人の文体にこれからもつきあえるのか。大丈夫か、自分、と問いかけつつ第三巻はいつ買おうかと悩んでいます。(笑)(2013/02/07) |
|||||||||||
 |
Ver. 3.01 |
|---|
| 管理番号:S076-022 | 32 歴史小説・西欧史 | 出版社:集英社 | |||||||
| 書名:バスティーユの陥落 | 小説フランス革命3 | ISBN978-4-08-746760-4 C0193 | |||||||
| 仏語題:La chute de la Bastille | |||||||||
| 集英社文庫 さ23-11 | 価格:495Yen | ページ数:272P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2011/11/25 | 購入:2015/2/10 | カバーデザイン:泉沢光雄 写真:アフロ |
|||||||
 フランス革命に限らず、歴史のイベントというものは、あとからいかにきらびやかに見えたとしても、その時代で歴史を創った人々にとっては泥臭いものの積み重ねであるもの。この
「本当は泥臭かったんだよ」 という歴史を、佐藤賢一さんはことさらにそれを強調するわけでもなく、実に泥臭く積み重ね、語っていきます。 フランス革命に限らず、歴史のイベントというものは、あとからいかにきらびやかに見えたとしても、その時代で歴史を創った人々にとっては泥臭いものの積み重ねであるもの。この
「本当は泥臭かったんだよ」 という歴史を、佐藤賢一さんはことさらにそれを強調するわけでもなく、実に泥臭く積み重ね、語っていきます。この巻は、1789年のパリ市民による有名なバスティーユ要塞襲撃事件から、和解のためのさまざまな手当て、試行錯誤、あがきを経て8月26日の人権宣言、正確には 「人間と市民の権利に関する宣言」 が採択され、10月5日から6日にかけて行われたパリの女たちによるヴェルサイユ大行進、そして国王一家のパリへの移動までの三ヶ月足らずの歴史を描きます。 まず焦点が当たるのは、カミーユ・デムーランとジョルジュ・ジャック・ダントンの二人。ともに当時29歳で弁護士。そしてジャン・ポール・マラ。46歳の医者。 1789年7月12日早朝、ふらふらと目覚めたデムーランは、昨夜フランス衛兵隊に助けられつつ群衆を率いて正規軍であるドイツ傭兵をパリのテュイルリ宮殿から追い払ったことで一躍英雄となっている自分にとまどっているところ。爆発寸前だったパリの民衆はついに立ち上がったのでした。飢えによって暴発寸前だったとはいえ、きっかけになったのはたしかにこの青年の声。 この結果としてパリが貴族の支配から市民の手による自立の道を進むことになるようだったのですが、ここでひとつ問題が出ます。市民を率いるのはだれなのか。飢えた民衆ではなく自分たちである、と進み出るのがいわゆるブルジョア階層。豪商たち。彼らが、パリに秩序を取りもどすのは自分たちが組織する民兵であると宣言します。 なぜならば、彼らはそもそも選挙民として政治にかかわっており、かつ軍隊の兵装を自弁できるから。 市政庁に集まった群衆を睥睨して、パリの商人頭、豪商フレッセルが言います。
しかし彼らはアンシャン・レジームの代表格である、とデムーランは思う。貴族たちの下でパリの街を支配してきた彼らブルジョアが支配権を握ったら、貴族の横暴を倒すために民衆が立ち上がった意味がない。 そこでこんな言葉が出ます。
そう、あのバスティーユにはあるんじゃないか。 そして、サン・タントワーヌ通り232番地にある中世の遺物に、パリ市民は殺到します。時に、1789年7月14日。 この騒乱は、史実と指摘されているとおり民衆側の勝利となります。サトケンはこれを、実に泥臭く、ねっちっこく描写します。こういう描写になると、この人の文章は躍動しますなぁ。
そして第一、第二身分は、この時点でも絶対的な軍事力を動かしうると思われていたのです。 時を移さず、国民議会は自分たちの権利を宣言することを考えます。これにより、国家を動かす一大戦力としての存在価値と大義名分を示すため。病んだフランス政体の象徴である貴族による弾圧政治を跳ね返す革命を正当化するため。 この急進的な流れに対し、穏健派というか消極派もいたのでした。その先鋒にミラボーがいるとなると、話は単純に石頭の守旧派による妨害とは言えなくなる。彼の説く、現時点では過激とさえ言える人権宣言が一人歩きをしてしまったら、本来の目指すべき目的である憲法がそれに拘束され、フランス国家としての統一を妨げる結果になりはしないか、という論も、無下に否定はできない。 デムーラン、ロベスピエールらは、制定に年単位の時間がかかる憲法より、立ち上がってなにがしかの勝利を得た今こそ、悠長なことを言っていないでまず宣言をすべきだ、と主張します。大貴族たちがとりあえず負けを認めて次々と亡命しているいまこそその機会だと。 1789年8月4日、多数決により憲法制定国民議会は、憲法制定に先駆けて 「人権宣言」、正確には 「人民と市民の権利に関する宣言」 を採択すると決議します。 この時代の人で、これが未来に何をもたらすか、見通せた人は誰もいません。 しかしここで議会は、王の地位について、王の権限についての議論でまた紛糾します。このとき、第一第二身分はむろんのこと、下層民衆も、むろんブルジョア階層も、国王を排除しようとは思っていません。 王の拒否権、王の絶対性を維持することを主張するミラボーは、こう説きます。
議会の混迷を腰砕けとみる民衆は、パレ・ロワイヤルに集まって気炎を上げます。集まったのが飢えた女たちだったことが運命を分けたのでしょうか。彼女ら、政治的にはなんの権利も持っていない衆愚の民は、パレ・ロワイヤルの英雄デムーランを交えて、実に軽いノリでこんな事を言いだしたのでした。
なんと国王をヴェルサイユの壮大な穴蔵から引っ張り出してパリの町の中に連れてきたのは、この女たちだったのでした。 この数ヶ月の動乱を描いて、この巻は終わり。革命はまだ序の口です。サトケン節、快調。(2015/8/18) |
||||||||||||||
 |
Ver. 3.01 |
|---|
| 管理番号:S076-023 | 32 歴史小説・西欧史 | 出版社:集英社 | |||||||
| 書名:聖者の戦い | 小説フランス革命4 | ISBN978-4-08-746771-0 C0193 | |||||||
| 仏語題:Les luttes des saints | |||||||||
| 集英社文庫 さ23-12 | 価格:495Yen | ページ数:272P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2011/12/20 | 購入:2015/2/10 | カバーデザイン:泉沢光雄 写真:アフロ | |||||||
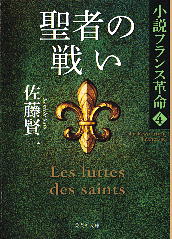 この巻でまず登場するのはタレイラン。このとき35歳。 この巻でまず登場するのはタレイラン。このとき35歳。右足が不具だった、というのが記録に残っていますが、その原因には諸説あるとか。佐藤さんは 「小説」 と銘打っているのだからどんな 「逸話」 を作ってもかまわないはずなのに、不明であるとします。
むろん、そんなものに頼らなくてもタレイランという人物は重厚です。シャルルマーニュその人まで遡る大貴族の家系で、タレーラン伯爵家の長男。パリ生まれ。足の障害のせいで父のあとを継いで陸軍に奉職することは出来なかったため、カルチェ・ラタンで学識を積み、聖職者としての道を進みます。このとき、つまりフランスに革命の波が押し寄せた1789年、彼はオータン司教という高位のカトリックの聖職者でした。 王なにするものぞ、という古い貴族の気概と、民主主義という新しい流れに乗ってみようという進取の衝動が、あふれんばかりの才覚に乗ってタレイランという人物の中に結晶化していったのでした。 タレイランが、45億リーヴルという文字どおり天文学的な負債を抱えているフランスの新たな収入源、税について、驚くべき提案をしたのは、10月10日の議会でのこと。
当時の教会財産は、推定30億リーヴルだったという。これをすべて国家が吸収すれば、国家財政は少しは回復します。 はたして、この提案は通るのか。
まず、医者にして科学者にして毒舌の文筆家という、はなはだ社会に迷惑な男、マラ。このとき46歳。
自由に何でも発言できる民主的な国家になったはずの革命フランスで、閣僚、パリ市長、ラ・ファイエット将軍らをこき下ろしたことで逮捕状が出たため、イギリスに政治亡命しようかと思案中。急進派。 そしてダントン。王室顧問会議付き弁護士にしてパリ、コルドリエ街治安委員。このとき30歳になったばかり。ジャコバン・クラブの会員にして論客。 フランス革命で、議会で左側を占めたために改革派・過激派が左翼と呼ばれ、反対側に座った保守的・守旧派的な人々を右翼と呼ばれることとなります。このあたりはまァ常識的に知っていましたが、それがテュイルリ宮殿 ちなみに、両者の中間に座を占めた穏健で無定見ながら多数派をなしている議員たちは、 そして登場するのが、 「デュポールが考え、ラメットが動き、バルナーヴが話す」 と称された左翼愛国派の若き三人の指導者。 アドリアン・ディポール、31歳。アレクサンドル・ドゥ・ラメット、30歳。アントワーヌ・バルナーヴ、29歳。 初期ジャコバン・クラブの一翼をなした彼らは、なにを求めるのか。 フランス王国という形態を変えないままで行われようという改革の行きつく先はどこなのか。 バスチーユ陥落の日付、1789年7月14日を革命記念日とするという決議がなされ、それから一年が経とうとするいま、なにが進行しているのか。 面白い。佐藤賢一はこういうアプローチであの時代を描いています。(2015/10/12) |
||||||||||||||
 |
Tweet | Ver. 3.01 |
|---|
| 管理番号:S076-024 | 32 歴史小説・西欧史 | 出版社:集英社 | |||||||
| 書名:議会の迷走 | 小説フランス革命5 | ISBN978-4-08-746783-3 C0193 | |||||||
| 仏語題:L'Assemblée se perd | |||||||||
| 集英社文庫 さ23-13 | 価格:495Yen | ページ数:272P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2012/1/25 | 購入:2015/2/10 | カバーデザイン:泉沢光雄 写真:アフロ | |||||||
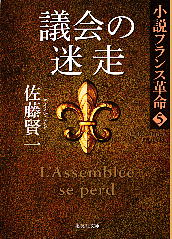
過激な思想から破綻に陥らずになんとか革命を軟着陸させようとするミラボーにとって、とりあえず手を組むとしたらここしかない。タレイランを仲介に使ってミラボーはラ・ファイエットに接近を測ります。 ターゲットは、バルナーヴが唱える、議会絶対権力思想。 フランスに新しい時代が来た、と革命政権は考えます。なんとなれば、人民が国家の主となる時代が来たのだから。 であれば、君臨する王という存在は、もはや無用とまでは言わないが、何一つ権限を持たせる必要はないではないか、と考えるのがジャコバン・クラブの過激派の思想。その先頭に立つのがバルナーヴ。 国王に絶対拒否権を与えるべき、とするミラボーの提案を、裏切り者として糾弾する姿勢。 ミラボーはなぜこのような提案をしたのか。そして1789年クラブの多数の中道ブルジョアを背景にして、どうやって過激思想に突き進みつつある議会を圧倒できたのか。
彼は絶対権力の存在をではなく、その一極集中を怖れていたのか。 しかしこうして革命の熱狂がいまだ継続しているパリの人々に冷水を浴びせる事件が次々起きます。 1274年以来公式にはローマ教皇領となっている都市アヴィニョンで発生した守旧派貴族の武装蜂起、南フランスの各都市で起きた争乱。ナンシー事件。 これによって、パリで革命を論ずる人々は思い知るのです。フランス全土が、パリと同じように革命の熱気にうたれて邁進しているわけではない、と。
徐々に健康を害しつつあるミラボーは、焦燥を憶えつつ迷走しつつある革命を軟着陸させようとします。その過程で、革命の第一人者としての地位すら目の前に。 すでにラ・ファイエットも影が薄い。 最後は、聖職者たちの反攻をどう凌ぐか、ということになりますが、これは次の巻に持ち越し。 しかしこの巻で、のちに革命政府を震撼させることになる一人の青年が登場します。かつてロベスピエールに、その身を一身に捧げるので使ってくれ、と熱心に手紙をよこした青年。
この巻は、1790年5月12日から、同年9月4日までの半年間の物語です。(2015/12/6) |
||||||||||||||
 |
Tweet | Ver. 3.01 |
|---|
| 管理番号:S076-025 | 32 歴史小説・西欧史 | 出版社:集英社 | |||||||
| 書名:シスマの危機 | 小説フランス革命6 | ISBN978-4-08-746792-5 C0193 | |||||||
| 仏語題:La crise du schisme | |||||||||
| 集英社文庫 さ23-14 | 価格:476Yen | ページ数:264P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2012/2/25 | 購入:2015/10/5 | カバーデザイン:泉沢光雄 写真:アフロ | |||||||
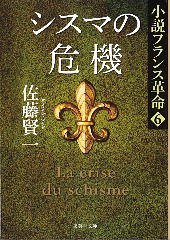 革命は終わりに近づいている ──と、1790年12月現在、民兵組織の中核を供給してきた富裕なブルジョア層は認識していたそうです。大貴族の専横は
「民衆の力」 ではねのけ、無事に我らの力を示して世の中を変えたではないかと。 革命は終わりに近づいている ──と、1790年12月現在、民兵組織の中核を供給してきた富裕なブルジョア層は認識していたそうです。大貴族の専横は
「民衆の力」 ではねのけ、無事に我らの力を示して世の中を変えたではないかと。ここで問題になるのは、このまま武器を民衆の、特に下層民の手に残してよいものか、という 「大人の」 議論。これに議会の中で地歩を固めつつあるジャコバン・クラブで噛み付いた者がいます。クラブがというより、ロベスピエールが。すべての市民が武器を持つのは権利ではないか、と。 しかし今やジャコバン・クラブの ミラボーのプラグマティックな思想は、常に妥協点と折衷をさぐるもの。いたずらに対立を深める手段は避けようとします。 しかしそれは、先鋭的な正義論とは折衷しづらいもの。未来を信じ正義を信じ理想を掲げる者には、過去との折衷や清濁併せ呑む度量というものは嫌悪の対象にこそなれ、未来への道程の一つとして考える事はできない。 フランス国王を頭に抱く新しい未来を夢見るミラボーは、ロベスピエールに代表される現在の破壊者、理想の追求者たちとは相容れない事を自覚しつつ、それでも一縷の希望を見ます。しかし、彼にはもう寿命が残っていなかった。 一人の英雄の終焉の前に、この巻ではシスマというあってはならない事態にスポットライトが当たります。 シスマとは、キリスト教の宗教界の内部分裂のこと。日本人にとってその意味は理解しづらいところがありますが、カトリック教会に精神世界が支配された彼らにとっては重大事。 フランス革命が進行し、市民の権利がなによりも大事なものであるという価値観の変化が起きると共に、キリスト教会がそれまで特権的に市民の財産の十分の一を提供させていた権利にまで踏み込むことになります。カトリックの教会は誰のためにあるのか、という事になったとき、フランスの先鋭的な革命議会はこれをフランス王国、なかんずくフランス国民の下にあるものであろうと考え始めます.。 しかしそもそも、カトリック教会とはその総本山としてのローマ教皇庁の支配下にあるべきもの。フランス国王、フランス国家などに従属すべきものではない。 1790年12月26日、フランス王ルイ16世は宣誓強制法案に批准の署名をおこないます。これにより、フランスのすべての聖職者は、憲法に、実質的にはその一部となる予定の聖職者民事基本法に宣誓することを義務づけられます。すなわち、ローマ教皇庁ではなくフランス議会に従え、と。 今まで超国家的特権を享受していた一般的な聖職者にとって、これは受け容れられるものではない。 かくして、シスマ、すなわちカトリック教会の分裂という彼らにとって重大な危機が発生したのでした。この決着は、どうつくのか。 国内がこの宗教上の大事で混乱している中、時代に逆行する愚行が見つかります。 マダム・アデライード(このとき58歳)とマダム・ヴィクトワール(このとき57歳)という王女、内親王たちがいます。先の国王ルイ15世の娘たちで、今のルイ16世から見ると叔母たち。この二人が軽率にも荷物を山積みにした馬車でパリから抜け出し、自分たちの行動が何をもたらすか何も考えずローマに向かったのです。 これが、フランスの議会と人民を激怒させました。宗教問題で大荒れの中で、国家の模範となるべき王室のやんごとなき姫たちが、たしかに無分別でわがまま放題ではあったのでしょうが、なんてことをしでかしたのか。 かくして半ば盲目的に、大貴族は敵であるが国王は国家の父であり味方だと思っていたフランスの人民たちは、国王その人に対しても猜疑の目を向けることになったのでした。 国王や王室の人々には、国外へ逃走する権利などない、我らの中にいるべきである、という論も議会で叫ばれることに。 これはいかん、と立ちあがったのがミラボー。彼は病躯を押して議会に立ち、国王を擁護します。 最後は、国王にだって人権がありではないか、人間としての権利があるではないか、とまで言う。 これでは、 「進歩的」 を自負する議会の知識階層までも敵に回すことになる。なぜ、ミラボーはそこまで妥協しようというのか。 この革命を軟着陸させる方策としての手段の一つだったのかもしれない、と、サトケン節が描くこの本を読んで思う。ミラボーのこの考えが正しかったのか、人々を納得させられたのかは、彼にもう10年、いや、もう5年の時間があれば見えてきたかもしれません。 しかし歴史は容赦ない。 1791年4月2日、ミラボー伯爵逝く。病死。享年42歳。フランス革命以後、最初に国葬によって葬られました。 残るのは、だれか。
残ったのは、ロベスピエールとタレイラン。水と油。 かたや孤児育ちで優等生。現実を無視してでも理想を貫きたい男。公理しかない男。 かたや大貴族の御曹司ながら、足が不自由で日陰者。理想など道具にしか思わない、物欲しかない男。 彼らは、 |
||||||||||
 |
Ver. 3.02 |
|---|
| 管理番号:S076-026 | 32 歴史小説・西欧史 | 出版社:集英社 | |||||||
| 書名:王の逃亡 | 小説フランス革命7 | ISBN978-4-08-746803-8 C0193 | |||||||
| 仏語題:La fuite du Roi | |||||||||
| 集英社文庫 さ23-15 | 価格:495Yen | ページ数:272P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2012/3/25 | 購入:2015/10/4 | カバーデザイン:泉沢光雄 写真:アフロ | |||||||
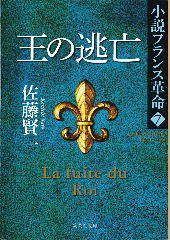 題名の通り、今回描かれるのはフランス革命の大きな曲がり角になったフランス国王一家の逃亡劇です。結果として国王一家は国境近くのヴァレンヌの町で正体が判明し、捕らえられ、パリに連れ戻されたのでした。これはヴァレンヌ事件として歴史に名を残します。 題名の通り、今回描かれるのはフランス革命の大きな曲がり角になったフランス国王一家の逃亡劇です。結果として国王一家は国境近くのヴァレンヌの町で正体が判明し、捕らえられ、パリに連れ戻されたのでした。これはヴァレンヌ事件として歴史に名を残します。この事件を、歴史史料に基づき、徹底的にルイ16世の視点で描いたのがこの本。ある意味、フランス革命という歴史の動乱の中で、ひとつの挿話と考えてもいい。 この物語の中でもそんな扱いです。
そうではなかったんじゃないか、とこの本で、佐藤賢一さんは新しい解釈を試みたようです。国王としての自覚と責任感を備えている様子を描写したのち、この騒乱がどう転ぶかわからぬままにイラつき、ミラボー亡き後どのようになすべきかを考える姿を見せます。 とはいえ、王権を第一に考えている様子のミラボーに頼り切っていた訳ではない。あくまで彼を推薦してきた王妃マリー・アントワネットの意に逆らわなかっただけ。実は内心、押しが強く自信満々なところが好きになれなかったのだという。
ああ、いかにもサトケン節。(笑) かくして陰謀は始まるのですが、ここで問題。使える駒があまりに少ない。その筆頭が、王妃の愛人という噂の絶えたことがないスウェーデンの貴公子フェルセン伯爵となると、ルイとしては不信感を抱かざるを得ない。妻との間柄もあるし、その能力についても。 その不安は的中します。 馬車を御すことを志願して馬を操るのですが、下手。石畳の凹凸が読めず震動が激しい。車幅感覚がなく内輪差がわからないので、曲がり角ではしょっちゅう建物にこする。それに、道に迷う。
なるほど、こういう解釈もありか。 この旅路の結果は、歴史に残っています。だからこのあとの成り行きについてコメントする必要はありません。 しかし、国王ルイの視点で、彼がこう考えていたんじゃないかと好意的に描写する王の逃亡劇、素敵。 一つ難があるとすれば、佐藤賢一さんは女性を描けない人じゃないか、ということ。マリー・アントワネットに限らず、この連作の中で女性はおもてだった活躍をすることはわずかであったことは歴史的事実であったことはたしかです。しかしサトケン節では、女性は後できゃんきゃんとヒステリックに騒ぐばかり。これもまた事実であったとしても、常にこれではあまりにステレオタイプすぎる。 解説として漫画家の池田理代子さんが面白いコメントを残しています。 ボンクラとされたルイ16世をこう描写したことについて、好意的ですね。こんな歴史解釈もいいな、という書き方に同感です。 ではなぜ、「ベルサイユのばら」という、あんなにも甘ったるい、歴史解釈がいい加減な少女漫画を今も誇るのかなぁ。 鐵太郎は、あの漫画が描く人間模様と歴史が好きではありません。異見には個人差があります、むろん。(2016/3/8) |
||||||||||||||
 |
Ver. 3.02 |
|---|
| 管理番号:S076-027 | 32 歴史小説・西欧史 | 出版社:集英社 | |||||||
| 書名:フイヤン派の野望 | 小説フランス革命8 | ISBN978-4-08-746816-8 C0193 | |||||||
| 仏語題:L'ambition des Feuillants | |||||||||
| 集英社文庫 さ23-16 | 価格:543Yen | ページ数:296P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2012/4/25 | 購入:2015/10/4 | カバーデザイン:泉沢光雄 写真:アフロ | |||||||
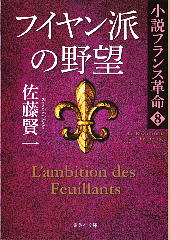 正体を悟られたことにより王一家の脱出行が国境近くのヴァレンヌで終わった翌日、1791年6月22日早朝から始まります。最初の計画とは違ったが、これぞ私の思うとおりである、と得意げなルイ16世の満足感から。 正体を悟られたことにより王一家の脱出行が国境近くのヴァレンヌで終わった翌日、1791年6月22日早朝から始まります。最初の計画とは違ったが、これぞ私の思うとおりである、と得意げなルイ16世の満足感から。元のハードカバー本ですと、「王の逃亡」 は前巻とこの文庫の30章のうち10章分ですので、ルイを主役とした物語はまだ続きます。 得意になっていた王が、国民の声、国外へ逃亡するのか、なぜ首都であるパリにいないのだ、王を逃がしてしまったらジャコバン・クラブに叱られる、といった声、そして国民衛兵隊の将校の登場に、だんだんと自分たちの状況がわかってくる様子が、サトケン節で描かれます。とはいえ、いきなり廃位される様子でもない。 そもそもこの時点で、フランスという国家から王国という形式を奪い、王をなくして新しい制度の国家を創設する、という考えを持った人はいなかったといっていい。王のいない共和国というものは、たとえば最近では、海の向こうにアメリカというもと植民地の国はあります。過去にもいくつもありました。 しかしそれは、国際的に勢力もない新興の国。フランスのような伝統ある国家が共和国になるなど、とんでもない。 どのような王政を存続させるのか、という議論は進んでいましたが、それだけのこと。 11章からは、デムーランの物語。 国王帰還をちょっと下卑た筆致で描写した新聞記事など、いかにもサトケン節らしいところ。しかしそれを書き上げたカミーユ・デムーランは、革命はもう終わりであろうかという感慨にふけりつつ、新婚生活を楽しんでいます。ミラボーが死んだ後、国王の立場はますます軽くなり、ブルジョア指導の下でパリの議会は国家の新しい法制度に奔走しているところ。 このまま国が治まるにしても、どのような着地点があるのかはまだわかりません。 このデムーランの提案で、国境近くで連れ戻された国王一家がパリに戻るにあたり、こんな布告が出されます。
裏切られたと思っている国民は王をさんざん罵倒するだろうが、王自身は身の安全を確信しているにちがいない。であれば、完全な沈黙で向かえるのが一番効果的ではないか。群衆がみな、だれも敬意を払って帽子を脱ぐことをせず、じっと黙って見送れば、王も考えるところがあるであろう。 テュイルリ宮に帰還したマリー・アントワネットが鏡を見て、自分の頭が真っ白になったことに気づいて悲鳴をあげたのはこのとき、といわれます。金髪と言うより白っぽい栗色の髪であったという彼女にとってそれほど不思議ではない状態だったそうですが、それはそれで歴史に名高い事件となったもの。 現時点でフランス革命の先頭を走っていると自他ともに認めるジャコバン・クラブの中で、ルイ16世の退位という発案がなされます。国王という制度自身をどうこう言う訳ではない。いまの、国民の信頼を失いつつある国王を、評判の悪いオーストリア出身の王妃ごと除いてしまおうという考え。これによって国民の不満のはけ口にしようという考えもあります。革命はもう終わらそうと言うブルジョアへの牽制という意味もある。 ここで、現在事実上ジャコバン・クラブを支配する三頭派、デュポール、ラメット、バルナーヴの三人の横槍が入ります。彼らは、王の逃亡を不埒者による誘拐事件である、というでっち上げで解決しようとしています。これによって王の地位を安定させようとする意図が透けて見える。ブルジョア階層がそのうさんくさい結果で満足するのなら、革命とは何だったのか。 いったい三頭派を中心とするグループはなにを考えているのか。 ジャコバン・クラブとは、そもそもが多種多様な考え方をもつ革命派の集合体のようなもの。デムーラン、ロベスピエール、マラ、ダントンらの考え方と合わない人々もいる。その方が多いかもしれない。 そんななかで、フイヤン僧院で集会を持つジャコバン・クラブの人々がいる、という報せが入ります。なにやら、三頭派を中心にして話し合われているらしい。その人々が、ジャコバン・クラブの先鋭的なメンバーを排除し、新しい政治勢力を作り始めます。 彼らは、ブルジョア、すなわち 少数派と化したジャコバン・クラブの面々は、どうやって対抗するのか。(2016/4/15) |
||||||||||
 |
Ver. 3.02 |
|---|
| 管理番号:S076-028 | 32 歴史小説・西欧史 | 出版社:集英社 | |||||||
| 書名:戦争の足音 | 小説フランス革命9 | ISBN978-4-08-746829-8 C0193 | |||||||
| 仏語題:L'approche de la guerre | |||||||||
| 集英社文庫 さ23-17 | 価格:552Yen | ページ数:304P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2012/5/25 | 購入:2015/10/5 | カバーデザイン:泉沢光雄 写真:アフロ | |||||||
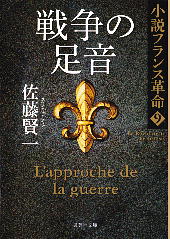 デュプレイ家に下宿するロベスピエールの憤懣から始まります。1791年8月27日。 デュプレイ家に下宿するロベスピエールの憤懣から始まります。1791年8月27日。7月17日に起きたいわゆるシャン・ドゥ・マルスの虐殺により、ブルジョア階層を基盤とするフイヤン派の勢力は、もう革命政権を支配するレベルになりつつあります。すべての国民の代弁者を自負するジャコバン派の地歩は、ますます狭くなるばかり。 なんとかしなくては、とあせるロベスピエール。 ちなみに、ジャコバン・クラブ会員であるモーリス・デュプレイの好意でその家に下宿させてもらっているのですが、清廉な政治家として記録に残るマクシミリヤン・ロベスピエールは、この家の長女エレオノール・デュプレイと内縁関係にあったのだそうな。 フランス革命は、のちの歴史で簡単に記されているように一直線に人民主権、国王排除、共和国形成に至ったのではない、とこの物語で語られます。まず革命がなされて貴族・僧侶階層が政権の中枢から排除されたあと、世の中を支配するのはブルジョア階層であるべきだ、という流れ。 政府を運営する者は、字もかけない数も数えられない無教養な愚民ではなく、財産と教養がある階層から選出されるべきだ、それこそが正しい民主主義であろう、と考える人びとがいるということ。それも正論なのかもしれない。 しかしロベスピエールは、本能的にそれを拒否します。すべてのフランス人がフランス国民として民主的に国家の一員となるべき、と。 そういうロベスピエールは、ペティオン議員と共に祖国の父と称えられ、貧民の守護者、民主主義の弁護人と人々に信頼されます。 のちに、恐怖政治を具現する存在となるロベスピエールには、このあと何があったのか。 内憂を抱える中で、実は外患もあるのでした。フランスという大国が革命という病魔に侵された、と考えた国外諸国は、軍隊をフランスの国境外縁に待機させています。人民が国家の主権を持つという恐るべき事態が、自分たちの国にも蔓延したらとんでもない。 フランスでこれと一戦すべし、と考えたのは、過激思想にとりつかれた革命最前線の人々ではなく、実は王室、貴族、ブルジョア階層であったという。 これを国外の力を借りて革命勢力を牽制しようと考えたルイ国王の考えだ、としたのは佐藤賢一さんの自論か。なぜ自論と思ったかというと、まるで外圧で国内問題を解決しようと考えた日本政府みたいな発想ではないか、ということ。これ、メジャーな論ではないような気がするから。ありえないとは言えないけれど。 この情勢の中で、国王と何やら結託しつつ人民の英雄として名をあげている政治家、アントワーヌ・バルナーヴの名を再びあげて、この巻は終わり。ここで佐藤賢一の描く小説フランス革命の前半が終わりです。 ちなみに、この本の148ページでロベスピエールは机に座り、乾いたペン先をインクに浸す場面が出てきます。ここに引っかかった。 この描写は、鉄の付けペンをインク瓶に浸す動作と考えていいですよね。ペン この時代の少し後、ナポレオン時代の帆船小説は多数読んでいますが、すべてインクを使う場合鵞ペンを使っていますよ。鉛筆も当時すでにあったのですが、これはインクを使うペンの話。ま、いいけどさ。(2016/5/13) |











