トップへ戻る 作家/分野 一覧 |
|
 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 書名 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 小説フランス革命 | 小説フランス革命 佐藤賢一の描くあの時代 | ||
| 佐藤賢一 ノンフィクション | 伝記、歴史解説書などのノンフィクション | ||
| S076-001・002 | 双頭の鷲(上・下) | 百年戦争で活躍した無頼漢、ベルトラン・デュ・ゲクラン | |
| S076-008 | カルチェ・ラタン | 16世紀、ルネサンス時代のパリの学生街 | |
| S076-011 | ジャンヌ・ダルクまたはロメ | 中世フランス・短編集 | |
| S076-012・013 | オクシタニア(上・下) | 中世フランス・13cに起こった宗教戦争の顛末 | |
| S076-014 S076-015 S076-018 |
黒い悪魔 褐色の文豪 象牙色の賢者 |
黒い悪魔、皆殺しの天使と呼ばれた男 フランスの文壇に名を残した劇作家の帝王 偉大な父の元で生きた文豪 |
|
| S076-030 | ハンニバル戦争 | ローマ史上最強の敵との戦いの顛末 | |
| S076-034 | 黒王妃 | 時代を切り開いた一人の女傑の物語 | |
| S076-035 | かの名はポンパドール | ルイ15世の友となった美貌の人 | |
 |
|---|
| 管理番号:S076-001・002 | 32 歴史小説・西欧史 |
新潮社 | ||
| 書名:双頭の鷲(上) | 仏題:L'aigle a deux tetes | 発行 1999年 | ||
| 新潮文庫 さ47-1 6692 | 価格:¥781 | ページ数:573P | 装丁:文庫 イラスト:高橋常政 |
|
| 初版発行:01/7/1 | 購入:01/7/8 | |||
| 書名:双頭の鷲(下) | 仏題:L'aigle a deux tetes | 発行 1999年 | |
| 新潮文庫 さ47-2 6693 | 価格:¥781 | ページ数:602P | 装丁:文庫 イラスト:高橋常政 |
| 初版発行:01/7/1 | 購入:01/7/8 | ||
  本の帯にに書かれたアオリ文句は、上巻が 本の帯にに書かれたアオリ文句は、上巻が「おれが戦争の天才だって? ─ああ、よく言われるよ」 下巻は 「乱世で生き残るコツ? ─実力だけだね、じつりょく」 見事なアオリですなぁ。(笑) 百年戦争と呼ばれる戦争は、イギリスとフランスの間で文字通り約百年に渡り、断続的に続きました。1337年に始まり、諸説はありますが1453年に終わったとされています。 むろん、戦闘の火種がなくなったのではない、単に飽きたからかもしれない。 1356年、イギリスは黒太子エドワードを擁して、ポアチエの戦いでフランス軍を撃破します。この戦いで、イギリスの優位が確定し、フランスはイギリス国王のものになるのか、と言う歴史の流れがあります。 むろん、イギリス王もフランス王も、特に違いはないのですけどね、当時は。 どっちが成っても、庶民にとっては別世界。儲けさせてくれる方が良い王様。
さて、イギリス軍の進軍に脅えるブルターニュの小都市ディナンに、ベルトラン・デュ・ゲクラン(1321-1380)という傭兵隊長がおりました。子供の頃は悪童でならし、大人になると軍人として稼ぐ、不良の模範となる立派な悪党です。(笑) 性格は、外観的には豪放無頼。内面はコンプレックスを抱える自閉症。しかし、戦えば天下無敵。佐藤さんのキャラですなぁ。 国王シャルル5世(1337-1380 賢明王 le Sage)に見いだされ、信頼され、無敵のコンビとなってフランスを復興させます。そして、「大元帥」すなわち国王以外の、王族を含むすべての国民に命令を出すことのできる地位にまで上り詰めます。 ジャンヌ・ダルクで名高い百年戦争の、日本人にはなじみの薄い、彼女が出てくる前の時代を切り取り、描き出した佐藤賢一節です。 母親との関係、幼少期のトラウマ、これまた佐藤節です。「醜いアヒルの子」という書評もあります。 その周りでも、僻みのあまり狂気に陥る弟、偉大な敵将、惨めに突き落とされる過去の男、面白いですなぁ。 個人的な好みから言うと、もう少しちがう人物であってほしいとおもう佐藤節の男たちですが、歴史絵巻として十分に楽しめました。 リデル・ハート氏が「戦略論」の中で、デュ・ゲクランの行動を「フェビアン戦略」の実践と言っています。またこの前後のエドワード二世やヘンリー五世の勝利も、トンマなフランス軍に助けられて勝ったに過ぎないと酷評しています。 なるほどねぇ。視点を変えるとロマンティックな歴史がボロクソにされますな。(笑)(05/3/1) なお、デュ・ゲクラン氏はコナン・ドイルの「白衣の騎士団」にゲスト出演していることが確認できました。(笑)(05/3/26) |
||||
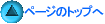 |
Ver. 2.19 |
|---|
| 管理番号:S076-008 | 32 歴史小説・西欧史 |
出版社:集英社 | |||||||
| 書名:カルチェ・ラタン | ISBN978-4-08-774458-2 C0093 | ||||||||
| 仏題:Quartier Latin | 価格:1900Yen | ページ数:438P | 本のサイズ:140×190HC | ||||||
| 初版発行:2000.5.10 | 購入:2006.1.29 | 表紙イラスト:塩田雅紀 | |||||||
 前にちょっと読んで放置していたのですが、読み直したら面白くて一気に読み切ってしまいました。 前にちょっと読んで放置していたのですが、読み直したら面白くて一気に読み切ってしまいました。カルチェ・ラタンとは、パリの一郭の地名です。このカルチエは地区を現し、ラタンとはラテン語のことです。つまり、「ラテン語を話せるような学識のある人々集まる地区」という意味で、中世、ルネサンスの学生が集まる街でした。そこから、「学生街」を意味するようになったとか。 この物語が始まった1536年、すでにそう呼ばれていたとそうな。 語り手は、パリの大手船会社クルパン家の次男坊、ドニ・クルパン。 あとがきに従うならば、パリの名物男として名を残した多彩な人物だそうです。1514年3月12日生まれ、1582年11月18日死亡だそうな。 今は、学生となったものの学位も取れず、女性の理想が高すぎていまだに奥手の自信のない男。部下になめられながらパリの夜警隊長という職を果たす22才の青年です。 時代は、フランスで最も愛された王の一人、フランソワ1世の治世。対外的には神聖ローマ皇帝に立候補したフランソワがハプスブルク家のカールに敗れたのち、スペインとオーストリアという二つのハプスブルク家に挟まれたフランスは、ドイツのプロテスタント諸侯と手を結んだり、オスマン帝国のスレイマン大帝の秘密条約を結ぶなど、さまざまな動乱の気配があり、カルチェ・ラタンもその余波は容赦なく襲ってきます。 彼の回想記という形で描かれるこの本では、実は彼ではなくマギステル・ミシェルという学僧が主人公となっています。ドゥ・ラ・フルト伯爵家の出身でありながら、実家に頼る様子はない。学校に学ぶ修道僧という立場にありながら、女はよりどりみどり、剣の腕も立つ快男児。 クルパンとこのミシェルが、パリの夜の街で起きる事件を解決していきつつ、自信のなかったクルパンが成長してい様子が描かれます。そこに神や、宗教や、時代の精神などが絡まって、ある種の精神文化まで得られますね。ジャン・カルヴァン、イニゴ・デ・ロヨラ、フランシスコ・ザビエルなどの、のちのイエズス会の重鎮たちが人間味たっぷりに出てきたりしますと、嬉しくなってしまうじゃありませんか。 クルパンの自己憐憫的、自虐的、マザコン的なところは、むろん佐藤賢一節です。いつもの通り。 そのせいかどうかわかりませんが、お話自体はちょっとばらけたところもあるような。 でもって、女性の描き方と来たら... 佐藤さんはこの方面は合格点がつけられませんねぇ。ま、それも賢一節か。 気がつかなかったのですが、ネット上に転がっているいろいろな書評によると、「薔薇の名前」を意識したような雰囲気があるそうです。 どうなんでしょう。 もうひとつ、気がついたところ。クルパン家は裕福な船会社です。大西洋から何百キロも離れたパリで、船会社が営まれる。つまり、セーヌ川の海運とは、この時代にこれほど大きなものだったと考えるべきなのでしょうか。ちょっと調べてみたくなりました。(08/3/14) |
 |
Ver. 2.7 |
|---|
| 管理番号:S076-011 | 32 歴史小説・西欧史 |
出版社: ISBN4-06-275318-9 | |||||||
| 書名:ジャンヌ・ダルクまたはロメ | 第一作品集 | 発行:2004年2月 HC | |||||||
| 講談社文庫 さ81-4 | 価格:571Yen | ページ数:325P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:06/2/15 | 購入:06/2/18 | 表紙イラスト:竹元良太 | |||||||
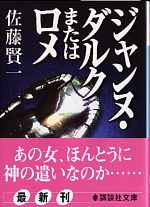 題名となった「ジャンヌ」を含め、7作の歴史点描で構成された短編集です。 題名となった「ジャンヌ」を含め、7作の歴史点描で構成された短編集です。時代は中世。1400年代の百年戦争後半。 ジャンヌ・ダルクまたはロメ ジャンヌ・ダルクの正体に怯えるジョルジュ・ドゥ・ラ・トレムイユが語り手です。 なぜ怯えるか。彼がシャルル7世の宰相であり、国王の寵が傾けばその場で地位を奪われる立場だから。 田舎の農夫の娘というふれこみのジャンヌという娘、父はジャック・ダルク、母はイザベル・ロメ。母方の姓を名乗る習慣もあって、ジャンヌ・ダルクまたはロメと名乗るという。 なぜ、たちまちのうちに国王の信頼を勝ち得たのか。なぜ平然と騎乗して武器を取れたのか。 トレムイユの立場を脅かす存在ではないのか。疑心暗鬼に駆られる宰相の探索。その驚くべき結論。 冷水を浴びせられる国王の言葉。 人はここまで冷酷になれるものか。 戦争契約書 傭兵としてフランスに渡った郷士の二人が交わした契約書。たがいを戦争義兄弟と呼び、万が一の時の財産分与を定めたもの。 実際に存在した古文書を元に、佐藤賢一が描く人間模様。佐藤さんって、下卑た人間関係が好きですなぁ。 ルーアン 1431年年頭、ある異端者をルーアンで審問すべくパリから旅立った若き学僧の視点です。 異端者とは、「ラ・ピュセル」という女。いまだフランス国王とは認められていないシャルルに信頼され、その代理人としてイギリスを責めたフランス女。ジャンヌ・ダルクとも名乗る。彼女の末路を見守る羽目になったジャック・ドゥ・ラ・フォンテーヌの心の葛藤と苦悩。 ここで肉欲の罪をかみしめる学僧。佐藤さんってこういう方向に考えるのが好きですね。 エッセ・エス カスティーリャ王国の忠臣たる無骨な騎士、グティエレス・デ・カルデナス。25歳の若武者。1469年。 国王エンリケ4世の妹イザベルの婚礼の相手は、アラゴンの王太子フェルナンドとなるのか。フェルナンドとは何者? 堅苦しい伝統を誇るカスティーリャと、自由闊達な商人の国アラゴン。はたしてその行く末は。 スペイン王国の前史を、佐藤節はこう語ります。「エッセ・エス、エッセ・エス!(あの方です、あの方です!)」 ヴェロッキオ親方 アンドレア・デル・ヴェロッキオはフィレンツェの職人です。絵を描き、彫刻し、建築をする、のちには芸術家と呼ばれるべき仕事をしています。 たくさんの弟子を使っていましたが、ひとり困った弟子がおりました。 他の弟子と同じ絵が描けない。暇さえあれば実験を繰り返し、工夫をするが、癖が強すぎる。 親方の指示を聞かないわけではないが、どうも浮いている。老人は困惑し、怒りに駆られます。 しかしその絵を再び見直したとき、愕然とします。そこに神の手を見たのです。 技師 1501年、フランス・ルイ12世の強大な軍隊がナポリに来ます。その道順にある、小さい町、ロカ。 この町に帰ってきたアントニオは、町を守る要塞を作る提案を町の参事会に提出します。 新しい要塞技術をもった俺に任せてくれれば、フランス軍の大砲に負けない防壁を作って町を守ってみせる。 さて、その意外な結幕はいかに。 ヴォラーレ 人は空を飛べるのか。夢を追うレオナルド・ダ・ヴィンチは、空を飛ぶ実験に熱中しています。 しかし、彼の心情を理解しない愚かな者ども。 嬉嬉として実験に打ち込む志願者の妻。完成しない絵の締め切りを示して契約の履行を迫る者たち。 芸術家とは、忙しいのだ。レオナルドは夢を追います。 こんな人間に媚びを売らなければならない下々の人間は、踏みつぶされてしかるべきなのか。やれやれですね。 この本の解説に関しては、面白い視点だと思いますが、ちょっと納得しにくい。これが正しい読み方なのでしょうか? よく分かりません。(06/5/2) |
 |
Ver. 2.14 |
|---|
| 管理番号:S076-012 | 32 歴史小説・西欧史 |
出版社:集英社 | |||||||
| 書名:オクシタニア(上) | ISBN4-08-746065-7 | ||||||||
| 欧題:Occitania(2003.7 集英社HC) | 価格:743円 | ページ数:467P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2006/8/25 | 購入:2006/8/26 | 表紙イラスト:八木美穂子 | |||||||
| 書名:オクシタニア(下) | ISBN4-08-746066-5 | ||||||||
| 欧題:Occitania(2003.7 集英社HC) | 価格:714円 | ページ数:442P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2006/8/25 | 購入:2006/8/26 | 表紙イラスト:八木美穂子 | |||||||
  オクシタニア。 オクシタニア。まるでおとぎ話に出てくる王国のような名前です。ファンタジーの世界なのでしょうか。 いや、作者は佐藤賢一。そんなはずはない。(笑) プロローグは1283年10月、フランス南部ピレネー山脈のにあるモンセギュールと呼ばれる城塞へあえぎながら登る修道士たちから始まります。頭立つのはエドモンと呼ばれる修道士。年齢は80になるのか90を越えるのか、自分でもわからないほどの高齢で、ドミニコ修道士会のトゥールーズの管区長の地位にある老人。 彼の過去の回想で物語は始まります。 宗教戦争というものがあります。かつてヨーロッパ中世に現れた陰惨な歴史です。 正しい宗教が悪い宗教を駆逐した、それが歴史です。むろん、勝った側の描いた歴史です。 その戦いが、キリスト教がキリスト教以外の宗教と戦ったことより、キリスト教の「正統派」が「異端」を相手にしたことの方が遙かに陰惨だったことは、歴史の語るところです。 その異端相手の戦争の一つに、「アルビジョワ十字軍」があります。13世紀の初頭に起きた、アルビジョワ派あるいはカタリ派とよばれる「異端」と「正統な」カトリックの戦いです。むろん、カトリックの勝利に終わりました。 この戦いには、実は政治的あるいは軍事的な背景もあります。当時フランスとは、国王を宗主とした諸侯のゆるやかな連合体のようなものでした。その中でフランス国王というものは、諸侯としての肩書きはどちらかというと小さなパリ伯にすぎず、北部フランスではそれなりの力を持っていますが、南部では名ばかりの宗主権しかありませんでした。 「はい」という言葉を「オイル」と発音するところから「オイル語圏(ラングドイル)」と呼ばれるのが北部。それに対しセヴァンヌ連山の南にある南部のオクシタニア地方では、「はい」を「オック」と発音するため、「オック語圏(ラングドック)」と呼ばれ、民族的にも精神的にも全くの異邦人でした。同じ言葉が、オイル語で「トゥールーズ」と呼ぶ都市をオック語では「トロサ」と呼ばれたりします。 歴史を遡ると、アリエノール・ダキテーヌ(1124~1204)がフランスの南6割を締めるアキテーヌ侯として君臨していたのは、この時代のほんのわずか前。フランス国内では、南と北は全く別な国家という意識を、少なくとも南部の人々は持っていた時代です。 このオック語を、佐藤賢一は関西弁で書く試みをします。 生真面目で堅く黒白をはっきりさせたいオックの人々。いいかげんで曖昧で自由を楽しむオイルの人々。 ある意味ステレオタイプですが、こういう描き方も面白いかも知れない。 物語は、三人の男を中心に描かれます。順番に登場して歴史を彩ります。 一人目は、フランス北部の小領主、シモン・ド・モンフォール。歴史の中で有名な、1208生まれで1265年に死んだ、英国ジョン王の娘を妻とした同名の貴族ではありません。その父親です。彼は、政治的な一種の捨て駒として、トゥールーズに猖獗する異端のカタリ派への十字軍の総大将に任じられます。あるいは、正確に言うとその任を押しつけられます。 なりはでかいが、自分に自信の持てない優柔不断である彼は、いかにも佐藤賢一ふうのキャラクターですね。妻へもコンプレックスを持っている彼が、戦うとこれが強い。連戦連勝でたちまち異端を追い詰めます。 二人目は、エドモン・タヴィヌスという青年。トロサの町の商家の名士の息子です。 なんということもなく民兵隊を率いる羽目になり、宗教にはあまり関心がなかったのにいつの間にかカタリ派の領袖にも期待され、ついにシモン・ド・モンフォールその人を戦死させる戦功を立てます。しかし、妻であったジラルダがカタリ派に傾倒するにつれ、その教えの根本的な無意味さに気づき、ついに当時カトリックの修道士ドミニコが起こした宗派に帰順します。 三人目はトゥールーズ伯レイモン7世(1197~1249)。オック語で言うと、トロサ伯ラモン。 宗教的にはかなりいい加減ですが、この異端の宗派の暴発を利用してアルビジョワ、トロサの盟主として北部に対する完全な独立を試みます。若い頃は美貌の貴公子として自他共に認めるいい男でしたが、中年になると単なるデブのおっさんになりさがります。 異端として法王に破門され、恭順の姿勢を示すための屈辱にも耐えますが、結局は叛乱に巻き込まれます。 そしてこの三人に、カタリ派に傾倒して完徳女となったジラルダ・ペトリコラという女がからみます。 佐藤賢一の描く女とは、ロクなもんじゃないの悪女ばかりなのですが(笑)、彼女はどうでしょうか。やりきれないところもありますが、こういう描き方で物語を進めようとしたのだとすると、こういう試みもあり、と思えばいいのでしょうかね。彼女も、宗教の狂熱だけで人を律することはできないことに気づくことがあるのか。 わかったふうなことを言い、コンプレックスに悩み、自信過剰に突き進んで足下を崩される展開の連続です。これに慣れないと、佐藤賢一は読めません。(おいおい)(07/1/7) |
 |
Ver. 2.17 |
|---|
| 管理番号:S076-014 | 32 歴史小説・西欧史 |
出版社:文藝春秋 | |||||||
| 書名:黒い悪魔 | 初出:オール読物 2002.1~12 | ISBN978-4-16-322050-X C0093 | |||||||
| 価格:2000Yen | ページ数:461P | 本のサイズ:140×192HC | |||||||
| 初版発行:2003/8/10 | 購入:2007/5/31 | 装丁:坂川栄治+藤田知子 | |||||||
 主人公は、アレクサンドル・デュマ。ただし、あの小説家ではありません。 主人公は、アレクサンドル・デュマ。ただし、あの小説家ではありません。トマ・アレクサンドル・ドゥ・ダヴィ・ドゥ・ラ・パイユトリ、と小説の中では言われた人物。 1762/3/25生まれ、1806/2/26死亡。フランスの軍人です。 フランス版Wikiで、「Thomas Alexandre Davy de la Pailleterie, dit le général Dumas」とありますので、名前について多少の違いは気にしないことに。(笑) 日本版Wikiのトマ=アレクサンドル・デュマを見てみると、驚きますよ。この本に書かれているアレクサンドル・デュマ将軍の生涯が、ほぼそのまま書かれているから。 なんだよ、これ。(笑) このWiki書いた人は「黒い悪魔」を読んだんじゃないだろうか?(笑)  トマ・アレクサンドルは、フランス植民地サン・ドマングで生まれました。カリブ海のイスパニョーラ島の西部地方で、スペイン語のサント・ドミンゴの方が通りがいいでしょうか? トマ・アレクサンドルは、フランス植民地サン・ドマングで生まれました。カリブ海のイスパニョーラ島の西部地方で、スペイン語のサント・ドミンゴの方が通りがいいでしょうか?父親は貧乏貴族、アレクサンドル・アントワーヌ・ダヴィ、ラ・パイユトリ侯爵(marquis Alexandre Antoine Davy de la Pailleterie)ですが、母親はマリー、奴隷です。 トマ・アレクサンドルは、白人と黒人との混血児、ムラートなのでした。 この混血児が運命のいたずらでフランスの軍人となり、ロベスピエールに心酔し、ナポレオンと出会い、決別し、戦いに明け暮れた生涯を失意のうちに終えます。黒い悪魔、皆殺しの天使と呼ばれた豪快な戦士の物語はそこまで。 その中で語られる話の中には、のちに「三銃士」あるいはその続編、また「モンテ・クリスト伯」など、文豪アレクサンドル・デュマで描かれる痛快な冒険がたくさん出てきます。 兵舎に入るなり三人の先輩・上官に決闘を申込み、ことごとく叩きのめす。処刑台に昇るロベスピエールを救出せんとトンネルを掘るが、最後の瞬間に間に合わず、その血を浴びる。橋の上で立ちはだかり、押し寄せる敵軍を一手に引き受けて味方の脱出を助ける。古城に幽閉され、瀕死の中でついに牢を出る。 本当なのでしょうか? 佐藤賢一氏は彼を、強い肉体と優れた頭脳を持ちながら、その性格が災いしてついに人の上に立てず、鬱々と怨念を抱えたまま生きた男として描きました。いつもの佐藤節ですねぇ。最後に生きる目的として彼が持ったものは、他人から見れば惨めな自己満足かも知れない。しかし妻と息子、文豪アレクサンドル・デュマにとって、最後の希望となりました。それもまた、佐藤節か。 面白いのですが、いくつか突っ込みどころ。(笑) デュマ将軍の副官が持つ双眼鏡。(当時は単眼鏡しかありません) デュマ将軍が牢の中で囓る黒いチョコレート。(固形のチョコレートは1847年にイギリスではじめて商品化されたそうです) ※ とあるサイトで固形のチョコレートの方が液体より先との情報あり。うーむ、知識不足かな。 デュマ将軍は乗る「戦艦」の丸窓から外を見ます。(戦艦──戦列艦の言葉はともかく、当時の木造戦闘艦には丸窓はありませんし、艦尾の司令官を含む高級士官の居室以外ではそもそも窓はありません。普通の乗組員は砲門があいたときか甲板に上がったときしか外は見ることができません。まして囚人では) その他、いろいろ。 こんな事を気にしちゃいけないんでしょうねぇ?(笑)(07/8/6) |
 |
Ver. 2.17 |
|---|
| 管理番号:S076-015 | 32 歴史小説・西欧史 |
出版社:文藝春秋 | |||||||
| 書名:褐色の文豪 | 初出:別冊文藝春秋 2003.7-05.3 | ISBN978-4-16-324610-X C0093 | |||||||
| 価格:2000Yen | ページ数:519P | 本のサイズ:140×192HC | |||||||
| 初版発行:2006/1/30 | 購入:2007/5/31 | 装丁:坂川栄治+田中久子 | |||||||
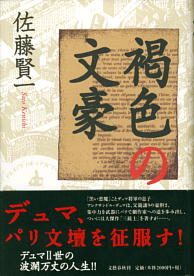 この本に描かれるアレクサンドル・デュマとは、「黒い悪魔」の息子として生まれた劇作家、アレクサンドル・デュマ(Alexandre Dumas 1802.7.24-1870/12/5)です。同名の息子も小説家として名を上げたことから、大デュマ、父デュマ(Dumas,
père)と呼ばれます。 この本に描かれるアレクサンドル・デュマとは、「黒い悪魔」の息子として生まれた劇作家、アレクサンドル・デュマ(Alexandre Dumas 1802.7.24-1870/12/5)です。同名の息子も小説家として名を上げたことから、大デュマ、父デュマ(Dumas,
père)と呼ばれます。偉大な父親を持った息子の苦闘、という描き方で佐藤さんはこの文豪を描こうとしました。 なにができるかわからない中で、もやもやと苦闘する少年の頃。 何をすれば親を越えられるか模索し、あれもこれもと思うまま正義を貫こうとする若い日々。 文筆業で頂点を極め、足下も見ずに駆けめぐる時代。 崩れる砂上の楼閣で豪快に笑いながら沈んでいく壮年時代。 大きな父親というものが、自分自身で作った虚像であったとしても、それを越えるために一生を捧げた巨大な人物、という描き方です。これを得意のサトケン節で書いていきます。 常に自分自身に対してしか主張できない根拠のない自信を抱きつつ、現実との乖離をコンプレックスのレベルでうじうじと悩む。主人公だけではなく、登場人物がみな同じように。 これがサトケン節のパターン。 この物語の最初の主人公のアレックス、つまり若きアレクサンドル・デュマの性格付けもそれに従っていますね。1/4の混血と異様に大きな体をもてあまし、自分の才能で、と言うより才能の欠如で、いったいなにができるのかを模索していた時代です。  しかし、そのあとの時代は勝手が違うようです。 しかし、そのあとの時代は勝手が違うようです。なにしろ、文豪アレクサンドル・デュマの人間としてのスケールは、ちまちまとコンプレックスに耽溺するような描写ではとても描ききれません。 彼が革命に参加したことがあったのは、知っている人はいるでしょうか。若い頃は、ナポレオン没落後のブルボン王朝を打倒する戦いに参加し、老いた日々にはイタリア統一戦争に貢献したジュセッペ・ガリバルディを援助しています。 この本に描かれたような介入のしかただったのかどうかは、わかりません。エネルギッシュという言葉だけでは説明できない、恐るべき行動力です。 その行動力は、女に対しても発揮されています。のちに別なかたちの文豪と呼ばれたアレクサンドル・デュマ・フィス、つまり彼の息子は、マリー・カテリーヌという女性との間の私生児です。彼を筆頭として、デュマにはたくさんの愛人とたくさんの私生児がいます。老いてなお愛人を囲ったと言うそのパワーは、恐るべきものと言うべきか。 むろん、恐るべきというのであれば、彼の文筆業を言うべきでしょう。 持って生まれた才能もありますが、若い頃に書記として身についた丁寧な文字で、機関銃のような勢いで書き上げる能力は、人間離れした恐るべきものだったそうな。 歴史や文学、戯曲などを学んだ若い作家に下書きを書かせ、最後に清書しながらデュマ自身の躍り上がるような文章に変えていく手法は、妬んだマイナー作家によって 『アレクサンドル・デュマ小説工場』 という告発本で不当に貶められる基礎にはなっています。 登場人物自身にその手法を語らせ、なお文学として読み物としての完成度を、天才の筆になる高みに追い上げたデュマのその腕を褒め称えれば、もはや何も言うことはなし。「三銃士」やその続編、「モンテ・クリスト伯」などに見られる父デュマ将軍の姿などは、ある意味付け足しか。 佐藤節は健在ですが、佐藤節で一刀両断できるほど、文豪アレクサンドル・デュマはヤワな人物ではなかったようです。佐藤さんのいつもの切れ味が鈍い。(笑) (07/8/14) |
 |
Ver. 2.23 |
|---|
| 管理番号:S076-018 | 32 歴史小説・西欧史 |
出版社:文藝春秋 | |||||||
| 書名:象牙色の賢者 | ISBN978-4-16-328920-5 C0093 | ||||||||
| 価格:1619Yen | ページ数:333P | 本のサイズ:135×195HC | |||||||
| 初版発行:2010/2/10 | 購入:2010/3/1 | 装丁:坂川栄治+田中久子 | |||||||
 |
Ver. 3.05 |
|---|
| 管理番号:S076-030 | 32 歴史小説・西欧史 |
出版社:中央公論新社 | |||||||
| 書名:ハンニバル戦争 | ISBN978-4-12-206678-6 C1193 | ||||||||
| 原題:HANNIBAL Secundum Bellum Punicum | 2016年1月 中央公論新社よりHC | ||||||||
| さ49-3 | 価格:920Yen | ページ数:528P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2019/ | 購入:2019/2/10 | カバーイラスト:永井秀樹 カバーデザイン:片岡忠彦 |
|||||||
 ハンニバルとは、むろんハンニバル・バルカ。BC247年に生まれ、BC183頃に死んだカルタゴの将軍。ローマは地中海の覇権をめぐって三度、巨大な通商国家カルタゴと戦いましたが、その二番目の戦い、第二次ポエニ戦争を開始し、実質的にこの戦争を支配したのがこの人。 ハンニバルとは、むろんハンニバル・バルカ。BC247年に生まれ、BC183頃に死んだカルタゴの将軍。ローマは地中海の覇権をめぐって三度、巨大な通商国家カルタゴと戦いましたが、その二番目の戦い、第二次ポエニ戦争を開始し、実質的にこの戦争を支配したのがこの人。 そのため、この戦いをハンニバル戦争と呼ぶこともあるのです。 そのため、この戦いをハンニバル戦争と呼ぶこともあるのです。カルタゴの名将ハミルカル・バルカの長子。ハミルカルが作り上げたイベリア(現代のイベリア半島)植民地を継承し、そこから長駆イタリア半島までアルプスを越えて遠征し、ローマ軍を何度も撃破しました。現代に至るまでその戦術が研究されている、古代切っての名将といわれます。 この本のオビに、「史上最凶の敵から祖国を守れ!」という言葉がありますが、ハンニバルを評する言葉は、は古代最強の名将で十分ですよ。つまらん煽り文句では、彼を汚すことになると思うのです。 ──閑話休題(笑)。 プロローグ と、第一部 カンナエと、第二部 ザマと、エピローグで構成されます。一人称で語られるのですが、語り手は実はハンニバルではない。徹頭徹尾、歴史の中でハンニバルとともに語られる男、プブリウス・コ  ルネリウス・スキピオ(BC236-BC183頃)の口で、この物語は語られます。 ルネリウス・スキピオ(BC236-BC183頃)の口で、この物語は語られます。ローマという国は、同姓同名がやたらと多い。このスキピオ君もその例に漏れず、それなりに高名な父親と全く同じ名前です。しかし彼は、強敵ハンニバルと戦い、最後の最後ですが、彼をアフリカの平原で堂々と決戦して勝利を得たことで名を残します。 そう、ローマ市民は彼を、スキピオ・アフリカヌスと呼んで讃えたのでした。まぁあだ名のようなもの。右は、そう呼ばれた壮年時代の姿。 この物語では、彼はアフリカヌスとは呼ばれず、ただスキピオとのみ呼ばれます。 プロローグに登場したのは、17歳の放蕩息子。ローマの六大名家のコルネリウス家の分家のひとつスキピオ家の次男であるプブリウス。父親が今年の執政官であるにもかかわらず、人妻との逢瀬に明け暮れる不良息子で、父親に叱りとばされています。 時に紀元前219年、ハンニバル・バルカが、イベリアに新カルタゴと名づけた植民都市を拠点にしてローマの同盟都市に攻めかかってから一年後のこと。ローマの執政官とは軍事的な指揮官でもあるため、父スキピオは一族をたばね、軍団の先頭に立たねばならない。 こいつぁ大変な事になった、と頭を抱える不良青年。 ちなみに新カルタゴとはラテン語でCarthago Nova。のちにカルタヘナという名となり、現代でも地中海沿岸に存在します。 第一部 カンナエ とは紀元前216年8月にイタリア半島のカンナエで行われた、ローマ軍とハンニバル軍の戦い。この戦い、第二次ポエニ戦争が始まって3年後に起きたもの。これに至るまで、数度の戦いでハンニバルに嘲弄され、連敗を続けていたローマ軍団が決戦を挑みます。ローマ軍約8万に対しカルタゴ軍約5万。 この戦いの経緯は、のちに二千年以上にわたり軍事史に残るもの。兵力が劣るカルタゴ軍は、歩兵戦において絶対の自信を持っていたローマ軍を包囲し、死傷者6万、捕虜1万という壊滅的な敗北を与えたのでした。 この章は、知識を鼻にかけた自惚れ気味の青年スキピオが、戦争と政治の矢面で現実を見せつけられ、苦悩し、抗う姿を描きます。そしてこの歴史の流れの中で何を見たのか。貴族の息子と言うことで百人隊長に任じられ、従僕のガイウス・ラエリウスに叱咤激励されて戦場を駆けまわり、敗戦を目の当たりにします。 カンナエの壊滅に至るまで、彼が見たものはなんだったのか。 しかし空前の大敗北の中で、敗残兵と共にローマの門をくぐったスキピオが見たものは、民衆、高官たち、そして。自分の方針を否定されて逼塞していた元老議員クィントス・ファビウス。
まァ若いスキピオくんは、外面は必死で前向きにふるまいますが、心はまだまだ落ちこんだまま。 なにしろ、ハンニバルにはまったく歯が立たないのだから。 第二部 ザマ とは紀元前202年10月に北アフリカ、現代のチュニジアのザマで行われた会戦のこと。ローマは3万4千の歩兵と8千の騎兵、カルタゴは5万の歩兵と3千の騎兵、そして80頭の戦像で対峙します。結果は、カルタゴ軍が2万の死傷者と1万5千の捕虜を出して決定的な敗北を喫し、第二次ポエニ戦争の終結に至ったのでした。 この戦いも、後世の研究の対象とされてます。かのパットン、ロンメルらも熱心にこれを研究したのだとか。 カンナエから5年後から、始まります。ハンニバルの絶対的優位のなかで、ローマはじっと耐えています。同盟都市国家が次々と離反しても、負けを認めない。南イタリアに王国を築くハンニバルに屈することはない。 24歳となったスキピオは、心のなかで凍りつくような不安を抱えつつ、数々の敗戦のなかでローマを支えた若い勇将として、明るい好漢の顔を崩さず人に対峙します。 彼を支えるのは、自分がやらねばという意志、そして探究心。古今の兵法書、歴史書を読みふけり、何が起きていたのか、今後どうすべきなのかを必死で研究します。天才ハンニバルに対し、徹底した後退戦法、負けないで相手の戦力ををそぎ落とすクィントゥス・ファビウス・マクシムス(「ローマの盾」と称される)の戦略、ハンニバルのいない戦場でカルタゴ軍をたたいて追いつめるマルクス・クラウディウス・マルケッルス(「ローマの剣」と呼ばれた)の戦略、それだけでは負けないかもしれないが勝てないのではないか。 では、なにを手本とすればいいのか。
こうして、若きスキピオが世に出ます。この章は、もがき、学び、少しずつ自信をつけて成長していく若者の物語。 イベリアで戦い、イタリアで戦い、北アフリカで戦った彼の戦略とはどういうものだったのか。 ザマの戦いの前、一度だけ顔をあわせた12歳年上のハンニバルとの会話は、どのようなものだったのか。 都市としてのローマに一指も触れずにイタリア半島を蹂躙したハンニバルの目的とは、いったいなんだったのか。 ザマの戦いで、天才が最後に命じた突撃とは、どういう意図だったのか。 なるほど、こういう解釈もありか。 エピローグ は、ザマの戦いから19年後。ハンニバルの訃報を聞いたスキピオの述懐というべきか。 第二次ポエニ戦争の終結後、敗戦し莫大な賠償金に呻吟する故国カルタゴのために奮闘し、しかし故国に追放されて小アジアの小国で死んだハンニバル。その死は、彼の存在を恐れるローマからの圧力による自殺だったという。 スキピオ自らも、一時は英雄と讃えられながら失脚に追いこまれ、一人リテルヌムの別荘で最後の時を迎えます。 歴史とは重いもの。 読後に思う。夢破れた老人になったスキピオとハンニバルが再び語り合う場面が、後世の伝説にあります。おそらく、空想。でも、そんな歴史があれば面白かったのに。 サトケン節は、そこは描いてくれません。残念。(2019/5/3) 読書メーターの記録より 読了:2019/3/31 |
|||||||||||
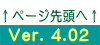 |
|---|
| 管理番号:S076-034 | 51 伝記・一代記・評伝 |
出版社:集英社 | |||||||
| 書名:黒王妃 | ISBN978-4-08-744110-9 C0193 | ||||||||
| 初出「小説現代」2011年9月号~2012年8月号 2012年12月・講談社より刊行 仏題:La Reine Noire | |||||||||
| 集英社文庫 さ23-27 | 価格:940Yen | ページ数:528P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2020/525 | 購入:2024/8/7 | 本文デザイン:アルビレオ | |||||||
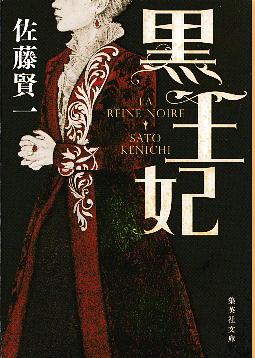 黒王妃とは、中世フランスで王妃、王の母后となったカトリーヌ・ド・メディシスのこと。夫であったフランス国王アンリ2世の死後、人前では生涯喪服として黒の衣装しか身につけなかったため、そう呼ばれたそうな。 黒王妃とは、中世フランスで王妃、王の母后となったカトリーヌ・ド・メディシスのこと。夫であったフランス国王アンリ2世の死後、人前では生涯喪服として黒の衣装しか身につけなかったため、そう呼ばれたそうな。そしてアクの強いサトケン節がちょっと薄れたこの人の物語が読めたのが、嬉しい。
メディチ家(Medici)ってのは、英語の薬(medicine)と同じ語源から来た言葉で「医師」出身を表す、と聞いたことがあります。金融業から身を起こしたという説もあります。いずれにしても、武で身を立て王侯貴族になった階層と違い、数代前にようやく爵位を得た程度の富裕な成り上がりなのです。 ありあまる財産をバックに輿入れ、ってのは平民あがりの新興貴族というだけで腰が引けるものですが、それに輪をかけて困った事がありました。彼女が生まれたすぐあとに両親が亡くなって孤児になったのはともかく、後見をしている叔父ジューリオ・デ・メディチ、教皇クレメンス7世の仲介で1533年にフランス王家の第2王子アンリ(1519-1559)と結婚したのですが、その翌年この教皇が亡くなってしまったのです。それによりフランスとローマの同盟も破棄されたため、彼女の存在価値はガタ落ちとなりました。 アンリ王子が兄フランソワの死後王太子と立てられ、父王の没後にアンリ2世として即位すると、彼女は王妃となります。しかし政治的バックを失った彼女は、大きな顔が出来ない。 加えて国王アンリには、20歳年上のディアーヌ・ド・ポワチエ(1499-1566)という愛人がいました。親にないがしろにされたアンリにとって母代わりの大事な人でしたが、そのために王妃が露骨に邪魔者扱いされるとは本末転倒な理不尽さ。 というのも、嫡男そしてそのスペアとなる男子を産めなければ、それもまた離婚の理由になるから。 海の向こうのイングランドで、ヘンリー8世(1491-1547)は嫡男を産まない王妃を何人処分したかを考えれば、人ごとではない。 その中で王妃としての務めを果たし、子を産むために当時考えられていたさまざまな医術、呪術、信仰を駆使して、10人の子女を産んだのは見事と言わねばならない。しかもそのうちの7人までもが成人したのですから。 こうしてこの本では、のちに一部では悪魔の化身ではないかと恐れられたこの母后「黒王妃」の生涯を、1560年つまり夫であるアンリ2世が事故死した翌年の、不穏な空気につつまれた年から物語が始まります。 このとき、王位に即いているのは長男であるフランソワ2世(1544-1560)。この前年にマリー・ステュアールと結婚していますし、その下にさらに3人も弟王子がいるので、フランス王家は盤石。 夫のアンリ2世の死後、カトリーヌを陰に陽にいじめ抜いた愛妾ディアーヌも舞台から去って、もはや母后カトリーヌを掣肘するものはない、はず。 にもかかわらず、この不穏な出だしはどういう事なのか。 語り方は、二重構造になっています。 各章の「表の話」は「今」からシャルル9世の御代に、1572年8月24日、聖バルテルミーの祝日早朝に起きた「聖バルテルミーの虐殺」までを描きます。 最初の章と最終章を除いた章それぞれの最後に、「裏の話」が語られます。これは、カトリーヌ・ド・メディシスの独白。「今」の話を絡め、おもてには出していない自分の本音をぶちまけつつ、屈辱的なフランス王室への輿入れの日から、夫のアンリ2世がモンゴメリー伯との馬上槍試合の怪我が元で亡くなるまで。 王の崩御には白い喪服を着けるというフランス王宮の慣習をただ一人破り、世の未亡人と同じ黒の喪服を身にまとい、生涯黒しか着なかったことで、「黒王妃 La Reine Noire」の伝説が始まります。  終章 30 血なんか珍しいものじゃありません は、1572年8月26日のルーヴル宮殿が舞台。腐臭を発しはじめた大量の、何百という死体が積み重なった中庭の前。 終章 30 血なんか珍しいものじゃありません は、1572年8月26日のルーヴル宮殿が舞台。腐臭を発しはじめた大量の、何百という死体が積み重なった中庭の前。旧教徒・新教徒の争いをなんとか宥和させる一つの手段として、気の弱い王シャルルを焚きつけ、狂信的な段階に入ってしまった 対立しか考えないものとの宥和は、ある段階を過ぎると言葉では無く剣でしかなしえないのかもしれない。 しかし、それを冷静に判断し、やってのける勇気と決断力を持つものは、わずかしかいない。 この時代、為政者の中でそれに気づき、なし得る胆力を持っていたのは、この「黒王妃」だけだったのか。
歴史をしっかり見据え、新たな解釈であり得べき人物像を作り上げ、生き生きと動かす。 ここで一つの歴史が作られ、このあと黒王妃の死後に、情けない三兄弟がしがみついていたフランス王位に新たな血、ブルボン朝の礎が据えられることになります──が、それは彼女のあずかり知らぬこと。 この本では、カトリーヌ・ド・メディシスがフランスに運びこんだ文化的な礎も読み取るべきでしょうけれど、歴史を切り開いた女傑の一人として語り継ぐネタになればそれでいいのではないかな。(2025/4/9) 読書メーターの記録より 読了:2025/3/29 |
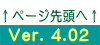 |
|---|
| 管理番号:S076-035 | 51 伝記・一代記・評伝 |
出版社:世界文化社 | |||||||
| 書名:かの名はポンパドール | ISBN978-4-418-13510-3 C0093 | ||||||||
| 初出「グレース」 2008年4月号~12月号 「家庭画報」2009年5月号~10月号 単行本化にあたり大幅に加筆・修正 | |||||||||
| 価格:2000Yen | ページ数:408P | 本のサイズ:135×195HC | |||||||
| 初版発行:2013/9/25 | 購入:2025/4/2 | 装幀・本文デザイン:木村裕治(木村デザイン事務所) 企画・編集:江本多圭子 肖像画写真:アマナイメージズ |
|||||||
 乏しい知識ですので不十分かとは思いますが、フランス王国の長い歴史の中で女傑と呼べる人は、中世でアリエノール・ダキテーヌとカトリーヌ・ド・メディシス、近世ではこのマダム・ポンパドゥールくらいじゃないか、と思っています。そして彼女以後、フランスには女傑と呼べる方は現れていない、と。 乏しい知識ですので不十分かとは思いますが、フランス王国の長い歴史の中で女傑と呼べる人は、中世でアリエノール・ダキテーヌとカトリーヌ・ド・メディシス、近世ではこのマダム・ポンパドゥールくらいじゃないか、と思っています。そして彼女以後、フランスには女傑と呼べる方は現れていない、と。意義がおありの方は多数おられるかと思いますが、知らん。(笑) 18世紀、ロココの世紀とは、ひたすら美しいものが追い求められた時代である、とまず断じられます。 そしてことさらに、女は美しくなければならなかった、と。 この美にやかましい時代の中で、25歳からその晩年近い42歳まで、数え切れないくらい肖像画が描かれた女性がいました。むろんその美貌を残すため。 すらりと背が高かった、とまず言います。しかし高すぎるのではない、伸びやかな女らしい肢体、折れてしまいそうな繊細さ、すぐ汚れてしまいそうな淡い色、脆さと背中合わせの雅やかさ。子供に母乳を与えた大きな乳房など卑しい、小さく優美な丸みであればいい。手も足もほっそりと長く、小さな卵形の頭に薔薇色の頬、秀でた額を輝かせる結い上げた淡褐色の髪、優美な半円を描く眉の下の、きらめく大きな青緑色の目。鼻だけが峰が立ちすぎるうらみがあるが嫌味なほどではない。唇は精巧に作られた人形そのもの。
そして、その肖像画の背景にあるものに注意を向けます。 愛犬や しかし地球儀、彼女の紋章が入った革表紙の分厚い本があるのはどうしてなのか。それも、ヴォルテール、モンテスキュー、そして当時初めて世に出た「百科事典」が。
物語は、8歳のジャンヌ・アントワネット・ポワソンとその弟、5歳のアベル・フランソワ・ポワソンが母親に連れられてパリの街を歩く1730年のシーンから始まります。(このあとの描写でジャンヌが9歳となったり、アベルの生年 1727/2/18 からして年齢差があわないとか、気になるけどまぁいいか)このとき町の占い師から「お嬢様はいつの日かフランスの王妃におなりあそばされます」と言われたとか。このエピソードはどこかで読んだような記憶がありますが、定かでないな。 父親のフランソワは横領事件を起こしてドイツに逃げ去り、親子三人で取り残されたのですが、したたかな母親ルイーズ・マドレーヌは、総徴税請負人であるトゥールネム──シャルル・フランソワ・ポール・ル・ノルマン・ドゥ・トゥールネムの愛人となって生活を確保していました。 このトゥールネムは、第三身分である平民階層の中でも成功した富裕なブルジョアで、すでに貴族の位も得ており、熱心にジャンヌ・アントワネットに教育を施します。すぐれた学者・芸術家を招いて、歴史、地理、フランス語、修辞学、科学、幾何学、哲学を学ばせます。さらに舞踏、戯曲の朗唱、楽器演奏、声楽。なんのためか。 このあたりの影の野心の流れは面白いのですが、ジャンヌ・アントワネットはただ大人の事情に転がされるだけの少女ではなかった──というのがサトケン節で描く主人公の肖像。 病弱で可憐な風貌、母の愛人は実の父ではないかという風説、その中で彼女はほんの子供のうちから、何を言われても晴れやかに顔を上げて微笑むことを覚えた人だったのだ、と。 1741年、19歳で彼女は結婚します。相手は、トゥールネムの甥、シャルル・ギョーム・ル・ノルマン・デティオール。貴族の位を持つ造幣局出計局長で、ブルジョアからの成り上がりながら地方領主でした。夭折した男子の後女児アエクサンドリーヌを得たのは1744年。 しかしこの時代のフランス上流階層にあっては、結婚してから恋愛が始まるのです。トゥールネムが腹にしまう目論見もありましたが、彼女自身にも野心はあったのです──そしてそれを実行する強い意志も。
「近所」であるヴェルサイユ宮殿に居住するやんごとなき陛下、ルイ15世の狩りの場に迷い込み、王の目に触れたのは事故ではない、彼女の小さな企み。それでどうなるかはわからない。 ここから始まる彼女の野心、行動力、王の寵姫の座を射止める試み。弟アベル・フランソワの制止は、ある意味彼女の決心を固めさせたのか。とはいえ、いくら期待しても、それは遙かな夢のはずだった。 1744年12月8日冬、ルイ15世の そして運命の道が開きました。 彼女がどんな女性だったのか。これは評価が分かれます。 佐藤賢一さんは、野心はありしたたかだけれど、自分の分を知ってむやみに背伸びせず内政的で、しかし誇り高くみずから手を下して他人を貶めることをしない公徳心のある芯の強い人、と描写します。 フランスの産業・芸術・文化をより開かれた豊かなものにするために心を砕き、国際政治において正義を貫く事を志向し、不倶戴天の敵であったオーストリアとの和解を求めます。 蒲柳の質であったために王との同衾が苦しくなったとき、初めて王に自分の秘密を打ち明け、許しを乞います。 彼女ジャンヌ・アントワネットが世にいう「冷たい身体」であるとは、どこかで読んだ記憶はあります。これが悪意ある風聞なのか事実なのかはわかりませんでしたが、このため王は寝室を共にすることがなくなった、と説明します。 しかし王は、当然のこととしてヴェルサイユから、寵姫の地位から離れることを願う彼女の訴えを、なんと拒否します。 夜の営みができなくてもかまわん、悦びが得られないならそれでいい、ヴェルサイユを出ることは許さん。
彼女が「王の愛人」から「王の友」になったのはこのとき。1750年代のいつか。 こののち、王としてフランスとしての矜持は持っているものの政治の細部に関わろうとしない王、そして政治に当たるべきなのに無能な諸卿に代わり彼女が自分の部屋で政務を行うようになります──そう簡単ではありませんが。 はたしてこれが、フランスの政治にとってどのような影響を与えたのか。 フランス政治を実質的に宰相として取り仕切った彼女の死後、25年たってフランス革命が起きます。 この25年という月日は、ポンパドゥール夫人という人がいたために延びたのか、縮んだのか。 それは歴史が考えるべきことですし、しょせんはイフのシミュレーションにすぎません。 しかし、フランスの歴史の中で、女傑の名に値する女性が何人かおり、彼女がその最後の一人であった、と鐵太郎は思う。 その女性を、かつて「女を描くのが下手」といわれた佐藤賢一さんがこんなに見事に描き出してくれました。感謝です。 小学生だか中学生だかわかりませんが、最初にこの方の肖像画を見たとき、え、こんな美しい人がいたんだ、とひたすら圧倒された記憶があります。名前はポンパドゥール夫人と知ったけれど、経歴も何もわからなかった頃。そしてそのあと、悲劇のフランス王妃マリー・アントワネットの肖像画を見て、なんてみっともない髪型、と思ったもの。このふたりの人物像、生き方の違いを知ると、感無量です。 それにしても、Wikipediaの彼女の項目、なんとなく悪意が感じられますね。どこかの学会の方でしょうか?(笑)(2025/5/31) 読書メーターの記録より 読了:2025/5/24 |
|||||||||||||||

 この本はもらい物。いらないから上げるとのありがたいお言葉。ビンボ人には神様に見えます。
この本はもらい物。いらないから上げるとのありがたいお言葉。ビンボ人には神様に見えます。


