トップへ戻る 作家/分野 一覧 |
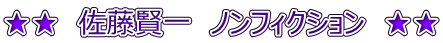
|
 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 書名 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| S076 佐藤賢一 メイン | |||
| 小説フランス革命 | |||
| S076-003 | ダルタニャンの生涯 | 史実のダルタニャン伯爵 | |
| S076-016 | 英仏百年戦争 | 英仏間に起こった大戦争の、入門敵解説 兼 新説 | |
| S076-017 S076-021 S076-031 |
カペー朝 フランス王朝史1 ヴァロワ朝 フランス王朝史2 ブルボン朝 フランス王国史3 |
佐藤賢一によるフランス王朝史 | |
| S076-029 | テンプル騎士団 | 謎に包まれた中世の騎士団の物語 | |
| S076-032 | シャルル・ドゥ・ゴール | フランスの栄光を信じ独裁者となった男 | |
| S076-033 | よくわかる一神教 | ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の世界史 | |
| S076-036 | 王の綽名 | 同じ名前が多かった欧州で、王にあだ名がついた経緯 | |

| 管理番号:S076-003 | 51 伝記・一代記 |
岩波書店 | ||
| 書名:ダルタニャンの生涯 | 史実の「三銃士」 | 岩波新書 771 | 発行 2002年 | |
| 価格:¥700 | ページ数:200P | 装丁:文庫 | ||
| 初版発行:02/2/20 | 購入:02/3/3 | |||
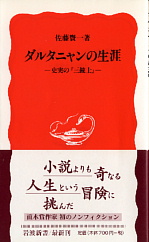 フランス人の名前で誰も知らないものがない名前に、アルセーヌ・ルパンとダルタニャンがありますね、、、 フランス人の名前で誰も知らないものがない名前に、アルセーヌ・ルパンとダルタニャンがありますね、、、と言っても、通用しない時代になっているようです。(しくしく) 永遠に人気を保つということが、いかに難しいか、と嘆くべきか、昨今の読書離れを嘆くべきか。 いや、読書が趣味だと公言する人間が少ないのは、今に始まったことではない。 さて、ダルタニャン。 実はこの本を買ったとき、著者にはまったく目もやりませんでした。内容をぱらぱらっと読み、次の瞬間レジに向かっていました。面白い本との出会いとは、こんなものです。 著者はむろん、佐藤賢一氏です。(読み始めてしばらく経ってから気づいた。) 「二人のガスコン」という小説で、これをふくらませたフィクションを書いていますが、厳密に言うとあちらの方が先(2001/1~3)。とすると、あちらを書くための資料が、このノンフィクションに結びついたと考えてもいいのかな? おそらくは、積み上げた資料をためつすがめつしているうちに、こんな面白い資料をこのまま腐らせるのももったいない、となったのではないか? ダルタニャンとは、実在したフランスの軍人貴族です。 銃士隊長も務めた人です。 しかし、その実像はどうだったのか。 この、謎とも言えない謎を掘りあかすと共に、歴史の波に消えた快男児がよみがえってきます。デュマの描くガスコーニュの溌剌たる青年とは少し違う、時代の中を精一杯生き抜いた一人の男の姿です。  若い時代の苦労あり、出世を極める苦労あり、晩年の家庭の苦労あり。 若い時代の苦労あり、出世を極める苦労あり、晩年の家庭の苦労あり。なんだ、苦労ばっかりしているな、この人。(わはは) 「ダルタニャン」が正式な家名ですらないことも、知りました。 銃士隊とは、どういうものかもわかりました。 ガスコン気質とはどういうものかも教えられました。 アトス、ポルトス、アラミスのモデルとなった男たちのことも、知りました。 ダルタニャンこと、シャルル・ドゥ・バツ・カステルモールは、1615年頃フランス南西部ガスコーニュ地方に生まれました。 そして、銃士隊長シャルル・ダルタニャン伯爵は、1673年6月25日 日曜日、イギリスとの戦闘のさなか、マスケット銃の弾丸によって戦死します。マスケット、それは、彼の銃士(mousqetaires)としての地位の象徴でもありました。なんたる歴史の皮肉。 ルイ14世が、彼の守護神たる軍人の死を、嘆きの手紙に記録しました。 一流の将帥でも、優れた技能者でも、才幹あふれる政治家でもない、一人の軍人。 そんな男の物語です。(05/4/2) |
 |
Ver. 2.17 |
|---|
| 管理番号:S076-016 | 53 史書・編年史 |
出版社:集英社 | |||||||
| 書名:英仏百年戦争 | 初出:小説すばる 2002.1-2002.5 | ISBN978-4-08-720216-X C0222 | |||||||
| 集英社新書 0216-D | 価格:680Yen | ページ数:237P | 本のサイズ:新書 | ||||||
| 初版発行:2003/11/19 第3刷:2004/1/12 | 購入:2007/6/30 | ||||||||
 小説すばるに連載されていたとき、これは「新説 英仏百年戦争」という題名だったそうです。そのままの題名でも良かったかも知れません。 小説すばるに連載されていたとき、これは「新説 英仏百年戦争」という題名だったそうです。そのままの題名でも良かったかも知れません。百年戦争とは、19世紀にまでなって名付けられた中世の戦争の集合体であり、諸説がありますが一般的には、1337/11/1のエドワード3世によるフランスへの挑戦から1453/10/19のボルドー陥落までの116年間の交戦状態を指すとされます。歴史家によっては、始まりを1294/5/19のギュイエンヌ押収、終結をピッキニー条約が締結された1475/8/29とする説もあります。また、エドワード3世がノルマンディーに上陸した1338年や、ギュイエンヌ、カンブレーにおいて戦闘が開始された1339年を開始年とする説もあります。 この間イギリスとフランスは、利害その他さまざまな理由によって国家として殴り合いをしたわけです。 この本は、百年戦争というイギリスをフランスの激突を、新しい視点でわかりやすく描いた本です。歴史解説書、歴史入門書と言ってもいいかもしれない。それに「新説」とつける理由はと言うと、新たな視点での事実の見直しという要素があるから。 歴史はフィクションである、というショッキングな言葉は、井沢流のアイ・キャッチャーみたいですね。その説明は長くなりますのでここには書きません。それなりに筋は通っているかな。 しかし、もっと大きなショックはほかにありました。 英仏百年戦争とは、イギリス人とフランス人の戦争ではない、ということです。 ああ、そうか。そう言われれば、そのとおりかもしれない。 百年戦争を始めたエドワード3世とは、イギリス人ではなかったというのです。 プランタジネット朝(1154-1399)の始祖であるヘンリー2世から始まり、リチャード1世、ジョン王、ヘンリー3世、エドワード1世、エドワード2世と連なる歴代の王も含めて、すべてがイギリス人ではなかった、というのです。彼らは、さらに遡ること 百年、1066年にイングランドの上陸して征服王朝を築いたノルマンディー公ウィリアムの時代から、まず第一にフランス人であり、フランス語が母語であったのだ、と。 であるから、呼び名からして改めなければならない。 彼らは、大国フランスの諸侯の一人であり、たまたま海外に領地としてイングランドを征服して王位を得ただけで、そもそもが、「フランスに領土を持つイギリス王ウィリアム」ではなく、「イングランド王を兼ねるノルマンディー公ギョーム」なのだと。そしてその後の時代の、英国史において燦然と輝く偉大な王たちも、アンリであり、リシャールであり、ジャンであり、エデュアルドであったのだという。 では、イギリス王が真にイングランド人、ウェールズ人、スコットランド人たちの王となったのはいつか。 それは、百年戦争が生み落としたものなのだ、佐藤節はこう言うのです。百年戦争が終わってはじめて、イングランドを統治する王はイギリス人の王となったのだし、フランスを統治する王は、イギリスを他国として認識する国家の王になったのだと。 この考えを元に、百年戦争自体を再構成し、わかりやすく説明してくれたのがこの本です。 入門書として歴史の流れを楽しむも良し、新説を楽しむのも良し。よい方向に期待を裏切ってくれた本でした。(07/8/14) |
| Ver. 2.23 |
|---|
| 管理番号:S076-017 | 53 史書・編年史 | 出版社:講談社 | |||||||
| 書名:カペー朝 フランス王朝史 1 | ISBN978-4-06-288005-3 C0222 | ||||||||
| 講談社現代新書 2005 | 価格:740Yen | ページ数:249P | 本のサイズ:新書 | ||||||
| 初版発行:2009/7/20 | 購入:2009/8/5 | 装幀:中島英樹 | |||||||
 カペー朝とは、遠い昔のフランスの王家です。987年より始まり、1328年まで14代の王を出していますね。この王朝のもとで、フランスは中世後半までにヨーロッパに冠たる大強国の地位を固めた訳です。 カペー朝とは、遠い昔のフランスの王家です。987年より始まり、1328年まで14代の王を出していますね。この王朝のもとで、フランスは中世後半までにヨーロッパに冠たる大強国の地位を固めた訳です。以下の王たちの姿が歴史に残ります。
しかし、従来の歴史解釈に肯んじることを是としない佐藤氏(つまり、アマノジャク史観ということですなw)はこの流れを、「いまのフランス」の歴史とは見ません。かつてユーグ・カペーが王位に就いた国は、分裂した大フランク王国の一部西フランク王国であり、佐藤氏はユーグ自身が王に祭り上げて再興したカロリング朝の王の死後、そしてその前史から、この歴史を語り始めます。 そもそもは諸侯の連合体をまとめる王、という立場であったカロリング朝は、西暦800年に即位した第二代の王シャルルマーニュの時代にその領土を広げ、その孫の時代、843年に三つに分裂したのだそうな。その西フランク王国が現在のフランスの元であると日本では習います。 佐藤さんは、そうではない、それは結果論に過ぎないといいます。王国の分裂は、財産が一子相続とされず、子らの数によって分割されて相続された時代にあっては当たり前の事だったと。つまり一時的に息子の世代で分割されても、全体として「我らはフランク」と考える領域は同じであったのだそうな。 すると現在のフランスに至る、独立したフランスというカテゴリーができたのはいつか。 諸説や諸見解を踏まえた上で、佐藤氏はカペー王朝ができたときからフランスが始まった、と考えるそうです。 フランス王のルイ13世、14世などの起源となるルイ1世が、シャルルマーニュの第三子であり、のちにフランスとなる土地をまったく統治していないカロリング朝のドイツ名ルートヴィヒ1世王(778-840)だったりするのですが、これはこれでややこしい話ですけどね。 かくして、パリ伯としてのちの大都市パリ近郊となる土地を領土とする伯爵家だったカペー家は、一度は衰亡していたカロリング朝を再興してルイ5世を立てたのですが、この王が986年5月に急死すると、後援者、摂政として影の男だった立場から表舞台に登場せざるを得なくなり、ここにカペー朝の王ユーグが誕生します。このあたり流れは、古代中国の殷の末期、周王は天下の2/3を領土としながら殷の臣下の立場にいたことを連想させます。あるいは、魏の武帝(曹操)があくまで後漢の皇帝の地位を求めなかった事とも。 東西の歴史で、同じようなことをするものですね。無理に簒奪して恨みをかったうえに責任を押しつけられるよりは、キングメイカーでいた方が気が楽ですから。 最初、この王朝も基盤は危うかったらしい。しかし幸運と力量と歴史の流れが、徐々にその地歩を固めていきます。 領土的にこの王朝の直轄地は、現代のフランスの版図を考えると、決して大きくありません。歴代の領土を平均して、フランスの中で1割にもならないのではないでしょうか。 しかし、南の広大なアキテーヌ侯領を賭けてイギリス・プランタジネット朝と血みどろの抗争を行ったのはこの王朝です。フランス国内の十字軍という、オクシタニア地方を舞台にした恐るべき内戦を経験したのもこの王朝です。そして法王の地位を揺るがした法王座の移動、アヴィニョンにローマ法王を迎えてローマ・カトリックから実質的な独立を勝ち取ったのもこの王朝です。 さらに、神殿(テンプル)騎士団を壊滅させてその呪いを受けたとされるのも、この王朝です。 サリカ法に拘束された男子継承というルールさえなければ、もっと継続したかも知れませんが、およそ三世紀半の時を経て最後の王シャルル4世が1328年2月1日に死に、後継者であったはずの息子はその前に早世していました。王の死んだ時点で妊娠していた王妃ジャンヌ・デヴリューの生んだのは女児でした。 この結果、分家の戦上手のヴァロア伯フィリップが、フランス王フィリップ6世として王位に就きます。 カペー家の血は、嫡流ではないにしてもそのまま継続され、ヴァロア朝、ブルボン朝、オルレアン朝と、フランス王はその流れを引きます。例外はナポレオン1世と3世のみ。ルイ16世が処刑されたとき、王としての地位を剥奪された彼が呼ばれた名は「ルイ・カペー」であり、マリー・アントワネットは「ルイ・カペーの寡婦」でした。歴史って面白い。 また、現在のスペイン王家はブルボン家の分家ですので、今もなおカペー家はその血を残しています。 この長い激動の時代を、一冊の本に凝縮したのがこの本。面白い。先週読んだ中国皇帝の本にはがっかりしたけど、これは面白かった。 こういう佐藤賢一節は、好きです。 佐藤さんのフランス革命史、内容を読んでその文体にちょっとためらってますが、面白いのかも。(09/9/13) |
||||||||||
 |
Ver. 3.01 |
|---|
| 管理番号:S076-021 | 53 史書・編年史 | 出版社:講談社 | |||||||
| 書名:ヴァロワ朝 フランス王朝史2 | ISBN978-4-06-288281-1 C0222 | ||||||||
| 講談社現代新書 2281 | 価格:920Yen | ページ数:368P | 本のサイズ:新書 | ||||||
| 初版発行:2014/9/20 | 購入:2014/9/20 | 装幀:中島英樹 | |||||||
 古代から中世にかけて未来にフランスと呼ばれる国家を統治したカペー朝のあと、ヴァロワ朝がそのあとを継ぎます。この本は、262年間に渡って国家を守った王朝と13人の王の記録です。 古代から中世にかけて未来にフランスと呼ばれる国家を統治したカペー朝のあと、ヴァロワ朝がそのあとを継ぎます。この本は、262年間に渡って国家を守った王朝と13人の王の記録です。フィリップ六世(幸運王 1328-1350) 本来、単なるヴァロア伯として終わるはずだったフランス王家の傍流のフィリップが王位に就きます。35歳という当時の中年で王の座についたため、世に言う le Bien Fortuné 幸運王。 しかし軍司令官としては凡庸、と佐藤氏は切り捨てます。取り柄は政治家として、ただ手堅いと言うことだけだ。と。 しかしその手堅さで、百年戦争の発端となったイングランドの挑戦を受け、クレシーの戦いで惨敗したのちもフランスは維持されました。 ジャン二世(良王 1350-1364) 歴史に le Bon 良王 として名が残ります。何が良いのかというと、当時の価値観で 「鷹揚にして勇ましい」、「騎士らしい」 ということ。それが、良い、ということなのだそうな。 軍を改革させ、諸侯や大貴族が寄り集まったフランスの軍隊を、エトワール騎士団を創設することなどにより、フランス王の軍隊へと変貌させようとしますが、ポアティエの戦いで再びイングランドのエドワード黒太子に惨敗します。 シャルル五世(賢王 1364-1380) 敗戦により莫大なものとなった父王ジャン二世の身代金を支払うなど、王太子のころから国家の財政と内政を支えてきたシャルルは、歴史上「税金の父」と呼ばれることもあります。通り名は、le Sage 賢王。健康には自信はなかったものの、人を見る目と優れた政治センスを備えていました。 彼が武将として見出したのは、ベルトラン・デュ・ゲクラン。このブルターニュの小貴族をフランス王軍の総指揮官に任じ、全戦略をまかせます。賢王とこの大元帥のデュオはフランス史上最強、と佐藤賢一氏は書きます。 シャルル六世(狂王 1380-1422) 11歳で即位したシャルルが受け継いだのは、百年戦争の強国フランス。同時に内憂で分裂寸前のフランス。 母ジャンヌの家系ブルボン家に精神異常の遺伝があったせいか、すぐれた執政の才を示しつつあったものの狂気に襲われます。現在では統合失調症や、躁鬱病の一種と診断されているようですが、そのために歴史上 le Fou 狂王 として知られました。 アザンクールの戦いから始まりイングランド王ヘンリー五世に大敗を喫し、フランスの命脈を危うくしますが、敵王が早死にし、彼シャルルが長生きしたために息をつくこととなりました。 シャルル七世(勝利王 1422-1461) シャルル六世の十番目の子供で、王子としても三番目であったシャルルは、期待されない存在でした。身体能力も劣っており、短足で運動音痴、しかも内気で引っ込み思案。その彼が王として即位できたのは、内紛に乗じてと言うよりジャンヌ・ダルクの存在。 彼女の活躍を文字どおり踏み台として、シャルルは百年戦争に勝利をもたらし、 le Victorieux 勝利王 と呼ばれます。 ルイ十一世(1461-1483) 長命だった父王のせいで、38歳という(当時としては)高齢で王位に就いたルイは、暴君として歴史に名を残します。しかし同時にブールゴーニュ公国、イングランドとの確執の中でフランス国家を拡充させる功績を上げます。 非常な切れものであると同時にエキセントリックな一面もあった王は、命尽きる二年ほど前から精神の平衡が狂い、半狂乱になって死んだそうな。 シャルル八世(1483-1498) ルイ十一世の晩年に生まれたシャルルは、狂喜した父王によって超過保護に育てられたそうな。13歳で王位に就いたのち、成人するまで姉夫婦が政務を代行していましたが、独り立ちすると意外にも対外戦争に打って出ます。一時はイタリア半島の南半分まで手に入れますが、諸国の反フランス同盟に敗退し、再起を期する中でアンボワーズ城の改築工事の視察中に柱に頭をぶつけて死にます。 ルイ十二世(1498-1515) シャルル八世の突然の死により王座が転がり込んできたのは、36歳で前王より八歳年上のオルレアン公ルイ二世。即位してルイ十二世。おそらく歴代フランス王の中でもっともIQが高かったろう、と作者が評する優等生タイプの人物。前王の王妃がブルターニュ公女であったために、結婚していた前王の王女との離婚を断行して前王妃アンヌと結婚します。時の教皇はかのボルジア家のアレクサンデル六世。 そのまま優等生でいればよかったものを、イタリアとの戦争でつまずき、王子をえられないまま死亡。 フランソワ一世(1515-1547) 血統からすると傍流に当たるアングレーム伯フランソワは、よく笑う男だったそうな。母親ルイーズ・ドゥ・サヴォアに溺愛された逞しい巨漢の派手好き男。自信家で楽天家。湯水のごとく戦争に金を使い、はては神聖ローマ皇帝選挙に打って出たりしますが、カール五世にしてやられ、ついにはイングランドのヘンリー八世とも戦端を開く羽目に。 戦争には勝ったものの、財政難に追いまくられた中で病死。 アンリ二世(1547-1559) フランソワの嫡男。年長の愛人ディアーヌ・ドゥ・ポワティエとの出会いも含め、父王には恨みしかもたない男。 みずからに自信を持たない気弱な青年であったがゆえに、着々と少しずつフランスの支配体制を強化し、イタリア戦争を終結させるなどの功績を上げますが、ミシェル・ドゥ・ノストラダムスの予言に有名な場面、騎馬槍試合の事故で死亡。 フランソワ二世(1559-1560) 前王妃カトリーヌ・ドゥ・メディシスの庇護の元、彼とふたりの弟が次々とフランス王位に就きます。 長男であったフランソワは、病弱だったそうな。耳鼻が特に悪く、慢性的な鼻づまりと友に中耳に膿がたまりやすく、しばしば黄色い膿が耳からあふれ、首まで垂れていたそうな。15歳で王位に就いたものの、あまり個性を発揮しないまま終わります。 妻はスコットランドのメアリー・スチュアート。この王妃の尻に敷かれたと言われますが、この美しい王妃が政治的に無能だったおかげで内紛は避けられ、若くして病死します。 シャルル九世(1560-1574) 兄のあとを継いだのは10歳の三男シャルル。幼い王として全国を行脚して人気者になるものの、宗教戦争に苦しめられます。 妹のマルグリッド、王妃マルゴとして有名な奔放な娘との比較から、作者はアンリ二世の子供たちはみな中性的だったのではないか、と評します。とはいえ、性的衝動も旺盛で、女とみると王という地位を利用してあたるを幸いと言うところもあったらしい。 サン・バルテミーの虐殺事件ののち、結核と思われる病気で死亡。 強すぎる母と弱すぎる自分からの解放、とは作者の弁。言い得て妙か。 アンリ三世(1574-1589) ポーランド王としてヨーロッパの彼方に送られていたのに、兄が死んだと聞いたとたんに大事な王位を放り出して帰国し、王位に就いたとのこと。途中でしっかり遊んできた上に、王となって最初に行ったのが宮廷エチケットの制定だとか。まァそんな人なのだそうな。刺繍の美しさを愛で、リボンの可愛らしさに歓声を上げ、絹地の滑らかさにうっとりする感性の持ち主、なんだって。 武勇に優れていたのですが、宗教戦争の争乱のさなかでもそんな人だったので、母カトリーヌがいなければどうなっていたことやら。 そんなこんなで騒乱の決着もつけられず後継者も定められないまま、遠縁のナバラ王アンリ・ドゥ・ブルボンに王位を譲って死にます。 なんだろね。 というところで、ヴァロワ朝はおわり。歴史って面白いねぇ。(2015/1/13) |
 |
Ver. 3.04 |
|---|
| 管理番号:S076-029 | 53 史書・編年史 |
出版社:集英社 | |||||||
| 書名:テンプル騎士団 | ISBN978-4-08-721040-8 C0220 | ||||||||
| 集英社新書 0940-D | 価格:900Yen | ページ数:288P | 本のサイズ:新書 | ||||||
| 初版発行:2018/7/18 | 購入:2018/10/3 | ||||||||
 14世紀初め、1307年10月13日、フランス国王フィリップ4世はなんの前触れもなく、国内のテンプル騎士団の会員を一斉に逮捕し、この騎士団を壊滅に追いこみます。騎士団の騎士たちは、一切抵抗せずに縛に就いたという。 14世紀初め、1307年10月13日、フランス国王フィリップ4世はなんの前触れもなく、国内のテンプル騎士団の会員を一斉に逮捕し、この騎士団を壊滅に追いこみます。騎士団の騎士たちは、一切抵抗せずに縛に就いたという。彼らは悲惨な拷問にかけられて反キリストであることを〝告白〟し、異端者として火焙りになった者もいるそうな。 全ヨーロッパにまたがって軍事、経済、政治、外交を掌握していたとされるテンプル騎士団が、なぜこうもあっけなく壊滅したのか。なぜフランス王はこれほどまで残酷にこの騎士団を敵視したのか。 この本は、テンプル騎士団の歴史と存在意味を新たな視点で掘り起こし、わかりやすく解説したものです。後世、さまざまな陰謀論の中でさまざまな形に描かれたテンプル騎士団とは、いったいなんだったのか。 佐藤賢一さんは、この謎を歴史を追って解説します。 章立ては、第一部がテンプル騎士団事件──前編。第三部がテンプル騎士団事件──後編。どちらも、1307年の騎士団壊滅の歴史を追っています。最後は、騎士団総長ジャック・ドゥ・モレーら最高幹部たちが火刑に処せられるまで。 この間にある 第二部 テンプル騎士団とはなにか が五つの章に分けられ、騎士団の歴史と変遷が描かれます。 第一章 テンプル騎士団は始まる 「ジェダイの騎士」という言葉から話を始めます。映画「スター・ウォーズ」に出てきたヒーローたちの集団。しかしなぜこの映画では騎士団という名を使ったのか。いわゆるヨーロッパの騎士とはあまりに違うではないか。 「ジェダイ」の騎士たちは、中世の騎士のように恋愛とか貴婦人の崇拝など行いません。これは御法度なのです。しかも、身分制度によって任命されるものではなく、奴隷のアナキンでさえ騎士になれる。禁欲を徹底させ、僧侶めいた衣装さえ着ている。これはなぜなのか。 もしや彼らはテンプル騎士団を下敷きにしているのではないか。ではテンプル騎士団とはどのようなものなのか。 十字軍が始まり、聖地エルサレムが「解放」されたとき、信仰に燃える西方のキリスト教徒は狂喜して聖地巡礼に殺到したと言います。しかしむろん、西欧州からパレスティナまでは遠い。しかも治安がいいとはお世辞にも言えない。 じゃあ、オレたちがみんなを守ってやろう、そうすれば神の祝福があるかも、と考えた二人の騎士、ユーグ・ドゥ・パイヤンとゴドフロワ・ドゥ・サントメールが作り上げた山道を警邏するボランティア団体が、エルサレムの一角に本部を設置し、その一角すなわちソロモン神殿(Temple)の名からテンプル騎士団と呼ばれる神の名による騎士修道会になるまで。 さまざまな人々の希望と思惑によって、テンプル騎士団は徐々に聖地の一大勢力となります。 第二章 テンプル騎士団は戦う この騎士団が正式な修道会となり、会則、慣習律、そして教皇勅書などが定められ、組織として確立していくにつれてその姿は「警備隊」「警察」から「軍隊」と変貌していきます。十字軍の名の元に西欧から送られてくる遠征軍が去った後、聖地を守るだけでなく攻める組織へ。そしてそのメンバーも。西欧から聖地に赴いた騎士だけから、現地の東方で徴募された兵たち、そして遠くイベリア半島でイスラムと戦うレコンキスタの一員としての兵たちも、騎士団の一員と。 イスラムと戦い慣れた彼らは、正規の十字軍の中で重要な戦力ともなり、行軍に当たって同じ聖地で結成されたヨハネ騎士団と友に常に前衛か後衛を期待されるように。そしてその組織は、ヨーロッパの歴史の中で最初、16世紀に日本で初めて常備軍を率いた織田信長の時代から四百年遡る12世紀に、彼らは常備軍と変貌します。 御恩と奉公の契約によってのみ成り立つ封建制軍隊とは、そもそも精神構造が違う。これで強くないはずがない。 第三章 テンプル騎士団は持つ 十字軍が二百年の苦闘ののち撤退すると、テンプル騎士団は拠点を聖地から西欧諸国の寄進された城塞、そして欧州の管区(province)に移動させます。ローマ教皇や諸王たちが、お膝元の西欧で彼らの存在の意味を考えはじめるのはこの頃。なんといっても彼らは聖地を神の剣、神の盾として守る者であり、教皇の命にのみ従うキリストの騎士ですから、東方で彼らの存在意味が薄れたにも関わらずその存在価値はまったく減じていない。寄付寄進の申し出はますます増大します。入団志願の騎士たちは途絶えることなく、しかもその財産を寄進することが習いとなりますので、その社会的地位も高まるし騎士団としての財産も増大するばかり。それを運ぶテンプル街道まで自力で作るほどに。 この寄付寄進熱は13世紀になると冷めていったそうですが、それでも所蔵する有形無形の財産は膨大であり、それを管理する必要ができます。そしてそれを行うことにより、元々持っていた軍事力に加え、自前の商業活動、経済活動を行う能力を身につけることになります。 第四章 テンプル騎士団は貸す その結果、修道院という聖域の中で莫大な財産が蓄えられ、運用されます。その財産をどう活用するのか。 中世の戦争では、キリスト教圏イスラム圏にかかわらず、のちの賠償金と同じような意味で身代金の支払いが敗者に課せられます。それをその場で支払うことができるのは、最前線にまで金融為替のシステムを持っているテンプル騎士団のみ。となれば、十字軍はテンプル騎士団を銀行がわりに使うようになります。 そして戦場だけではない、西欧においてもテンプル騎士団による金融活動が行われるようになります。その結果、テンプル騎士団によって経済的に支配された諸国家は、政治的にも支配されることになります。 むろん誰もこの状態を支配とはいいませんが。 第五章 テンプル騎士団は嫌われる という訳で、テンプル騎士団はやがて嫌われたのだ、というのが佐藤賢一さんの話の持っていく方向。 特に事実上国家の金庫をテンプル騎士団に預けていたフランスでは、「美男王 le Bel」と呼ばれたフィリップ4世(1268-1314 仏王在位1285-1314)が、1307年、ついに自分の金庫番に牙をむいたのだ、と。 そして、フランスのテンプル騎士団はある日突然異端の嫌疑を受け、すさまじい拷問の中でその容疑を認め、解体されたのでした。他の国にもテンプル騎士団は拠点を置き、それなりに生き残りますが、アヴィニョンに教皇座が移り、フランスという安全圏で一種の亡命政権を築いた教皇がテンプル騎士団を異端として破門すれば、もうその先はない。 こうして、歴史は作られたのだ、と。 このあたりの歴史を、佐藤賢一さんは実にわかりやすく軽妙なタッチで描いてくれます。 その視点はウェットではないけれど、さりとてシニカルでもない。おどろおどろしい歴史の闇と思われていたものも、こんな感じに解説されるとわかりやすいね。 ちょっと偏執狂的(失礼)でしつこいところがある小説のときのサトケン節ではなく、こういう文体で語ってくれますと、読んでいて実にたのしい。 なるほど、こう言うことだったのかもしれない。(2018/10/27) 読書メーターの記録より 読了:2018/10/10 |
 |
Ver. 3.05 |
|---|
| 管理番号:S076-031 | 53 史書・編年史 | 出版社:講談社 | |||||||
| 書名:ブルボン朝 フランス王国史3 | ISBN978-4-06-516433-4 C0222 | ||||||||
| 講談社現代新書 2526 | 価格:1000Yen | ページ数:456P | 本のサイズ:新書 | ||||||
| 初版発行:19/6/20 第1刷:19/7/8 | 購入:2019/10/11 | 装幀:中島英樹 | |||||||
 この巻はブルボン朝なので、構成としてはフランス革命までで、そのあとの(ナポレオン)ボナパルト朝、ブルボン朝の尻尾、オルレアン朝は別になるのかと思っていました。でもまぁ、あんなちっぽけなものは全体のオマケに過ぎない、ということでしょうか。ボナパルト朝を除いて、その後の王朝もこの本に入っています。オマケとして、かな。 この巻はブルボン朝なので、構成としてはフランス革命までで、そのあとの(ナポレオン)ボナパルト朝、ブルボン朝の尻尾、オルレアン朝は別になるのかと思っていました。でもまぁ、あんなちっぽけなものは全体のオマケに過ぎない、ということでしょうか。ボナパルト朝を除いて、その後の王朝もこの本に入っています。オマケとして、かな。で、この本は1589年8月2日に即位したアンリ・ドゥ・ブルボンから始まってフランス革命で断絶し、様々な歴史を経てオルレアン公ルイ・フィリップがひっそりと王座を捨てたのが1848年2月24日。これがブルボン朝の本当の終焉でした。 そこまでの長い歴史の中で、ブルボン朝が成し遂げたことはなにか。
で、本文。  第一章 大王アンリ四世(1579年~1610年) 第一章 大王アンリ四世(1579年~1610年)ヴァロワ朝最後の王アンリ三世が若い修道士に刺されて絶命した時、その宮廷にいた35歳のアンリ・ドゥ・ブルボンは、当時その血筋からして王位継承の最高位にあった事もあり、故王の遺言もあって、ヴァロワ朝の断絶を受けてその王位を継ぎます。フランス人に今もなお最も愛されるブルボン朝の「大王」、アンリ四世の誕生でした。 そのあとの歴史の流れから見ると、その登極はの流れは当然、必然のように思われますが、実はそう簡単な道程ではなかったのだそうな。 生まれも、ややこしい。父アントワーヌ・ドゥ・ブルボン。カペー朝の第9代ルイ9世の六男で末子のロベールを始祖とする、王家の分家のひとつから始まります。クレルモン伯爵家という小さな領地を持ち、ボルボン、ボルボネなどとも言われるブールゴーニュ公家の分家の名乗りブルボンを姓に持つ妻の領土を得てブルボン卿を名乗り、ラ・マルシェ伯、ヴァンドーム泊などの名乗りを持った、ヴァロア朝の王室からみれば分家の分家でした。つまり、王家の中でははぐれ者。 母は、フランス西南部、スペインとの国教近くの大領主アルブレ家のジャンヌ・ダルブレ。ピレネー山脈の向こうはもうスペインに取られたものの、かつて12世紀以降イングランド王家になびいていたこともあった土着の豪族の、末裔。さまざまな有力家門を吸収して成り上がった一大勢力で、建前上王家に服さないナバラ(フランス語でナヴァール)王家を名乗っていました。いってみれば、父はナヴァール王家の入り婿。生まれた子をナヴァールの息子として育てたいと考える勢力がいても不思議はない。 と言うわけで、アンリはヴァロワ朝末期の宗教戦争の動乱の中で改宗を繰り返し、新教徒のナヴァール、旧教徒のフランス王家の立場を上手く泳ぎ渡ろうとします。時代と趨勢に流されてなのか、したたかな計算の上でなのか。 宗教に支配される時代の中で、それを越えようとしたのがアンリの生涯だったらしい。 華やかというか生臭い多数の愛人たちをかかえ、勢力的に生き、勢力的に政治を行い、常備軍を新設し、税を軽減して「良王 le bon roi)と呼ばれ、宗教的寛容を唱え、豪快に生きたのが、まさにアンリ四世。 国家の基盤を固めている途中で、修道士くずれのフランソワ・ラヴァイヤックにより、56歳で暗殺されます。 第二章 正義王ルイ十三世(1610年~1643年) 「正義王 le Juste)という呼び名は、どうやら本人が言いだしたらしい。由来が、9月27日の天秤座、正義を象徴する天秤によるものだとは、なんとも興醒めなのですが、それはそれ。  父王の死後、9歳で王位に就きますが無論自分で政治は行えない。まず母后が摂政となりますが、この前王妃が著者に言わせると 父王の死後、9歳で王位に就きますが無論自分で政治は行えない。まず母后が摂政となりますが、この前王妃が著者に言わせると
この摂政が、フランスの政治路線をアンリ四世の意向に反して親スペインに路線に変換します。これが国内の旧来の帯剣貴族(noblesse d'épée)と新興の法服貴族(noblesse de robe)の対立をまねきます。ここで母后が見出したのは、リュソンの司教で聖職代表議員であったアルマン・ジャン・ドゥ・プレッシ・ドゥ・リシュリュー。彼女は敵だらけになった中で味方として力を発揮しそうなこの男を重用します。 王は子どもの頃から高慢で不遜、おまけに嫉妬心が強く、いつも自分が中心でないと気がすまない性格だったそうな。母親に屈服させられる恨みは長じるに従って大きくなり、16歳になって成人するや母の寵臣コンチーノ・コンチーニとその妻レオノーラ・ガリガイと共に母を排除します。夫妻は殺され、母后は追放。 このとき失脚したリシュリューを、王は母との対決にあたって仲介役として採用。王権確立の柱にします。 三銃士の時代背景で有名なルイ十三世の治世とは、フランス王権の確立への不器用な道程と思えばいい。無責任で有能とはいいがたいこの王を中心に時代は動き、宰相リシュリュー枢機卿の豪腕によりフランス国家の基礎が固まります。 疎遠だった王妃アンヌ・ドートリッシュとの間に、22年間望まれていた子供が、それも男子が生まれた経緯については、事実は謎だが公式発表からして何とでも想像できるもの。それもまた、歴史の落とした余話か。 宰相リシュリューが死んだのは1682年12月、それを追うようにルイ十三世は結核により翌年5月崩御します。  第三章 太陽王ルイ十四世(1643年~1715年) 第三章 太陽王ルイ十四世(1643年~1715年)と言うわけで新王ルイ十四世が4歳8ヶ月で即位した時、フランス国家はとりあえず盤石でした。なにしろ、リシュリューが育てた後継者マザランと、リシュリュー路線を継承することに転向した王太后アンヌ・ドートリッシュがスクラムを組んでいたのですから。 呼び名はむろん「太陽王 Roi-Soleil」。バレエが好きで、太陽神アポロンの紛争で踊ったことでこの名がついたのだそうな。なんともお気楽な感じです。 しかし即位後は30年戦争真っ盛りで、これに勝ち抜こうと必死になっているマザランの元で重税を課せられたフランスは、不満分子をため込んだ状態が沸騰します。この二回のフロンドの乱が、ルイ十四世の心に一生祟ることに。 対外戦争からベルサイユ宮廷文化の確立までたくさんのことをやらかし、在位72年はフランス王朝最長であり、1715年9月1日に誕生日まであと4日残して76歳で崩御。糖尿病らしい、とのことです。長寿を全うした君主の通例で、フランスの栄光をこれでもかと高めてくれた王に対し、国民は冷ややかな見送りだったそうな。  第四章 最愛王ルイ十五世(1715年~1774年) 第四章 最愛王ルイ十五世(1715年~1774年)ルイ十四世の曾孫として、わずか5歳で即位したのが十五世。これだけ世代をジャンプしたのは、無論その間にいた王子たちが十四世に先んじて死んでしまったため。天然痘と麻疹が多かったようです。一度は王太子として立てられたブールゴーニュ公ルイ夫妻も麻疹で死に、そのまた息子つまり十四世の曾孫の兄弟のうち、長男は1歳にならず夭折、次男は両親と同じ病気で死亡。最後に残った三男のアンジュー公ルイが十五世として王位に就きます。わずか5歳で。 ほっと安堵の息を漏らしたのはだれだったのか。ちなみにこの三兄弟、みんなルイという名でした。安直なネーミングですな。 ついた呼び名は「最愛王(le Bien-Aimé」。歴代のフランス国王の中で一番の美男だったことによるのか、即位後すぐヴェルサイユからパリに居城を移したことによるのか。 幼王ですから、むろん摂政がつきます。今回は十四世の甥、オルレアン公フィリップ二世。この摂政がまず行ったことは、先王が定めた王位継承権まで与えられた先王の愛人の息子たちを次々排除すること。なかなかに陰険。 この大人たちの権謀術数の中で、それなりにきちんと帝王学を学んで成人した十五世ですが、歴代フランス王の中でも屈指の体格を誇り体の中のエネルギーの発散場所に困ることになったとか。で、狩りに熱中したあと励んだのが女性。 王を支える廷臣たちが勤勉だったこと、「爺や」と著者が言う傅役だったフレジュス司教のちの枢機卿フルリイが優秀だったこと、また寵姫の中から現れたポンパドール侯爵夫人という傑物が宮廷を仕切ったこと。さまざまな要因が重なり、美男の漁色王の治世は盤石でした。なんともはや。 この一世を風靡しひとつの文化体系まで作り上げたポンパドール夫人なきあと、ナンバーワン寵姫となったのが平民出身のジャンヌ・ベキュことデュ・バリー伯爵夫人。野心家ではあるがポンパドール夫人のような才覚もなく、チヤホヤされたいだけの女だったと著者は切り捨てます。
いくつか動乱はあったにしてもとりたてて大過なく最期を迎えたのですが、
 第五章 ルイ十六世(1774年~1792年) 第五章 ルイ十六世(1774年~1792年)若々しい青年王(即位時19歳)として登場したルイ十六世は国民には好意的に受けとめられたのですが、なんともパッとしない。五人兄弟の真ん中、三男で、影が薄かったこともあったらしい。勉強家で真面目、利発でもの静かな理系男子であったとのことですので、王家でなく彼の才に見合う家に生まれれば幸福な人生を送れたことでしょう。しかしヨーロッパ最強の王国の王になってしまったのが運の尽き。 啓蒙思想が一世を風靡し、大西洋のむこうで英国の植民地が独立してアメリカ合衆国を名乗る時代の中で、十六世は毅然とした施政を見せることは終始ありません。ありていに言えば、煮え切らない。態度がいつも中途半端。 熟慮する性格といえばそうなのでしょうが、そのあと断行することがなければなんとも弁護しようがない。フランスの財政破綻という国家の大事がなければ、廷臣に人がいればなんとかなったのかもしれませんが、時代がそれを許さなかった。王妃の浪費など、その中ではささいな問題だったはず。 王妃が非難の対象になった問題に関しては、もし十六世がまともな寵姫をおいていれば、彼女らがなんとかすべき問題だったはずなのですが、これに関しては真面目で堅物だった十六世の性格が裏目に出ます。 かくして革命が起き、進行し、暴走し、王を廃することを決し、ついに元王は「ルイ・カペー」という名で処刑されることになります。1793年1月21日、在位18年、享年38歳。 第六章 最後の王たち ルイ十六世が「フランス王」ではなく「フランス人の王」、そして元王として処刑されたあと、その長男はルイ十七世と呼ばれます──が、そう呼んだのは国外に逃亡していた王弟プロヴァンス伯ルイ。本人は革命派に捕らわれたまま、1795年6月8日に悲惨な最期を遂げた、らしいのですが身代わりを残して脱出した説もいくつかあるとか。  で、その次は自分だと立ったのがプロヴァンス伯ことルイ十八世。ウェストファリアの地でアンシャン・レジームの復活を高らかに宣言しては、逃亡貴族はともかくフランス国民は納得しません。 で、その次は自分だと立ったのがプロヴァンス伯ことルイ十八世。ウェストファリアの地でアンシャン・レジームの復活を高らかに宣言しては、逃亡貴族はともかくフランス国民は納得しません。一代の風雲児ナポレオン・ボナパルトが台頭し、ロシア遠征を経てライプツィヒで敗北し、退位したあと堂々とフランスに乗りこみ、正式な王であると宣言します。しかし
 そのあとを継いだのが、末弟のアルトワ伯シャルル、シャルル十世。68歳で王位に就いた彼は、王権神授説に凝り固まった石頭の守旧派。対外戦争で負け続けたあげく、1830年7月の七月革命を経て、8月2日に退位する事となります。 そのあとを継いだのが、末弟のアルトワ伯シャルル、シャルル十世。68歳で王位に就いた彼は、王権神授説に凝り固まった石頭の守旧派。対外戦争で負け続けたあげく、1830年7月の七月革命を経て、8月2日に退位する事となります。亡命後、オーストリア領ゴリツィアで1936年11月に最後はコレラで死亡。享年79歳。  最後に国民が選んだのは、次のナポレオンを生むかも知れない共和制ではなく「フランス人民の王」を立てた君主制でした。即位したのはブルボン嫡流から見て分家、ルイ十四世の弟フィリップ・ドルレアンから始まるのオルレアン家のルイ・フィリップ一世。 最後に国民が選んだのは、次のナポレオンを生むかも知れない共和制ではなく「フランス人民の王」を立てた君主制でした。即位したのはブルボン嫡流から見て分家、ルイ十四世の弟フィリップ・ドルレアンから始まるのオルレアン家のルイ・フィリップ一世。しかしこの「七月王政」は反政府運動の弾圧の失敗により破綻し、1848年2月24日ルイ・フィリップは退位を宣言してイギリスに亡命。ヴィクトリア女王から拝領した屋敷で2年後に1850年8月死亡。享年76歳。 その後第二共和制が成立し、さらに第二帝政などは起こりましたが、ついに王政は復活せず、ブルボン朝、そして王国としてのフランスは終焉となりました。 ブルボン朝とは、フランスにとってどんなものだったのか。 犬にたとえて、たまに番犬として働けるだけだったカペー朝の王たち、猟犬として死にもの狂いに走り回ったヴァロワ朝の王たちに比べ、優雅に歩きまわるだけの血統書付きの犬だったのか。だから、革命に倒れたひとりを除き長寿を全うできたのか。 しかし、それだけのことなのか。 いやあ、佐藤賢一さんの歴史ノンフィクションは面白いね。(2020/03/06) 読書メーターの記録より 読了:2019/12/12 |
|||||||||||||||
 |
|---|
| 管理番号:S076-032 | 51 伝記・一代記 |
出版社:KADOKAWA | |||||||
| 書名:シャルル・ドゥ・ゴール | 自覚ある独裁 | ISBN978-4-04-400732-4 C0122 | |||||||
| 角川ソフィア文庫 1-419-1 | 価格:1240Yen | ページ数:732P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2022/11/25 | 購入:2022/11/19 | カバー写真:©ND/Roger-Viollet/amanaimages カバーデザイン:國枝達也 |
|||||||
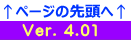 |
|---|
| 管理番号:S076-033 | 56 宗教史・文化史 | 出版社:集英社 | |||||||
| 書名:よくわかる一神教 | ユダヤ教、キリスト教、イスラム教から世界史をみる | ISBN978-4-08-744626-5 C0195 | |||||||
| 2021年6月 語り降ろしを主とした単行本として刊行 「第三部第五部」を追加して文庫化 | |||||||||
| 集英社文庫 さ23-31 | 価格:740Yen | ページ数:324P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2024/3/25 | 購入:2024/5/4 | カバーデザイン:今井秀之 写真/istock.com , stevenallan |
|||||||
 フランス史を中心に欧州を舞台にした歴史小説を書いている佐藤賢一さんによる、「歴史解説」もの。欧州史・中東史を理解するには、彼らの中に刻み込まれた源を一つにする三つの一神教、ユダヤ教・キリスト教・イスラム教を理解する必要があるよね、という趣旨ということか。 フランス史を中心に欧州を舞台にした歴史小説を書いている佐藤賢一さんによる、「歴史解説」もの。欧州史・中東史を理解するには、彼らの中に刻み込まれた源を一つにする三つの一神教、ユダヤ教・キリスト教・イスラム教を理解する必要があるよね、という趣旨ということか。プロローグは、2001年9月11日の夜。著者が日本の自宅で風呂上がりに、早朝のニューヨークの世界貿易センターにジャンボ旅客機が突っ込んだ映像に唖然としたこと。 犯行がイスラム原理主義のアルカーイダにより行われた事、宗教が絡んでいる事がわかってくるにつれ、そしてその後の世界の流れ、アフガニスタンやイラク、イスラエルとアラブで行われている戦争を見るにつけ、宗教と文化の対立が原因である事を考えざるを得なくなります。
世界の宗教とその信徒を上から言うと、資料により、また時期により数値が異なりますが、著者の調べた数字によると、第一位がキリスト教で24.48億人で世界人口の32.9%。次いでイスラム教徒が17.52億人で23.6%。第三位はヒンズー教徒で10.19億人で13.7%、第四位は仏教で5.21億人で7.0%とのこと。 実を言うと、宗教というカテゴリーだけで言うと第三位には10億人強の「無宗教徒」が入るのですが、ややこしいのでカウントしていません。また「世界三大宗教」ではないヒンズー教が仏教より上にありますが、ヒンズー教はインド以外ではほぼ信仰されていないので「世界」という観点では外れているそうな。 注目すべきは、ただ一つの神のみを信じる「一神教」が一位と二位を占め、世界人口の半分を超えているという事。 そして世界が今直面している紛争は、ほぼ皆この一神教が問題のタネ、原因の一つになっているという事。 しかもこの主要な複数の一神教が、源を一つにしていたとは。 何か理由があるのではないか。 という訳で、西洋史に主軸を置いた歴史小説を多く書いている著者が、彼の視点でこの一神教というものを解説しました。 多神教である事があたりまえの原始宗教の中で一神教という概念ができたのは、おそらくエジプトの古代王朝の一つ、第18王朝のアメンヘテプ4世(在位:BC1362?-BC1333)の時代でした。多神教の時代に、祭司階層の専横に対抗するために行われた政治的な宗教改革として断行されたのですが、この王の一代限りで元に戻ります。 この概念を、これより約百年後に「出エジプト」を行った「ユダヤ民族」が吸収し、自らが神に選ばれた民族であると自負するために一つの宗教として確立させたのではないかと言う説を、著者は提示されます。 かもしれない──そうでないかもしれない。 とはいえ、多神教が当たり前だった世界の中で、少なくともユダヤ民族は唯一の神に選ばれた民族としてのアイデンティティを得ました。それから千年以上の年月を経て、古代ローマ帝国の統治下で、キリスト教が生まれます。 簡単に書くとこれだけですが、この千年以上の年代の中で、またそれ以前の長い歴史の中で、どこまでが神話でどこからが史実に裏付けされた歴史的事実なのかわからない、さまざまな物語があります。その時代を「ユダヤ人」の視点で語り継がれてまとめられたのが、いわゆる「旧約聖書」。ユダヤ教徒、キリスト教徒、イスラム教徒が聖典(の一つ)としている書物です。 これは、いくつものいろいろな種類の文書の総称なのですが、その名で読んでいるのはキリスト教徒だけです。ユダヤ教徒にとって(内容に少し違いはあるけれど)これは「旧」ではない聖典そのものです。キリスト教徒にとって、この宗教の根幹を築き上げた「神の子」イエス・キリストの名において神と教徒が交わした「新しい契約」の書である「新約聖書」があるため、「旧約聖書」と呼ばれたのです。 ユダヤ教は、長い弱小民族の虐げられた歴史の中で、民族のアイデンティティを守るためのよすがとして、ユダヤの国が滅びたのちも、離散の民になったユダヤの民と共に欧州世界に広がります。しかしユダヤ教はユダヤの民のみが神に選ばれた民であるという信仰が根幹で、ユダヤ教徒=ユダヤ人 というのが基本ですので、この宗教はユダヤ人以外に信仰される事はありません。 キリスト教の方は、元々はユダヤ教の戒律を母胎にしていましたが、身分国籍を問わず神の救いがあるというその教えのためローマ帝国世界に大きく広がり、やがて国教となりました。ローマ帝国が東西に分裂したのち、西暦476年に滅びた西帝国の残滓の中に生まれた蛮族の国家でもキリスト教は広まり、東ローマ帝国ではキリスト教が違う形で爛熟します。 西暦610年、アラビア半島の商人だったムハンマドが、突然天使の訪問を受けて信仰に目覚め、 イスラムの聖典 無論彼らの教えの中でイエスは単なる(ムハンマドより劣る)預言者ですので、新約聖書は聖典ではありません。そして旧約聖書は こうして成立した三つの一神教は、源を一つにしますが、その成り立ちからいって相容れるものではありません。 そして一神教であるがゆえに、多神教より自分たちの正しさを疑わない。 印象と違ってイスラム教が、他の宗教に対して寛容で融和的であった事は事実ですが、かといって他の宗教を自分たちと同等の価値があるなどとは思わない。 歴史の流れの中で、一神教は世界を覆っていきます──その歴史を、宗教的でない視点で、歴史小説を書くときのアクの強いサトケン節を封じた「です・ます体」で、佐藤賢一さんは丁寧に描いていきます。 とはいえ、なぜこの一神教が世界の主流を占めるようになったのか。なぜこの一神教が世界の主要な紛争の原因になったのか。 これは、歴史を追うだけでは簡単に説明できそうにありません。 最後の章は、ウクライナ戦争を俎上に挙げます。 これは「今」を語るとき、無視する訳にはいきません。 ウクライナという国家が9世紀のキエフ大公国の流れを汲むものであったとしても、その国家建設は歴史の時間感覚からすると直近と言っていい1991年12月であり、ロシアという大国との軋轢で辛酸を舐めたとか、短い中でいろいろな歴史があったのですが、そこでこの本の主題である一神教がどうかかわるのか、というとややこしい。 何がややこしいかというと、ここで語られる宗教論は、多神教に対応する一神教ではないし、ユダヤ教・キリスト教・イスラム教の歴史でもない。キリスト教の中にある三つの分派、カトリック、プロテスタント、オーソドックスの相克でさえない。 ウクライナは この争いが今も祟っているのだそうな。 でも、だ。 世界の中の一神教というこの本の主題の中で、このテーマは(当事者にとって大問題なのかもしれませんが)微細にすぎないか、と鐵太郎は思いました。ほかに論ずべき事があるんじゃないか、と。 かくも、人々の中で宗教というものは大きな意味があるものなのである、ということは認識できるけど。 うーん。 そうそう、佐藤賢一さんって、歴史小説の時のアクの強いねちっこい書き方のものより、こういうため込んだ知識と資料をふんだんに使って歴史解説する本の方が読みやすい感じがします──ああ、歴史小説の方も好きですよ、むろん。 (2024/9/24) 読書メーターの記録より 読了:2024/7/27 |
||||||||||
| 管理番号:S076-036 | 50 ノンフィクション一般 | 出版社:日本経済新聞出版 | |||||||
| 書名:王の綽名 | 副題 | ISBN978-4-296-11894-6 C0095 | |||||||
| 英題:The King also known as | |||||||||
| 日本経済新聞 11892 | 価格:1700Yen | ページ数:232P | 本のサイズ:130×188SC | ||||||
| 初版発行: 2023/11/9 |
購入: 2025/6/16 |
装幀:アルビレオ 装画:King WilliamⅠ(The Conqueror) first Norman king of England; oil on panel, unknown artist, c.1590-1610, National Portrait Gallery, London. (Photo by VCG Wilson/Corbis via Getty Images) |
|||||||
 欧州の王たちにはなぜ同じ名前が多いのか。 欧州の王たちにはなぜ同じ名前が多いのか。これを佐藤さんは、どの血統か、誰の子かが重要視されたこと、ゲルマン人の末裔として侵略してきた人々なので、土地にちなむ名前より父祖や過去の偉大な人物の名をつけるのだ、と説明します。 だから区別を付けるために綽名を使うんだよ、と。なるほど。 漢字文化である日本は、親や主君から名前の一時をもらいますが、発想が違うのですね。ちなみに漢字文化の源流である中国では、現代ではともかく過去は、名前が一時であることが多い事もあって、同じ字は忌避されます。これも面白い発想かな。 紹介されるのは55人+1人。それぞれ4ページにきっちり収め、手早くそのいわれを説明してくれます。面白い。 小王 Pippin der Jüngere フランク王 ピピン1世 在位:751-768 フランク王国の第二王朝カロリング朝の始祖なのに「小」とは。これは先代の王国の 敬虔帝 Ludwig der Fromme フランク皇帝 ルードヴィッヒ1世 在位:813-840 王じゃなくて皇帝。フランク国王だけど西ローマ皇帝を継いだことになっているので。信心深く敬虔だったので英語で「ザ・パイアス」敬虔帝なのだが、禁欲さが足らず若い後妻の生んだ子に長男に与えた財産を切り崩そうとして、後はしっちゃかめっちゃか。 禿頭王 Charles le Chauve 西フランク王 シャルル2世 在位:845-877 敬虔帝の末子。父に愛されて幼いうちに土地や財産を与えられたあげく、一生家族内で戦争続いたそうな。頭が寂しかったのではなく王冠がなかったからハゲ扱いされたとか、出家はしないで修道院長になって一時剃髪したからとか、諸説あり。 肥満帝 Karl der Dicke フランク皇帝 カール3世 在位:876-887 分裂していたフランク王国を再統一して帝国の皇帝となったのだけど、どうもぱっとしない。皇位にしても棚ぼたで得た印象がある上、ヴァイキングとの戦いも投げやり。太っていたという記録はないが、ぜい肉太りの帝国の皇帝という印象が正しいのかも。 単純王 Charles le Simple 西フランク王 シャルル3世 在位:898-923 血統では王になるべき存在ながら若すぎて即位できず、19歳でようやく王位に就けたものの王としては国を守れず無能をさらけ出す。正直な、まっすぐなといった英語で「ザ・シンプル」という綽名は、馬鹿な、無能な、という意味になってしまったとか。 美髪王 Harald Hårfagre ノルウェー王 ハーラル1世 在位:872-930 デーン人のデンマークと並ぶヴァイキングの雄、ノース人のノルウェーの初代王。求婚した女の言葉に従い、全ノルウェーを征服するまでは髪を切らない、櫛も入れないと誓い、ノルウェーを平定して結婚し髪を切ったらほれぼれするようないい男だったとか。 青歯王 Harald Blåtand デンマーク王 ハーラル1世 在位:960-985 デンマークを平定したゴーム老王の息子。「ブラタン」と呼ばれたという伝説から、ブロ(青)+タン(歯)ではないかということでそう言われたらしいけど、青い歯とはつまり虫歯だらけの黒い歯じゃないか、と。無線通信の規格「Bluetooth」に名を残します。 捕鳥王 Hainrich der Vogler 東フランク王 ハインリヒ1世 在位:919-936 東フランク王国で、王は血統ではなく実力で選ばれた時代の王。しかもフランク人ではなくザクセン人だったということで、これ以後ここはドイツ化が進むのだそうな。そういう意味で、運良く鳥を捕まえた王は歴史の曲がり角に立っていたと言えるのかな。 合羽王 Hugues Capet フランス王 ユーグ・カペー 在位:987-996 陰の実力者でいたかった家系のボンボンが、カロリング家が途絶えたことで王になります。フード付きの外套、つまり聖職者の身なりをしていたため 殉教王 Edward the Martyr イングランド王 エドワード 在位:975-978 イングランドをほぼ統一した同名のエドガー王の息子で特に何もしていないのだけど、陰謀がらみで継母に殺され、その遺体がなんと一年経っても腐敗しなかったという伝説がありました。いろいろ政治的理由で崇拝されることになり殉教王に。 聖大公 Володимир Святославич キーウ大公 ウォロディーミル1世 在位:978-1015 東スラヴ人の国家であるキーウ公国を発展させ大公国とし、東ローマ帝国の皇女を妻とする代わりにキーウ大公国をキリスト教化してローマ圏に食いこませた実力者。この国を自分の祖と主張するウクライナでは大統領がウォロディーミル・ゼレンスキーなのだけど、俺の国こそキーウ大公国直系だというロシアの大統領はウラジーミル・プーチンなのです。 征服王 William the Conqueror イングランド王 ウィリアム1世 在位:1066-1087 子のない信仰心篤い王エドワード(懺悔王)の死後、イングランドの王位を争ったノルマンディ公ギヨーム2世が勝利し、ウィリアム1世としてノルマン朝の始祖となります。庶子としての生まれとか息子たちの反乱とかでいろいろあったけど、それはそれ。 文人王 Könyves Kálmán ハンガリー王 カール マーン 在位:1096-1116 ハンガリー王の長子だったけれど、吃音とか盲目に近いとか背骨が曲がっているとかいろいろで、聖職者になります。しかし王となった叔父が死んだため即位。頭脳明晰のため文人王と言われましたが、徹底的に酷薄で苛烈、情に流されない王であったとか。 勇敢王 Alfonso le Bravo カスティーリャ王 アルフォンソ6世 在位:1072-1109 中世の王であれば勇敢は当然かもしれませんが、ことさらにそう言われたのは、イベリア半島で 戦士王 Alifonso lo Batallero アラゴン王 アリフォンソ1世 在位:1104-1134 スペイン語だとアルフォンソ1世。11世紀に独立した新生ナバラ王国の4代目で、29回の戦いに勝利した優れた騎士として戦士と呼ばれたのだそうな。アラゴンの王も兼ねていたののだけど、戦士すぎて王妃も子もなく、没後に周囲を困らせたとか。 修道士王 Remiro lo Monche アラゴン王 レミーロ2世 在位:1134-1137 アリフォンソ王が自分の死後は十字軍の騎士団に王国を譲るなどと言い残したので、あわてた貴族たちが聖職に入っていた末弟を王に立てます。娘を産ませてさっさと修道院に入りますが、退位せず娘婿の統治をじっくり見守り指導しひっそりと世を去ります。 赤髭帝 Friedrich Barbarossa 神聖ローマ帝国 フリードリヒ1世 在位:1152-1190 シュヴァーベン大公だったが叔父コンラート3世に指名され、そのあとホーエンシュタウフェン朝の二代目皇帝に。バルバロッサがイタリア語でフリードリヒがドイツ語なのはなぜかわかりませんが、ドイツほったらかしでイタリアで戦い続けたとか。 尊厳王 Philippe Auguste フランス王 フィリップ2世 在位:1180-1223 フランス中世を代表する名君とな。名ばかりの西フランク王国を受け継ぎ、国内の大諸侯を併呑して王領を拡大し神聖ローマ皇帝を打ちのめしてフランス王国の基礎を築いたとか。だからといって 獅子心王 Richard the Lionheart イングランド王 リチャード1世 在位:1189-1199 吟遊詩人の著から生まれた、英国史に名高い英雄王。十字軍の活躍で男を上げたのですが、まさに心から獅子で、戦いしかせず生涯を送り、戦場で命を落とした人。10年弱の在位の中でイングランドにはほんの半年しかおらず、国民に重税をかけたとか。 欠地王 John Lackland イングランド王 ジョン1世 在位:1199-1216 プランタジネット朝の三代目で、イングランド史上最低の愚君なのだとか。欠地王というのは幼かったので父から領土を与えられなかったせいなのだそうですが、王位についたのちイングランド以外の領土をすべて失ったていたらくを見れば、なあ。 入植王 Sancho o Povoador ポルトガル王 サンシュ1世 在位:1185-1211 ポルトガルは、国の成り立ちはスペインとは違います。カスティーリャ王国に領土を貰ったブールゴーニュ公家の傍系公子のポストカーレ伯領を元に、王国となったもの。サンシュはその二代目で故郷から人を移民させたため入植王と呼ばれたとか。 熊候 Albrecht der Bär ブランデンブルク候 アルブレヒト1世 在位:1157-1170 背の高い美男子だったという候がなぜ熊なのか。フランク王国の北東の辺境、ドイツの真ん中あたりの辺境伯がどのようにして侯国になり、ポーランド公領と一緒になってプロイセンになったのか。ベルリンとは、この候にちなむ「熊リン」なのか。ほう。 詩人王 Teobaldo el Trovador ナバラ王 テオバルド1世 在位:1234-1253 シャンパーニュ伯ティボー4世が、母方の伯父ナバラ王サンチョ7世の跡を継ぐことになったのですが、この人はいかにも中世的な貴婦人に憧れる吟遊詩人的人物だったのだそうな。憧れの女性のためにいろいろやらかし、ナバラ王家はなんとか存続したけど。 黒女伯 Marguerite La Noire フランドル女伯 マルグリット2世 在位:1244-1280 北ベルギーのフランドル伯領の女領主が黒とな。スキャンダルの訳は、重婚の疑い。カトリックの「離婚」つまり結婚の無効取消のタイミング。教皇庁が許可するまで4年間重婚していたということで、その後30年にわたる継承戦争の元に。だから、黒と。 長脛王 Edward Longshanks イングランド王 エドワード1世 在位:1272-1307 1世と言うけれど、イングランドにはその前に3人もエドワード王がいるのだとか。とはいえこのエドワードは傑物だったそうな。長脛というか身長が高かったのは遺体を計測して明らかで、ウェールズを併合したし、あやかりたい人だったらしい。 美男王 Philippe le Bel フランス王 フィリップ4世 在位:1285-1314 長身で端正で、ともかくいい男だったそうな。ひどく寡黙でカペー朝屈指の名君と言われているのだけど、イングランドや教皇やテンプル騎士団や、さまざまな相手を敵にして容赦なく勝利した手腕は恐るべきものなのだけど、無口なのでよくわからない。 フランスの雌狼 Isabella She-Wolf of France イングランド王妃イザベラ 在位:1308-1327 長脛王の息子エドワード2世は愚君と言われるけれど、その王妃のイザベラは美女なのに綽名がつくほど嫌われます。両性愛で無能なダンナとの間に4人子供を作り、無能な王を廃位させたのち愛人と国政を私物化。最後は息子に隠居させられます。 金袋大公 Иван Калита モスクワ大公 イヴァン1世 在位:1328-1340 モンゴルの支配の中でモスクワ大公となり、ウズベク・ハンの徴税官として金を集め、その金を貸し付けて儲け、モスクワ周辺の土地を買いあさり、「タタールの軛」を使って勢力を拡大し、モスクワがロシア史の主役になる源流となります。 大口女伯 Margarete Maultasch チロル女伯 マルガレーテ 在位:1335-1363 マウルタッシュとは「ポケット口」のこと。つまり悪口。再婚した時に結婚の無効手続きをしなかったので重婚となってしまいふしだら女扱いに。それだけでならともかく、「不思議の国のアリス」の「醜い公爵夫人」の絵のモデルにされてしまった。 残酷王 Pedro o Cruel ポルトガル王 ペドロ1世 在位:1357-1367 法に基づく統治で知られた名君なのになぜそう呼ばれるかというと、訳がある。王子の時妻の侍女を愛してし、王太子妃の死後その侍女との結婚を望むが許されず、その侍女を処刑した父の忠臣をのちに残酷な方法で処刑し、残酷王と呼ばれたのだとか。 黒太子 Edward the Black Prince イングランド王太子 エドワード 生没年:1330-1376 エドワード3世の長男で、父王の片腕として百年戦争で奮戦した軍事的カリスマ、英雄。フランスでの残虐行為で 良王 Jean le Bon フランス王 ジャン2世 在位:1350-1364 ヴァロア朝の二代目、ジャン王。父の即位が百年戦争のきっかけとなり、イングランドとの戦いで奮戦して「 悪王 Carlos el Malo ナバラ王 カルロス2世 在位:1349-1387 ルイ10世の娘ジャンヌがフワナ2世としてナバラ王になったのち、息子カルロス2世は百年戦争の中で、自分にもフランス王位の権利があると陰謀まみれの生涯を過ごしたとか。その醜い死にざまで「悪王」の名を轟かしますが、しょせんは小悪党レベル。 賢王 Charles le Sage フランス王 シャルル5世 在位:1364-1380 狂王 Charles le Fol フランス王 シャルル6世 在位:1380-1422 賢王によって勝利に沸き返るフランスを遺されたのですが、20歳半ばで狂気の発作に襲われた後、死ぬまで42回もの発作に襲われ、国内は何度も内乱状態に陥ります。病名についてはいまだ諸説あり。とはいえ「愛され王」という綽名もあるんだとか。 勝利王 Charles le Victorieux フランス王 シャルル7世 在位:1422-1461 百年戦争に勝利した王であるのに、評判はあまり良くない。五男で兄たちが死んで王太子になり、国内の内乱に翻弄されてヘンリー5世に叩きのめされるなど不運続きの中、不思議に家臣に恵まれジャンヌ・ダルクが活躍し、運良く勝利王になれたのだとか。 突進公 Charles le Téméraire ブールゴーニュ公 シャルル 在位:1467-1477 フランス王家の分家を祖とするヴァロア・ブールゴーニュ公の最後の人。フランス王の支配下にあるはずなのに神聖ローマ帝国領にまで食いこむ領土を使い勢力を伸ばし、古代の 平和公 Amedeo il Pacifico サヴォイア公 アメデオ1世 在位:1416-1440 アルプス西側のサヴォイアの領主。ピエモンテ大公家、ジュネーヴ伯領を併合して領土を広げ、安定した小国家を作り上げただけでなく、「 豪華王 Lorenzo il Magnifico ロレンツォ・デ・メディチ 生没年:1449-1492 15世紀のイタリア、フィレンツェのメディチ家当主。王でも公でも君主でもない豪商・銀行の当主、しかも君主のいない共和国の一員がなぜ ドラキュラ公 Vlad Drăculea フランク王 ピピン1世 在位:1448、1456-62、1476-77 現在のルーマニア南部のワラキア公。同名の父王がハンガリー王の竜騎士団に叙せられ 航海王子 Henrique o Navegador ポルトガル王子 エンリケ 在位:1394-1460 船酔いがひどい体質で、ほとんど海に出なかったと。でも彼は、イスラム商人に頼らない交易で国を富ますことを本気で考え、自分の財産も、就任したテンプル騎士団総長の地位もフルに使って、探検航海のための事業を進め、その名で呼ばれたのだとか。 不能王 Enrique el Impotente カスティーリャ王 エンリケ4世 在位:1454-1474 身も蓋もない情けない綽名といえばこれか。二度結婚し、一回目は13年たっても妻は処女、二回目は娘が生まれたものの皆がベルトランという男の娘だと信じたとされ、最後は大人の事情に押しつぶされて本当に不能なのだとされてしまったとか。
この二人は夫婦。それぞれ別な国の王でありながら、二人力を合わせて800年かかった「 狂女王 Juana la Loca スペイン女王 フワナ1世 在位:1504-1555 「カトリック両王」の娘で初代スペイン王。ブールゴーニュ公フィリップに嫁いだのだけれど夫を愛するあまり頭のタガが外れ、兄弟親族の死により王位継承者となり夫が急死すると埋葬を許さず、その柩と共にスペイン各地をさまよったそうな。 血塗れ女王 Bloody Mary イングランド女王 メアリー1世 在位:1553-1558 イングランド王ヘンリー8世の長女として生まれたが。父王が息子が欲しいあまり国教会を起こして王妃を取りかえていったため、庶子扱いに。父王の死後、弟王子をはさんで王位に就くと、カトリックを復活させて新教徒を多数処刑したためこの綽名。 処女王 Elizabeth The Virgin Queen イングランド女王 エリザベス1世 在位:1558-1608 イングランドは女王の時代に栄えるというジンクスを作った人。メアリー1世の異母妹。生涯結婚しなかったので処女王と呼ばれました。結婚話は、国外でも国内でもいろいろありましたが、政治的イメージを優先したのか、穢れなき国母として死にます。 慎重王 Felipe el Prudence スペイン王 フェリペ2世 在位:1556-1598 スペインの黄金の世紀を象徴する王。この人の代でカスティーリャ、アラゴン、ナバラの三国をスペインとしてまとめ上げ、一時はポルトガル王、ミラノ公、シチリア王などまで兼ねます。冷静で慎重でしたが、海洋政策はあちこち破綻しました。 待望王 Sebastião o Desejado ポルトガル王 セバスティアン1世 在位:1557-1578 先王ジョアン3世が亡くなった後9人いた子供はすべて死んでおり、スペインに嫁した長女の夫スペイン王太子に王位が移ればスペインに併合されるという時、最後の王太子の妃が妊娠中で父王の死後18日目に誕生したのがこの人。ただし凡庸だったらしい。 雷王 Иван Грозный ロシア皇帝 イヴァン4世 在位:1533-1584 3歳で即位した時にはモスクワ大公でしたが、17歳になって「全ロシアの 助平ジジイ Henri Vert-Galant フランス王 アンリ4世 在位:1589-1610 いや間違ってはいないけど、といいたくなる言葉の選択(笑)。ブルボン王朝の始祖であり、内乱状態だった国内の宗教対立を鎮め、フランス史上屈指の名君で、多くの人を愛し、多くの人に愛され、多くの子をなした──じゃあやっぱり助平ジジイか。 殉教王 Charles the Martyr イギリス王 チャールズ1世 在位:1625-1649 エリザベス女王の後、スコットランド王ジェームズ6世がイングランド王となったところでこの国はイギリスとなった、という理解でいいか。そのスチュアート朝の二代目がこの人。ピューリタン革命により処刑されたのでのちに殉教王となった。 太陽王 Louis le Roi Soleil フランス王 ルイ14世 在位:1643-1715 72年という治世の長さはいまだギネス記録。フランス・ブルボン王朝の最盛期を象徴する王であり、バレエで演じた役から「太陽王」と呼ばれます。ヴェルサイユ宮殿を作り上げてそこに貴族を集め堅固な中央集権政治を行い絶対王制を確立しました。 最愛王 Louis le Bien-Aimé フランス王 ルイ15世 在位:1715-1774 長寿だった前王のため、14世の曾孫である15世は民衆が歓呼する可愛い少年として即位し、長身(175㎝)で美男の王として国民に愛されます。子孫を残し、愛妾ポンパドゥール夫人を含め優れた側近に政治を丸投げして無難に在位期間を過ごしました。 解放皇帝 Pedro o Libertador ブラジル皇帝 ペドロ1世 在位:1822-1831 ナポレオン戦争のあおりでブラジルに逃れたポルトガル王家の中で、帰国しなかったペドロ王子がここで植民地独立の波に乗ってポルトガルよりの独立を宣言しブラジル帝国を作りました。おかげで彼は解放者となり、ブラジルは大国として残ります。 市民王 Louis-Philipe le Roi Citoyen フランス王 ルイ・フィリップ 在位:1830-1848 フランス革命、王政復古ののち、旧体制のシャルル10世は7月革命で追われ、「フランスの王」ではない「フランス人民の王」オルレアン公ルイ・フィリップが国民の歓呼の中で即位します。でも「ブルジョアの王」だとバレて追われてしまったとな。 このページを書き始めた時は、全部についてまとめる気はなかったのですが、何だか面白くなって55人+1人全部を、佐藤さんは4ページに、こちらはほぼ2行にまとめてしまいました。後で読みかえした時面白そうだな。 とはいえ思うのは、やっぱり佐藤賢一さんの歴史ノンフィクションって面白い。ちょっと自分の考える方向と違うところがあって、それがまたいい。(2025/11/15) 読書メーターの記録より 読了:2025/11/13 |
|||||||||||

