 トップへ戻る  読んだ本の分類 |
|
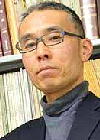 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |
|---|---|---|---|
| S158-001 | チンギス・カン | 新たな視点で見直すチンギス・カン像 | |
 |
|---|
| 管理番号:S158-001 | 51 伝記・一代記・評伝 |
出版社:中央公論新社 | |||||||
| 書名:チンギス・カン | “蒼き狼”の実像 | ISBN4-12-101828-1 C1222 | |||||||
| 英題:Chinggis Khan(2006) | |||||||||
| 中公新書 1828 | 価格:760Yen | ページ数:248P | 本のサイズ:新書 | ||||||
| 初版発行:2006/1/25 | 購入:2022/8/9 | ||||||||
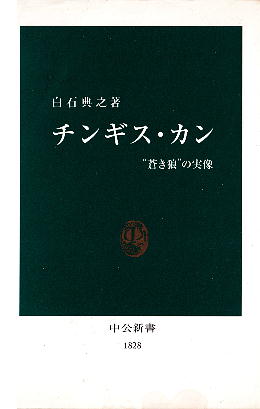 はしがき と題された文はこんな話から始まります。 はしがき と題された文はこんな話から始まります。
「 そもそも「カン」とは、ユーラシア北方の草原地帯にいたトルコ系・モンゴル系遊牧民族が使っていた称号で、国の〝王〟や部族〝長〟などの意味だったそうです。それに対し「ハーン」という称号があって、それは「カン」より上の唯一無二の君主を指す言葉であり、中国で言う〝皇帝〟と同義とされています。元は「カガン」という発音だったそうですが、13世紀ごろから「カァン(カーン)」となり、「カン」と同じような発音の変化があって「ハーン」となったのだとか。 彼の生前の時点では「 モンゴル族の源流について、『元朝秘史』はこのように記述しています。
この漢字音写本の『元朝秘史』を邦訳した 中国の史書においてモンゴルの祖先の姿が描写されたのは、8世紀に遡ります。 唐の歴史をまとめた『 モンゴル族は、トルコ民族との争いを避けてアルクネ この眇たるモンゴル族が、四世紀にわたる雌伏の期間を経て、気候変動や中国その他周囲の王朝の変遷などの影響を受けつつ徐々に西進し、統一へと向かいます。 12世紀からの金との抗争までの歴史を、モンゴル各部族の勢力範囲の変遷と共に「鉄」の産地と比較対照しています。気候による食生活の変遷と共に、地下資源も彼らの盛衰の要因と捕らえているところが興味深い。 カムク・モンゴル国の君主の末裔としてテムジン、のちのチンギス・カンは生まれますが、彼の出生の秘密とか名前の由来とかの疑問は別として、テムジンという言葉には当時のモンゴル語で「鍛冶屋」という意味があったそうな。彼の生涯が鉄にいろいろな意味で関係したことを考えると、面白いとのこと。 チンギスの生年には諸説あるそうです。西暦に直すと、『蒙韃備録』では1154年、『集史』では1155年、『元史』では1162年、『聖武親政録』では1167年となっています。一般的には『元史』の説が有力で、これに従うと没年の1227年から数えで享年66という事になるのだそうな。これに対し、フランスの有名な内陸アジア史学者ポール・ペリオ氏は1167年を支持しており、この方が多くのチンギスの事績にあうと考えたそうです。 チンギス13歳の時に、モンゴル族の族長であった父イェスゲイは仇敵であるタタル族に謀殺されます。その後、弱小の家に転落したチンギスの家は辛酸を舐めることになるのです。
雌伏の時代のチンギスの家は、たしかに力もなく貧しかったが、それなりの放牧地を持つ部族の長であったようです。妻ボルテを迎える前の遊牧可能な土地面積は500平方キロメートル程度、結婚後にはその倍になっていました。 チンギスの名が東西の史料に初めて出たのは、金と共にタタル族を殲滅したウルジャ河(1196)の戦いです。 この戦いにおいてチンギスは『元朝秘史』によるとケレイト部族の君主トオリルと語らって金に助力し、父の仇であるタタル族を攻めて大きな戦果を上げたとされます。この戦勝は金の皇帝章宗の命で指揮官として遠征した この「九峰石壁戦勝碑」は戦いの後に金とモンゴルとの境界線をあきらかにするために設置され、ヘルレン河の南岸に今も残ります。この碑石は二基あり、女真字の方はモンゴルの言語学者によって紹介されていますが、漢字碑石を発見したのは1991年、日本を代表する北アジア考古学者の
この二つの碑文のどちらにもチンギスに関する記述はなく、モンゴル側が書くほどチンギスの功績は大きくなかった可能性はあるそうです。しかし金の皇室の一員である完顔襄の立場では、公式文書となる碑文に異民族の助けによって勝利したと書きたくはなかったのかも。とはいえテムジンは、トオリルと共に完顔襄にその功績を認められ官爵「 この百人隊長という言葉で、当時のチンギスの勢力を知ることができます。動員可能な兵が百人いるということは百戸の配下を持つということであり、おおよそ300人程度を支配していたというのが妥当ではないか、と筆者はいいます。
こうしてチンギスは、金の勢力下で勢力を伸ばしますが、モンゴルの中でも金に属さないグループとの対立が激化し、ついに1201年、コイテンという高原で対決しました。この戦いでモンゴル族の東部グループを撃破しますが、チンギス自身も首に毒矢をうけるなど苦戦しました。 この戦いで、敵方の東部グループを率いたジャムカという人物について、著者はこんなことを書いています。
ジャムカについては、チンギス・カンに関するいろいろな話の中で出てくる人物で記憶があります。Wikipediaでも実在の人物として描かれています。それが、お話を盛り上げるための架空のキャラクターかもね、とは。 筆者の視点は面白い。 1206年、チンギスの生まれ故郷オノン河上流にモンゴル族の有力者が集まり、最高意志決定会議「クリルタイ」が開かれます。その席上で、チンギスは「
この一代記は、チンギスが大帝国を作った後、その後継者の話へと進みます。
 とチンギスが評した四人の息子たちの中で、ウゲデイがチンギスに後継者として指名されますが、チンギスの死後混乱が起き、最終的にウゲデイがカンの、そしてカアンの地位を継ぎますが、子孫たちに遺恨が残ります。 とチンギスが評した四人の息子たちの中で、ウゲデイがチンギスに後継者として指名されますが、チンギスの死後混乱が起き、最終的にウゲデイがカンの、そしてカアンの地位を継ぎますが、子孫たちに遺恨が残ります。ウゲデイについては、オゴデイという名で知られていますがオゴタイという呼び方もあります。モンゴル語の発音の問題です。これは、第五代 この評伝は、時代的にはチンギスの死後ウゲデイが父を越えようとして無謀な戦いと兄弟の軋轢を残して没するまで、そして第5章でチンギスの死後の忘却、伝説化、調査、歴史再構成の歴史が語られ、そして
なるほどね。 研究書の集大成のようなものなのですが、実に面白い。 この本は、いつか余裕ができたら、じっくり読み直して再び楽しみたい評伝・一代記のひとつです。(2025/2/20) 読書メーターの記録より 読了:2022/9/21 |
