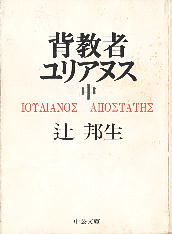トップへ戻る 作家/分野 一覧 |
|
 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |
|---|---|---|---|
| T003-001・002・003 | 背教者ユリアヌス (上・中・下) | キリスト教に背を向けたローマ皇帝の物語 | |
 |
Ver. 3.03 |
|---|
| 管理番号:T003-001、002、003 | 32 歴史小説・西欧史 |
出版社:中央公論社 | |||||||
| 書名:背教者ユリアヌス 上 | ΙΟΨΛΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ | ISBNなし | |||||||
| 中公文庫 A48 | 価格:380Yen | ページ数:396P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:74/12/10 第4版:76/2/15 | 購入:1976/7/28 | 表紙・扉:白井晟一 | |||||||
| 書名:背教者ユリアヌス 中 | ΙΟΨΛΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ | ISBNなし | |||||||
| 中公文庫 A48-2 | 価格:360Yen | ページ数:364P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:1975/1/10 | 購入:1976/7/30 | 表紙・扉:白井晟一 | |||||||
| 書名:背教者ユリアヌス 上中下 | ΙΟΨΛΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ | ISBNなし | |||||||
| 中公文庫 A48-3 | 価格:440Yen | ページ数:440P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:1975/2/10 | 購入:1976/7/30 | 表紙・扉:白井晟一 | |||||||
※太文字にしたのは、この小説の中での表記です。ローマ人の名前は長いので、小説的にはわかりやすくするためか短くしています。 30歳そこそこの年齢で死に、しかも皇帝在位は2年にも満たない。それだけ見たら、あの時代にたくさん現れた簒奪皇帝の一人、と思っても不思議はない。 後世呼ばれた二つ名が「背教者」、つまりキリスト教の教えから逃げ出し、かつての異教を復活させようとした復古思想の人、となると、単なる石頭の守旧派かとも思えます。しかも哲学者であったとなると、その確信はますます強くなるもの。 しかし、そんな人物を描いて辻邦生さんがこの本で毎日芸術賞を取ったはずがない。 実はこの人は、不幸な生い立ちの中で育ちますが、希有な才能と克己心、そしてバランス感覚に富んだ理想主義を発揮し、短い生涯ながらその名を未来に残した人だったのでした。  ユリアヌスは、大帝と言われたコンスタンティヌス1世の異母弟ユリウス・コンスタンティウスとその妻バシリナの間に、AD331年あるいは332年に生まれます。337年にコンスタンティヌス帝が死ぬと、その時存命であった大帝の長兄コンスタンティヌス2世、次弟コンスタンティウス2世、三弟のコンスタンスの三人が正帝となり、従兄弟に当たるダルマティウス、ハンニバリウスが副帝となって帝国は分割統治されました。 ユリアヌスは、大帝と言われたコンスタンティヌス1世の異母弟ユリウス・コンスタンティウスとその妻バシリナの間に、AD331年あるいは332年に生まれます。337年にコンスタンティヌス帝が死ぬと、その時存命であった大帝の長兄コンスタンティヌス2世、次弟コンスタンティウス2世、三弟のコンスタンスの三人が正帝となり、従兄弟に当たるダルマティウス、ハンニバリウスが副帝となって帝国は分割統治されました。このときの政変で、帝弟ユリウスは家族とともに暗殺されます。命じたのは政権の掌握を策した正帝コンスタンティウス。 当時ユリウスには、一緒に殺された二人の息子以外に、幼い息子たち、コンスタンティウス・ガルスとユリアヌスがいました。彼らは年少のため命は取られずにすんだのですが、そのまま342年より約6年間軟禁状態と。 340年、コンスタンティヌス2世は弟コンスタンスとの抗争の末に殺害され、その後コンスタンスは西方の正帝として政情は一時安定しますが、将軍マグネンティウスの反乱によって殺されました。 この状勢を見てコンスタンティウス帝は、兄弟のうち兄ガルスを副帝に任じてマグネンティウスを討伐しましたが、猜疑心の強いコンスタンティウスはガルスの忠誠度を疑い、354年に処刑します。翌年ユリアヌスを副帝に登用して西方を担当させますが、ガリアの兵を東方の守りにつけるために抽出しようとしたため、ガリア兵がこれに反発してユリアヌスを皇帝として推挙します。 困惑したユリアヌスはコンスタンティウスに釈明するためにコンスタンティノポリスにむかいますが、その途上で自分を征伐するために進撃していたコンスタンティウスが頓死し、死に際に自分を後継者に任じたことを知ることに。 単独帝となったユリアヌスはさまざまな改革を行いますが、ペルシア遠征の途上で敵兵から受けた傷がもとで363年に死にました。 凄惨な経歴を持った人でありながら、立志伝の人ではない。能動的に生きたと言うより、常に運命の中に押し流される人生だったといえばいえる。その彼がなぜ、「ローマ帝国衰亡史」においてギボンに、「ローマ人の物語」において塩野七生にあれだけページ数を割いて描写されたのか。このような長大な小説の主人公となったのか。 この人物を描写するために、作者はたくさんの人々をユリアヌスという人物の周囲に配置します。 まず登場するのは彼の生母、バシリナ。彼女は皇弟ユリウスの後妻としてユリアヌスを生みます。太陽のような子供産む、と予言されてもそれを心の中に秘めたまま、産後の肥立ちが悪化して若くして逝きます。 そして父、ユリウス。実直に兄を支えながらも、兄の体に流れる卑しい女の血のためとしか思えない粗野や軽佻さ、奇妙な臆病さにいらだたしさを感じています。
ニコメディアの司教エウセビウス。彼はコンスタンティヌス大帝の遺言と称するものをもとに、キリスト教をローマの宗教とすることに尽力すると共に、ガルスとユリアヌスの少年時代を支配します。
兄ガルス。末弟と同じように不幸の中で生きた少年は、どこかふてぶてしさと酷薄さ、そして利己的ななにかを持った青年となります。年少のユリアヌスをかばうことで衛兵たちにある種の尊敬を得ますが、彼らを監視する宦官オディウスとはしばしば対立することに。 しかしまさか、幽閉の彼のもとに皇帝コンスタンティウスその人が現れ、皇妹コンスタンティアと結婚のうえ副帝に任ぜられるとは。 そして、彼なりにその職務に邁進していたはずなのに、いつの間にかコンスタンティウスの猜疑心と宮廷内の陰謀で反逆者の汚名を着せられるとは。
しかし354年、彼は一方的な裁判のすえに処刑されます。ガルスにどんな責任があったというのか。 ユリアヌスの周囲に現れる、彼をひとりの人間としてつきあってくれる人々たち。まず、軽業師のディア。
宮廷では四面楚歌のユリアヌスに味方ができたのは偶然なのか。
そして、ヘレナ。コンスタンティウスの末妹。30過ぎの、存在感が薄い処女。
皇帝コンスタンティウス。彼は良い為政者だったのか。少なくともその猜疑心と優柔不断によって何度か国家を危機に陥れましたが、平時の統治能力はともかく、危機に当たっての判断は適確であったかもしれない。遅きに失することはあったものの。 その彼が、帝国の東方と西方、両方が危機に瀕しているとき、ある決断を下す。
エウセビアはそれをどう見ていたのか。 このあたりの描写は、秀逸。こんな歴史もあったのかもしれません。 為政者としても軍人としても指揮官としてもまったくのど素人であるユリアヌスは、ガリアで苦闘します。
ゾナス。ユリアヌスがはじめて学問に志したときから、最初その正体を知らないまま学友となった青年。そして彼が皇族であり、副帝となったのちも親友でありつづけた男。東方のエデッサでかつて学友ケルススにであい、こんな会話を交えます。
陰になり日向になりユリアヌスをかばっていたエウセビアが360年に病死すると、送りこんだ手の者である将軍たちがその実績から罷免されていく情勢の中で、自分たちの地歩が崩されていくことに危惧を抱いていた宮廷内にいる宦官オディウス、侍従長エウビウスなど反ユリアヌス勢力は、自分たちが生き残るために次の陰謀を進めることに。彼らの長い手と、コンスタンティウスの猜疑心がぶつかったその先にあったものは、なんだったのか。 とある夜更け、ガリア軍の書紀ガムスが若い騎兵隊長ネヴィッタに、皇帝からの新しい指令がユリアヌスに送られたことを伝えます。法で禁じられていた、ガリアの兵をアルプスの向こう連れて行くことを命じたもの。
苦悩のすえ、ユリアヌスはこの命令に従うと決断します。しかし、彼に心酔するガリアの将兵は、承諾しない。 隊長ヨヴィウス、ネヴィッタらの元に集まったガリアの兵は決起し、ユリアヌスを皇帝の名で呼び、逡巡する彼に詰め寄る。
ローマ皇帝とは、そもそもが兵士が自分たちの ここから、皇帝ユリアヌス、短命な、キリスト教に背を向けた守旧派の哲学者皇帝の物語が始まります。 彼はさまざまな宮廷改革、国家改造、軍制改革を行います。その情熱と実績は、さまざまな批判の言葉を述べつつも、エドワード・ギボンが、塩野七生が、そしてさまざまな歴史家が高く評価しています。 しかし、彼の寿命はそこからほんのわずかで絶えたのでした。どの神かはわからないのですが、彼を支配した神は、彼に寿命をそれだけしか与えませんでした。 この希有な人物の生涯を、辻邦生は、実に淡々と、その生から死まで描いています。 ああそうか、こういう書き方をしていたんだ。長い文章だけど、それぞれの描写が優しいね。 彼のわずかな治世があとどのくらいあれば良かったのか。 ルイ14世の、漢の武帝の、ヴィクトリア女王の、それぞれの治世の最後の20年を彼に与えられなかったんだろうか、などと夢想します。名君と言われた君主の、醜悪といってもいい老年時代の何年かをユリアヌスに与えられたら、どれだけのことを成し遂げられただろう。 死児の歳をかぞえる愚であることは百も承知で、そんな事を考えました。 この本で作者は、ユリアヌスの遺骸がメソポタミアの砂漠で皇帝旗に包まれたところで筆を置きます。 そのあと、結果として無謀だった遠征からローマ軍が帰還するまでに舐めたさまざまな苦難も、後継者となった皇帝ヨヴィアヌスの無残な運命も、そのあとの時代の流れも、何も描きません。 ユリアヌスの、残酷な言い方ですが結果として何もできなかった人生を描くには、それで充分なのかもしれません。(2016/12/25) 読書メーターの記録より 読了:上巻 2016/10/12 中巻 2016/10/14 下巻 2016/10/21 |