 トップへ戻る  読んだ本の分類 |
|
 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |
|---|---|---|---|
| T098-001 | 物語としての旧約聖書 | なるほど、こういう旧約聖書もありか | |
 |
|---|
| 管理番号:T098-001 | 56 宗教史・文化史 | 出版社:NHK出版 | |||||||
| 書名:物語としての旧約聖書 | 人類史に何をもたらしたのか | ISBN978-4-14-091283-6 C1314 | |||||||
| NHKブックス 1283 | 価格:1800Yen | ページ数:352P | 本のサイズ:130×180SC | ||||||
| 初版発行:2024/1/25 | 購入:2024/4/24 | 画:「ミケランジェロがシスティーナ礼拝堂に描いたアダムとエバ」 (写真提供:ユニフォトプレス) |
|||||||
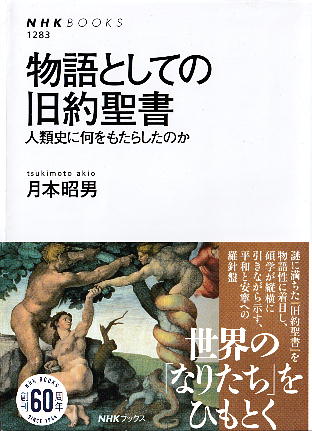 「旧約聖書」とは、キリスト教の立場でいうと、「新約聖書」と共に宗教的な聖典とされる書物。 「旧約聖書」とは、キリスト教の立場でいうと、「新約聖書」と共に宗教的な聖典とされる書物。ユダヤ教的には新約聖書は聖典ではなく、いわゆる旧約聖書はミクラーあるいはタナハと呼ばれます。 キリスト教は、ユダヤ教世界でいずれ登場すると予言されていた救世主──ヘブライ語でメシア、ギリシア語でキリスト──がついに現れ、ユダヤ人だけでなく世界を救うことになった後の教義です。その考えに基づき、キリストが生まれた後の歴史、教え、手紙類などを集め、新たな神との契約、つまり新約聖書を作り上げました。 ユダヤ教世界では、キリストはまだ出現していません。 イスラム教の人々にとっては、旧約聖書を経典とし、源流は同じ神を崇拝する一神教ですが、その形態。教えは異なりますが、旧約聖書の物語や教えはある程度引き継がれています。 この本は、旧約聖書を、宗教性をある程度廃し、思想と信仰の特色をさぐることで人類の宗教史に計り知れない影響を及ぼした秘密をあきらかにしようという試みです。 まず語られる 第1章 天地創造 人間と自然の調和を願って の最初は 一 天地創造と七曜制 です。 旧約聖書の第一書である創世記の1章から11章は神話的な物語群です。天地創造から始まってエデンの園の物語があり、その息子たちによる兄弟殺し、ノアの洪水、バベルの塔へと続く物語は「原初史」と呼ばれます。ここから、古代イスラエルの民の自然観、人間観、文明観などが読み取れるようです。 まず天地創造の中で、六日で天地万物を創造し七日目には安息を取ったという話。古代イスラエルで七曜制が確立し七日目に労働が禁じられる律法が定まったのは、BC6世紀のことでした。
三 被造物としての自然 の中で、まったく相容れない日本神話との関連が語られます。類似ではなく相違ですが。
のちにユダヤ教はユダヤの人々「だけ」の宗教になりましたが、旧約聖書においては人類すべての源が描かれ、だからこそキリスト教はイスラエル=ユダヤという民族的枠組みを超えて世界宗教となり得たのだとすると、感慨深い。 その他、この本はさまざまな方向から旧約聖書を、その矛盾点や原典となった書籍の多彩さ、さまざまな思想、批判的精神と多様性、描かれる歴史の奥に見えるもの、などをわかりやすく展開してくれます。 旧約聖書をキリスト教徒としてではなく、歴史研究家、思想研究家という視点で解説した本、と言えばいいのかな。 アダムの息子カインとアベルから始まる兄弟間の確執など、旧約聖書で描かれる始祖の姿には、さまざまな人間くさい美醜が見て取れます。楽園を追われた人々が時代を経て集まり、町を造り、バベルの塔事件で再び四散します。そしてノアの方舟事件で選ばれた民以外、そしてカインの末裔も滅びますが、このへんは歴史物語としての整合性に問題がある、と指摘されます。たしかにね。 そして久しぶりに読んだあの「理論」。ノアの二男ハムがノアに失礼をしたために、ノアは怒ってハムの息子カナンを「兄弟たちの奴隷になるがよい」と呪います。のちにアフリカの諸語は「ハム語」と類別され、それゆえにアフリカ系の人びとは奴隷としてよいという解釈に結びついたのだ、という理屈に至る。 宗教観を利用した西欧文明の理不尽さ・醜悪さを再確認。牽強付会と思った人もいたんだろうになぁ。 そして、最初の偉大な「父祖」でありユダヤ教・キリスト教・イスラム教の「信仰の父」、アブラハムとその子孫たちの物語。神に愛されたアブラハム(その当時は「アブラム」と名乗っていましたが)は、カナンすなわちパレスティナのすべてを与えると約束されます。そこには三つの約束があるという。 一つ目は、カナンの地は永遠に彼と彼の子孫に与えられること。 二つ目は、彼の子孫は「地の塵のように」増えていくこと。 三つ目は、地上のあらゆる民族を、彼と彼の子孫が祝福することになるだろうということ。 アブラハムと彼の子や孫たちは、清廉潔白であり続けた訳ではなく、さまざまな悪行を行ったこともありました。しかしここで、その子孫であることでアイデンティティを保とうとした弱小なユダヤ民族は、この約束を記録し記憶することによって何千年もの間生き抜き、現代まで強固な信仰を残しています。 そしてその思想をある程度継承したキリスト教とイスラム教は、第三の約束に従って世界にその教えを広げました。 驚くべきもの、かな。 その恩恵に浴しなかった異教徒の地に住んでいても、これは驚くべき、と評せざるを得ない。 この世界観はどういうことか。ここで、第8章 カナン定住 のなかに興味深い一節があります。 時代が下って、アブラハムの孫ヤコブが息子ヨセフのつてでエジプトに移住し、運命の変転を経てそのエジプトを脱出してカナンの地に戻ってきた時代のこと。カナンの地にはすでに多くの都市国家が造られ、イスラエルの民がここに定住するためには、平和的に居場所を見つけるか戦って先住民を駆逐しなければなりません。 ここで、旧宅聖書の記述は奇妙な矛盾を見せるのです。 まず、エジプト脱出の立役者モーセの死後そのあとを継いだヨシュアを中心にしたヨシュア記では、有名なエリコの戦いを含め、武力による制圧の歴史が語られます。ヨシュアの指揮のもと、最終的にペリシテの地を除くカナン全域をイスラエルの民が支配し、12の氏族がくじを引いてそれぞれの土地の境界線を定め、改めて神と契約を結びます。 もうひとつは、ヨシュア記のあと、ヨシュアの死後から預言者サムエルの時代までを描いた この士師記の描写によれば、イスラエルはカナンの人々を征服することはできていません。ヨシュア記によれば征服されたとされるタアナク、ドル、メギドといった町々が、その地域を分配された氏族が我がものとしていないとされていたり、ダン氏族はアモリ人によって山地に追いやられ、平地に下りることができなかったなどとも書かれています。 どちらが正しいのか──については、むろん多くの研究があり、さまざまな見解と解釈があります。 カナンの地は軍事的に占領されたのか、平和的に浸透されたのか、というのが大きく分けて唱えられていた論。 イスラエルの考古学者によって、画期的な研究がされます。彼らはパレスティナのほぼ全域を調査して小さな遺跡の分布を踏査した結果、BC12世紀から10世紀にかけて人口が数十名から数百名程度の集落が急激に増加したことをあきらかにします。そしてこれが、最初期のイスラエルの民の居住地であったと結論したのでした。 そこから考察・推論を重ねた結果(詳細を省略しますと)イスラエルの民はその時そこで生まれたのではないか、という仮説が登場したのでした。 すなわち、長老アブラハムからエジプト脱出までのすべての話が、幻の建国神話だったのではないか、という恐るべき推論。いつの時代の誰が行ったのかはわかりませんが、そのような建国神話を造ったのだとしたら。 これは、まったくの仮説です。いつの日か新たな史籍・史料が現れてもっとはっきりするまでわかりません。 しかし、と論を進めてみます。 仮にそうだとすれば、旧約聖書とは、イスラエルの民のための書であると同時に、カナンつまりパレスティナを中心としたその時代の全世界、すなわちエジプトから中近東、メソポタミアそしてその周辺部すべての世界の起源まで書した歴史書を含むのだ、という理屈が成り立ちうるのです。 面白い。 人類史の、中世・近世を経て、旧約聖書によって育てられた三つの宗教は、少なくともそのうちの二つは、世界宗教となるために大きく変貌し、教えを洗練させて勢力を広げます。その過程で排他的な固陋さを発揮したり改革されたりしていき、現在に至っています。 旧約聖書が、その母胎となるだけの大きさと人の目を引く魅力とを持っていたと思うと、恐るべきものと思うべきか。
著者はあとがきの中で、
そう、いろいろな意味で難しい旧約聖書を、ここまできれいにまとめたとは。 今後も、新しい解釈はいくらでも出てくると思います。 そんな中で、いまこの時点でこういう解釈に基づく『物語としての旧約聖書』が読めてよかった。(2025/1/29) 読書メーターの記録より 読了:2024/08/13 |
|||||||||