 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
 トップへ戻る |
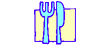 作家/分野 一覧 |
上橋菜穂子ページへ |
|||
| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |
|---|---|---|---|
| U004-016 U004-017 U004-018 U004-019 |
鹿の王 1 鹿の王 2 鹿の王 3 鹿の王 4 |
謎の疫病と、ヴァンとホッサルという二人の男 この災厄の裏にあるものはなにか 黒狼病とはなんだったのか 終幕。<鹿の王>とはなんだったのか |
|
| U004-020 | 鹿の王 水底の橋 | 二つの医術の相克と、歴史を動かしたもの | |
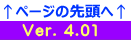 |
|---|
| 管理番号:U004-016 | 17 ファンタジー類 | 出版社:KADOKAWA | |||||||
| 書名:鹿の王 1 | 鹿の王 | ISBN978-4-04-105489-5 C0193 | |||||||
| 2014年9月 KADOKAWAより単行本として刊行 | |||||||||
| 角川文庫 う25-1 20369 | 価格:640Yen | ページ数:304P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2017/6/25 10版:2020/4/10 |
購入:2024/5/14 | カバーイラスト:ヤマモトマサアキ カバーデザイン:高柳雅人 |
|||||||
 いつか読まなくてはと思っていたシリーズでしたが、コロナ禍が一段落して再び注目されたこともあり、挑戦することにしました。そうか、こういうお話だったんだ。 いつか読まなくてはと思っていたシリーズでしたが、コロナ禍が一段落して再び注目されたこともあり、挑戦することにしました。そうか、こういうお話だったんだ。火薬というものが存在しなかった、いまの世界を規準とするとおおよそ14〜16世紀あたりのテクノロジーを背景にした、ファンタジー世界が舞台。 魔法的なものはありますが、パーティーだのダンジョンだの経験値だのスライムだのが出てくる、コンピュータRPG設定におんぶしたみっともない十番煎じものではありません。上橋菜穂子さんの構築する、緻密で深い背景を持った正統派ファンタジーです。(まァ正統派の定義については私論ですので論議はしませんがw) 主人公は、二人。 一人は、ヴァンという壮年の男。 東から勢力を伸ばす 一族を失ったのち愛する妻と子が疫病で去られたヴァンは、<独角>の頭としてその策を引き受けます。彼には失うものは何もない。 しかし、そこで事件が起きます。事件と言うには超自然的なできごと。 夜遅く、 普通人をわざわざ襲わない山犬が、なぜ襲ってきたのか。 そしてなぜ、噛んだだけで去っていったのか。 疑問を解決する暇もなく、次に起こったのは奇妙な病の蔓延。胸が軋むような咳をして、次々と死んでいきます。 しかしヴァンだけは死にませんでした。八日目にすさまじい頭痛と悪寒に襲われますが生き残ってしまいます。しかも、聴力とか膂力とかがとんでもなく発達したようで、音により敏感になっただけでなく、奴隷たちを拘束していた太い鎖を引きちぎってしまったのでした。 いったい何があったのか。 わからぬまま、ヴァンは地下深くの坑道から地上に這い上がります。そこで見たものは、死屍累々の光景と、ただ一人母親に守られて生き残った幼女だけ。彼はその幼女を連れて岩塩鉱山を脱出し、知っている街に向かいます。その途中で出会ったのは、足を痛めて歩けない旅の男。 いろいろあってヴァンは、幼女をユナ( もう一人の主人公は、ホッサルという青年。まだ26歳。 彼が登場したのは、ヴァンが逃亡した後の岩塩鉱山。大量の死者が出た緊急事態に、その原因を探るべく与多瑠に付き従って現れ、実質的に指揮を執ることになります。 オタワル人は、アカファに国の支配を譲って背後にひっこんだ形ですが、さまざまな技術を持った人々であったため、医術だけに留まらず土木、建築、鉱山開発、冶金などにおいても高い技能と実績を持ち、アカファが東乎瑠帝国に併合されたのちも、多少うさんくさく思われつつも支配されながら敬意を払われ、恐れ忌まれながら重用されていたのでした。 リムエッルとその孫ホッサルは、医術においてその筆頭と言っていい存在。 ホッサルは、賭け闘士だったマコウカンを従者としてこの事件に取り組むのですが、現場に入るや否やまずこの病を、感染力の強い特殊な疫病、 ホッサルの従者というかパートナーであるミラルがあとで、状況が理解できないマコウカンにこう説明しています。
読んでいる読者としては、これはきわめて「先進的」な考えであり応援したくなりますね。 主人公格ではないけれど、もう一人気になる人がいます。 ホッサルがヴァンの足どりをたどろうとしたとき、案内として雇われた、サエという跡追い狩人の女。娘、と言われていますが30を過ぎた落ち着いた感じの人。すご腕には見えなかったけれど、山に入ればあらゆる事ができる女狩人。 強靱な精神と技術、そして穏やかで優しい風貌。バルサをちょっと思いました。 山で狼の群れに襲われたとき、彼女は断崖から落ちて行方不明となります。そのまま死んでしまったのか。 この物語は、まだ序盤。 紆余曲折がありますが、この巻では互いに出会うことはありません。 出会えばなにかが燃えあがる可能性を見せつつ、この巻は終わります。 あいかわらず、上橋さんはいいものを書きますね。見事だ。(2024/8/14) 読書メーターの記録より 読了:2024/7/29 |
||||||||||
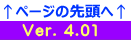 |
|---|
| 管理番号:U004-017 | 17 ファンタジー類 | 出版社:KADOKAWA | |||||||
| 書名:鹿の王 2 | 鹿の王 | ISBN978-4-04-105508-3 C0193 | |||||||
| 2014年9月 KADOKAWAより単行本として刊行 | |||||||||
| 角川文庫 う25-2 20370 | 価格:640Yen | ページ数:336P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2017/6/25 5版:2017/10/30 |
購入:2024/5/14 | カバーイラスト:ヤマモトマサアキ カバーデザイン:高柳雅人 |
|||||||
 三つの章から構成されます。 第四章 これはホッサルの章。「承前」という言葉(蛇足ですが、前の文章を受けた続き、という意味です)でわかるように、前巻の終わりが 第四章 黒狼病 の 一 御前狩り を受けて 二 黒い犬たちの襲来 で始まります。これは、元々「鹿の王」は二分冊の本で、それを文庫化に当たって四分冊としたために起きた切れ目。 東乎瑠帝国のアカファ領主一家と招待されて同行する帝国に併合されたアカファ王の一家が、その他の近習たちと鷹狩りを楽しんでいる席に、黒い犬たちの群れが襲いかかる場面から始まります。 さすがに歴戦の戦士たちですので、女子供を庇って応戦しますが、犬たちはいきなりなにかの合図を聞いたように去っていったのでした。 ホッサルの言葉で噛まれた人を急いで集めて治療しますが、彼が作った
しかし心を決して治療に当たるホッサル。祭司医長としてもその医療行為自体を否定はせず、 アカファ人は黒狼熱では死なない、という奇妙な噂が蔓延し、このままでは種族間の争いになりそうな気配があるなかで、ホッサルは病を治療する新しい仮説を見つけます。 第五章 < 流行り病が流行っているらしい、という噂がヴァンが身をよせているオキ氏族の家にやって来ます。「狂犬ノ病」ではなく「 この風聞は、真偽のほどは別として、東乎瑠帝国への恨みが残るアカファ人にとっても、いまだに心服しきっていない内部の旧敵に困惑する東乎瑠にとっても、心に引っかかってしまうもの。これが内紛の元になるのか。 風評被害とは、かくも恐ろしい結果をもたらしうるもの。 同時にヴァンは、かつて岩塩鉱で謎の山犬に噛まれたために起きた身体の変調が表に現れてきます。自分だけではない。
悩むヴァンの前に、< <谺主>の里で出会ったのが、サエという女性。無論ヴァンは知りませんが、ホッサルの道案内として雇われ、川に落ちて行方不明になっていたあの女狩人でした。 このサエは、二人の未来にどう関わるのか。 そして<
第六章 「アカファの呪い」の意味を考えるホッサルら。このアプローチがあまりに「現代的」であることにとまどいを覚えますが、でないと疫病への対応を考えるホッサルのお話は成立しない。<多脂のネズミ>という、現代の成人病あるいはアルツハイマーへの治療法の試みもまた、同じか。< そのホッサルたちが調べたことのひとつ。かつてアカファ王国に住んでいたユタカ地方の三氏族の一つ、<
今起きているこの災厄は、誰かが人為的に起こした策略なのか。では誰が、なんのために、どうやって。 どう防げるのか。 壮大な物語は、まだ道半ばです。(2024/9/18) 読書メーターの記録より 読了:2024/9/14 |
|||||||||||||||
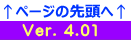 |
|---|
| 管理番号:U004-018 | 17 ファンタジー類 | 出版社:KADOKAWA | |||||||
| 書名:鹿の王 3 | 鹿の王 | ISBN978-4-04-105509-0 C0193 | |||||||
| 2014年9月 KADOKAWAより単行本として刊行 | |||||||||
| 角川文庫 う25-3 20426 | 価格:640Yen | ページ数:272P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2017/7/25 | 購入:2024/5/14 | カバーイラスト:ヤマモトマサアキ カバーデザイン:高柳雅人 |
|||||||
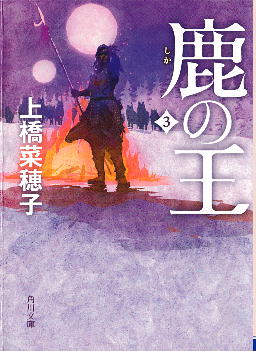 この本から、二人の主人公、ヴァンとホッサルの行動が同じ章で描かれるようになります。二人の出会う道筋という事になるのかな。 この本から、二人の主人公、ヴァンとホッサルの行動が同じ章で描かれるようになります。二人の出会う道筋という事になるのかな。第七章 <犬の王> 前巻の最後、さらわれたユナを追う旅の中で出会ったサエがアカファ王の密偵であり、アカファ岩塩坑から脱走した奴隷を追えと命ぜられていたことを知ったヴァン。彼女がなぜ自分とユナに関心を持っているのかがわからぬまま、彼女の残した痕跡を追ういます。 そして出会ったのは、< 姿を消したサエは、どれだけ事情を知っていたのかわからないが、なにか心に記するものがあったらしい。 そこで聞いた<キンマの犬>の話。なぜヴァンに注目するのか。 <犬の王>と名乗る老人は、何者か。 第八章 辺境の民たち ホッサルの従者であるマコウカンから始まります。彼の氏族はなにやらいわれがありそうです。そもそも彼ら主従が< トゥーリムは言います。ホッサルのようなオタワルの人にとって そのため、火馬の民の族長がアカファの岩塩坑に放ったたった五頭のキンマの犬が、あらゆる人々を罹患させて殺したことがどういう事になるか、わかっていたのだと。そしてその先にあるもの、起こることに戦慄したのだと。 しかも、あの岩塩坑から二人だけだが死なない人がおり、それがホッサルが追っているものなのです。 それだけではすまなかった。< ホッサルたちに発見されたユナ。<火馬の民>からサエを連れて脱出するヴァン。この先、彼らの運命はどこで交錯するのか。 第九章 イキミの光 ミラルが顕微鏡を持って来た、という話に、え? と思ったのですが、のちにこの世界、肉眼では見えない細菌を研究できるレベルにまで光学系の機器が発達しているという設定があるとわかります。しかも、その細菌よりはるかに小さい、細菌濾過機を使ってもくぐり抜けてしまう<極小病素>というものが存在することまで研究が進んでいたのでした。そして、細菌に対抗するために開発された抗細菌薬がそれに効かないことがわかり、アカファ岩塩坑の遺体から黒狼熱の病素がその<極小病素>であることが確認できたのでした。 地衣類からその<極小病素>を抑制する効果が確認されたので、 というくだりで、おや、この世界では青カビからじゃなかったのかと思ったけど、この世界の医学生理学の発達はむっちゃ早いな。 ミラルが疫病に罹患し、自分の治療薬を持ってこいと要求するホッサル。そこで驚くべきことが。 ホッサルが<極小病素>を抑制する新薬をミラルに処方したとき、ユナが、その薬が光っていてきれいだ、と叫んだのでした。 これはどういうことか。不意に現れた、ユナが「おちゃん」と呼ぶ男は何者か。 ついに、主要人物の運命が交錯します。さて、次巻でお話は終息するのか。(2024/10/7) 読書メーターの記録より 読了:2024/10/1 |
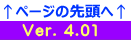 |
|---|
| 管理番号:U004-019 | 17 ファンタジー類 | 出版社:KADOKAWA | |||||||
| 書名:鹿の王 4 | 鹿の王 | ISBN978-4-04-105510-6 C0193 | |||||||
| 2014年9月 KADOKAWAより単行本として刊行 | |||||||||
| 角川文庫 う25-4 20427 | 価格:640Yen | ページ数:352P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2017/7/25 第11版発行:2020/3/5 | 購入:2024/5/14 | カバーイラスト:ヤマモトマサアキ カバーデザイン:高柳雅人 |
|||||||
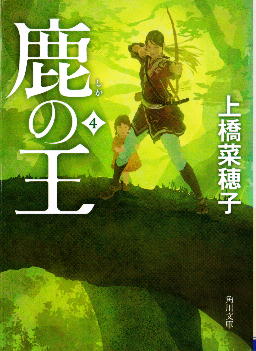 ヴァンとホッサルの、初めて顔をつきあわせて話をする場面から始まります。サエとミラルも共に。 ヴァンとホッサルの、初めて顔をつきあわせて話をする場面から始まります。サエとミラルも共に。互いの立場と思いを話すうちに、共感と同時に相容れないものもわかってくる四人。 <鹿の王>のこと。人の力では壊せない鎖をヴァンが引きちぎれた訳。薬が光って見えたユナと、嗅覚が異常に発達したヴァンの秘密。「裏返り」の意味。病に罹る者と罹らない者の違い。<病み済み>という言葉の意味。体の中にある、外来の病素と戦う兵士のこと。病の種を持っていながら病まない人、獣のこと。地衣類を食べる飛鹿。火馬の乳を飲んで育ったユナ。胎児のとき、人は指に水かきを持っていること。
そしてこの言葉、死後の救済を前面に掲げる「神の救い」に違和感を覚えた鐵太郎が宗教を離れた理由のひとつを説明しているような気がします。 いや、人の思いは人それぞれ。閑話休題。 この物語には、さまざまなテーマが入っています。 生理学、病理学、疫病と免疫と治療、政治、帝国の侵攻、被支配種族の思惑、民族の興亡、医学と神学の相克、民間伝承、誇りと自己犠牲、そして愛。 アニメ映画「鹿の王 ユナと約束の旅」では荒唐無稽に近いファンタジーで逃げていた超自然的な展開を、この原作ではじっくりと科学的なアプローチで、あり得べき世界を構築して描いています。映像ファンならアニメでもいいのでしょうが、この物語の意味を知りたければ原作の方がはるかに上です。 この物語には。支配された種族の反乱、というテーマが一本貫かれています。それに絡んでさまざまな政治的・軍事的な陰謀が進行しているのですが、その陰謀が、根が深い。 元は氏族の恨みだったものが、さまざまな要素で醸成されて膨れ上がり、複雑化し、一筋縄ではいかないものになります。
謎また謎の中で、ヴァンは考え続け、悩み続け、模索し続けます。 またホッサルも、帝国と支配された旧王国の狭間で起きる陰謀の中で葛藤します。彼の義兄トマソルの企んだもの、その助手であったシカンの思惑と悪意。 シカンという若者の、滅ぼされた民族の怒りと悲願を継承しようという思いについて、トマソルはヴァンに同意を求める。
独角は故郷を守るため死兵になった英雄じゃない、故郷を失い、許されるなら一刻も早く死にたいと思う悲しい戦士たちの事なのだ、と後でマコウカンに言いますが、彼でも理解できたかどうか。 <鹿の王>の説明がなされるのは、この巻の後半。 老いた牡の ひねくれ者だったヴァンの父は、かつて若く、大人への階段を上ったばかりのヴァンたち若者にこういったとか。
そのとき父はこういったのだとか。──それは、それが出来る者がやることだ、と。 敵の前にただ一頭で飛び出して、踊ってみせるような心と体を持った鹿だけが、できることだ。 そんな才を持って生まれなければ、己の命を全うできたろうに、なんと、哀しい奴じゃないか。 だが、運命が見えてしまったとき。ヴァンは悩み、迷う。そして問う。
終盤、山に去っていったヴァンの後を追おうという人々が現れます。 道を示すのは、ユナ。赤子から幼女、そして少女に成長しつつある彼女は、父として育ててくれたヴァンの居場所をつねに間違えない。そしてヴァンを慕う部族民のトマと 締めくくりはホッサル。まだまだ前途多難ですが、未来への道筋は出来たと心に期すものが。(2024/10/15) 読書メーターの記録より 読了:2024/10/11 |
||||||||||||||
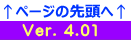 |
|---|
| 管理番号:U004-020 | 17 ファンタジー類 | 出版社:KADOKAWA | |||||||
| 書名:鹿の王 水底の橋 | 鹿の王 | ISBN978-4-04-109292-7 C0193 | |||||||
| 2019年03月 KADOKAWAより単行本として刊行・加筆修正して文庫化 | |||||||||
| 角川文庫 う25-5 22203 | 価格:800Yen | ページ数:464P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2020/6/25 第5版発行:2021/8/15 | 購入:2024/5/11 | カバーイラスト:ヤマモトマサアキ カバーデザイン:高柳雅人 |
|||||||
 題名は「鹿の王」で同じ世界の物語ではありますが、前回の話と直接繋がってはいません。とはいえ主人公となるのは前回の一人、滅びたオタワル王国の王族の末裔で医術師のホッサル。ヴァンは出てきませんので、あのあとサエとかユナとかとどうなったのかはわかりません。幸せになって欲しいけど。
題名は「鹿の王」で同じ世界の物語ではありますが、前回の話と直接繋がってはいません。とはいえ主人公となるのは前回の一人、滅びたオタワル王国の王族の末裔で医術師のホッサル。ヴァンは出てきませんので、あのあとサエとかユナとかとどうなったのかはわかりません。幸せになって欲しいけど。