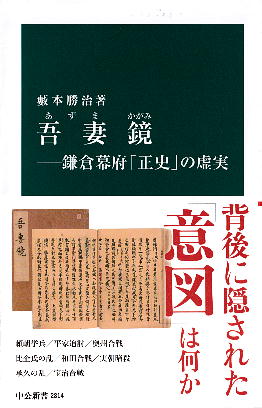 はじめに の冒頭、シロートむけには爆弾発言となる言葉が。 はじめに の冒頭、シロートむけには爆弾発言となる言葉が。
『吾妻鏡』は、鎌倉幕府の歴史を詳細に、かつ生き生きと記録するほぼ唯一のまとまった文献である。そのため、室町時代から江戸時代を経て現在に至るまで、根本史料として重要視されてきた。したがって、現在一般にイメージされる鎌倉時代の歴史像は、『吾妻鏡』に基づいて形成されてきたと言っても過言ではない。
たとえば、源 頼政の主導による以仁王の挙兵、以仁王の令旨(命令書)による頼朝の旗揚げ、頼朝に疎まれた義経の腰越状の訴え、二代目将軍頼家の暗愚、三代目将軍実朝の文弱、実朝暗殺事件の黒幕としての北条義時、後鳥羽上皇が倒幕を企てた承久の乱──。いずれも、『吾妻鏡』の記述をもとに形成され広く流布している。
しかし実は、これらはすべてフィクションである。近年の研究により、『吾妻鏡』の中で構築された虚構のストーリーの産物である事がわかってきた。(Pi) |
では、『吾妻鏡』とはなんなのか。
単なる「物語」なのか。だれかのプロパガンダなのか。
それだけなのか。
あるいは、戦後歴史学が提唱した、草深い東国の地に住む質実剛健な武士たちが腐敗した貴族社会を打倒して新たな歴史を作った、という階級闘争的な世界を具現する文書なのか。
しかし、そのような見方は、現在を肯定するための拠り所として過去を召喚し解釈する行為の産物であって、端的に言えば誤りである。
そこで本書は、歴史学の進展により明らかになってきた鎌倉時代の実像に照らすことで、『吾妻鏡』を信ずべき「記録」の枠から解放し、事後の視点から振り返って歴史を叙述する一種の「物語」として読み直していきたい。そのストーリーをひもとき、相対化してゆくことは、一般に事実を信じられてきた歴史像を相対化してゆくことにもなるだろう。ひいては、歴史を物語ること、すなわち、言葉の力で過去像を再構築してゆくという、人間の営みの一端を明らかにすることができれば幸いである。(Piv) |
ふむ。
そして、 序章 『吾妻鏡』とは何か から始まり、 第一章 頼朝挙兵(1180年)、 第二章 平家追討(1185年)、 第三章 奥州合戦(1189年)、 第四章 比企氏の乱(1203年)、 第五章 和田合戦(1213年)、 第六章 実朝暗殺(1219年)、 第七章 承久の乱(1221年)、 第八章 宝治合戦(1247年)、 終章 歴史像の構築 と語られます。
『吾妻鏡』とは元々は正史、つまりある史観に添って過去の歴史を記述したものです。であるがゆえにまず「誰が誰のために」というところをはっきりさせる必要があります。
誰が に関して、これは時の政権である鎌倉幕府です。
そして 誰のために に関しては、一般に考えられていることと違うのです。この書は、鎌倉将軍のためでも、源家総軍のためでもなく、鎌倉幕府を作り上げた一大の英雄源頼朝の思想を正しく継承した徳人である北条泰時と彼を祖として執権を送り出し武家社会をリードした北条得宗家のために作られたのだ。
そのために『吾妻鏡』の前半、すなわち宝治合戦までは、さまざまな物語によって歴史が作られています。しかしだからこそ後半は、虚構を積んでまで守る必要がなくなり事務的な記録の羅列になってしまったとされる。そうなのか。
また宝治合戦以降の政治の流れについても、政治的暗闘や軋轢などがあったはずなのに、あたかも天意によってなんの騒乱もなかったかのように淡々と、公家将軍が退位して後継者がその座に座り、執権が引退してそのあとを次のものが継ぐと言った重大事件が語られます。
なぜか。
これは、『吾妻鏡』が正史である事によるのではないか。
ここでは一つの可能性として、同時代の正史を作成することにまつわる根本的な困難を検討しておきたい。『吾妻鏡』後半部分で、得宗家の絶対性の物語とは別の眺望を開示する他者や、その位置づけを含めた立体感ある歴史の流れが描けていないのは、記述対象となる時代が、体験者世代の多く残る、記憶に生々しい近過去だからではないだろうか。
たとえば『吾妻鏡』の最終記事から編纂時期までのおよそ35年間の記事が作成される、と仮定しよう。そのとき、物語られるべき大きな事件は何があるかと考えると、おそらく二つの問題系列が想起される。一つは、全国規模で未曾有の激震が走った蒙古襲来の系列。もう一つは、安達氏が排斥された霜月騒動、および執権貞時が御内人平頼綱を排した平禅門の乱の系列である。
ところが、いざそれらを叙述しようとすると、前者は、まだ利害関係者が多く存命であり、幕府の正史として忠臣を限定すると支障が生じる。竹崎季長の『蒙古襲来絵詞』や石清水八幡宮の『八幡愚童訓』は、蒙古撃退に功があったと主張し恩賞を求めるために作成されたものである。そのような、過去像の私的な語り直しは、それぞれの立場の利益を主張するために行われた。しかし幕府の統治者として、その意味で公敵に利害を調整する得宗家の立場から俯瞰的に語り直す作業は、まだ困難だったはずである。
また後者は、乱の結果から逆算すると、安達氏を討った平頼綱を反逆者とする軍記物語を構築する必要がある。しかし、これも利害関係者が多く存命である以上、逆臣や忠臣を公式に認定すると必ず異論が生じ衝突を生むため、正史としては語りにくい。立場により見え方が変わってしまうと言う現象。まさに、「真相は藪の中」の状況に陥るのが現代史である。(P268-269) |
過去の歴史を公式な正史として描くとすれば、「その時」の歴史を正当化するために、正義と悪、正論と反逆、忠臣と逆臣はきちんと記録しなければならない。そしてその判定が曖昧な中、片一方に断ずれば必ず軋轢が残るとしたら、勢い完全決着の歴史など語れない。
なるほど。
であれば、このように評価することができる、という。
『吾妻鏡』はその編年体の配列の上に、幕政史上重要ないくつかの合戦を軍記物語的手法を用いて叙述することによって、幕府統治者の正統性を保証するための歴史像を構築することに成功した希有の歴史書である。その編纂作業は、幕府を構成する御家人たちの功績をちりばめることで、各家のアイデンティティを言語によって創出してゆくという、ダイナミックな営為が展開される現場でもあった。
だが、それぞれの立場の利害調整という現実的なしがらみによってその契機を喪失したとき、出来事を意味づけるべく横溢していた言葉の力は失われ、『吾妻鏡』は単線的に支配者の絶対性を語る規範の書へと姿を変えていった。事象の解釈や価値判断が積極的になされなくなれば、歴史叙述は出来事の羅列となり、焦点の定まらない過去は像を結ばず、歴史は立体感ある眺望を持ち得なくなる。かくして、虚構に彩られた鎌倉幕府の正史は精彩を失い、やがて散逸し、約三百年後に再び関東で幕府を開く徳川家康により収集されて新たな解釈を付与されるまで、時を待つこととなったのである。(P270) |
当初の目的を失った書であり、新たな価値観に基づいて再利用されるまで眠っていても誰も困らなかった、と。
そして現代人が勝手に解釈して、この「物語」は正しいはずだ、なに正しくない? じゃあこの文書は駄文だ、と言ったところで、そんな次元で見るかぎりなんの意味もない行為だ、と。
ふむ、なるほど。
いささか美文調になったことで当惑しましたが、要するにそういう事なのかな。
やはり、歴史は面白いね。(2025/3/19)
読書メーターの記録より 読了:2025/3/8 |




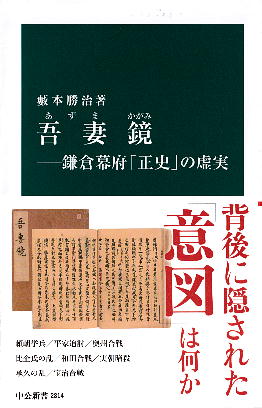 はじめに の冒頭、シロートむけには爆弾発言となる言葉が。
はじめに の冒頭、シロートむけには爆弾発言となる言葉が。