 トップへ戻る  読んだ本の分類 |
|
 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |
|---|---|---|---|
| A065-001 | 日ソ戦争 | 日本が戦った最後の戦争の様相 | |
 |
|---|
| 管理番号:A065-001 | 52J 戦史・戦争ノンフィクション(日本) |
出版社:中央公論新社 | |||||||
| 書名:日ソ戦争 | 日本帝国最後の戦い | ISBN978-4-12-102798-6 C1221 | |||||||
| 中公新書 2798 | 価格:980Yen | ページ数:304P | 本のサイズ:新書 | ||||||
| 初版発行:2024/4/25 7版:2024/10/20 | 購入:2024/11/26 | ||||||||
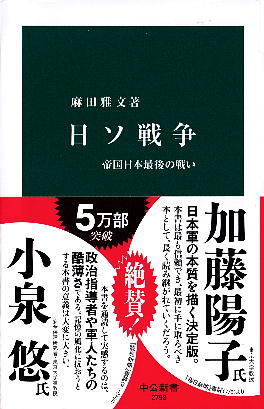 1945(昭和20)年8月15日、日本は太平洋戦争における敗北を認め、終戦を宣言し、ここで第二次世界大戦は終結したとされます。(厳密には、降伏文書に署名し受諾された9月2日とか) 1945(昭和20)年8月15日、日本は太平洋戦争における敗北を認め、終戦を宣言し、ここで第二次世界大戦は終結したとされます。(厳密には、降伏文書に署名し受諾された9月2日とか)しかしこのとき、連合軍内の密約に従い中立条約を一方的に破棄して日本に宣戦したソヴィエト連邦は、なおも東アジアにおいて日本と交戦状態にありました。この戦いは、かつては特に日本の歴史上では無視されていましたが、現在では日ソ戦争として記録されています。戦争は1945年8月8日から9月5日まで継続し、この間にソ連はおよそ185万人、日本は100万人超の兵力を動員して、それぞれ数万の死傷者が出ます。民間人の死者は、ソ連はゼロ、日本側は24万を超えたとのこと。 この戦いの名称は、日本史的にはまだ確定していないようです。日本の防衛省防衛研究所戦史部では、この一連の戦闘を Wikipediaのソ連対日参戦の項目では、この項目を日ソ戦争と改名すべきか、議論が続いている由。決着は今のところついていません。 この本は、その様相を、新たな視点で克明に描き出したものです。 戦争が始まった原因は、というか要因の一つとして、
1943年11月28日のいわゆるテヘラン会議で行われた米英ソの首脳会談の席上、ヨシフ・スターリンはフランクリン・ローズヴェルトに対し、対日戦に加わるのはドイツが崩潰した時だと述べたのだそうな。 この時点でソ連はいわゆる「大祖国戦争」に勝利できそうだという目途は立っていましたが、戦線は一進一退で被害は甚大、とてもほかに戦線を作る余裕などなかったのでした。そのため、米英にビルマ作戦などと言う余計なことはせず、欧州戦線を少しでも早く勝利で終わりたかったのです──それは息切れしているソ連が少しでも早く休みたいという願望。 それを米英は、ドイツ軍が壊滅すればソ連はすぐ日本を攻めるというふうに解釈します──しようとします。 1945年2月4日に始まるヤルタ会談は、同床異夢の三国が虚々実々の駈け引きの中で騙し合い、妥協し合います。 最終的にスターリンの遼東半島の租借要求は旅順港のみの租借、それも「自由港」にするという線まで煮詰められ、モンゴルは人民共和国として中国領から割譲され、満洲の利権は中ソ共同経営になるなど、アメリカは同盟国である中国の顔を立てます。しかし南樺太や千島列島などはソ連側の要求が通る。
この対日方針は、基本的に4月12日にローズヴェルトが病死したのち米大統領に昇進したトルーマンも継承しています。 ポーランド問題など欧州戦線における米ソの亀裂があり、トルーマンは対ソ不信のため、ヤルタ協定を一歩でもソ連が破ったらただではおかないと激怒しますが、米軍部の説得により頭を冷やします。ロシア人が対日戦に参戦すれば、それでアメリカ兵10万の命が助かるではないか、と。 しかしここに、米国が極秘とした、今後の戦争の帰趨を変える兵器、すなわち原爆の問題など、情勢の変化が出てくる。 一時はソ連の参戦を哀願するばかりだった米英は、ポツダム会談においてソ連・モロトフ外相が提案した、米英がソ連が対日宣戦を世界に示す形で要請するという案を蹴りました。ヤルタで合意した三人の中で、ローズヴェルトは死に、チャーチルは英国選挙で負けて政権から退いていますので、ソ連の立場は怪しくなります。
そしてソ連は日本に昭和20(1945)年8月8日に宣戦布告し、その後攻め込みます。だから不意打ちではない、と。 その宣戦布告がソ連の日本大使館にのみ伝えられ、大使館から日本への通信網が遮断されていても知ったことではない。 日本人はソ連の背信を責めますが、ぶっちゃけ戦争も政治もやったもの勝ちなのです。信義とか正義などは後回し。 結果として負ければ負けた方が戦争犯罪人にされるだけなのです。それが、歴史で培われた人間のルール。 こんな事実もあります。
最初、少しでも早くソ連を日本に参戦させることで自国の兵の死傷者数つまり政権党への国民の票が減るのを防ごうとしたアメリカは、原爆の開発成功と共にソ連抜きでも「損害の少ない勝利」をおさめられると確信して放置します。 1943年以降、早く連合国側に立って日本に参戦してほしいと米ソに要請されていたソ連は、どうせ日本は中立条約など破って攻めかかるのだからその時になれば戦う、とアメリカをいなしつつ支援を得ていたのですが、このままでは戦後の分け前が少なくなるとあせり、8月6日の広島原発の報を知って開戦の予定を早めます。 イギリスは、東アジアにおいてはアメリカ主導を認めつつもドイツが敗北したことで傍観の体制になります。 同床異夢というか、三者三様。 無条件敗北という屈辱を国家として肯んじることができない日本は、ソ連に仲介の労を取ってもらえると信じます──このときの日本は、自分の願望と世の理屈と他者の思惑の区別がつかない状態に陥っていました。 ここまでが 第1章 開戦までの国家戦略──日米ソの角逐。 そして戦争の様相、第2章 満洲の蹂躙、関東軍の壊滅 第3章 南樺太と千島列島への侵攻 第4章 日本の復讐を畏れたスターリン と続き、最後は おわりに──「自衛」でも、「解放」でもなく と言う文で最後を締めます。 ここで語られるのは、不意をつかれ、宣戦が崩潰し、事前の戦略がまったく意味をなさなくなった中で日本は日本軍は何をしたのか、がまずひとつ。 そして悲惨な戦争で疲弊しきり、ようやくドイツの降伏で息絶え絶えに戦勝を喜んでいたソ連兵士が、いかにして極東の地まで来て祖国の防衛でもなんでもない戦争を戦ったのか。 ソ連兵にとって、負ければ虐殺、勝てば収奪・略奪しか知らなかった戦争とは、極東ではどういういうものであったのか。 日露戦争の復讐という題目で日本に勝利したスターリンは、味方とは従属するもの、敵とは滅ぼすものと考えるのが当然であり、いずれ日本は必ず復讐すると考えます。それを防ぐためにスターリンが行った手が四つ。 ①日本の(スターリンが望む)民主化の推進 ②対日防衛網の構築 ③南樺太と千島列島の併合 ④シベリア抑留 しかし①は、日本占領軍司令官となったマッカーサーの拒否により頓挫します。②は、日本を仮想敵国とする中ソ友好条約の締結として結実します。アメリカまで対日同盟網を広げようとしましたがアメリカは同調しませんでした。③の、南樺太と千島列島の併合については、アメリカの奄美諸島・小笠原諸島・沖縄の支配に対応して行われます。本来領土権を主張する根拠のない千島列島に関しては、日本との平和条約のあとにすべきという意見があったそうですが、スターリンは強引に自国領に年入します。 そして ④シベリア抑留。これで日本の戦意を挫けるとスターリンは思ったのか。 日本の厚生労働省の算出した人数は57万5千人、研究者による統計分析によると61万1237人がシベリアに送りこまれ、約6万人が亡くなっています。が、いまだにこの正確な数にしてもその様相にしても、わかっていません。 ソ連に正式な記録はないそうです。彼らにとってこの記録は、意味を持たないのです。そんな国なのだ、彼らは。 当初、満洲の都市建設のために捕虜を使役する予定だったものが、なぜシベリア抑留になったのか。主に三つの説があるのだそうな。
米英も枢軸国から現物賠償を取り立てていますが、年月と共に返却したものも多い。
しかも関東軍から没収した戦利品のうち、航空機・戦車・火砲などは、中国共産党にほとんど引き渡し、自分のふところを痛めずに中国共産党に恩を売ったとなると、本当に容赦がない。 こんな「文化」を持った国と日ソ中立条約を結び、誠意を持って対応すれば裏切らないはずと考えた日本でした。むべなるかな、というべきか、夜郎自大というべきか。 なるほどねぇ。我が国は、こんな「文化」をいまだに持っている国が目の前にあるのか。 ところで、日本に一番近い外国は、大韓民国でも中華人民共和国でもありません。彼らが実効支配している千島列島が目の前にあるロシアです、困った事に。 今後もそのままなのでしょうか。(2025/6/13) 読書メーターの記録より 読了:2025/4/10 |