 トップへ戻る 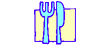 作家/分野 一覧 |
|
 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 書 名 | 翻訳者 | メ モ | |
|---|---|---|---|---|
| B088-001 | エリザベス女王の事件簿 | 芹澤 恵 | 実は影の名探偵たっだエリザベス女王 | |
| B088-002 | エリザベス女王の事件簿 バッキンガム宮殿の三匹の犬 | 芹澤 恵 | これは、犬三匹分考えないとわからん大問題だな! | |
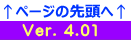 |
|---|
| 管理番号:B088-001 | 40 ミステリ一般 |
出版社:KADOKAWA | |||||||
| 書名:エリザベス女王の事件簿 | ウィンザー城の殺人 | ISBN978-4-04-111019-5 C0197 | |||||||
| 原題:The Windsor Knot(2020) | 翻訳者:芹澤 恵 | ||||||||
| 角川文庫 17-1 23265 | 価格:1300Yen | ページ数:999432P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2022/7/25 | 購入:2023/6/24 | カバーイラスト:くぼあやこ カバーデザイン:鈴木成一デザイン室 |
|||||||
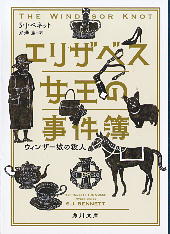 エリザベス二世の登場する英国王室が絡む小説を前に読んだことがあったのですが、個人的にコレジャナイ感がしていました。設定がおかしい、ありえない、と。でもこの本はどうかな、と手に取ってみたら、見事に裏切られました。これ、面白いじゃないか。 エリザベス二世の登場する英国王室が絡む小説を前に読んだことがあったのですが、個人的にコレジャナイ感がしていました。設定がおかしい、ありえない、と。でもこの本はどうかな、と手に取ってみたら、見事に裏切られました。これ、面白いじゃないか。わが家、と思う幼い日々の思い出が詰まったウィンザー城の前で、ポニーに乗ってくつろぐ女王から始まります。 結果から言うのなら、老衰でお亡くなりになる6年ちょっと前のこと。 くつろぐ、と言っても、頭に引っかかっているものはあります。昨夜行われた若いピアニスト、24歳のマクシム・ブロツキーを中心にしたパーティのあと、彼が部屋で死んでいたのでした。自殺らしい状態で、衣装戸棚の中で腰紐で首を吊られて死んでいたそうな。その上、いささか異常な姿で。 あと2週間もすれば90歳になる女王を動揺させる報告はしたくない、という様子の女王秘書官サー・サイモン・ホルクロフトに圧力をかけて詳細を聞きだす女王。
奇妙な現場の状態ではあったものの一度は自殺と片づけられたこの事件に、女王はなにかうさんくさいものを感じます。はためには、そして側近を含め女王を取り巻くほとんどの人が思っていたのは、女王とはあと二週間で90歳になる老女であり、あんまり細かいことを考えず寛容に全てを見通し、時々癇癪を起こす愛すべき存在。 しかし実は、そうではなかった。 女王エリザベス二世とは、60年以上もの長い間英国の王座にあり、類い希な記憶力と判断力を持ち、チャーチル、イーデン、マクミラン、ダグラス=ヒューム、ウィルスン、ヒース、キャラハン、サッチャー、メージャー、ブレア、ブラウン、キャメロンと、2016年4月までで12人の首相を指名し、その政治を見守り、助言し、時に指導してきた人なのです。そして2016年現在の世界情勢にも目を配り、海千山千の各国首脳と渡り合って来た人なのです。名目上の君主というスタンスではありますが、ただのお飾りではない。 MI5── 女王は、プーチンと目の前で語り合いその本性をかいま見ていますので、こんな告発は馬鹿げていると思います。ウラジミール・プーチンは残酷な暴君であるが決して愚かではない。こんな杜撰なミスをおかすはずはないし、敵方の宮殿であからさまな諜報活動を行い、死体を転がすなどと言う馬鹿げたことを考えるはずがないし、報復で何が行われるか想像できないはずがない。 しかしこの自惚れた坊やには理解できないらしいし、学ぶ気もないようだ。まして女王の意向を考える気もないようだ。 たとえ腹の中は煮えくり返っていても、女王は女王としてふるまわなくてはならない。 その夜、オバマ大統領の来訪に関連して女王の了解を得る事項があって午前に参上したサー・サイモンは、打ち合わせのあとで新人の秘書官ロージーを呼ぶよう言われます。 ロージー・オショーディはナイジェリアにルーツを持つ新任の女王秘書官補。29歳。才気があり立場をわきまえた女性のようですが、女王としてはまず確認する必要があります。
これになんとか合格できたロージーは、女王が気になるあのピアニスト事件の調査に取りかかることとなります。首席秘書官であるサー・サイモンを含め、ほぼ全ての関係者に秘密で。 そこでだんだん分かってきました。女王に仕えた人々の中で、ある特定の人々だけが、女王が気にし心配し調査したいと思った何かを女王の意を受けて調べていたことを。なにか女王だけが気付いた異常な事態、そして表面上静穏に収めたい事態があったとき動いていた事を。女王個人の〝お願い〟によって。 五里霧中の彼女がふと思い出したのは、この仕事の引き継ぎを受けたとき、メンタルヘルス面の問題というあいまいな理由で身を引いた前任のケイティ・ブリッグスから聞いた奇妙な言葉。
さらに驚くことを言います、王室の職員はもっと陛下を信頼すべきだと。特に、首席秘書官であるサー・サイモンなどは。
さて、直属の上司であるサー・サイモンの目を盗んで、ロージーの調査が始まります。 その結果、なにが判明したのか。その後、さらに二人の若者が命を落とした原因はなにか。ロシアの関与はあったのか。 さまざまな調査結果、起きた事・起きなかった事、報道されたこと・報告されたこと。 関与したさまざまな人々の報告が、女王に集まり、そして混迷の度合いを深める。そして、
そして事件は解決される。苦い結果であろうと。 解決した女王は、いつものようにその結果をすべてしかるべき立場の人たちに任せ、何もなかったように次の日を迎えます。無能と軽蔑している相手であっても、女王の内閣が承認した人物であればそのまま信頼される閣僚であらねばならない。
読み終えて思ったことが二つ。 一つは、C・S・フォレスターが書いた小説「海軍提督ホーンブロワー(Hornblower in the West Indies)」の中の一編、『南海の星(The Star of the South)』の中でホーンブロワーが同じ事をしてたな、というもの。彼は、有能でない自分の旗艦艦長に、あたかも彼が名案を思いついたように誘導して彼に功績を立てさせたのでした。最初に読んだ若いころには納得できなかったけれど、いま読むとなぜそうしたのかがわかってきます。人を育てるものは高圧的な叱責ではなく温かい励ましなのだ、ということ。 もうひとつは、日本でこういう話はできないものか、というもの。のほほんと「あ、そう」とぼそぼそ言うだけの老人と思われたあの人は、実は類い希な記憶力と判断力を落ち、一歩下がったところで全てを見通していたという。であれば、こんなお話を考える人がいてもいいんじゃないかなぁ? >ある日佐々淳行氏(まあ誰でもいいんだけど)の事務所に電話が入る。目立たない黒い車に乗せられて走ると、行く先はなんと吹上御所。何事ならんと血圧が上がった佐々氏の前に現れたあの方は、ゆったりとした口調で不思議な話を始めた・・・ ダメですか?(笑) 読書メーターの記録より 読了:2023/10/1 |
|||||||||||||||
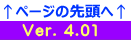 |
|---|
| 管理番号:B088-002 | 40 ミステリ一般 |
出版社:KADOKAWA | |||||||
| 書名:エリザベス女王の事件簿 バッキンガム宮殿の三匹の犬 | ISBN978-4-04-111020-1 C0197 | ||||||||
| 原題:書名アルファベット(発行) | 翻訳者: | ||||||||
| 角川文庫 17-2 23559 | 価格:1700Yen | ページ数:576P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2023/2/25 | 購入:2023/8/30 | カバーイラスト:くぼあやこ カバーデザイン:鈴木成一デザイン室 |
|||||||
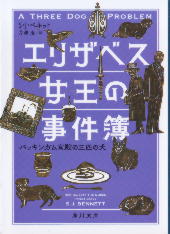 プロローグ は、2016年10月某日の早朝、日頃の運動不足を補おうと考えた女王秘書官のサー・サイモン・ホルクロフト(54歳)が、まだ人のいないはずのバッキンガム宮殿の屋内プールに現れます。しかしそこで、とんでもないものを発見してしまったのでした。 プロローグ は、2016年10月某日の早朝、日頃の運動不足を補おうと考えた女王秘書官のサー・サイモン・ホルクロフト(54歳)が、まだ人のいないはずのバッキンガム宮殿の屋内プールに現れます。しかしそこで、とんでもないものを発見してしまったのでした。それは、プールサイドの大きな赤黒い血液だまり。そしてその真ん中に横たわる女性。宮殿のお仕着せである白いワンピースを着たその顔に、サー・サイモンは心当たりがあります。
テーブルの蜂蜜の容器に『デイリー・テレグラフ』を立てかけて読んでいる夫君フィリップ殿下は、この年95歳。とはいえ耄碌した老人ではない。あちこち衰えているが、細君の言葉の腰を折るくらいはお手のもの。
絵に関してですが、女王がその場でどのような圧力をかけたのか分かりませんが、海軍は「なにかの間違いでしょう、この絵は我々の所有の品物です」という趣旨の返答を行ったようです。君主と言えども、英国女王であればあるほど、理路整然たる反論を権力で覆すことはできない。 で、朝食にノースウィングで執務を取る女王は、前回非公式な「任務」において手駒として使ったこともある秘書官補・ロージー・オショーディに命じ、この件を調べさせます。 とりあえずロージーがざっと調べたところでは、この絵は しかし女王は納得していない。
そこに、いくつもの事件が絡み合ってきます。 まずは、古びてしまったバッキンガム宮殿で、膨大な量の配線の絶縁材の劣化による漏電事故への対策。これは、1992年にウィンザー城で発生した漏電火災のために、五年の歳月と数千万ポンドが費やされた苦い記憶がありますので、簡単に後回しにできるものではない。 それとほぼ同格な事件のように女王手許金会計長官サー・ジェームズ・エリントンが女王付き秘書官サー・サイモン・ホルクロフトに語ったのは、サー・ジェームズの有能な秘書メアリ・ヴァン・レネンが辞表を出した件。有能な秘書は同じ重さの黄金より価値がある、とされた時代ではないにしても、彼らおっちゃんにとって馴染みの有能な秘書が去るのは仕事上のダメージが大きい。 ちなみに、「秘書官」と「秘書」は仕事上全然別物です。 この、有能な秘書の件が尾を引きます。ロージーもその中に巻き込まれますが、メインの事件と絡むことになるとはまさか思ってもいませんでした。 このメアリがやめることになったのは、謎の人物から深刻な嫌がらせを受けていたことが一因。原因も分からず、警察に届けても無駄だったそうな。 ここで、シンシア・ハリスという王室の 仕事は正確・適確・丁寧で女王ご自身の信頼も篤いのですが、同僚にはとかく評判が悪いらしい。苛め、こき下ろし、傍若無人を繰り返し、彼女のために職を失った職員もいたらしい。メアリ・ヴァン・レネンも彼女につらく当たられていましたので、まさか彼女への嫌がらせの原因も彼女ではないかと疑われたことも。 しかし彼女が、なぜか殺されていたのでした。そう、冒頭の描写。いったいなぜ。誰に。どうやって。 極秘の捜査を進めさせる中で、女王はふと考えることに。
そしてこの「 とはいえまさか、この女王の絵の紛失から始まった事件が、二件の殺人に、そして大規模な陰謀に、 この結末はどうやって、誰がつけたのか。 女王はその結果に満足できたのか。 最後に明かされる、なぜ女王があの絵にこだわったのか、なぜ女王はひと目見てあの絵が複製でも同じような絵でもなく自分のものだと確信できたのか、が明かされます。 この下手クソな絵、と罵りつつ、素人画家として絵筆を取る事もある夫君フィリップが、描かれた王室ヨットブリタニア号の船上に自分の姿を手を加えてくれたものだから、という顛末が心を温かくしてくれます。なるほどね、じゃあひと目見て本物とわかるわけだし、複製だと言われてもありえないと断じる訳だ。 いかにも英国らしい粋な会話があちこちにちりばめられ、それもまた良しです。 たとえばサー・サイモンと殺し方のスタイルを話すロージーの会話。
そうそう、原題のThree Dog Problem とは、むろんホームズの名言「パイプ三服分の問題」に絡ませた言葉ですね。あえてシャーロッキアン的に訳せば「充分な熟慮を要する難問」かな。 あちこちいろいろ楽しめました。エリザベス女王の事件簿は今後刊行されるのかな。出たらぜひ読みたい。(2024/2/21) 読書メーターの記録より 読了:2023/1/15 |
|||||||||||||||||

