 トップへ戻る  読んだ本の分類 |
|
 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |
|---|---|---|---|
| I012-001 | スペイン無敵艦隊 | 海の覇権をめぐる大国と新興国の争い | |
 |
|---|
| 管理番号:I012-001 | 54 歴史点描 |
出版社:原書房 | |||||||
| 書名:スペイン無敵艦隊 | ISBN4-562-01195-5 C0022 | ||||||||
| 価格:1800Yen | ページ数:284P | 本のサイズ:130×195HC | |||||||
| 初版発行:1981/12/24 第3刷:1982/7/20 | 購入:1982/8/8 | 表紙イラスト: | |||||||
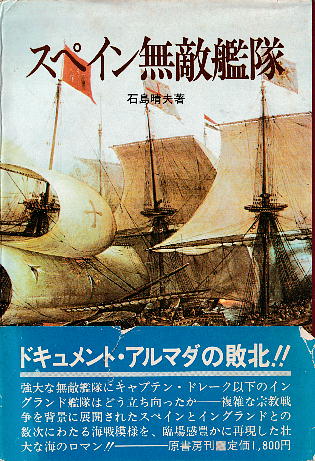 スペイン無敵艦隊とは、後世にその名がつけられたスペインの艦隊で、主に16世紀後半にイングランド征服のため遠征した艦隊を指します。 スペイン無敵艦隊とは、後世にその名がつけられたスペインの艦隊で、主に16世紀後半にイングランド征服のため遠征した艦隊を指します。これはスペイン王フェリペ2世の主導のもとに行われ、イングランド女王エリザベス(1世)指揮下のイングランドの船乗りたちによって撃退されました。それが、歴史。 この歴史を広い視野でさまざまなエピソードをちりばめつつ多角的に描いたのがこの本。 昭和50年代半ばは、シーパワーという言葉が一般社会で取り沙汰された時代でした。制海権という概念を包括する海を支配する力すなわちシーパワーが、日本の経済はペルシア湾から日本に至るタンカー網を含め、実に脆い交易ラインによって保たれていることが認識され始めた時代。 そう、日本人は太平洋戦争において、通称破壊というすさまじいボディブローによって息の根を止められながら、それを理解できず、戦争は政治と軍事だけで行われるのではなく、経済活動も戦争に欠かせないことを知らない人が、かくも多くいたのでした。 この時期にこの本が刊行されたのは、その波に無縁ではないようです。 「アルマダ」、と著者はこの艦隊のことを呼びます。アルマダとは、スペイン語で船団、艦隊のこと。無敵艦隊という名前自体が、当時呼ばれた名ではないことなどを考え、このスペイン艦隊のことをアルマダと呼ぶこととするのだそうです。 またこの当時、イギリスと呼べる国はありません。ブリテン島には三つの国があり、ウェールズとイングランドはまとめてイングランド王国ですが、スコットランドは別な王国です。なのでスペインと戦ったのはイングランドなのです。 まず最初に指摘しておくこと。スペイン無敵艦隊の名で示されたイングランドの海上での勝利は、イングランド(当時)にとって「大」がつく快挙でした。しかし歴史を俯瞰すると、この勝利はスペインとイングランドでは認識が違うのです。 のちに日が沈むことがない大英帝国が生まれた歴史を知っている後世の人々は、主にイングランドの視点で見るので、1588年のこの一連の海戦が旧大国スペインへの新興国イングランドの決定的な勝利となり、これ以後スペインは衰退の道をたどる、というふうに認識してしまいます。が、違うのです。 スペインの欧州における軍事的序列は、この戦いのあとでもナンバーワンでした。海でイングランドが、陸でフランスがその覇権を揺るがすのは次の次の世紀になってからと言っていいかな。 この本では、1588年5月から9月にかけて行われた第1回のアルマダ海戦の歴史を描くにあたり、1554年7月にスペインを発ってイングランドに到着した130隻もの大艦隊の描写から紐解きます。 英仏海峡の強い西風を背に受けてサザンプトン沖に停泊した艦隊は、ドイツ、スペイン、ネーデルランドの支配者にして神聖ローマ帝国皇帝カルロス1世(カール5世)の長男フェリペ王子(当時27歳)とその随員を上陸させました。目的は、時のイングランド女王メアリー・チューダー(当時38歳)との婚礼。ポーツマスで補給を受けた艦隊主力はそのまま帰還し、八千の兵士を乗せた輸送船はそのまま対岸のフランダースに向かいます。カトリックの女王の統治下にあったイングランドは、スペインと短いながらも文字通り蜜月期間をすごしました。とはいえ11歳上の女王との結婚生活は必ずしもうまくいかず、1556年には父王の死去に伴い、王子はフェリペ2世として即位したのちは疎遠になります。 王位を継承できる子供を得られぬままメアリーが1558年に死去すると、次に25歳で王位に就いたエリザベスは反カトリックの立場を取ったため、両国間は険悪になります。宗教的な対立も険悪なのですが、経済的・軍事的・文化的対立も両国の確執の原因となります。しかしそれだけではない。 著者はここで、二人の王の環境・性格も対立要因となったと書き加えます。
 さらに両国の対立は、1587年4月のドレーク率いるイングランド艦隊によるカディス港焼き討ち、そして一連の沿岸襲撃から6月のアゾレス諸島襲撃により、頂点に達します。 さらに両国の対立は、1587年4月のドレーク率いるイングランド艦隊によるカディス港焼き討ち、そして一連の沿岸襲撃から6月のアゾレス諸島襲撃により、頂点に達します。かくして1588年5月、アルマダがリスボン港を出港します。この間、両国ともさまざまな経緯・戦争準備があり、意に添わぬ混乱はありました。しかしさまざまな理由(イングランドへの十字軍的懲罰行、ネーデルランドの反乱、スコットランドの救援、その他)などの理由により、フェリペ二世の使命感は高く、戦う気満々。 その経過と結果をこの本は 第一章 イングランドの先制攻撃 から説き起こして、 第二章 無敵艦隊の出発 第三章 海戦 第四章 アルマダの敗北 と双方の熾烈な戦いの様相を詳細に描きます。 このアルマダ海戦のあとのイングランドのスペインへの反撃とその挫折が 第五章 イングランドの反攻 で描かれました。 第六章 その後のアルマダ で描かれるのは、あの1588年の戦いを第一回として、そのあと四回、第二回から第五回までの、やや規模が小さくなったアルマダ海戦を描写し、第二二節 最後の小競り合い として消耗し尽くした両国の最後の戦いを描きます。それは、1602年、イタリア人フェデリコ・スピノラ公に焚きつけたられたスペイン王が、スペインの沿岸を荒らしに来たイングランドの戦隊と戦います。都合半年以上かけて行われた戦いのあと、15年余りにわたり次々と顔を変えた将たちによって行われた戦争は、これをもってついに終了しました。 これほどまでに長引いたのは、イングランドにとって一回の戦争での負けが国家の滅亡へ結びつく生存の戦いであり、スペインにとって敵対する新興国の存在を許せば国の威信に関わる問題だったから。 戦争終結後、イングランドでは穀物の不作と物価高騰、戦費調達のために乱発されて特許状により利益独占の弊害、財政窮乏により事実上破産していた王室、民衆の怒りと貴族たちの離反に対する対策が急がされます。女王はついに議会への介入を決意し、庶民院の議長を通じて戦争のため歪んでいた各種の制度を正す旨、宣言します。 1600年11月30日、ホワイトホール宮殿に召集された140名の議員たちを前にエリザベス女王が行った演説は、後世に「黄金の演説」として讃えられたとか。
ユリウス暦で1603年3月24日、エリザベス女王は政治的混乱を避けるためにカトリックの血縁者、スコットランド王ジェイムズ6世を後継者として指名したのち、45年という長期の統治期間の末に69歳で死去します。スペインとの戦争の終結を見届けたあとのこと。 スペインのフェリペ二世は、それに先だつ5年前、1598年9月13日に71歳で没しています。 まさに二人の国王がその晩年に、互いに意地を貫き通した戦争だったのでした。 強権をふるったプロテスタントの女王が育て上げたイングランド海軍は、カトリックの王たち、ジェイムズ1世、チャールス1世の時代に衰退しますが、清教徒革命(1642-1649)によりイングランドを統治したクロムウェルによって復活し、海上に覇を唱えるために次の敵オランダと対戦しますが、それは次の世代の話。 なるほど、こういう歴史があったんだね。 ところで、この本の前書きはこのような文章で始まっています。
何が違うかというと、まずいま日本で「四大海戦」を検索すると、四つに絞れないこと。 おそらく世界どこでもそうでしょう。 世界中で国民によってなにを「歴史の転換点」と考えるかの基準にズレがあり、自分たちの視点で大事件と思われる海戦を「四大」の中に入れる傾向があるから、決まったものがない。「レパントの海戦」が入ってくるのはまだしも、「ミッドウェー海戦」「レイテ海戦」が入ってくるとおいおいと言いたくなる。それが入るのなら「ユトランド海戦」がなぜ入らない。 極めつけは、いささか噴飯ものなのですが「閑山島海戦」が入っていること。これは、朝鮮の「忠武公」李舜臣が、日本の「名将」脇坂安治率いる「強大な」日本水軍を壊滅させたというもの。あ、そこ引かないで! これは朝鮮の人にとって大事件かもしれませんが、日本人にとってほぼ知られていない戦いです。脇坂安治という武将がまず大軍を率いる重要な武将ではない。それほど有名ではない。日本水軍は各地の海賊大名などが率いる部隊を集めたものですが、「統一された強大な水軍」などではない。李舜臣を知っている人がそもそも日本では極少数派。日本の視点で見るとあの戦いは秀吉の朝鮮侵攻の中のひとつの海の合戦にずぎず、歴史の流れに影響はない。(と日本では認識しています) つまり四大といっても、それを提唱する人によって異なるのでこだわる必要はないよね、と。(2025/6/24) 読書メーターの記録より 読了:2020/11/5 |