 トップへ戻る  読んだ本の分類 |
|
 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |
|---|---|---|---|
| K117-001 | 論争 関ヶ原合戦 | 新たな視点で俯瞰するこの戦いの様相 | |
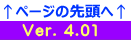 |
|---|
| 管理番号:K117-001 | 59 日本・戦国史 |
出版社:新潮社 | |||||||
| 書名:論争 関ヶ原合戦 | ISBN978-4-10-603887-7 C0321 | ||||||||
| 新潮選書 | 価格:1500Yen | ページ数:272P | 本のサイズ:130×190SC | ||||||
| 初版発行:2022/7/25 | 購入:2023/1/21 | ||||||||
 関ヶ原合戦に絞ってあの時代を見直し、様々な俗説や新説を検討した上で最もありうる「関ヶ原戦略」を開示したもの。 関ヶ原合戦に絞ってあの時代を見直し、様々な俗説や新説を検討した上で最もありうる「関ヶ原戦略」を開示したもの。なのかな? 関ヶ原の戦いに関して、著者はかつてそれまでの解釈とは違う歴史解釈をさまざまな媒体で著してきたそうです。そしてこれが、この時点では集大成になるものなのでしょうか。 まえがきで、関ヶ原合戦をめぐる議論を行うにあたり、筆者は三つの方法論をとっていると宣言します。 1.第一次史料原則 歴史学の基本的な立場ですが、解明すべき事柄に関して、同時代に同時進行的に作成・産出されていた史料、日記・覚え書きに代表される記録類、法令、勘定帳簿などを第一に参照する。 2.遺跡、地形、景観、それらの位置関係など、時代を経て大きく変形していない場合は第一次史料として活用する。海浜や河川は変化が大きいので史料としての有効性に欠けるが、山は植生を別にして歴史的に同一性を保持していると考えられる。 3.のちの時代に作成された後代史料も、必ずしも第二次史料として排除せず、「木を見て森を見ず」の害に陥らないよう考慮しつつ活用する。 4.第二次史料であっても、生成の経緯・系統を別にする複数のものが問題事案について同一の事実を語っている場合は、第一次史料に殉じる扱いをしてもよい。二次史料であるだけで排除すべきではない。 5.「芝居がかった話は嘘と見なして差し支えない」という見解は、もっともらしく流布している言葉であるが、「芝居がかった真実」を示す史料は多く、派手な話であるからと言って無責任に排除すべきではない。たとえば信長が桶狭間の戦いの前に幸若舞いの「敦盛」を待ったというエピソードは芝居がかっているが、充分に事実と考えて差し支えないという例もある。 という原則を立てて、論じていきます。 まず第一章で秀吉の死。そして、関ヶ原前野の政治抗争。会津征伐。三成の挙兵と小山の評定。西軍の展開と全国各地の戦い。東軍の展開と家康の戦略。関ヶ原合戦。それから、合戦後の国制。 最初の章で語り始めた秀吉政権の権力構造の解説は、なかなか新鮮で面白い。すでに世に知られたもので鐵太郎が知らないだけだったのかもしれませんが、秀吉がいかにして武力を背景に全国で豊臣政権の絶対的な支配権を握ったか、という解説のあと、そのシステムを海外に展開したのが朝鮮出兵なのだ、という説明がすごいですね。
ああ、倫理観・釈然、ていうのは、日本は幸運なことに他国と国境を接し、国境が動いたり征服されたり征服したりという歴史を知らずに近代までの歴史を過ごしていたわけですが、世界では強い国が弱い国を攻め、略奪し、虐殺し、併合するなどは日常茶飯事といっていい歴史を経ています。その視点で見れば秀吉の朝鮮出兵などは、構想倒れの征服失敗の一例にすぎず、結果としての無能は笑われても、倫理的にどうたらなど言えないはず。 いや、これは別な話。閑話休題。 慶長の役の、竜頭蛇尾となった結末と戦線縮小・撤兵にあたっての思惑の違い、そこから繋がる関白秀次事件の結末は、壬申の乱すなわち吉野の山に追放された大海人皇子の逆襲という故事を秀吉が知っていたから、という説。そして秀吉の死。 ここから説き始めて、北政所と淀殿が対立していたという通説の件。ところが筆者の言では、歴史学会の研究結果による考えでは、関ヶ原合戦全体として北政所のスタンスは西軍寄りであり淀殿との意見の相違はなかったとするのが主流なのだそうな。それに対し筆者は、新たに発見された浅野幸長・黒田長政より小早川秀秋宛の密書に政所に縁のある秀秋は東軍に付くべきであると書かれていたことを元に、北政所は家康方であったと断じます。 かくも、歴史上の定説とは史料一つでひっくり返るものであるという。 で、秀吉死後の朝鮮撤兵から、豊臣七将の石田三成襲撃事件、会津征伐と直江状の真偽、石田三成と直江兼続の事前通謀はあったのか、「内府ちがひの条々」は誰が書いたのか、と関ヶ原に至るさまざまなイベントへの通説と著者の論が書かれます。 小山の評定での山内一豊の居城明け渡しは、いかにも芝居がかったシーンではあるけれど、事実であると判断します。 家康が会津に向かったことを好機として挙兵した政軍に対し、緒戦段階ですでに吉川広家は本家毛利を守るため家康と手を結ぼうとし、小早川秀秋共々西軍にありながら内応を約していたということも。 丹後田辺城での息子に家督を譲って隠居となった細川幽斎の、500の寡兵で一万五千の大軍に対して行った壮絶な籠城戦、京極高次の同じく寡兵での近江大津城の籠城戦、上杉領伊達郡への伊達政宗の攻略戦、九州における黒田如水と加藤清正の孤軍奮闘など、東軍の視点に立った描写が続きます。 関ヶ原の戦いに遅参したことでのちに問題になった秀忠の軍勢と、家康が配下においた軍勢はほぼ同数です。 このとき手持ちの軍勢を二つに分けたのは、東軍として配下に入った諸将の軍勢が東海道を主に使ったため、人馬逓送の問題があったことが大きい。これは通説通りであり、秀忠の中山道方面軍が、決戦にあたって二方面作戦を避けるため信州上田城を制圧する任を負っていたのも当然のこと。これ以前にも、秀忠軍は宇都宮に対上杉軍用の長大な土塁を築く任務を終えています。 上杉のみならず挙動の怪しい佐竹義宣や関東全般への抑えとして、家康二男の結城秀康が総大将として宇都宮に据えられました。 秀忠軍と家康軍の兵数は、数だけならほぼ同数ですが、主力は秀忠軍であったと説明し、付き従う将士のリスト一覧を出しています。これによると、家康に従う将の中で、もっとも禄高が高いのは井伊直政(12万石)、そして彼の娘婿である家康四男松平忠吉(10万石)。これだけが主兵力。次に軍目付として本多忠勝(10万石)がいますが、これは秀忠軍にいる嫡男本田忠政に兵の大半を与えていますので、家康側近としての立場だけ。あとの将兵はほとんど一万石以下の旗本クラス。つまり、二線級戦力です。 それに対し秀忠に従う軍は、猛将榊原康政を筆頭に、「野戦の名手」徳川家康を支えてきた先頭集団。 この天下分け目の戦いの中で、手持ちの兵に不足するという不利をどのように克服したのか。 さまざまな、従来語られていた「説」があります。これを全体の流れを書きしるす中で、独立したコラムを儲けて論を述べています。これが全体で11あります。
書き手に恵まれると歴史はまたいろいろな面で楽しいものです。うん。(2024/12/1) 読書メーターの記録より 読了:2023/7/14 |
|||||||||||