トップへ戻る 作家/分野 一覧 |
|
 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |
|---|---|---|---|
| M110-001 | ミッドウェー海戦 第一部 知略と驕慢 | あの海戦の陰にあったもの | |
| M110-002 | ミッドウェー海戦 第二部 運命の日 | あの海戦の光と影 | |
| M110-003 | 作家と戦争 | 昭和2年に生まれた二人の作家 | |
| M110-004 | 空母瑞鶴 ソロモン前線へ | 南太平洋海戦以後の海軍の戦い | |
 |
Ver. 3.02 |
|---|
| 管理番号:M110-001 | 52J 戦史・戦争ノンフィクション(日本) |
出版社:新潮社 | |||||||
| 書名:ミッドウェー海戦 | 第一部 知略と驕慢 | ISBN978-4-10-603706-1 C0331 | |||||||
| 新潮選書 | 価格:1600Yen | ページ数:400P | 本のサイズ:130×190SC | ||||||
| 初版発行:2012/5/25 | 購入:2016/3/28 | ||||||||
 はじめに と題された序章は、この文章で始まります。 はじめに と題された序章は、この文章で始まります。
読み始めての感想なのですが、正直この方の句読点の使い方に馴染みにくいところがあります。個人の趣味といったらそう言うことでしかないのですが、それでも読み進めていくうちに、この本の魅力がそれ以上あることがわかり、これはありがたいと思ったもの。 閑話休題。 史上最強の艦隊が出港するところを見送る山本五十六海軍大将の姿から始まります。場所は、瀬戸内海、柱島錨地。戦艦大和の後部上甲板。1942年5月27日。 この日瀬戸内海を出発したのは、水雷部隊である第10戦隊、旗艦長良と12隻の駆逐艦。第8戦隊の重巡利根、筑摩。第3戦隊第2小隊の戦艦榛名、霧島。第1航空戦隊の空母赤城、加賀。第2航空戦隊の空母飛龍、蒼龍。そして随伴タンカー4隻。 翌日、サイパン島より第二水雷戦隊と、陸軍の一木支隊、海軍陸戦隊を運ぶ輸送船が出港。そのまた翌日、広島港より第2艦隊の空母瑞鳳と第4戦隊の重巡愛宕、鳥海。第5戦隊の重巡妙高、羽黒。第3戦隊第1小隊の戦艦金剛、比叡。第4水雷戦隊の旗艦由良と8隻の駆逐艦。それを支援する第7戦隊の重巡三隈、最上、熊野、鈴谷。 さらに26日、北方のアリューシャン列島のアッツ島、キスカ島攻略部隊も出撃します。第5艦隊、第4航空戦隊その他の部隊。 それを後援するため29日に出撃する主力部隊は、第1戦隊の戦艦大和、長門、陸奥を始めとして、戦艦7、軽巡3、空母鳳翔、その他。参加艦艇145隻。当時の世界でも最強と言っていい戦闘部隊でした。 しかしこの大作戦は破綻し、日本海軍は無残な大敗を喫します。なぜか。 この謎を、開戦後70年たって見直したのが、この本。はたしてどんな新しい視点があるのか。 まず、山本司令部の様子。おそらくこの時代で最も日米の戦力差と国力、そして戦争遂行能力を見切っており、そのアメリカを圧倒するには続けざまの勝利を得て精神的に追いつめるしかないと思っていた連合艦隊司令長官・山本五十六大将。戦術家としての自信を持ち、奇策で勝利を収めた勝利体験でますます増長してミッドウェー作戦を強行する連合艦隊先任参謀・黒島亀人大佐。砲術出身の超エリートで艦隊派のお目付役的な頑固者でプライドの高い連合艦隊参謀長・宇垣纏中将。 この三人ですら意思統一ができていなかった連合艦隊の 「総意」 というものが、従来日本海軍が温めてきた持久戦ののちに艦隊決戦に持ち込んで勝利するという、日本海海戦の勝利の延長線上にある戦略を守らんとする軍令部と真っ向から食い違う。しかしその軍令部、そして太平洋での戦略にまったく関心を持たなかった陸軍の意向を、ハワイ奇襲作戦の英雄、作戦の神である山本大将の権威が押し倒して、ミッドウェー作戦が進行します。 その中で、孤独な本心を手紙に残す山本五十六。その心を残した手紙を、戦後に公開して山本を愛した友人たちの憤激をかった河合千代子の話。 空母飛龍の掌航海長、すなわち航海長の補佐で航海部門の下士官のトップの地位にある准士官・田村士郎兵曹長に対して、
この重大な大作戦の直前に、すでに決まったことだからと言うことで定期人事異動が行われたことで、組織体系ががたがたになったにていたらく。指揮官たちの手足となる部下たちがさまざまに交替させられ、ハワイ以前より猛訓練を重ねて実績を上げたチームが再起動せざるを得なくなったのが、なんとミッドウェー作戦の一ヶ月から二ヶ月前。 空母飛龍の新任の飛行長となった川口 早くから航空攻撃の優位性を主張してきた飛龍艦長加来止男大佐にとって、飛行隊の指揮官たち、艦の守りの要である見張員、航海関係の士官たちの作戦直前での交替は、腹立たしい事この上ない。 第二航空戦隊の二番艦蒼龍の艦長は、柳本柳作大佐。「海軍の乃木さん」「融通のきかないコチコチの石頭」「兵学校44期二聖人の一人」などとあだ名されるくそ真面目で取っつきにくい。ゆっくり身体を休めるのは罪悪だ、とでも思いこんでいるような生真面目、不器用さ。求道一路という言葉が浮かぶ、清廉な人。幸運なことに、この蒼龍では他艦のような人事異動の波はかぶらず、艦攻隊などはほぼ真珠湾攻撃時のレベルを保っていたそうな。 とはいえ、あの時とは違い、あまりにもずさんな機密厳守態勢と慢心気分は、蒼龍艦攻隊の阿部平次郎大尉を憤慨させます。 敵方にまわるチェスター・W・ニミッツ大将は、ワシントンの人事局長からいきなり、先任順位で言うと27人の提督を飛び越えて海軍少将から大将に進級して太平洋艦隊司令長官に任じられた人。前任のキンメル大将こそ更迭されたものの、司令部の幕僚にはいっさい非難の言葉を与えず留任させ、真珠湾攻撃で士気が下がりきっていたハワイの海軍司令部を叩き直した人。 さらにアメリカ軍の沈滞した士気を上げるため、無茶を承知でドゥリットル東京空襲作戦を行い、見事に成功させています。 情報によって日本軍のミッドウェー作戦はほぼ掌握していたものの、戦力としては日本軍に劣る航空部隊と三隻の空母を保有するのみ。これを迎撃させるための第16機動部隊の指揮官として、勇猛果敢なウィリアム・ハルゼー中将(兵学校卒業時でいうとニミッツの一期上) を予定していたのですが、彼が重度の皮膚病で倒れてしまったのでやむを得ず後任に、ハルゼーの提案をうけてレイモンド・A・スプルーアンス少将を任命します。 もうひとつの第17機動部隊指揮官フランク・J・フレッチャー少将は、これに先だつ珊瑚海海戦での慎重・消極的な作戦行動が非難されていましたが、ニミッツが留任させ、再戦の機会を与えます。 この時点で、おそらく史上最強の海上部隊であったであろう第一航空艦隊を率いるのは、南雲忠一海軍中将。熱狂的で一歩も譲らない艦隊派の領袖の一人として名を上げ、山本五十六が不信視している人物。水雷部隊の指揮官としての実績はありましたが、彼の本領はむしろ事務官僚としてのものであったという。 几帳面で真面目に一心に事務処理をこなす人。その一方で航空戦の指揮や作戦内容についていっさい関わりを持たない。航空参謀が起案した作戦案を参謀長がサインすれば、そのまま無条件で裁可するだけ。進取の気質に乏しい守旧派将官。しかも小心。 それを補佐する南雲の腹心である参謀長草鹿龍之介少将は、鉄砲屋すなわち砲術専攻であり、創生期の海軍航空隊の発展に努めた人物ではあったものの、発想は海軍官僚そのもの。ハワイ作戦の功労者、特に戦死者を全員二階級進級させることに熱心に取り組んだことは、その現れか。 航空消耗戦、相手を叩きのめすまで執拗に戦う戦法を邪道と決めつけ、機をうかがって強烈な一撃を浴びせてさっと引く戦法に美学を求める人であったという。前線では艦橋で泰然自若としている、と本人は言うが要は腰が抜けているだけ、と言われたそうな。 となると、重要となるのが航空甲参謀源田実中佐。首席参謀大石保中佐が部下の進言に鷹揚にうなずくのを美徳と考える人であるので、彼一人でこの強大な戦闘部隊を動かさなくてはならない。彼は共に協力して運営すべき航空乙参謀吉岡忠一少佐の介入すらいっさい許さず、独力でこの艦隊の航空作戦を立案します。 ハワイでの大成功がさらに彼を増長させ、もはや誰も彼の決定に異を挟めない。 日本海軍が必勝を期して、アメリカ陸海軍が決死の覚悟で守りを固めていた時、6月2日、クェゼリン環礁に置かれた第六艦隊、すなわち潜水艦部隊の基地で、米空母の特徴的な通信波を傍受したそうです。ここにもまた、司令長官を務める小松輝久中将にまつわるドラマがありましたが、それは別の話。 この情報はただちに艦隊参謀長の了解の元、艦隊司令長官名で軍令部総長、連合艦隊司令部、機動部隊司令部、先遣部隊の格潜水艦当てに打電されます。しかし、南雲機動艦隊ではこの重要な緊急電報を受け取っていなかったという。 あくまで、敵空母の情報はない、という状態で決戦に臨んだのだそうな。 しかし、と第六艦隊通信参謀・高橋勝一少佐はのちにこう言います。
友永丈一大尉第一次攻撃隊の総指揮官となった理由には、なにか驚かされるものがあります。空母・赤城の飛行総隊長であった淵田美津雄中佐が虫垂炎で出撃できなかったことは事実ですが、空母・加賀に飛行隊長楠美正少佐がおり、友永より兵学校二期先輩だったのです。しかし彼が総指揮官となったのは、こんな事があったから。
しかし、この時点でなお、日本海軍機動部隊は一つの戦力としてみる限り世界最強だったといっていい。アメリカ軍に情報の優越があり、日本軍に慢心と制度上の欠陥があったとしても、です。 その慢心と制度上の欠陥がそれ以上大きくならず、戦場の運が味方すれば。勝ち戦の驕りがなければ。 重巡・利根の偵察用零式水偵のカタパルトが故障しなければ。 重巡・筑摩の偵察機、筑摩一号機が雲の上を飛ばず、雷雲を決して海面を注視していたなら。そしてその機長が、米軍の空母機と空中戦をしたことを報告していたなら。 運命の時はせまります。(2016/9/5) |
|||||||||||||
 |
Ver. 3.02 |
|---|
| 管理番号:M110-002 | 52J 戦史・戦争ノンフィクション(日本) |
出版社:新潮社 | |||||||
| 書名:ミッドウェー海戦 | 第二部 運命の日 | ISBN978-4-10-603707-8 C0331 | |||||||
| 新潮選書 | 価格:1700Yen | ページ数:448P | 本のサイズ:130×190SC | ||||||
| 初版発行:12/5/25 第3刷:12/9/15 | 購入:2016/4/11 | ||||||||
 1942年6月5日午前6時15分(現地時間)、総隊長友永大尉がミッドウェー島の二つの小島を眼下に納めたときから、下巻は始まります。しかしこの接近はすでにPBY飛行艇やレーダーによって捕らえられ、二つの島の滑走路から迎撃の戦闘機が発進しています。 1942年6月5日午前6時15分(現地時間)、総隊長友永大尉がミッドウェー島の二つの小島を眼下に納めたときから、下巻は始まります。しかしこの接近はすでにPBY飛行艇やレーダーによって捕らえられ、二つの島の滑走路から迎撃の戦闘機が発進しています。この緊迫した戦場へ、日本軍の大攻撃部隊は、レーダーによる捕捉をまったく気にする様子もなく三千から五千メートルの高度で堂々と進撃したという。自信というより無防備、無邪気、脳天気といわざるを得ない。これは、驕りというより無能というべきかもしれません。 ミッドウェー島攻撃が不徹底に終わり、攻撃部隊からの状況報告が上がります。敵基地の高角砲いまだ健在、滑走路は小型機の発着可能。 この情報を受けてなすべきであったのは、結果判断かもしれませんが状況に応じた対応。敵高角砲と滑走路の破壊。
この状況判断には、裏があったと森氏は書きます。
戦いに最もふさわしい指揮官が最高指揮権を持たず、敵の必死の反攻で壊滅的な打撃を受けて〝泰然として腰を抜かしていた〟司令部の功罪をどう描くべきか。さまざまな構造的欠陥を持ち、劈頭の奇襲の成功に自惚れ、戦争の意味を持たず、敵国の姿・実力も知らず、40年近く昔の成功体験に酔い、彼らはこの戦場にあった。 にもかかわらず、日本海軍は強かった。正しく運用されれば、鎧袖一触とはいかないにしても、勝利を収められてなんの不思議もなかったのです。 いくつかの例外を除けば。
しかし確たる理由もなくこの命令に反し、しかもいっさい状況報告をせずに全速で額行動を取り、途中で自分の艦隊の重巡が衝突事故を起こしたにもかかわらずそれを放置して、完全に沈黙を守ったまま戦場を去っています。 この戦場で戦う男はいます。上級指揮官の失態をいっさい口にせず、自分が指揮できる状況になった瞬間に自分の存在を示す。
航空戦とは、それまで海軍の将兵が考えていた砲撃戦、水雷戦のように時間がかかるものではない。瞬時の判断と戦運によってたちまち決着がつくものであり、しかもその過程で短期間に恐るべき彼我の損害が生まれるものである。これを、日本海軍の将帥のみならずアメリカ海軍の提督たちもこの戦いで思い知ったのでした。 この教訓は、どのように受け継がれたのか。 日本の4隻の主力空母が壊滅したのち、洋上に漂う赤城をどうするのかを決断したのは、山本五十六自身。首席参謀たる黒島亀人は、作戦失敗が自分の失態であることを感情的に捕らえ、司令部は混乱します。その混乱の中で、撤退戦をきちんと指揮したのはそれまで艦隊派として浮いた存在だった宇垣纏参謀長。
こうして、赤城艦長の青木泰二郎大佐は、沈められたた空母のなかで〝ただ一人生き残った艦長〟の汚名をかぶり、苛酷な人事をうけます。これが、海軍だけでなく当時の日本の姿。当時だけだろうか。 そして敗残の南雲司令部は。
山本五十六の先進性と政略に関する視点は正しかったかもしれません。しかし実際の戦争に当たって彼の才覚は、連合艦隊司令長官でなくその上かその下、海軍大臣か機動部隊指揮官としてのものだったのかもしれません。 ただでさえ硬直した日本海軍の人事体系の中で、これが最大の人事ミスであったのかも。 むろん、他の将兵のミス人事に関する論を重ねればきりはないのですが。 戦闘詳報、ミッドウェー海戦における戦闘記録の中で、「本日敵出撃ノ公算ナシ」 の信号の記録はないそうです。それ以後のいかなる戦史にも登場していないそうです。昭和51年まで。 この年の3月19日、著者・森氏は当時吉岡興業という会社の社長となっていた元航空乙参謀・吉田忠一氏にインタビューしました。 何時間にもわたる会話の中で、南雲中将への批判論にたいし、長官を敬愛する吉田氏はかんしゃく玉を破裂させて反論します。 そして、いう。
なんというべきか。 この失態は、あの時代の日本人の失態です。 今の日本人に、これと同じメンタリティが残っていないか。よく考えなくては。 そんな事を考えつつ、読み終わりました。 今の時代になって読めるようになった歴史です。言葉などにフィクションが入っていることは充分考え裸得ますが、読んで損はない。 誇るべき事と、恥ずべき事。両方に正しく向き合わなければ、歴史を学んだとは言えないのだから。(2016/9/10) |
||||||||||||||||
 |
Ver. 3.03 |
|---|
| 管理番号:M110-003 | 63 文学評論・解説 | 出版社:新潮社 | |||||||
| 書名:作家と戦争 | 城山三郎と吉村昭 | ISBN978-4-10-603644-6 C0395 | |||||||
| 新潮選書 | 価格:1500Yen | ページ数:400P | 本のサイズ:130×190SC | ||||||
| 初版発行:2009/7/25 | 購入:2016/6/15 | ||||||||

城山三郎(1927/8/18-2007/3/22)と吉村昭(1927/5/1-2006/7/31)は、どちらも昭和2年生まれ。どちらも、少年時代は軍国主義一辺倒の中で育ち、18歳で終戦を迎えた世代であり、軍隊生活をギリギリで体験しています。 その体験がさまざまなものに影を落とし、作家となった二人には奇妙な共通点がある、という。 この本は、そうして長い昭和の時代を過ごした二人の軌跡を追ったもの。 第一部 城山三郎の戦争 皇国少年として幼い頃を過ごした城山三郎こと杉浦英一は、明治33年に生まれた杉本五郎という陸軍軍人の書いた 『大義』 という軍人精神の教えに心服していたそうな。尊皇思想の根源を 「禅」 の思想に求め、厳しく自分を律して純忠である事を唱えたもの。 しかし年長になり、ぎりぎり三ヶ月の海兵団での生活をへて、大人たちの醜い欺瞞を目の当たりにします。平然と部下を虐待する軍隊というものに対する失望も。さらに戦後の左翼勢力の台頭にとまどう戦中世代としての姿。 その時代を過ぎて生まれた、作家・城山三郎とはどんな人物だったのか。 戦争に対する思いは、どのように変化し、結晶化していったのか。 第二部 吉村昭の昭和 小説家として身を立てようと勤務のかたわらで執筆にいそしんだ吉村昭は、芥川賞を何度かのがします。しかし、四度の落選。
もしそうであったなら、「戦艦武蔵」、「総員起シ」、「陸奥爆沈」といった戦史小説や、「桜田門外ノ変」、「天狗争乱」、「彰義隊」といった歴史小説も、挑戦されることなく終わり、大衆性の乏しい高尚文学的なものが書き連ねられたであろう、とのこと。 そうでなかったことは、文学界にとっても本人にとってもよかったのか。 二人の小説家の生涯と交流、少年期の戦争、青年期の葛藤、文学への思い。微妙な路線の違い。 著者の綿密な取材と緻密な構成は、この二人の大作家を余すところなく描写し、対比しています。これはなかなかのもの。 そういう意味で、記念碑的なものなのだろう、と思う。 ただし、と鐵太郎は思う。 文学というものをどのように捕らえるのか、という意味において、鐵太郎は異なる視点を持っているんだろうな、と気づきます。 高みに上がるための過程としての文学、純文学という世界に至る修練。これは鐵太郎には理解できていない。 城山三郎と吉村昭。どちらの著作も好きです。しかし文学者の葛藤は、特に面白いとは思わなかった。 純文学の基本である私小説も、好みではない。 文学とは読んで楽しめるもの、あるいは心地よい一夜くれるもの、と考えるようになった鐵太郎の好みを規準として。 だから、意見には個人差があることを前提とした上ですけど、読んで楽しくない、感動できないので、この手の本は苦手といって終わります。まァ、こんなこともあるさ。すまんね。(2016/10/14) 読書メーターの記録より 読了:2016/8/4 |
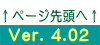 |
|---|
| 管理番号:M110-004 | 52J 戦史・戦争ノンフィクション(日本) |
出版社:潮書房光人新社 | |||||||
| 書名:空母瑞鶴 ソロモン前線へ | [空母瑞鶴戦史]ラバウル航空撃滅戦① 甦る精鋭 新生航空隊の戦い |
ISBN978-4-7698-3399-4 C0195 | |||||||
| 単行本:令和2年9月「ラバウル航空撃滅戦(第一部)」 改題 潮書房光人新社 | |||||||||
| 光人社NF文庫 も-1399 | 価格:891Yen | ページ数:264P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2025/4/24 | 購入:2025/4/1 | カバー写真:提供・「丸」編集部 | |||||||
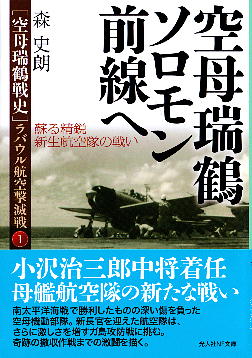 今(2025年)の時点でかなり新しい時代に書かれた太平洋戦争の戦記です。かつて著者が上梓した『勇者の海 空母瑞鶴の生涯』(光人社 2008年)、『空母瑞鶴の南太平洋海戦 軍艦瑞鶴の生涯 戦雲篇』(光人社 2014年)
の改訂かもしれませんが、確認できず。 今(2025年)の時点でかなり新しい時代に書かれた太平洋戦争の戦記です。かつて著者が上梓した『勇者の海 空母瑞鶴の生涯』(光人社 2008年)、『空母瑞鶴の南太平洋海戦 軍艦瑞鶴の生涯 戦雲篇』(光人社 2014年)
の改訂かもしれませんが、確認できず。副題を見るかぎり、ですが、空母瑞鶴戦史なのかラバウル航空撃滅戦なのか、よくわかりません。少なくとも瑞鶴の一代記ではない。 物語は、1942年11月9日、空母瑞鶴が第三艦隊と共に南洋のトラック等錨地より帰投して呉軍港に入港した二日後、第三艦体の司令長官であった南雲忠一中将が佐世保鎮守府司令長官に転出し、小沢治三郎中将が親補されるところから始まります。ミッドウェー海戦(1942年6月)の敗戦の後、南太平洋海戦(1942年10月)により一応の雪辱を果たしての勇退の形式を取りますが、南雲忠一という人は、ハワイ海戦からミッドウェー海戦での「(南雲長官は)泰然自若として腰を抜かしていた」「あれは南雲艦隊ではなく(航空参謀の)源田艦隊」と言われたように、空母を使いこなす勇猛果敢な名指揮官とはとうてい言えない指揮ぶりと評されます。 これに対する小沢治三郎は、水雷畑から軍政関連でキャリアを積んだ南雲と異なり、わずかな海外出張、海軍大学校教官勤務などを除くとずっと海上にあり、海戦時は金剛型戦艦の第三戦隊司令官職にあった人物ですが、海軍の年功序列に阻まれて機動部隊の指揮官にはなれませんでした。機動部隊の司令長官としては、優柔不断な老害となった南雲よりはるかに評価されていた人物。 その彼が、ようやく太平洋戦争で海の主役として躍り出た空母機動部隊の司令長官となったのは、緒戦の連勝を無にするミッドウェーの敗戦後、いやそのあとの、南雲が「名誉挽回のため一矢報いる機会」を与えてもらったあと。 実はその時点で、日本海軍の航空機動力はとんでもない打撃を受けていたのでした。未来の視点で見て、挽回できるかは微妙。
1942年11月14日、小沢治三郎中将は第三艦隊旗艦である空母瑞鶴に着任します。 六尺(181㎝)近い長身、兵学校から「鬼がわら」の俗称で知られる肩幅広く精悍な面構えで、それまで長官・参謀長共に覇気のない姿で沈滞していた司令部の空気を一気に変えます。 そして「幕僚ぎらい」のうわさのある、つまり作戦立案において綿密であると共に自分で作戦指揮ができる能力と活力を持っており、参謀長や幕僚たちを遠慮なく叱りとばしていたと言われるこの猛将のもとで、新規艦隊編成が行われます。 それからしばらく小沢中将の生まれ育ち、性格、海軍軍人として水雷屋で名を上げたこと、酒好き、芸者によくモテて宴会芸に長けていたこと、艦橋に上がれば無口でめったに口を開かないが、全神経をいつも張りつめていてどんな些細なことも見逃さないこと、などが語られます。
この言葉の真意は、「若い航海士だったら、曇りや歪みのありうるガラス越しに見張りをするなどもってのほか。常在戦場の心でガラスを下ろして双眼鏡を使え」ということ。直属上官でないのだから直接叱りつけるよりわからせるやり方のようです。 で、小沢提督中心に話が進むかと思ったら、話はもっと広がります。 第二章冒頭で語られる田中正臣少佐という人は、鐵太郎の記憶にありません。 読んでいると、著者はこの少佐を仇役にしようとしているのかと思われる節あり。 ミッドウェー、南太平洋海戦と戦いの中で搭乗員の消耗を続けた第三艦隊は、新しい搭乗員を迎えて訓練を開始します。その中で、真珠湾以来の古参組でもう内地教育部隊に移動してもおかしくない八重樫春造飛曹長に焦点が当たります。 この人は、真珠湾攻撃時の第二次攻撃隊に名前が載っています。その後の動向はわかりませんが、架空ではありません。ただしこの本の中での言動は、事実かどうかわかりません。 彼が知った新任の飛行隊長の名が、田中正臣少佐。彼は1937年の中国戦線の杭州攻撃が初陣で、旧式の三菱89艦攻数機で攻撃したものの中国軍の米国志願兵フライング・タイガースの戦闘機に迎撃され、当時の田中中尉の一機のみ空母加賀に帰還できたのだそうな。そのとき恐怖のあまり機から立ち上がれなかったとひそかに言われていますが、それ以外は目だった戦歴もないまま、このたった一つの「武勇伝」を大袈裟に語って「評判」を積み重ねていたのです。霞ヶ浦、大分などの航空隊ののち教育部隊に教官勤務したのち、空母飛龍の飛行隊長を真珠湾攻撃直前に解任されたのですが、どうやら第一線部隊の指揮官として不適と判断されたらしい。それが今回第三艦隊の飛行部隊総隊長になったのは、村田少佐・友永少佐と第一級の指揮官が失われたため。 この田中少佐の、「超低空高度雷撃砲」に、八重樫飛曹長は真っ向から異を唱えます。敵の電探も索敵技術も進歩している中で、そんな危ない戦法では全滅だと。 トラック等錨地で上陸した宴席の場で、実戦をくぐり抜けた経験からそんな戦法はできっこない、「ここは練習航空隊とはちがいますよ」と洩らしたのが疳にさわったらしい。酒の入った席ではありますが、「貴様、生意気だぞ」と田中少佐は八重樫飛曹長をこぶしで殴り付けたとか。 軍隊で、上が下を殴るのは日常茶飯事ですが、士官が兵を殴るのもあまり褒めたものではないという風潮があります。まして士官が下士官を殴るなど普通起きません。佐官が一番下の二等兵から昇進して「水兵の元帥」といわれた兵曹長(准士官)クラスを殴るとはもってのほか。殴られた八重樫飛曹長(海軍航空兵曹長)はその後すぐ、内地の宇佐航空隊教官に転勤命令が出たとか。 あり得たエピソードなんだろうか? よくわかりません。 第三章の中で、「追われた二人の日米戦争功労者」と題された一節があります。
情報班の指揮官は少将の弟ジョン・レッドマン中佐が就任しました。彼はミッドウェー海戦の際、日本軍の作戦目的はニューカレドニア方面だと主張し、ロシュフォートの情報とまったく異なる結論を出していた人。 ロシュフォートはレッドマン兄弟の権力欲、嫉妬により第一線を追い出されたのでした。彼抜きの海軍情報部は、のちに「ケ号作戦」の情報を日本軍が構想した通り、「撤収」ではなく「大攻勢」と錯覚したのでした。 日本側では、〝面倒くさい男〟が最前線から追われます。 当時の第二水雷戦隊、日本海軍最高の突進部隊として〝花の二水戦〟と呼ばれた水雷部隊の司令官は、 彼我の戦力と結果は、こちらは駆逐艦8隻(1隻沈没)、敵方は重巡4隻(1隻沈没・3隻大破)・軽巡1隻・駆逐艦6隻。 この圧倒的な勝利により米海軍から「不屈の提督 "redoubtable Tanaka"」と称賛されたにもかかわらず、田中提督は一月後に二水戦司令官を解任され、その後舞鶴警備隊司令官を経てビルマ方面根拠地隊司令官に左遷され、そこで終戦を迎えます。 人生そんなもの、か。 この本の最後は、第四章「奇跡のガ島撤収作戦」。 ガ島とは、日本軍が攻め込んで占領した最南端の島、ソロモン諸島ガダルカナル島。東京から直線距離で 5,450km。2.940浬。 この島に、陸海軍あわせて合計約3万2000名が上陸したのですが、米軍の反撃に遭い補給はまったく途絶え、最終的に戦死約1万4000名、行方不明約2500名という損害を受けても米軍の基地建設にまったく対抗できず、将兵は餓島と呪ったもの。 ここの将兵をなんとかして撤退させよ、という山本五十六連合艦隊司令長官のごり押しが、ついに天皇を含め大本営での決定に至り、行われたのが「ケ号作戦」。 ケ とは捲土重来を意味していたそうです。 この章で、三度に分けて行われた撤収作戦の経緯と結果が描かれます。 撤退、いやのちの「報道用語」で転進した兵員は、海軍が832名。陸軍は第一次作戦で5201名・第二次作戦で4760名・第三次作戦で1,972名で計11,933名、合計12,682名と報告されます。 何重にもなる幸運と果断な決行によって成功した撤退作戦ですが、むろんこれは日本軍の「終わりの始まり」の烽火。 瑞鶴はどこへ行ったんだ、と思いつつ第一巻おわり。(2025/08/09) 読書メーターの記録より 読了:2025/8/4 |
