トップへ戻る 作家/分野 一覧 |
|
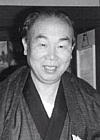 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |
|---|---|---|---|
| N050-001 | 八甲田山 死の彷徨 | 日露戦争前に起きた、ある冬の日の悲劇 | |
| Ver. 2.23 |
|---|
| 管理番号:N050-001 | 30 歴史小説・日本史 |
出版社:新潮社 | |||||||
| 書名:八甲田山 死の彷徨 | ISBN978-4-10-112214-4 C0193 | ||||||||
| 新潮文庫 に2-14 | 価格:514Yen | ページ数:336P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:78/1/30 第83刷:10/6/10 | 購入:2012/5/6 | 表紙イラスト:富岡惣一郎 | |||||||
 この本は、何度かひろい読みはしたけれど、本格的に読んだのは今回が初めて。 この本は、何度かひろい読みはしたけれど、本格的に読んだのは今回が初めて。衝撃的な内容については、何度読んでも変わらないのですが、今回何十年ぶりかで読み直してみると、いろいろなことに気づきます。 高校生、大学生のとき読んだものとは、読後感がぜんぜんとは言わないがけっこう違いました。 違いがあって、そこがいい。多分ね。 この企てに参加したのは、第五連隊と第31連隊。どちらも第八師団麾下の部隊です。 昔と違って今は、多少はミリ関係の知識がついたのですが、それでも第八師団には思い当たるものがない。番号からして日清戦争以後に将来に備えて拡張された陸軍の新しい部隊の一つでしょうが、日露戦争の黒溝台でいささか無様な戦いをした以外には、第二次大戦でも記憶がない。 八甲田山で雪中行軍した二つの連隊は、この師団に属します。第5連隊と、もうひとつは第31連隊。 これまた番号で考えると、この事件が起きた1902年頃で見るならば、片や日本陸軍創設のときからの歴史を持つ古参連隊、こなた数年前に編成された新参部隊。競争意識があって不思議はない。 はたして史実はどうだったのか分かりませんが、この小説(この本は、史実を元にしたフィクションです。そこを間違えると誤解が出ます)においてそれは鮮明に出ます。また、下級将校の中では互いに交流があったと言うことも。 軍隊という世界観で言うと、軍人たる彼らは一般国民とはかけ離れたエリート、というより選民意識があります。これは、かつて江戸時代、武士がその他の町民に対して持っていたものの延長でしょうか。旧士族出身が幅をきかせる士官たちの世界に、平民の立場で、しかも陸軍教導隊から下士官を経て這い上がった神田大尉(史実では 一般市民に対して、何の遠慮もなく命令し、要求します。渋る市民に対して、恫喝を平気で行い、意志を通します。軍の命令とは、武士のそれと同じく上意下達、上が何かを言えば無理とわかっていても下は従えというもの。 映画 「八甲田山」 において、一方の雪中行軍を成功させたヒーローでもある徳島大尉(史実では 映画では、一時道案内役を引き受けて軽やかに雪の上を導いてくれた秋吉久美子 演ずる滝口さわに対して、いかにも兵隊らしい敬礼でこれに謝していますが、実際は別な部落への案内されて到着すると、投げ与えるように50銭を銀貨を渡して後ろにまわれと怒鳴りつけます。
地元の案内人を先頭に次の村に入るなどと言う事が、滅相もないことだったのは、武家の時代と変わりはない。 その後、案内役をさせた次の部落の7人に対する苛酷な扱いは、目を覆わんばかり。軍人とは結局あんなものか。 むしろ、昭和期の軍人の方が、特に下級将校は、まだましだったのかも知れない。だから彼らは226事件を起こしたのか。 閑話休題。 本筋の、零下何十度にも達した極寒の中での苦闘の描写も、恐るべきものです。新田次郎という作家の技量を褒め称えるべきか。 なにより恐るべきは、死んでいく兵士たちが、常に士官たちに火を譲り、焚き火の前には立たず、ばたばたと死んでいくこと。士官たちは兵を犠牲にすることになんの痛痒も感じず、そして彼らもまた上官を、大尉どのを、少佐どのを救うために我が身を犠牲にする。これが軍隊。 このすさまじい世界を、なんの感想も交えず、淡々と描いているのが新田さんの文章のすさまじいところ。 いや、まいったね。 悪役となった山田少佐(史実では 神田大尉の部隊が、途中で遭難した徳島大尉の部隊とすれ違い、その中から三挺の小銃を持っていき、それがあとで問題になったというエピソードがあります。関わった将兵、特に神田大尉の苦悩は、大変なもの。軍隊という特殊組織の、エリートであるべき士官でなければこれは苦悩とはいえない。肩をすくめ、互いにうなずきあって「大人の判断」をすればすむこと。ふうむ。 しかしこれも、エピソード自体、実はフィクションらしい。なんと。 このヒーローとなった神田大尉も、日露戦争の激戦の中で戦死し、第八師団自体が全滅に等しい大損害を受けたそうです。歴史の歯車の何と無情なこと。 新田さんの筆さばきにすっかり嘲弄されました。こういう人に鼻面を捕まえられて振り回されるのは、本読みにとって快感というべきか。 ふむ、この作家の本、もっと読んでみたくなりました。(2012/8/16) |
||||||||||