 トップへ戻る  読んだ本の分類 |
|
 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |
|---|---|---|---|
| N071-001 | 「不屈の両殿」島津義久・義弘 | 戦国末期から江戸初期、島津家を守った二人 | |
 |
|---|
| 管理番号:N071-001 | 51 伝記・一代記・評伝 |
出版社:KADOKAWA | |||||||
| 書名:「不屈の両殿」島津義久・義弘 | 関ヶ原後も生き抜いた才知と武勇 | ISBN978-4-04-082341-6 C0221 | |||||||
| 角川新書 K-367 | 価格:1360Yen | ページ数:456P | 本のサイズ:新書 | ||||||
| 初版発行:2021/8/10 再版発行:2021/9/10 | 購入:2023/1/1 | 図版:耳川合戦図屏風(部分)(相国寺所蔵) | |||||||
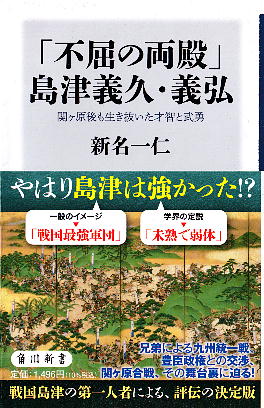 出だし、はじめに という序文の中で、著者は現代での島津義久・義弘兄弟や島津家の扱われ方について嘆いています。 出だし、はじめに という序文の中で、著者は現代での島津義久・義弘兄弟や島津家の扱われ方について嘆いています。
島津義弘の賭け』(山本博文)と、『島津奔る※ 』(池宮彰一郎)くらいしか見当たらず、そんなものかと思っていたもの。 ※この本、盗作疑惑などの理由で現時点で絶版です。 その中でスポットが当たるのは島津義弘の壮年期から老年期の活躍で、それ以前のこの兄弟についての情報は希薄でしたね、たしかに。 続けて序文で、
島津氏の由来は、鎌倉初期に源頼朝から しかし文明8((1476)年の桜島大噴火による政情不安もあって奥州家が衰退すると、本家から分出した庶家の島津 この抗争のさなか、相州家の島津 貴久は天文8(1539)年に島津本宗家の座つまり奥州家を継承して島津氏第15代当主となりますが、最終的に真の意味で「三州統一」となるまではこれから38年の年月を要し、天正6(1577)年に親子二代かけてようやく達成することに。 ですので、二兄弟の幼年期・青年期は国内平定で追われ、ある意味苛酷な実戦経験を積む場になったということもできます。 義久の元服は天文15(1546)年、14歳のこと。直後に迎えた室は父の腹違いの妹、つまり義久にとって叔母。義弘も兄とほぼ同じ頃元服し、迎えた妻はすぐ前にようやく貴久に従属した北郷忠孝の娘。 姻戚関係で勢力を確立するためのさまざまな手管がみられます。これも、勢力確立の手段。 義久46歳、義弘44歳に至って、父祖の悲願であった三州統一を達成します。それは、最大の敵であった大友勢を撃破した高城・耳川合戦の翌日のこと。このとき、16代当主となっていた義久が義弘に宛てて戦勝を祝した感状は、兄弟二人の初陣から書き下ろして統一事業全体に対する弟の功績を称え感謝したものだった、と著者は書いています。
こののち島津家は肥後から北上し、筑前・豊前・豊後の一部を除き九州の大半を勢力下に収めます。このような強大な軍事力や朝鮮出兵や関ヶ原での義弘の戦いっぷりなどで、島津家は〝九州最強の戦国大名〟というイメージがついています。 が。
とはいえ、なぜそのような評価がついたのかについて著者が研究家の言葉を拾って調べてみると、 ①朝鮮軍役のとき、一万の兵を割り振られながらそれだけ動員できなかったこと⇒国人を統合する実力がない未熟な国 ②島津氏の 程度でしかないので、根拠としては弱いのではないか。 そこで筆者が検証する戦国島津家の姿とはどうだったのか。 重臣談合からのボトムアップの形を作ることで国をまとめた義久の政治とはどういうものだったのか。 国をまとめる義久に対し、その名代として義弘が前に出たときどうなったのか。 なるほどね。 「名代」とは、天正12(1584)年に義久の命により重臣談合が行われ、その中で提唱された話。52歳になっていまだ男子を得られず健康に難があった義久が、自分の代わりに肥後平定の陣を指揮する者として2歳年下の義弘を指名することを望んだためのもの。これにはもちろん後継者問題も絡みます。 この談合の結果を義弘に伝えますが、義弘は二ヶ月以上固辞したあげく受諾します。このとき、「名代」と共に「守護代」とも呼ばれたらしい。 むろん、江戸時代に入ってのように、お家存続のために形式的な後継者を立てるのではなく、一族を取りまとめられる即戦力の後継者を選ぶのだから、選択肢は義弘しかいません。まさに、島津氏の九州統一戦と共に秀吉による「天下静謐」、つまり天皇の名前まで使った全国平定が行われ、九州全土を秀吉の意図による平和の強制が行われようという時です。 天正14(1576)年の時点で、義久としては薩隅日三ヶ国に加え肥前・肥後・筑後を実効支配しており、その六ヶ国を自分の分国と認識しています。しかし秀吉の「国分案」では、島津家は薩摩・大隅・日向・肥後半国のみを安堵するとのこと。筑前侵攻か豊後侵攻かで国論が割れ、神慮つまり このあとの、羽柴秀長を総司令官とする上方軍と島津との戦いの経緯の結果、島津家は降伏して領土を大幅に削られます。義久は出家して「龍伯」と名乗り、島津は薩摩一国となるのですが、ここで秀吉の「一本釣り」つまり直接知行地を与えて自分直属の大名にする手が使われます。その結果、義弘が「新恩地」として大隅一国が与えられ、早くに秀吉に降伏した この終戦処理の中で、秀長の陣に同行していた島津四兄弟の末弟・家久が病死します。秀長による毒殺と書かれた記録もありますが、ここでは真相は不明としています。 九州統一の戦いとそれに続くこの敗戦で、島津家中で様々な混乱が起きます。処分に抵抗する家臣あり、謀反を起こす領民あり。そもそもの問題は、この混乱の中で地頭クラスの重臣の統制を取りきれない島津家中の問題なのですが、これが落ち着くまでに長い時間を要します。
兄義久と弟義弘の、島津家中の中での方針に違いはなかったはずですが、道が違ってきたのはこの後。 天正16(1588)年閏5月、義弘は大坂城で秀吉に見参します。その翌月「従五位下侍従」に叙任し「公家成」することで、豊臣政権の「公儀」を担う「豊臣大名」となり、「羽柴薩摩侍従」と呼ばれます。さらにその翌月「従五位上」い序され、官職で兄義久を上まり、位階でも兄と並びます。豊臣政権としては、これによって義弘を島津家の当主と認め政権内に取り込んだ形になりました。 しかし国元では、島津本宗家つまり この結果、
この二人に隙が生じたのは、時期的には「唐入り」前夜あたり。京に在籍して秀吉の臣として務めている義弘と、健康に不安を抱えながら国元で経営に腐心する義久の間で考え方にズレが生じます。これを山本博文氏は
しかし二派に分裂したという理解ではおかしくないか、というのが著者の見解。そもそも両者は対等ではなく、義弘の勢力は彼に直接従っていて信頼できる少数の重臣に限られ、彼自身の領地の外の、島津家全体には存在しないといっていい。 唐入りの軍役のための日本全体の土地台帳作成の命が下り、義弘が国元の義久に伝えても、まったく進展しないという事態になります。義久としては戦国期以来の「重臣談合」方式で経営を行うため、秀吉の命令があると伝えられても即断できない。命令できない状態だったのでした。上意下達・即断即決ができない戦国大名のままの制度の欠陥が露呈します。 その結果、「唐入り」の動員がかかったとき、義弘がいくら国元に秀吉の命を伝えても、それを受けて義久が軍勢催促を申しつけても、国衆・重臣たちは誰一人責任を持って決断せず参集しないまま時ばかり過ぎます。一万人の軍役を課せられながら、義弘の元には千人も揃っていなかったため、「日本一之遅陣」と嘆く手紙を国元に送ります。 この惨状は、兄弟が二派に別れていたためというより、島津家中の問題のしわ寄せが秀吉麾下にいる義弘にいったというべきか。そしてその先頭にいると思われる国元での当主義久は、国元での調整、安定を重視しバランス感覚で徐々に国内統制を行おうとし、遠く京に入る義弘は、日本全国を統制して朝鮮に向かおうとする豊臣政権を目の前で見て、焦燥感に駆られています。 この温度差が、形としては同じ志を持つ「両殿」の施政に違う道を歩ませます。 この原因を、池波彰一郎さんは「島津奔る」の中で義久の「妬心」である、中央で生き生きと活躍する弟への嫉妬である、と断じました。読んでいた当時はなるほどと思ったのですが、今はどうかと思う。 義久は、天正10(1582)年ころよりたびたび「虫気」を発症し病臥することがあったそうです。また、本人も自覚していますが、老いと短気のため我を忘れることも度々だったとか。義弘は兄が、そんな時には諫めてほしいという願いをされても、遠慮して兄を常に立てる姿勢を取っていたらしい。長年兄に小言を言われつつもじっと耐え忍び、反論して兄の機嫌を損ねれば家中が破綻することを恐れていたらしいことは、兄の元に養子として出した嫡男・ 国元で、旧弊な家臣をあやしながら経営していた兄、兄へ京の情勢を報告し、動いてくれない家中に苛立ちながらも強く兄を責められない弟。 そんな方向で考えると、義弘が「日本一之遅陣」と嘆いたことも関ヶ原での寡兵も、やむを得ざる事態だったのかも。 そういう状態を十分承知していた豊臣方、石田三成などでも、義久を隠居に追い込む事ができない事情もあります。義久とその側近のみが、大きな利権を持つ琉球との交渉窓口を持っており、義弘はまったくそれに参加していなかったこと。 なるほど。 複雑な事情は、この本のようにうまく解説されるとすっと頭に入ります。そういう目で見ると、島津の家の複雑さ、「両殿」という奇妙な制度の意味、そして義久・義弘の間柄も、確認できます。 なるほどねぇ。 この本で知ったトリビアを三つほど、上げておきます。 朝鮮出兵すなわち文禄・慶長の役の末期、慶長3(1598)年に行われた
また時代は下って関ヶ原での脱出行の話。 慶長5年9月15日の関ヶ原合戦での島津義弘の思惑と失望と決意は飛ばします。何万の東軍の中に孤立した島津の1500の寡兵は、前代未聞の敵のいる方向への戦場離脱を敢行し、わずか数十人になって脱出したのですが、そのおりの話。
で、このとき義弘は66歳。生涯最後の戦いと考えて死に花を咲かせるとまで考えていたのですが、国元ではまた違う戦いも行われました。 関ヶ原の戦いの直後、戦争の帰趨を見定めて九州の東軍方の諸将が主人不在の西軍の領土に襲いかかります。 小西行長不在の肥後などが討ち果たされる中で、島津は万全の防御態勢を敷いて迎え撃ち、国境を守り抜いた上で、10月22日和睦の書状を提出します。この中の書名は、島津忠恒・義久の連署。しかも。
この「両殿」の、硬軟取り混ぜた姿勢により、島津はそののち様々な政治工作を経て62万石の石高を安堵されます。 実は義弘の苦労はそのあとも続き、いろいろ愚痴もあるのですが、それらすべて込みでこの歴史は面白い。 掘り出してくださった著者・新名さんに感謝です。(2025/3/5) 読書メーターの記録より 読了:2023/4/28 |
||||||||||||||||||

