トップへ戻る 作家/分野 一覧 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 書 名 | 翻訳者 | メ モ | |
|---|---|---|---|---|
| O019-001 | 紅はこべ | 西村孝次 | フランス革命時、仏国貴族を救い出す謎の快男児 | |
| O019-002 | 隅の老人の事件簿 | 深町真理子 | シャーロック・ホームズのライヴァルたちの一人 | |
| Ver. 2.5 |
|---|
| 管理番号:O019-001 | 24 近代冒険小説 |
出版社:東京創元社 | ||||
| 書名:紅はこべ | 発行:1905年 | |||||
| 原題:The Secret Pimpernel | 創元推理文庫Fオ1-1 | |||||
| 翻訳:西村孝次 | 価格:\640 | ページ数:389P | 本のサイズ:文庫 | |||
| 初版発行:70/5/22 第33刷:03/9/19 | 購入:2006/2/18 | 表紙イラスト:レズリー・ハワード主演 『紅はこべ』ユナイテッド・アーティスト 1935年 |
||||
 先日、TVでドラマ化された「紅はこべ」が放映されました。面白い。歴史的にどうだったのかはちょっと怪しいのですが、こんな冒険譚もまたよきかな。 先日、TVでドラマ化された「紅はこべ」が放映されました。面白い。歴史的にどうだったのかはちょっと怪しいのですが、こんな冒険譚もまたよきかな。というわけで、何十年ぶりかでこの本に会いに行きました。でも、子供向けの訳で何度か読みましたが、創元版の「紅はこべ」は、実は始めて。今まで読んだ本は、どうやら抄訳・意訳だったらしいですね。 舞台は1792年、革命の嵐が吹き荒れるフランス。 虐げられた民衆の怒りが革命となって爆発してから3年経っています。それまで特権階層であった貴族たちが、次々と処刑されていく恐怖の時代です。このフランス人貴族を次々と救い出し、イギリスに亡命させる謎の一団がありました。その首領の正体は不明。「紅はこべ」とだけ呼ばれています。 何者なのか。 いや、この先この本を語るなら、謎の答えを抜きにしては語れない。困ったな。(笑) この本の主人公、というか、スポットライトを浴びる登場人物は、元はフランス人であるマルグリート・サン・ジュスト。現在はイギリス貴族パーシー・ブレイクニーの妻です。二人は熱烈な恋愛結婚らしい。 ところが、貴族としてのプライドの高い夫と、フランス的な高慢さを持つマルグリートは、結婚後一日も経たない間に、ささいな言葉の綾で夫婦としての信頼を失い、今は仮面夫婦として外面だけの生活を送っています。夫は妻にあくまで礼儀正しく、気遣いを欠かしませんが、一片の愛情も示しません。妻もまた、冷ややかに頭を下げてそれを受け入れます。 しかし、心の中を思うとき、実はマルグリートは夫に対する愛情を失っておらず、密かに煩悶しています。 そこに登場する、謎の紅はこべとその一統。彼らによって救い出された旧知のフランス貴族。そして同じく旧知の、いまや革命側の有力者であるショーヴラン。陰謀の中に潜む陰謀。 紅はこべの正体とは? 二人の愛情は戻るのか? イギリスからフランスへと繰り広げられる冒険。 時代背景的にどうなのか、つじつまは合うのか、そんなことはあまり考える必要はありません。楽しめました。 この小品を元に、連続ドラマが作られたわけも分かります。物語としては一応完結していますが、悪役も健在だし、冒険の種もたくさんあります。決してこの作品の完成度が劣っているとは言いませんが、これを元にたくさんの冒険譚が作られたわけがよく分かります。 読者を引きずり込む面白さが小説の一大要素なら、この本は傑作の名に値するのではないかな。 (06/4/18) |
| Ver. 2.12 |
|---|
| 管理番号:O019-002 | 43 ミステリ近代以前 |
出版社:東京創元社 | |||||||
| 書名:隅の老人の事件簿 | ISBN4-488-17701-8 C0197 | ||||||||
| 原題:The Casebook of the Old Man in the Corner (1909-) | 創元推理文庫Mオ1-1 177-01 | ||||||||
| 翻訳:深町真理子 | 価格:\580 | ページ数:346P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:77/8/19 第17版:03/12/12 | 購入:2006/8/5 | 表紙イラスト:P.B.ヒックリング画 カバーデザイン:小倉敏夫 |
|||||||
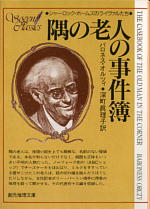 久しぶりにこれを読みました。 久しぶりにこれを読みました。買っていなかったことに気づき、面白そうなので買ってじっくり読み直しました。 シャーロック・ホームズのライヴァルの一人として、また安楽椅子探偵(アームチェア・ディテクティヴ)として、一時代をなした特徴的な探偵だとのことですね。何しろ特徴的なことに、名前がない。 無酵母パン製造会社(エイアレイテッド・ブレッド・カンパニー)のノーフォーク支店、略称「ABCショップ」という軽食喫茶店と言う店があります。そこで、主人公であり聞き役である「イヴニング・オブザーバー」紙のポリー・バートン記者の向かいに座り、横柄に話しかける変な老人がいます。 青ざめた顔、痩せこけた体。禿げ上がった髪をなでつけ、内気そうに、神経質そうに、手にした紐をいじり、複雑な結び目を作ってはほどく。 犯罪に謎などない、と言いきり、迷宮入りの事件や一見解決した事件について次々と独特な推理を働かせ、鮮やかに全く別な解決策を見せてくれます。 安楽椅子探偵とはいいながら、裁判所などに足繁く通って情報収集しているところを見ると、結構活動的。というよりはおせっかいか。 同時に、かなり独断的で鼻持ちならないほど自信家ですね。 とはいえ、お話を読み返して、これはホームズのライヴァルではない、と思いました。 人間的な深みとか、文化的な面白さがない。キャラクターもあまりにステレオタイプ。 トリックとして面白いものがあります。しかし、裁判とか審問の席で取り調べが行われ、衆人環視の中で新たな証拠が提示されて無罪を勝ち取るなどと言う、無茶なパターンが多い。警察の捜査とか裁判とかについて、作者の知識を疑いたくなりますな。 最後の事件など、消化不良と言うより、それで何が言いたいの、と思ってしまったのですよ。 一番唖然としたのは、「商船<アルテミス>号の危機」でした。と言うより、この短編集の評価を決したのはこの一編ですね。 内容のトリックはまあまあ。しかし描かれたお話は何? 時は1903年、日本にとってこの時代は大変な意味を持ちます。1902年に対露政策を目的とした日英同盟が締結され、1905年に日露戦争が起きます。英国にとって、東洋の野蛮国であろうがどうであろうが、日本は味方、ロシア帝国は敵であったはず。少なくともそう思っていました。 ところが、オルツィはそうは書かなかった。陰謀をもくろむ卑怯なスパイ国家・日本に扇動された許すべからざる事件である、と断じています。正当なるロシア帝国の、土台を揺るがす犯罪的革命家が英国の商船に妨害行為をした、という。 その英国船とは、卑劣な東洋の日本に対抗して旅順港を守るロシア軍に、高性能速射砲を輸送する途中だったのだそうな。旅順に急行する<アルテミス>号に、直前に敷設された機雷原の海図を届けようとする任務を負った英国海軍大佐の手元から、その秘密の海図が盗まれたのだという。どう見てもこの英国軍大佐、売国奴なのですが。 オルツィにとって、国際情勢や国家の意志より、ロシア帝国を揺るがす不逞な革命家や極東の生意気な小国の方が憎かったのでしょうね。 それとも、当時の英国人は本当にそう思っていたのか。 英国という国は、同盟関係にある国の敵に対して、平気で高性能兵器を売る国なのか。 いや、多分オルツィ女史がそう信じていたのではないか。 ああ、この人は庶民を見下ろし、野蛮人を軽蔑する貴族だったんだね、最後まで。 敵国ロシア帝国の南下政策を押さえるために、英国政府は従来のどこにも与しない政策を棄ててまで日英同盟を結んだ。そして旅順港は、日本にとってと同時に英国東洋艦隊にとって最大の障害であり、日本陸軍はこの攻略に大変な犠牲を払った。 しかも日本は、当時諜報戦に関しては全くの素人。欧州を舞台にしたスパイ活動など、日露戦争以前には不可能でした。 英国人の中で、東洋の新興国への侮蔑がなかったとは言いませんが、これが歴史の真実であるはず。 ま、そんなわけで、それ以後のトリックも面白いところはあったのですが、世界観が違うという印象に隠されてしまいました。 いや、正確に言うと作者の世界観らしきものが不快でした。 残念と言うべきか、どうなのか。悩むところです。 (06/10/26) |
 本名:バロネス・エムスカ・マグダレーナ・ロザーリア・マリア・ヨゼファ・バルバーラ・オルツィ・バーストウ。ハンガリー生まれの女流作家。ハンガリーの古い貴族の家柄の末裔。バロネスとは、男爵夫人のこと。
本名:バロネス・エムスカ・マグダレーナ・ロザーリア・マリア・ヨゼファ・バルバーラ・オルツィ・バーストウ。ハンガリー生まれの女流作家。ハンガリーの古い貴族の家柄の末裔。バロネスとは、男爵夫人のこと。