トップへ戻る 作家/分野 一覧 |
|
 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |
|---|---|---|---|
| O034-001 | 英国軍艦勇者列伝 | ロイアルなネイヴィーたちへの哀惜と愛惜 | |
| O034-002 | 英国軍艦勇者列伝2 | 「なんだか蛇の目のフネだから」より、その2 | |
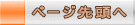 |
Ver. 3.01 |
|---|
| 管理番号:O034-001 | 52 戦史・戦争ノンフィクション | 出版社:大日本絵画 | |||||||
| 書名:英国軍艦勇者列伝 | Legend of British Fighting Ships | ISBN978-4-499-23086-5 C0076 | |||||||
| 価格:2600Yen | ページ数:240P | 本のサイズ:135×195HC | |||||||
| 初版発行:2012/6/14 | 購入:2014/8/14 | カバーイラスト:佐竹政夫 | |||||||
 表紙絵は、荒海を突っ切るトライバル級駆逐艦。ここだけでは分かりませんが、この絵はこの左右に広がって、後ろにキング・ジョージ五世級戦艦とイラストリアス級航空母艦、そしてソードフィッシュ雷撃機とサンダーランド飛行艇も描かれています。格好いいね。 表紙絵は、荒海を突っ切るトライバル級駆逐艦。ここだけでは分かりませんが、この絵はこの左右に広がって、後ろにキング・ジョージ五世級戦艦とイラストリアス級航空母艦、そしてソードフィッシュ雷撃機とサンダーランド飛行艇も描かれています。格好いいね。この本を買おうという決断の元には、この表紙絵が少なくとも25%は占めてます。 残りの75%のほとんどが、岡部さんの蛇の目なフネへの愛ですね。(笑) この蛇の目なフネというのは、解説が必要かな。ここでいう蛇の目とは、ラウンデル、軍用機の国籍マークのこと。このうち、同心円の国籍マークを、蛇の目と通称します。実は英国だけでなく、さまざまな国が採用しているんです。日本の国籍マーク、赤い円も、白色の縁取りがあるものも含めて、ある意味蛇の目の仲間。 この同心円のマークを最初に採用したのは、フランス軍らしい。それを見て、英国も軍用機のマークを、内側から青・白・赤の蛇の目マークにしたそうです。だから、唯一でも最初でもないんですよね。でも、ファンの人たちは英国の飛行機を差して蛇の目のヒコーキ、となぜか呼ぶ。 で、その流れで、蛇の目マークなど使っていない英国艦のことを岡部さんは愛情をこめて蛇の目なフネと呼ぶんです、きっとね。 この本は、艦艇模型雑誌「ネイヴィーヤード」に連載している岡部さんのコラム「なんだか蛇の目なフネだから」をまとめたもの。 英国海軍の艦艇について、面白いネタをいろいろたくさん集めてくれています。 章題は、こんな感じ。 フネの名付けは大変だ HMS“反社会的悪ふざけ”号 商船改造、商船を守る リアル HMSユリシーズ ハンサムJ 使い切り軽巡 老骨に荒波 H.M.サブマリン 帝国の種族たち 勇猛なる種族 戦いに生き、戦いに斃れ 分家の種族 地味~な戦艦 地味~な戦歴 名物、高速敷設艦 戦場を駆け抜ける 帝国の後継者? リアンダー・マンたちのフネ そして終章 虎は美しかった テーマは、英国海軍の艦名の付け方。ワークホースとして海を駆け巡った巡洋艦たち、駆逐艦たち、潜水艦たち。防空軽巡洋艦ダイドー級、岡部さんが愛するトライバル級駆逐艦。地味に生涯を終えたロイアル・ソヴァレン級戦艦。韋駄天のアブデエル級敷設巡洋艦。フリゲートの代名詞になったリアンダー級。最後は、日本の注文で作った当時世界最強の巡洋戦艦「金剛」の改良版である、タイガー級巡洋戦艦。 そうだよ、あんなフネがあったっけ。そうだよ、ブリティッシュな奴らって面白いフネの名付け方なんだぜ。そうだよ、ジョンブル海軍はあんなふうに、歯を食いしばって戦ったんだ。そうだよ、奴らはあんなにものすごい損害を出して、最後まで一歩も引かなかったんだよ。 そうだよ、あいつらのフネって、あんなに格好いいじゃないか。 最後の妄想が、楽しいね。 もし13.5インチ砲搭載の第一次大戦用のフネだったタイガーが、1930年代に近代化改装されたとしたら、インド洋あたりに進出することもあったのかもしれない。もしそうだったら、インド洋まで進出したことがある日本の南雲艦隊と当たることがあったかもしれない。南雲艦隊の前衛にいた高速戦艦「金剛」が、自分の妹と砲火を交えることがあったかもしれない。 だとしたら面白いかもしれないけれど、そうならなくてよかったね。 プラモデルの世界では、ウォーターライン(水線上の姿のみの模型)を初めとして、たくさんの艦艇が販売されています。 日本軍がメインなのは当然ですが、次がアメリカで、その先はあまり出ていません。ドイツ、イギリスも目だったところばかり。 でもさ、もっとブリティッシュな艨艟たちがあってもいいよね。ダイドー級とか、小さなU級潜水艦とかもね。 こんな事をいろいろ考えさせてくれ、楽しい時間を過ごさせてくれた岡部いさくさんと、蛇の目のフネで戦った男たちに、敬意を。(2014/9/7) |
 |
|---|
| 管理番号:O034-002 | 52 戦史・戦争ノンフィクション | 出版社:大日本絵画 | |||||||
| 書名:英国軍艦勇者列伝2 | Legend of British Fighting Ships 2 | ISBN978-4-499-23304-0 C0076 | |||||||
| 価格:2700Yen | ページ数:240P | 本のサイズ:135×195HC | |||||||
| 初版発行:2020/10/28 | 購入:2020/10/2 | カバーイラスト:佐竹政夫 | |||||||
 勇者列伝、その2。 勇者列伝、その2。購入し、読んだのがもう5年前とは。ちょっと目をそらすとこれだ。(笑) で、前巻でネタにしなかった蛇の目の艦船あれこれ。 BFS001 補助対空艦──およびスコッチのシングルモルトについて── 補助対空艦スプリングバンク 輸送船団の護衛任務のために作られた艦艇。戦場に駆り出されたCAMシップ、補助対空艦のこと。そして最初に補助対空艦に改装された貨物船スプリングバンクにちなみ、スコットランドのウィスキー蒸留所スプリングバンクのこと。 BFS002 中古駆逐艦引き取ります、いや、むしろください 〝タウン〟級駆逐艦 1940年にアメリカから譲ってもらった50隻の駆逐艦のこと。緒戦で駆逐艦が無茶苦茶消耗して船団護衛にさく余裕がなくなったため、カリブ海方面の英国軍施設と引き換えにアメリカの中古駆逐艦を譲り受けたもの。 この錆だらけで水漏れする老朽艦を死に物狂いで修理・改装して、英国式護衛艦としたものに、十把一絡げに中小都市の名前をつけたのがタウン級駆逐艦。華々しい戦果を上げた訳じゃないけど、苦しいとき英国海軍の台所をささえた老嬢たちでした。 BFS003 エンタープライズ、発進! E型軽巡洋艦HMSエンタープライズ アメリカで有名なエンタープライズは、独立戦争以前から原子力空母まで、スペースシャトル・オービターから宇宙を馳せる主役宇宙船にまでなりました。英国にも、勇ましさや強さを表す抽象的な名詞とか形容詞を軍艦の名にする伝統があって「大壮途」みたいな意味であるエンタープライズは、英国に就役した軍艦としてだけでも、1705年フランスから分捕った24門フリゲートから始まり2003年に就役した測量船まで十隻くらいあります。その中で、高速艦を目指して作られたエメラルド級軽巡洋艦の一隻、エンタープライズ。排水量7700トン、6インチ砲連装1基・単装5基、8万馬力、33ノットと、なかなかのもの。1936年就役の老嬢だったけど、そこそこ働いて1946年に退役。お疲れさん。 BFS004 21精機駆逐艦・・・ タイプ45駆逐艦(前編) 現代では戦艦はないし巡洋艦もロシアの以外亡くなっちゃったよねぇ、米海軍のタイコンデロガ級は駆逐艦の船体にイージスのっけただけだし、てな話から始まって英国の駆逐艦のお話。(本の刊行時に)最新のタイプ45デアリング級。搭載ミサイルの話。 BFS005 ・・・でも6隻 タイプ45駆逐艦(後編) そのタイプ45の話、続き。防空駆逐艦として最新の設備を整え、「統合電気推進」というシステムを備えた新鋭艦。最初いろいろトラブルはあったのもの、一番艦デアリングが2009年に就役したのち続々とそのあとに続いた──のだけど、12隻建造予定が結局6隻しかできなかったのだそうな、って話。国際的な売り込みとかいろいろあったけど、結局予算がねぇ。 BFS006 「ハンサムJ」の妹たち N級駆逐艦 第二次大戦の気配が濃くなってきた1938年に建造計画が立ったうちのひとつ。大型のトライバル級のあと、小型のJ級8隻と同級のK級8隻が作られ、新型連装砲をのせたL級8隻とM級8隻の建造計画が進む中、この砲塔がダメだったらという保険で作られたのがJ・Kと同級のN級8隻。ネイピア、ネリッサ、ネスター、ニザム、ノーブル、ノンパレル、ノーマン、ノースマン。なんと、ノースマン以外はみんなオーストラリア、オランダ、ポーランドに移籍された上、ノースマンも英国に従軍しているグルカ兵への敬意のため彼らの故郷ネパールに改名したとのこと。 地中海などでこつこつと戦い、華々しい戦果や武勇伝はなかったもののネスターを除いて全艦無事生き延びたのだそうな。 BFS007 勇ましいちびの巡洋艦 アレスーザ級軽巡洋艦 ちょっとでも強いフネを、と8インチ砲をのせた重巡を作りたがった日米海軍と異なり、英国は巡洋艦を通商路警備用と割り切っていたので6インチ砲搭載の軽巡をいっぱいそろえたがったもの。その結果、軍縮条約の枠の中で7000トン級のリアンダー級9隻と5250トン級アレスーザ級6隻を計画します。最終的にアレスーザ級は6インチ砲を連装3基乗せて4隻、アレスーザ、ガラティア、ペネロピ、オーロラが1935年から37年に就役。 3番館ペネロピは地中海で奮戦し、いたるところ穴だらけになって「HMSペッパーポット」というあだ名で呼ばれたそうですが、むろんこれは悪口ではない。この艦の活躍を元にフォレスターは「巡洋艦アルテミス The Ship」を書いたのだそうな。 BFS008 船酔いするキャプテン 〝キャプテン〟級フリゲイト 護衛艦艇が不足する英国海軍は、なんとかして数をそろえなくてはならんとあの手この手。アメリカが護衛駆逐艦という新しい艦種を大量生産すると聞きつけ、 設計上の想定より軽い砲を乗せたことなどで動揺周期が大きく操艦が難しい上、「ダメージコントロールがないにし等しい」「使い捨て」と酷評されましたが意外にしぶとく、7隻戦没したものの大半が生き延びて戦後アメリカに返還されました。 BFS009 無事これ名艦 戦艦ハウ 同じクラスの中で運命の明暗が分かれたフネとして例に出されたのは、戦艦キング・ジョージⅤ級。 ネームシップの一番艦は独戦艦ビスマルク撃沈に参加。二番艦プリンス・オブ・ウェールズは不運が重なった末にマレー沖で日海軍に沈められる。三番艦デューク・オブ・ヨークは北海で独巡洋戦艦シャルンホルストを撃沈。しかし四番艦アンソンと五番艦ハウは、というと目立たない。この二隻の艦名はフッド級の二番・三番艦につけられる予定で、そもそもはジェリコーとビーティと名づけられる予定だったのに、諸事情でこの名になったそうな。 戦艦ハウの戦歴は、1942年12月から2年8ヶ月。その間あっちへ行きこっちへ行き、地上目標への艦砲射撃や対空護衛ばかりで華々しい戦果はなし。しかしこの間前線で戦いぬき、「無事に生き延びさせてくれた艦」として生を全うしたのです。 BFS010 想定寿命3年 コロッサス級軽空母(前編) 戦争が始まって3年目で英海軍がいちばん欲しかったのは艦隊防空力、つまり空母。そこで1942年度に、正規空母4、軽空母10の計画をたてます。軽空母の方はとことんスペックダウンし、装甲なし、高角砲なし、機関は巡洋艦用で2軸、排水量は基準で1万トンちょっとというスペックなのですが、機能として意地が見られます。ボイラーとタービンは前後・左右に振り分け、アイランド、エンクローズドバウ、エレベーター2基、カタパルト1基、搭載数は露天繋止含め52機ときたもんだ。しかも実用寿命は3年とこの戦争のためだけにと割り切ってます。 最終的にコロッサス級として16隻が建造されましたが、いくらインスタントでも空母、一番艦のコロッサスが竣工したのは1944年12月で、日本が降伏するまでに完成したのは5隻だけ。そのあと1946年に3隻が竣工します。さらに2隻は搭載機の整備・修理施設のない極東へ派遣されることを考えて「航空機整備艦」となり、さらに後期の6隻は終戦時進水直後か進水前だったので、設計変更されてマジェスティック級という別なクラスになりますが、1隻は完成しませんでした。 BFS011 空母発達史のかすかな輝き コロッサス級軽空母(後編) で、実戦前に第二次世界大戦が終わってしまったのだけど、コロッサス級は1950年からの朝鮮戦争で英海軍の主力となります。乗せたシーファイア戦闘機が米空軍のB-29爆撃機に誤射で撃ち落とされるという不名誉な事件もあったり。 そののちは英海軍縮小の中であちこちに貸与・移譲・売却されたりして、中には2001年まで現役だった艦もあったとか。 BFS012 狩場の駆逐艦 ハント級駆逐艦 1937年頃、艦隊用の大型駆逐艦を補完する「安い、早い、小さい」駆逐艦が必要になりました。J/K級、O/P級などの流れの中で、さらに小型の駆逐案が計画されます。それが護衛駆逐艦ハント級。最終的に86隻建造されます。 設計安定が悪いなどのゴタゴタがあったりして、まず排水量1000トン、速力27.5ノット、4インチ連装両用砲2基でまず建造されたのがタイプⅠと呼ばれる最初の型が23隻。1941年までに竣工します。 少しずつ改良・再設計され、次のタイプⅡは36隻。タイプⅢは28隻。タイプⅣは2隻。すべて海に出て、23隻喪失しました。 BFS013 2級のフリゲイト ブラックウッド級フリゲイト 第二次世界大戦が終わった後、冷戦相手のソ連とどう戦うか考えた英海軍、ソ連の潜水艦への対応に迫られます。国力を使い果たしたイギリスは、仮に次の戦争が起きた時に海上輸送路をどう守るのかという課題に対し、182隻のフリゲイトが必要と回答します。内訳は、対潜艦が107隻、対空任務艦が59隻、対空指揮艦が16隻。 で、安価な対潜フリゲイトとして計画されたのがタイプ14、ネームシップの名を取ってブラックウッド級。 おりからの朝鮮戦争で、最初2+10隻の計画が、10隻また10隻と合計32隻に膨れあがったのですが、第三次世界大戦に延焼しそうにない事がわかり12隻で終わります。これもまた、いろいろな時代の英海軍の著名な艦長たちの名を取っています。 ぱっと見て、4番艦エクスマスが初代エクスマス子爵となったエドワード・ペリュー、6番艦ハーディがネルソン提督旗艦ヴィクトリーの艦長で提督の最期を看取ったトーマス・ハーディから取っていることがすぐわかりますが、他の艦長たちも調べればわかるはず。 BFS014 恐れを知らぬ者たち 〝ドレッドノート級〟戦艦(前編) 英海軍ってのは、ときどき時代を突き抜ける発明をします。そのひとつが、戦艦ドレッドノート。 1905年の日本海海戦で勝利した日本の第一戦隊6隻の戦艦は、12インチ連装砲を2基4門と6インチ単装砲14門そなえていました。最新鋭の「三笠」は1902年就役ですが、これがこの時代の「戦艦」のスタンダードだったのです。しかし英海軍はなんと1906年に、12インチ連装砲5基10門、副砲なし、というとんでもないフネを作ります。しかも速度は、三笠の上記レシプロ機関18ノットに対し蒸気タービン機関により21ノット。これがドレッドノート。彼女がその後の海軍の、いや海戦の様相を決定的に変えます。 「恐れを知らぬ」という意味のドレッドノートは、初代の16世紀の40門鑑から数えて8代目なのだそうな。 その後、このドレッドノートの改良型が立てつづけに世界を席巻します。日本ではこれを「弩級艦」「超弩級艦」「超々弩級艦」と呼んだもの。やっと表紙の「超ド級」が出て来ましたな。(笑) イギリスとドイツで作られたドレッドノートとその後継者たちが、第一次世界大戦の海戦で砲火を交えます。 BFS015 それに続く者たち 〝ドレッドノート級〟戦艦(後編) 従来の世界の海軍の戦艦を、自分たちのものも含めて一気に旧式化したドレッドノートの出現以降、世界一の海軍の座を維持するため英国海軍は立てつづけにドレッドノートの後継艦、改良艦を就役させます。その結果、実用上の欠点への根本的な改良はなおざりにされ、数だけが増えていく。しかし英国海軍は、これをやめると追いつかれるのでやめられない。ほかの海軍国もやめられない。 これがひと息つくのは、第一次世界大戦が終わってから。ふう。 BFS016 「シャイニー・シェフ」 〝タウン級〟軽巡洋艦シェフィールド 第二次世界大戦で赫々たる戦果を上げた英国軍艦は数々あります。巡洋艦としてはタウン級軽巡洋艦・サザンプトングループの5番艦、シェフィールドが白眉でしょうか。ビスマルク追撃戦、バレンツ海海戦、シャルンホルスト撃沈と大西洋での英国海軍の決定的な戦いすべてに参加しています。基準排水量9102トン、6インチ三連装砲塔4基12門搭載ってのは英国としてはかなり大きいのですが、これは日本の最上型、1万トン・6インチ三連装砲塔5基15門への対抗としてのフネだったから。15門はいくら何でも無理、というのは日本はトン数をかなり誤魔化していたからですが、それでも12門とはかなりの重武装です。 軍艦の艦内にはドアノブとか手すりとかはふつう真鍮製で、常に磨かないとすぐ緑青を拭くのですが、軽巡シェフィールドではステンレスを使っていたのだとか。ステンレス生産が盛んだったシェフィールド市はこれがえらく気に入ると共に、いつも艦内がピカピカ光っていたシェフィールドは「 BFS017 マレーからの贈り物 戦艦マレーヤ 第二次世界大戦の英海軍は、戦艦17隻と巡洋戦艦3隻で開戦し、戦艦3隻と巡洋戦艦2隻を失います。生き延びた戦艦の中でも運命はいろいろなのですが、目立たないながら地味に生き残った一隻にクイーン・エリザベス級戦艦5番艦マレーヤがあります。このクラスは、ドレッドノート級から発達した戦艦群の中でひとつの到達点となった高速戦艦の嚆矢といえるもの。 このクラスはそもそもクイーン・エリザベス、ウォースパイト、ヴァリアント、バーラムの4隻だったのですが、当時イギリス領だったマラヤ(今のマレーシアとシンガポールあたり)が献金してもう一隻建造されたもの。これがマレーヤ。竣工は戦艦伊勢の竣工よりちょっと前の1916年。 1916年のジュットランド海戦に参加した後、改装されて第二次世界大戦に参加します。決して怠けていた訳ではないけれど、魚雷一発受けただけで戦争を生き延びたのは、幸運と言うべきかな。 BFS018 国王陛下のスーパー・ドレッドノート キング・ジョージⅤ世級戦艦 ドレッドノートの就役後、イギリスもドイツもより大口径な主砲を持つ戦艦を作ろうと躍起になります。ドレッドノートと同じ12インチ級の主砲を持つ戦艦を「弩級」、それより大きい13.5インチ砲戦艦を「超弩級」と呼んでその嚆矢となったのがオライオン級4隻、1912年に全艦就役。その改良型として建造されたのがキング・ジョージⅤ世級戦艦(先代)4隻、1912年から翌年にかけて就役。キング・ジョージⅤ世、センチュリオン、オーデイシャス、エイジャックス。第一次世界大戦が始まった時、このクラスが最新鋭でした。戦争前に触雷で沈んだオーデイシャスを除く3隻はジュットランド沖海戦に参加しました──が、ほとんど射撃の機会はなく終戦。 このうちの一隻センチュリオンだけが数奇な運命をたどりますが、それはまた別な話。 BFS019 彼らもまた勇者 トローラー、ドリフター 第二次世界大戦で地味に縁の下を支えた艦戦というといろいろありますが、地道に仕事をこなしたフリゲイト群よりもっと地味だった海軍のフネがトローラーやドリフターという艦種。 トローラーとはトロール漁船、つまり底引き網をするためのフネ。ドリフターとは流し網漁船。どちらも250~500トン程度の小さなフネですが、英国の漁船なので小さいとはいえ荒海に強い。英国海軍はこれらを徴用して、英国海軍の行くところすべての海で働かせたのでした。対潜任務、掃海任務などで活躍というか重宝され、どこでも働き、時にはドイツ戦闘機を撃墜する勇者もいたとか。
その他、各エピソードの間にはさまれた英国海軍史のミニ・エッセイもまた素敵でした。(2025/7/3) 読書メーターの記録より 読了:2020/10/19 |
||||||||||