トップへ戻る  読んだ本の分類 |
|
 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |
|---|---|---|---|
| O044-001 | 「砂漠の狐」ロンメル | 名将と称えられた人物の実像 | |
| O044-002 | 戦車将軍グデーリアン | 装甲部隊を作り、戦い、勝利した、といわれた男の実像 | |
| O044-003 | 独ソ戦 | ナチス・ドイツという怪物がソビエト連邦という怪物を生みだした | |
| O044-004 | 「太平洋の巨鷲」山本五十六 | 山本五十六を軍事的側面で評価すると | |
| O044-005 | 天才作戦家マンシュタイン | 名将マンシュタインの真の姿とは | |
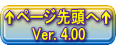 |
 |
|---|
| 管理番号:O044-001 | 51 伝記・一代記 |
出版社:KADOKAWA | |||||||
| 書名:「砂漠の狐」ロンメル | ヒトラーの将軍の栄光と悲惨 | ISBN978-4-04-082255-6 C0222 | |||||||
| 角川新書 K-254 | 価格:900Yen | ページ数:320P | 本のサイズ:新書 | ||||||
| 初版発行:19/3/10 第4版:19/4/20 |
購入:2021/9/25 | 写真:トブルクで前線基地を視察するロンメル(1942年5月30日) Picture Alliance:アフロ |
|||||||
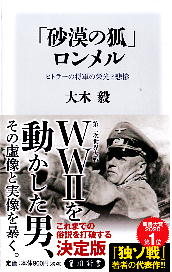 1944年10月14日午前6時、フランスでスピットファイアの銃撃を受けて重傷を負ったのち療養を続けていたドイツ国防軍のエルヴィン・ヨハネス・オイゲン・ロンメル陸軍元帥は、自宅で、休暇で戻っていたひとり息子のマンフレートにこう言ったそうです。 1944年10月14日午前6時、フランスでスピットファイアの銃撃を受けて重傷を負ったのち療養を続けていたドイツ国防軍のエルヴィン・ヨハネス・オイゲン・ロンメル陸軍元帥は、自宅で、休暇で戻っていたひとり息子のマンフレートにこう言ったそうです。
これは事実であるのかは、実はたいした問題ではない。遺族はそう考えていたということ。ここまで国家に忠誠を捧げ功績を挙げたのに、この仕打ちは何なのだ、という怒りと考えていいのか。 歴史の「事実」とは、人の証言が重きをなすから、こんなものもあり、なんだよね。
この本は、この後ロンメルの実物大の人物像を伝記的に描きつつ、ロンメルを完全無欠な名将として見かけ以上に大きく描いてきた過去と、デイヴィッド・アーヴィングらによる誇張、虚偽を含めた「名誉欲に駆られた無謀な指揮官ロンメル」が形成された経緯、そして2000年以降の指揮官としての冷静な評価へと続きます。 また、2010年代に入って進んだ新たなロンメル批判として、ヒトラーの軍人であったロンメルを評価できるのか、という問題意識も出てきたそうな。これには、全否定すべき存在であるアドルフ・ヒトラーに、軍人としてであったとしても追従しその権力を守る立場だったロンメルを、英雄として評価することは妥当か、という問題なのでしょうか。 ロンメルはアウトサイダーだった、という言葉で第二章は始まります。 軍人としてのロンメルは、ドイツ帝国内において、南西ドイツ、ヴュルテンベルク王国のハイデンハイム出身であったため、ドイツ軍の主流であるプロイセン王国出身の軍人たちに比べメインストリームから外れていた、と語られます。それはロンメルの父親が軍人ではなく、数学の教授であるという中流階層の名望家であり、「理系」であったことが関連します。 当時プロシア直系の「将校適正階級」ががっちり固めている花形の兵科はハードルが高く、中産階級出身者が将校となれる兵科は、砲兵や工兵のような数学や物理学の知識を必要とするものに偏っていました。であればロンメルはこれを目指すべきであったはず。しかし運悪くロンメルが父の命令により軍人を志願したとき、砲兵も工兵も士官候補生の秋はない状態。騎兵科は「将校適正階級」の独占するところ。やむを得ずロンメルは、1910年7月19日、ヴュルテンベルクの歩兵連隊に士官候補生として入隊します。 これによりロンメルは、①「将校適正階級」の登竜門たる兵科に入れず、②ドイツ将校団の本流であるプロイセン軍にもバイエルン軍にも入れず、③ドイツ軍のエリートコースである幼年学校・士官学校を経ずに将校に任官したのでした。これが軍人としてのロンメルの大きなハンディになります。
こうした背景を持つロンメルは、第一次大戦において果敢な軍人としての評価を積み立て、戦後の軍縮の中でもヴァイマール共和国の「 ロンメルは、上を目指すには不十分な足場に立って軍人という階梯を登るにあたり、無理をして果敢な軍人としての実績を積み上げると共に、その実績を過度に自己宣伝するという手段をとります。不正な方法ではないものの、功績を他人に取られまいと執拗に自己アピールしたのは事実でした。しかし、戦場の英雄としての勲章を持つ身であるが参謀教育を受けないままだったロンメルは、高級指揮官としての教育もまた受けないままであり、のちに軍団や軍を指揮する高級将校になったときに意外なハンディを背負うこととなるのでした。これもまた、運命。 ロンメルとヒトラーの関係は、複数の説があります。妻ルチーの手記や戦後に書かれた本によると、ロンメルはナチス及びヒトラーに対して軽蔑を隠し冷淡な姿勢を見せていたように書かれていますが、現実にはそうではなかっただろうというところ。ドイツが復興し軍人の権威が高まるならば、当時の軍人は積極的にヒトラーに忠誠を誓ったろうし、ロンメルが一人それに距離を置いたなどと考える根拠はない、ということ。現実として、そう考えるのが妥当か。 1937年、ヒトラーの政権において拡大したドイツ国防軍の中でポツダム軍事学校の戦術教官となったロンメルは、授業用に準備したノートやメモを元に回想録と戦術教科書を兼ねた著作を刊行します。この「歩兵は攻撃する(Infanterie greift an)」は、1945年までに40万部を売り上げるという、この手の本としてはとほうもないベストセラーになったとのこと。 本自体は、1990年代のアメリカ合衆国軍で二等軍曹以上の階級の軍人に必読の書であると喧伝されるなど後の世まで残る名著でしたが、当時総統になっていたアドルフ・ヒトラーの目にとまったことが、ロンメルの運命を開くこととなりました。 ロンメルは名将であったのか。 これに関しては、「名将」の規準をどこに置くかで異なります。ロンメルのさまざまな欠点、自己顕示欲、戦略的思考の欠如、指揮官先頭を追い求める余りの単独前線視察癖、独断専行などはもちろんですが、それを裏返せば第二次大戦の総帥としてユニークな、果敢に勝利に邁進する革命的な指揮官の姿ともなります。しかしそんな単純なものでもない。
アフリカの失陥ののち、一時危機的な健康状態で病床に伏したのちなんとか回復したロンメルは、ヒトラーの命により西部戦線で連合軍の侵攻を食い止める任務に就きます。このとき、老練な陸軍の長老でありクレバーな指揮官であるゲルト・フォン・ルントシュテット元帥と防御方針で対立することになりますが、結果としてはどっちもどっちというところらしい。とはいえ、その折衷、つまりロンメルの海岸で絶対線を引く作戦とルントシュテットの内陸に機動性の高い機甲軍を置いて臨機応変に動かす作戦のあいだの、中途半端なものが行われたために、西部戦線での敗色は濃厚となります。これにはロンメルがノルマンディー上陸のその日に休暇を取っていたという痛恨のミスも関連しますが。 この直後ロンメルは、ルントシュテットと共にヒトラーに対し、戦争の推移を見るかぎり西側との政治的解決、つまり和平交渉も検討すべきではないかと申し入れますが、ヒトラーはけんもほろろに拒否。これをふくめ、いくつかの出来事がのちのヒトラー暗殺未遂事件にロンメルの関与はあったのかという問題に絡みます。 ここでなにがあり、ロンメルの死、ドイツ首脳による粛正までになにがあったのかについて、いまだに諸説があるそうですが、大木氏はアーヴィングが『狐の足跡』で著したロンメル非難を否定します。アーヴィングは、ロンメルは暗殺計画など知らず、参加もせず、最後までヒトラーに忠実だったと記述し、英雄としてのロンメルを地に引きずり落としたのですが、
大木氏はどうやら、アーヴィングの言い分が腹に据えかねたらしい。 ロンメルの生涯を追ったあと、終章で「ロンメルとは誰だったのか」とまとめます。 彼の、軍人としてのさまざまな欠点を列挙したのち、それにもかかわらず人々の賞賛を集める将としての力量があったという。そして、そういった毀誉褒貶の上に立ち、ロンメルには特筆すべき美点がある、といいます。
騎士道的な振る舞いが出来た要因には、凄惨な東部戦線に配置されなかったという偶然もある、けれど。
読書メーターの記録より 読了:2021/11/11 |
|||||||||||||||||||
 |
|---|
| 管理番号:O044-002 | 51 伝記・一代記 |
出版社:KADOKAWA | |||||||
| 書名:戦車将軍グデーリアン | 「電撃戦」を演出した男 | ISBN978-4-04-082321-8 C0222 | |||||||
| 角川新書 K-310 | 価格:900Yen | ページ数:344P | 本のサイズ:新書 | ||||||
| 初版発行:2020/3/10 | 購入:2021/9/25 | 写真:1943年、ソ連視察飛行中のグデーリアン AP/アフロ |
|||||||
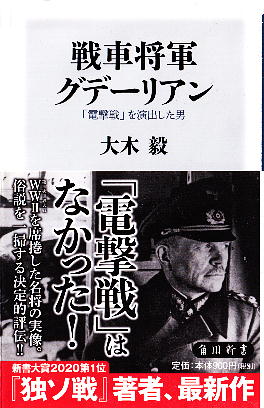 序章は、「さらば夏の日よ」と題されて、1940年5月、つまりドイツ機甲軍団にとっての夏、最良の時を描写します。ハインツ・グデーリアン装甲兵大将が、第19自動車化軍団を率いてマース川北岸よりアルデンヌを越えてフランス国土をへ強襲をかけたのはそのとき。 序章は、「さらば夏の日よ」と題されて、1940年5月、つまりドイツ機甲軍団にとっての夏、最良の時を描写します。ハインツ・グデーリアン装甲兵大将が、第19自動車化軍団を率いてマース川北岸よりアルデンヌを越えてフランス国土をへ強襲をかけたのはそのとき。
そしてそこに至る彼の奮闘ぶりと、そこからの凋落、そして彼の虚名と真の姿を描き出します。 グデーリアンの評価の変遷については、すでにいろいろ書かれています。 1922年に第7自動車隊に配属されたときから機械化戦争の可能性に注目し、一貫してドイツ装甲部隊の発展とともに昇進していきます。装甲部隊の運用理論を世に問うた『 1951年に英国の軍事評論家のリデル・ハートの勧めもあって回想録『電撃戦』を刊行し、その英訳版によって世界に戦車戦の名将として知られるようになります。 戦後のポジティヴなグデーリアン像は、このリデル・ハートとの二人三脚で生まれたものと言ってもいい。 1999年代になって、アメリカの軍事史家ロバート・チティーノが、グデーリアンの実績は認めるもののドイツにおける装甲部隊の創設・育成は彼一人のものではないと指摘します。ついで2006年に同じくアメリカの軍事史家ラッセル・A・ハートがグデーリアン伝を著し、事実と照らし合わせると『電撃戦』に書かれた内容は訂正されるべきと論じ、オーストリアの戦史家デイヴィッド・ストーエルもまたグデーリアンの書簡などの史料に基づき『電撃戦』の誇張や恣意的記述を暴露しています。 その他、さまざまな研究により、『電撃戦』の上司そのものが戦争指導を巡るヒトラーその他との軋轢に関しての自己弁護であり、収入を得るための手段だったことも判明していきます。 これらは、米陸軍の研究のためという面や、ドイツ国防軍高級将校がヒトラーに戦争責任をお汁蹴る方便の面もあったようで、単純にグデーリアンひとりを非難することもできない。とはいえそれだけでなく、
ならば素顔のハインツ・グデーリアンとはどんな人物だったのか。 こうして描き出される、グデーリアンという人物についてのあれこれ。グデーリアンをグデーリアンたらしめたものとは何か。 まず、読み方。Wikipediaのグデーリアンの項によると、
グデーリアン家の出自について、オランダ出身説、アルメニア説、スペイン説などいろいろあったそうですが、ドイツ人牧師のハンス・グデーリアン氏の研究により、1680年にポンメルンもしくはブランデンブルク地方より ドイツ東部で繁栄したグデーリアン一族の、西プロイセンに領地を持つ一家の長男としてハインツ・グデーリアンは生まれます。彼の家は、姓に貴族のしるしである「フォン」こそ加えていませんが、地方の大地主・名望家でした。父親のフリードリヒ・ヴィルヘルム・ハインリヒ・マティアス・グデーリアンは、一族の中珍しく陸軍将校となり、 この時代のドイツの幼年学校は、生徒たちを上に立つ「指導者」の資質を得られるように教育を行った、といいます。軍隊的に厳しく質実剛健な教育と同時に、10代の生徒たち一人一人に退役した兵士などによる従者が付けられて身の回りの世話一切を任せることで、兵士に対しどのように接すべきかを叩き込まれます。また親称の「 ここは、指揮官を 1905年2月に少尉候補生試験を受け、1907年2月に高校卒業試験資格に合格し、同年4月にメッツの 1913年10月にグーデリアンは、ドイツ軍人にとって最高のエリートコースである参謀将校への登竜門である陸軍大学校への入学を許可されます。当時彼は25歳で、同期生168名中の最年少でした。ここでのちに元帥となるエーリヒ・フォン・マンシュタインと出会います。 マンシュタインとは親友であった、と書かれる読み物もありますが、そうではなかったそうです。不仲ではないが親密でもない、「俺お前」の仲ではなかった。どちらのせいかは明言されていませんが。 在学中、第一次世界大戦が始まります。ここで学校半ばで前線に送られたグーデリアンは、戦闘の中で才覚を発揮し、1918年2月に陸軍参謀本部付きを命ぜられます。これは、晴れて参謀将校の証しである深紅色の筋を脇に付けたズボンを履く権利を得たこと。
ドイツの敗戦とドイツ国防軍の解体の中で、グデーリアン大尉は派遣された参謀として赤軍と戦闘を続ける義勇軍 1922年1月にミュンヘンの第7自動車隊付の参謀職に補せられたとき、これは懲罰人事と疑ったらしい。当時自動車部隊は とはいえこれが、グデーリアンの未来を開くことになりました。 最初、彼に課せられたのは自動車輸送部隊の運用でしたが、のちに自動車修理、整備工場・燃料庫・施設建築・技官任用、さらに道路・交通施設案件までも担当させられます。そんな無茶な、と抵抗しますがやむを得ずそれに邁進するうちに、彼は自動車から、舞台が担当することになる装甲車両、そして戦車まで扱うことになり、いつの間にか装甲部隊のエキスパートとなったのでした。運命とはかくも不思議なもの。このあたり、回想録でもさまざまな形で自分はこのテーマの先鞭をつけた先駆者である、とグデーリアンは書いています。実際、彼の功績によるものは大きい。しかしそれ以前に第一人者と目されていた人物はおり、彼一人の功ではない。
1935年より作戦部長に補せられたエーリヒ・フォン・マンシュタインは、自伝でこのあたりを語っています。 年長の将軍たちが革新的なアイディアに対して拒否反応を示したことは事実であるが、陸軍参謀本部が装甲兵科の意義を無視したりグデーリアンに同調しなかった訳ではない。グデーリアンがただ装甲兵科のことのみ注視していた事に対し、参謀本部は陸軍全体のことに目配りしなければならなかったのだ、と。
ここで「昇進」ではなく「進級」という言葉を使っているのが、軍事史研究者の大木さんらしいところ。 東部戦線におけるグデーリアンの働きに関しては、作戦次元での何度もの大勝利はあったものの、戦略に介在していなかったグデーリアンの責任はあまりありません。まぁ、そういう立場なのか。 ただここで、グデーリアンと戦争犯罪の関わりも指摘されます。 1941年3月のヒトラーの演説による、通常の軍刑法に基づく裁判手続きを停止せよ、つまり敵性民間人は軍法会議にかけず、パルチザンは捕虜としないで即座に殺せ、などという人権無視の命令と、同年6月のいわゆる「コミッサール指令」、ソ連軍の中に配置されるイデオロギー敵に軍を監督する
無役となったグデーリアンは、悪化していた健康の養生に努めると共に、東部ドイツに土地を与えられるというヒトラーからの知らせを聞きつつ1943年初頭まで過ごした──と回想録にありますが、実際はヒトラーに125万ライヒスマルク(彼の階級や先任順序から考えて俸給の50年分くらいに相当)の特別下賜金を受けて懐柔された上、ポーランドの土地を(住民を強制退去させて)「購入」していたのでした。このへんの、部下の蛮行に目をふさぎ良い土地を(結果として)強奪したことについて、常に口を閉ざしています。 グデーリアンがヒトラーに召喚され、 それが挫折したのは、歴史の通り。1943年5月にミュンヘンで行われた作戦会議の後、フォン・クルーゲ元帥に決闘を申し込まれたという前代未聞の話も、周囲に敵ばかり作るグデーリアンの扱いにくい性格を示す例といえるのか。 ノルマンディ上陸作戦、ヒトラー暗殺事件、連合軍の東西からの進撃と敗色濃厚となったのち、彼は1944年7月に空席となっていた陸軍参謀総長まで兼任するよう命令され、最後の戦いの指揮を取ります。この戦乱の中で、彼はヒトラーの理不尽な命令の中で救えるものは救おうとしたと記録します。しかし現実にはそうでなかった。
この、装甲部隊を創設して運用するにかけて天賦の才を発揮した人物は、その方面において偉大であった。この評価は、多少削られることはあるにしても、本筋においておそらく崩れない。 しかし彼が同時に、プロイセンに連なるドイツ人としての、極端な国粋主義・反共・反スラヴ主義は若い頃から揺らいでおらず、戦後に至っても1949年に元ナチ党のカウフマンによって設立されたネオナチ組織に加盟していたという、旧時代の価値観から脱却できない人物であった事も事実であったようです。 この革新的であると共に旧弊な男に、英国人の軍事評論家・軍事史研究家のバジル・リデル=ハートが接近します。彼は「ドイツ国防軍軍人は基本的に戦争技術者であり、軍人として国家とヒトラーに忠誠を誓い、ヒトラーに道具として使い捨てられた」という自論のもと、グデーリアンに回想録を書かせ、さらにそれをより英国人に受けの良いように英訳して刊行します。 そして、グデーリアン神話が始まったのでした。なるほど、ペンは剣より強い。 なるほどね、そういうことか、という言葉しか残らないのが残念。またいつか読み直してみよう。(2025/1/27) 読書メーターの記録より 読了:2022/1/16 |
||||||||||||||||||
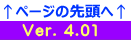 |
|---|
| 管理番号:O044-003 | 52 戦史・戦争ノンフィクション |
出版社:岩波書店 | |||||||
| 書名:独ソ戦 | 絶滅戦争の惨禍 | ISBN978-4-00-431785-2 C0222 | |||||||
| 岩波新書 1785 | 価格:860Yen | ページ数:250P | 本のサイズ:新書 | ||||||
| 初版発行:2019/7/19 第13刷:2021/3/5 | 購入:2023/3/9 | ||||||||
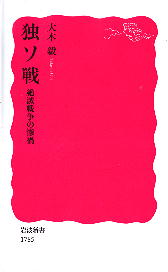 ソ戦とは、第二次大戦の帰趨を決めた大きな、そして悲惨な戦争。それは1941年6月22日に、独ソ不可侵条約を一方的に破ったナチス・ドイツとその同盟国により始まり、1945年5月8日にドイツ国防軍ヴィルヘルム・カイテル元帥がドイツの首都ベルリンで無条件降伏文書の批准手続きを行ったことにより、終結しました。この戦いは、それまでの想像を絶するものでした。 ソ戦とは、第二次大戦の帰趨を決めた大きな、そして悲惨な戦争。それは1941年6月22日に、独ソ不可侵条約を一方的に破ったナチス・ドイツとその同盟国により始まり、1945年5月8日にドイツ国防軍ヴィルヘルム・カイテル元帥がドイツの首都ベルリンで無条件降伏文書の批准手続きを行ったことにより、終結しました。この戦いは、それまでの想像を絶するものでした。
1939年の時点で日本の総人口は7,138万人で、戦闘員では210万~230万人(2.9~3.2%)、非戦闘員で55万~80万人(0.8~1.1%)が死亡したとされています。 しかし独ソ戦の損害はそんなものではない。ソ連は1939年の人口は、1億8879万人。第二次大戦では戦闘員866.5万~1,140万人(4.5~6.0%)、民間人を軍事行動やジェノサイドで450万~1000万人(2.4~5.3%)、疫病や飢餓で800万~900万人(4.2~4.8%)、最終的に2700万人(14.3%)が失われたとされています。 ドイツの場合、独ソ戦だけでなく他の戦線の損害も含むのですが、1939年の総人口6,930万人に対し、戦闘員として444万~531万人(6.4~7.7%)を死なせ、150万~300万人(2.1~4.3%)の民間人が失われたのでした。 この差は、なぜ起きたのか。大木氏はこう書きます。
パウル・カレルなどの清廉潔白なドイツ軍礼賛をベースに持つ著作を見た後なら、特に。 独ソ戦の開幕に当たって、スターリンがなぜ、リヒャルト・ゾルゲを含む多くの情報がドイツの背信と対ソ戦争の兆しを伝えていたのに無視したのかについての説明から始まります。対英不信と、権力醸造が確立していない状態でドイツへの強攻策を考えられない状態だったということ。不安は国内の大粛正というかたちで顕在化し、その結果ますます対独戦争を行える状態じゃなくなっていったこと。軍隊の背骨である将校たちの大半を処刑した後、戦力としては骨抜きとなった赤軍は戦える状態ではなかったという。 そしてヒトラーは、英国を屈服させることが不可能とわかった時点で、手詰まり状態をなんとかするには英国の救援に来るであろう二つの大国の一つを叩くことを決意します。ソ連を叩けば、東方植民地を作り上げられるし英国の抗戦意志をくじくことができるに違いないのだと。 かくして1940年12月18日にナチス・ドイツの対ソ戦争が決定され、作戦名「バルバロッサ」が始動し、1941年6月22日に総兵力330万に及ぶ兵力が、バルト海から黒海までほぼ3000キロに及ぶ戦線でソ連領になだれ込みます。
緒戦のバルバロッサ作戦がロシアの広大な領土の中で電撃戦が通用せず失敗し、短期決戦構想が挫折した後、相手の継戦意志をくじいて戦争終結に導く「通常戦争」は不可能となります。その後に出現したのは、イデオロギーに基づく「世界観戦争」と「収奪戦争」。 それは、ヒトラーという人間を単に「悪魔化」してその能力を過小評価するのではなく、彼の思想を著作(主として「わが闘争」)と言行から読み解き、なぜナチス・ドイツは西欧州のあとソ連に攻め込み、それによってなにを得たのか、どうしてそうせざるを得なかったのかを解説します。そしてこう結論づけます。
結果として、ソ連という(ある意味で)無限の人的資産を持ち、英米から無限というに等しい援助を受けた敵を相手にしてついに息切れし、敗戦の中からかつてソ連陸軍が育て上げた合理的な戦略・作戦・戦術の戦い方を全面に押し出した将星たちがソ連軍を立て直したことでナチス・ドイツの足は止まり、後退を始めます。 しかし、ドイツにとって独ソ戦には「絶滅戦争」の旗が立っていた以上、軍事的合理性は失われます。頑迷な「死守、死守、死守」命令の責任は、基本ヒトラーにすべて課せられていますが、はたしてそれだけでいいのか。 この戦いの帰結としてその概念が固定化された「絶滅戦争」というイデオロギーは、初期のナチス・ドイツの戦争を正当化し、後半はソ連の醜悪な反撃とベルリン劫掠を正当化しました。それは、共産主義の成果を防衛する事が祖国を守ることであるというイデオロギーとナショナリズムを融合させた論理は、「敵」に対する無制限の暴力を発動させます。 そしてその結果として、ソビエト連邦という超大国、軍事国家が戦後の北部アジアから東欧までの地に睥睨します。 そういう歴史の流れと、その流れを解明できるようになるまでの長い歴史の流れを、この本は新書一冊の中で提示してくれました。見事です。(2023/8/19) 読書メーターの記録より 読了:2023/4/23 |
|||||||||||||
 |
|---|
| 管理番号:O044-004 | 51 伝記・一代記 |
出版社:KADOKAWA | |||||||
| 書名:「太平洋の巨鷲」山本五十六 | 用兵思想から見た真価 | ISBN978-4-04-082382-9 C0221 | |||||||
| 角川新書 K-365 | 価格:920Yen | ページ数:336P | 本のサイズ:新書 | ||||||
| 初版発行:2021/7/10 | 購入:2023/1/25 | ||||||||
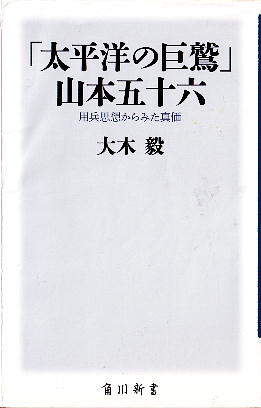 戦中戦後、名将と讃えられた軍人はいろいろいますが、総じてその評価は三段階になるようです。 戦中戦後、名将と讃えられた軍人はいろいろいますが、総じてその評価は三段階になるようです。まずは、名将・聖将論。これをテーゼとします。 そしてその評価をひっくり返す、凡将・愚将論。これがアンチテーゼ。 それから、行き過ぎた暴論を立て直し新たな知見で歴史を構成するジンテーゼ。 これは、世界中のあちこちでさまざまな人物について行われているようです。 この手法を山本五十六の評伝を書くにあたって用いる、まずこれが一つ。 そしてもっと重要なこと。
まったく先見の明を誇るつもりなどありませんが、鐵太郎は子どもの頃から歴史が好きでしたが、小学校はともかく中学高校の図書館に、軍人を軍事的に評価できる解説書が全くないことが疑問であり不満でした。アレクサンドロスがイッソスの戦いで寡兵で大軍を破った、というのなら、どうやって勝ったのか。その戦略は、作戦は、実際の戦闘の流れは、指揮官たちは何を考えてどう判断したのか、何を持って勝利条件とするのか、どのような規準で褒賞されたのか。そして戦いに使われた技術、つまり武器や戦闘方法はそれまでに比べて進歩していたのか、などを解説した本が、ほとんどなかったのです。 また、軍人はどのように軍人たり得るのか、軍人が政治家になる時どう変化するのかは、何を読んでも書かれていないのです。 無茶な推論で言いますと、学生には知ることが許されない分野だったようなのです。 これが、ものすごく不満でした。最近ようやく風が吹いてきて、ちょっと嬉しい。 著者、大木氏は、序章で上の文章に続けてこう書きます。
このあとの序章では、西欧で発展した戦略・作戦・戦術の区分と、これに関するいくつかの論を説明し、本文に入ります。
なお彼高野五十六が、長岡の名家山本家の名跡を継いで山本五十六になったのは32歳(1916年5月)のことなので、彼の生涯の半分以上は高野姓でした。 といった幼少期、少年時の逸話などは、長岡という内陸の地に生まれ育った少年がなぜ海軍を志したのか、後年の彼の性格や信条、行動規範などはどのような背景から生まれたのか、といったのちの山本五十六を形作った要素を推論するためのものになりますので、この本の概略をメモする目的からするとあまり意味は無いかもしれません。ので、もっとあとの時代を追うこととします。 ひとつメモしておきたいのは、少壮の士官であった時のさまざまな逸話について。 山本について語られる時、必ず出てくる言葉があります。「博才」と「情」。 かつて山本五十六の人物像を語る時、「博打好き」がよく論じられました。将棋にしてもトランプにしても、ブラフと攻め一方の勝負をしたがる傾向があったとか。そこで太平洋戦争での山本戦術が博打的だったと言われたもの。しかし大木氏は、遊戯と本当の戦争を混同するのは愚かであり単純に結びつけるべきではないが、そういう「癖」のある人であった事は留意すべきと言います。 また「情」については、平時において部下の命を大事にした人という評価は多かったのでした。 事故などで部下が行方不明になり生死が案じられると一睡もせず報告を待っていたとか、冷徹であることを要求される指揮官としては過剰と思える情の深さを示したりしています。有名な、空母赤城の艦長時代の話が有名ですね。着艦失敗した航空機がそのまま止まらず甲板を動いていくのを、わが身を挺して走り寄って主翼にしがみつき、あわてた山口多聞中佐ら士官・兵たちが機体に取り付いてあやうく止めたという。 この話に疑問を呈したのが山本昌雄氏(陸士55期・戦後自衛隊で一等陸佐)。彼の海軍と山本五十六を批判する本の一冊で、坂井三郎氏に聞いたとして氏の『嘘です、そんなことはありえません』という証言を上げ、軍神捏造の典型例としています。 この話について大木氏は、海軍上層部への怒りがたぎっていた晩年の坂井氏による感情の発露であろうと推測しています。このエピソードについては、おそらく事実だろう、と。
山本五十六の考え方の根源には、この加藤大将の思想があったのだと。しかし。 海軍内でのいわゆる「条約派」と「艦隊派」の対立において、山本が「条約派」すなわち良識派として条約派三羽ガラスと呼ばれるようになったのは歴史的事実ですが、最初からその路線で行った訳ではないのでした。 ワシントン軍縮会議(1921-1922)のあとのロンドン軍縮会議(1930)に、山本は全権 しかし断固として妥協案でまとめる姿勢を崩さない首席全権の若槻礼次郎に対し、海軍側のトップである財部がそれに同調する姿勢を示すと、決定に従うように海軍随員を押さえたのは山本でした。 この豹変ぶりにはいったい何があったのか。 同時に、このときのどっちともいえる姿勢が、艦隊派の台頭と主に軍縮賛成派が次々と海軍を追われながら終われずにすんだ遠因であると言われます。では、山本はどういう立場に立っていたのか。 これについては、本人の言はなく、周囲の判定も、海軍省からの指示に従った説から、財部大臣へのへつらい・八方美人の日和見主義者説まで、さまざまでした。 これに関し大木氏は、さまざまな傍証より山本は、①財部彪海軍大臣の人格識見や能力を評価せず軽蔑していたこと、②軍人としてまた海軍随員として、主張すべき事は言うが決定が下ればそれに従ったのだ、という論を唱えます。
とはいえこの時点では、海軍戦略を構築するまでにはなっていなかったそうな。山本五十六が未来の国防を考え、新しい海軍戦術は艦隊決戦ではないと喝破するまでには、もう少し時間が必要でした。 その後、海軍航空本部長(1930/12)としてで日本と世界の航空産業、航空技術の知識を吸収すると共に航空機の戦力化について研鑽を積んだのち、第一航空戦隊司令官(1933/10)となって戦力としての航空機、搭乗員の技量を徹底的に高めることに努めます。ここでは、政治的・戦略的判断より、いったん戦うこととなった時いかに戦うか、いかに勝つか、そのために誠心誠意現有戦力の強化に努める姿が見えてきます。 とはいえ戦術を論じていればいい指揮官と、戦略を策定する司令官職の立場はおのずから異なります。 この葛藤は、山本が第二次ロンドン軍縮会議(1934)に、今回は代表の一人として出席したことで変わってきます。 当時まだ少将であった山本(1937年11月に中将に進級)が、各国とも大将級の人材をそろえたロンドン会議に出席できた訳、というのが当時の世相。満州事変(1931)後に拡張主義が台頭した日本で、強硬な政策を唱えた艦隊派が勢力を増し、 しかしその指摘が正しいとすると、艦隊派は落胆することになります。山本はすでに、単に艦隊戦力保持拡大を訴える志士ではなくなっていたから。 とはいえ、「 鬱々と帰国した山本は、1935年12月に航空本部長に任ぜられます。ここで山本が押し進めたのが航空戦力の拡充。特に渡洋爆撃可能な陸上攻撃機は、のちに戦略爆撃機の発想に繋がりますが、そもそもこれは魚雷を搭載できることからも分かるように、より下の次元、作戦・戦術的な兵器でした。外敵に対し渡洋爆撃で先制攻撃を行う発想ですので、戦略とは言えない。 しかし開発された96式陸上攻撃機が、その長航続力と爆弾搭載能力により日中戦争において戦略爆撃に使われたこともまた、真実。 この仕事っぷり、戦艦不要論などにより、先進的ではあるものの航空偏重のきらいもあったのですが、同時に戦艦それ自体の存在価値も認めています。
そして、1936年12月。山本五十六は さらに同年10月に軍務局長として この三人があたったのは日本とドイツとの同盟阻止、というふうに理解されていますが、実はさまざまな難局に対応しています。まず、最初北支事変と呼ばれた日中戦争において、陸海軍を統合する大本営をおくべきかという問題。次にパネー号事件。そして96陸攻による中国内陸部への渡洋爆撃。 このあたりの戦争の推移を述べつつ、米内、山本などの対応に矛盾とか解釈が分かれる内容があることも明記されています。わからない、まだ納得できる定説はない、と変な断じ方をしない書き方をするのも、大木さんの文章の特徴か。 わからないことは、変にこじつけず今はまだわからないと書くことも、大事ですよね。 こうして、後世の史家の視点で見るといろいろな矛盾を抱えつつ、山本五十六はついに海に出る。戦略をつかさどる海軍省の軍政家として歩みを進めながら、1939年8月30日、連合艦隊司令長官に補せられたのでした。 ヒトラーのポーランド侵攻に対し英仏がドイツに宣戦を布告し、第二次世界大戦が始まったのがその数日後。9月3日。 太平洋戦争が勃発するのは、その2年3ヶ月後。 これ以後の山本五十六の作戦、勝利と敗北、そして前線視察中の戦死までは、戦う軍人としての1年4ヶ月でした。 彼はどのように考え、何を行い、日本をどうしようとしたのか。 いまだ、さまざまな矛盾点、見解の相違がある山本の行動について、きっちり説明できる未来は来るのか。わかりません。 そして純軍事的に考えて、戦う艦隊最高指揮官、用兵家としての評価が最後に来ます。 統率、という視点で見ると、心を許さないものへ対する「無口」という欠点はあったにしても、人心掌握の観点からは山本五十六の力量は充分に評価できます。 戦術次元に関しては、判断を下せない、といいます。戦場で下級指揮官としての実績がないから。 作戦次元については、まず真珠湾攻撃についていろいろ批判はあるものの傑作と言っていい、とまず断じます。しかしそれ以後のMI作戦、ガダルカナル戦役に関しては作戦上いろいろな欠点があり、高い評価はできない。総じて愚将とは言わないが、平凡かそれ以下ではないか、とのこと。 戦略次元は、高く評価できるといいます。いきすぎた戦艦温存、航空戦力整備能力の過大評価といった限界はあるが、航空総力戦を予想しての軍戦備の推進、日独伊三国同盟が対米戦争に繋がるとの洞察、対米戦争は必敗という認識。すべて山本五十六の戦略的センスは見事であった、と。 ラインの一部を扱うにすぎない連合艦隊司令長官として、ほぼベストの戦略眼であったのではないか。
この論もまた、歴史の評価を経なくてはいけないと思いますが、現時点でうなずける論ではないかな。(2025/07/12) 読書メーターの記録より 読了:2023/7/17 |
||||||||||||||||||
 |
|---|
| 管理番号:O044-005 | 51 伝記・一代記 |
出版社:KADOKAWA | |||||||
| 書名:天才作戦家マンシュタイン | 「ドイス国防軍最高の頭脳」──その限界 | ISBN978-4-04-082429-1 C0222 | |||||||
| 角川新書 K-485 | 価格:1200Yen | ページ数:452P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2025/6/10 | 購入:2025/6/13 | ||||||||
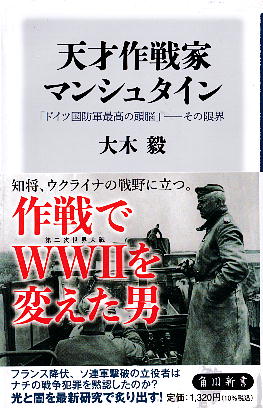 第二次世界大戦最高の名将の令名高きマンシュタインの姿を、現代の視点で軍人として見直したもの。山本五十六のときと同じように、その生涯や生きざまを描写しますが、同時に軍人としての評価を、戦術、作戦、戦略のレベルで行っています。 第二次世界大戦最高の名将の令名高きマンシュタインの姿を、現代の視点で軍人として見直したもの。山本五十六のときと同じように、その生涯や生きざまを描写しますが、同時に軍人としての評価を、戦術、作戦、戦略のレベルで行っています。目次の前の序章は、この本文で始まります。
1887年11月24日、古い貴族の家柄であるフォン・レヴィンスキー家当主、プロイセン軍将校エドゥアルトは男子を授かります。通算で第10子。フォン・レヴィンスキー家とフォン・マンシュタイン家を含む三家は、長年にわたっていずれかの家に男子が絶えた場合他の家から養子縁組をする習慣がありました。この赤子は事前の約束どおり洗礼の後、マンシュタイン家のゲオルクとヘートヴィヒ夫妻に引き渡され、
このあたり、明らかにロンメルやグデーリアンより毛並みがよい。最初から紳士で士官であることを期待されて、高額な授業料を払ってもらって陸軍幼年学校教育から陸軍士官学校へ進むことができたのだから。 生徒としてのマンシュタインはさほど目立った存在ではなかった、といわれます。しかし順調に階梯をこなし、少尉候補生を経て近衛連隊の少尉という申し分の無い軍歴のスタートを切りました。 ドイツ帝国の中で社会的地位の高い軍隊の士官という階層のなかでも、ぬきんでて別格扱いされたのがドイツ軍の中枢である参謀将校だったそうです。マンシュタインがこの登竜門である この本は、こうしてまずマンシュタインの生涯を、今までいいかげんだったところとか誤っていたところを含め見直して書き進めます。このへんはまァいつでも見られる。 有能で誇り高い、気位の高い自信家だったという描写で充分か。そして、致命的な不運を免れたことも。 主眼となる(といち読者として思っている)ところは、彼の評判を固めた第二次世界大戦の欧州戦場において彼が何を行って名を上げ、なにが問題となって戦後指摘されたのか。そして戦術家、作戦家、戦略家としての彼の能力の評価。 という訳でそこを主点としてこの記事では書き進めます。 忠誠を捧げる対象がドイツ皇帝から変遷を経てヒトラーへと変わっていったとき、マンシュタインがナチスをどう思っていたのか、という疑問にまず答えています。これはむろん、単純なものではない。戦後の彼の自伝は徹底的に反ナチ思想で貫かれており、国防軍の軍人として心ならず上の命令に従っただけ、というスタンスになっているから。これは自己保身による欺瞞があるのだけれど、どの程度なのかが論者によって変わります。
とはいえ、反感を持ちつつ自分の有能なエリート参謀将校としての価値を元に存在感を示していたのは事実。 その過程において、ついに1934年8月2日より国防軍の忠誠対象が国家ではなく「国防軍最高司令官アドルフ・ヒトラー」になったとき、マンシュタインもまたそれにならい、それがのちの総統との衝突や反ヒトラー抵抗運動との関係で重大な意味を持つようになるのでした。 1935年7月、マンシュタイン大佐は陸軍参謀本部第一課長(作戦)となり、1936年10月に48歳で少将に昇進します。さらに同年10月に第一部長となります。この職は日本陸軍で言えば参謀本部参謀次長に相当するもので、参謀本部のナンバーツー。この立場で、ナチス・ドイツの戦略・戦術計画に深くかかわることになります。 この時期のマンシュタインの功績はいろいろありますが、とりあえず三つ。 ●軍内部で検討していた再軍備計画に倍するヒトラーの強引な軍拡要求に従い、驚異的な速度で1936年10月までに36個師団を編制したこと。 ●装甲部隊の拡充のみを連呼するグデーリアンの献策を支持し、現実的な方法で装甲部隊の創設・拡張を押し進めたこと。 ●装甲車両の一つとして歩兵の支援を行う大口径砲搭載の 第二次世界大戦がはじまってからの、マンシュタインの戦歴(抜粋)。 ●1939年9月、南方軍集団司令官ルントシュテット上級大将の参謀長(中将)としてポーランド侵攻作戦に従事。17万の捕虜を得るという包囲殲滅作戦を立案し実行。 ●1939年10月、西部戦線に移動して「A軍集団」と改称されたルントシュテット軍の参謀長としてマンシュタインは、フランス侵攻作戦「黄号」に関し従来とは頃なる「マンシュタイン・プラン」を策定し、ルントシュテットの支持を得てOKH(陸軍総司令部)に具申し続け、ヒトラーに直訴までしてついに作戦方針を変更させる。これにより、「作戦時限で戦略的不利を相殺する」という不可能をなし遂げたが、作戦発動時にマンシュタインは第38歩兵軍団長に「栄転」したことで作戦の実働に参加できなかった。 ●1940年5月、英国軍のダンケルク撤退以後フランス掃討戦が行われ、マンシュタインは第38軍団長として連合軍の撃滅およびフランス中部・南部占領のための「赤号」作戦に従事。ロワール川まで一気に掃討する戦果を上げて歩兵大将に進級する。 ●1941年3月、ヒトラーの対ソ戦略変更に伴い、第56自動車化軍団長(装甲部隊)に異動。バルバロッサ作戦に北方軍集団・第4装甲集団の隷下で参加。8月、南方軍集団の第11軍司令官に異動。 ●1942年7月、クリミア作戦に参加しセヴァストポリ要塞を激戦の末攻略。この功により元帥に進級。 ●一時レニングラード攻略のため北方戦線に移動するが、ソ連のスターリングラード奪還作戦により、1942年11月南方のドン軍集団司令官に補され、包囲された第6軍救出任務は失敗するものの戦線を維持したのち、1943年3月、ハリコフを再奪還して戦術的な天才を示した。 ●ヒトラーから自論である「 ここ、Wikipediaではスターリングラード救援戦のあとで「後手からの打撃」が機動防御作戦として行われたかのように書いてありますが、この本ではこの構想は結実しなかったとしています。 ●1943年6月、延期に延期を重ねてきたクルスク ●1944年3月、東部戦線における敗退などの責任を取らされて南方軍集団司令官を解任される。 このあとは終戦まで、マンシュタインは軍の作戦には関与しません。再任に備えて情報を得るための手立てはしていましたが、それだけ。1944年7月の、シュタウフェンベルク大佐によるヒトラー暗殺事件に関してある程度承知していましたが、報告しない・関与しない方針を貫きます。 これは他の反ヒトラー抵抗運動に関与した人々と同じ、彼の「良心」と「服従」の葛藤を示すものという考えもありますが、マンシュタインはそんなナイーヴな人ではない。歴史的な解釈は定まっていませんが、彼が日和見を決めこんだのには、さまざまな理由がありそうです。 マンシュタインは、1945年1月29日、突然ヒトラーに会いに行くと言い出します。実際に宰相府に行き、相当地下壕の前に立ったのですが、総統は会話を拒否したとか。 このときマンシュタインがなにを言おうとしていたのか、解釈はいろいろできますが、歴史の謎です。 マンシュタインは1945年5月5日、英陸軍のバーナード・モントゴメリー元帥に身柄を預け、これ以後は、客人・捕虜・戦犯容疑被告人・受刑者となり、18年の禁固刑に処され、1953年5月7日に正式に釈放されます。 その後、軍人として復権し、ある意味悠々自適な晩年を送ったとか。 彼がはたして戦争犯罪に相当する行為を行ったのかは、この先も議論は続くでしょう。 しかしこの本の書かれた目的は、著者・大木毅さんによる、軍人としての彼の評価。 まず作戦次元において、卓越していたと評します。戦争前の作戦や軍備構想の立案において優れた才覚を見せていましたが、西方攻勢作戦の立案で前評判に恥じない功績を上げました。
しかし戦略次元になると、ちょっと様相が変わります。 戦争というものが軍隊だけでなく国民全体で行われるものとなった現代の視点で見ると、はたしてそういう視点で理解していたのか。戦場で勝つことだけが戦争に勝つことだと錯覚していなかったか。 ナチの戦争犯罪にうっすらと荷担しつつ超然としていたその姿勢は、ドイツの国防軍高級将校としては正しかったのかもしれない。しかし戦争に勝つために、その姿勢は正しかったのか。国民を背負った国家の軍人として、それでよかったのか。 第一次世界大戦において、戦争とは軍人たちのぶつかり合いではなく、国民国家を総動員した戦いとなったのです。しかし第二次世界大戦を戦った将帥の一人として、それは理解できなかったらしい。
そしてこう締めくくられます。
ではどうすればよかったのか。どのような行動を取れば「戦略の次元においても卓越していた」と評されたのか。 この本を読んだだけではわかりませんでした。まだまだ勉強が足りないな。(2025/07/17) 読書メーターの記録より 読了:2025/7/6 |



