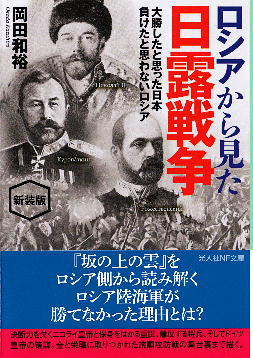 �@�{�̒��\���̗��ɂ����������͂�����܂��B���̖{�̓��e�����������́A���B �@�{�̒��\���̗��ɂ����������͂�����܂��B���̖{�̓��e�����������́A���B
|
�@�{���ł́A1904�`05�N�ɓq���Đ��ꂽ���I�푈�ɂ��ĕ`����Ă��܂��B
�@���E�ɖ������闤�C�R���ł��������V�A�ɒ����{�ł����A�ł̓��V�A�͂��̐킢�ɂǂ̂悤�ɗՂ̂��B
�@�v����忓��������A���}�m�t�����̓y�䂪��炬�n�߂�����A�ꐧ�̐��̎x�z�҂����Ɩ��O�A�푈�ɑ��鋭�d�h�ƐT�d�h�A���܂��܂ȗv�f�ɏœ_�����ć����V�A����������I�푈��ǂ݉����m���t�B�N�V�����ł��B�iP2�j |
|
�@�����āA���̃y�[�W�ɂ���ȕ��͂��B
| �@�@�͂��߂Ɂ@�����������̂̓��}�m�t�����Ń��V�A�l���ł͂Ȃ��iP3�j |
�@�Ȃ�قǁA�������������ł��̗��j��`���̂��A�ƈ�ǂ�����A����������ƈ��Ȃ����ȁHw
�@�܂����I�푈�Ɏ������o�܂ɂ��āA���{���̍l���ƃ��V�A���̍l�������g�p�Ƃ��钘�҂̍l��������܂��B���{�͓��{���̍l�@���菑���āw���{�A�����킦��x�I�ɂ����l�����A���V�A���̎���𗝉����悤�Ƃ��Ȃ��A����ł̓o�����X�������̂ł́B
�@������ǂ�Ŏv���̂́u��������v�Ƃ������{��̌ꊴ�B�ǂ������̒P��́A�u����̍l���ɋߊ��E����Ɋ��Y���v�I�Ɏg���Ă��Ȃ����B������A�u�E�l�Ƃ̍l���𗝉����ׂ��v�Ƃ����Ƒ���ɓ����������ƌ��߂��Ă��܂��悤�Ɏv���܂��B
�@�u��������v�ˁu���葤�̍l�����Âɐ������Ď����̔��f�̌��Ƃ���v�Ƃ����l���͂����Ȃ��̂��B
�@�ǂ������̍������A�l�������ꗂ̈���ƂȂ�悤�ȋC�����܂��B
�@���Ă����ł��̖{�ł́@���V�A�͂Ȃ��푈���n�߂��̂� ���� �c��j�R���C�Ƃ��̐b������ ���� ���V�A�Ɨ����̎v�f ���� �s�R�̏��N���p�g�L���̐^�� ���� �A�W�A�̕s�v�c
���� ���̎��A���V�A�w�c�� ���� �o���`�b�N�͑��̗��R ���� �����ču�a���@�Ƃ������̏͂ƁA���Ƃ����ɂ����āA�Ƃ��ā@�u�a���͐푈�̉������@�Ƃ����\���ł��̐푈�̔w�i�A��Ƃ��ă��V�A���̎�������܂��B
�@���V�A�̍��h�Ƃ������R���͑����̂��߂ɁA���ăs���[�g�����i�݈�1689-1725�j�͔_�z��������ĕ����̓������m�ۂ������Ƃ����邻���ł����A���̖��w�Ŕ_�v�Ƃ��ĈȊO�Ȃ�̋Z�p���Ȃ��j�������A�푈�̂Ȃ�����ɓs��̒��ʼnƒ{���݂Ɉ���ꂽ���Ƃ��A���ʂƂ��ď�ɎЉ�s����������ނ��ƂɂȂ����̂������ȁB���Â����������ł��B
�@���V�A���i�|���I���푈�Ńt�����X�鍑�R�����ނ��A�t�����X�{���܂Œnj��������ƂŁA�A���N�T���h���ꐢ�i�݈�1801-25�j�͗E����y���܂����A���̌��ʉ��B�Ŏ��R�l���v�z�ɐڂ������m�����������c�`�Ō̍��ɗA�����邱�ƂɂȂ�A�ꐧ�̐��̓y���h�邪�����A�Ƃ�����߂͖ʔ����B��������n�߂邩�A�Ƃ�����������܂����B
�@�Ƃ͂������̉e���ŁA�ꐧ�̐��ɕs�������N�Ўq�����̔������N���A�Y�Ɗv���ɂ��Z�p�v�V���o�ė����������{��`�����V�A�̑̐��ɔP�����܂ꂽ���ʁA�Љ�^�����ٓ����A�����������鐧�x�̋����ƒ��r���[�Ȕ_�z����̌��ʁA���V�A�̐����̐��̓}���N�X�v�z�̉e���Ƌ��Ɏ��q�g���̒���������ނ��ƂɁB�����܂ł��Ȃ��E���W�[�~���E���[�j����M���Ƃ���v���Ƃ����ł��B

�@ �j�R���C�Q���@���V�A�c��
�݈� 1894/11/1-1917/3/15
���v 1868/5/18-1918/7/17 |
�@���}�m�t����14��ɂ��čŌ�̃��V�A�c��B���I�푈�E��ꎟ���E���ɂ����Ďw���I�Ȗ������ʂ������A���V�A�v���ɂ����Ċv���R�ɉƑ����X�e�E���ꂽ�B |
�@���̃��V�A�̓��J�̒��ŁA���V�A�c��̖��ɂ��Γ���̌��������ꂽ�Ƃ����B�ނ��A�Z����G�̔ؑ��ގ��ō����̖ڂ����炻���Ƃ��邽�߂ɁB
�@����ɂ́A�u�����v�������Ȃ�����ۓI�ɂ������I�ɂ��r������Ă��܂����V�A�c��Ƃ����n�ʂɏA���ɂ͂��܂�Ɂu�f�łƂ����p������ӎv�v�Ɍ�����A26�̎Ⴓ�̃j�R���C�̎v��������܂��B
�@���̍c��Ɏ����̑唼�̎����ɑ呠��b�Ƃ��čc���⍲��������ɏA���Ă����E�C�b�e�i�Z���Q�C�E�E�B�b�e�@1849-1915�j�́A�j�R���C�ɂ��ĉ�z�L�ł����L���Ă���Ƃ��B
�@�u�Ⴂ�c��́A�ނ�N���҂ɑ��Đe���I���h���Ă����B����͂܂��V��̎ア���i�ƋC���ɂ����̂ł���B���̏�Ԃ����A�������̊��܂킵�����ۂ̈ꌴ���ł���B�����ƒ[�I�Ɍ����A�j�R���C�̎����ɂ��������ł�������B���ƂɃj�R���C�̎����̏����͂����ł������B�����A�ގ��g�͂܂��������ꂽ�l�i�Ƃ��Č���Ă��Ȃ������̂ł���v
�@�T�d�Ɍ��t��I��ł��邪�A�������ł���������I�m�Ɏw�E���Ă���B�u�ア���i�ƋC���v�����Ё����������Ƃ����̂ł���B�j�R���C�����̏����ɂ����遃�Ё��Ƃ͉������p�����ď\�N�ڂɔ����������I�푈�ɂق��Ȃ炸�A�܂��c��Ƃ��Ċ������Ă��Ȃ����n�����푈�Ɣs�k���������Ƃ����Ă���̂ł���B�iP56�j |
�@���̉�z�L�́A�����̒�����ǂ�ꂽ1907-1912�N�ɏ�����A�c�邠�邢�͐��{����̌��{�E�v��������Č��e�͊O���̋�s�ɕۊǂ���A�����1923�N�Ƀx�������ŏ��߂ă��V�A��ł����s���ꂽ�̂������ȁB
�@������b�Ƃ����t���̒��ƂȂ�n�ʂ��Ȃ����V�A�鍑�ł́A�c�鎩�g���t�c�Ŋt���̎�����Č��������ꐧ�̐��ł��������߁A�E�B�b�e�͎��ɍł��c��̐M�������l���ł����B���̔ނɂ��Ă��������]�����ł��Ȃ����V�A�c��Ƃ́A�Ȃ�ƌ������炢���̂��B
�@���Ȃ݂ɃE�B�b�e�͓��I�푈�ɂ͐T�d�Ȏp�������܂������A�푈���Ƃ�����ł͂Ȃ��A�܂����ӋC�ȓ��m�̔ؑ���@�������ł͂Ȃ��A���������҂āA�Ƃ����X�^���X�������Ƃ��B
�@�O�����Ɏn�܂郍�V�A�̓��{�ւ̖��m�ȁu�����点�v�Ɋւ��A���{�͍��Ƃ̊�@�Ƒ�������ł����A���V�A�͖��_�Ⴄ�B�@���Έ������ގ㏬���ł�����ׂ��ɂ��Ă��A������o�����͎������������߂�A�ƍc�鎩�g���܂ߎv���Ă������ƁB����͎i�n�ɑ��Y���������Ă������Ƃł����A�����ɂ������������Ƃ��m�F����ƂȂ��Ȃ��ł��B
�@�����Ă��̐킢�́u��Z�����E���v�ƌĂ�邱�Ƃ�����܂��B���̐푈���P�ɕ��͂ƍ��Ђ̑����ł͂Ȃ��A�����҂̍��Ƃ����{�A�Y�ƁA�Ȋw�A�����ӎ��ȂǁA���Ƃ̑��͂��グ�Đ킢�A���ꂪ�S�ʐ푈�Ƃ��Ď��̐��E���̌��^�ƂȂ����Ƃ����Ӗ��ŁB
�@���_�ǂ�������̈ӎu�͂Ȃ������Ȃ������͂��B
�@�����Ă��̐킢�́A�����ғ������̈ӎu�E�Ӑ}�����ł͂Ȃ��A���ӂ̍��Ƃ₻���]�ސl�X�̎v�f���������̂͂��܂܂Ō����Ă������ƁB���������ꂪ�A���Ȃ�I���ȈӐ}�ɂ���čs���Ă������ƁA����̓��B���B�b�h�ł��B
�@���Ƃ��h�C�c�c��E�B���w�����B�ނ͋�N���̃j�R���C�����_���A���ɜ������ē����ւ̐i�o�ɋ�肽�Ă����܂��B�]�Z�퓯�m�ł������E�B���w�����������Ƃ��Ă����j�R���C�ł����A�݂��ɂ�����J�킷�鉼�z�G���I�ȑ���Ǝv���Ă����ɂ�������炸�A�����̌��v���d�����邱�ƂɂȂ��Ă����܂��B�R�͏�ɑh�C�c�헪�ɐ�O���Ă����ɂ��ւ�炸�A���̊Ԃɂ����{�Ƃ����G����������ނ��ƂɂȂ����̂̓h�C�c�c��̈Ӑ}���������Ƃ����Ă����̂��B
�@���̂�����̍��ې����̗��\�ɂ��āA���{�͂��܂�ɂ����C�ł��肷������������Ȃ��B
�@�키���ƂɂȂ������������̖�������܂����B
�@�܂����̃N���p�g�L���B���m�ɂ͋ɓ������E�Γ��{�R���i�ߊ��Ƃ��ăA���N�Z�C�G�t�Ƃ����c��̒��b������A�n�ʂ͗��R��b���疞�F�h���R�i�ߊ��E���i�ߊ��ƂȂ����ɂ�������炸��Ό��͂����ĂȂ��������Ƃ�����܂����A������키�R�l�Ƃ��Ă̕]���͍�������܂���B
�@���V�A�{��̌��VA�EA�E�A�o�T�͔ނ������]���܂��B
| �@�u�N���p�g�L���͗��R��b�ɂ��Ȃ邾�낤�B��������ƈ̂��Ȃ邩������Ȃ��B���������ǂ݂͂�Ȕނɂ��Č��ł�������Ƃ�������̂��B�Ȃ������킩�邩�B�ނ͒m�b������E���ȏ��R�����A�ނ̐��_�͂܂�Ŏi�ߕ��t���̕������v�iP113�j |
�@�N���p�g�L���ɂ��������i�C�R���܂Ƃ��ł͂Ȃ��E��⋐������܂�ɂ����e���E�����̎����E�Ȃǁj�͂���܂����A�ނ�������u�ދp��p�v�����Ƃ��Ďw�����O�ꂵ�Ȃ��������ƁA�茩���Ȃ����j�������т��Ȃ��������ƂȂǂ��A���ʂƂ��ĉ��x���s��ꂽ��K�͂ȉ��ɂ����āu���ĂȂ������v���ƂŖ����Ƃ��ĕ]���͂���܂���B
�@���{�R�́u�����v�ƍl���܂�������ɂƂ��Ă͂����łȂ������Ƃ������ƁA�ł�������͕ʂȖ��B
�@�嗤�ɂ����钳��헪�ɂ����āA���V�A�͊��S�ɓ��{�ɔs�k���Ă����Ƃ�������������܂��B�����������m�l��̎����Ă��郍�V�A�l���A�����E���F�̍L��ȓy�n�̒��ŏ\���Ȑ����������ł���͂����Ȃ���A���{���͓����푈��ɐ���ɂȂ��������������̉�����O��I�ɗ��p���ă��V�A�̍A���܂Ő������邱�Ƃ��ł��܂����B
�@���̖{�Œ��҂́A�Ό��^���i1868-1942�@�ޖ������R�����卲�j�A���������i1860-1945�@�{���F�ԓc���V���@�ޖ������R����j�Ȃǂ̖��O�������܂��B���O���ʂ����l���Ƃ��ẮA���Ό���Y�i1864-1919�@���R�叫�j������܂����A
| �@������H��̕]���͂��܂��܂ŁA���s�������Ƃ�������������B������ɂ��Ă������͎��s���āA���߂Ė���݂ɏo��B�]������Ȃ��ē��R�Ȃ̂ŁA�X�p�C�Ƃ͂����������̂ł���B�v�iP138�j |
�@�ƁA�ǂ������������鏑�����ł����B���ɃC�`���c����̂����H(��)
�@������ɂ��Ă����{�̒����̓��V�A�̂�����͂邩�ɍ������ʂ��o���Ă����A�Ƃ������Ƃ炵���B
�@���V�A�̓��I�푈�Ɋւ��钘��ł́A���{�ŗL���Ȃ̂́u�������v�iA�EN�E�X�e�p�[�m�t���j�Ɓu�c�V�}�v�iN�E�v���{�C���j�����邻���ł��B�i��҂�ǂ悤�ȋL��������̂ł����A�͂邩�̂Ȃ̂œ��e�͒肩�ł���܂���B�j
�@�����͂ǂ�������J�I�Ȕs����ނɂ��A�i�n�ɑ��Y�̕]�ɂ���
| �@�u��҂͓��{�l�̍��̐����́A���ׂĈ��]��@�q����ŏo�����̂ł���Ƃ��A����A���V�A�̈����I���Z�ƕ��m�́A���̔R����悤�Ȉ����S�������Ă����h���A���{�l�ɏo���������A���₤�����{�����ć��j�Y���鏟���҇����炵�߂悤�Ƃ����A�Ƃ����Ӗ��̂��Ƃ������Ă�����v�iP167-168�j |
�@�Ȃ̂������ȁB
�@�ǂ�����\�r�G�g���{���������Ĉȍ~�̏o�łŁA�ŏI�I�ɔs��̐ӔC�����V�A���O�ł͂Ȃ��鐭���V�A�̃��}�m�t�����ɖ₤�������ɂȂ��Ă��܂��B���ʂ���{�Ƌ��ɐꐧ�̐��̎x�z�w����ׂ����ƁA���ꂪ�\�r�G�g���Y�}�̕��j�������Ǝv�������̂��B
�@�X�e�b�Z���ƃ��W�F�X�g�E�F���X�L�[�Ƃ�����l�̔s���ɂ��Ă��A���҂͐h���]�����c���܂��B
�@�T�؊�T���R�����ɂ��Ăł����A�����U����̏d�݂Ƒ���ȋ]���킴��Ȃ��������ƂŁA��O�͖����A���ꎞ�����Ƃ���A���݂͕s���̗E���Ƃ��Ă̕]���ɗ�����������悤�ł��B��O�́A���̖�����������Ƃ������ɂȂ�Ɠ��{�Ƃ��Ă͑���������ł����ė~�����Ƃ������Ƃŗv�ǖh�q�̌����Ƃ��ĕ]����܂��B���������ɔނ͌R�@��c�Ɋ|����ꏈ�Y���߂������ꂽ�Ƃ����B
�@���W�F�X�g�E�F���X�L�[�����ɂ��āA�ނ͊͑����^�q�����邾���̔\�͂ɂ�������l���Ƃ��āA���̊͑��͕�����ׂ����ĕ������Ǝ茵�����B�ނ̕��j�͓��{�͑��Ɛ키���Ƃł͂Ȃ��E���W�I�X�g�b�N�`�Ɉ�ǂł������������ނ��Ƃ������ƒf���A��p�������Ȃ��q�C�����Ƃ��܂��B���{�C�C��̊J�n���A���̃��V�A��͓ˑR�̐w�`�ύX���s���Ċ͑��������������܂ܐ퓬�J�n�ƂȂ�A��ł��܂��B
�@���̖{�ł͓ǂ݂��҂̌��Ńn�e�i���������_�ł��Ă����̂ł����A���̂�����̕`�ʂŃA�n�A�ƂȂ�܂����B
�@�v���{�C���u�c�V�}�v�̒��ŏ����Ă��邱�Ƃ����p���Ă��܂��B
�@���W�F�X�g�E�F���X�L�[���Ȃ��ˑR�A�w�`�^�����v�������̂��B�v���{�C�͂����w�E����B
�@�u�Ƃ��Ƃ����̂Ƃ��A���ꂾ���y�e���u���O�ł��̐푈�\�͂��ӐM�I�ɐM�����Ă������͑��i�ߒ������W�F�X�g�E�F���X�L�[��ɁA�N��l�Ƃ��ė\�����Ă��Ȃ��������Ƃ������オ�����B�퓬���܂��n�܂邩�n�܂�Ȃ������ɒ�̂��������Ȑw�`�^���̂������Łw�I�X�����r�A�x�͑O���́i���Ғ��A������Ō���A�����[���j�Ɋ͎��˂����ސS�z����A�@�ւ��~����������Ȃ������B�G�͂��̋@��𗘗p���ď\�Z�_�̏������s���A���s�R�[�X�����A����܂�C���w�I�X�����r�A�x�ɗ��т��������v
�@�헪�ɏڂ����Ȃ��M�҂͏�����Ă���ȏ�̒lj��`�ʂ͂ł��Ȃ��B���{�R�̏���������Â����Ƃ���遃�\����@���Ɗւ���Ă���̂ł��낤���A������̐擪�ɂ����I�X�����r�A���W���C�𗁂сA�퓬���{�i�������̂͂��ꂩ��ł���B�iP230�j |
�@�܂��v���{�C���̒��삪�������Ȃ��̂����p���������Ȃ��̂��A�������w�E�������_������܂��B
�@�C��J�n���A�u�I�X�����r�A�v�͑�����̐擪�ł����A������̌�ɂ����̂ł͂Ȃ�������̍��ߌ��Ɉʒu���Ă���A������̍Ō���̃t�l�ɓ˂�����ł����Ȃ����擪�̒��O�ɋ@�ւ��~����ȂǂƂ����댯�ȓ���͂��Ă��܂���B�����̃��V�v�����C�@�ւł�����A�@�ւ��~������Ďn���ɉ��\���������Ԃ�������܂��B
�@���{�͑��͊C�활�����V�A�͑��̓���}���邽�߃��̎����`�����鏇�����s���܂����A�ނ��16�_�ł͂���܂���B���̐�@�́u������@�v�Ƃ��Č��`����܂������A�����̓��{�C�R�́A���Ȃ��Ƃ����܂ł��̐�@���u�����v�Ɠǂ�ł��܂���B
�@�u�I�X�����r�A�v���W���C�𗁂т��͎̂����ł����A����͓��{���ɋ߂����̐퓬�ɂ��������߂ŁA������̌�ɂ����̂ł͉������܂��B
�@�s�����W�F�X�g�E�F���X�L�[�́A�����̓��{�ł͗����Ɠ����悤�Ɂu�D�ꂽ�G���v�I�ȕ]�������ꂽ�悤�ł����A�C���ɍ����ۊC�R�a�@�Ŏ��Â��ċA�����A�{���ŌR�@��c�ɂ�薳�ߔ����͏o�܂����R�ЂD����đޖ��������܂��B
�@�܂�A���V�A�C�R��������ׂ����ĕ������̂��A�Ƃ����B
�@�u�a��c�ŁA���͊ш�i1873-1949�j�Ƃ������j�w�҂ɃX�|�b�g��������܂��B���{���{���琳���ɗv������|�[�c�}�X��c�ɂ�������{�̌����������肵���l���B�u�����̎����ɑ��āA�����̎������o���ɂ���悤�ł���A�����ڂŌ��Đ��E�̗������Ȃ��v�Ƃ��āu�����S��r���Č����ȗ���œ��I�푈���܂Ƃ߂�v�ƕ]���ꂽ������G�[����Ă��x�����܂��B
�@�������ՂƂ�����{�Ă���A�|�[�c�}�X���͓��{���S���E���������Y�ƃ��V�A�S���Z���Q�C�E�E�B�b�e�̊Ԃōs���܂��B���҂̐S���𒍂������̌��ʁA���B�e���̗��Q�ɑË�����������܂��B���̌��ʓ��{�͐폟�����͂��Ȃ̂ɓ슒���������Ȃ��������ʂɁB�̍��ɖ߂��������ƃE�B�b�e�͂ǂ�����A���������҂��鐬�ʂ�ꂸ�����z��������܂��B
�@���j�̔�����B
�@����ƌ���������A�ʔ����l�^������܂����B
�@���V�A�����Ŕ��Q����郆�_���l�̂��߂ɁA�A�����J�ŐS���𒍂��œ��{�̂��߂ɐs�͂��Ă��ꂽ�S�ă��_���l����̉�W�F�C�R�u�E�V�t���A����͎i�n�ɑ��Y���́u��̏�̉_�v�ł��Ȃ�D�ӓI�ɕ`����Ă���l���ł����A�푈�����{�̊O�邽�߂ɐ��͂��X���Ă��ꂽ�̂��A�|�[�c�}�X�u�a��c�̑O��A���V�A�S���̃E�B�b�e�̂��߂ɃA�����J�̐��_�����V�A�ۛ��ɂ��邽�߈Ö��̂��Ƃ��B
�@������܂��A���j�̔�����̂��́B
�@�Ƃ͂����A�ǂݏI����Ă����v�����B
�@�����܂Ń��V�A�����ƂƂ��Đ킦�Ȃ���Ԃł����āA���V�A�R�l�����\�Ď�Ȃ̂��Ƃ���ƁA���{�R�̕����Ԃ�͂���قLjӖ����Ȃ������̂��B���V�A���Ȃ߂��d�͍����������A�Ȃ�Γ��{�͂ǂ��������̂��B
�@���̕��ɖ{����ł͌��s�����Ȃ������̂��A���҂̌��E�Ȃ̂��B
�@���[��A������Ɣ[�������Ȃ��nj㊴�B�i2024/9/19�j
�@�Ǐ����[�^�[�̋L�^���@�@�Ǘ��F2024/9/6�@ |

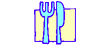

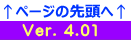
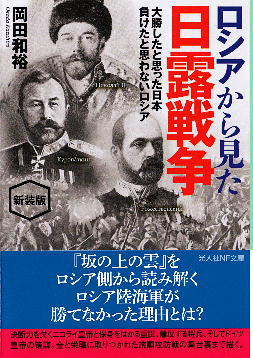 �@�{�̒��\���̗��ɂ����������͂�����܂��B���̖{�̓��e�����������́A���B
�@�{�̒��\���̗��ɂ����������͂�����܂��B���̖{�̓��e�����������́A���B