トップへ戻る 作家/分野 一覧 |
|
 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 書 名 | 翻訳者 | メ モ | |
|---|---|---|---|---|
| R002-001 | 金星の尖兵 | 井上一夫 | 人類唯一のテレパスが遭遇した事件 | |
| R002-003 | 自動洗脳装置 | 大谷圭二 | 自分が人殺しだったと知った技術者 | |
| R002-004 | わたしは“無” | 伊藤 哲 | 思想やモラルなどをテーマとした奇妙な短編集 | |
| R002-005 | パニック・ボタン | 峰岸久 | ラッセルの1950年代の日本オリジナル短編集 | |
| Ver. 2.23 |
|---|
| 管理番号:R002-001 | 10D ディザスター・侵略SF | 出版社:東京創元社 | |||||||
| 書名:金星の |
ISBNなし | ||||||||
| 原題:Three to Conquer (1956) | 翻訳者:井上一夫 | ||||||||
| 創元推理文庫 737 631-1 | 価格:170Yen | ページ数:273P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:1965/12/24 第7版:1971/2/26 | 購入:1973/3/18 | 表紙イラスト:金子三蔵 | |||||||
 1980年4月1日、万愚節の日よりこのお話は始まります。 1980年4月1日、万愚節の日よりこのお話は始まります。ただし、この本が書かれたのは1956年ですから、24年後の未来。 大都市では移動道路がいくつかできているし、月に気密ステーションが6ヵ所できている。金星探検が進んでいるという話だ。火星へ着陸できるという噂もあるが、成果はないようだ。でも自動車はエンジンが後部になって燃料が添加剤を入れたアルコールになった程度で特に大きな違いはない。一台2000ドルで作れるヘリコプターが話題になっている。短波無線の電話を使うこともできる。電話機も、テレビ機能はむろん付いている。 そんな程度の未来です。 主人公ウェイド・ハーパーは、「細菌を手術できる器具の製作者」です。なんだかわかりますか? マイクロサイズのメスだの鉗子だのや、それを操作する機械を作っている人だそうな。 同時に、彼は副業というか趣味として、迷宮入り事件の解決を行っています。彼が何の気なしに誰かをにらむと、罪の意識のある人間の声が聞こえるのです。そう、彼は世界にひとりしかいない(?)、テレパスだったのです。 ある日、死にかけた警官の声を聞いたことで女性の拉致事件に巻き込まれたハーパーは、救出された女性が事件などなかったと主張したことに疑問を持ち、女性の家に向かいます。 自宅の前で鍵を取り出した彼女に、テレパシーの「触手」を伸ばした時、普通なら絶対に気づかれないはずのその精神接触に気づいた彼女は振り向き、こういう心の叫びを上げました。 「この地球人の畜生め!」 金星(ヴィーナス)とヴィールスの類似からこのアイディアを得たのかも知れない、とあとがきで厚木淳さんが書いています。 謎の異星人が、今きみの後にいるかも知れない、という恐怖は、冷戦の開始という当時の社会情勢をリアルに示していますね。 そういえば、近未来と、ミステリと、超能力と、異星人侵略テーマの融合などは、今でこそ珍しくも何ともありませんが、この時代はSFの最先端でした。アイディアはたくさん出ましたが、半世紀近く経って読むに耐える面白いものは、あまりありませんね。この本は、どうかな。 警官でもFBIでもないハーパーは、風采が上がらない中年男で、犯罪に対しても陰謀に対しても素人です。しかし危機に当たって示した彼の示した正義感は、いかにも健全なアメリカ人らしいものです。こんな人たちが、当時の理想だったのかも。 ラッセルのユーモアにあふれた文章が、スリリングな展開を盛り上げます。面白いね、この人の文章。 (09/6/14) |
| Ver. 2.23 |
|---|
| 管理番号:R002-003 | 10 SF一般 | 出版社:東京創元社 | |||||||
| 書名:自動洗脳装置 | ISBNなし | ||||||||
| 原題:With a Strange Device (1964) | 翻訳者:大谷圭二 | ||||||||
| 創元推理文庫 809 631-3 | 価格:170Yen | ページ数:238P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:1970/1/9 第2版:1970/6/19 | 購入:1973/11/25 | 表紙イラスト:真鍋博 | |||||||
 「洗脳」という言葉を最初に知ったのはこのSFじゃなかったかな。 「洗脳」という言葉を最初に知ったのはこのSFじゃなかったかな。この言葉は、正しくは 「ある人の思想や主義を、根本的に変えさせること」 という意味です。なんと、この言葉を最初に作ったのは中国なのだそうな。第2次大戦が終わって朝鮮戦争の頃、彼らは自分たちの 「誤った思想を持った人の知識を思想教育で洗い流し、正しい思想を流し込む」 行為を 「洗脳」 と名付けたそうです。その思想教育のものすごさ、恐ろしさに唖然とした西欧側がこれを「Brainwashing」と呼び、日本人はこの言葉を、あらためて「洗脳」と翻訳したとか。なんとまあ、言葉の流れとは面白い。 言葉自体はインパクトがあるのですが、1970年頃の日本の翻訳者・編集者たちは、この「洗脳」の意味をよく理解していませんね。あるいは、どうせわからないだろうと読者の知識に高をくくっていたのかも。 この本の題名に使われている「洗脳」は、間違った意味で使われています。自動でもないし。 主人公はリチャード・ブランサム。アメリカの防衛施設に勤務する冶金学者。 この厳重な研究所では、色で勤務場所の重要度が分けられます。黄色レベルの作業者が青色レベルに入る事は許されない。青色レベルが黄色に入る事は出来ても、紫色レベルに入ることはできない。ヒエラルキーの頂点に立つ黒色レベルになると、神か大統領と同じ権限を持つことになる。 しかし最低レベルの白色クラスであっても、この研究所に入る際には、厳重きわまりない検査をされてようやく入れるし、何か怪しい行為をすればすぐに放逐される。トイレの中でさえもプライバシーなど欠片もない。 しかしここまで厳重に管理された最重要施設でさえ、無敵ではなかったのでした。 赤区域の技術者であるブランサムが最初に聞いたのは、同じ職場の高真空内現象の専門家ヘイパニーがいきなり辞職したこと。 全く何の説明もなく、ともかくやめたいという。上司や保安関係は、ノイローゼ、病気などはもちろん、脅迫などの陰謀、そして最悪の可能性、彼が国外へ行こうとしていないかまで調査します。しかし、全くその兆候がない。ヘイパニーはこの、保安関係のこともあり緊張を強いられるものの高給と将来の年金まで保証された職を投げ打ち、皿洗いでも何でもして食いつなぐが、この仕事だけはしたくないという。 しかし、何らかの理由で職を離れた職員は、実は彼が最初ではなく、むろん最後でもなかったのでした。 ブランサムの身の回りだけでも、マクレーンとシンプスンはアマゾンに休暇旅行で行ってそのまま蒸発。ジャコバートはアルゼンチンの大牧場の女富豪と結婚したと言って去っていった。ヘンダースンは出し抜けにやめて、西部のどこかで金物屋をしている。マラーは自殺したらしい。アーバニアンはドライブしていてそのまま海に飛び込んだ。 何か起きているんじゃないかい? というのは、ブランサムにとっては単なる食堂での噂話。 しかしそのあと、ブランサムの身に大事件が起きます。 いつものように汽車待ちの間、軽食堂でコーヒーを飲んでいると、長距離トラックの運転手らしい男たちのうわさ話にを聞きます。バールストンの町で洪水があり、街道の横の大木が倒れ、20年ほど経った女の骸骨が現れたのだという。 ブランサムは驚愕する。その白骨死体とは、かつて彼が殺してしまった女ではないか。 政府によって生まれたときからのことを完全に調べ上げられ、徹底的に照査され、完璧に無傷な彼の履歴の中で、たったひとつの傷。 ありえないはずの、新しい事実が今あらわれた。どうして。 ブランサムは誰にもそれを話せないまま悩み、やがて決心して1週間の休暇を取ってバールストンに向かったのでした。 しかし、バールストンという町には、全く彼の記憶にあるものがない。しかも洪水など誰も聞いていない。白骨死体などなにもない。 いったい何が起きているのか。 冷戦時代なのですね。「金星の尖兵」よりももっとストレートに「彼らの脅威」を正面に立てています。 ラッセルのユーモアあふれる文章が、この物語では少し硬い。SFの世界でも、こんなお話が書かれていたのですね。 (09/6/14) |
 |
Ver. 3.04 |
|---|
| 管理番号:R002-004 | 10 SF一般 | 出版社:東京創元社 | |||||||
| 書名:わたしは“無” | ISBNなし | ||||||||
| 原題:Somewhere a Voice(1965) | 翻訳者:伊藤 哲 | ||||||||
| 創元推理文庫 631-4 | 価格:260Yen | ページ数:272P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:1975/9/26 | 購入:1975/10/6 | カバー:金子三蔵 | |||||||
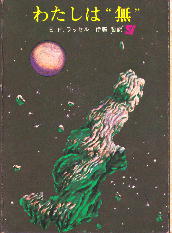 エリック・フランク・ラッセルの、さまざまな主題で思想やモラルというSFではふつう描かないテーマをもとにした短編集です。 エリック・フランク・ラッセルの、さまざまな主題で思想やモラルというSFではふつう描かないテーマをもとにした短編集です。どこかで声が・・・ Somewhere a Voice(1953) 旅客船<スター・クイーン>号が小惑星の衝突によって破壊され、わずかに9名が救命艇で近くの惑星に墜落し、命は助かりました。ここ、ZM17の第6惑星ヴァルミアには、救急ステーションがありますのでそこまで行けばいいらしい。しかしそこまで、距離は一万七千から二万マイル。歩いていけるのか。 副機関長で反応炉技師のビル・マレットは、生き残った連中を見て心の中で悪態をつく。役に立つ有能な乗組員は、自分を入れてわずか3人。あとは東欧の惨めな移民夫婦、黒人だからどうせ馬鹿なはずの機関助手、食堂の下働きの無学な中国人、ユダヤ人だからダイヤを後生大事に持っているはずの馬鹿な商人。こいつらといっしょに徒歩で旅するのか。 自覚していないさまざまな偏見に満ちたマレットの旅路の中で、聞こえた声とはなんだったのか。 U-ターン U-Turn(1950) 火星にすむ287歳のダグラス・メイソンは、三回目の若返り処置を行ったのち、「生命終末ビル」の受付前に立ちます。もはや生きる必要を感じなくなったから。しかしこの合法的自殺施設で「死んだ」メイソンは、そこで何を見たのか。 彼は、何から、どこへU-ターンしたのか。 忘却の椅子 Seat of Oblivion(1941) 人間の霊魂を解放し他の人間に移すことが可能な技術を知った凶悪な逃亡犯ジャンセンは、開発者のウェインを脅して見知らぬ青年に自分自身を移します。これにより、「ジャンセン」は死んだことに。これが上手くいったことに味を締め、犯罪を犯す度にまったく別な人間に乗り移る事を繰り返すジャンセン。しかしウェインの取引の話に乗ったために彼は。 凶悪犯罪者の人格や人権がまったく考慮されなかった時代ですねぇ。 場違いな存在 Displaced Person(1948) 公園のベンチでわたしが出会った紳士は、非の打ちどころのない威厳のある姿。音楽が好きだという。 他人の言葉にまったく耳を貸さない自らの栄光に酔いしれた指導者のことを話します。それに対する反乱を指揮したのが彼なのだという。それは失敗し、彼は再起をもくろみますが、いまの彼には居場所がない。どこにいても場違いな存在。 最後に、自分の名前をそっとつぶやく。ふたたび天を望む堕天使だと。 ディア・デビル Dear Devil(1950) 地球に着陸した宇宙船から降りた火星人たちは、その荒廃ぶりに唖然とします。その中の一人、士気を維持するために乗船している詩人のファンダーが、一人でここに残りたいと志願しました。彼はこの惑星で出会った子供に「悪魔(デビル)」と呼ばれます。 ゆっくりと滅びゆく火星人たちは、生きのびるための世界を探していたのですが、ここでたった一人残された火星人ファンダーは、いったい何を残せたのか。 わたしは“無” I Am Nothing(1952) 独裁者ダヴィッド・コーマンは、レイニの奴らに最後通牒を送ることと共に、艦隊司令に進撃の際には自分の息子リードを先頭に立てるよう命じます。何もかも自分の意志で決め、その意志を他人に押しつけることになんの疑問も持っていなかった彼にとって、それがそのまま行われることはあたりまえのはず。しかしその息子がレイニの娘と恋に墜ち、戦争が終わるまで自宅で彼女を世話して欲しいと母親に手紙をよこしたとき、コーマンは愕然とします。この娘は何者なのか。 “無”とはいったい何だったのか。 なるほどね、こんな時代にラッセルはこういう指摘、主張をSFの場で書いていたのか。 SFとして、とか科学的世界としては、もはや時代からはるかに取り残されているけれど、ラッセルの言葉は奇妙に新しいところがあって、面白い。(2017/6/11) 読書メーターの記録より 読了:2017/5/8 |
| Ver. 2.23 |
|---|
| 管理番号:R002-005 | 10SS SF短編集 | 出版社:東京創元社 | |||||||
| 書名:パニック・ボタン | ISBNなし | ||||||||
| 原題:The Timeless Ones AndOtherStories (?) | 翻訳者:峰岸久 | ||||||||
| 創元推理文庫 631-5 | 価格:300Yen | ページ数:282P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:1978/11/17 | 購入:1978/11/27 | 表紙イラスト:スタジオぬえ 加藤直之 | |||||||
 あとがきによりますとこの短編集は、“Far Stars”(1961) をそのまま訳出する予定だったそうです。しかし諸事情のため、収められていた6本の短編の3本までが他の短編集に収録されてしまい、初紹介の機会を失ってしまったのだそうな。そこで、他のラッセルの短編を3作選び出し、原本の未訳文と合わせてアンソロジー的な短編集としてまとめたのだそうです。 あとがきによりますとこの短編集は、“Far Stars”(1961) をそのまま訳出する予定だったそうです。しかし諸事情のため、収められていた6本の短編の3本までが他の短編集に収録されてしまい、初紹介の機会を失ってしまったのだそうな。そこで、他のラッセルの短編を3作選び出し、原本の未訳文と合わせてアンソロジー的な短編集としてまとめたのだそうです。原本にあった3作は※マークを付けてあります。 追伸 P. S. (1953)※ 老いた医師ハリスン先生の遠い遙かな過去、彼が少年だった頃、「宇宙間交流協会」という組織が募集して選抜した異星人との文通相手として選ばれたことがありました。千人に一人の幸運に喜んだものの、少年だった彼は文通相手が女の子らしいと知って落胆したもの。しかし数年間、間をおいた文通が続くにつれ、リーバ星のバンドラシャンダというペンフレンドと彼の間には、情愛に似た友情が芽生えます。 それから数十年。妻を得て死に別れ、子もいないままに町の名士になっていたハリスンの前に現れた青年は、彼になにを告げたのか。
さあ息を吸って Now Inhale (1959) ゴンバール人に捉えられた地球人ウェイン・テイラー。地球を敵視する彼らは、問答無用で彼を処刑しようとしています。 しかし彼らの習慣で、なにか最後にゲームを終えてから最期を迎えるのだそうな。条件は、白熱するゲームであること。勝っても負けても、終われば即処刑であること。これは、と思ったテイラー。何を考えたのか。 時を持たぬ者 The Timeless Ones (1952)※ 宇宙文明の初め、あらゆる生命の起源を調査しているクスティス・ヴジャーム教授、かつて滅びたケンタウリ星のモルダリア人の歴史を研究してある発見をしました。彼らに取って代わったのが、いまそこにいる、柔らかい軽い皮膚で、二本しか足のない哀れなミッジーたちらしい。戦いではなく、一万六千年の年月をかけ、いつの間にか取って代わってしまった。しかもミッジーは決してそれを意図した訳ではないらしい。いつの間にか、文明種族が消え、ミッジーが残っている。 教授の研究によると177の星系が、ゆっくりとミッジーに支配されていたのでした。そして今もこの惑星上にミッジーはいる。数千年前から。人の嫌がる仕事をしながら。そこの洗濯店のまえで卑屈に微笑んでいる黒い目の、時を持たぬ者が。 黄禍論の一つのパターンなのかな? 洗濯店しか入り込む隙間のなかった西欧の社会で苦闘した東洋人は、こうも見られたのか。 証人 The Witness (1951) 1977年5月17日、ある裁判が行われています。判事は5人、陪審員はいない、10億の市民がTVを通じて注視している裁判です。 被告は、プロキュオンの領域のいち惑星から来たマエスという生物。身長3フィートほどで明るい緑色をしており、“教育を受けたサボテン”といった外観。大きな、訴えるような光を湛えた金色の目。頭に宝石を付けたヒキガエル、といった感じ。 田舎町の家や食料品店に入り込んで食料を食べた、というのがその生物の「罪」らしい。 裁判はだんだんとそのテレパシー能力を持つが会話が出来ない異様な生物への敵意に支配されていきます。 マエスがチョークで黒板に、自分は故郷の世界を追われた不適格者だったと書くことで、人々の嫌悪はさらに高まる。 絶体絶命のなかで、弁護人が最後に持ち出した弁護側証人とは、一枚の写真でした。 パニック・ボタン Panic Button (1959) 地球人というのは、忌々しい種族なのでした。アンタリア人が銀河を旅して新しい惑星を発見してその領有権を宣言しようとすると、必ずそこにいるのです。しかも、アンタリア人が堅実にひとつひとつの惑星を丁寧に開拓してそれから新たな進出をするのに、彼らは新しい惑星の目だつ所に怠け者の地球人一人を住まわせ、後から来るアンタリア人をあざ笑うだけ。そして次の星に行ってしまう。 ここは非常手段に訴えてでも星を手に入れなくてはいけない、と考えたのはラガスタとカズニッツ。彼らは地球人の家に入り込み、拉致しようとします。地球人は平気な顔をして壁のボタンを指さし、君らが来た時にもうあのボタンを押したよといいます。 根気仕事 Legwork (1956)※ アンドロメダ人ハラシャ・ヴァナシュのささやかな地球侵略と、それを迎え撃つことになった地球人たちの奮闘。 ストーリーを書いてしまうとこれだけなのですが、この短編集でいちばん長い作品は最後までスリリングでユーモラスです。 あとがきで、この短編集の成り立ちと共に、ラッセルという人は当時の英国SFの伝統的な、重厚さや、シリアスで社会性が強い特徴をあまり持たない作家だと紹介しています。アメリカの雑誌が活躍の場だったことが大きいのではないか、と説明します。 それでもアメリカナイズされていながらアメリカの者とはひと味違う、人間の心が社会の規範がもつさまざまな “こわばり” を大きく広げて見せるさまはやっぱりイギリス人作家だね、とのこと。 そうかな? と思ってしまった。 たしかにそういわればそんなイメージもあるけど、無理にアメリカ作家、イギリス作家の範疇にあてはめすぎていない? 当時はこんなステレオタイプの分類があったんだね、とちょっと懐かしく思い出しました。 (2011/5/26) |
||||||||||