 トップへ戻る  読んだ本の分類 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 書 名 | 翻訳者 | メ モ | |
|---|---|---|---|---|
| Z009-001 | ジョゼフ・フーシェ | 「完全無欠な裏切り者」の生涯 | ||
| Z009-002・003 | マリー・アントワネット(上・下) | 関 楠生 | 負け戦を戦いぬいたお姫様 | |
 |
 |
|---|
| 管理番号:Z009-001 | 51 伝記・一代記・評伝 |
出版社:中央公論新社 | |||||||
| 書名:ジョゼフ・フーシェ | ──ある政治的人間の肖像── | ISBN978-4-12-207542-9 C1123 | |||||||
| 山下肇訳 『ジョゼフ・フーシェ』(1970年、潮文庫)を底本とし、山下萬里が全面的に改訳したものです。 | |||||||||
| 中公文庫 ツ2-3 | 価格:1300Yen | ページ数:392P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2024/7/25 | 購入:2024/8/4 | カバー画:René-Théodore Berthon Edouard Dubufe 《Joseph Fouché dit Fouché de Nantes, duc d’Otrante》 19世紀後半 カバーデザイン:高林昭太 |
|||||||
 |
|---|
| 管理番号:Z009-002・003 | 51 伝記・一代記 |
出版社:河出書房新社 | |||||||
| 書名:マリー・アントワネット(上) | ISBN4-309-46282-0 C0197 | ||||||||
| 原題:Marie Antoinette(1932) | 翻訳者: 関 楠生 | ||||||||
| 河出文庫 ツ1-1 | 価格:650Yen | ページ数:368P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:1989/6/22 新装版初版:2006/11/20 | 購入:2025/2/12 | カバーデザイン:渡部和雄 カバーフォーマット:佐々木暁 |
|||||||
| 書名:マリー・アントワネット(下) | ISBN4-309-46283-9 C0197 | ||||||||
| 河出文庫 ツ1-2 | 価格:650Yen | ページ数:336P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:1989/6/22 新装版初版:2006/11/20 | 購入:2025/2/12 | カバーデザイン:渡部和雄 カバーフォーマット:佐々木暁 |
|||||||
 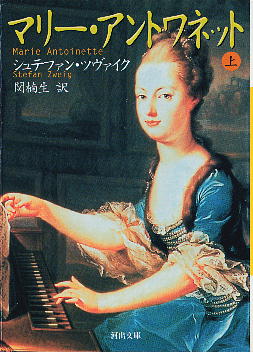 評伝「ジョゼフ・フーシェ」を読んだあとで、そういえばこの方は「マリー・アントワネット」の評伝でも有名だったっけ、あの漫画「ベルサイユのばら」のアイディアの元になった本じゃなかったか、と連想は進み、入手してみました。 評伝「ジョゼフ・フーシェ」を読んだあとで、そういえばこの方は「マリー・アントワネット」の評伝でも有名だったっけ、あの漫画「ベルサイユのばら」のアイディアの元になった本じゃなかったか、と連想は進み、入手してみました。「ベルサイユのばら」に関してはいろいろ意見はあるのですが、まァこれだけ年月が経つと、昔思っていたこともどうでもよくなるようです。
この本が書かれた時代(1930年代)に限らず、彼女を描くということは彼女をどんな視点で見るかで変わるから。 告発者が革命側であったとき、王制を倒す大義名分として王家の中に悪者を作る必要ができ、この外国から下りてきた贅沢好きな王女様は格好の悪役となり、マリー・アントワネットをギロチンに書けるためなら何を書いてもよかったのでした。 しかしブルボン王朝が復権したとき情勢はがらりと変わります。これを描くツヴァイクの言葉が面白い。
ツヴァイクは、この女性を、平凡でごくありきたりの、賢くもなく愚かでもなく、火でも水でもなく、善を行う力もなく悪におもむく意志もない、およそ英雄たるべき資質など持っていない人だとまず断じます。 そして英雄たるべき資質を持った人ならば、悲劇的な緊張を強いられらばされるほどその真価を発揮し、天高く飛翔するのだが、平凡な人はそのような緊張を欲せず必要ともしない。運命が変転すればおびえ、不安に駆られ、逃げ出す。それが当たり前で何ら恥じる事はない。しかし。
そして、嫁に出された子供の話から始まります。 ハプスブルク家とブルボン家の欧州での主導権争いがいつまでたっても決着がつかず、もういいかげん一息入れようや、となったのは、オーストリア帝国の実権を握るマリア・テレジアによるもの。もう一人は、というと佐藤賢一さんの筆によればポンパドゥール夫人ことルイ15世の筆頭公妾なのですが、ツヴァイクはショワズール公としていますね。男がなしえなかったメンツより平和への路線転換を女同士がやってのけたという佐藤さんの筆も面白いけれど、どうなのかな。 その絆として婚姻を行うのがハプスブルク家の面目躍如。とはいえ、独身ではあるけれど孫がいるし品行方正とは言い難い王でも、口やかましいオールド・ミスである三人の王娘たち候補から外されます。で、その結果すったもんだの外交交渉の末の1770年、ルイ15世の孫で王太子となった16歳のルイ=オーギュストに、オーストリアの故フランツ1世とマリア・テレジアの間の第15子(11女)である14歳のマリア・アントニアが嫁いだ訳。彼女はフランスに入るや否やフランス語読みでマリー・アントワネットと呼ばれ、のちにはドイツ語を忘れてしまう彼女にとってただ一つの名となるのでした。 忘れてしまう、という点では、10歳をすぎたころからこの娘は
これは大変な事。相手は、欧州で、すなわちある意味で世界で最も高い格式とぎっちぎちの儀礼で縛られたフランス王室です。そこに嫁ぐ未来のフランス王妃となるべき者が、作法どおりのダンスも正確なアクセントのフランス語もできないとなったら、外交的にもとんでもない事。 すったもんだの末にフランスから教師として派遣されたヴェルモン神父は、こんな報告書を送ったそうな。
そしてもうひとつ、未来の悲劇を開く重要な問題がありました。 王太子から王となったルイ16世の、身体的欠陥とそれによる精神的欠陥。スペイン大使は本国にこう報告しています。
ツヴァイクは、この男性としての役割を果たせなかったことが、ルイ16世の、狩りや鍛冶仕事への偏愛つまり肉体的優越への憧れがありつつ宮廷内から諸外国中枢にまですべてその欠陥が知られている事を知っているため、優柔不断と精神的未熟、そして劣等感を生みだした、としています。そのため、政治に対しても妻に対しても、格別思いを入れることができないまま鷹揚に受入れ、常に敬意を払いつつ何の反論もしない優しい王・優しい夫になってしまった、と。 では妻はどうだったのか。ツヴァイクはマリー・アントワネットを奔放な女とは描かず、優しい無知で無垢な少女が夫を愛そう、夫の子を宿そうと努めた様子を描写します。その結果、22歳になるまで性的な充足を得られず、奇妙な方向へその精神的活力を向けることとなってしまったと。
しかし、遅すぎた。王は精神的な虚弱さを改善できず、王妃は子を育てる楽しみは得たものの自分を律することができず、そして二人とも自分たちはヴェルサイユの主であることは知っていましたが、フランス王国の王であることは知らなかったのでした。 フランス王国を一枚の紙に描いたとき、婚礼の後のマリー・アントワネットの移動範囲は、ヴァレンヌ逃亡を除くと、小指で押した先くらいしかならなかった。彼女はヴェルサイユに住んでパリに遊びに出る以外、フランス王国を結局最後まで知らなかった。 この不幸が悲劇ですめばまだしも、惨劇になってしまったのは、ある意味、運。 ルイ15世の死とルイ16世の即位、そしてマリー・アントワネットがフランス国民に愛され、誰にも掣肘されない王妃となったのは1774年5月。この報に暗い予感に襲われて愕然としたのはただ一人だった、とツヴァイクは記します。
しかしこの哀れな末娘が「真剣に努力すること」を決心し、この母の娘として恥じない気概を見せた姿を見ないまま世を去ったことは、どうだったのか。 王妃としてのマリー・アントワネットを非難する材料として上がれ得るものはいくつかありますが、そのうちの有名な三つとして、トリアノン宮、フェルセン伯スキャンダル、そして首飾り事件があります。 前者は元は結婚の贈り物として王から送られたもので、元はルイ15世の寵姫ポンパドゥール夫人が救済のために建てたもの。それをマリー・アントワネットは、煩わしいヴェルサイユ宮から逃れる避難所として使ったのですが、それに費やした費用は、金額の価値を知らない、資産のやりくりに苦労したことがない、求めばなんでも与えられる立場だった彼女にふさわしいものとなります。繊細で優雅で華美をおさえたロココ調の、ルイ16世様式として後世に残ったこの美文化は、マリー・アントワネットの美意識によって生みだされましたが、その費用は彼女が関知するところではなかったのでした。
間を取ってざっくり 1リーヴル≒1万円 として考えると、200万リーヴル≒200億円 ということになります。 東京スカイツリーの建造費用は、ある説によると1,430億円とのこと。それでは革命は起こせませんよね。 しかしこの、自分だけが楽しめる場所を見つけ、貴族たちの生活様式とか礼儀とか格式とかに背を向けたことで、無邪気な快楽主義者であった彼女は、重大な失敗をしてしまったのでした。
フェルセン伯スキャンダルとは、スウェーデンの名門貴族で王室顧問であるフレドリク・アクセル・フォン・フェルセン侯爵の子である、ハンス・アクセル・フォン・フェルセンとマリー・アントワネットとの関係。 夫との結婚生活が成り立っていなかった頃、自分の心に巣くう気鬱症などで、女友達だけでなく彼女を取り巻く騎士たちにも目を向けるようになってしまったマリー・アントワネットの視線の先にいたのが彼。人の心を遊び半分で誘惑して楽しんでいた彼女にとって、それは恋愛感情だったのか、本当に信頼できる友人を求めてだったのか。 王妃の愛人という地位の争奪戦もあったのですが、フェルセンはまずあわてて身を引きます。あまりに危険すぎるから。 しかし王妃が王との結婚生活し成就させて子供たちを儲け、女として自覚できるようになったのち、アメリカ独立戦争の戦果ののちにフランス宮廷に現れたフェルセン伯は、ただのスウェーデンの色男ではなく、真に信頼できる人となっていたのは間違いない。 そもそもルイ16世とマリー・アントワネットの間には、時間はかかったけれど対等な敬意と信頼を育むことはできましたが、愛情はない。ルイ16世に同性愛的傾向はなかったのは間違いないのですが、人を真に信頼することはできなかったらしい。 その隙間を埋めることができたのが、彼、フェルセン伯であり、彼は王と王妃に信頼され、王妃が命を落とすまで尽くしました──正確には、尽くそうとしました。 その姿は、秘めた恋などと言う洒落た言葉で形容できません。王妃が何をしようと、その行動は常にだれかに見られていたから。悪意ある人が触れ回ればスキャンダルとなる。 首飾り事件の首謀者は、ジャンヌという女(事件発生時29歳)。ジャック・ド・サン・レミという飲んだくれの密猟者の嫡出子で、このジャックは男爵の称号を持ち本当に先祖をたどるとヴァロワ家の末裔だった、とツヴァイクは書きます。 ニコラ・ラモットという憲兵士官と結婚してジャンヌ・ド・ヴァロア・ド・ラモット伯爵夫人を名乗った彼女が、マリー・アントワネットに嫌われたロアン大司教をどのように利用したのか、カリオストロを名乗る詐欺師はどう関係したのか、お話としては面白いのですが、1785年に起きた160万リーヴルというとんでもない価値の首飾り事件にかかわる詐欺事件は、マリー・アントワネットに屈辱を与えて終わります。王妃には何の責任もなかったのですが、民衆も貴族も、王妃マリー・アントワネットが恥をかき、怨嗟の声を上げられるなら大歓迎だったのでした。 そして革命が起きる。引き金になった事件はいくつもありますが、首飾り事件と同時に起きた告発は民衆を激昂させました。それは、大蔵大臣(財務総監)を解任されたシャルル・アレクサンドル・ド・カロンヌがぶちまけたもの。 ルイ16世の12年の治世下で、フランス王室の負債は12億5千万リーヴルになっていた、と。 プチ・トリアノン宮も王妃の首飾りも、この金額に比べたら九牛の一毛にすぎないのですが、感情論ではそうはいかない。 革命の勃発となったバスチーユ襲撃、次代のフランス王となる王弟たちを含めた貴族たちの離反・逃亡、ヴェルサイユからパリのチュイルリー宮への移動。このすべてが国王夫妻に背を向ける中で、現れたのがハンス・アクセル・フォン・フェルセン。 しかし彼について、ツヴァイクのペンによると記録は少ないのだそうです。オーストリアからマリー・アントワネットに従い、「王妃が髪にさすピンの一本一本を三度も観察する」とまで言われたメルシー=アルジャントー伯爵アントワーヌでさえ、おおやけの急報にただの一度も彼の名を記したことはない。王妃に近かった人々にかぎって、フェルセンはマリー・アントワネットの恋人であったとは口にしていない。 なぜ。 ロマンチックな心情ながら几帳面な性格だった彼は、杓子定規に精密な日記をつけ、毎朝天候、気圧の記載を欠かさなかったと言います。そして大事なところは特殊な暗号で記録していたのだと。その日記はどうなったのか。 しかしこの本の真髄は、革命が起き、王の立場がだんだんと悪くなり、革命の生贄として王と王妃が槍玉に上がったとき、マリー・アントワネットという女性がどう変貌したか、どう生きたか、どう自分の未来を見つめたか、そしてどう死んだかを描く事。 下巻は、息も尽かせずその物語に読者を引き込みます。 この王妃は、精神的に鈍くなり何の感動もしない王の本音を知ることはできたのか。 王の無感動の姿は本当だったのか。 しかしツヴァイクはこのぼーっとした王はほぼ無視。あくまで苦難と侮辱の中で怒りと責任と矜持を自覚する王妃を追います。その中で、わずかにほっとする言葉。
ヴァレンヌ逃亡とその失敗について、ですが、これもまた国王夫妻の積極的な希望によるものではない上、たび重なる無意味な遅延と計画変更によって失敗した、とのこと。 佐藤賢一さんは「小説フランス革命7」中でこのヴァレンヌ逃亡事件を扱い、ルイ16世を持ち上げ、フェルセンを気ばかりあせる無能な間抜け扱いしますが、それもまた歴史小説の手法。このような献身的なフェルセンもまた面白い。 フランス革命に対する民衆の思い、知識人の思い、宮廷人たちの思い、貴族たちの思い、国外に逃げた王族たちの思い、諸外国の思い。皆、さまざま。 王弟プロヴァンス伯(のちのルイ18世)もアルトワ伯(のちのシャルル10世)も、自分たちに王位が転げ込むことを期待して、16世夫妻の国外脱出も軍隊による救援も、徹底的にサボタージュするのみ。ルイ16世は不決断ゆえ役立たず。忠実に同行知れくれる義妹のマダム・エリザベトは分別もなく外国に逃げている兄弟たちの意のまま。 マリー・アントワネットに対し無私の忠誠心を持っていたのは、ツヴァイクの筆によればただ一人、フェルセンのみ。 彼は1792年2月ひそかにパリに侵入し、国王夫妻と会談した、と記録されます。他の誰にもなしえなかったこと。 その時何があったのかは、歴史の中で定説はありません。 ルイ16世の最後の夜は、偉大なものであったと言う。ツヴァイクの皮肉な筆によれば、彼自身の無感動な性格が、死の試練に動じない道徳的偉大さを与えた、つまり鈍いから動転しなかったのだ、とのこと。それでも最後は飾れた。 王妃の、いや「カペ未亡人」の場合はどうだったのか。 最後の、革命裁判所におけるマリー・アントワネットの姿。これはツヴァイクが本当に描きたかった彼女の姿なのか。 最後の屈辱、母子相姦という言われなき言い掛かりが行われた理由、その経緯、彼女の対応が、歴史に残ります。 王が死んだのち、国王ルイ17世として立つこととなった少年の、子供らしい反発と家族へ向けた憎しみ、そして告発状への子供っぽい署名「ルイ・シャルル・カペ」。悲劇としか言いようがない。 それを証拠として母親を弾劾する裁判長の声に、マリー・アントワネットは傲然と頭をあげて答えたという。
食べ物不足、運動不足、絶え間ない出血で着物を汚しながら彼女は、一日目15時間、二日目12時間、法廷に一人で立ち、戦い続けたのでした。しかしその政治ショーのゴールは最初から決まっていたもの。 1793年10月16日、彼女は運命の最後の階段を下りきり、ギロチンで処刑されます。 罪人として果たして彼女は有罪だったのか、についてツヴァイクは、結果として罪状の一つについて有罪である、と断じました。それは、フランス国王が国民国家の首長であるという概念を持っていたら、という注釈がつきます。 それ以外の、濫費とか国政の壟断とかについては、罪とは言えない、と。 なるほどね。 ちなみに、 マリー・テレーズは母親に期待されない事を自覚し、精一杯正しく行きようと弟にきつくあたっていたらしい。 ルイ・シャルルは厳格な母、愚痴っぽい叔母、あたりのきつい姉と四人で狭い家で暮らす少年時代が辛かったらしい。 しかたないよね。 そうだ、いずれ中野京子さんの方の訳でも読んでみたい、これ。(2025/07/31) 読書メーターの記録より 上巻読了:2025/7/21 下巻読了:2025/7/25 |
 オーストリアのユダヤ系作家・評論家。1930年代から40年代にかけて大変高名で、多くの伝記文学と短編、戯曲を著した。特に伝記文学の評価が高く、『マリー・アントワネット』や『メアリー・スチュアート』『ジョゼフ・フーシェ』などの著書がある。
オーストリアのユダヤ系作家・評論家。1930年代から40年代にかけて大変高名で、多くの伝記文学と短編、戯曲を著した。特に伝記文学の評価が高く、『マリー・アントワネット』や『メアリー・スチュアート』『ジョゼフ・フーシェ』などの著書がある。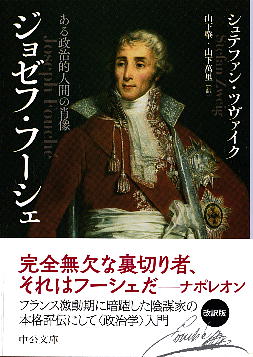 ジョゼフ・フーシェ、というと、思い当たるイメージは、「秘密警察の親玉」「監視国家の元締め」「暗黒の帝王」的なものしかなく、フランス革命からその後の歴史の中で、都合よく立場を入れ替えて上手く立ち回った機を見るに敏な変節漢としてはタレーランに比べて小物、という認識しかありませんでした。
ジョゼフ・フーシェ、というと、思い当たるイメージは、「秘密警察の親玉」「監視国家の元締め」「暗黒の帝王」的なものしかなく、フランス革命からその後の歴史の中で、都合よく立場を入れ替えて上手く立ち回った機を見るに敏な変節漢としてはタレーランに比べて小物、という認識しかありませんでした。


