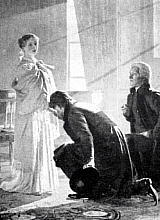トップへ戻る 読んだ本の分類 |
|
 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 書 名 | メ モ | |
|---|---|---|---|
| K072-001 | ヴィクトリア女王 | 時代を作った女王の一代記 | |
| K072-002 | ジョージ五世 | 激動の時代に生きた英国国王 | |
| K072-003 | 女王陛下のブルーリボン | 英国最高のガーター勲章とその歴史 | |
| K072-004 | 悪党たちの大英帝国 | 七人の「悪党」から見る英国史 | |
| K072-005 | 立憲君主制の現在 | 「君主制」は時代遅れなのか | |
| K072-006 | 貴族とは何か | 貴族制度の歴史からみる今 | |
| K072-007 | 女王陛下の影法師 | 女王(国王)秘書官という影法師の役割 | |
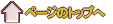 |
Ver. 2.22 |
|---|
| 管理番号:K072-001 | 51 伝記・一代記 |
出版社:中央公論新社 | |||||||
| 書名:ヴィクトリア女王 | 大英帝国の“戦う女王” | ISBN978-4-12-101916-5 C1222 | |||||||
| 中公新書 1916 | 価格:860Yen | ページ数:288P | 本のサイズ:新書 | ||||||
| 初版発行:2007/10/25 | 購入:2009/3/17 | 表紙オビ:フランツ・ヴィンターハルター画の肖像画 | |||||||
 題名のヴィクトリア女王とは、イギリスの女王(在位:1837/6/20 - 1901/1/22)にして初代インド女帝(在位:1877/1/1日
- 1901/1/22)であったヴィクトリア(Alexandrina Victoria 1819/5/24 - 1901/1/22)のことです、むろん。 題名のヴィクトリア女王とは、イギリスの女王(在位:1837/6/20 - 1901/1/22)にして初代インド女帝(在位:1877/1/1日
- 1901/1/22)であったヴィクトリア(Alexandrina Victoria 1819/5/24 - 1901/1/22)のことです、むろん。この方の生涯については、スタンリー・ワイントラウブ氏の著作で一度読んだのですが、かなり前なのでほとんど忘れています。それを含めた断片的な知識なら、歴史オタ的にぽちぽちとありました。 幼少期のちょっと可哀想な育ち。いきなり降りかかった王位継承権、王位に就いた若さ(若干18歳!)。 アルバート王子との出会い、結婚。たくさんの子供たち。孫たち。
イギリスの議会制民主主義、重商主義、植民地政策による世界帝国が頂点に達した時代。 首相・閣僚たちの責任内閣制度が充実し、「君臨すれども統治せず」の原則が固まった近代の幕開けの人。 英国史上最も長く生き、最も長く王位にあり、少なくとも近代以後では最も多く暗殺の危機にあった英国国王。 この印象は、この本を読んで、あちこち変わりましたね。 63年の長きにわたり王位にあり、そのほとんどの間で国政に何らかの形で関与していただけでなく、英国の名誉と利権を守るためにあれほどまでに手を尽くしていたのかとは、知らなかった。 英国の議会制度の成り立ちと運営、英国王が果たしうる責任と義務、国王が下す指導あるいは命令が、合法非合法にかかわらずどのような権威を持っていたのか、これは驚くべき事です。 意志の強い、気の強い人だったようです。かくあるべきという信念を持ち、自分が学んで身につけた知識と判断に重きを置き、信頼する側近には耳を傾ける。人に対する好き嫌いもはげしく、人を憎めば断固として許さないが、礼儀上必要であれば会って打ち解けた会話もする。やがてその相手の美点を見極めれば許しもする。 敵となった人にも味方となった人にも畏敬され、尊敬される。 距離を置いた人々にとっては謎の人。 女傑です。単なるお飾りのお婆さんなどではない。 こんな女戦士を帝王にいただくことができた英国は、幸運と言うべきか、不幸と言うべきか。 すべては、結果が過去を正当化するものです。それが歴史というもの。 1860年代から1900年頃にかけ、彼女の統治下で保守党と自由党の二大政党が、次々と内閣を組織しては交代しています。議会(下院)で多数を取った政党が政権に就くというルールが固まったのもこの時代。下院は内政と財政と植民地を統括し、上院は外交を統括する、という棲み分けも面白い。ただし、流動的なところはありますが。 保守党のディズレーニと自由党のグラッドストンが双璧でしょうか。どちらの人物にしても、今まで知らなかった人物像が書かれていましたね。 英国史上唯一のユダヤ系首相であるベンジャミン・ディズレーリ(1804-1881 1876年・初代ビーコンズフィールド伯)はイタリア系ユダヤ人の子であり、小説家上がり。女王にも内閣にも話を通さずにスエズ運河の株式の買収という離れ業を行うという果断なところがあり、対外的には「強いイギリス」を標榜した強硬姿勢で女王の高い評価と信頼を得ました。女王の与えようとした公爵位を謝絶し、ガーター勲章のみ受けとった人物でもあります。 ウィリアム・グラッドストン(1809-1898)は保守党員として下院議員になった人ですが、やがて自由党に移ります。選挙によって有権者の支援を得て議会で多数を取るという民意を重んじる議会政治を確立することに功績があり、対外的には「小さな英国」を標榜し、国際紛争には極力傍観姿勢をとって火中の栗を拾わない姿勢を取ることを主張します。国内的にはアイルランドへの自治権の増大などの過激な政策を採り、時にはこれが彼の命取りになったりした人。GOM(Grand Old Man)という異名を持ち、ヴィクトリア女王にとっては不倶戴天の政敵ですが、英国の国政の重鎮でした。 ほかにも、英国国内ではいろいろな政治家が現れ、ヴィクトリアの味方も敵もありました。国際的にも彼女や英国(これは必ずしも同じではない)の味方も敵もあります。国際的な敵としてはプロシアのビスマルクが最大の好敵手であったかも知れない。 この女王の長い長い統治下で、史上最高齢の皇太子となってしまったバーティことアルバート・エドワード、のちのエドワード7世が、女王に徹底的に低評価され、中年になっても国政に参加させてもらえなかったという点について、もし正統に次期国王または女王の代行者として扱っていたらどうであったかという議論がありますが、この本ではそこまでは踏み込んでいませんね。これも面白いテーマだと思うのですが。 単なる国王でしかなかったためにフオーストリア皇帝、ロシア皇帝などの下位に立たなければならなかったことが女王のプライドを偉く傷つけ、そのために公式なインド女帝の称号にこだわったのだそうな。 今まで公式な国王のサインとして、「V.R.」(Victoria Regina)とだけ書いていたのが、「V.R & I」(Victoria Regina et Imperatrix)と書いて「女王にして女帝ヴィクトリア」を名乗れることが如何に嬉しかったかという記述は、なかなか面白い。 この人があったればこそ巷間言われる大英帝国は存在し得た、といって過言ではないようです。 その功罪は別として。 こういう人物たちが、国家の頂点で丁々発止と国家の権益と名誉のために戦う時代が去り、互いの話を聞けない小物ばかりが残ったとき、ヴィクトリア時代が終わり、世界は大戦争の時代になる。 国政をゲームのように扱った人々の功罪はあるにしても、総力戦の悲劇を招いたのは彼らの不在だったのか、世界が「進化」してそのような人々の存在を許さなくなったからなのか。 ヴィクトリア女王とその時代は、歴史として面白い世界でした。この本は新しい視点と知識を与えてくれました。それだけを楽しめばいいのに、こういう余計なことを考えてしまうのは間抜けなマニアのサガなんでしょうかねぇ。困ったもんだな。(笑) 一つトリビアみっけ。 1879年、天候不順の年でした。アイルランドの不在地主(イングランドにいます)の一人アーン伯爵が、アイルランドの不作にもかかわらず、従来と同じ地代を払えと差配人(さはいにん)を通して命じます。そんなものを払ったら、みな飢え死にする。一計を案じた農民たちは、差配人自身の農園の奉公人もすべてやめさせ、村では彼らに一切物を売らず、差配人は飢え死にしかかって降参したそうな。この戦術は、その差配人の名前で有名になりました。彼の名は、退役陸軍将校チャールズ・ボイコット大尉。 これ以後このような行為はボイコットと呼ばれたのだそうな。 シャーロック・ホームズの事件簿に、「第二の汚点」という事件があります。 ヨーロッパの某国(おそらくプロシア)の君主が感情にまかせて書いてしまった手紙を英国外務省が受け取り、首相・植民地担当大臣は血相を変えて箝口令を敷きます。この手紙が紛失し、国際間に緊張が走る事件なのです。当時の時代情勢が如何に脆弱なものであったか、フィクションの世界で描いています。 この事件を、内容に鑑みワトスン博士は、年代の10の位まで曖昧にしていますが、ベアリング=グールド氏は1886年10月のことだとしています。この年、7月にグラッドストンがアフリカでの敗戦による英雄チャールズ・ゴードン将軍の見殺しなどの失政などにより辞職し、対外強硬派である保守党のソールズベリが政権を取った時でした。こんな所にも歴史が見えてきます。面白い。 日本において、特に昭和天皇は、如何にこれを学びどのように実践しようとしたのか考えるとちょっと面白い。明らかにこの歴史のうちの何かを取り入れようとした節がありますから。 むろん、歴史も国体も違うのだから同じ事はできません。近代の議会に対する帝王の立場というのは、そういう意味では全くの新興国であった日本で同じ事はできない。同じく天皇制が千年以上存在した日本では、天皇が自らの責任で決断を下して命令することは、慣習上も法制上もできなかった。 類似点より差異が多い日英の王室ですが、象徴として君臨しようとしていることでは似ています。 見習えることは少ないのですが、学べることが皆無ではありません。こういう事もまた、面白い。(09/4/24) |
|||||||||||||||
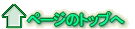 |
Ver. 2.23 |
|---|
| 管理番号:K072-002 | 51 伝記・一代記 | 出版社:日本経済新聞出版社 | |||||||
| 書名:ジョージ五世 | 大衆民主政治時代の君主 | ISBN978-4-532-26127-6 C1222 | |||||||
| 日経プレミアシリーズ127 | 価格:890Yen | ページ数:240P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2011/6/15 | 購入:2012/3/31 | 表紙写真: Granger/PPS通信社 | |||||||
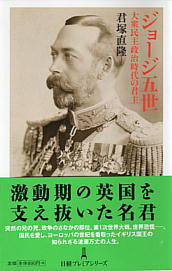 英国王ジョージ五世とは、英国近代史に名高い二人の女王、ヴィクトリアとエリザベス(二世)の間に君臨した四人の国王の一人です。 英国王ジョージ五世とは、英国近代史に名高い二人の女王、ヴィクトリアとエリザベス(二世)の間に君臨した四人の国王の一人です。その前後の英国国王とは、こんなかんじ。
ジョージ五世の統治期間は25年7ヶ月。そんなに短くはありませんが、前後の女王二人が長いので、短く見えますね。 20世紀の初頭に皇太子となり、日露戦争の直後に王位に就き、ヒトラーがドイツの首相に就任した事(1935年)を見届けて死んだわけですから、彼の生涯は苦闘の連続といってもよかったのかも。 この人の生涯を追ったのがこの本。基本、好意的です。「ヴィクトリア女王」のときも思いましたが、そういう暖かい肯定的な視点もいいんじゃないか? 1865年、バッキンガム宮殿にほど近い英国皇太子私邸マールブラ・ハウスで生まれた皇太子アルバート・エドワードの次男は、同年7月7日にウィンザーのセント・ジョージ・チャペルで行われた洗礼式で、ジョージ・フレデリック・アーネスト・アルバートと名付けられました。王室内でこの少年は、「ジョージー」と呼ばれます。 兄である長男は、アルバート・ヴィクター・クリスチャン・エドワード。同じく王室内では「エディ」と呼ばれていました。この兄が、27歳の若さで病死します。死因はインフルエンザと肺炎の併発による、と発表されます。 これにより26歳の「ジョージー」は皇太子の長男として、英国王位継承者第二位になりました。 長男エディについては、いろいろな評判、主として悪評があります。「男娼宿通い疑惑」、「知能がまともではない、白痴疑惑」、はては「切り裂きジャック事件犯人疑惑」まで。これらの悪評について、君塚さんは言及はしますがコメントはしません。風評はあるけど取り合わないよ、というスタンスは好感が持てます。 「ジョージー」の生涯は、祖父でありヴィクトリア女王の夫君であったアルバート公の死(1861年)から始まった王室存続の危機、共和制運動の激化などの洗礼で始まり、その後も常にさまざまなドラマチックな動乱の中でした。一つ間違えれば王室の危機、英国の壊滅、欧州政治の崩壊につながりかねない事件が目白押し。如何に危ない橋を渡ったのか、如何に難しい判断を行ったのか、振り返るとそら恐ろしくすらなります。 しかしその中で、彼はときには間接的に、ときには積極的に政治の世界に介入しました。ここが、日本とは違うところ。
たとえその間に、スキャンダラスな行為で英国を破滅させかねなかった無能な王が短期間挟まれたとしても、ジョージ五世はたしかに英国を支え、次の時代にそれを引き継いだ王の一人であった、と。 なんか、いいな。こんな暖かい視点の伝記って。 ミリオタ的には、この人とその息子たちの名は、第二次大戦の艨艟たちの艦名として記憶されます。 キング・ジョージ五世級戦艦の最初の三隻。 一番艦「キング・ジョージ五世」、略称KGV。二番館「プリンス・オブ・ウェールズ」、略称POW。三番艦「デューク・オブ・ヨーク」、略称DOY。 英国の旧弊な設計思想が災いして、防御力は優れていたものの兵装でも機関でもぱっとしなかったことは確かですが、DOYは北海で独戦艦「シャルンホルスト」を撃破する功績をあげています。 しかしPOWは、モデルとなった王の呪いか(笑)あまりよい戦歴はなく、むしろ史上初めて航空機の攻撃によって撃沈させられた戦艦として有名です。撃沈したのは、むろん日本の海軍航空隊。 何か皮肉を感じたのは、鐵太郎だけではないはず。(にやり)(2012/06/14) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
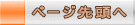 |
Ver. 3.01 |
|---|
| 管理番号:K072-003 | 56 宗教史・文化史 | 出版社:中央公論新社 | |||||||
| 書名:女王陛下のブルーリボン | 英国勲章外交史 | ISBN978-4-12-205892-7 C1131 | |||||||
| 中公文庫 き39-1 | 価格:914Yen | ページ数:344P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2014/1/25 | 購入:2014/1/26 | カバー写真:ガーター・セレモニーのエリザベス2世女王(PPS通信社提供) カバーデザイン:中央公論新社デザイン室 |
|||||||
| ブルーリボンとは、英国のガーター勲章のこと。英国にある九つの勲章の中で最高の権威を持つものです。その大綬(たいじゅ)、つまり勲章を肩からかける帯の色から、そう呼ばれています。 この本は、このかつてイングランドで生まれたブルーリボンの歴史を、その成り立ちや政治的な意味、そして日本との関わりまで絡めて丁寧にわかりやすく説明したものです。 はじめに、と題されて1998年5月にロンドン、バッキンガム宮殿で行われた晩餐会のことから始まります。この日、女王エリザベス二世は、イブニング・ドレスの上に日本の最高の勲章である大勲位菊花大綬章の大綬(サッシュ)を右肩から左腰にかけ、その横に座る当日の主賓、日本国第125代天皇明仁(あきひと)が燕尾服の上着の下に、左肩から右腰へ鮮やかなブルーの大綬を身につけていたのでした。 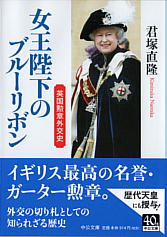
それはともかく。 ガーター勲章、正式には The Most Noble Order of the Garter KG とは、フランスとの百年戦争のころにできたそうです。1340年代らしい。時のイングランド国王はエドワード三世(在位1327-1377)。1344年に王がウィンザー宮殿で「アーサー王と円卓の騎士」の故事にちなんで円卓の饗宴を催した年なのか、1348年に王が「黒太子(Black-Prince)」の異名を持ったエドワード王太子と24人のガーター勲爵士をウィンザーに召集したときなのか、見解は分かれているようです。 この24という数字は、アーサー王が12人の騎士を選んだことに由来し、王と王太子がそれぞれ12人ずつ、合計24名と言う事なのだそうな。現在でも王族や海外の王族を除くと英国国内では勲爵士の数は24人以下とされているそうです。 この勲章がなぜガーターの名が付いたかというと、国王主催の舞踏会でとある貴婦人が王自身と踊っている時に靴下止め(ガーター)を落としてしまったことが発端といわれます。まさにその時、のちに騎士道精神の権化と讃えられたエドワード三世は、羞恥に身の置き所もないくだんの貴婦人のガーターを拾い、平然と自分の膝に留め、「悪意を抱く者に災いあれ(Honi Soit Qui Mal Y Pense)」と呟いたそうな。これが伝説となり、ガーター勲章の元となった、と。 真偽のほどはわかりませんが。 この勲章は、元々は地方領主に過ぎなかったイングランド王が自らの権威を高めるために作り出したこの勲章が、イングランドがその勢力を伸ばして伸張し、連合王国となって世界の四分の一を支配する超大国にのし上がる過程でこの勲章がどのように使われ、どのように政治的・外交的な道具として利用されたかを描いています。 なるほど、面白い。 そして、異教徒でしかも一度は対等な、不倶戴天の敵となったこともある東洋の一国家、日本が、どのような経緯で明治帝から始まり代々の天皇にこの勲章を授与させることができたのか。 キリスト教徒ではない国家の君主にこの勲章を贈ることはなぜ難しかったのか、という原因の一つに、この勲章は国王、女王の積極的な意志あるいは同意がなければできなかったというルールがあります。さらに欧州の近世・近代史の中で起きたように、国王がミーハーなら、内閣あるいは摂政が歯止めをかけます。彼らは基本的に保守勢力ですので、原則は守る方にいくもの。 にもかかわらず、エドワード七世時代(在位:1901-1910)に海外の異教徒の君主に贈ったガーター勲章は、ペルシャ皇帝(1902)とムツヒト、すなわち明治天皇(1905)のみ。 ジョージ五世時代(在位:1910-1936)は、ヨシヒト、すなわち大正天皇(1912)とヒロヒト、すなわち昭和天皇(1929)のみ。 ジョージ六世時代(在位:1936-1952)は、異教徒君主への贈与なし。 エリザベス二世時代(在位:1952- )は、アキヒト、すなわち今上天皇(1998)だけ。エチオピア皇帝ハイレ=セラシュ一世にも贈られています(1954)が、これは実はキリスト教徒。 保守的な英国王室の流れがくっきり見える中、日本の天皇だけがなぜ例外となり得たのか。 ああ、こんな歴史があったのか。なるほどねぇ。 巻末の「外国君主のガーター勲章受章者一覧」と「近現代イギリス歴代君主が授与された外国からの勲章一覧」などの資料も含めて、歴史の一ページを、楽しめる本でした。(2014/6/14) |
||||||||||
 |
Ver. 3.06 |
|---|
| 管理番号:K072-004 | 54 歴史点描 | 出版社:新潮社 | |||||||
| 書名:悪党たちの大英帝国 | ISBN978-4-10-603858-7 C0322 | ||||||||
| 新潮選書 | 価格:1400Yen | ページ数:320P | 本のサイズ:135×190SC | ||||||
| 初版発行:2020/8/25 | 購入:2020/12/19 | ||||||||
 「悪党」といっても、成功した犯罪者とか格好良い悪役と言う意味の悪党ではありません。英国の歴史を作り上げた政治指導者たちの中で、一部であまり評判のよろしくない七人──ヘンリー八世、クロムウェル、ウィリアム三世、ジョージ三世、パーマストン子爵、ロイド=ジョージ、ウィンストン・チャーチル──を「悪党」と呼び、彼らが悪党として指弾されながら何を為したのかを描き出したもの。なるほどそういう見方もあるのか、と目からウロコが落ちる思い。 「悪党」といっても、成功した犯罪者とか格好良い悪役と言う意味の悪党ではありません。英国の歴史を作り上げた政治指導者たちの中で、一部であまり評判のよろしくない七人──ヘンリー八世、クロムウェル、ウィリアム三世、ジョージ三世、パーマストン子爵、ロイド=ジョージ、ウィンストン・チャーチル──を「悪党」と呼び、彼らが悪党として指弾されながら何を為したのかを描き出したもの。なるほどそういう見方もあるのか、と目からウロコが落ちる思い。それにしても、君塚さんの筆致は読みやすく、またわかりやすくていいなぁ。 第一章 ヘンリ八世 ──「暴君」の真実  トップバッターはヘンリ八世。離婚を禁じたカトリックの教えの中で、六回結婚し二回離婚し二人の王妃を処刑した人。艶福家というか好色漢だったそうで、私生児を宿した愛妾数知れずなのだそうな。その上公の場で最も多くの処刑を行った残虐性や、戦費や衣装代の支出がものすごい浪費家であったことも「暴君」「悪党」と言われた所以か。 トップバッターはヘンリ八世。離婚を禁じたカトリックの教えの中で、六回結婚し二回離婚し二人の王妃を処刑した人。艶福家というか好色漢だったそうで、私生児を宿した愛妾数知れずなのだそうな。その上公の場で最も多くの処刑を行った残虐性や、戦費や衣装代の支出がものすごい浪費家であったことも「暴君」「悪党」と言われた所以か。しかし歴史的見にると、この人が王になった時代は、ヨーロッパ国際政治の中で弱小国であったイングランドが、薔薇戦争という激烈な内戦をようやく納めたチューダー王朝の始まりのとき。始祖となったヘンリ七世はその王権がやや不安定だったものの、二代目の八世はこの混乱した国家の絶対権力を持った独裁者でした。 しかし旧約聖書のダビデ王を理想としたこの王が目指したのは、教会と国家を統治下におく真の王たること。幾多の困難を強引にねじ伏せたヘンリの豪腕が作り上げた国家イングランドは、短命に終わった二人の王を経て、エリザベス一世の治世で盤石となります。  第二章 クロムウェル ──清教徒の「独裁者」 第二章 クロムウェル ──清教徒の「独裁者」エリザベス一世の死後、遠縁にあたるスコットランド王ジェームズ六世がステュアート朝イングランド王ジェームズ一世として王位に就きます。この王は前女王の輔弼機関として確立された議会を尊重する姿勢を見せますが、そもそもが「王権神授説」の提唱者。だんだんと議会との軋轢が生まれました。二代目のチャールズ一世の時代になると、父に負けじと戦争政策や宗教政策でさらに議会と対立します。ついに起きた国王派と議会派によるイングランドの内戦で、クロムウェルは頭角を現し、ついに議会派のリーダーとして勝利したのち、国王を処刑することに。 この「王殺し」がクロムウェルの毀誉褒貶に大きく関わったのでした。 護国卿(Lord Protector)として600万人の人口をもつ「グレート・ブリテンおよびアイルランド」の支配者となったクロムウェルは、「王」でなかったがゆえに過去のしがらみを断ち切った政治を行い、イングランド王国をグレート・ブリテンに育て上げました。王政復古後に指導者となったクラレンドン伯爵はこう評したとか。
 第三章 ウィリアム三世 ──不人気な「外国人王」 第三章 ウィリアム三世 ──不人気な「外国人王」ネーデルランド(オランダ)総督ウィレム二世とイングランド王チャールズ一世の王女メアリの間に生まれたウィレム三世は、生まれた時にすでにオランイェ公・ナッサウ伯である父が病死しており、建前上そもそもが世襲ではない総督の地位も奪われて不遇な年少時代を過ごします。このへんの歴史背景はデュマの「黒いチューリップ」に出てきますね。元首の地位に上がれる道は断たれていたはずですが、カルヴァン派の聖職者から王侯にふさわしい教育を受けていたそうな。 イングランドの王政復古後、ヨーハン・デ・ウィットの死後に権力をつかんだウィレムはネーデルランドの総督兼陸軍司令官となり、イングランド国王チャールズ二世の弟ジェームズの長女メアリと政略結婚します。その血統が、イングランドの名誉革命によってカトリック教徒である国王ジェームズ二世が追放されたのちの王座にウィレムを迎えることに。 厳密に言うとウィレムは妻メアリと共にウィリアム三世として共同統治のイングランド王・スコットランド王・アイルランド王となったのですが、オランダ総督としての地位はそのまま。であるから、人気があれば全ての国から期待される為政者であったはず。 事実彼の王としての施政は、議会を尊重し、宗教的には寛容な姿勢をとり、交易を充実させて世界に冠たる商業国家の基礎をつくり、海軍力を蓄えて敵対するフランスとの関係を好転させた立派なもの。にも関わらず、なぜ嫌われたのか。  第四章 ジョージ三世 ──アメリカを失った「愛国王」 第四章 ジョージ三世 ──アメリカを失った「愛国王」ステュアート朝の断絶ののち、イングランド王位は遠縁であるドイツ北部のハノーファー選帝侯に継承されます。カトリック君主の即位を禁止する法と兼ね合いもあるのですが、このへんの「血統主義」は日本の常識では理解しにくいものがあります。でもそれはお互い様。その結果、英語が一言も話せないハノーファー選帝侯ゲオルクが、イングランド=スコットランド連合王国の国王、ハノーバー朝ジョージ一世として即位します。とはいえイギリスの政治に全然興味を持たないジョージ一世と二世の存在は、英国議会とそれに立脚する議院内閣制が確立する原因となります。 そのあとを受けて22歳で即位したジョージは、当時議会の多数派を占めていたホイッグ政権と衝突しますが、さまざまな施策を提示したもの。 しかしアメリカ独立戦争の敗戦、頑迷な性格のため敵の増加、子息たち(九男六女)の教育の失敗、自身の精神錯乱(のちに「ポルフィリン症」と名づけられた遺伝性疾患)などにより、運命の歯車が狂っていきます。  第五章 パーマストン子爵 ──「砲艦外交」のポピュリスト 第五章 パーマストン子爵 ──「砲艦外交」のポピュリスト11世紀まで遡る由緒正しい貴族でしたが、経済的にあまり恵まれない中小貴族でした。しかしアイルランド貴族であったために貴族院ではなく勢力を伸ばしつつあった庶民院に議席を得ることができます。 トーリー党に席を置いていましたが基本的に一匹狼を貫き、英国の無派閥リーダーの先駆けと言われました。外交官、首相として政界をリードします。欧州に平和をもたらした会議外交の提唱者であり、ナポレオン戦争後の欧州の政治の安定に力を注ぎます。しかしその自由主義的政策と共に、砲艦外交、英国の権益および利益を追求し、阿片戦争などで非難を浴びます。 彼の施策によって形成された帝国主義はアジア、アフリカのヨーロッパ人の支配という結果を招き、「悪党」と言われてもしかたがないところ、 しかし選挙権の拡大を予見し、中産階級や労働者階級の好意を得る政治を行うのちの「大衆民主主義」の萌芽を作った功績は揺るがない。  第六章 デイヴィッド・ロイド=ジョージ ──「王権と議会」の敵役 第六章 デイヴィッド・ロイド=ジョージ ──「王権と議会」の敵役マンチェスターの弁護士資格を持つ教員ウィリアム・ジョージの息子として生まれ、生まれてすぐ父を肺炎で失います。母の実家である靴屋のロイド家で育ち、姓をロイド=ジョージとして勉学の末に「弱者のための」弁護士となります。 27歳で庶民院の議員となりますが議員が皆地主階層以上である事に愕然。しかし萎縮することもなく、ウェールズの非国教徒として地歩を固め、庶民の代表として名を上げます。 のちに経済学者ケインズに
第一次世界大戦を勝ち抜いた内閣を率いた庶民出身の宰相は、なにを行った人だったのか。 ロイド=ジョージの弟分であったチャーチルは、彼の死後追悼演説を残します。
 第七章 ウィンストン・チャーチル ──最後の「帝国主義者」 第七章 ウィンストン・チャーチル ──最後の「帝国主義者」いわずと知れた英国で(おそらく)最も知られた男。ランドルフ・チャーチル卿の三男として生まれた貴族のボンボン。陸軍士官学校卒ながら軍人に見切りを付けてジャーナリストを目指した気まぐれ男。25歳の若さで庶民院に当選し、6人の君主に仕えることとなった議員。保護貿易に傾きつつある保守党から自由党に鞍替えした反骨漢。若き海相に任じられて海軍作戦で大失敗し、閣僚を辞任して前線に向かったはねっ返り。1929年より10年間不遇の時を過ごし、公私ともにどん底の時期を過ごした孤高の人。ヒトラーの台頭とチェンバレンの失政により海相に復帰した国民の人気者。 国王ジョージ六世の不審、親独派の政治家たちの反対を押し切って英国首相の座に上り、不退転の意思で第二次大戦を戦い抜いた不屈の男。そして、世界の改変の中で、大英帝国が世界の超大国の座から滑り降りていく事を知りつつ、最後まで超大国の元首として世界を導こうとした男。 若い時は「生き急ぐ若者 Young man in a hurry」と呼ばれ、老いてなおスターリン、トルーマンと対抗しようとした「生き急ぐ老人 Old man in a hurry」。 この大英帝国最後の帝国宰相は、どれほどの悪党だったのか。 こんな視点で見る英国史、素敵です。(2021/01/02) 読書メーターの記録より 読了:2020/12/27 |
||||||||||||
 |
Ver. 3.06 |
|---|
| 管理番号:K072-005 | 54 歴史点描 | 出版社:新潮社 | |||||||
| 書名:立憲君主制の現在 | 日本人は「象徴天皇」を維持できるか | ISBN978-4-10-603823-5 C0322 | |||||||
| 新潮選書 | 価格:1400Yen | ページ数:304P | 本のサイズ:135×190SC | ||||||
| 初版発行:2018/2/25 | 購入:2021/2/9 | ||||||||

しかし第一次大戦が終わっても、彼が望んだように民主的な共和制が世界連合を生みだして永久平和が訪れる世界には成りませんでした。ウェルズが憎んだ帝国主義にルーツを持つ君主制が滅びることはなく、この本の執筆時期である2017年現在、国際連合に加盟している193の国家のうち、君主制を採用しているのは日本を含め28ヶ国で、さらにイギリス女王が国家元首を兼ねる「英連邦王国」15ヶ国を加えると43ヶ国にもなります。これを国連加盟国の五分の一に過ぎないと考えるべきか、五分の一もあると考えるべきなのか。 ウェルズが百年前に説いたように、共和国が世界の大半を占めて世界連合も作られた時代になっているのですが、あに図らんやウェルズがかくあるべしと予期した平和な世界にはなっていません。それどころか、君主国が必ずしも強圧的な独裁的統制国家であるのではなく、共和国が国民が自由にその意思を反映できる民主的な国家ばかりではない、という現代の姿を見たら、ウェルズはどんな顔をすることでしょうか。 ではなぜ、ルイ14世に代表される国王が支配する絶対国家、あるいはプロシアの末裔ドイツ帝国のような軍国主義帝国が、国民が喜んで国王という世襲の元首を国の中心に置く現代の君主国家が登場し得たのか。これを君塚さんはヨーロッパの諸王国の歴史の流れによって説明します。 むろん王国とは、ヨーロッパだけでなく中東、アフリカ、アジアに点在しますし、そこには必ずしも民主制と言い切れないところはあります。それも歴史です。 第二次大戦後の日本の占領時、GHQは今後の日本のあるべき姿を考えた時、第一次大戦直後に確立した理論「民主主義と君主制は両立しない」という考え方によって天皇制を廃する事を検討したそうです。 しかし、第一次大戦後帝国製を廃したドイツがワイマール共和国を経てナチス・ドイツ政権に至った経緯と、戦火を浴びながら戦後に政治的に安定していた北欧の君主国を考えた時、国家の形として君主制イコール独裁制ではない、共和制イコール民主国家ではない事に気づいた結果、「民主的天皇制の日本」という結論に至ったのだそうな。 歴史とは試行錯誤の連続で、その成功例の一つが戦後日本の天皇制であったらしい。 こういった様々な君主制とは何か、立憲君主制とはどんなものかについて論じたあと、世界各国の君主制の話になりますが、まずイギリスの歴史から本論は始まります。 民主的という言葉はあてはめるのが難しいのですが、英国で中世的な王だけの独裁政治から議会と調整しつつ政治を行う体制に移行し始めたのは、英国、当時のイングランドがブリテン島と大陸、フランスの一部に領土を持った時代、つまりアンジュー帝国を作り上げたヘンリー二世(1133-1189 在位:1154-1189)以後の時代ではなくその前、デーン人の王カヌート(990?-1035 イングランド王在位:1016-1035)に遡るのだそうな。カヌートはイングランドだけでなくデンマーク、ノルウェー、スウェーデンにまたがる北欧の王国も統治下にあったので、イングランドを四つの伯爵領に分けて代理統治させていたのだそうな。 のちのアンジュー帝国も含めて海外の地にまたがった別な国家も統治下にある王を抱いていたために、代理統治機構が発達し、王もこの機構を使いこなすためにある程度尊重せざるを得ず、その結果この機構がのちに議会に変遷していく過程で立憲君主国家として確立していったのです。この長い長い歴史を手早くしかしゆったりと描いたのが、第Ⅰ部。その中で描写されるのが、のちに昭和天皇となった 第Ⅱ部で、現代のイギリス王室、北欧の王室、ベネルクスの王室がまず描かれます。これらは、ある意味成功例と言っていい。そのあとで描かれるのが、アジアの君主制。ネパール王国の悲劇、タイの君主制の未来、ブルネイ君主制のゆくえ。 湾岸産油国の「王朝君主制」の成り立ちと今後。 それぞれの君主の行うべき仕事、義務、権利、権力、権威。 終章で語られるのは、むろん日本の象徴天皇制。 天皇の激務とそれを語る事がなかった平成の天皇陛下(今の上皇陛下)の思い。女性皇族のゆくえ。 日本がアジアの君主制ではなく欧州の、特に英国式の君主制をある程度志向するのなら、「女帝」のどこがいけないのか。 そう、日本は東洋式の君主制から脱皮しようとした事があったのだから、すんなりと男女に関わりない「絶対的長子相続制」を洗濯する事だってできるはず。 かつてタイの近代化の父でもあるチュラロンコーン大王が
そんなこんな、いろいろな事を君塚さんは論じています。面白いね、これ。(2021/01/22) 読書メーターの記録より 読了:2021/1/18 |
|||||||||||
 |
 |
|---|
| 管理番号:K072-006 | 56 宗教史・文化史 | 出版社:新潮社 | |||||||
| 書名:貴族とは何か | ノブレス・オブリージュの光と影 | ISBN978-4-10-603894-5 C0320 | |||||||
| 新潮新書 | 価格:1600Yen | ページ数:296P | 本のサイズ:130×190SC | ||||||
| 初版発行:2023/1/25 2刷:2023/2/20 | 購入:2023/12/30 | ||||||||
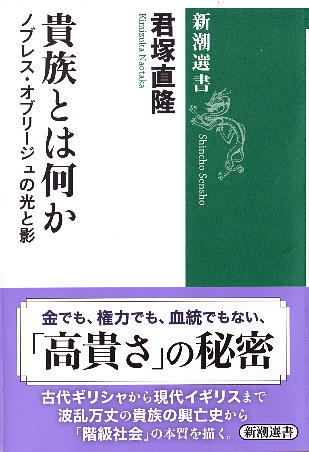 はじめに と題された序文は、こんな文章で始まります。 はじめに と題された序文は、こんな文章で始まります。
これは、1789年に起きたフランス革命で王政も貴族政も廃止された後、皇帝となったナポレオンによりフランスに新たな貴族政が定められ、「成り上がり者」が爵位を得たことで、いろいろ問題が生じたのです。そこで由緒ある貴族としてひと言あるべきと考えたド・レヴィ公爵が、訓戒を垂れようと書いたものがこれ。 貴族という存在が生まれた古代、「最善の人々による統治(優秀者支配)」という思想が生まれます。 かつてギリシアの大哲学者プラトンが理想の政体として思い描いたのが「徳」を備えた人々による「貴族政治」という概念。古代ギリシア語でいう「貴族 aristos(άριστους)」とは、「すぐれた」「優秀な」を意味する言葉であり、すぐれた者が民を導く政体こそが貴族政であった、という。 すなわち最初から、人は平等であるという概念よりも、人には優れた者と劣った者がいるという考え方に立っています。 この年にまでいろいろ世の中を見ているうちに鐵太郎はこう思うようになりました。ぶっちゃけ、そのとおりではないか。 自分が偉いと自惚れるものは不快ですが、その中に本当に優れたもの、人の上に立つ器量の者がいるではないか。 そうでない馬鹿も多いのですが。 その、真に人より優れた者を持ち、しかも社会を導く責任を自分に課したもの、それが最初のいわゆる貴族なのか。 「徳」のある人物もしくは人々こそが人々の上に立つべき、と言う発想が、プラトンによる「哲人王」の統治という概念に結びつきます。そしてもし、人の上に立つ「徳」を持っていると評価された人々が、それを意識して克己心を発揮して自分を高め、よりよい人間になろうとしたならば、結果として理想の国家となりうる、と解釈できるのでしょうか。 それが西はギリシャからローマ文化の原点となり、同時にその発想が東の中国でも、倫理観念の原則によって私利私欲を抑えて公儀に向かう「士大夫」という「貴族」が存在していたのだ、と。 これが形こそ変え、東でも西でも、こういう貴族とは個人の能力や義務感ではなく家柄・血統の違いが貴賤の原点とみなし、特権的に地位や財産や領主権が継承されるものとなっていきます。 東西における貴族の「爵位」についての説明が、興味深いものです。 元老院議員の身分から皇帝が選ばれるのが通常であったローマ帝国において、軍人皇帝時代以後、ディオクレティアヌス帝(在位284~305)を含め下層階級から皇帝となるものが増えます。このあと、元老院議員が主に務めていた軍団司令官職「legatus legionis」が皇帝直属の部下が占めるようになり、「dux」と称されてのちにこれが「公」、公爵位になります。 しかし次代のコンスタンティヌス1世(在位306~337)の時代、さらに自分の側近を重職に就けたことで彼らが「comes」と呼ばれるようになり、これが英語でいう「companion」となります。彼らが皇帝の諮問機関である枢密院を構成したり属州総督も皇帝側近が務めるようになると、彼らが「伯 Comes」となっていきます。これが日本語で「伯」と訳されます。 これらの役職が爵位となり、古代から中世へと繋がっていきます。 東の古代中国においては、殷(BC17C~BC1043)から周王朝(BC1046~BC256)に時代が移る中で「周侯」であった周が王朝を築き、宰相クラスに「公」の爵号を与え、記録上は「侯」ですが諸侯に「侯・ これが「公・侯・伯・子・男」の五爵にまとめられたのが、西周のあとの春秋時代(BC770~BC403)。ここで孔子(BC552~BC479)が為政者の「徳」の大切さを述べています。
そしてその方が一般的になりやすい。これは洋の東西問わずある意味当然の帰結です。 そこで、為政者は意識してかせずしてか、統治のために「徳」による貴族をシステム化し、「法治」のための官僚制、階級制として定着させることとなります。それが、貴族政。 しかし中国では、最終的にこのシステムを破壊します。「科挙」という人材登用制度によって。 隋王朝(581~618)において、天子独裁を実現するため、全国土から皇帝が望む考え方・思想・事務処理能力を持つ人材を直接集めるシステムを作り、貴族階層を不要としたのです。 この君主独裁制の確立に従って、中国の貴族階層は消滅します。しかし西方では違った。 こののちの、どのように西方ではローマ帝国崩壊ののちに貴族制度は王朝の藩屏として育ったのか、存在し得たのかが解説されます。それは、貴族というと短絡的に考える、「階級制度の上位にあって既得権益を守ることしか頭にない暴力集団」的なものもたしかにあるのですが、それだけではない。 中国の五等爵制度の名称を、たまたま欧州の爵位も五つだったので翻訳の時借用したのですが、これについてちょっと詳しい説明があります。 公爵とは、ローマ帝国の軍団司令官「dux」から強大な領主の名称となり、中世にはドイツのバイエルン、シュヴァーベン、ロートリンゲンなどの有力諸侯は「公もしくは大公(dux)」と呼ばれ、イタリア語で duca、フランス語で duc、スペイン語で duque、英語で duke となります。ドイツでは同じ軍団司令官の意味の Herzog が使われます。 侯爵とは、「dux」に匹敵する称号として存在する「princeps プリンケプス」に由来します。これは元老院で最初に発言できる者」という意味ですが、ドイツ語の「第一人者」つまり Fürst がドイツの第二番目の爵位となります。これが他の地方では、「伯 comes」より格式が高い「辺境伯 marchio」が第二位の爵位の意味となり、イタリア語で marchese、フランス語で marquis、スペイン語で marqués、英語で marquess となります。 伯爵とは、皇帝側近の companion が属州総督となり、領主としてそのまま継続して「伯 comes」になります。フランク王国になってもこれが継承され、カール大帝の時代には王国に500もの伯領が生まれたそうな。イタリア語で conte、フランス語で comte、スペイン語で conde となり、ドイツでは別な事情で Graf という名称で呼ばれます。インググランドではスカンジナビアで総督を意味する jarl が古英語になまって earl となりました。 子爵とは、大きな勢力となった伯の下で比較的小さな領域を統治する「副伯 vicarius」と呼ばれる下役人でした。それがイタリア語で visonte、フランス語で vicomte、スペイン語で vizconde、ドイツ語で Vicomte、英語で viscount となります。英語の viscount の発音ですが、「ヴァイカウント」です。昔そんな名称のタバコがありましたっけ。 男爵とは、ラテン語の「一人前の男 baro」から来ます。重労働あるいは傭兵の意味から来ているそうな。これがイタリア語で barone、フランス語で baron、スペイン語で barón、英語で baron、ドイツ語では「自由身分の男」を意味する Freiherr になります。 「男爵」が東西でなぜか同じ意味の「男」であるのは偶然だろうか、と著者の一言。さあね? 第二章は、中世以後のヨーロッパ貴族の盛衰、フランス革命以後の凋落、そして現代。 それから第三章で、現代でもなお貴族制度と貴族院を保持しているイギリスの姿。 最後の第四章は、日本。平安貴族のような古代の貴族制度が、中世、近世まで存続し、明治の近代を迎えていきなり西欧の貴族制度導入により混乱する姿。そして貴族院。 貴族院とはどういうものか、どうあるべきか、どうなったのかについて、いろいろな考察があります。 英国の貴族院、すなわち一定の家名を持った貴族の一家から一人終身の議員が出て貴族院の一角を占めることが、英国の政治をどのように導いたのか、という考察は面白い。 単純に考える驕り高ぶった貴族さまがふんぞり返っている姿がないとはいえない。しかし彼らは、ある意味大所高所に立って国政を見守り国王を助ける存在であった、という解説は、「徳」の政治という最初の考え方に繋がるものがあります。 むろん世の中理想だけで進むものではありませんけれど。 そして日本の参議院のことに著者の筆が移ります。 戦後、貴族院が廃止されて一院論も出た中で参議院として存続した制度です。それなりに意味もあり、理想もあったはず。衆議院より長い任期で、ある程度大所高所で国政を見守る立場であることが期待されたのに、なぜ衆議院のカーボンコピーといわれる、存在感の薄い存在になってしまったのか。 ではどうすべきなのか。何も選挙だけが民主主義のやり方ではないと考えてもいいではないか、という言葉。 この問題提起は、目を引かれます。 そうなんだな、歴史をみないと人は道を誤るんだな。そしてそれに見あうだけの成熟した人々になりたいもの。 貴族の歴史だけかと思ったら、思いもよらず深い所まで掬い上げてくれた本でした。(2025/2/23) 読書メーターの記録より 読了:2024/12/26 |
|||||||||||
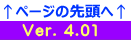 |
|---|
| 管理番号:K072-007 | 54 歴史点描 | 出版社:筑摩書房 | |||||||
| 書名:女王陛下の影法師 | 秘書官から見た英国政治史 | ISBN978-4-480-51164-5 C0122 | |||||||
| 2007年7月 筑摩書房より刊行 | |||||||||
| ちくま学芸文庫 キ34-1 | 価格:1300Yen | ページ数:400P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2023/2/10 | 購入:2024/1/24 | カバー装画:Lithograph of Queen Victoria's Imperial State Crown カバーデザイン:細野綾子 |
|||||||
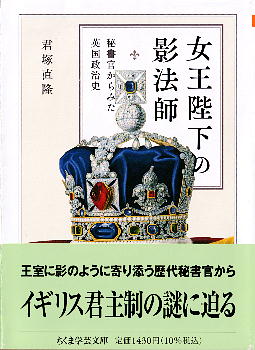 はじめに の最初に書かれた話は、2004年5月10日の徳仁親王の発言。雅子妃殿下の「人格を否定するような」動きが宮内庁に見られた、というもの。 皇太子(当時。むろんこの方2024年現在今上陛下です)の真意は別として、そもそもこのような発言をせざるを得なかった訳として、「側近の欠如」という問題があるのではないか、と君塚さんは指摘します。 かつて昭和天皇には、入江相政氏という半世紀にわたって補佐し続け、絶大な信頼を寄せられた人がいたそうです。しかしいまは、各省庁からの順送り人事で宮内庁や東宮の職員が数年ごとに移動するため、そのような人物がいない。皇太子の発言もそのせいではないか、と。 むろん日本には日本の事情があり、過去の経緯もあります。一概にこの制度は駄目だと否定することはできません。しかし皇室史を知るものにとって、歯がゆさを感じざるを得ないことなのはたしかです。 では、それに対して英国では。 2005年4月にチャールズ皇太子(現・英国国王チャールズ3世)がカミラ・パーカー・ボウルズとの結婚を女王である母・エリザベス2世(2022年死去)に願い出ます。これは1772年に制定された王族婚姻法に基づくもので、王族の結婚は君主の承認が必要だから。この法律は、2013年に制定された王位継承法によって廃止されますが、王位継承順位の最上位6人は今も君主の承認が必要とのこと。 この時点で女王が、ダイアナ元妃(1996年離婚・1997年死去)の記憶が国民に生きていたこと、相手が離婚歴のある女性である事などで必ずしも喜んでいたわけではなかったのですが、この母子というか女王と皇太子の話し合いは、皇太子秘書官サー・マイケル・ピートのお膳立てにより円滑に行われました。 秘書官というクッションがあればこそ、皆のメンツが保たれ、スムーズに業務が進行したのです。この本の執筆時点の2007年時点で、英国王室には主要な各王族すべてに秘書官が配されていたそうです。現在も継続しているはずですが、英国にはこのようにして王族が公務に関わる際には秘書官が補佐する習慣が根づいています。 特に女王(あるいは王)秘書官の役割は重要です。彼らは女王と英国政府の仲介役として、国内外のさまざまな問題・情報を女王に報告すると共に助言もします。また女王が国家元首を兼ねている英連邦王国14ヶ国や、英国の陸海空軍や、イングランド国教会や、女王が葬祭や会長を務める600を越える各種団体についても、間に入って連絡係となります。国内外の公式・非公式な行事のアレンジを行い、その際の交通機関の手配・公式写真・マスコミ対応を統括すると共に、1760年から連綿と続く王室の記録を収めた王室文書館の管理を行います。その上、国内外さまざまな所に移動する女王のそばに、つねに控えています。 激務ですね。 それから始まる本文では、まず序章として、現代における王室の意義を説きます。 世界の中では、君主制度をとらない国家の方が圧倒的に多いのですが、しかし君主制をとる国は200近い世界の国家の中で28ヶ国あります。その中で君主が政治の実権を持っているのはサウジアラビア、ヨルダン、ブルネイと言ったわずかな例だけで、大半の国では議会やそれに立脚する内閣が国家統治の実権を持ちます。しかし、各国それぞればらつきはある者の、君主の存在意味が薄れたわけではない。それにはそれなりのメリットがあるのだ、という話。これはわが国の皇室の存在と共通するものもあるし異なるものもあるので、この話を日本の制度に敷延することは出来ませんけど。 そののち、君主制という基盤を持った英国という立憲君主制国家の中に、王室と議会、国民を仲介する役目を負った「秘書官」がどのように現れたのか、という歴史を遡ります。それは、国家の情報と機密に関係があるのだと。
英国の秘書官の萌芽は、英仏百年戦争時、リチャード二世の即位から始まるのだそうな。彼は百年戦争を起こしたエドワード三世の嫡孫、かつかの有名な「黒太子」エドワードの嫡子で、わずか10歳で即位します。戦時に当たって英国議会は国政に対し監視や統制が厳しかった、というのはいかにも英国(当時はイングランド)らしいところですが、その監督を嫌って王やその側近が議会によらない行政機関を設置して寵臣政治を進めていった過程で、宮廷財務室から分離した「国王秘書官室」が発達し、「国王秘書官 King's Secretary」という役職が登場したのだそうな。彼の任務は、 この制度は、1534年に国王ヘンリー八世の元で「国王秘書長官 Principal Secretary of State」に就任したトマス・クロムウェルの時代にひとつの頂点を迎えますが、彼の処刑と共に一時衰退します。盛り返したのは、八世の娘エリザベス一世の時代。 ウィリアム・セシル、フランシス・ウォルシンガム、ロバート・セシルといった辣腕家がこの職を占め、女王の宰相の役目を果たします。そののち、スチュアート朝、ピューリタン及び名誉革命期を経てハノーヴァー朝になるにつれてこの役職の重要度は増し、秘書官も一人から二人体制になり、役職の目的が国王の補佐から国家を支える事に変貌するに付けて国務大臣、内閣の母胎となっていったのでした。閣僚による内閣においても名称は踏襲されますが、同じ大臣を表す言葉ですが、のちに出来た Minister より Secretary の方が格上とされるそうです。 しかし国王を直接補佐する秘書官もまた必要であり、老いて目の不自由なジョージ三世の補佐官としてサー・ハーバート・テイラーが近代最初の「国王秘書官 Private Secretary」に任ぜられます。年給2000ポンドだったとのこと。 テイラーは謹厳実直・公正無比な勤務ぶりで信頼を勝ち得ましたが、その後ジョージ三世が精神病で皇太子が摂政となったとき、彼が重用したジョン・マクマホン、サー・ベンジャミン・ブルームフィールドが無能な上に権力と富に耽溺する愚人であるとともに即位したジョージ四世の不人気もあって、いったん国王秘書官職は廃止されます。 その後、死亡した四世に代わって即位したウィリアム四世が高齢だったため、前々国王に仕えたテイラーが再び国王秘書官の職についたのですが、今度はその頑固な忠誠ぶりが問題となって政府側からその存在意味が疑われます。 その後即位したヴィクトリア女王の治世下でも、国王秘書官という制度の必要性は認識されつつ、使う側や秘書官に任じられた人々の手腕などにより、さまざまな問題があり歴史がありました。結果としてこの、女王、王配、皇太子などにつく秘書官という制度がきちんと機能した理由として著者は、まず陸軍軍人であったから、と言います。 その理由を三つ上げています。第一に、最も大切な要人である王室の人々を体を張って守れるボディーガードであったこと。第二に、陸海軍の最高司令官やそれに準ずる軍事的な役職に就くにあたり、現場の軍事的な知識をアドバイスできる立場にあったこと。そして第三に、軍の将官として勤務していた彼らには「守秘義務」と国家に忠誠を誓う義務が課せられていたから。
こうして誕生した制度の変遷と、ヴィクトリア女王以後、大衆に根ざした立憲君主として君臨し、国民を導くと共に寄り添おうとした国王たちや女王と、彼らを支え続けた国王秘書官の姿が、丁寧に描かれます。 歴代の英国国王たちが、英国の政治、外交、戦争などの歴史の中でどのような役割を果たしたのかについて、日本の皇室と比較することは意味がありません。日本は長い歴史と文化と伝統を持っているけれど、立憲君主国家としての歴史は事実上ないと言っていいくらいだし、天皇に対する日本人の敬意や敬愛も、かならずしもみな同じではない。 しかし英国には、こんな歴史があり、それを秘書官という人々が支えていた。これを知るだけで、この本には価値がある。 彼らを使いこなせなかった王や、伝統と義務を理解できない国王に離反した側近たち、秘書官たちの姿も描かれます。彼らが皆、優れた人格と非の打ちどころのない自制心を持っていたわけではない。 第四章の半ばで描かれる、だらしない性格でいいかげん、気まぐれな王と、知的で有能で勤勉で、しかも厳格すぎる自分の性格と狭量さを自覚できず他人の怠惰を許せない秘書官という組合せがなければ、「王冠を賭けた恋」の顛末は防げたかもしれないという一節は興味深い。 なるほど、英国にはこんな歴史があるんだ。 末尾の方で、2005年度の女王(当時)秘書官らの給料が書かれています。むろん英国の公式な官僚ですので、調べればわかること。それによると、当時の女王秘書官であったサー・ロビン・ジャンヴリン(1946年生まれ。1999-2007 エリザベス女王秘書官)の年給は、167,000ポンド(日本円にして4176万円ほど)であり、この金額は王室関係者としては、女王手許金会計長官に次ぐものなのだそうな。しかも女王秘書官は60歳を過ぎると年額39,000ポンドの年金も支払われるとのこと。 なるほど、重責なんだねぇ。 2007年に出された原著を文庫本として2023年に刊行するにあたり、その後の歴史の流れの中で秘書官たちが果たした役割や彼らの苦悩も追加されて描かれます。ハリー王子と結婚したメーガン妃の自由奔放ぶり、我の強さに辟易する秘書官の姿と、のちのハリー夫妻の王室離脱など、書かれていることはわずかですが英国王室の視点で英国王室の内幕もさりげなく載せています。そして、2022年9月のエリザベス二世の崩御とチャールズ三世の即位。 チャールズ皇太子時代、いずれ王位に着くときには、ジョージの名で即位したいと願ったこともさりげなく書かれています。チャールズという名の王が二人とも縁起が悪い(一人は処刑され一人は王朝の終焉の原因となった)ためなのですが、結局この意志は通りませんでした。三世がその名を高めてくれればヨシとなるのかな。 文庫版に追加された解説で、歴史学者として著名な伊東之雄氏が、君塚さんのイギリス君主制、イギリス近代史・現代史の研究に関して賛辞を呈しておられます。氏は、それまで訳語がバラバラだった Private Secretary という言葉に氏自身の論文で「国王(女王)秘書官」という言葉を当てた方だそうですが、君塚さんが2007年に刊行した本書で日本にこの言葉が定着したとして、君塚さんの功績を称えておられます。 また氏は、君塚さんが、従来近代日本の君主制は近代ドイツとの比較で論じられることが多かった風潮の中で、英国王室との比較を本格的に論じたことを評価しておられます。そして、従来の英国王室を「君臨すれども統治せず」とされていた中で、戦前の近代日本の天皇と同じように政治に積極的に関わってきたという論を展開する方向で、高い功績を上げたと。 なるほど、歴史とは面白い。この研究に参加してみたいと思ったはるか昔を思い出しました。手遅れですが。(2024/10/20) 読書メーターの記録より 読了:2024/6/8 |
||||||||||||