トップへ戻る 作家/分野 一覧 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 書 名 | 翻訳者 | メ モ | |
|---|---|---|---|---|
| 岩波文庫版 モンテ・クリスト伯 全七巻 | 世界に名を轟かした復讐譚(新旧計14巻) | |||
| 三銃士&ダルタニャン物語 全11巻 | 名高いフランスの冒険者の物語(計13巻) | |||
| D005-020 | 黒いチューリップ | 宗 左近 | 政治とロマンスとチューリップと | |
| D005-021・022 | 王妃の首飾り(上・下) | 大久保和郎 | フランス革命前夜、宮廷内大事件 | |
| D005-023・024 | 王妃マルゴ(上・下) | 榊原晃三 | 聖バルテミーの虐殺と悲劇の王妃 | |
| D005-025 | 赤い館の騎士 | 鈴木豊 | フランス革命時、王妃救出作戦 | |
| D005-026 | ポーリーヌ | 小川節子 | 1830年代 不思議な怪奇ロマンス小説 | |
| D005-034 | メアリー・スチュアート | 田房直子 | 数奇な運命に生きた悲劇の女王 | |

| Ver. 3.02 |
|---|
| 管理番号:D005-020 | 32 歴史小説・西欧史 | 出版社:東京創元社 | |||||||
| 書名:黒いチューリップ | ISBNなし | ||||||||
| 原題:La Tulipe Noire(1850) | 翻訳者:宗 左近 | ||||||||
| 創元推理文庫 512A | 価格:210Yen | ページ数:384P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:71/3/26 第4版:72/11/10 | 購入:73/7/8 | カバー:日下弘・永井孝子 | |||||||
 1672年8月の、オランダ、ハーグ市から始まります。 1672年8月の、オランダ、ハーグ市から始まります。この時代のオランダは、歴史的に言うとヴェネツィアの後を継ぐような交易大国として世界と商売をする通商国家として繁栄していました。国名はより正確にはネーデルランド連邦共和国であり、北部の七州とその他の属州などとが連合したものです。現代のオランダ王国の先祖といってもいいけれど、若干の違いはあります。国体は共和国を名乗りますが総督(統領 stadhouder)を国家元首に抱く時期がほとんどでした。 この総督の地位には長年のあいだ、オラニエ=ナッサウ家(Huis Oranje-Nassau)の人々が就いていたのですが、オラニエ公ウィレム二世(1626-1650 総督在位:1647-1650)が若くして死んだ時から八日後にその後継者たる嫡子ウィレム、のちのウィレム三世(1650-1702 オランダ総督在位1672-1702)が生まれたという経緯があります。その結果、この若者の生涯の前半は、国家元首による統治を嫌う共和主義者のために単なる貴族の子として育てられたのでした。  その時代、オランダ共和国において1653年からホラント州法律顧問の地位にあったのが、ヨハン・デ・ウィッテ(Johan de Witt 1625/9/24-1672/8/20)。ホラント州法律顧問とは、総督のいない共和国にあって国家元首に限りなく近い存在。 その時代、オランダ共和国において1653年からホラント州法律顧問の地位にあったのが、ヨハン・デ・ウィッテ(Johan de Witt 1625/9/24-1672/8/20)。ホラント州法律顧問とは、総督のいない共和国にあって国家元首に限りなく近い存在。この本の訳文ではジャン・ド・ウイット総理大臣としていますが、これはフランス側から見た言葉であると共に古い知識による翻訳ということで、まァしかたないか。 このヨハンが、若きウィレムの傅育官も務めていたというのが歴史の皮肉。 ヨハンの兄がコルネリス・デ・ウィット(Cornelis de Witt 1623/6/15-1672/8/20)。この本ではコルネイユ、あるいはコルネリウス・ド・ウイット、またの名をリュアール・ド・ピュルタンとし、オランダの堤防監督官にしてオランダ共和国の代議士としています。 彼ら二人(右の彫像は、彼らの出身地ドルトレヒト市に残るもの)は、当時のオランダ(ネーデルランド連邦)を、君主に相当する総督の地位に就くべきオラニエ公が若いことを利用して、君主制ではなく共和制の国家にしようと考え、そういう政策を続けたようです。しかしこれが人民の憤激を買ったのでした。 彼らは捕らえられ、拷問され、裁判にかけられ、その執行を待たず無残にリンチにかけられます。その肉は小間切れにされ、一切れ十スーで売られた、とデュマは描写しますが、スーというものが1/20リーヴルを示すフランスの貨幣単位であることを考えると、当時の噂話のレベルの話かもしれません。とはいえ凄惨なものであったことは絵画(←グロ注意)にも残っています。 この兄弟の血と肉を階段として、オラニエ公ウィレム三世は総督への地位に上がっていく、とデュマは描写します。言い得て妙か。 ところで、デュマは基本的に君主制、貴族制の側に傾倒する人ですから、ウィレム三世の復権に好意的です。しかし同時に高邁な心を持つ人々を称える男でもあるので、この兄弟の味方もしています。
こんな時代と政治情勢を背景に、デ・ウィット兄弟が殺された日からこの物語は始まります。 コルネイユの捕らえられていた牢の牢番の娘、ローザ・グリフュスは、優しい少女でした。彼女は最期が近いド・ウイット兄弟の会話から、ジャンがかつて友人との間で交わした書簡があることを知ります。 その書簡は、
彼が愛したのは、実はチューリップでした。丹念にチューリップを栽培し、次々と新種を発表して、彼は名を上げます。 この時代、オランダは実はチューリップ愛好家によって支配されていたのでした。彼らはこう言う。
この青年に、嫉妬深い、実にわかりやすい隣人がいます。悪人。悪人といえば、ローザの父親も悪人なのですがこれはまた後日。 イザーク・ボクステルは、子どもの頃からチューリップを愛する市民でした。情熱を持って育て、作り上げたチューリップは町の評判になり、遠くの町の上流社会からも注文があるほど。 しかし彼の隣の家でチューリップを栽培し始めた男がいたのでした。この青年コルネリウスは素人だったのですが、チューリップにかける情熱はボクステルに勝るとも劣らない。しかも金がある。中庭にある建物を一階分高くして暑気を避けるようにしたのですが、その結果ボクステル(の鋭敏な感覚によると)の庭の温度を二分の一度ほど下げ、かつ風通しを悪くしてしまったのでした。 その二階部分のガラス窓の中には、不幸なボクステルにはとても手にできないチューリップ栽培の道具と、聖域ともいえる乾燥室があったのです。しかもそこで、このコルネリウスは漆黒のチューリップの製造に成功しつつあるらしい。 どうにもならない嫉妬に捕らえられたボクステルは、こっそりとこの二階を監視し始めます。そこで驚くべきものを見たのでした。総督派であるボクステルにとって謀反人であるコルネイユ・ド・ウイットがこの部屋を訪れ、入念に封をした書類の包みを戸棚の中にこっそりと入れるのを。 ウイット兄弟が惨殺されたとき、ボクステルは不意に気がつきます。 憎むべき隣人が二度とチューリップを栽培できなくできる手段と、黒いチューリップという素晴らしい宝物が自分のものになるという機会が、目の前にあることに。 かくして、まったくなにも知らず政治にもなんr関心のなかったコルネリウス・ファン・ベルル氏は、1672年8月20日、自宅のその乾燥室で官憲に逮捕されてしまったのでした。謀反人コルネイユ・ド・ウイットの自筆の書類の隠匿という疑いようのない罪状で。
半狂乱になったボクステルは、逮捕されてローザの父グリフィスが看守となっている牢獄の中にいるコルネリウス青年から貴重なチューリップの側芽を奪い取ろうとあの手この手。 この純真な青年に恋をしたローザは、チューリップを育てることとコルネリウスを救うことを決心してあの手この手。 さあ、この決着はどうなるのか。政治的な勝利を手にしたオレンジ公ウィリアムは、市井の一事件をどう裁いたのか。 アレクサンドル・デュマ・ペールが紡ぎだしたささやかなロマンス冒険です。堪能しました。 突っ込みどころは、訳文ですね。あちこち言いたいことはありますが、ともかくオレンジ公ウィリアムという英語式の表記が一番かな。オランダ式にオラニエ公ウィレムとする、あるいは徹底してフランス式でオランジェ公ギヨームとする手はあったはずですがそうはしていません。 最終的にこの人は、英国の王座があいたことで、漁夫の利を得る形でイングランド王ウィリアム三世(右絵)となります。それを考えての訳文なのでしょうけど、このときはまだそう呼ばれなかったのです。 うーむ、気に入らんなぁ。(笑)(2016/7/19) |
||||||||||||||
| Ver. 2.15 |
| 管理番号:D005-021・022 | 32 歴史小説・西欧史 |
出版社:東京創元社 | |||||||
| 書名:王妃の首飾り(上) | |||||||||
| 原題:Le collier dela reine(1849) | 創元推理文庫 作者別 512B | ||||||||
| 翻訳:大久保和郎 | 価格:330Yen | ページ数:623P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:1972/4/7 | 購入:1972/7/15 | 表紙イラスト:日下 弘 | |||||||
| 書名:王妃の首飾り(下) | |||||||||
| 原題:Le collier dela reine(1849) | 創元推理文庫 作者別 512C | ||||||||
| 翻訳:大久保和郎 | 価格:330Yen | ページ数:621P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:1972/5/26 | 購入:1972/7/21 | 表紙イラスト:日下 弘 | |||||||
  かの有名な漫画「ベルサイユのばら」が出たちょうど同じ頃に、この本は訳出されています。合わせたのでしょうかね? かの有名な漫画「ベルサイユのばら」が出たちょうど同じ頃に、この本は訳出されています。合わせたのでしょうかね?ぼくにとって幸運と言うべきか、ぼくはこの本を、漫画を読むより先に読みました。漫画は姉が単行本で買いましたので、読んだのはその後。 そして、発表当時すでに傑作の名を得ていたこの漫画と、この本を読み比べて、漫画という文化に対しての評価を大幅に下げてしまったものでした。漫画をある程度評価できるようになるためには、それから20年かかっています。 まあ、単なる石頭なのですけど(爆笑)。 漫画の方は絵は綺麗で、恋愛ものとして面白いのかも知れませんが、歴史をあつかったお話としてはあまりにもいい加減、と思ってしまったんですよね。 この本の最初に、二章からなる約60ページのプロローグというか短編がついています。 1784年4月初旬、リシュリウ老元帥の屋敷で、元帥とその家令との会話が第一章です。午餐に迎える8人の来客とそのもてなし方について、エスプリあふれる会話が展開します。 ここを読んで引き込まれない読書好きがいたら、お目にかかりたい。 第二章は会食の席。謎の人物カリオストロ伯爵が、自分が永遠の命を持っていると言い、謎に満ちた若返りの秘宝を語り、場の人々を魅了し、恐怖に怯えさせます。この章もまた、読んで引き込まれない読書好きがいたら、お目にかかりたい。是非とも。 クレオパトラの時代より伝わるダイヤモンドの指輪、などという設定的におかしいお話は無視しましょうね。(笑) さて、本編はジャンヌ・ド・ラ・モット・ド・ヴァロアという女から始まります。彼女が自分の貧しい家に迎えた女性たちは、慈善団体の幹部と名乗ります。ジャンヌの目には彼女の正体はわかりませんでしたが、彼女こそはマリー・アントワネット・ジャンヌ・ジョセーフ・ド・ロレーヌ、すなわちフランス国王ルイ16世妃そのものでした。 この物語は、このジャンヌがあの手この手を使って成り上がろうとする物語であると共に、さまざまな人々が野心と欲望のままに権謀術策を弄する物語です。その中に、フランス革命前夜にブルボン王家を揺るがした「首飾り事件」もあります。 誇り高き人々と、高貴な心。気高さと名誉。デュマはこういう描写が得意ですね。それと、パノラマを見回したような色とりどりの描写。 マリー・アントワネットの生き方。ルイ16世との関係。王弟プロヴァンス伯(のちのルイ18世)、アルトワ伯(シャルル10世)との間柄。 当時の時代を背景としたデュマの解釈は、読んでいて楽しい。 ロアン枢機卿という人物が出てきて、「首飾り事件」で重要な役回りを演じます。ロアン家の誇りを示す家銘 ─ 王にはなれぬ、公では御免だ、われらはロアン ─ を読んだ後で漫画を読むと、誇りも名誉心もない間抜けなデブのキャラクターが情けなくなりますな。まして、高貴な貴族たるもの、マリー・アントワネット・ド・フランスなどという名前に瞞されるわけがない。(と、昔ひとりで怒っていました(笑)。) 王家の体面を保ち、王妃の高貴な名誉を守るため、ささやかな幸せと、ささやかな純愛が押しつぶされ、歴史は動きます。 デュマの大河ロマンです。この話の前に「ジョセフ・バルサモ」という本があり、この後に「アンジュ・ピトゥ」、「シャルニー伯爵夫人」と連なり、大きな連作となっていましたが、今さらこの本以外はもう翻訳されないでしょう。 寂しいですね。(07/2/14) |
| Ver. 2.23 |
|---|
| 管理番号:D005-023・024 | 32 歴史小説・西欧史 |
出版社:河出書房新社 | |||||||
| 書名:王妃マルゴ(上) | ISBN978-4-309-46133-6 C0197 | ||||||||
| 原題:La Reine Margot(1845) | 翻訳者:榊原晃三 | ||||||||
| 河出文庫 テ2-1 | 価格:750Yen | ページ数:395P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:1994/10/4 | 購入:1994/11/18 | カバーデザイン:渋川育由 フォーマット:栗津 潔 | |||||||
| 書名:王妃マルゴ(下) | ISBN978-4-309-46134-4 C0197 | ||||||||
| 河出文庫 テ2-2 | 価格:750Yen | ページ数:384P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:1994/10/4 | 購入:1994/11/18 | カバーデザイン:渋川育由 フォーマット:栗津 潔 | |||||||
  実在した主要人物についてはブログに飛ばしました。この本、重厚な歴史小説なので、背景を調べ始めるときりがないったらありゃしない。 実在した主要人物についてはブログに飛ばしました。この本、重厚な歴史小説なので、背景を調べ始めるときりがないったらありゃしない。→「王妃マルゴ」へのメモ ともかく、その人物は下記の通り。 カトリーヌ・ド・メディシス 43歳。 マルグリット・ド・ヴァロア 19歳。 シャルル9世 22歳。 アンジュー公アンリ 20歳。 アランソン公フランソワ 17歳。 アンリ・ド・ナヴァール 18歳。女丈夫の母が暗殺されて二ヶ月。 アンリ・ド・ギーズ 22歳。 その他、実在するけどお話としては重要な役割ではない人たち、コリニー提督、ラ・ロシュフーコー、モンモラシー元帥、クロード・ド・ヴァロワ(マルゴの姉)などが出てきます。 実在したようなんだけどはっきりしない人たちとして、最も大きい存在は、 シャルロット・ド・ボーヌ=サンブランセ かな? ソーヴ男爵夫人であり、カトリーヌ・ド・メディシスの化粧係の侍女。カトリーヌの黙認の元にナヴァール王アンリの愛人となっています。 このお話は、1572年8月18日に始まります。この日、アンリ・ド・ナヴァールは正式にマルグリット・ド・ヴァロアと婚礼の式典を上げます。この結婚に対しは、新教側・旧教側の反対勢力もあり、、ローマ法王グレゴリウス13世が結婚許可証の発送を遅らせたことなど、いろいろ気の揉める事はありましたが、母后カトリーヌとシャルル9世が押し切った形になっています。この結婚に積極的に賛成していたはずのアンリの母ジャンヌ・ド・ナヴァールが、何らかの秘密をかぎつけて母后カトリーヌに2ヶ月前暗殺されたらしい、という不穏な風説もありましたが、まずはめでたいところ。 この新婚の夜、マルゴは自分の寝室にアンリ・ド・ナヴァールを迎えます。いささかあわてているのは、彼女の心変わりを疑うギーズ公がすでに現れ、彼を小部屋に押し込んだせいだったりする。いかにもフランス宮廷ね。しかし、会話はけっこうシビア。
政治情勢は行き詰まりつつあります。シャルル9世は、カトリック一派に対しても、ユグノー(新教徒)に対しても、一定の距離を取って両方の顔を立てようとしているのですが、800人以上のユグノー貴族が今回パリに現れ、さらに何十人か集まるという。両勢力の反目は限界を超えつつあります。この情勢の中で、シャルル9世は決断せざるを得なくなる。 デュマの登場人物たち、とくにクレバーな政治感覚を持つ人びとは、情熱的に愛や友情や敬慕を誓う熱い心と、一瞬で心を切りかえるシニカルさを併せ持ちます。シャルル9世もその一人。「アンリオ」と呼んで慈しむ従弟(正確には又従兄弟)であり義弟となったアンリ・ド・ナヴァールに対しても、必要となれば切り捨てる非情さを持ちながら、一瞬後には身を挺して友を助ける複雑な接し方をします。その逆もしかり。 このへんのデュマ節が、なんとも言えず素敵です。 幕間劇といった形で、二人の青年が紹介されます。 一人は、ルラック・ド・ラ・モル伯爵。ユグノーの貴族で、アンリ・ド・ナヴァールによってはるかプロヴァンスから呼ばれた24、5歳の青年。上品な顔立ち。黒髪、青い目、日焼けした顔に薄い口ひげ、輝くばかりに白い歯。優しく愁いを含んだ笑顔。 もう一人は、アニバル・ド・ココナス伯爵。カトリックの貴族。ギーズ公の遠縁に連なるもので、ピエモンテ出身でそこの訛りが目立つ。ラ・モルと同年配。庇のそり返った帽子の下に豊かで縮れた赤茶色の髪。きらりと光る灰色の目。バラ色の顔色、薄い唇、褐色の口ひげ、見事な歯。白い歯を輝かせた長身で広い肩の美丈夫。 デュマの、タペストリーをゆっくり見まわすような描写は素敵です。 この二人が、夜空の下で鶏肉のローストを焼いている見事な絵が描かれた宿屋の下で出会うのです。フランドルとのいくさということで呼び集められた貴族ばかりで宿に空きがないということで、この二人で相部屋になりました。宗派の違う二人ですが何となく気が合い、この親父が作った大きなオムレツを二人で分けることとなります。どうやらこの親父、肉がうまく焼けないらしい。(あはは) 政治判断と、母后カトリーヌの策謀、そしてギーズ公の陰謀は8月24日についに暴発します。「サン・バルテミーの虐殺」事件。 奇襲を受けたユグノー側は次々と殺戮され、3000人が殺されたと言います。この騒乱の直前、アンリは母后カトリーヌの、町へ出て気晴らしでもしたらどうか、という言葉とマルゴの顔色にただならぬ気配を察して、マルゴの部屋に行く。この部屋に、暗黒の町で斬り合って重傷を負ったラ・モルとココナスが庇護を求めて転がり込み、事態は急展開。 真っ暗な町に、陰惨な虐殺と政治的な陰謀が渦巻きます。こんな中で、いくつかの友情と愛が生まれます。 ラ・モルとココナスの友情、アンリ・ド・ナヴァールとアンリ3世の奇妙な信頼関係、ラ・モルとマルゴの愛、ココナスとマルゴの友人アンリエットの恋。アンリエットとは、ギーズ公の従姉妹であるヌヴェール公爵夫人。 夫公認の愛人、妻公認の愛人が当たり前だった当時の時代を背景に、恋のさや当ては幾重にも絡み合います。 「三銃士」の物語のミレディ、「二十年後」のモードントなど、デュマの物語には悪魔的人物が現れます。「モンテ・クリスト伯」ではエロイーズ・ド・ヴィルフォールでしょうか。この物語では母后カトリーヌがその役ですね。彼女は愛するものを守るため、剣で殺すことができない相手には毒を使って、次々と敵と見定めた人を始末していきます。 手袋に潜ませた毒、ワインに入れた毒、唇に塗る軟膏の中の毒、本の装幀に塗りつけた毒。 最後の、本の毒は「薔薇の名前」(ウンボルト・エーコ)に出てきます。ページの外側に毒が塗られているために、ページがくっついて指を舐めてめくらなくてはいけなくなるのです。悪魔的で、見事な毒の使い方ではありませんか。 悪魔的人物が仕込んだ悪魔的な毒が、予想を超えた悲劇を生みます。 そしてその罪が、フランスと国王に忠誠を尽くそうとする若い青年たちに降りかかります。理不尽な悲劇と言うより惨劇というべきか。 デュマ・ペールのペンは、見事にこの争乱の歴史に一つの説明を付けました。 正しい歴史であるはずはないが、あり得たかも知れない。そう思わせる歴史小説を書くことが、歴史小説家の喜びなのでしょうね。 偉大なり、デュマ・ペール。(09/5/21) 映画「王妃マルゴ」は1994年にイザベル・アジャーニ主演で映画化されました。この本は、そのおかげで翻訳できたようです。 なんにしても、めでたい。 映画はDVDに落としたはずなんだけど、見つからなかった。やたらと暗~い画面で、マルゴが無意味に淫蕩な女になっていて、ラ・モルが情けない役どころだったような記憶があります。見直す必要あり、ですね。 パリの市(まち)の首切り役人カボッシュ、という人物が出てきます。上巻P266で名乗り、最後に重要な仕事をします。 医術に精通していますが、一般の医師からは無視されます。権力者の命令によって人を処罰し、拷問し、処刑します。 しかし、サディストなどではありません。穢れた卑しい職に就きながら、矜持と責任感を持って仕事をします。仕事としてに人を鞭打ち、骨を砕き、首を切り落とし、死体を清めて埋葬します。そう、あのムッシュ・ド・パリ(Monsieur de Paris)なのです。「死刑執行人サンソン」で描かれたシャルル=アンリ・サンソンの遠い先輩に当たります。 しかし不思議なことに、Googleでもフランス版Wikiでも、死刑執行人の呼応式名称として「Monsieur de Paris」という項目は存在しません。 本当に「ムッシュ・ド・パリ」という言葉があるのだろうか? 今、ちょっと疑問がわいてきました。はてな。 σ(・_・)? |
||||||||||
| Ver. 2.4 |
| 管理番号:D005-025 | 32 歴史小説・西欧史 |
出版社:ブッキング | ||||
| 書名:赤い館の騎士 | マリー・アントワネットを救え! | 発行:1846年 | ||||
| 原題:Le Chevalier de Maison-Rouge | ||||||
| 翻訳:鈴木豊 | 価格:2500Yen | ページ数:686P | 本のサイズ:130×190ソフトカバー | |||
| 初版発行:03/10/15 | 購入:03/10/31 | 装幀:クリエイティブ・ステーション・ビィピィ | ||||
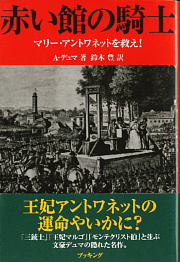 この本との出会いはそもそもは、復刊ブックコムという、絶版となった本をリクエストに応じて復刊するサイトから始まります。ふと、何かの弾みにデュマで検索をかけたところ、この本が投票中でした。 この本との出会いはそもそもは、復刊ブックコムという、絶版となった本をリクエストに応じて復刊するサイトから始まります。ふと、何かの弾みにデュマで検索をかけたところ、この本が投票中でした。名前だけは知っていたので、ダメモトで投票しましたところ、数ヶ月後に復刊が決定。 こうして、なんの縁かこの本を手に入れることとなったのです。 とはいえ、読み始めてしばらくは、なかなか波長が合いませんでした。なにしろ、150年も昔の本ですからね。少し読んで投げ出していたのですが、このたび読み直し、このクライマックスに感激しました。ここまでやるか、デュマ、恐るべし。 1793年3月10日の夜から、話は始まります。 フランス革命が始まったのは1789年7月、ルイ16世が処刑されたのが93年1月21日ですから、時はいわゆる恐怖政治の時代。ささいな疑惑が容疑者を生み、容疑者は即決裁判で即ギロチンへ送られる社会。フランス国民の半分が密告に怯え、もう半分は密告するネタを探していた恐るべき時代です。 この時代を背景に、二人の青年が登場します。国民軍の中尉であるモオリス・ランディと、その友人である夜警の伍長マクシミリヤン・ジャン・ローラン。生真面目な愛国者モオリスと、言葉の端々で詩を謳い、名言の引用で茶化す陽気なローラン。 この二人がこの夜出会った不思議な娘。彼女は志願兵に呼び止められて衛兵所へ連れ込まれようとしています。彼女を救ったことで、運命の網の目にはいるのです。 革命政府に忠実な愛国者なら決して使わない言葉、彼らをムッシュウと呼び、貴族的な二人称「あなた(ヴー)」を使うこの娘。愛国者は、「きみ(テュ)」と呼び、市民(シトワイヤン)、女市民(シトワイエンヌ)と呼び合わなくてはいけない時代です。 彼女は何者なのか。たちまち恋に落ちてしまったモオリス。当惑するローラン。 ひそかに地下で進行するマリー・アントワネット救出作戦。 謎の人物、赤い館の騎士、つまりメーゾン・ルージュの騎士とは何者か。 時代の波は冷ややかに進行します。実際に何度も行われたとされる王妃救出作戦もすべて失敗に終わり、93年10月16日、王妃は処刑されます。王妃、すなわちマリー・アントワネット・ジャンヌ・ジョセーフ・ド・ロレーヌ、オーストリア大公女、フランス王妃です。 最期の言葉として歴史に残ったのは、処刑台の上で死刑執行人の助手の汚い手が身体に触るのをよけようとして、執行人のシャルル・アンリ・サンソン──この名も歴史に残されています──の足を踏んでしまってつぶやいた、 「許してください、ムッシュウ。わざとやったわけではありませんから」 でした。 さて、それでも事件は終わらない。二人の青年はどうなったのか。 どんどんとカタストロフは進行しますが、こんなクライマックスになるとは思いませんでした。すごい。 この本は、出版されたときからすでに事実に乗った完全なフィクションだと思われていました。しかし、G・ルノートルというフランス革命史家が、メーゾン・ルージュからさかのぼってルージュヴィル侯爵家の記録をたんねんに調べていくうちに、マリー・アントワネットの側近、崇拝者、愛人としての同侯爵すなわちアレクサンドル・ゴンスという人物が、小説に書かれたような冒険をしていたことを発見しました。ルノートル氏は「真説 メーゾン・ルージュの騎士 A・D・J・ゴンズ・ド・ルージュヴィル」という研究書を1894年に発表し、その中に書いているそうです。 いろいろな意味で、大デュマ、恐るべし。(06/2/27) |
| Ver. 2.17 |
|---|
| 管理番号:D005-026 | 24 近代冒険小説 |
出版社:日本図書刊行会 | |||||||
| 書名:ポーリーヌ | 原題:Pauline(1838) | ISBN978-4-8231-0666-0 C0097 | |||||||
| 翻訳:小川節子 | 価格:1600Yen | ページ数:209P | 本のサイズ:135×195HC | ||||||
| 初版発行:2005/5/10 | 購入:2007/6/30 | 装丁:五味恵子 | |||||||
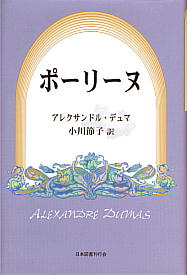 「近代冒険小説」というカテゴリーに分けてみたけど、ちょっと違いますね。いわゆるロマンス小説でしょうか? ハーレクインとか、そういう本を読んだことがないのにこんな事を言うのは変ですが、ああいう系統な気がします。 「近代冒険小説」というカテゴリーに分けてみたけど、ちょっと違いますね。いわゆるロマンス小説でしょうか? ハーレクインとか、そういう本を読んだことがないのにこんな事を言うのは変ですが、ああいう系統な気がします。構成は、まず主人公の、そして大部分もう一人の語りで勧められます。だから、常に一人称。 一人の人間が、体験や思いをこんなに覚えているはずがないじゃないの、という突っ込みは愚かでしょう。それをいったらこの話自体が成り立たない。(笑) 1834年の終わり頃、と「私」は語り始めます。 時は、ナポレオン戦争が終わったあと、王政復古があり、頑迷なブルボン王朝に民衆が絶望し、1830年におきた7月革命で、ブルボン王朝の進取派であるオルレアン公が新しい王として迎えられた時代です。かつての貴族の価値観がまだ生きていて、騎士の矜持が青年貴族の自律精神の基本であった時代。 「私」の出会った男は、アルフレッド・ド・ネルヴァルという青年でした。この青年が、自らの体験した驚くべき物語、「私」がかつて一度だけ生前の姿を見て、事情もわからぬままにその墓に祈りを捧げたポーリーヌ・ド・ムーリヤンという女性との物語を語ってくれます。 かつてこの本は、この第七章だけが「オラース伯爵」として発表されたこともあるそうです。この超人的な男がなにをもたらしたのでしょうか。 総じて読み慣れないせいか、感情移入しにくいところがあります。時代のせいと、内容のせいでしょうか。 でも、時代がかったものの言い方が、妙に気に入りました。たとえば、相手を殺してやりたいという憎悪を抱いた「僕」が、生意気なヤツだと怒りを露わにする相手とかわす一触即発の場面。
こんな会話、展開などあり得ないよなぁ、と思いつつ、そんな時代、そんな世界もあったのかと考えておもしろがる。 あ、これって銀河英雄伝説を読む楽しみのひとつだな。 久しぶりにデュマ節を楽しみました。 でも、怪奇ロマンス小説をこんな視点で読んでは、いけなかったのじゃなかろうか?(笑)(07/11/18) |
||||||||||||
 |
Ver. 3.01 |
|---|
| 管理番号:D005-034 | 51 伝記・一代記 |
出版社:作品社 | |||||||
| 書名:メアリー・スチュアート | ISBN978-4-86182-198 C0097 | ||||||||
| 原題:Marie Stuart 1587(1839) | 翻訳者:田房直子 | ||||||||
| 価格:2400Yen | ページ数:288P | 本のサイズ:135×195HC | |||||||
| 初版発行:2008/8/30 | 購入:2013/12/15 | 装画:16世紀にエコール・フランセーズで制作された 白い喪服姿のメアリー・スチュアート |
|||||||
 メアリー・ステュアート(Mary Stuart 1542~1587 スコットランド女王メアリー1世・在位:1542~1567)とは、ラフに言うとイングランド女王エリザベス1世(1533~1603 イングランドとアイルランドの女王・在位:1558~1603)の時代の人。徳川家康(1543~1616)より一つ年長。 メアリー・ステュアート(Mary Stuart 1542~1587 スコットランド女王メアリー1世・在位:1542~1567)とは、ラフに言うとイングランド女王エリザベス1世(1533~1603 イングランドとアイルランドの女王・在位:1558~1603)の時代の人。徳川家康(1543~1616)より一つ年長。スコットランド王家に生まれ、生後6日で王位につきます。1558年に2歳年下のフランスの王太子と結婚、のちにフランソワ2世となった夫の王妃となりますが、1560年に16歳の王が病死すると、翌年スコットランドに戻ります。女王として国内のプロテスタントとカトリックとの融和を図ろうとします。 1565年、メアリーはイングランドの王位継承権を持つ従弟ダーンリー卿ヘンリー・スチュアートと結婚。しかし彼は、結婚直後にその無能で粗野で無責任な性格を見抜かれ、王としての地位も与えられず遠ざけられます。1566年、メアリーが長男チャールズ・ジェームズ、後のスコットランド王ジェームズ6世及びイングランド王ジェームス1世を生んだのち、翌年ダーンリー卿は死亡。この本では、寝室の下に火薬を仕掛けられ、爆死させられたという説をとりますが、それにしては死体の描写が綺麗すぎるのでは。 メアリーに次に取り入ったのは、ボスウェル伯ジェームス・ヘップバーン(1535~1578)。彼は煮え切らないメアリー女王を誘拐して結婚を迫り、1567年に王配(女王の配偶者)となります。しかしこの時点で、実質的にメアリーはプロテスタント側の虜囚。新たな夫となったボスウェルの大言壮語や無責任な自惚れなどに辟易する暇もない。 スコットランド、ロッホリーヴァン城に監禁されたメアリーは、1567年6月に退位文書に署名を強いられます。その後脱出に成功してイングランドに逃げ込みますがここには親族であるとともに政治的な敵であるエリザベス1世がいます。 イングランド王の継承権を持つメアリーは、エリザベス女王にとって様々な意味で邪魔者でした。 メアリーは、これ以後19年囚人としてイングランドで過ごした後、反逆者として1587年処刑されます。 このメアリーの生涯を、デュマは当時の資料を駆使して情感たっぷりに描き出します。常に女として振る舞うことが当たり前だったメアリーの、感情に揺れる心を描写することによって、この不幸な女王の行方を巧みに浮き彫りにします。ふむ。 この物語は、1839年から40年にかけて刊行された「有名な犯罪(Crime célèbres)」全八巻の一巻だそうです。このシリーズは、歴史上の18の有名な事件をデュマがまとめたもので、ノンフィクションのジャンルに入るようです。 デュマに関して後世の視点で言えば、「アンリ三世とその宮廷」、「アントニー」などの初期の演劇の後にまとめられたもので、「三銃士」、「モンテ・クリスト伯」、「王妃マルゴ」などの傑作のための足がかり、習作となったものといえるかもしれません。 メアリー・スチュアートという人物を、国を統べる王、国家を運営する政治家、国土を守る軍人としての器は何もない、事が起きれば女としてしか振る舞えない人物と描きます。当時の、そして現在の解釈としても違和感はないのですが、これを肯定的に描いているのかどうか、そのあたりが微妙です。 鐵太郎としては、この本の中でも対比されている、国家に大事があれば女ではなく王となったエリザベスと比べて、歴史上役立った人物かというと落第点しか上げられないのです。デュマとしてはどう評価しているのでしょうね。読み取りにくいところです。 一人の、辛酸を舐めつくし不孝を堪え忍び、毅然として死んでいった女性としてのみ描いているのか、王として無能だった女の、運命に翻弄された生涯を描いているのか、どうなんでしょうね。 実を言うと、デュマの名がなければ、そこそこ面白い伝記として楽しめたと思うのですが、その名があるためにもっと大きなものを期待してしまいました。「モンテ・クリスト伯」を読みながらでは、この本はどうも軽すぎましたね。(笑)(2013/12/25) |
 フランスの小説家・戯曲家。トマ=アレクサンドル・デュマ将軍の子として北フランスのヴィレール・コトレに生まれる。ナポレオンがデュマ将軍の死後、遺族に終身年金を下付しなかったため、幼少期は貧しい生活を余儀なくされ、まともな学校教育を受けることが出来なかったという。
フランスの小説家・戯曲家。トマ=アレクサンドル・デュマ将軍の子として北フランスのヴィレール・コトレに生まれる。ナポレオンがデュマ将軍の死後、遺族に終身年金を下付しなかったため、幼少期は貧しい生活を余儀なくされ、まともな学校教育を受けることが出来なかったという。