トップへ戻る 作家/分野 一覧 |
|
 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 書名 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| H031-001 | 聖断 | 戦争を終わらせるため苦闘した人々 | |
| H031-002・004 | ルンガ沖夜戦 | 1942/11 ガダルカナル島沖で行われた日米の海戦 | |
| H031-005 | 徹底分析 川中島合戦 | 信玄vs謙信 異説 | |
| H031-012 H031-013 H031-014 H031-015 H031-016 H031-017 |
昭和史探索 1 昭和史探索 2 昭和史探索 3 昭和史探索 4 昭和史探索 5 昭和史探索 6 |
大正15年昭和元年から昭和20年までの激動の日本史1~6 | |
| H031-018 | それからの海舟 | 勝海舟ファンの書いた江戸開城後の海舟の半生 | |
| H031-019 | 歴史探偵 近代史をゆく | 近代史の落穂拾い | |
| H031-020 H031-023 H031-024 |
日露戦争史1 日露戦争史2 日露戦争史3 |
日本を決めたあの戦いを見直す | |
| H031-021 | 歴史のくずかご | 112篇の歴史エッセイ | |
| H031-022 | 日本のいちばん長い日 決定版 | 1945年8月15日、なにがあったのか | |
| H031-025 | 戦士の遺書 | あの戦いの最後に男たちはなにを残したのか | |
 |
★このページはUnicodeです。★ |
Ver. 3.06 |
|---|
| 管理番号:H031-001 | 54 歴史点描 | 出版社:文藝春秋 | |||||||
| 書名:聖断 | 天皇と鈴木貫太郎 | ISBN4-16-339900-3 C0031 | |||||||
| 価格:1300Yen | ページ数:416P | 本のサイズ:135×195HC | |||||||
| 初版発行:1985/8/15 | 購入:1986/3/30 | 表紙:八月九日午前での最高戦争指導会議 画・白川一郎 |
|||||||
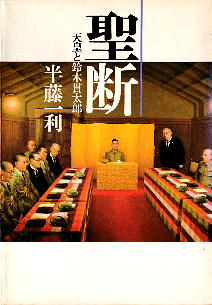 この本を読み直したのは去年の8月。今年の1月になって、著者である半藤一利さんの訃報が伝わってきました。ひとつの時代が消えていくのかな。 この本を読み直したのは去年の8月。今年の1月になって、著者である半藤一利さんの訃報が伝わってきました。ひとつの時代が消えていくのかな。「聖断」とは、明治憲法下では内閣の輔弼、軍部の上申によってのみ国政を定めるとされていた天皇が、その枷を越えて、自ら決を下して国政を動かすために判断を示すこと、と考えていいでしょう。基本的に、明治憲法に反する行為です。 特にこの本で描かれる「聖断」とは、終戦に至る国家の決断です。 戦前の日本帝国は天皇の独裁国家だったという「悪の帝国信仰」に取り憑かれている人に申し訳ないけど、日本の組織は誰かが絶対権力を持てるものではない。 敗戦濃厚となり、国民の塗炭の苦しみを見たとき、天皇は終戦への思いを強くします。しかし、彼は国家元首であり軍部の暴走に煮え湯を飲まされていたし、政党政治の限界も見てきた立場。しかも戦争の遂行にあたり帝国の大元帥として作戦の遂行にも携わり、叱咤激励さえ能動的に行っていたのでした。それが、天皇という「機関」のなすべき仕事であったから、です。 ゆえに、天皇裕仁の口から終戦を切り出すことは、出来ませんでした。
鈴木貫太郎は、鳥羽伏見の戦いの日に生まれ、心やさしい少年として育ち、賊軍の子弟として官界への立身の道は閉ざされていたために海軍への道を選びます。海軍兵学校を14期生として卒業し、真面目で倹約家の肝の据わった若手士官として教育され、戦いで名を上げます。 日清戦争では、大尉の水雷艇艇長として参戦。いまだ戦力として未熟な40トンたらずの小艇を指揮する勇猛果敢な姿により「鬼貫太郎」の勇名を得ます。 日露戦争において、イタリアより回航してきた装甲巡洋艦「春日」の副長として黄海海戦を戦ったのち、戦意の衰えた駆逐隊指揮官に代わり第四駆逐隊の司令となって猛将の名を轟かせます。 「鬼貫太郎は、夜襲のとき新聞を読み、敵の探照灯で新聞が十分に読めるようになると初めて魚雷発射を命じる」という伝説が生まれたのもこの時。 日露戦争後は海軍大学教官として教育に当たったのち、練習艦隊司令官、海軍兵学校長を経て少将に進級語は海軍省人事局長を経て、海軍次官としてシーメンス事件の後始末にかかります。 このころ、病没した妻の後添えとして足立たかという女性と再婚します。彼女は皇太子裕仁と次弟・秩父宮雍仁親王の養育係を務めた人物。 貫太郎はその後第二、第三艦隊司令長兼を歴任した後、1924年(大正13年)に連合艦隊司令長官に、翌年海軍軍令部長に就任します。これらを歴任しているとき、摂政から天皇になった裕仁の知遇を得、昭和4年に侍従長珍田捨巳伯爵が脳出血で死去したあとの後任に請われたのでした。固辞する鈴木に、一木宮内大臣は最後に殺し文句で説得したそうな。
このとき鈴木貫太郎は77歳、枢密院議長。十年ほど前の2.26事件において反乱将校等の銃弾を浴びて瀕死の重傷を負ったこともあり、第一線をとうにに去った老人。
この本は、主として鈴木貫太郎という一人の軍人・政治家を中心に、戦争終結という困難に立ち向かった人々を描きます。茫洋とした、現代なら老害と言われかねない老人が、どのように「聖断」を引き出し、陸軍の反乱を抑え、玉音放送を行えたのか。あの歴史の流れの中で、何が行われたのか。 半藤さんの筆致は、いまと変わらず、生き生きとあの時代を描写してくれます。(2021/05/05) 読書メーターの記録より 読了:2021/8/16 |
||||||||||||
| 管理番号:H031-002・004 | 52J 戦史・戦争ノンフィクション(日本) | ||
| 書名:ルンガ沖夜戦 | PHP研究所 | 発行 2000年 | |
| 価格:¥1500 | ページ数:260P | 装丁:46ハードカバー イラスト:谷井 建三 |
|
| 初版発行:00/1/10 | 購入:01/1/31 | ||
| 書名:ルンガ沖夜戦 | PHP文庫 は9-11 | 発行 2000年 | |
| 価格:¥571 | ページ数:322P | 装丁:文庫 イラスト:谷井 建三 |
|
| 初版発行:03/7/18 | 購入:03/7/26 | ||
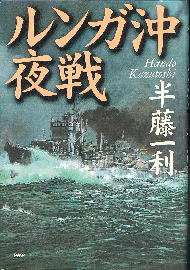  「あとがき」からの抜き書きですが、この本の原型は1971年9月に(株)R出版より「魚雷戦・第二水雷戦隊」の題名で出版されました。その後、1984年5月に朝日ソノラマ文庫より航空戦史シリーズの一冊として「ルンガ沖魚雷戦」として出版されたそうです。 「あとがき」からの抜き書きですが、この本の原型は1971年9月に(株)R出版より「魚雷戦・第二水雷戦隊」の題名で出版されました。その後、1984年5月に朝日ソノラマ文庫より航空戦史シリーズの一冊として「ルンガ沖魚雷戦」として出版されたそうです。その後、紆余曲折を経て、海軍史家の雨倉孝之氏の校閲を得てこの題名で再刊されたもの。ハードカバーで出たあと、文庫としてもまた再刊されました。 (不覚にも、気づかずにそのまま文庫を買ってしまいました) ルンガ沖海戦(米国名"The Battle of Tassafaronga")は、1942年11月30日に行われた、日本海軍が完勝した最後の海戦です。戦争に与えた影響は、あまり大きくはありません。1942年5月に行われたミッドウェー海戦を頂点として、下り坂を滑り落ち、転げ落ちながら必死に戦った日本軍の、ささやかな栄光です。 場所は、遙かな南洋、ニューギニア島の東方、ソロモン諸島のガダルカナル島沖。無謀な進出のあと、飢餓に苦しむ陸軍を支援するために補給物資を満載し、ろくに闘うこともできない形となっていた日本海軍の駆逐艦部隊8隻。待ちかまえる米国海軍は20センチ砲を搭載した重巡洋艦4隻、軽巡洋艦1隻、新鋭駆逐艦4隻。 圧倒的な戦力の差があります。 さらに戦力の差を広げる要素として、ふたつ。米軍は日本艦隊の行動をすべて捕捉しており、待ちかまえていたこと。そして、日本軍より遙かに優秀な水上レーダーを搭載していたこと。 日本が行った無謀なガダルカナル進出については、語るスペースはありません。その結果として、島に取り残された陸上部隊に補給物資を届けることができるものが高速駆逐艦しかないという、馬鹿げた状況に追い込まれたことだけ。 猛暑と絶え間ない空襲、そして不眠不休の中で、乗組員もフネも酷使され、とうに限界を超えていました。
第二水雷戦隊、つまり泣く子も黙る日本最高の突進部隊の指揮官は、開戦以来、田中瀬三海軍少将。当時51歳。 磊落にして細心。酔うと「コガネ虫は金持ちだ、金蔵建てた・・・」と歌う酒好き。 彼は、麾下の駆逐艦にこう序列をつけます。 警戒隊=長波(ながなみ)、高波(たかなみ)(任務・敵の奇襲警戒) 第一輸送隊=親潮、黒潮、陽炎、巻波(任務・ドラム缶各艦240個、タサファロンガ輸送) 第二輸送隊=江風(えかぜ)、涼風(すずかぜ)(任務・ドラム缶各艦240個、セギロウ輸送) 23時06分、待ちかまえる米国艦隊の最新鋭レーダーが、敵性の映像をキャッチします。ライト少将の間髪を入れぬ命令に従い、艦隊は転蛇し、高速で突進しつつ20センチ砲をもたげ、照準を合わせ始めます。 水雷戦隊は警戒艦を除いてほとんど停船しています。田中長官の座乗する旗艦長波も、低速で戦列の中にあります。戦隊が、補給物資を満載したドラム缶を海に流そうとしたまさにその瞬間、23時12分、沖合で警戒に当たっていた高波が超短波の隊内電話を発します。
1960年春、田中瀬三氏を訪問した半藤一利は、こんな話を聞きます。
アメリカ海軍は、田中瀬三とその麾下の日本駆逐艦部隊を恐れ、好敵手として高く評価しました。 しかし日本海軍は、田中少将を戦隊司令官の任務から解き、軍令部出仕を命じます。事実上の解任です。 ルンガ沖夜戦のあと、なおも無謀な輸送任務にかり出される駆逐艦部隊の苦衷を上申し、歯に衣を着せぬ批判を行うこの軍人が疎ましかったのか。 日本海軍が太平洋戦争に投入した駆逐艦は、合計112隻。 終戦時に残存した駆逐艦は下記の通り。 「潮(うしお)」「響(ひびき)」「雪風(ゆきかぜ)」「涼月(すずつき)」「冬月(ふゆづき)」「春月(はるづき)」「宵月(よいづき)」「夏月(なつづき)」「花月(はなづき)」わずか9隻という。(※あれ? 駆逐艦「神風」もいたはずでは?) ルンガ沖を戦い抜いた駆逐艦は、一隻も残りませんでした。 文庫版では、佐々淳行氏(半藤氏と同い年)が解説を書いています。 海上自衛隊護衛艦「たかなみ」を見学したあと、帰りの電車の中でこの本を思い出しました。 こんな歴史が、再び繰り返されないことを。(05/6/4) |
||||||
| Ver. 2.16 |
|---|
| 管理番号:H031-005 | 59 日本・戦国史 |
出版社:PHP研究所 | |||||||
| 書名:徹底分析 川中島合戦 | ISBN978-4-569-57746-6 C0195 | ||||||||
| 2000年6月にPHP研究所よりHC | PHP文庫 は9-10 | ||||||||
| 価格:¥552 | ページ数:282P | 本のサイズ:文庫 | |||||||
| 初版発行:2002/5/15 | 購入:2003/8/6 | 装丁:安彦勝博 装画:谷井健三 挿絵:森義利 | |||||||
 戦史研究家である半藤氏が「川中島」をその研究分野の視点で見たらどうなるのか。 戦史研究家である半藤氏が「川中島」をその研究分野の視点で見たらどうなるのか。この本の興味はここですね。 旧日本陸軍というと、日本史の中では嫌われものです。傲岸、横暴、近視眼的、猪突猛進、無責任、我が儘、自己保身。いいところなしですね。(笑) しかし、国家を守る軍隊として、決して前例踏襲だけでなく、さまざまな歴史の研究も行っていました。軍隊史、戦史が中心ですが、過去の歴史を研究することについて決して怠っていません。日本陸軍参謀本部が編纂した「大日本戦史」には、戦国時代の主要な合戦がすべて研究され作戦資料となっています。桶狭間から大阪の陣まで。 ところが、川中島合戦だけはない。 なぜか。 この合戦が、信頼に足る資料がないから、これが原因ではないかと作家はいいます。 信玄と謙信が一騎打ちをしたという合戦は、第5次川中島合戦というのがほぼ定説で、この激戦はさまざまな史料があります。しかし、信頼できるものは皆無と言っていい。武田方で描いたものと上杉方で描いたものが、日付、場所、武将すべてが食い違い、整合しない。内容は陳腐な軍談のたぐいでしかない。 最も信憑性が高いとされている「甲陽軍鑑」では、合戦そのものの記録がほんのわずかしかない。 この合戦を再構成するには、さらに想像力がいるのか。 さて、こういう主題、こういうイメージでこの本は書かれると思っていたのです。ところが違った。もっとウエットな視線ですね、これ。 子供の頃の講談から頭に入った、おまえは信玄派か、それとも謙信派か? 両雄の人間的な違い。チーム監督のように常に衆議にかけて決を下した信玄と、孤高の独裁者として越後の諸侯をまとめなければならなかった謙信。 2000年当時の王貞治監督の指揮ぶりに話が飛んだりもします。昭和17年頃、半藤氏はガキ大将として王少年を虐めたこともあるとか。 第5次川中島合戦といえば、いわゆる「啄木鳥(きつつき)戦法」が有名です。約1万2千の上杉軍と対峙した約2万2千の武田軍が取った別働隊による急襲作戦です。 この作戦についての批判・解釈について、突っ込み不足を感じましたね。新しい解釈でもっと違う考えがでるのかと思ったけれど、余り新しい解釈は出ませんでしたね。旧態然とした魚鱗の陣と車懸かりの戦法のまま。もっと違う解釈を期待したのですが、物足りない。 孫子の兵法よりの引用や、旧軍の「統帥参考」などからの言葉で講談調を盛り上げ、これはこれで面白いのですけど、どうせ半藤さんが書くのならもっと厳しい戦史や軍事的解釈を期待したのですが、そうはいきませんでした。 ちょっと残念。 戦争研究家の視点として面白いところは、武田軍の戦術はミッドウェイ海戦の南雲艦隊であり、戦略はノモンハンの関東軍であった、というところかな。 せっかく優位な立場でありながら、戦術的な目的をあいまいにして、投機的な別働隊作戦に半分以上の戦力を使ったこと。信濃と越後の国境線を確保すべき戦略目標が、たんなる砦の争奪戦になってしまっていること。そして、半分強の戦力しかない上杉謙信に名をなさしめ、謙信の戦略目的 ─ 「関東管領としての示威行動と武田の主戦力に打撃を加えること」─ を完了させ、あたら優秀な将兵を殺してしまったこと。 士気高く、戦意に満ちた兵が遭遇戦となって叩き合うと、どれだけの被害が生ずるか、この合戦が証明しました。わずか4時間ほどの戦いで、越後軍の損害は72パーセント、甲州軍の損害は62パーセント。我が国の歴史上、2万以上の兵力が戦った合戦としては、おそらく空前にして絶後の激闘でした。 こののち、両軍ともこのような合戦はしません。この損害が本当だとしたら、たかが勢力争いで、これほどの損害を許容できる軍隊・国家など世界中のどこにもありませんから。 戦略的な方面ばかりでなく、戦術的、あるいは個人的武勇を見ても、ものすごい合戦だったんですけどね。半藤さんになら紋切り型の説明ではなく、もっと広い側面を描いて欲しかった。(07/6/11) |
| Ver. 2.16 |
|---|
| 管理番号:H031-012 | 53 史書・編年史 | 出版社:筑摩書房 | |||||||
| 書名:昭和史探索 1 | 1926-45 | ISBN978-4-480-42221-8 C0121 | |||||||
| ちくま文庫 は24-3 | 価格:¥760 | ページ数:301P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2006/12/10 | 購入:2006/12/10 | カバーデザイン:神田昇和 | |||||||
 史実をもって語らしめよ、これがこのシリーズのコンセプトです。 史実をもって語らしめよ、これがこのシリーズのコンセプトです。 歴史とは、ヒストリーであり、ともすると物語(ストーリー)となってしまうものです。民族のアイデンティティが揺らぐとき、新たな物語が歴史の衣をまとって「正史」として現れ、唖然とする陰謀史観が歓呼の声で迎え入れられ、世を闊歩するのです。 歴史には事実の裏付けが必要なのに、断片的な史実が新たな解釈のうえで推定の山の中にパズルのピースとしてはめ込まれ、事実として神聖不可侵のものとなる。そしてそれが正義となる。 それが歴史だろうか? どんな歴史書でも、材料として取り上げた史実の組み合わせ、料理のしかたで、新たな解釈が可能です。半藤さんが築こうとしたこのひとつの歴史解釈も、万人の共感を期待できるものではないかも知れない。それでも、ナマの史実の中に「面白い」といって悪ければ「興味深い」物語があるものです。 昭和の前半という歴史の中で、これを味わって見ることもまた一興。 むろん、面白ければね。 昭和とは、むろん大正天皇の崩御のあと、若き皇太子が登極するところから始まります。しかしその即位の前、昭和2年の段階で、日本は暗雲の中を旅していました。 不景気による銀行の経営悪化、金融恐慌、対外融和派の若槻礼次郎内閣のあとの、強硬外交をスローガンにした田中義一内閣の誕生。第一次及び第二次山東出兵。対中国国交悪化。若手陸軍将校たちの台頭。 即位した天皇は矢継ぎ早に勅語を下しました。その中でも注目すべきは、最後の元老となった西園寺公望(1849-1940)に昭和の時代にあっても元老として輔弼せよとの言葉でしょう。かくして天皇は、新しく台頭しつつある民族主義・帝国主義思想を拒否し、融和的路線を選ぶことを内外に示します。この勅語の率直さは、この人ならではの虚飾のない言葉です。 しかし、陸軍軍人出身である田中義一に引きずられた日本は、夜郎自大の権益追求路線を突き進みます。 その先に張作霖事件があります。日本が軍閥である張作霖を援助しつつ操ろうとし、日本の軛を拒否し始めた彼を謀殺して、それをもって中国への武力侵攻を行おうとした事件です。いやしくも、国家の藩屏として国防の任に当たるエリートが考えたにしては、この恐ろしいほどにずさんな作戦は何なのでしょうか。 これが発覚したとき、天皇は断固とした処置を執るように命じ、田中首相は恐懼してこれを約しました。しかし、陸軍内の暴走は止めようにない。進退窮まった田中首相の余りにも拙劣な対応が若き天皇を激怒させました。 このあたりの歴史の、生々しい一次史料は鬼気迫るものがあります。歴史の重みでしょうか。かつての通史とは異なり、天皇は怒りを露わにしたあと、こういったといいます。 「辞表を出してはどうか」 と。 この冷厳な言葉を吐いた天皇が、その後なぜ「若気の至り」と反省し、「沈黙する天皇」であろうとするようになってしまったのか。 この謎の解釈が、この本のひとつの柱になります。 最後に、田中義一が首相になるためにどのくらい財産をつぎ込んだのか、何のためにそうまでして首相の座が欲しかったのか、について。 この本の流れのままであるのなら、功成り名を遂げる、ただそれだけのために、宰相としてのビジョンも哲学もない人間を総理の座に押し上げ、その財産を骨の髄までしゃぶり取った日本の政治とはいったい何だったのか。 暗い時代へ進んでいく日本は、出だしからして暗澹たるものです。 この本は、昭和元年(大正15年)から昭和4年までの時代を描いています。(07/6/14) |
| Ver. 2.17 |
|---|
| 管理番号:H031-013 | 53 史書・編年史 | 出版社:筑摩書房 | |||||||
| 書名:昭和史探索 2 | 1926-45 | ISBN978-4-480-42222-4 C0121 | |||||||
| ちくま文庫 は24-4 | 価格:¥880 | ページ数:447P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2007/1/10 | 購入:2007/6/9 | カバーデザイン:神田昇和 | |||||||
 第2巻は、昭和五年(1930年)-昭和八年(1933年)の歴史です。 第2巻は、昭和五年(1930年)-昭和八年(1933年)の歴史です。この4年間に、激動の萌芽というか、激動それ自体がゆっくりと吹き上がっています。 昭和五年は、世界不況で幕を開け、ロンドン軍縮会議とその結果として一枚岩だった海軍の派閥的な分裂が起きます。そして、誰も知らなかった言葉、「統帥権干犯」という怪物が目覚めます。 統帥権干犯 ─ 軍隊は誰に対して責任を負うのか。国家の国軍の用兵を、国家元首の代行である内閣が管理せずして誰が管理するのか。国家・国民のためにあるべき軍隊が、国家元首直属という美名に隠れて、誰にも責任を負わない軍隊へと変貌する恐ろしい歴史がここにあります。 昭和六年には満州事変が起きます。このきっかけとなる三月事件、事変後の十月事件。どちらも責任を負う者はいない。 満州国建設の理論には、見るべきものがないわけではない。しかし行われたものは、自らの力に酔った暴力組織が、恫喝によって政見もなにもないずさんきわまる国家まがいの砂場を作っただけのこと。後付のきれい事などどうでもいい。組織的収奪がなかったことなどどうでもいい。ここで行われたのは侵略そのものです。 昭和七年、上海事件が起きます。これもまたずさんな謀略でした。日本の俊英の中から選抜された陸軍高級将校たるものが、なぜにこれほど愚かなのか。満州の状況を調査したリットン調査団の報告はこの国家を暴走させます。 この年、満州国は独立を宣言し、5.15事件もこの年に起きます。 昭和八年。「十字架上の日本」という言葉、「さようなら」という挨拶を残し、松岡洋右はジュネーブの国連総会において国際連盟からの脱退を宣言します。心ならずも本国の訓令によってこういう状況に追い込まれた松岡は、忸怩たる思いで帰国を送らせますが、見事なまでに夜郎自大となってしまった日本の朝野は、歓呼して彼を英雄として迎えます。誰がこんな歴史を作ってしまったのか。 この年、ゴー・ストップ事件が起き、皇太子(2007年現在の今上天皇)が誕生します。 内閣の承認なしで、天皇の意志を無視し、陸軍の命令に反して行われた出兵とは何だったのか。それを掣肘できないだけでなく、処罰も出来なかったとはいったい何が悪かったのか。 彼ら陸軍軍人をしてそのような暴走を行わせた原因とは何か。政財界の放埒とはどうだったのか。世界の情勢とは言わないまでも、相手の立場になって考える事がなぜ出来なかったのか。政治が悪かったのか、教育が悪かったのか。 どこで、何が間違えたのか、今さらかも知れないけれど、考えてみることは重要でしょうね。(07/11/4) |
| Ver. 2.19 |
|---|
| 管理番号:H031-014 | 53 史書・編年史 | 出版社:筑摩書房 | |||||||
| 書名:昭和史探索 3 | 1926-45 | ISBN978-4-480-42223-1 C0121 | |||||||
| ちくま文庫 は24-5 | 価格:880Yen | ページ数:406P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2007.2.10 | 購入:2007.7.21 | 表紙イラスト:神田昇和 | |||||||
 第3巻は、昭和九年(1934年)-昭和十一年(1936年)の歴史です。 第3巻は、昭和九年(1934年)-昭和十一年(1936年)の歴史です。3年間の間になにがあったか。三つあります。「陸パン」と「天皇機関説」と「2.26」。 日本が大きくねじ曲がった3年間です。 まずは「陸パン」。ひょうきんな名前ですが、戦慄すべき内容です。 正式には「国防の本義と其(その)強化の提唱」といいます。1934年(昭和9年)10月に陸軍省新聞班が発行したパンフレットです。通称「陸軍パンフレット」。略して「陸パン」。 国体国民を憂えた陸軍将校が、天下国家の視野に立ち、西欧の老獪な帝国主義とアジアの幼稚な民族主義の狭間の中で、国家を醜悪な衆愚政治、拝金主義から理想的な政体へと昇華させるべく書き上げた文章です。その意図はある意味清廉潔白、個人た派閥の利益など考えず、高い理想を胸に抱いています。 国家の総体としての依って立つべきところ、すなわち生存し発展する基礎を戦争におき、それは総力戦であると位置づける。それは第一次大戦でドイツが敗戦した原因を、武力では敗れておらず経済戦及び民衆の厭戦起草によって敗れたと位置づけたところから始まります。 この総力戦の概念において、国家改革を打ち上げる中で陸軍は二つの思想に別れたのでした。合法的な斬新的推進を志す改革派と、非常時にあってクーデターを含む非常な手段をとって急進する改革派のふたつ。 組織・機構の制度改革を重視する前者は「統制派」と呼ばれ、人の刷新で変革が起きると考えた後者は「皇道派」と呼ばれました。 この「統制派」のエースであった永田鉄山陸軍少将を中心にまとめられたのが、この「陸軍パンフレット」です。 「たたかひは創造の父、文化の母である」と説き始めるこの文は、一つの理想を語りつつ、「国防は国家育生発展の基本的活力の作用である」と論を進め、「国民の必勝信念と、国家主義精神との培養のためには、国民生活の安定を図るを要し、就中勤労民の生活保証、農山漁村の救済は最も重要な政策である」と展開します。 あたかも、軍の力を背景とした国家の番犬であるべき彼らが、自らを寄生虫ではなく知の巨人であるかのごとくに説くのです。 「天皇機関説」 これも説明はややこしい。東大教授である美濃部達吉博士の憲法学説を、国体を破壊する危険思想であると断じたことから始まると見なされがちですが、実は奥が深い。 詳しい説明は割愛しますが、美濃部博士の説くところが天皇の地位を掣肘するものなどではなく、日本という国家を西欧あるいはアジアと比較するならある種独特の、天皇を頂点とする極めて特殊な政体である、という一つの説明に過ぎません。これをして、天皇個人にいかなる権限があるのか、天皇という国家機関の最高権威にいかなる権限があるのか論ずるのは、ある意味象牙の中の論争に過ぎない。 これが、「機関」という特殊な法律用語が、「マシーン」というような卑近な言葉だと誤解あるいは曲解されたことにより、美濃部博士はいかな正論も受け付けられずに指弾されて断罪され、日本という国家は、天皇という地位どころかその言葉すらはばかるような悲惨な疑似宗教的狂熱に犯されていったのでした。 誰がこの責を負うべきか。 そして、「2.26事件」。 鐵太郎の母が子供のころ、この事件に遭遇しています。庶民にとっては恐ろしい騒乱であり、戦争へとつながる陰惨な時代の、目に見える入り口となりました。 いわゆる青年将校が何を目指したのか、それをいわゆる「皇道派」上級士官たちがどう利用しようとしていたのか、誰がこれに利用されたのか、誰がこれを利用して自らの権力の伸張を図ったのか。 昭和帝の怒り。有名な言葉。「朕ガ股肱ノ老臣ヲ殺戮ス、此ノ如キ凶暴ノ将校等、其精神ニ於テモ何ノ恕スベキモノアリヤ」 真崎甚三郎大将の鬱勃たる手記は、鬼気迫るものがあります。なぜこの私が糾弾されねばならないのか、という。 下達されぬ命令に対し、なぜ抗命したと言われるのか、という青年将校の怒りもある。 徴兵された兵としてこの反乱軍に参加した小林盛夫二等兵、のちの五代目柳家小さんの手記など、実にヴィヴィッドです。 刑期を終え、汚名を着せられたまま生き恥をさらした青年将校が、事件後50年たって呻きます。 つまり陛下が2.26事件を失敗に追いこんだということです。私は、いまでも天覧相撲にお見えになると、ああ、この方がわれわれの事件を潰したんだなぁ、と思いますよ。(笑) パチパチと手など叩いておられるけれども。 この事件についていろいろ読んだので、ある程度わかっていたつもりでした。しかし、こんな見方もあるのか。 2.26事件を起こした将校たちは、その精神に於いて真剣だが全く間違っており、彼らの暴発が日本を戦争に引きずり込んだ、という考え方は、まあ一般的な見方でしょうが、そのまま単純に信じてはいけないのかも知れない。 歴史は、見直してつらいところも多いけど、面白い。(08/3/22) |
| Ver. 2.21 |
|---|
| 管理番号:H031-015 | 53 史書・編年史 | 出版社:筑摩書房 | |||||||
| 書名:昭和史探索 4 | 1926-45 | ISBN978-4-480-42224-8 C0121 | |||||||
| ちくま文庫 は24-6 | 価格:900Yen | ページ数:495P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2007/3/10 | 購入:2008/3/26 | 表紙イラスト:神田昇和 | |||||||
 第4巻は、昭和十二年(1937年)-昭和十四年(1939年)の歴史です。 第4巻は、昭和十二年(1937年)-昭和十四年(1939年)の歴史です。出だしは、12年の1月21日。国会本会議場に、「がさつ」きわまりない騒動がおきます。 「軍民一致」という陸軍大臣寺内寿一の連呼に、国会議員浜田国松が噛み付いたのでした。国民と軍とは別々なものではないはずだ、と。これを軍人への侮辱と一蹴しようとした寺内に、有名な反撃が。 「速記録を調べて僕が軍隊を侮辱した言葉があったら、割腹して君に謝する。なかったら君割腹せよ」 当時、敬意より畏怖、畏怖より恐怖の対象として捉えられていた「軍」に対する、政党政治家の渾身の抵抗だったのですが、この喧嘩は高くつきました。怒り狂う寺内陸相は閣議で議会の解散を主張しますが、閣僚のの猛反対をくらい、ついに辞表を叩き付ける。当時の内閣では、陸海軍相は陸海軍の推薦がなければ立てることはできず、陸軍はこれを拒否したのでした。広田弘毅は内閣総辞職に追いこまれます。 後継首相に押された宇垣一成陸軍大臣は、かつて行った軍縮の恨みを買い、陸軍の猛反対を受けて流産。 林銑十郎陸軍大将が後継首班になったものの世情はよろしくない。その次に、国民の期待を一心に受けて昭和12(1937年)6月4日に首相の座に着いたのが登場したのが公爵・近衛文麿でした。 昭和12年というと、11月4日に呉の海軍工廠で、軍艦大和の起工式が行われています。戦争の時代にいよいよ突入していったのでした。国家予算30億4千万円の時代に、陸軍予算が7億2千万、海軍予算6億8千万。軍だけで総予算の46%を占める財政がまともと言えるのか。 またこの年の12月13日より、支那事変と称して中国に攻め入った日本軍は、南京攻略ののちに市内で略奪行為に走り、のちに南京大虐殺とされた事件を起こしています。はたしてこの規模はどの程度だったのか、今もなお論争の決着がついていません。30万人という数字が噴飯ものだとしても、何らかの事件があったのは事実。 正しい数字が大事なのか、悲劇をただ何も言わず償うのが正しいのか。過去は大事にするが常に未来だけをみる民族と、親の国であることを常に意識させたい、過去を忘れない民族と。これが問題をさらに大きくしました。 悪名高い「大本営」が宮中にできたのは、昭和12年11月20日であるとか。 昭和13年は1月16日の、日中間を泥沼に落とし込んだ、連戦連勝にのぼせ上がった近衛首相の「国民政府を相手にせず」声明で明けます。 ここでは悪名高き「慰安婦」についても語られます。性・売春婦の問題は、あの時代の事を現代の倫理観で裁くのは無意味。また、ほかに生きるすべのなかった人々を、その行為によって責め、罪とするのはおかしい。現実に最前線にまで「従軍」した慰安婦を、単純に非道な軍によって強制されたとだけ言ってしまっては、単純すぎるのではないか。 どこまで続く泥濘(ぬかるみ)よ と歌に歌われたごとく、日中戦争は泥沼に入り込みます。なんのための戦争なのか。誰のための戦争なのか。何を目的とした戦争なのか。 7月6日、国境線のわずかな小競り合いで始まった日ソ間の争いを、参謀本部の制止にも、朝鮮軍司令官の静観命令にもかかわらず、現地の第19師団は独断で夜襲攻撃をかけ、ソ連の反撃に大打撃を受ける。これではならじとさらに後方部隊を動員する。張鼓峰事件です。 「今後は朕の命令なくして一兵だに動かすことはならん」と怒号する烈々たる昭和帝の言葉も空しい。 12月23日、近衛首相は談話の形式で東亜の未来を説きます。 「日満支三国は、東亜新秩序の建設を、共同の目的として結合し、相互に善隣友好、共同防衛、経済提携の実をあげんとするものである」 これが、英米の決定的な不審を買いました。当時の日本は、これがいかに夜郎自大な、主観だけで作られた構想であったことに気づかなかったのでしょうか。日本は外交下手です。当時も今も、ね。 のちに出征兵士のテーマ、玉砕のテーマとなってしまった名曲「海ゆかば」も、この時期に世に出ました。 昭和14年5月、満州国とモンゴル人民共和国の間の国境ラインで、そもそも草原地帯であるために曖昧なままで放置されていたその地帯に、日ソ両軍の戦車部隊が激突します。ノモンハン事件です。この戦いについてはたくさんの書物が書かれましたので、詳細はどうでもよろしいでしょう。日本陸軍がその自信の鼻をへし折られた事件と言えばいいか。 確かに数字に表れる被害で言えば、ソ連の方が日本を上回っています。しかしソ連の精緻窮まる砲撃と戦車による物量作戦に、日本陸軍がなすすべもなく戦略目標を落とせなかったことは事実。いや、そもそも戦略目標などあったのか。 この年の始めに近衛内閣はその場当たり的、無責任な施政に終止符を打って退陣し、平沼騏一が後を継ぎます。平沼内閣は、内では国内の統制を強化し、外では日中問題の終息を計りますがはかばかしくなく、またヨーロッパの情勢も見誤り、ナチス・ドいつが8月23日に独ソ相互不可侵条約を締結したことで衝撃を受け、8月28日に「欧州の天地は複雑怪奇」という珍声明を発して総辞職します。 またこの年の12月26日、朝鮮併合(明治43年8月)に伴う施策として、「朝鮮戸籍令改正」が公布され、今に至る韓国の反日感情の温床となっています。いわゆる「創氏改名」。これに関してはいろいろ意見もあります。半藤さんは批判的。 日本の戸籍制度に合うような姓を持てという命令は、朝鮮の文化を否定するものであることは事実かも知れません。 しかし鐵太郎は思う。 仮に、朝鮮併合が半永久的に継続したとしたら、もしも朝鮮がたとえば北海道のように日本の一つの地方となったのだとしたら、そこだけ特殊な戸籍制度であれば換えって統一感を阻害したのではないだろうか。 みんなが日本人なんだよ、日本式の名前を持とうよ、日本式の制度で生きようよ、という考え自体は、決して間違ってはいなかったと思う。 しかし、日本人は外の人とのつきあい方がヘタだった。他民族を同化した経験が不足していた。 そして朝鮮は、ウリ(自分と自分の仲間)とナム(それ以外の他人・敵)との区分けが、日本以上に激しい民族だった。 お互いに相手を理解せず、相手が自分の真心を理解しないことが許せなかった。これは、悲劇なのか、喜劇なのか。 次は、世界戦争へ転げ落ちる日本の時代です。(08/9/28) |
| Ver. 2.21 |
|---|
| 管理番号:H031-016 | 53 史書・編年史 | 出版社:筑摩書房 | |||||||
| 書名:昭和史探索 5 | 1926-45 | ISBN978-4-480-42225-5 C0121 | |||||||
| ちくま文庫 は24-7 | 価格:880Yen | ページ数:437P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2007/4/10 | 購入:2008/4/9 | 表紙イラスト:神田昇和 | |||||||
 第5巻は、昭和十五年(1940年)~昭和十六年(1941年)ですね。 第5巻は、昭和十五年(1940年)~昭和十六年(1941年)ですね。この巻では、国家の元首たるべき昭和帝の言葉は、時代を動かしません。もはや天皇の言葉も判断も、時代の中で軽くなってしまったらしい。 1940年・昭和15年。 2.26事件から4年、この間に首相は広田弘毅、林鉄十郎、近衛文麿、平沼騏一郎、阿部信行と変わり、昭和15年1月16日に米内光政が内閣を組織します。短命という一言だけでは形容しきれない。しかも7月22日には、再び近衛文麿に大命は降下するのでした。 ヨーロッパで始まった戦乱とドイツ軍の怒濤の快進撃に幻惑され、「バスに乗り遅れるな」が合い言葉となった時代です。 泥沼の出口が見えない支那事変の中、政治は政党の軍部を片眼に見るへっぴり腰の中で、昭和15年2月2日、気骨ある最後の政治家の議会演説が、憲政史上の最後の光になります。 「ただいたずらに聖戦の美名にかくれて、国民的犠牲を閑却し、いわく国際正義、いわく道議外交、いわく共存共栄、いわく世界の平和、かくのごとき雲をつかむような文字を文字を並べ立て・・・・」 この演説を行った斎藤隆夫議員は、3月7日に議会から除名されました。 3月25日、政党人100余人が結集して「聖戦貫徹議員連盟」を立ち上げ、全政党を解散して強力な新党を結成しようと宣言します。神輿に担ぎ上げたのは、担がれるといい気になる近衛文麿。さっそく枢密院議長を辞して「大政翼賛会」の首領となります。 この年は、日本の紀元でいうと、神武天皇の即位から数えて2600年目、つまり皇紀2600年でした。大祝典が行われたそうです。 零戦、つまり日本海軍の零式艦上戦闘機が正式採用されたのはこの年でした。 ♪金鵄輝く日本の 栄えある光身に受けて 今こそ祝えこの朝(あした) 紀元は二千六百年 という歌を、歌が好きだった父はさかんに歌っていましたっけ。 これをフトドキな子どもたちは、こんな替え歌にして怒られたらしい。 ♪金鵄上がって十五銭 栄えある光三十銭 鵬翼高い五十銭 紀元は二千六百年 全部、タバコの銘柄です。 1941年・昭和16年。 悪名高い「戦陣訓」は、この1月に当時の陸軍大臣・東條英機によって作られました。これには、こういう理由がありました。 昭和12年から続く支那事変で、軍規・風紀が乱れ、「非違犯行」、各種犯罪事件が多発したのだそうです。これを取り締まると共に、下士官兵に対して戒めになる文章を作る必要があった。しかし、もともと「軍人勅諭」というものがあり、それを守っているはずなのだから、このような事態は起きていないはず。もっと細かいわかりやすい戒めを作った方が良いのではないのか。 という訳で、学界の有識者まで集めていろいろと考えて作った戒めが、これ、「戦陣訓」だったのでした。その中の一文、
松岡洋右が再び登場します。この人はどういう人間だったのか。 ドイツと組んで日本の勢力を展開する、という。日独伊三国同盟によってアメリカを牽制するという。 3月に単身ドイツに乗り込み、リッベントロップやヒトラーその人と渡り合い、日本外交をまとめる。ナチス首脳部の反対を振り切って4月にソ連に向かい、スターリンと直談判して日ソ中立同盟を締結する。 得意満面での帰国。しかし、本国の指令は全く無視し、交渉状況も全く報告しないまま。 結果オーライで成果を上げればそれで良し、という風潮なのでしょうか。 前例のない、帰りの汽車のホームにまで見送りに来てがっきと抱きしめたスターリンに驚く一同。感激して舞い上がらんばかりの松岡。 しかし、この裏でナチスは独ソ線の準備を固め、1941年6月22日にソ連に、300万人のドイツ兵がなだれ込みます。 夜郎自大の外交には、誰が責任を取るべきなのでしょうか。 もうひとつ、書いておくべき事があります。 ハル・ノートに至る日米交渉の中で、ただ一回だけ、日米が妥協できるシチュエーションがあったのだそうです。 両国が納得できる妥協案にまとまりかけたときがあったそうなのです。詳細は、省きます。 これを崩したのは、外相松岡洋右の帰国でした。勝手に外遊先で交渉を次々進める外相の留守時にようやくまとまった交渉結果に、自信のかたまりと化した松岡外相はいたくプライドを傷つけられ、鼻も引っかけずにひっくり返したのだそうな。 そして根拠もない暴論と共に強硬姿勢で交渉を再開し、しかもその外交交渉はすべてアメリカ側に解読されている。 転落以外にどうにもならない歴史となった。
大東亜戦争、戦後の呼称で太平洋戦争の開幕です。(08/11/1) |
|||||||||||
| Ver. 2.22 |
|---|
| 管理番号:H031-017 | 53 史書・編年史 | 出版社:筑摩書房 | |||||||
| 書名:昭和史探索 6 | 1926-45 | ISBN978-4-480-42327-6 C0121 | |||||||
| ちくま文庫 は24-7 | 価格:950Yen | ページ数:617P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2007/5/10 | 購入:2008/5/21 | 表紙イラスト:神田昇和 | |||||||
 第6巻は、昭和十七年(1942年)~昭和二十年(1945年)です。あの戦争と、その終幕のとき。 第6巻は、昭和十七年(1942年)~昭和二十年(1945年)です。あの戦争と、その終幕のとき。この巻では、前巻とは逆に、昭和天皇が国家元首としての存在感をついに示します。緊急事態の最後の支えがあると安心するものですが、その支えが本当に機能したことがあるのだと思うと、心が少し温かくなります。 大日本帝国は、対英米開戦に際して、戦争終結の構想をこう描いていたと言います。
太平洋戦争の戦争を追っていけばきりがない、として作者は、できるだけ代表的な記録のみを追っています。しかしそうは言っても、政治や生活文化でなく、戦争の記録に終始したのは、こりゃあ作者の方針なのか限界なのか。(笑) 1942年・昭和17年。 緒戦の大勝利で有頂天になった日本ではありますが、結果として日本がこの戦いで講和を得るのなら、この年の春しかなかったかもしれません。しかし、それが許される時代ではありませんでした。この戦争で、おそらく最も唾棄すべき醜態をさらした牟田口廉也(むたぐち・れんや)陸軍中将(1888~1966年)の景気のいい手記と、良識ある軍人として日本のみならず欧米にも名高い今村均(いまむら・ひとし)陸軍大将(1886~1968)の回想の併記が面白い。 また、東條首相の議会演説もあります。今の視点で見るからわかるのですが、景気のいい空論ですな。 この年の6月、運命のミッドウェイ海戦が発生します。 ここで、日米はある意味でイーブンの立場になったのです。勝ちまくっていた日本軍が急停止した状態。 この時もしも日本の政治が、戦略が、戦術が上手くかみ合い、国家が一つにまとまって戦争を行ったとすればどうなったか。その帰趨は今もわかりません。しかしすくなくとも、あんな無様な戦争をすることはなかったはず。陸軍がどうの、海軍がどうのと言う問題ではない。 1943年・昭和18年。 南洋のはるか彼方、ソロモン諸島のガダルカナル島に取り残された日本軍の救出作戦が、この年2月最初に行われ、1万人以上の将兵が救出されます。しかし投入された人員は約3万人であり、戦闘で死んだ兵は5千程度。残りは餓死と、友軍による「始末」でした。悲惨といわずしてなんといえばいいのか。 しかし、事ここに至っても、日本は真の意味での戦争に対する「総動員体制」はできていなかったのです。自由の国アメリカはすでに、徴兵制から始まり、非戦闘員の軍需教育、統制経済体制の策定、通信・交通・輸送システムの戦時体制推進、国民への戦争教育などを次から次へと進めていたにもかかわらず。 召集令状の発送にかかわった陸軍士官の手記(P193)に見る、公平無私であるべき兵役への召集の際の「地獄の沙汰も金次第」の実体には、唖然とするしかない。 1944年・昭和19年。 この年の1月、無謀とか悲惨とか形容されるインパール作戦、正式名称「ウ号作戦」を、大本営陸軍部は認可します。作戦は3月より始まり6月に終了しますが、この戦いは、驚くべき杜撰さ、いい加減さ、その指揮官牟田口廉也の無能・無責任・無思慮で有名です。 首相・陸相・軍需相を兼ねる東條英機が、総参謀長までも兼任して「東條幕府」とまで言われるほどに権力を集めたのは2月です。本人はいたって真面目な官僚軍人だったと言われますが、軍政家として政治家としての無定見・無能がどうにもならず、サイパンの玉砕のあと、グアム、テニアンまで墜ちて、7月18日についに退陣せざるを得なくなります。 この後任首相の決め方が、おやおや。 「小磯という人は知らないが、米内、平沼両君が褒めるなら結構だろう」(P351)という重臣の言葉は、なんともはや、です。 特攻、生還を期さない自殺攻撃が始めて実戦投入されたのは、レイテ海戦の時でした。日本側呼称で「捷一号作戦」のときです。 特攻を始めて指揮官として考案し、命令を下したのは大西中将と言われ、彼は「特攻の父」と呼ばれます。しかし彼の思惑が、実際には巷間伝わるものとはこれほどずれていたとは知らなかった。新しい話が読めました。 また、特攻隊の最初の指揮官は関行男海軍大尉でしたが、彼が兵学校士官であったことが今まであえてそのために選ばれた、とされていましたが、吉岡忠一氏(終戦時中佐・ルソン島で捕虜となる)はこう飛行機乗りの気質を書いています。
またこのときに「神風(しんぷう)隊」という名が決まったと言うのが通説なのですが、これももっと前に決まっていたという。歴史って不思議。 この年9月より、本土も爆撃に包まれる中で、陸軍は政府にも海軍にも知らせず、本土決戦に備えて長野県の松代に大本営を移すことを考え、巨大トンネルを造り始めたそうな。これは翌20年春には一般にも知られるようになったそうですが、これを聞いた昭和帝は日本の先頭に立って戦う最高司令官の顔で不快げに言われたそうな。
1945年・昭和20年。 フィリピンが墜ち、硫黄島が墜ち、沖縄が戦場になり、主要都市すべてに絨毯爆撃が行われます。ついに3月10日に帝都が大空襲で壊滅するに至り、小磯内閣は万策尽きて退陣するしかなくなる。 老齢ゆえにと辞退する78歳の鈴木貫太郎元海軍大将に対して、天皇が言う。
ソ連を仲介とする、という後世の視点で見れば脳天気窮まる外交交渉が頓挫し、広島、長崎に原爆が落ち、それでも一億特攻という夢想を叫ぶ軍部に対し、御前会議における天皇の聖断を仰ぐという、憲政史上あってはならない奥の手を使った鈴木貫太郎首相。それに答えた昭和天皇。 歴史はこうして次の曲がり角を曲がりました。 こののち、さまざまなことがおきます。降伏という言葉が恥であると、なんとかして言葉尻を捕まえてごまかそうとした部隊。降伏文書に誰を出すべきかでもめた内幕。木と紙でできた日本家屋を焼夷弾で焼き尽くし、民間人を殺戮したアメリカ第20空軍司令官ルメイ少将に、戦後勲章を贈った日本政府。 「もし平和が戦争の経験のあとにしか来ないならば、平和は常にあまりに来かたが遅すぎる。平和は常に死者の上に築かれるのか」 あとがきにある、フランスの哲学者アランの言葉だとか。 かくして戦争は終わったのですが、その結果どんな日本ができたのか。その日本はこれからどこに進むのか。 大きく変わったと皆信じるようですが、日本人の本質は昔の愚行を繰り返すことが意外に多いのです。過去を見直すことは、たしかに未来のためになると思います。嫌な歴史だけど、避けて通るわけにはいきませんよね。(09/1/23) |
|||||||||||||
| Ver. 2.23 |
|---|
| 管理番号:H031-018 | 54 歴史点描 |
出版社:筑摩書房 | |||||||
| 書名:それからの海舟 | ISBN978-4-480-42443-3 C0121 | ||||||||
| ちくま文庫 は24-11 | 価格:780Yen | ページ数:375P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2008/6/10 第12刷:10/1/25 | 購入:2010/3/4 | 表紙イラスト:菊池信義 | |||||||
 作者の半藤一利氏は、東京府東京市向島区(現在の東京都墨田区)の生まれですが、祖先は長岡藩士だったそうな。また戦時中に疎開した新潟県で、そのまま県立長岡高校(地元では有名校ですぜ)にも進み、幕末の歴史の中で「賊軍」扱いされた徳川家と長岡藩の中で育ちます。そのせいか、薩長軍は「官軍」などではなく「西軍」であり、たまたま弾戦争に勝った暴力組織以外の何ものでもない、という考えなのだそうな。 作者の半藤一利氏は、東京府東京市向島区(現在の東京都墨田区)の生まれですが、祖先は長岡藩士だったそうな。また戦時中に疎開した新潟県で、そのまま県立長岡高校(地元では有名校ですぜ)にも進み、幕末の歴史の中で「賊軍」扱いされた徳川家と長岡藩の中で育ちます。そのせいか、薩長軍は「官軍」などではなく「西軍」であり、たまたま弾戦争に勝った暴力組織以外の何ものでもない、という考えなのだそうな。
そのなかでも、江戸っ子の勝海舟、半藤さんの言う勝っつぁんは大ファンなのだそうな。 で、書かれたのがこの本。 「それから」というのは、江戸開城の談判、勝海舟一世一代の名場面以後の生涯です。これを、「歴史探偵」(自称)の視点で描いたものなのですが、堂々と宣言するように海舟びいきの姿勢ですので、まともな歴史解釈とすると割り引く必要はありそうですな。 普通こういう本は、作家としての基調がどうあれ、公平な視点で描くというのがルールなのだそうですが、はなっから勝っつぁんびいきであるといわれれば苦笑いするしかありませんな。ある意味、公平を装って自分の田んぼだけに水を流し込む文章より潔くていいですよね。  日本語で外国語に翻訳しにくい言葉として、大宅壮一さんによると、いっそとどうせとせめてがあるのだそうな。日本人独特な感性だそうです。第二次大戦の時、幕末の時、 「どうせじり貧ならば、せめて死中に活を求めて、いっそのこと一花咲かしてみようじゃないか」 と、現状を直視しない無責任な連中が国を滅ぼしかけたもの。「氷川清話」の一文にあるように、勝海舟は鈴木貫太郎と同じようにボロ船を指揮させられて、いっそともどうせともせめてとも言わず、リアリズムに徹しきって船をこぎ続けたそうな。歴史の中で、彼らの扱いは大きくありません。その前の為政者たちの華々しい失敗と、そのあとの華々しい後継者のみがクローズアップされるものです。 そんなこんな時代の舵取りを取り上げないでどうする、といわんばかりの作者の筆さばきが、読んでいて痛快ですね。 無駄話めいた話として、 芝居や映画に出てくる、「からうしの毛」のものです。西軍の指揮官がかぶる帽子です。 これは、薩摩は黒、長州は白、土佐は赤と決まっているのだそうな。これをごちゃ混ぜにする阿呆な演出家がいる、とのこと。 また、これは「宮さん宮さん」を歌いながら江戸に進軍するときにもかぶっている映画がありますが、これも真っ赤な嘘だそうな。 これはそもそも、西軍が江戸城を占領したあと、倉庫にあったこの毛を総督府が使ってかぶり物を作ったのだそうです。   さらに遡ると、これはかつて さらに遡ると、これはかつて『徳川に 過ぎたるものが二つあり 唐のかしらに本多平八』 と謳われた、徳川四天王の一人本多平八郎忠勝(←左絵)の兜飾りの「からうし」の毛を、徳川武士たちが彼の武勇にあやかろうとして、我も我もと真似ようとしたために江戸城にたくさん貯えられていたそうです。 それを田舎者の西軍どもが分捕って、自分を飾るのに使ったのだそうな。 そう、まるでイギリス陸軍が、モスクワからナポレオンが分捕ってきた毛皮の帽子をワーテルローで分捕ったようなものらしい。(右写真→) なるほど、歴史って面白い。
江戸開城のあと、振り上げたこぶしのやり場に困った薩長の軍勢をなんとかなだめようという努力が潰え、それでも少しでも平和を保とうと奮闘する勝海舟。ある見方でいうのならば、節操のない変節漢そのものです。幕臣でありながら徳川の看板を利用したり、西郷隆盛とのコネを利用したりして戦争を回避しようとする。このコネを使って自分の手の者をうまく栄達させる。自分は責任を取って蟄居する訳でもなく、ちゃっかり旧幕臣や徳川家と新政府の仲介役になる。あっさりと政治から身を引き、ご意見番気取りにいいたい放題の放言をのこす。 これを、勝っつぁんの立場に立ってみたらどうなるのか。 福沢諭吉は、勝海舟が大嫌いだったらしい。 清廉で真面目で、主義主張がしっかりとしていて、前向きで上を向いた生き方を愛した福沢にとって、江戸っ子的でいいかげんで、折衷的でその場限りに見える勝海舟の生き方、処世術は許せなかったのかもしれない。 福沢の血が噴き出るような詰問の問いに対し、勝海舟はあっさりとこう答えています。
半藤さんは、これを「あひるの水かき」と呼びます。水の中で一生懸命水をかいていても、表から見えるのは優雅な水鳥の動きだけ。 この本はその視点に立って、勝海舟の「それから」の姿を描いていきます。 一方的な歴史観もしれないけど、こんな歴史解釈もあるんだよね、と楽しめる本です。(10/3/11) |
||||||||||||
 |
Ver. 3.01 |
|---|
| 管理番号:H031-019 | 54 歴史点描 | 出版社:PHP研究所 | |||||||
| 書名:歴史探偵 近代史をゆく | ISBN978-4-569-67948-8 C0130 | ||||||||
| PHP文庫 は9-16 | 価格:571Yen | ページ数:272P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2013/3/18 | 購入:2013/8/28 | 装丁:上田晃郷 | |||||||
 この小論集は、1993年6月より95年6月までの2年間、月刊誌「KORON(公論)」に「歴史探偵 日本近代史をゆく」のタイトルで連載した全35話から25話を選び、編集し直したものだそうです。 この小論集は、1993年6月より95年6月までの2年間、月刊誌「KORON(公論)」に「歴史探偵 日本近代史をゆく」のタイトルで連載した全35話から25話を選び、編集し直したものだそうです。明治40年の、日露戦争直後に起きた第6号潜水艇の悲劇と、この事件と夏目漱石の関わりから始まります。その次は、日本海軍の名参謀と称えられた秋山真之の手紙から見るその才と、203高地をめぐる戦いにおける彼の役割と結果。後者に関しては、結果論と無い物ねだりではないか、と鐵太郎は思うのだけれど。 昭和16年の開戦直前、重臣・若槻礼次郎が開戦を主張する東條英機首相の
最後の陸軍大臣・下村定(しもむら・さだむ)大将の、昭和20年11月28日の衆議院本会議における答弁、
それから。 軍への〝赤紙〟(召集令状)ならぬ〝白ガミ〟(徴用令状)を受けて外地に送られた作家たちのこと。 「国民政府を対手とせず」と強硬かつ無責任な態度で国政を破綻させた近衛文麿。 「秩父宮殿下を説得し、軍を屈服させてみせる」と言い切った石原莞爾の真意。 パネー号事件に際し、その危機的状況を察知して、迅速・的確かつ真摯な謝罪を行った駐米大使・斉藤博。 阿部定事件の裏の裏。 原爆の使用について、最初から 「目標は一貫して日本なのである」という話。 マッカーサーの、日本軍の進駐直後の東京見物。 歴史の1コマ1コマを、うまく切り取って味付けしています。こんな歴史ちょっと見も、面白いね。(2013/12/9) |
||||||||||||
 |
Ver. 3.01 |
|---|
| 管理番号:H031-020 | 53 史書・編年史 |
出版社:平凡社 | |||||||
| 書名:日露戦争史1 | ISBN978-4-582-45443-7 C0021 | ||||||||
| 価格:1600Yen | ページ数:392P | 本のサイズ:135×195HC | |||||||
| 初版発行:2012/6/20 | 購入:2013/11/21 | 装幀:菊地信義 | |||||||
 プロローグは、明治三十七年二月四日 と題して日露戦争前夜の様子。 プロローグは、明治三十七年二月四日 と題して日露戦争前夜の様子。
この第一巻は、さらに数年時代をさかのぼった明治34年、すなわち二十世紀が始まった西暦1901年の1月22日、英国の黄金時代を具現するヴィクトリア女王が世を去った時から語り起こされます。そしてさまざまな歴史の様相を並べたあと、開戦、そして劈頭の聯合艦隊による旅順港奇襲攻撃と、第一軍による鴨緑江突破まで。 この間に、さまざまな事がありました。 ロシアとの交渉をついにあきらめるまで、政府として国家の経営を主導してきた人々は、いったい何をしたのか。 新聞を主とするマスコミは、この事態をどう報道したのか。 日本の国民は、この情勢をどう受け止め、何を望んだのか。 ロシアの皇帝、政府、人民は、この情勢をどう捉えていたのか。 世界は、何を考えていたのか。 そして、この歴史をちがう方向に流すことが出来たかもしれない分岐点は、いったいどこにあったのか。 歴史探偵を自認する半藤さんの視点による、いまの、平成の視点で見た、歴史の掘り起こしです。 これは、華々しいものではありません。しかし、恥じる事もない、百年前の日本人の苦闘です。 明治のあの時代、日本は日清戦争に勝ったとは言えいまだ二流どころか、まだ三流国家でしかなかった。国防のために、すさまじい金額を国家予算から捻出しなければならないと考える、弱小国家でした。
この時ロンドンでは、のちの文豪・漱石となる夏目金之助がこの風潮に冷ややかな感想を漏らしていたとか。 そして当時、こんな貨幣価値だったのだそうな。
これによって計算しますと、漱石の二番目の下宿ハムズテッドの下宿代は、朝夕の食事付きで週二ポンドつまり月八ポンド、すなわち週4万円で月16万円! 留学費が月に約30万円のなかからそれだけ、というと、かなりリアルにきつい。 そして、当時の一円とは、シリング換算から回り込むと現代の2300円くらいに相当すると言う事になります。漱石の自宅には、国家から二十五円、すなわち5.7万円が支給され、その一割が軍艦建造費として差し引かれていたらしい。この換算、本当かな? 1884年から1890年のいつか(諸説あり)起きたとされる「ぶな屋敷(The Adventure of the Copper Beeches)」という作品の中で、教養ある婦人が家庭教師をする場合の給料として月に4ポンドなのだそうな。これが相場らしい。ところが彼女に最終的に年120ポンドの給料を払うという依頼主が現れ、その高額な提示に驚いた娘が、ほかの不審な点もあってホームズに相談に来ます。 漱石が留学生として支給された月15ポンドは、留学生としてはまあまあ妥当なのかな。 ロシア宮廷の勢力図と全能のロシア皇帝についての寸評。
蛮国に対する強い軍事国家の姿勢のままに押してくる(としか見えない)大国ロシアに対して、
彼らは皆、若い頃維新の戦いをくぐり抜け、生き延びた戦士だった。戦いというものがやってみないとわからない博打だと知っていた。 そしてその上で、一朝事あらば身命を賭して戦う覚悟があった。 この覚悟の上にたち、責任を持って国家を統制し、掌握したその手を、緩めるつもりはなかった。 ここが、昭和の政治家と決定的に異なっていたところ。 帝大七博士として有名な七人の高名な東京帝国大学の博士たちは、この政府首脳の苦悩も知らず、我らこそ国政と軍事の最高の有識者とばかり対露強硬論を政府に強要します。体よく元老にあしらわれても、なお声高に主張を叫ぶ。 そして、マスコミがこれに乗る。
しかしそのエリートたちでさえ、戦争を避ける道をどこかであきらめた節があるのです。そこが、歴史の皮肉なところ。 しかしこの中で、おそらく大物としては唯一戦争に心底から反対の姿勢を示していた人物がいた。 これは明治天皇の言葉を、侍従長徳大寺実則(とくだいじ・さねつゆ)が寺内陸軍大臣に告げたもの。明治36(1903)年10月12日。
しかしこの時点で、ロシアの対日外交は、恫喝と言うより意識的とさえ思えるほど、超スローモーでしかも高圧的。あきらかに、日本を軽蔑し、挑発している、としか思えない。その陰で、この無気味な帝国は何を画策しているのか。もはや、立つしかない。 日本政府は、この時もう不退転の決意で戦争準備に入っていたのでした。あとは、大義名分とタイミングの問題。 そこで邪魔になるのが、無責任に血気にはやる国民と、それに煽られて煽り立てるマスコミ。 先鋭的な主張を繰り返す外務省政務局長・山座円次郎が、外務大臣・小村寿太郎にその弱腰を責めると、小村は平然と返す。
かくして、戦端は開かれる。明治37(1904)年2月6日、栗野駐露公使がロシア帝国ラムズドルフ外相に、小村外相がロシア公使ローゼンに国交断絶の最後通牒を手渡し、2月8日仁川沖で日本帝国海軍第二艦隊第四戦隊はロシア海軍装甲巡洋艦ワリャーグを沈め、戦争が始まります。 この巻は、日本海軍による旅順包囲戦から有名な閉塞作戦、ロシア海軍名将マカロフ提督の戦死、黒木陸軍大将麾下の第一軍の快進撃、そして奥保鞏(おく・やすかた)大将麾下の第二軍が上陸するまで。 ここまでは、多少のミスもあるけれど、ほぼ日本側の予定通り。さて、この先は。(2014/3/6) |
|||||||||||||||||
 |
Ver. 3.01 |
|---|
| 管理番号:H031-021 | 54 歴史点描 | 出版社:文藝春秋社 | |||||||
| 書名:歴史のくずかご | とっておき百話 | ISBN978-4-16-790172-1 C0195 | |||||||
| 文春文庫 は8-25 | 価格:540Yen | ページ数:240P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2014/8/10 | 購入:20134/10/1 | カバー画と題字:半藤一利 デザイン:加藤愛子(オフィスキントン) |
|||||||
 歴史探偵を標榜する半藤さんが、1999年4月から文藝春秋の営業部が書店や取次会社に配布する「新刊のお知らせ」に、歴史ネタのコラムを書いていました、そうです。それが2014年3月で180回にもなったのだそうな。 歴史探偵を標榜する半藤さんが、1999年4月から文藝春秋の営業部が書店や取次会社に配布する「新刊のお知らせ」に、歴史ネタのコラムを書いていました、そうです。それが2014年3月で180回にもなったのだそうな。そこでこれをまとめてみようと思ったのだそうな。文庫本で。 そのままではうまくおさまらないので、文庫の見開きにページにおさまるように、オリジナルの一話900児を1189字に増やし、180話の中から100話を選び出して十二ヶ月それぞれに分け、読みやすくまとめました。 これが、その本。 最初の一編は、初富士のこと と題して、富士山にまつわる話。そして新年の話。こんな風に始まります。 7話の 新イロハ歌の傑作 に面白い話。 イロハ歌とは、四十七文字を一字ずつしかもすべて使って作った歌。昭和27年に、これに張り合おうという人がでてきたらしい。 乙女花つむ野辺みえて われ待ちゐたる夕風よ うぐひす来けん大空に 音色もやさし声ありぬ ちょっと色っぽく お江戸街唄風そよろ 青柳けぶりほんに澄む 三味の音締め燕も 恋ゆゑ濡れてゐるわいな なんてのが出来たのだそうな。ほう。 夏の鯉のぼりの話では、かつて関ヶ原の東は腹が黄色で西は白だった、大日本帝国時代には「コイにはクローが先に立つ」ことからクロつまり真鯉が上になっていたとか。 秋山真之の名文の例として、例の「浪高し」だけでなくこんなものもあったのだそうな。海戦の戦闘詳報に「此の時夕陽已に春き」とあり、これはのちに「明治三十七八年海戦史」では「此の時夕陽まさに没せんとし」と直されてしまった一節があったそうな。「春き」(厳密には、この字の「日」は「臼」の字)は「うすずき」と読み、日が沈むこと。秋山さんは学があったねぇ、という話。 鈴木貫太郎首相のポツダム宣言受諾は、ちょっと遅すぎたきらいはあるけれど、あれしかなかったんじゃないか、とか。 戦艦ミズーリ上で降伏文書に署名した時、勝者側が勝手にたくさんパーカーを用意して記念品として持ち帰ろうとしたのに、わが全権の重光葵は自分の愛用の古びた国産万年筆を出して署名し、そのまま持ち帰ってしまった話とか。 新宿のとある酒場で、若いサラリーマンが気楽に「同期の桜」を歌っているのを聞いて、半藤さんと静かに飲んでいた吉田満氏がすっくと立ち上がって、腹の底から想いをこめて「同期の桜」を歌った思い出。 「戦争に生き残ったものが、今のこの安気な時代に飽食して、盛りの花を愛でて、短い法要をすませた安堵感に身を任せて、死者への挽歌をうたうべきではない」(吉田満氏) 胴上げとは、江戸時代の大奥にもその記録がある古い日本の習慣で、節分の日や煤払いのあとなどに年男や家の主人を胴上げしたこともあるそうな。そもそもは厄落としの意味なのらしい。じゃあ、優勝監督の胴上げはどうなんだろうね、とか。 宮中で蹴鞠をする時、貴人が濡れないように庭の木に鞠を蹴り上げて梅雨を落としたそうです。これが露払いという言葉の始まり。 露にははかないものという意味もあり、これを美しいと考えた人があり、秋の季語となりました。 「うちのカカアがよ」と言う時の「カカア」の語源。万葉集の山上憶良の長歌に出てくる「可可布(かかふ)」なのか、日本書紀に出てくる「伽摩烏(かかあ)」なのか。「嬶」や「嚊」という当て字にはどんな意味があるのか。 肩の凝らない、面白いエッセイ集です。歴史探偵の満目躍如。(2015/4/8) |
 |
Ver. 3.01 |
|---|
| 管理番号:H031-022 | 52J 戦史・戦争ノンフィクション(日本) |
出版社:文藝春秋社 | |||||||
| 書名:日本のいちばん長い日 決定版 | ISBN978-4-16-748315-9 C0195 | ||||||||
| 文春文庫 は8-15 | 価格:600Yen | ページ数:384P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:06/7/10 第22刷:15/5/25 | 購入:2015/6/26 | カバー:2015「日本のいちばん長い日」製作委員会 | |||||||
 右の表紙絵は二つありますが、普通は左側のものです。2015年夏、映画が作られますので、タイアップとしてその上に右のカバーがさらに巻かれています。 右の表紙絵は二つありますが、普通は左側のものです。2015年夏、映画が作られますので、タイアップとしてその上に右のカバーがさらに巻かれています。今のところ近所ではこの映画を放映していないので、見ていません。このままだと、数年後にWOWOWで見ることになるのかな。ふう。 1945年7月27日、四年近く世界を相手に戦争を行ってきた日本帝国が、連合国によるポツダム宣言を受理した日から始まります。 平和への道筋を示されたこの宣言を、日本政府は静観するという判断を行います。これが報道で黙殺とされ、reject(拒絶)と訳されて原爆投下やソ連の対日参戦を正当化されることとなったといわれます。 この時代であっても先見の明のある人々は、戦争をやめなければ日本は滅びる、と感じていました。少しでも早く終戦しなければ、この国は消滅しかねない、と。そのためには、この国の歴史上初めての降参、敗戦も甘受すべきだ、と。 平和は絶対に守らねばならない。簡単なことじゃないか、頭を下げればいいじゃないか、なんでわからない、馬鹿かお前ら。 しかし、それは出来なかったのです。 これを現在の視点で批判することはたやすい。無能、無定見、非人道的などと非難することもたやすい。 それは時代のせいだった、という説明では、素直に得心できないのが現代人。そのために、というわけではないのでしょうが、この時代になにがあったのか、どうやって五里霧中の時代の霧の中をさまよい、あの歴史に至ったのかを、1945年8月14日午後0時から翌8月15日午後0時までの24時間を追うことで説明してくれます。 阿南陸軍大臣の側近である軍務課員竹下正彦中佐が、天皇陛下の口から終戦の命令が出ると聞いて、それでも継戦すべきと主張し、そのための策、“治安維持のための兵力使用権”を行使すべきだと主張します。
敗北を認めず、歯をむき出して肯んじない男たちもいます。たとえば、海軍の海軍302航空隊司令、小園安名大佐。
陸軍省に課員を集めて聖断のことを告げ、それに従わなければならないと説く阿南陸相。そしてさらに言う。
しかし、一部の青年将校が動く。陸軍軍務局課員の畑中健二少佐は、不穏な言葉を発します。
閣議では、立場を守ると言うよりも納得するための問答が続いています。これは、やむを得ざるセレモニーなのか。
面目を保つための、納得させるための、意地を通すためだけの議論が続きます。終戦の詔勅、つまり玉音放送の言葉について、一言半句を巡って交える舌戦の行きつく先は。
しかしそこに、国家とはこうあるべきだと考え、必要なら実力でそれを貫こうという男たちがうごきだす。終戦を告げる玉音放送を何としてでも阻止することが、この国のために絶対に必要なのだと信じる男たちが。
陸軍の信望を一手に集める陸軍大臣・
そして陰謀は進み、なんと天皇を守る最後の盾であるべき近衛師団の将校たちが動いてしまったのでした。
しかしすでに、叛乱の徒が神輿に担ごうとした阿南惟幾は、最後の時間を迎えようとしていたのでした。
日本の歴史は、激流の中で進路を定めます。
そして、阿南惟幾の、最後に残した謎の言葉。
あの方さえも、こんな事をいいます。
そして、首相としてこの難局を乗り切った鈴木貫太郎はしみじみと漏らす。
こんなぎりぎりの修羅場を乗り越えて、いまの歴史がある、と半藤一利氏はこの歴史を残します。 この記述すべてが正しいのかどうか、わからないけれど、このようにまとめられると圧巻としかいいようがない。 後世に残すべき名著の一冊と考えていい、と思うのでした。(2015/8/28) |
|||||||||||||||||||||||
| Ver. 3.02 |
|---|
| 管理番号:H031-023 | 53 史書・編年史 |
出版社:平凡社 | |||||||
| 書名:日露戦争史2 | ISBN978-4-582-45444-4 C0021 | ||||||||
| 価格:1600Yen | ページ数:416P | 本のサイズ:135×195HC | |||||||
| 初版発行:2013/2/26 | 購入:2015/11/5 | 装幀:菊地信義 | |||||||
 この巻では、緒戦の勝利に我を忘れて有頂天になる民草たちの軽薄さから、ロシアの通商破壊戦になすところも無く振りまわされる連合艦隊、黄海海戦と蔚山沖海戦、旅順攻撃開始、遼陽会戦、沙河の対陣、そして203高地の激闘と旅順陥落までを描きます。明治37年(1904)5月から、明治38年(1905)1月まで。 この巻では、緒戦の勝利に我を忘れて有頂天になる民草たちの軽薄さから、ロシアの通商破壊戦になすところも無く振りまわされる連合艦隊、黄海海戦と蔚山沖海戦、旅順攻撃開始、遼陽会戦、沙河の対陣、そして203高地の激闘と旅順陥落までを描きます。明治37年(1904)5月から、明治38年(1905)1月まで。この巻での主題は、この旅順要塞にこもったロシア太平洋艦隊をどうするか、という事を中心にしたさまざまな戦略と戦闘です。 まずは、第一巻で描かれた劈頭の旅順港奇襲の戦果不十分、港口を閉塞する作戦の失敗ののちの、主力艦隊による旅順港封鎖。艦隊の大打撃を受けて陸軍による要塞攻撃への方針転換。大陸遠征軍の再編成と、満州軍の成立。 首山攻略戦と、沙河会戦。日本陸軍の辛勝と、追撃できなかった理由。 ロシア、ウラジオ艦隊の通商破壊戦に翻弄される陸海軍。 陸軍戦力の三分の一を占める強力な打撃軍である第三軍の編成と旅順攻撃。海軍が編成した陸戦重砲隊の意外な活躍。 第二次黄海海戦によりロシア艦艦体に痛撃をあたえるも取り逃がした連合艦隊。 攻城戦三倍則というはるか昔にさかのぼる経験則を知りつつも、ほぼ同数の戦力でアジア最強、いやおそらく当時の世界最強の要塞を攻める乃木隷下第三軍。 数々の伝説を築き、屍山血河の中で歯を食いしばって二〇三高地に挑んだ将兵たちと、旅順開城。 まずは、緒戦の陸海軍の大活躍に欣喜雀躍する民草の軽薄さの描写から始まります。
しかしその影では、最前線で必死に戦う兵士たちと、彼らを戦わせるべき指揮官たちの試行錯誤が続きます。日本にたったの六隻しかない、日本人が血と汗で精一杯背伸びして購入した戦艦のうちの二隻、 この大損害、大失態の中で、海軍を統括する
しかしこの背後で、かつて陸軍に対してわが海軍の力をもってすれば、旅順要塞に陸軍が手を出す必要なしと言いきった海軍の方針転換が起きました。彼我の戦力比が一気にくずれた今、陸上から旅順港内の敵艦を砲撃するより他に制海権を得る事はできない。 このための海軍より旅順要塞を攻略して欲しいと陸軍に「要請」する必要が出ます。これは、実は陸軍の重鎮たる陸軍次官・ 後世の視点から見れば、満州軍という四つの野戦軍の上に上級司令部を設け、そこに このドタバタ、泥縄の中で5月25日、 屍山血河、という言葉が始めて出ますが、むろんこれが最後ではない。 戦訓に学ばず愚行をくり返す日本、南山要塞の戦訓にしたがって旅順の防護を固めたロシア、という描写が出てきます。遙かな未来、太平洋戦争に至っても同じ事をくり返した日本という姿も。嘆息するしかない。 その国民性も同じ。熱しやすく冷めやすい。 通商破壊戦によって日本の兵站機能に打撃をあたえたロシアのウラジオ艦隊に対し、それに対応した またこのとき、作者は日本軍の 「攻撃は最大の防御なり」という美名の元で、攻めに徹して守りを怠る姿勢を指摘します。この考え方が上村提督の失敗をまねき、下って太平洋戦争時の凄まじい民間人の被害をまねいたという。 日本人の多くは、軍隊をみずからの護民のためではなく武人が持つ武器としてとしか認識できない、ということか。多分、今もなお。 旅順攻略戦において、日本軍は強襲攻撃により、何千何万の将兵を死に追いやります。これが作戦として、用兵として正しかったのかの議論については、感情論を無視したとしても議論の残るところ。著者は、人間としては優れていたものの用兵家、軍事指揮官として乃木希典はその能力に欠け、任に当たるべき人ではなかったとの立場をとります。しかし時代を考えるべき、とも言う。
沙河会戦において、日本軍の将帥たちの物語もあります。 従来可能な限り敵軍より数的に優勢な情勢を作って勝利を重ねてきた日本軍が、始めて正面切っての開戦を迎えるにあたり劣勢な彼我の情勢の中で苦闘します。特に獅子奮迅の活躍をしたのが第一軍。その将たる また、旧仙台藩出身の この戦勝に浮き足立ち、景気のいいことばかり連呼する民草に警鐘を鳴らそうという試みもあったらしい。開戦より半年経ち、国家の米びつの底をみて蒼白になっている政府関係者たちにとって、景気のいい戦勝より一刻も早い停戦、それもちょうどよく勝ちの形に持ち込んだ停戦以外に国家の財政、そして国家そのものを救う道はないと承知しています。この戦争がさらに数年続いたら、この国家の未来はない。 政府のメンバーだけでなく、宿老たる立場だった山県有朋の言葉も残ります。
政府をあずかる政治家も、国家を護るべき軍人も、その目標に対して一丸となっていたのがこのとき。 戦地にある弟を思う有名な新体詩、「君死にたまふこと勿れ」が詩誌 「明星」に発表されたのもこの頃。 そう、ここに至る経緯を評してこうあるべきであったとか、即刻争いをやめて平和を断固守るべしとか、尊い人命を磨りつぶす愚行は醜悪であるという論理は、正しいであろうけれど今はまた別。だれが戦いの悲惨さをどう描こうと、ここに至って国家のなすべき事は、なんとかして勝つこと。それしかなかった。 しかしいくさは人間がするもの。そしてどんな人間であっても、自分の能力と実績になにがしかの自負があれば、他人の容喙を受ける事を嫌うもの。 さまざまな経緯を経て、満洲軍総参謀長児玉源太郎は、司令官大山巌名義で参謀総長山県有朋よりの二〇三高地に攻撃を集中せよとの命令にこう答えました。
かくして明治天皇の名による訓令に対しても素直に従わず、
昭和の前線の陸軍部隊は、ある意味これを踏襲したのだから。 しかし明治の満洲軍の考えは違った。彼らは、大山司令官も児玉総参謀長も、最前線の第三軍の自由裁量に任せ、戦争に関しては督戦しても助言しても乃木第三軍の判断に任せていたのだそうな。であるから、本国よりの戦略、戦術転換命令に対し従わなかったのは第三軍の頑迷によるのだそうな。 海軍の苦衷、戦争遂行への不安を元に御前会議まで開いて決定した戦略転換を拒否する乃木第三軍に、非難は集中することに。 戦争途中にあっては軍司令官の更迭それ自体は何ら異常なことではない。日清戦争においても、山県軍司令官自身が消化器を痛めてという理由をつけてですが、前線から下げられています。 にもかかわらず乃木は、なぜ更迭されなかったのか。 これには、明治天皇が漏らしたという言葉 「乃木を更迭すれば、乃木が死ぬであろう」が元である、と言われていました。しかしどうも違うらしい。天皇の言葉としては、「旅順はいつか陥落するにちがいないが、あの通り兵を殺しては困った。乃木も宜いけれども、ああ兵を殺すようでは実に困るな」 と言ったのみらしい。 では乃木の更迭を.止めたのはだれなのか。山県総長と大山総司令官である、と言うのがこの本の結論。 かくして人格・人徳高く清廉潔白で克己心に富み、しかし近代戦争には疎い意志強固な司令官によって第三軍の将兵は血反吐にまみれ、旅順要塞の埋め草となったという。ではどうすべきだったのかは別問題。 第三軍の伴明に業を煮やして児玉総参謀長が旅順を督戦し、戦術転換を行ったという話に関して、この本でも新たな史料を元に描いています。これが、意外なことと言ってはなんなのですが、「坂の上の雲」 とほぼ同じ解釈。 無能な乃木希典、頑迷固陋で怠惰な参謀たち。数々の欠点はあるものの明楼果断な児玉源太郎。 ふむ、そういう解釈なのか。 しかし結果として、乃木司令官の指揮のもと、日本陸軍第三軍は将兵の血と肉を惜しみなく捧げて二〇三高地を占領し、旅順要塞を落としたのでした。
そう、旅順要塞は陥落しロシア第一太平洋艦隊は壊滅しましたが、まだまだ戦争は続きます。(2016/3/31) |
|||||||||||||||||
| Ver. 3.02 |
|---|
| 管理番号:H031-024 | 53 史書・編年史 |
出版社:平凡社 | |||||||
| 書名:日露戦争史3 | ISBN978-4-582-45446-8 C0021 | ||||||||
| 価格:1600Yen | ページ数:416P | 本のサイズ:135×195HC | |||||||
| 初版発行:2014/1/24 | 購入:2016/3/28 | 装幀:菊地信義 | |||||||
 第三巻は、戦争の終わり。 第三巻は、戦争の終わり。第十二章 「血の日曜日」と黒溝台 「水師営の会見」から始まります。旅順要塞の降伏の会談が行われたところ。そして第三軍を糾弾する声。しかし、国際的に乃木の名将ぶりが喧伝されています。 満洲軍総参謀長・児玉源太郎は、恐ろしい事をいう。
そして、厭戦気分のロシア国民、黒溝台の苦戦と立見尚文中将の活躍。 第十三章 奉天・乾坤一擲の大決戦 ひと息ついた海軍の立て直し、そして竹島領有。
奉天会戦のはじまり。苦闘する将兵たち。戦闘の推移とその結果。疲労困憊する陸軍将兵。
第十四章 決戦前夜の両艦隊 大勝利の報に沸く日本の民草たち。提灯行列、大祝賀会。しかしその陰で、奉天会戦の結果として日本陸軍将兵の死傷者の数。
バルチック艦隊の来寇を前に、陸軍の作戦案を蹴る海軍。連合艦隊の必死の探索。 第十五章 「皇国の興廃この一戦にあり」 どの海峡で敵が来るかで激論となる連合艦隊。203地点で発見されたバルチック艦隊。この発見には、連合艦隊司令部の中での侃々諤々の討論と、一人の参謀の主張と、一人の司令官の判断と、司令長官の決断があったという。
第十六章 ポーツマス軍港と日比谷公園 大海戦の終了。ニコライ二世とルーズベルト大統領の思惑。講和会議。戦艦ポチョムキン。 難航する講和会議と樺太攻略。先進各国の思惑と外交政治。そして創られた平和。 政治と戦争の実態を知らぬ民草の興奮と失望。日比谷公園の暴動。
エピローグ 万歳、万歳、万歳の渦 凱旋する大山元帥麾下の将軍たち。乃木大将。大和魂とは。 半藤さんご贔屓の反骨漢、夏目漱石の筆で、この時代を描いています。
半藤さんの視点は、むろんまっすぐではない。半藤式のバイアスがかかっています。 それを良とすべきか否とすべきかは、人によって違うもの。ただこの本は、半藤一利という歴史探偵が掘り起こした歴史の一コマとしてたのしむべきもの、ではないのかな。 それはそれで面白いのだから。(2016/9/13) |
||||||||||||||||
 |
|---|
| 管理番号:H031-025 | 52J 戦史・戦争ノンフィクション(日本) |
出版社:文藝春秋 | |||||||
| 書名:戦士の遺書 | 太平洋戦争に散った勇者たちの叫び | ISBN978-4-16-791925-2 C0195 | |||||||
| 単行本:1995年1月 ネスコ刊、旧版文庫(底本):1997年8月 文春文庫刊 | |||||||||
| 文春文庫 は8-37 | 価格:780Yen | ページ数:320P | 本のサイズ:文庫 | ||||||
| 初版発行:2022/8/10 | 購入:2022/8/11 | デザイン:増田寛 | |||||||
 単行本として1995/1に刊行され、1997/8に文庫化され、著者逝去後の2022/8に新装版として再刊行されたもの。読んでいなかったことに気づいて購入し一読。 単行本として1995/1に刊行され、1997/8に文庫化され、著者逝去後の2022/8に新装版として再刊行されたもの。読んでいなかったことに気づいて購入し一読。28人の日本陸海軍軍人の言葉を集めたもの、というと簡単すぎるかな。歴史の要にいたよく知られた大将・元帥たちから、始めて知った この満淵大尉は、戦争末期の昭和20年5月25日に、千葉県上空で墜落したB29の米兵(おそらくエムリー少尉)を惨殺したことで戦後BC級軍事法廷に立たされます。しかし本人も周囲も犯意をとことん否定したのでした。満淵中尉は三重県で神主をしており、本土決戦を控えて応召された人物でした。武士道精神をきわめていた彼は、重傷を負って助かる見込みの無い俘虜を人道的に「介錯」したのであり、残虐行為を行ったとは思っていない。とはいえ戦争という異常な世界の中で、さらに文化と文化の対立があり、しかも連合国の軍事法廷はまず報復という目的が明確であった以上、なにをどう主張しようと無意味ででした。死刑判決を受けた満淵大尉として行えるのは、毅然として死を迎えることだけ。 そんな「勇者」もいた。 現代では勇者とは言えないかもしれないけれど、勇者でした。心のどこかにしまっておきたい生き方かも。 終戦直前の昭和20年8月10日のラジオと翌日の新聞朝刊に、陸軍大臣の名前により「全軍将兵に告ぐ」という国民に継戦の檄を飛ばす訓示が伝えられたそうです。昭和天皇の聖断によりポツダム宣言の受諾という国家の方針が定まったのは10日の午前2時ですから、その直後。これは連合国に日本の政治方針についての疑惑を与え、国民にはいよいよ一億玉砕の覚悟を硬くさせます。 この訓示は陸軍首脳の意を受けたものではなく、大本営報道部部員兼情報局情報官 苦悩の末、彼は敗戦後の事務処理を勢力的にこなしたのち、彼と心を共にする愛妻、そして二人の愛児と共に9月1日、ミズーリ号艦上で降伏の調印が行われる前日、自殺してその生を終えます。「草莽の文」という鮮烈な遺書を残して。 現代の価値観では犯罪的な愚行でしょう。しかし彼もまた勇者であったかもしれません。 ほかにも、伊藤整一海軍中将、安達二十三陸軍中将、山本五十六海軍大将、水上源藏陸軍少将、宇垣纏海軍中将、野中五郎海軍少佐、山下奉文陸軍大将、有泉龍之助海軍大佐、大田実海軍少将、栗林忠道陸軍中将、庄司元三海軍技術中佐、猪口敏平海軍少将など、さまざまな勇者と評すべき軍人たちの最期の言葉が描かれます。 「特攻の父」という盛名あるいは汚名を押しつけられた大西瀧治朗海軍中将や、「グズ元」と謗られ妻にさっさと自決しなさいと迫られた杉本元陸軍大将の真意など、ああそうだったのか、と認識を改めさせられるものもありました。 この著の中でただ一人、終戦時までに死に至らなかった「ラディカル・リベラリスト」井上成美海軍大将がいます。たしかに彼はその時死ななかったかもしれませんが、戦う軍人としてではなく国家を支える軍人として、鮮烈な生涯を送っています。 重いなぁ。 最後、本間雅晴陸軍中将と阿南惟幾陸軍大将に多くのページが割かれます。 本間中将は、緒戦のフィリピン攻略戦の指揮を執った勇将。その時発生した米軍捕虜虐待の責任を取る形で、実は敗戦した事実を認めないマッカーサーの個人的な憎悪を受け、東京裁判の場で不当窮まる政治ショーの結果として有罪宣告されます。 裁判の終盤、夫人である本間富士子が証言のために法廷に現れ、夫が軍人として清廉であったこと、この戦争自体に最初から反対していたこと、フィリピンの人々に大して友好的・平和的に軍政を行うよう努めたが政府の怒りをかって更迭されたことなどの長い弁明の言葉の最後をこう結びます。
終戦時陸軍大臣であった阿南惟幾大将は、8月15日の夜明けに自決するとき、ぽつりと「米内を斬れ」と言ったといいます。 これにはいろいろ解釈がありますが、謎は残っています。 阿南大将とは、大臣になるような軍政畑にいた人ではなく、陸軍を二つに分けた統制派(幕僚グループ)にも皇道派(隊付将校)にも属さない無色の教育畑の軍人であったがゆえに、2.26事件の混乱のあと陸軍中央に迎えられた真摯な軍人。海軍で「グズ政」と呼ばれた米内光政と同じく、妙に目立たず侮られながら、いつの間にか「阿南のほかに人なし」と呼ばれ欠かせない人となります。 この二人がともに同じ目標に向かって同じような考えで突き進み、終戦へと国政を導きますが、実はこの二人最後まで互いを理解できなかったのだという。 あるいは、腹芸と大局観で動ける軍人であった米内の大きさに対し、現実を踏まえ忠誠一途であの手この手を考える阿南はどうしても相容れなかったのかも。 彼の自決のあと、鈴木貫太郎首相がこんな言葉を残します。
人によってはもう歴史の彼方かもしれないのだけれど、忘れてはいけない歴史であり、「歴史探偵」であった半藤一利氏が我々に残した最高の人物史です。(2022/11/6) 読書メーターの記録より 読了:2022/10/13 |
|||||||||||
